"������" �����̗z���� 162 �l�@�ی����ƈ�Ë@�ւ̕ɍ�
�V�^�R���i�E�C���X�� PCR �����ŗz���ɂȂ����ƈ�Ë@�ւȂǂ�����������̂ɁA�����s���\�̊����Ґ��Ɋ܂܂�Ă��Ȃ��l�� 162 �l�����邱�Ƃ����������B�@�ŏ��̕Ɍ�肪�������̂��A�����Ґ����Ԉ���Ă���̂��B�@�����͔������Ă��炸�A�s���m�F���}���ł���B�@�z���҂͂̕قږ����A�s������̂��߈�Ë@�ւ��猟�����ʂ�����ďW�v�\���쐬���A�z�[���y�[�W�Ō��\�B�@����̊����Ґ��͕ی�������̐����ȕ���ɁA�s���m����Ƃ��ē��X���\���Ă���B�@�z����������s�ɕ��͂��܂ł̎��ԍ������邽�߁A��̂���͐����邪�A�{���͂قڈ�v���邱�ƂɂȂ��Ă���B
�Ƃ��낪 29 �����_�ł̗��҂̗v�l��������ƁA�z���Ґ��͊����Ґ���� 162 �l�������B�@������A�����̗z���҂́u���\�҂��v�ɂȂ��Ă���A����������Ԃ͓�T�Ԉȏ㑱���Ă���B�@�s�̊����Ґ��������Ă� 5 ���ɓ����Ă����x�A�ی����Ȃǂ���̕R��Ȃǂ����o�B�@�s�͂��̍ہA�W�v����蒼���Ă��邱�ƂȂǂ���A����̌덷�ɂ��ẮA��Ë@�ւȂǂ���́u�z���Ґ��v�̕�����Ă���\���������Ɛ����B�@���҈�l�̌������ʂ��d�����Čv�コ��Ă�����A�A���m�F�̂��߂̌������ʂ����������肵�Ă���^��������Ƃ݂Ă���B
�������̏ꍇ�A�s���u�z���Ґ��v�Ȃǂ���Z�o����z�������㉺����B�@�z�����͓s���O�o���l�E�x�Ɨv���̊ɘa��ėv���f���郂�j�^�����O�w�W�̈�Ƃ��Ă���A�w�W�̐M�������h�炬���˂Ȃ��B�@����ɁA����������ی����Ȃǂ���̕R��Ȃǂ��Ƃ���A�ŋߌ����X���ɂ���Ƃ���銴���Ґ��́A�����Ƒ����������ƂɂȂ�e���͌v��m��Ȃ��B�@�s�́u���̉\���͂Ȃ��ƍl���Ă���v�Ɣے�B�@�덷�̌����ɂ��Ĉ�Ë@�ւɖ₢���킹��Ȃǂ��Ċm�F���}���ł���B
�������s�̗z���Ґ��Ɗ����Ґ��� ��Ë@�ւȂǂ��s�ɕ��� PCR �����́u�z���Ґ��v�� 7 - 28 ���Ōv 486 �l�B�@�����Ԃɓs�����\���������Ґ��͌v 324 �l�B�@6 ���ȑO�́u�z���Ґ��v�́A���Ԉ�Ë@�ւł̕ی��K�p�����Ȃǂ��܂�ł��炸�A��r�ł��Ȃ��B (���{���A�����V�� = 5-30-20)
�S���� 75 �l���V�^�R���i�����@�k��B�s�� 26 �l�m�F
�V�^�R���i�E�C���X�̍����̊����҂́A29 ���ߌ� 9 �����݂ŐV���� 75 �l���m�F����A�v 1 �� 6,882 �l�ɂȂ����B�@���҂� 6 �l�������B�@28 ���ɁA�k��B�s�� 80 �㏗�������S�����Ɣ��\����Ă���A���킹�Čv 890�l�ɂȂ����B�@�k��B�s�ł� 26 �l�̊������m�F���ꂽ�B�@1 ��������Ƃ��Ă͉ߋ��ő��B�@4 �� 30 ������ 23 ���A���ŐV�K�����҃[�����������A5 �� 23 ������}���B�@7�@���A���Ōv 69 �l�̗z�������������B
�k�������s���͂��̓��̑��c�Łu�� 2 �g�̂܂��������ɂ���v�Ƙb�����B�@6 �� 1 ������s���w�Z�̖{�i�I�ȍĊJ��\�肵�Ă������A���łɎ��{���Ă���ߑO���Ƃ݂̂̑Ή��ʑ����邱�Ƃɂ����B�@�܂������s�ł͐V���� 22 �l�̊������m�F���ꂽ�B�@�ً}���Ԑ錾���������ꂽ 25 ���ɂ� 8 �l���������A���̌㑝���������A4 ���A���� 2 �����L�^�����B�@�s�́A�x�Ɨv�����ɘa���邩�ǂ����̖ڈ��̈�Ɂu1 ��������̊����҂� 20 �l�����i1 �T�ԕ��ρj�v�������Ă���B�@�s�� 6 �� 1 ���ߑO 0 ���ɁA�f��ق�X�|�[�c�W���Ȃǂւ̋x�Ɨv�����ɘa���A�u�X�e�b�v 2�v�Ɉڍs����B�@������� 30 ���ɂ����{��������Ō������Ă������A�����Ȃǂ�����߂��B (asahi = 5-29-20)
�����̕����쒆���a�@�A9 �l�����@�N���X�^�[��������
�����쒆���a�@�i�����s������s�j�� 28 ���A�Ō�t��a�@�E�� 4 �l�Ɗ��� 5 �l�̌v 9 �l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ��������Ɣ��\�����B�@���ɂ� 10 �l�̓��@���҂����M�Ȃǂ̏Ǐ��i���Ă���APCR �������Č��ʑ҂����Ƃ����B�@5 �l�ȏ�̊����҂��o��N���X�^�[�i�����ҏW�c�j�����������\��������B�@�a�@�ɂ��ƁA5 �� 21 ����A���_�ȕ��a���̐E�� 1 �l���R���i�����ǂƐf�f���ꂽ�B�@���̕a���ɂ͌v 62 �l�̊��҂����@���Ă���A���̂������M�������� 16 �l���@PCR�@���������B
���̂ق��A�����a���ɂ����Ō�t��a�@�E���̌v 4 �l�ɂ��Ă��A�Z���ڐG�҂Ƃ��Č������邩�������Ă���B�@�a�@�͊����g��h�~�̂��߁A���݂͊O�����f������߂���A���_�ȁE���ȐV�K���@�̎����n�r���𒆎~�����肵�Ă���B�@�q��p��Y�@���́A�u���҂̊F�l�A���Ƒ��̊F�l�B�@�n��̊F�l�A�W�҂̊F�l�ɂ͑�ς��S�z���������������܂��Đ\�������܂���v�ƃR�����g���o�����B�@�����J���Ȃ̃N���X�^�[�ǂ͓s�̗v���ɉ����A�a�@�̒����ɓ������B (asahi = 5-28-20)
�V�^�R���i�u�� 2 �g�v�ɔ�����@PCR �����̐V��@���X
���N���邩�킩��Ȃ��V�^�R���i�E�C���X�̊����u�� 2 �g�v�B�@���̎��ɔ����A�������@�탁�[�J�[�� PCR �����̐V��@�����Ő��ݏo���Ă���B�@�������Ԃ��Ï]���҂̊������X�N��啝�ɏk�����A�������������g��̒�������߂�Ƃ����B
�^�J���o�C�I�i���ꌧ���Îs�j�́A���t���犴���̗L���ׂ鎎����J�����Ă���B�@���܂͕@��̂ǂ̉��ɖȖ_�����Č��̂��̎悵�Ă��邪�A�V�������Ɛ�p�e��ɂ��o�������ł��ށB�@��Ï]���҂̊������X�N�����点�邾���łȂ��A����Ō��̂�����Č����@�ւɑ���Ƃ������g�������ł���\��������Ƃ����B�@���x���]���̎�@�Ƃقړ����B�@���łɌ� 200 �����̕��Y����Ԑ��𐮂��Ă���B�@����A���̔F�Ȃǂ��o�Ĕ���������j���B
����⌟�����u���肪����x�m�t�C�����a������i���s�j�́A75 ���Ō��ʂ�������S�����������u�p�̎�����J�������B�@���̂��`���[�u�ɓ���đ��u�ɃZ�b�g���邾���ŁA�R���i�̈�`����o�ł���B�@���܂͏n���̌��������ׂ��ȉ��x���������Ȃ��� 4 - 6 ���Ԃ����č�Ƃ��Ă��邽�߁A�~�X��u�ڋl�܂�v�̌����ɂȂ��Ă����B�@���̑��u���g���Ό���̕��S�y���ɂȂ���Ƃ����B�@�����̍L�����c������ɂ́A�������ʂ�f�����W�߂ĕ��͂���K�v������B�@���Ð��쏊�i���s�s�j�͈�Ë@�ւƘA�g���A�I�����C���ŊǗ��ł��Ȃ�����������B�@��c�P�v�В��́u�������ʂ������āA�z���グ��悤�Ȏd�g�݂Â��肪�K�v���v�ƈӗ~�������B
�s�������ԂɊ��҂���B�@�_�ˎs�͎�����肪����V�X���b�N�X�i�_�ˎs�j�ȂǂƘA�g���A6 �����猟���\�͂���������B�@���������͂��Č����Ԑ����\�z����̂͑S���ŏ��߂ĂƂ����B�@�����J���Ȃ���\�Z�ȂǂŖ��Ԃ̓������x��������j���B�@���j�����ljۂ̒S���҂́u�� 2 �g�ɔ����APCR �����̐v������Ȑl���͋ɂ߂ďd�v���B�@���Ԃ̑n�ӍH�v�̗͂���Ȃ���A�A�g���� PCR �����̑Ԑ����������Ă��������B�v�Ƙb���Ă���B (�����M���A�䓌�ʁAasahi = 5-26-20)
�u�s���ȓ�v�@���ă��f�B�A�������A���{�̃R���i��
���{�͐V�^�R���i�E�C���X�̗��s�}�~�ɐ������Ă����̂��낤���B�@�e���̃f�[�^�͂��A�l�� 10 ���l������̊����Ґ��⌟�������A���Ґ����ׂ��B�@�����͓��{�̌����̐���A�����͂̂Ȃ��ً}���Ԑ錾�̌��ʂ��^�⎋���Ă������ă��f�B�A�́A���݂̏������ƂƂ��ɓ`���Ă���B�@�����V���͎�v7�J�� (G7) �ɂ��āA���ꂼ�� 10 ���l������̗v�����Ґ��Ɗ����̗L���ׂ錟���������r�����B�@���������͊e���̐��{���\�Ɋ�Â����B�@�č��͊e�B�̔��\���܂Ƃ߂����Ԃ̏W�v�l��p�����B�@�܂��A�v���Ґ��́A���E�I�ɂ݂Ĕ�r�I��Q���}�����Ă���A�W�A�E�I�Z�A�j�A�n��̍��X��I�сA10���l������̐l�����ׂ��B
���̌��ʁA���{�� G7 �ŁA10 ���l������̊����Ґ��� 13.2 �l�ōł����Ȃ������B�@����A���������ŏ��� 212.8 ���ŁA�ő��̃C�^���A�̖� 4% �������B�@�p���� 1 �� 20 �����̌������߂����i���{�̖ڕW�� 1 �� 2 �����j�A����Ȃǂ֖� 80 �������̌����L�b�g��X�����Ă���B�@���ۂɌl���������������s���Ȃ��߁A����̔�r���ɗX�����͊܂߂Ă��Ȃ��B�@�����A�܂߂��ꍇ�� 1.5 �{�߂� 5,013.0 ���܂ő�����B
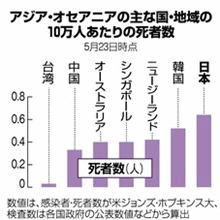
�܂��A10 ���l������̎��Ґ��́A�A�W�A�E�I�Z�A�j�A�n��̑����̍��X�œ��{�� 0.64 �l��菭�Ȃ������B�@���Ƃ��A�����̐��ۑt��������p�̗v���҂� 7 �l�ŁA10 ���l������ł� 0.03 �l�������B�@�p�I�b�N�X�t�H�[�h��ɋ��_��u���A�e���̊����f�[�^�Ȃǂ��W�v���Ă���c�́uOur World in Data�v�ɂ��ƁA���{�� 5 �� 23 �����_�� 100 ���l������̊����Ґ������E 208 �J���E�n��̂������������� 136 �ԖځB�@���������Ґ��� 94 �Ԗڂ������B�@�������������A�W�A�n��œ��{�������Ґ������������̂̓t�B���s���ƃ����f�B�u�������B
����A���B���a�\�h�Ǘ��Z���^�[ (ECDC) ���܂Ƃ߂��e���f�[�^���V�����W�v�����Ƃ���A���{�́AG7 �̒��ōł������g��̑��x��}�����߂Ă����B�@�����҂��l�� 1 �疜�l������ 1 �l�ȏ�ɂȂ��Ă���s�[�N�ɒB����܂ŁA�č���t�����X�A�h�C�c�� 35 ���O�ゾ�����̂ɑ��A���{�� 52 ���������B�@�܂��AG7 �� 1 ��������̐V�K�����Ґ��̐��ڂ��݂�ƁA�ł��������������ŁA�č���C�^���A�� 1 �疜�l������ 900 �l���Ă������A���{�� 50.9 �l�i4 �� 17 ���j�������B
�V�^�R���i�E�C���X��}�������Ɍ�������{�̏��A�C�O���f�B�A�͋����Ƌ��ɓ`���Ă���B�@�����͂̂Ȃ��O�o���l�� PCR �������̏��Ȃ��ɂ�������炸�A���{�Ŋ������L����Ȃ��������Ƃɒ��ڂ��A�u�s���ȓ�v�A�u��������v�ȂǂƕĂ���B�@�����牽�܂ŊԈ���� �c �ł��Ȃ����{�̊����g��͍L����Ȃ������̂��A���ă��f�B�A�����ڂ��Ă��܂��B�@���Ƃ͂ǂ��l����̂ł��傤���B
�Ď��t�H�[�����E�|���V�[�͓��{�̐V�^�R���i��ɂ��āu�����牽�܂ŊԈ���Ă���悤�Ɏv����v�Ǝw�E������ŁA����ł�����́u�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�S�Ă����������Ɍ������Ă���悤�Ɍ�����v�Ɠ`�����B�@�u��������吨�̊ό��q������Ă������Ƃ��l����ƁA���̎��җ��̒Ⴓ�͊�Ղɋ߂��v�A�u���{�����b�L�[�Ȃ����Ȃ̂��B�@����Ƃ��D�ꂽ����̐��ʂȂ̂��A���ɂ߂�͓̂���B�v�Ƃ̌������������B
�u�s���ȓ�v�Ƒ肵���L����z�M�����̂́A�I�[�X�g�����A�̌������� ABC ���B�@������ʋ@�ւ̍��G�Ԃ�⍂��Ґl���̑����A������Ȃ��ً}���Ԑ錾���u��S�����������߂̃��V�s�̂悤�������v�ƕ\���B�@�u���{�͎��̃C�^���A���j���[���[�N�ƂȂ�\�����������v�Ǝw�E�����B�@�C�O�ł͂���܂ŁA�p BBC ���u�h�C�c��؍��Ɣ�ׂ�ƁA���{�̌��������̓[������t���Y��Ă���悤�Ɍ�����v�ƕ�ȂǁA���{�� PCR �������̏��Ȃ����^�⎋������������ł����B�@�ău���[���o�[�O�ʐM�͂��̓_�ɂ��āA�u�� 1 �g�����킵���͖̂{���ɍK�^�v�A�u�i�� 2 �g������O�Ɂj������ 1 �� 10 �����ł���悤�ɏ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ̘b���܂Ƃ߂��B
�p�K�[�f�B�A�����́u��S���ڑO�̏��琬������ցv�Ƃ̃^�C�g���ŁA���{�l�̐����K���������g���h�����Ƃ̌�����`�����B�@�� �}�X�N�𒅗p����K���A�� �������ň����n�O��肨���V������K���A�� �����q���ӎ��A�� �ƂɌC���ʂ��œ���K���Ȃǂ��A�u���{�̊����Ґ��̏��Ȃ��̗v���Ƃ��ċ�������v�Ǝw�E���Ă���B�@���{�̐��Ƃ������������{�l�̕�����K���������g���h��������Ƃ݂�B�@�������a�@�n�q�҈�ÃZ���^�[�̕l�c�ĘY�����i�n�q��w�j�́u���{�l�̐����u���ƃ}�X�N�������A�� 1 �g�̗}�����݂Ɉ��̖������ʂ������\��������v�Ƙb���B
����ŁA�� 1 �g��Ƃꂽ���A�� 2 �g�̊g�傪���O�����Ƃ��Ē��ӂ��Ăт�����B�@�u�����҂����Ȃ������Ƃ������Ƃ́A�Ɖu�����l�����Ȃ��Ƃ������ƁB �� 1 �g��芴���҂�������\��������v�Ƃ����B�@PCR �������̏��Ȃ��ɂ��Ắu���Ȃ������̂ł͂Ȃ��A�ł��Ȃ������v�Ǝw�E�B�@�u�������𑝂₹�A�Ǐy���z�����҂��o��B�@�����͏h���{�݂ł̊��҂̎�����ł����A�a�@�Ŏ��e���Ă�����ԈႢ�Ȃ���Õ��Ă����B �� 2 �g������܂łɊ��҂̎��e�̐��Ȃǂ𐮂��A�������𑝂₹��悤�������Ă����K�v������v�Ƙb���B (��{�i�A���c���q�Aasahi = 5-26-20)
�A�ً}���Ԑ錾��S�ʉ����@�O�o��Â����l�A�i�K�I�Ɋɘa
���{�W�O�� 25 ���[�ɋL�҉���A�V�^�R���i�E�C���X���ʑ[�u�@�Ɋ�Â��ً}���Ԑ錾�ɂ��āA�k�C���Ǝ�s���̓����A��ʁA��t�A�_�ސ�̌v 5 �s�����ŏI�����A�S�s���{���ʼn�������ƕ\�������B�@�����߂��Ă��� 49 ���Ԃ������B�@���{�͊O�o��C�x���g�J�Â̎��l�A�x�Z�Ȃǂ̗v����i�K�I�Ɋɘa������j���B�@�́u�킸�� 1 �J�����ŗ��s���قڎ��������邱�Ƃ��ł����v�Ƌ����B�@�ė��s�ɔ����A��Ñ̐��̏[���� 2 ���~�̗\�Z��ςݑ����Ɛ��������B�@���{�̊����Ǒ�͐V���ȋǖʂɓ������B (kyodo = 5-25-20)
�V�^�R���i�E�C���X�A���{�̊�����
���{�͐V�^�R���i�E�C���X�Ɋւ���ً}���Ԑ錾�̑Ώۂ�����A���s�A���ɂ̊� 3 �{��������������j���B�@�u���� 1 �T�Ԃ� 10 ���l������̊����Ґ��v�� 3 �{���� 0.5 �l��������Ă���A�ً}���Ԑ錾�̉���������Ɣ��f�����B�@�_�ސ�A�k�C���A������ 0.5 �l���A�ڈ������Ă��Ȃ��B�@1 ��������Ɋm�F���ꂽ�����̊����҂� 5 �� 20 ���� 35 �l�������B�@4 ���A���� 50 �l����������B�@20 ���Ɋ����҂��m�F���ꂽ�̂� 7 �s�����ŁA�_�ސ삪 18 �l�ōł����������B�@�����ē��� 5 �l�A��� 5 �l�A��� 3 �l�A�Ȗ� 2 �l�A�k�C�� 1 �l�A��t 1 �l�������B
�ً}���Ԑ錾�̑ΏۂƂ��Ă��� 8 �s���{�����ׂ�ƁA�� 3 �{���i���A���ɁA���s)�́A������� 0.5 �������B�@��s���͍�ʂƐ�t���ڈ�����������A�_�ސ�Ɠ����� 0.5 ���Ă���B�@�k�C���� 0.63 �Ŗڈ��������Ă���B�@���{�͐錾�����ɂ������s�� 4 �s���͈�̂łƂ炦����j�ŁA��s���Ɩk�C���͐錾���p������B�@1��������Ɋm�F���ꂽ�����҂̐��́A5 �� 20 ���� 35 �l�ŁA11 ���A���� 100 �l����������B�@�ً}���Ԑ錾�̑ΏۂƂȂ��Ă��� 8 �s���{���� 33 �l�ŁA�S���� 9 ���ȏ���߂��B �ً}���Ԑ錾�̑ΏۂɂȂ��Ă��Ȃ����Ŋm�F���ꂽ�͓̂Ȗ����������B
�v�����Ґ��� 5 �� 20 �����_�� 1 �� 6,223 �l�ɏ��B�@�ً}���Ԑ錾�̑ΏۂƂȂ��Ă��� 8 �s���{���őS���� 75% ���߂�B�@�S���̗ݐϊ����Ґ��̑����y�[�X�͊ɂ₩�ȓ݉��X���������A5 �� 15 - 20 ���� 6 ���A���ő��������O���� 0.5% ����������B�@�v���Ґ��� 5 �� 20 �����_�� 784 �l�ɒB�����B�@�����y�[�X�� 4 �����{�͑O���� 10% ����������������A������ 1% �O��܂ʼn������Ă���B�@�ً}���Ԑ錾�̑Ώۂ� 8 �s���{���� 609 �l�ŁA�S���� 8 ���߂����߂�B
�v�����҂����݊������Ă���l�A�����l�A���҂� 3 ���ނ���ƁA�����l�ɂ� 5 �� 8 ������×{���Ԃ��I�������l���W�v�Ɋ܂܂�Ă���A5 �� 20 �����_�� 1 �� 2,286 �l�ƂȂ����B�@���������҂� 7 �����������ƂɂȂ�B�@�������Ă���l�� 4 �� 30 ���� 1 �� 285 �l���s�[�N�Ɍ����X���������Ă���A�����ł� 4,000 �l��������Ă���B�@�s���{���ʂ̗v�����Ґ���l�� 10 ���l������Ō��Ă݂�ƁA�����͐l����Ō��Ă��ł������A4 �� 29 ������ 30 �l��ɂȂ����B�@��s���A����_�ȊO�ł͖k�� 3 ��(�ΐ�A�x�R�A����)�̊������������B�@�ً}���Ԑ錾�̑Ώےn��͕��ɈȊO�� 7 �s���{������� 10 �ʂɓ����Ă���B
�������Ă��邩�肷�� PCR �����̎��{�l���́A1 �� 4,000 - 5,000 �l��̓��������Ȃ��Ă���B�@���J�Ȃ��ߋ��̕�啝�ɏC���������߁B��t�̌����l���ɏd�����������B�@�_�ސ�ł͌����������W�v���Ă������A15 �����猟���l���ɕύX�B�@�ɂ��Ă��W�v��ς����Ƃ����B�@����܂ł� 1 ���̌����l���� 8 ���� 1 �� 2,389 �l���ő��B�@���{�W�O�� 1 ��������̌����\�͂� 2 �����ɂ�����j���f�������A������S����t�̕s���ȂǂŎ��{�����͑��Ă���B
5 �� 7 �����_�� 20 ��ȉ��͏d�ǎ҂� 6 �l�o�Ă��邪�A���҂͂��Ȃ��B�@30 ��ł� 2 �l���S���Ȃ��Ă���B�@60 ��ȏ�͏d�lj����₷���A70 �ォ��͎��҂��}������B�@70 ��ȏオ�v���҂̖� 8 �����߁A�����҂̂����ŖS���Ȃ����l�̔䗦�������v������ 10% ����B�@80 ��ȏ�ɂȂ�ƒv������ 15% �߂��܂ō��܂�B�@�Ȃ��A5 �� 13 ���� 20 ��ȉ��ŏ��߂ĂƂȂ鎀�҂��m�F���ꂽ�B
�N��ʂ̗v�����Ґ���l�� 10 ���l������Ō��Ă݂�ƁA5 �� 7 �����_�ōł������҂������̂� 50 ��i2,555 �l�j�����A10 ���l������ɂ���ƍs���͈͂̍L�� 20 �オ 19.5 �l�ƍő��ƂȂ�B�@30 ��A50 ��� 15 �l���Ő��l�������B�@70 ��ȏ�͐l����Ō���Ɣ�r�I���Ȃ����A�d�ǂ⎀�Ɏ���P�[�X���ڗ��B (nikkei = 5-21-20)
������ 5 �l�����A3 �l���S�@2 �T�ԘA���� 50 �l�����
�����s�� 19 ���A�V���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����� 5 �l���m�F���A3 �l�����S�����Ɣ��\�����B�@�s���̊����҂̗v�� 5,070 �l�A���҂͌v 244 �l�ƂȂ����B�@1 ��������̊����Ґ��� 2 �T�ԘA���� 50 �l����������B�@5 �l�̂��������_�Ŋ����o�H���킩��Ȃ��l�� 3 �l�������B (asahi = 5-19-20)
�މ@�����������u�ėz���v�ɂȂ������R�@��t���w�E���� 3 �̉\��
���ꌧ�� 17 ���A������ 1 �x�m�F���ꂽ��APCR ������ 2 �x�A���ɂȂ������A�Ăїz���ɂȂ������҂��������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�@���Ƃ́u���m�ȏ�Ȃ��A�����ł͂��邪�A�E�C���X�ʂ����Ȃ��������߂ɁA�E�C���X�����o����Ȃ��\���͂���v�Ǝw�E���Ă���B�@�Ăїz���������o���ߔe�s�̉�Ј������́A4 �� 12 ���ɐV�^�R���i�E�C���X�̊����� 1 �x�m�肵���B�@���̌� 2 �x�A�����������߁A5 �� 1 ���ɑމ@�B�@��Ɏ���×{�����Ă���A�Z���ڐG�҂͓����Ƒ� 1 �l�ŁA���݁A�����ɏǏ�͂Ȃ��Ƃ����B
���������a�@�����Ǔ��Ȃ̒Ŗؑn���t�́A�Ăїz���ɂȂ������R�ɂ��āA�u���͂ł���قǂ̏�Ȃ��A���m��Ȃ��Ƃ������v�Ƃ�����ŁA3 �p�^�[���̉\����������B
- �̓��̃E�C���X�ʂ����Ȃ����߁A����܂ł� PCR �����ŃE�C���X�����o����Ȃ�����
- �މ@������ɍĂъ�������
- �{���͉A���ł���̂ɁA����̌����ŗz���ɂȂ����u�U�z���v
(2) �̍Ċ����ɂ��ẮA1 �x�������Ă���R�̂�����Ƃ݂���̂ŁA�Z���ԂɍĂъ�������\���͒Ⴂ�Ƃ݂�B�@�z���̊m�F���m���ł���A(1) ���ł��l������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ���B
�E�C���X�����邩�ǂ����ׂ� PCR �����́A�E�C���X�̗ʂ����Ȃ���Ό��o����Ȃ����Ƃ�����B�@�̓��̂ǂ��ɃE�C���X���c���Ă��邩�͐��m�ɕ����炸�A���o�̎d���ɂ���Ă��������܂��B���̂��߁A���ʂ̃E�C���X���̓��Ɏc���Ă�����ԂŁA�A���ɂȂ邱�Ƃ��l������B�@�Ŗ؈�t�́u�̓��̃E�C���X�ʂ����Ȃ���A���̕��A�l�Ɋ������L����͂����Ȃ��ƍl����̂����R�v�Ɛ����B�@���炩�ɖƉu�������Ă���ȂǓ��ʂȏ��Ȃ���u���Ȃ��Ȃ����E�C���X���A�ˑR�ɑ̓��ő�����Ƃ������Ƃ͍l���ɂ����v�Ƙb�����B (����^�C���Y = 5-18-20)
�Q�ƋL�� (5-10-20)
���@���@��
4 ���މ@ �� 15 ���ɂ܂��Ǐ�@�L���� 40 ��j�����ėz��
�L�������R�s�� 17 ���A4 �� 12 ���Ɋ������m�F���ꂽ���s�� 40 ��̌������j���ɂ��āA�މ@��ɍēx�A�z�������������Ɣ��\�����B�@�����̊����҂͉��� 166 �l�ƂȂ����B�@�Ăїz�������������j���� 5 �� 4 ���ɂ�������މ@�B�@����ŗ×{���Ă������A15 ���ɕ@�Â܂��̂ǂ̒ɂ݁A���ɁA�S�g�̌��ӊ��Ȃǂ̏Ǐo�āA16 ���ɋA���ҁE�ڐG�ҊO������f���A17 ���� PCR �����ōēx�A�z�������������B�@�L�������ōėz�������������̂� 2 ��ځB (asahi = 5-17-20)
���@���@��
�k�C���ŐV���� 8 �l�������A���� 1 �l�͍ėz���@1 �l���S
�k�C���ƎD�y�s�� 17 ���A�����ŐV�^�R���i�E�C���X�̊����҂�V���Ɍv 8 �l�m�F�����Ɣ��\�����B�@���̂��� 1 �l�͍ėz���������B�@�����̊����҂͉��� 1,014 �l�ɂȂ����B�@�܂��D�y�s�̊����� 1 �l�����S���A�����̎��S�҂� 75 �l�ƂȂ����B (asahi = 5-17-20)
���@���@��
1 ���ɑމ@�����ߔe�s�̏����A�Ăїz���@���ꌧ��������
���ꌧ�� 17 ���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ�����APCR ������ 2 �x�A���ƂȂ��đމ@�����ߔe�s�� 60 ���Ј������ɂ��āA�Ăїz�����m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�@�����V���̏W�v�ł́A�����̊����҂͌v 144 �l�ƂȂ����B�@���͗z���������A�̓��Ɏc�����E�C���X�̍Ċ������Ȃ̂��A�V���Ȋ����Ȃ̂��ȂǏڂ������ׂ�K�v������Ƃ��āA�V�K�����҂Ɋ܂߂邩�ǂ����̔��f��ۗ����Ă���B
���ɂ��ƁA������ 4 �� 12 ���Ɋ������m�F���ꂽ��A2 �x�A���̌��ʂ��ł� 5 �� 1 ���ɑމ@�B�@9 ���ɂȂ��Ă̂ǂ̈�a������M���������B�@����ȍ~�A���ɏǏ�͂Ȃ��������A13 ���ɍČ��������Ƃ��� 16 ���ɂȂ��ėz�����m�F���ꂽ�B�@���݂́A�����ǎw���Ë@�ւɓ��@���Ă���B�@�����͑މ@����O�o�� 3 ���قǂŃ}�X�N�𒅗p���Ă����Ƃ����B�@�Z���ڐG�҂͓����� 1 �l�B�@���ꌧ�� 14 ���A�V���Ȋ����҂� 4 �� 30 ���ȍ~�m�F����Ă��Ȃ��ȂǂƂ��āA�x�Ɨv�����ꕔ�������ĉ��������B (asahi = 5-17-20)
�k�C���� 7 �l�����m�F�@���������� 1,000 �l������@�V�^�R���i
�k�C�����ł� 16 ���A�D�y�s�� 5 �l���܂� 7 �l���V�^�R���i�E�C���X�Ɋ����������Ƃ��V���ɔ��\����A�����Ŋ������m�F���ꂽ�l�� 1,000 �l���ĉ��� 1,006 �l�ƂȂ�܂����B�@�܂��A���������D�y�s�� 70 ��̒j�������S���A�����ŖS���Ȃ����l�� 74 �l�ƂȂ�܂����B�@�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A�D�y�s�� 5 �l�A�Ύ�n���� 1 �l�A�I�z�[�c�N�C���� 1 �l�̍��킹�� 7 �l�ł��B
�D�y�s�Ŋ������m�F���ꂽ�l�̂����A40 �㏗���̓N���X�^�[���������Ă���s���̃R�[���Z���^�[�ɋΖ����Ă���ق��A70 �㏗���͖k�C������Z���^�[�ɓ��@���Ă���Ƃ������Ƃł��B�@�Ύ�n���� 30 �㏗���͎D�y�s�k��ɂ�����V�l�ی��{�݁u��˃A�J�V�A�n�C�c�v�̐E�����Ƃ������Ƃł��B�@���̂����D�y�s�̊����҂͉��� 620 �l�ƂȂ�܂����B�@�܂��A����܂łɁA���������D�y�s�� 70 ��j�������S���A�����ŖS���Ȃ����l�� 74 �l�ƂȂ�܂����B�@�����Ŏ��Â��I�����l�͉��� 589 �l�ƂȂ��Ă��܂��B
�D�y�s�́A�����҂ƐE�� 85 �l�̊������m�F����Ă���u��˃A�J�V�A�n�C�c�v�ɂ��āA�����g��Ɏ��~�߂�������Ȃ����Ƃ��d���݂āA�{�ݓ��Ɍ��n���{����ݒu�������Ƃ𖾂炩�ɂ��܂����B�@���{�������A���^�C���Ō��n�̏���c�����A�{�ݑ��Ɗ����h�~���v���ɐi�߂Ă����Ƃ��Ă��܂��B�@�D�y�s�ی������ǂ̎O�X�Y�ی������́u���{���Ɏs�̐E�����풓�����邱�ƂŌ��n�̏����^�C�����[�ɓ��肵�A�����h�~��ɂ������Ă��������v�Ƙb���Ă��܂����B (NHK = 5-16-20)
1 ���l�K�͂̍R�̌����A�����ɂ����{�@���J���\��
�������M�����J������ 15 ���A�t�c��̋L�҉�ŐV�^�R���i�E�C���X�̊������̗L���ׂ�R�̌����� 1 ���l�K�͂ōs���ƕ\�������B�@������Η�������n�߂�B�@4 ���ɐ�s���Ď��{�����R�̌����ł͓����s�� 0.6%�A���k 6 ���� 0.4% ���z�����������A�����L�b�g�̐��\�ɖ�肪����\��������A�]��������B�@�R�ۗ̕L�𐳊m�ɒ��ׂ邽�ߑ�K�͒����ɏ��o���B
�����ł͍R�̗̂L�������łȂ��R�̗ʂ����ׂ�B�@�o�ϊ����̖{�i�I�ĊJ�Ɍ����āA���m�Ȋ����̔c�����}�����B�@�R�̌����͓����s����{�A���ꌧ�Ȃǂ��Ǝ��Ɏ��{����ӌ��������Ă���B�@���J�Ȃ� 4 ���A�C�O�ŏ��F���ꂽ�����L�b�g 4 ��ނƌ������� 1 ��ނ̐��\��]�����邽�ߓ����A���k�ōR�̌��������{�����B�@���{�ԏ\���Ђ�ʂ��Č������t�����������B
���̌��ʁA�s�� 500 �l���̂��� 3 �l (0.6%)�A���k 6 �� 500 �l���̂��� 2 �l (0.4%) ���z���������B�@���Ԃ��ۗL���闬�s�O�̍�N 1 - 3 ���̊֓��E�b�M�z�n��� 500 �l���̌��t�ł� 2 �l (0.4%) ���z���������B�@���s�O�̌��̂�����z�����o�����ƂȂǂ�����Ƃ́u�i�������ʂ�����ėz���ƂȂ�j�U�z�����܂܂�Ă���ƍl������v�ƕ��́B�@����̌��ʂ����Ō����L�b�g�̐��\��R�ۗ̕L����]������͓̂K�łȂ��Ƃ��āA�V���ȑ�K�͒������K�v�Ɣ��f�����B (nikkei = 5-15-20)
�����s�ŐV���� 30 �l�������@9 ���A���� 50 �l�����
�����s���� 14 ���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V���� 30 �l�m�F���ꂽ���Ƃ��W�҂ւ̎�ނł킩�����B�@1 ��������̊����Ґ��Ƃ��Ă� 9 ���A���� 50 �l����������B�@12 ���܂ł̊����҂̗v�� 4,997 �l�������B (asahi = 5-14-20)
���Q���A�V���� 17 �l�������@�a�@�ŏW�c�����@�V�^�R���i
���R�s���̕a�@�̓��@���҂�E���Ȃǂ��킹�� 17 �l���A�V�^�R���i�E�C���X�Ɋ������Ă������Ƃ��V���Ɋm�F����܂����B�@���̕a�@�ł́A���E���Ƃ��ċΖ�����j���Ƃ��̓����̊��������łɊm�F����Ă��āA���Q���͕a�@�ŏW�c�������N�����Ƃ��Ă��܂��B�@�V���Ɋ������m�F���ꂽ�̂́A���R�s���̖q�a�@�ɓ��@���� 50 �ォ�� 90 ��܂ł̊��҂Ȃ� 11 �l�ƁA���̕a�@�ŊŌ����̐E���Ƃ��ċΖ����Ă��� 30 �ォ�� 50 ��܂ł̒j�� 6 �l�̍��킹�� 17 �l�ł��B
���̕a�@�ł́A���E���Ƃ��ċΖ����Ă��� 30 ��̒j�������M�Ȃǂ̏Ǐ��i���A���̌�A12 ���ɂȂ��Ċ������m�F����A������ 40 ��̏����ƁA�j���̉Ƒ��� 10 ��̏����� 13 ���A�������m�F����Ă��܂����B�@���̂��߁A���Q���⏼�R�s���a�@�̐E������@���҂Ȃǂ̌�����i�߂����ʁA�V���� 17 �l�̊������m�F����A���͂��̕a�@�ŏW�c�������N�����Ƃ��Ă��܂��B
���̂����ŁA�����o�H�ɂ��Ă͈�ʂ̊O���Ƃ͋�ʂ��ꂽ�a���Ŋ������������Ă��邱�Ƃ�A���@���҂ɑ��O������̌������̎��l�����߂Ă������ƂȂǂ���A�a�@�̐E�����������A��������@�������ɂȂ������\��������Ƃ��Ă��܂��B�@���Ȃǂ͍���A�����҂̏ڂ����s�����m�F����ƂƂ��ɁA�Z���ڐG�҂ւ̌������s���A�̔c���Ɗ����̊g��h�~�ɓw�߂邱�Ƃɂ��Ă��܂��B
17 �l�̊����m�F�́A���Q���� 1 ���ɔ��\���������҂̐��Ƃ��Ă͍ł������A�����Ŋ������m�F���ꂽ�̂� 68 �l�ƂȂ�܂����B�@���Q���̒����m���͋L�҉�ŁA���R�s���̕a�@�ŐV�^�R���i�E�C���X�̏W�c�������m�F���ꂽ���Ƃɂ��āu�����o�H�͂܂��킩���Ă��Ȃ����A�z���Ɗm�F���ꂽ�l�ƐڐG���������l�ɂ͎���ҋ@�����肢����ȂǁA����ȏ�̊����g��h�~�ɃX�s�[�h���������đΉ����Ă���v�Əq�ׂ܂����B
�܂��A�����m���͈��Q�����ł̊����m�F�̏ɂ��āA13 ���A�����[�����Ɛ����o�ύĐ��S����b�ɘA���������Ƃ𖾂炩�ɂ��������Łu�ً}���Ԑ錾�̉����ɂ��Ĉ��Q�����ǂ̂悤�ɂȂ邩�͂킩��Ȃ����A�ǂ̂悤�ɂȂ낤���A����܂Ō����ɂ��`�����Ă���Ƃ���A���� 31 ���܂ł͌��݂̌x�����x�����ێ����Ή����Ă��������v�Əq�ׂ܂����B (NHK = 5-14-20)
�u�R���E�R�̌�����i�߂����v���r�m���A���Ɏx�����߂�
�����s�̏��r�S���q�m���� 11 ���A�V�^�R���i�E�C���X���S�����鐼���N���o�ύĐ����Ɠs���ʼn�k�����B�@���r�m���͉�k��A�w�ɁA�]���� PCR �����Ƃ͕ʂ̍R���E�R�̌��������{���邽�߁A���Ɏx�������߂����Ƃ𖾂炩�ɂ����B�@�u���ꂼ��̓��������āA�s�Ƃ��Ă�������i�߂����v�Əq�ׂ��B
�R�������̓E�C���X���`�Â��邽��ς����ڌ��o������@�ŁA���� 13 ���ɂ����F����ƌ����܂�Ă���B�@�R�̌����͑̓��ŖƉu�������N�����ۂɂł���R�ׂ̂���̂ŁA�ߋ��̐V�^�R���i�̊�������������B�@������� PCR ���������������ʂ�����������Ƃ���Ă���B�@���r�m���́u�R���E�R�̌����̗L�������m�F���āA���₩�ɓ�����}���Ă������������v�Əq�ׂ��B
���r�m���́A�ً}���Ԑ錾�̉�����ɂ��Đ������Ƙb�������Ƃ����炩�ɂ����B�@���̏�Łu�l�X�Ȑ����␔�l���i������Ɂj���邪�A�ǂ̂悤�Ȍ`���l������̂��O�����ēs�ɒm�点�Ăق����Ƃ��肢�����v�Əq�ׂ��B (�y�����l�Aasahi = 5-11-20)
�V���� 70 �l�����m�F�@���������҂͌v 1 �� 5,860 �l��
�V�^�R���i�E�C���X�̍����̊����҂� 10 ���ߌ� 9 �����_�ŁA70 �l���V���Ɋm�F����A�v 1 �� 5,860 �l�ƂȂ����B�@���҂� 9 �l������ 633 �l�B�@1 ��������̊����Ґ��́A8 ���ȗ��Ă� 100 �l������B�@�����s�ł́A�V���� 22 �l�̊������m�F���ꂽ�B�@1 ��������̊����m�F�Ґ��� 50 �l�������̂� 5 ���A���B�@�_�ސ쌧�ł͐V���� 13 �l�̊����� 2 �l�̎��S�����\���ꂽ�B�@�S���Ȃ��������� 1 �l�́A�N���X�^�[�i�����ҏW�c�j���������Ă��鐹�}���A���i��ȑ�w���l�s�����a�@�̓��@���҂ŁA�s���� 80 ��j���B�@���a�@�֘A�̊����҂͌v 58 �l�ɁB
���{�ł� 11 �l�̊������m�F���ꂽ�B�@�{�́A�x�Ƃ�O�o���l�v���̒i�K�I�����Ɍ����ēƎ���u��ヂ�f���v���f���A�@ �����o�H�s���̊����҂� 10 �l�����A�A �z������ 7% �����A�B �d�Ǖa���g�p���� 60% ������ 7 ���A���B���Ƃ��Ă���A���̓��� 3 ���A���ƂȂ����B�@�k�C���ł͎D�y�s�ŐV���� 9 �l�̊����� 5 �l�̎��S���m�F���ꂽ�B�@���s�{�͐V���Ȋm�F���[���ŁA3 �� 19 ���ȗ� 52 ���Ԃ�Ɋ����[�����L�^�����B (asahi = 5-10-20)
���V�^�R���i�� 16 �l�������@�N���X�^�[�����̂������܂�V���A�є\�̕a�@�@�V���ɉz�J�̕a�@�ł�
���Ȃǂ� 9 ���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����҂��V���� 16 �l���������Ɣ��\�����B�@����܂łɊm�F���ꂽ�z���҂� 962 �l�i�`���[�^�[�A���Ҋ܂ށj�A���҂� 41 �l�ƂȂ����B�@�d�ǎ҂� 10 �l�B�@�����҂̎w���Ë@�ււ̓��@�� 79 �l�A��ʈ�Ë@�ււ̓��@�� 136 �l�A�z�e���×{�� 63 �l�A����ҋ@�� 102 �l�B�@281 �l���މ@���A�×{�I���� 244 �l�ƂȂ����i9 ���ߌ� 6 �����݁j�B
���ɂ��ƁA���NJ��ŐV���Ɋ��������������̂� 8 �l�B�@����܂łɊ����҂��o�Ă����V���s�̖x�m���a�@�ł́A�Ō�t�P�l�Ɠ��@���� 1 �l�̊������m�F���ꂽ�B�@�є\���a�a�@�ł���Ï]���� 3 �l�̊��������������B�@�������s�ɂ��ƁA�V�^�R���i�E�C���X�̃N���X�^�[�i�����ҏW�c�j���������Ă���u�ʂ̍�����{���f�B�J���Z���^�[�i�k��y�C���j�v�ŐV���� 5 �l�̊����������B�@�ق��ɓ��s�ݏZ�� 50 ��j���� 70 �㏗���̊��������������B�@�j���͓��@���ŁA�����͓��@�\��B
�z�J�s�ɂ��ƐV���ɖk�C�a�@�i���s�������j�ɋΖ�����s���ݏZ�� 60 �㏗���Ō�t�̊��������������B�@�����͌y�ǂŌ��ݓ��@���B�@���a�@�Ŋ����҂��m�F���ꂽ�̂͏��߂ĂŁA�����ƐڐG�̂������a�@�X�^�b�t 5 �l�Ɗ��� 1 �l������ PCR �������Ă���Ƃ����B (��ʐV�� = 5-10-20)
�����`���́u�R�̌����L�b�g�v�Ɉ�Ë@�ւ���\�����ݎE�� - �킸�� 4 ���Ԃ� 15 �����I��
�\�t�g�o���N�O���[�v����В��̑����`����5��9���A���g��Twitter�A�J�E���g�ŁA��Ë@�����ɖ����Œ���u�V�^�R���i�R�̌����L�b�g�v�̐\�����ݎ�t���J�n�B�������ɐ\�����݂���1�����ו��ł���15���ɒB���A��t���I���������Ƃ\�����B�@�����́A5��2���Ɂu�\�t�g�o���N�O���[�v�̎Ј��ƉƑ��̑S�ĂɐV�^�R���i�R�̃e�X�g�������j����v�ƃc�C�[�g�B200�����̌����L�b�g���������Ƃ𖾂炩�ɂ����B���킹�āA���p����]�����ÊW�҂���W�҂ɂ������Œ�����j�������Ă����B
�܂��A5��8���ɂ͌������ʂ̎ʐ^�ƂƂ��Ɂu���̗F�l�Ŋ����҂̏ꍇ�A�R�̃e�X�g�ł��z���̃��C�������m�ɏo�܂����v�ƃc�C�[�g�B���̌������x�ɖ�肪�Ȃ����Ƃ��A�s�[�������B�@�����āA5��9��13��12���ɁA��Ë@�ցE�f�Ï��E���Ȉ�@�Ȃnj����̍R�̌����L�b�g�����̎�t�t�H�[���i�uGoogle�t�H�[���v�j���ATwitter�Ō��J�B���ꂩ��킸��4���Ԍ��17��34���ɁA671�̈�Ë@�ւȂǂ���15�����̐\�����݂�����A��1���̎�t���I���������Ƃ\�����B�@��2�����ו��i18���j�͓�����A���߂Ď�t���ĊJ����Ƃ��Ă���B (������ACnet = 5-9-20)
PCR�A�s�����܂�Ȃ��ڈ��ɘa�@��]�ґ��֑̐�������
�V�^�R���i�E�C���X�̌����g��̒x��ɕs�M�������܂�Ȃ��APCR �����ɂȂ��鑊�k�̖ڈ��� 8 ���A�ύX���ꂽ�B�@37.5 �x�ȏ�̔��M�Ȃǂ̏������Ȃ��Ȃ�A��������]����l�͑����邱�Ƃ��\�������B�@���₩�Ɍ���������̐��Â��肪�}�����B
�ی����u���̖ڈ��A�h�g��̖����ʂ����Ă����v
���M�Ȃǂ̏Ǐo�Ċ������^���l���o���ꍇ�A�ی����Ȃǂ̋A���ҁE�ڐG�ґ��k�Z���^�[�����k�����ƂȂ��Ă����B�@��f�̖ڈ��́A�������邩�ǂ����f�����p�̋A���ҁE�ڐG�ҊO�����Љ�邩�ǂ����̔��f�ɂ��g���Ă����B�@�k���{�̂���ی����ɂ͌�������]���鑊�k���A�d�b�ő��X�Ɗ��Ă���B�@���ɂ͕s��������A�ƌ��������߂�l�������Ƃ����B�@�S���҂͍��̖ڈ����K�v���̍����ɂȂ�A�u���̖h�g��̖������ʂ����Ă����v�Ɩ������B
���C�n���̕ی������́u���Ґ�������قǑ����Ȃ������̂ŁA���Ȃ��^�p�ł��Ă����v�ƌ����B�@����ŁA�����҂��}�������s�s���ɂ��āA�u�ی����̖{���̖����́A�����g���h�����ƁB�@���̂��߁A�����o�H���ǂ���l�̒����⌟����D�悵�A�ڈ������i�ɉ^�p����������Ȃ������ʂ�����̂ł͂Ȃ����B�v�Ƃ݂�B�@�u�����́A�d�lj��������Ȑl�𒆐S�Ɍ����ɂȂ��Ă����v�Ɠ����s���̕ی����̒S���҂͘b���B�@�Ώۂ��i���Ă����w�i�ɂ́A�]�ސl���E�����Č��ꂪ�������邱�Ƃ�h���ӎ����������Ƃ����B
�ی����̐V�^�R���i�֘A�Ɩ��́A���҂�����������ɓ͂��o���Ē������錋�j�Ȃǂ���܂ł̊����ǑΉ��ƈႢ�A�d�b���k�⌟���̉ۂ̔��f�̒i�K����ւ��B�@��t�Ƃ̒����APCR �����̌��̍̎�ȂǑ���ɂ킽��A�u�傫�ȕ��S�ƂȂ��Ă���v�ƑS���ی�������̓��c���F��͂����B�@�ی���������ɁA��������オ�K�v���ǂ����f���A����������̐��̐������i�݂���B
������f�̖ڈ��̕ύX�ŁA��������]����l�͑����邱�Ƃ��\�z�����B�@�����s���̕ی����̒S���҂́u�\���Ȏ���Ԑ��𐮂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�a����×{�{�݂��K�v�ŁA���͑S�̂̃o�����X���l����ׂ����B�v�Ƒi����B�@�����ǂɏڂ�������F�E�O���[�o���w���X�P�A�N���j�b�N�@�����A�u�Ώۂ��L�����Ă����₩�Ɏ�f�ł�����������Ă��Ȃ���Ί��҂̕s���͍��܂�B�@�n��̈�Ë@�֑S�̂ŏ[��������K�v������B�v�Ƙb���B (���Y�S�q�A�����疾�A���ڍʎq)
���������j���u�����ł�Ȃ����ԁA�s���������v
�u�����Ƒ�����Ă����̂ɁA�����炩�B�@�������߂Ă����A�s���Ȗ����𑗂炸�ɍς̂ɁB�v�@4 �����{�Ɋ������m�F���ꂽ�_�ސ쌧�� 40 ��̒j����Ј��́A�����J���Ȃ��������u�ڈ��v���APCR ��������ǂɂȂ����B�@3 �����{�A38 �x�ȏ�̔M�� 3 ���������B�@�u����������Ȃ����B�v�@�n���̐f�Ï��ɋ삯�����A�x���̏Ǐ�͂Ȃ������B�@�u4 ���A�����ڈ��B�@�������M������Ό������l���܂��傤�v�ƈ�t�Ɍ����A��M�܂���������ċA��B�@�����A�M�� 36 �x��ɉ��������B
���� 4 ����{�A�[�H�̃L���`�̏L���������Ȃ������B�@�����̃R�[�q�[�����L�B�@�ʂ̕a�@����f���ďL�o�ُ̈�����x���i�����B �悤�₭��ꂽ�����ŁA�z���Ɗm�F���ꂽ�B�@�m�F�܂ł̖� 2 �T�ԁA�j���͕s����������܂܁A�Ȃ� 5 �̖��̂��鎩��ʼn߂������B�@�����ɕ�������A���C�� 2 ���� 1 ��B�Ƒ��Ƃ̐ڐG���ɗ͔������B�@���ʓI�ɉƑ��͊������Ȃ��������A�u���������Ă�����Ǝv���� �c�B�v�@���ł�������o����B
�����s���ň�l��炵������j�� (29) �́A4 ����{����M�ƌ����������ɋꂵ�B�@�M�͈ꎞ�� 40 �x�߂��ɁB�z�c�̒��ŕی����ɓd�b���������������Ԍo���Ă��Ȃ��炸�A���߂��B�@�I�����C���f�ÂŎ�f������t�o�R�ŁA�ی����ƘA���������̂� 1 �T�Ԉȏ�߂�����B�@�����A�����ɂ͔��M�O�����ē�����Ȃ������B�@�u�����̑̉����݂Ă���v�ƌ��߂������A�j���̑̉��́A�u�ڈ��v������� 37.4 �x�ɁB�@���ǎ�f�͂����A���̌�͏��X�ɉ����B�@�u�Ǐ������Ă��钆�A�����ł肪�Ȃ����Ԃ͕s���������v�ƌ����A�����̊Ԍ����L���邱�Ƃ����}����B
�����s������ŕv�Ƒ��q�� 3 �l��炵�̏��� (53) �̉ƒ�ł� 4 �����߂ɑ��q���A�����ĕv�Ȃ��������Ŕ��M�B�@�������ӊ��ŐQ����A�悤�₭�ی����ɓd�b�������B�@���̍��ɂ͔M���������Ă������߂��A�S���҂Ɂu�����̃n�[�h���͍����v�ƌ����A�����͒f�O�����B�@���������̗L���͂킩��Ȃ��܂܁B�@�����́u�f�����f�f�ł���悤�ɂȂ�����v�Ƙb���B (���R�S�j�A�F��m���A�ē����q)
���J���u������v�A�u�e�͓I�ȑΉ����A�Ɛ\���グ�Ă����v
�������M�E�����J������ 8 ���̊t�c���ŁA�ڈ������k���f�̊�̂悤�ɂƂ炦���Ă���Ǝw�E���A�u��X���猩��Ό�����v�ƌ�����B�@�����̂Ɂu���x�ƂȂ��ʒm���o���A���k���f�͒e�͓I�ɑΉ����Ă������������Ɛ\���グ�Ă����v�Ƌ��������B�@�ڈ������\���ꂽ 2 �� 17 ���A�������J���͉�Łu�ʏ�̕��ׂ�C���t���G���U�Ȃ畽�ς��� 3 - 4 ���ʼn��݂��邪�A�i�V�^�R���i�́j����ɑ����Ƃ����w�E���������B�@��̓I�Ȑ����͐��Ɖ�̈ӌ��܂����B�v�ƌ�����B�@�����A���̌�A�ی����̑��k�Z���^�[�ɁA�����f����A���ҁE�ڐG�ҊO���ł̎�f�𑊒k���Ă��A�Љ�Ă���Ȃ��Ƃ������P�[�X���o�Ă����B
���J�Ȃ� 3 �� 13 ���A�ڈ��͈ꗥ�ɓK�p�����A�Y�����Ȃ��l�ł��܂��ď_��ɔ��f����悤�����̂ɒʒm�����B�@��ʂ̈�Ë@�ւ��犴���̋^��������Ƒ��k���������P�[�X�́A��Ë@�ւ̔��f�d���ĕی�������f�����邱�Ƃ����߂��B�@�� 22 ���ɂ͉��߂Ēʒm�������̂ɏo�����B �u37.5 �x�ȏ�̔��M�� 4 ���ȏ㑱���v�Ɓu�������邳�v���A���������Ȃ��Ƒ��k�ł��Ȃ��Ǝ~�߂��Ă���Ƃ̐�������Ǝw�E���A�ǂ��炩�ɓ��Ă͂܂�Ύ�f�̒��������Ăق����ȂǂƋ��߂��B�@�������邳�⑧�ꂵ���̂���l�� 4 ���ȏ㑱���Ȃ��Ă��A�����ɑ��k���Ă��炢�A��f�̒���������悤���߂��B
�������A�������番����ɂ����Ɣᔻ�����������ڈ��̕����� 3 �J���߂��ς��Ȃ������B�@8 ���̉�ŁA���������x���̂ł͂Ȃ����A�Ɩ��ꂽ�������J���͂����q�ׂ�ɂƂǂ߂��B�@�u�x���Ƃ��l�X�ȋc�_�����������Ă���B�@����������}���Ă���B�v�@���J�Ȃ̒S���҂̐����̏�ł́A�ŏ��̖ڈ���������₷���������A�ύX���x�ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�ƕw���玿�₪���������B�@�S���҂́u���Ƃ̐搶�ɁA���_���������Ȃ��ƁA�����̐l�ɗ�������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��������v��������A�����ɂȂ����v�ƌ�����B
����̕ύX�ɂ��āA�֒J����E������w�y�����i�ЊQ�Љ�Ȋw�j�́u���������^��������Ă��ڈ��̏����ɓ��Ă͂܂�Ȃ��� PCR ��������i�K�Ɏ���Ȃ��Ƃ����̂�����ŁA��ÂɃA�N�Z�X���铹���i���Ă��邱�Ƃɑ����̐l���s���A�s�M��������Ă����v�Ǝw�E���������ŁA�u�����̏����Ȃnj������߂�������͈��|�I�ɕs�����Ă���B�@�w����x�A�w����s���x�ȂǂƂ��܂����̂ł͂Ȃ��A�̐������Ɠ������̍������ɗ͂����Ȃ��ƁA�s������w���܂邾�낤�B�v�ƌ��B
���`�̊��[������ 8 ���̋L�҉�ŁAPCR �����̖ڈ��̕ύX�ɂ��āA�u���̏ɓK�������̂Ƃ��ׂ��A���J�Ȃɂ����āA���Ƃ��ÊW�҂̈ӌ����Ȃ��猟�����Ă���v�Əq�ׁA���J�ȂőΉ����Ă���Ƌ��������B�@�܂��A�u37.5 �x�ȏオ 4 ���A���v�Ƃ̖ڈ������������߂ɁA��������ꂸ�ɏd�lj���������ɂ��āA�L�҂���u���{�Ƃ��Ė�肪�������Ƃ͍l���Ă��Ȃ��̂��v�Ɩ��ꂽ���A�u��҂̐f�f�ɂ���āA�K�v�ȕ��͌������邱�Ƃ��ł��Ă���v�Ɠ�����ɂƂǂ߂��B (�x�c�����A�������Aasahi = 5-9-20)