J & J ワクチン、米 FDA が一時中断を推奨 まれに血栓
米製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソン (J & J) が開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、米食品医薬品局 (FDA) は 13 日、米国内での接種の一時中断を推奨すると発表した。 ごくまれではあるものの、深刻な副反応が起きているためという。 FDA によると、J & J のワクチンを接種した 6 人に深刻な血栓が生じたことが報告された。 6 人は 18 - 48 歳の女性で、1 人は死亡、もう 1 人も危機的な状況という。 米国ではこのワクチンがすでに 600 万回以上接種されている。
米疾病対策センター (CDC) は、14 日にこの問題について検討する会議を開く予定という。 FDA は「検討が完了するまで、一時的な中断を推奨する。 副反応の可能性について認識し、血栓が生じた際の治療を準備しておくことが重要だ。」としている。 FDA は J & J に加え、ファイザー製とモデルナ製の計 3 種類の新型コロナワクチンについて緊急使用許可を出している。 ホワイトハウスで新型コロナ対策を担うザイエンツ調整官は「J & J 製はこれまでの米国での接種の 5% 未満しか占めていない。 3 億人の米国人に十分な量のファイザー製とモデルナ製のワクチンを確保している」とし、「州などと協力し、J & J のワクチン接種が予定されている人には、速やかにファイザー製かモデルナ製に変更してもらえるようにしている」との声明を出した。
バイデン大統領も「十分なワクチンがあるということは、基本的に 100% 疑いがないことだ」と話した。 一方で、欧州連合 (EU) へのワクチン供給には懸念が生じている。 FDA の発表を受け、J & J は「欧州でのワクチンの展開を延期することを決定した」と発表した。 英アストラゼネカ製のワクチンの供給が遅れている EU では、J & J のワクチンを 4 - 6 月の 3 カ月で 5,500 万回分調達できると見込んでいた。 J & J のワクチンは接種が 1 回で済む点も期待されていたが、供給の遅れが続くと、EU 全体で接種計画の見直しが必要になる可能性がある。 (ワシントン = 合田禄、ブリュッセル = 青田秀樹、asahi = 4-14-21)
◇ ◇ ◇
J & J の新型コロナワクチン生産に競合他社が協力
アメリカのバイデン大統領は 2 日、製薬大手のジョンソン・エンド・ジョンソンの新型コロナウイルスのワクチンの生産に、同業のメルクが協力すると明らかにしました。
「本日、我々は大きな前進を発表します。 通常は競合している世界最大のヘルスケア・製薬会社の 2 社がワクチンで協力します。 ジョンソン・エンド・ジョンソンとメルクは協力して、ジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンの生産を拡大します。(アメリカ バイデン大統領)」
バイデン氏は 2 日、このように述べた上で、5 月末までにアメリカのすべての成人に十分なワクチンを提供できるという見通しを示しました。 また、バイデン氏は、学校の安全な再開に向けて今月末までにすべての教職員が少なくとも 1 回、ワクチンの接種を受けられるよう各州に対応を求めました。 (TBS = 3-3-21)
◇ ◇ ◇
接種 1 回の J & J ワクチン、米で使用許可 日本でも治験
米食品医薬品局 (FDA) は 27 日、米製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソン (J & J) が開発した新型コロナウイルスのワクチンについて 18 歳以上に緊急時の使用を許可した。 1 回の接種で十分な効果が得られるほか、通常の冷蔵庫で保管できるため、接種の加速が期待される。 米国で使用許可が出ているのは米ファイザーと独ビオンテック、米モデルナが開発したワクチンの 2 種類。 いずれも十分な効果を得るには 2 回の接種が必要としている。
FDA は J & J のワクチンについて、1 回の接種で新型コロナの発症率を 66% 減らす効果を確認。 重症化率も 85% 減らす効果があるとしている。 主な副反応としては接種場所の痛みや頭痛、倦怠感などだが、ほとんどは軽いという。 FDA は「(ワクチン接種による)利益がリスクに勝る」としている。 J & J は米国内で、3 月末までに 2 千万回、6 月末までに計 1 億回分を供給するとしている。 日本国内では治験が始まっているが、供給計画は決まっていない。 (ワシントン = 香取啓介、asahi = 2-28-21)
◇ ◇ ◇
米 J & J ワクチン、緊急時使用を申請 接種 1 回で効果
米製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソン (J & J) は 4 日、自社の新型コロナウイルスのワクチンについて、緊急時の使用許可 (EUA) を米食品医薬品局 (FDA) に申請したと発表した。 1 回の接種で効果が得られ、零下 20 度で 2 年、2 - 8 度で 3 カ月は安定的に保管できるといい、従来のワクチンの流通設備を使うことができる。
J & J はワクチンについて、米国や中南米、南アフリカでの臨床試験(治験)の結果、1 回の接種で新型コロナの発症を防ぐ効果が 66%、重症化を防ぐ効果が 85% あったとしている。 すでに使用を許可されている 2 種類のワクチンは 2 回の接種で約 95% の有効性とされる。 FDA は諮問委員会を開き、可否を決める。 許可を得られれば、米国では米ファイザーと独ビオンテック、モデルナが開発したワクチンに続き 3 種類目となる。 J & J は近く、欧州医薬品庁 (EMA) にも、承認申請をする。 (ワシントン = 香取啓介、asahi = 2-5-21)
国産ワクチンなぜ出遅れ? 過去にもあった「ギャップ」
新型コロナウイルスに対するワクチンの高齢者への接種が 12 日、始まる。 使われるのは海外製で、日本メーカーも開発に着手はしているものの、実用化のめどはたっていない。 国産ワクチンは、なぜここまで出遅れてしまったのか。 大阪府の創薬ベンチャー、アンジェスは昨年 6 月、国内で最初に新型コロナワクチンの治験を始め、500 人が参加した第 2 段階までの結果を解析中だ。 予定している最終段階の数万人規模の治験を終える時期はわからない。 当初は今春の実用化も期待されていたが、予定より遅れている。
同社の創業者、森下竜一・大阪大寄付講座教授は「感染症でのワクチン開発の経験がなく、データを積み重ねるのに時間がかかった。 海外では政府の援助で新しいタイプのワクチンの基本技術ができており、その差は大きい。」という。 高齢者に今回接種される予定のワクチンは、米ファイザー製の「m (メッセンジャー) RNA ワクチン」。 ウイルスの遺伝情報を使う新しいタイプで、スピード開発が可能になった。
第一三共は、同じタイプのワクチンの治験を今年 3 月下旬に始めた。 男女 152 人が参加し、今年中に 2 回の接種を終え、データがまとまる見込み。 だが、その後に必要となる大規模な最終治験の見通しが立っていない。 4 月 5 日にあった中期経営計画説明会で真鍋淳社長は、「新型コロナ向けだけでなく、将来発生しうる感染症にも利用可能な技術として、mRNA ワクチンを確立したい」と話した。 ほかにも開発に着手している国内メーカーは複数あるが、実用化のめどは見えていない。 (江口英佑、瀬川茂子)
開発支援の当初予算、米国は 100 倍
日本のワクチン開発は、海外に比べてどうして遅れたのか。 ワクチンに詳しい北里大の中山哲夫特任教授は、日本でかつてあった「ワクチンギャップ」と、感染症への危機意識の低さを指摘する。 日本では 1970 年ごろから、天然痘のワクチンなど予防接種後の死亡や後遺症が社会問題になり、訴訟も相次いだ。 92 年の東京高裁判決では国が全面敗訴。 それ以降の約 20 年間は、新しいワクチンの開発や海外からの導入などに消極的になり、使えるワクチンが海外に比べて少ない「ギャップ」の状態が続いた。
「単に海外よりワクチンの品目が少ないだけでなく、積極的な政策を執ってこなかった『ポリシーギャップ』の側面も重要だ」と中山さんは語る。 海外では 2000 年ごろから、重症急性呼吸器症候群 (SARS)、エボラ出血熱、中東呼吸器症候群 (MERS) など、死亡率の高いウイルス感染症が次々と流行。 それに対応するため、ワクチン開発が大きな課題となった。 mRNA ワクチンはもともと、がんの治療手段として研究されていたが、迅速にワクチンをつくれる技術として注目され、新型コロナに応用された。 生物兵器テロの対策として研究が進んだ経緯もあり、欧米のワクチン行政には安全保障策としての側面がある。
健康な人にうつワクチンには高い安全性が求められ、開発には長い時間がかかる。 日本は安定した需要が見込める定期接種のワクチンを、国の関与のもとで小規模なメーカーがつくる「護送船団」方式がとられてきた。 ワクチンが主に使われる子どもが減って市場が縮む中、国からの支援は乏しく、企業の開発意欲も高まらず、研究開発が進まない構造が続いた。
新型コロナを受け、米国は当時のトランプ政権が「ワープスピード作戦」を掲げ、有望なワクチン候補に 1 兆円規模の資金を投じた。 日本政府もこれまでに、治験の結果を待たずに企業の量産体制を支援するなどしてきたが、開発支援のための当初の予算額は 100 億円と、単純計算で 100 倍ほどの開きがあった。 アンジェスの DNA ワクチンなど、国内でも新しいワクチンの「種」はいくつかあったが、「この差が、開発遅れの決定打となった。(中山さん)」
低い信頼度、世論を見極めているうちに
日本人は副反応への懸念などから、ワクチンに対する信頼度が一般的に低いとされている。 川崎医科大の中野貴司教授(小児科)は、「国は、ワクチンの開発をどう支援するかについて、『まず世論の動向を見極めてから決める』という体質になっていたのではないか」とみる。 新型コロナは発生から感染の広がりがあまりに速く、世論を見極める間もなく、海外に先行された。 そう見えるという。 開発や量産が難しい中低所得国にワクチンを行き渡らせることも大きな課題だ。 日本がワクチンの開発力を高めることは、国内での「自給自足」だけでなく、こうした国にワクチンを供出できることにもつながる。
米デューク大の集計によると、4 月 2 日時点で、日本、米国など 27 カ国・地域の確保量が、世界全体のワクチン供給量の 54% を占めていて、中低所得国用にワクチンを共同購入して分配する仕組み「COVAX ファシリティー」が確保する量は 13% しかない。 特定の国だけで接種が進んでも、ワクチンをうてない地域が残る限り、そこでウイルスが残り続け、感染の脅威は消えない。 新型コロナワクチンの公平な分配を独立した立場で検証する世界 12 人の委員の 1 人、国立国際医療研究センターの蜂矢正彦医師は「新型コロナは日本だけでなく、世界共通の問題だということも忘れないでほしい」と話す。 (野口憲太、編集委員・田村建二、asahi = 4-10-21)
| 治験の進展 | 補助金 | ||
|---|---|---|---|
| 生産体制の整備 | 研究開発費 | ||
| 塩野義製薬(大阪)など | 国内治験を開始(昨年12月) | 223億円 | 14億円 |
| 第一三共(東京)など | 国内治験を開始(3月) | 60.3億円 | 1.5億円 |
| アンジェス(大阪)など | 国内治験を開始(昨年6月) | 93.8億円 | 20.1億円 |
| KMバイオロジクス(熊本)など | 年内に大規模治験開始の意向 国内治験を開始(3月) | 60.9億円 | 10.6億円 |
ファイザー製ワクチンの副反応、高齢者は「大幅に低い」 … 予想以上に年代間で差
米ファイザー製の新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応は、65 歳以上の高齢者では発生率が大幅に低いとする健康調査の中間報告を厚生労働省研究班がまとめた。 37.5 度以上の発熱は、全体では 38% に起きたが、高齢者は 9% と 4 分の 1 にとどまった。 抵抗力のある若い世代ほど副反応が強い傾向は知られているが、予想以上に年代間の差があることが浮き彫りになった。
9 日午後に開かれる厚労省の有識者検討会で報告される。 この調査は、2 月から接種を受けた医療従事者のうち約 2 万人が対象。 今回の中間報告では、1 回目の接種を受けた約 1 万 9,000 人と、2 回目も受けた約 1 万 6,000 人のデータを集計した。 それによると、2 回目の接種後の方が 1 回目より副反応が強く表れ、年齢が高くなるほど発生率が下がる傾向がみられた。
2 回目接種後に 38 度以上の高熱が出たのは、全体では 21% だったが、高齢者は 4% と大幅に低かった。 20 歳代では 30%、30 歳代では 25% だった。 だるさと頭痛は、全体の 69% と 54% にみられたが、高齢者では 38%、20% と低かった。 ただし、接種した腕の痛みは全体で 91% だが、高齢者でも 80% が感じており、他の副反応と比べると差は目立たなかった。
男女差も目立っており、女性の方が男性よりも副反応が強かった。 特に頭痛は、女性の 62% が訴えたのに対し、男性は 37% と差が大きかった。 37.5 度以上の発熱は女性 42%、男性 30% だった。 高齢者への優先接種は、12 日に始まる予定だ。 研究班の伊藤澄信・順天堂大客員教授は「一般に、年齢とともに免疫反応は弱まるため、高齢者の副反応の割合は低いと予想していたが、これほど大きな差が出るとは驚きだ」と話している。 (yomiuri = 4-9-21)
第一三共・KM バイオ、治験開始 コロナワクチン、安全性確認
第一三共は 22 日、東大と開発中の新型コロナウイルスワクチンについて、国内で臨床試験(治験)を開始したと発表した。 初期段階では約 150 人に接種し、安全性などを確認する。 明治ホールディングス傘下の KM バイオロジクス(熊本市)も同日、被験者への接種をスタートさせた。
第一三共のワクチンは、ウイルスの遺伝情報を伝える「メッセンジャー RNA」を人工合成して投与し、抗体を作る技術。 米製薬大手ファイザーや米バイオ医薬品企業モデルナのワクチンも同様の技術を使っている。 KM バイオ社は、感染力をなくしたウイルスを使う「不活化ワクチン」の開発を国立感染症研究所などと進めている。 初期段階は 210 人に接種し、抗体ができるかどうかなどを確認する。 年内に治験対象を広げ、2023 年度の実用化を目指す。 日本企業が開発する新型コロナワクチンでは、大阪大発ベンチャーのアンジェスが昨年 6 月に、塩野義製薬が 12 月に、それぞれ治験を始めている。 (jiji = 3-22-21)
500 万人中 30 人に血栓 … アストラ製ワクチン、独仏伊などで「一時停止」
【ベルリン = 石崎伸生】 英製薬大手アストラゼネカが開発した新型コロナウイルスのワクチンについて、ドイツとフランス、イタリア、スペインは 15 日、使用を一時停止すると相次いで発表した。 接種後に血栓ができる症例が報告されているためで、欧州では既にデンマークやノルウェーなどが一時停止している。 欧州連合 (EU) の薬事当局「欧州医薬品庁 (EMA)」は、18 日に緊急会合を開き、同社製ワクチンへの対応が必要かどうかについて結論を出す予定だ。
ドイツのイェンス・シュパーン保健相は 15 日、一時停止の決定について「予防的な措置だ」と説明した。 今後、EMA の判断を待って、再開するかどうかを決める。 独国内では同社製ワクチンの接種は 160 万回以上行われた。 このうちワクチン接種との関連が疑われる血栓の発症例は 7 人で、シュパーン氏は「リスクは低い」とも述べた。 フランス政府も EMA が判断を示すまで使用を停止する。 マクロン大統領は 15 日、「EMA が容認すれば、すぐに再開したい」と語った。
EMA によると、10 日時点で欧州で同社製ワクチンの接種を受けた約 500 万人のうち、血栓ができたのは 30 人という。 EMA は 15 日の声明で、血栓の症例について「一般と比べて多くはない」との見解を示した。 一方、同社は 14 日、英国や EU で同社製ワクチンの接種を受けた 1,700 万人以上のデータを調べた結果、特定の年齢層や性別で血栓のリスクなどが高まる証拠はなかったと発表し、安全性を強調した。 同社は、日本でも 2 月 5 日に承認を申請している。 (yomiuri = 3-16-21)
◇ ◇ ◇
血栓できて女性が死亡、アストラゼネカ製のワクチン接種を停止
【ロンドン = 緒方賢一】 デンマーク政府は 11 日、英製薬大手アストラゼネカが開発した新型コロナウイルスのワクチン接種を 2 週間停止すると発表した。 60 歳代の女性が接種後、血栓ができて死亡したことを受けた措置という。 ロイター通信によると、接種後に血栓ができたケースはほかにも明らかになっており、ノルウェーやアイスランド、イタリアなどもアストラゼネカ製のワクチンの接種を見合わせた。
ただ、接種と血栓との因果関係は不明で、欧州連合 (EU) の薬事当局「欧州医薬品庁 (EMA)」は「現時点ではワクチンの副反応とする証拠はない」として接種を続けても問題ないとしている。 EMA によると、10 日現在、欧州で同社製ワクチンの接種を受けた約 500 万人のうち、血栓塞栓(そくせん)症を発症したのは 30 人という。 同社は、日本でも 2 月 5 日に承認を申請している。 (yomiuri = 3-12-21)
◇ ◇ ◇
アストラゼネカ製ワクチン接種後の死者 5 人に 因果関係は不明
日本でも春ごろから接種が始まる見通しとなっているアストラゼネカ製の新型コロナワクチンをめぐり、韓国の保健当局は 4 日、新たに 3 人がワクチン接種後に死亡したと発表しました。 イギリスの製薬大手・アストラゼネカ製のワクチン接種後に死亡したことが新たに確認されたのは、韓国国内の療養型病院に入院していた 50 代の男性 2 人と 20 代の女性です。 いずれも基礎疾患があったということで、3 人のうち 1 人は接種から 15 時間後に、残る 2 人はおよそ 40 時間後に死亡しました。
韓国ではアストラゼネカ製のワクチン接種は先月 26 日から始まりましたが、接種後の死亡が確認された人は、3 日、4 日の 2 日間であわせて 5 人となっています。 因果関係は今のところ明らかになっていませんが、韓国政府は原因を調査するとしています。 (TBS = 3-4-21)
◇ ◇ ◇
韓国でワクチン接種後に 2 人死亡
【ソウル】 韓国疾病管理庁は 3 日、新型コロナウイルスワクチンの接種後に死亡した事例が 2 件あったと明らかにした。 ワクチンと死亡の因果関係は不明で、同庁が調査している。 死亡したのは 50 代と 60 代の男性。 2 人とも長期療養者向け病院に入院し、英アストラゼネカ製のワクチンを接種後に呼吸困難や発熱などの症状が表れ、その後死亡した。 同庁によると、韓国でこれまでワクチン接種を受けたのは計約 8 万 7,400 人。 そのうち接種後に頭痛などの症状が発生した事例として 209 件が報告されている。 (jiji = 3-3-21)
中国製ワクチン接種の男性 2 人死亡 香港
香港政府は 13 日、中国製の新型コロナウイルスのワクチンを接種した男性 2 人が死亡したと発表しました。 ワクチンとの因果関係はわかっていませんが、2 週間あまりで 6 人が接種後に死亡していて、接種のキャンセルが増えています。 香港政府は 13 日、中国のシノバックが製造した新型コロナウイルスのワクチンを接種した 67 歳と 80 歳の男性が接種の数日後に死亡したと発表しました。 2 人とも糖尿病や高血圧の持病があったということです。
香港では、一般市民のワクチン接種が始まってから 2 週間あまりで 55 歳から 80 歳の合わせて 6 人が接種後に死亡しています。 当局は「ワクチン接種と死亡の因果関係は確認されていない」としています。 ただ、市民の間では不安が広がっていて、シノバックのワクチン接種を予約したものの接種会場に現れず、キャンセルする人が 3 割に達する日も出てきています。 これに対し、香港政府の林鄭月娥行政長官は、「ワクチン接種のメリットは、リスクを上回っている」などと市民に積極的な接種を呼びかけています。 (日テレ = 3-14-21)
コロナの変異、世界で追跡 遺伝情報シェアが対処の鍵に
新型コロナウイルスは一定の頻度で遺伝情報の変異を蓄積して、時に感染力などの性質を変えている。 どんな変異が起きているのかを世界中で共有する仕組みも整備され、新型コロナの研究は従来にないスピードで進んでいる。
変異とは「設計図」のコピーミス
2020 年 4 月、米国のチームによる、専門家の査読を受ける前の論文が公開され、研究者の注目を集めた。 新型コロナウイルスの遺伝情報に生じたたった一つの変異がウイルスの感染力を強め、世界的な感染拡大の「主流」になっている。 論文はその可能性を示唆していた。 その後の数カ月で、中国・武漢市で初めて確認されたウイルスはほぼ検出されなくなり、この変異を持つウイルスが取って代わった。 変異は「D614G」と呼ばれ、日本でいまも感染が続くウイルスに受け継がれている。
新型コロナウイルスの遺伝情報は、ウイルスの設計図である「RNA」と呼ばれる物質に書き込まれている。 RNA は、塩基と呼ばれる物質が約 3 万個並んだ構造をしている。 塩基には 4 種類あり、A、U、G、C という記号で表される。 新型コロナウイルスが感染した細胞内で増えるとき、自分の RNA をコピーするが、そのとき、ある塩基が別の塩基に置き換わったり、欠落したりするミスが起きる。これが変異だ。 新型コロナはインフルエンザウイルスなどと比べてミスが少ないとされ、ミスが受け継がれる頻度は、1 カ月で約 3 万個の塩基のうち 1 - 2 個だ。
塩基の並びが変わると、その情報をもとに作られ、たんぱく質を構成するアミノ酸の並びも変わって、たんぱく質の構造まで変わる場合がある。 冒頭に紹介した D614G 変異では、塩基の並びが変わったことで、ウイルス表面の「スパイク」と呼ばれるたんぱく質をつくる 614 番目のアミノ酸がアスパラギン酸(略号 D)からグリシン (G) に変わり、スパイクの構造も変わった。
スパイクは、ヒトの細胞の表面にある「受容体」と呼ばれる分子と結合して感染の足場となるが、国立感染症研究所の徳永研三・主任研究官らの研究によると、この変異でウイルスの細胞への侵入効率が、変異がない場合に比べて約 3.5 倍になっていた。 徳永さんは「この変異によりヒトの受容体にさらに適合するようになったという点で、現在知られている変異の中でウイルスの性質へ最も大きな影響を与えたのが D614G 変異だと考えられる」と話す。
論文は昨年 6 月には査読前の論文として発表され、今年 2 月に科学誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」で掲載された。 https://www.nature.com/articles/s41467-021-21118-2
研究を後押し 進む遺伝情報の共有
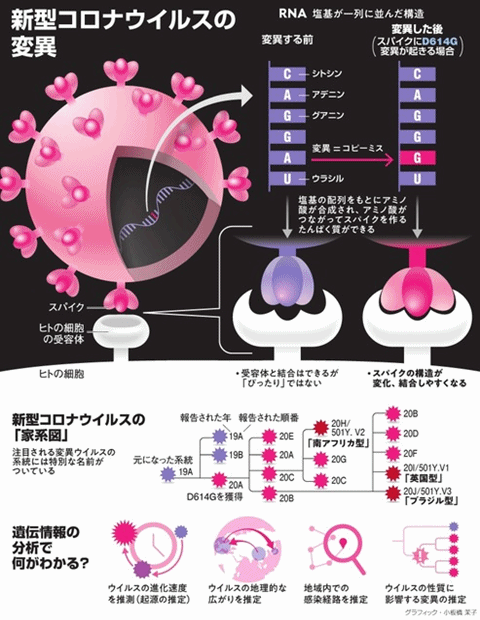
受け継がれた特徴的な変異を目印にすると、世界中の新型コロナを「クレード(分岐群)」と呼ばれるグループに分類できる。 方法はいくつかあるが、国際的な研究プロジェクト「Nextstrain」では 2 月末時点で 12 のクレードに分けており、「家系図」を描くこともできる。 19 年末に武漢市で検出されたウイルスが属する「19A」から始まり、以降、検出された西暦の下二桁と、確認された順番をアルファベットで表してクレード名にしている。 「20A」からは D614G 変異を持ち、世界中に広がった。
ウイルスの遺伝情報の分析に詳しい東海大の中川草講師は「全世界でほぼリアルタイムで変異を追跡できるのは、人類史上初めてのこと」と話す。 大きく役だっているのが、十数年前にできたウイルスの遺伝情報を世界で共有する枠組み「GISAID (鳥インフルエンザデータ共有国際イニシアチブ)」だ。 新型コロナウイルスが世界中で流行を始めてから約 1 年で 60 万を超す新型コロナの全遺伝情報が報告された。 「これは驚愕の数字です」と中川さんは話す。
かつては、病原体の遺伝情報を解析し登録した人の知的財産権などが十分守られておらず、別の研究者が匿名で利用することができた。そのため、データを出すことに消極的になる例もあった。 この枠組みではデータ利用が登録制で明確となり、利用者は、提供者の貢献を認めてその権利を守ることで、無料でデータを研究に使うことができる。 「インフルエンザなどでこの仕組みがうまく回り出していた。 今回、新型コロナにうまく利用できた」と、国立感染症研究所の長谷川秀樹・インフルエンザウイルス研究センター長は話す。
ワクチン効果への影響も注視
遺伝情報を調べることは、リスクの高い変異ウイルスにいち早く気づくことにも役立つ。 好例が英国にある。 ジョンソン首相が昨年 12 月、記者会見し、感染力が強まったおそれがある変異ウイルスが、同国内で急拡大していると警告した。
この変異株には「N501Y」という変異があり、スパイクとヒト細胞の受容体との結合が強まるとの試験管での実験結果が昨年 9 月に発表されていた。 そしてその変異を持つウイルスが実際に検出され、感染が急拡大していることでジョンソン首相の警告につながった。 その後数カ月のうちにこの変異ウイルスは世界 90 カ国以上で確認されるほど広がってしまったが、「これほど早く警戒を発したことは、従来では考えられなかった」と東海大の中川さん。
世界でワクチン接種が始まっているが、ウイルスが変異してワクチンが効かなくなることも心配されている。 実際、南アフリカで広がる変異株はワクチンが作る免疫から逃れる可能性が指摘されている。
ウイルスが人体にもたらす病気の重さ(病原性)などを研究する京都府立医科大の中屋隆明教授は「まだ多くの人が免疫を持っていない日本の現状では、このような変異を持つウイルスが優先的に増える理由はあまりない」としたうえで、「免疫を持った人が増えることは、『免疫から逃れる』変異を獲得したウイルスが優先的に生き残るような『圧力』になる」と語る。 一方、新型コロナに対する免疫がどのくらい持続するかはまだ不明で、獲得した免疫が次のシーズンになる前に低下するような場合、免疫から逃れる方向への「圧力」も小さくなると考えられるという。
今後、新型コロナの流行のしかたがどのように変わるかはわからない。 海外で起きたような変異が国内でも起こる可能性はあり、中屋さんは「どんな変異が生じているかに注意しつつ、感染者が増えないようにすることが重要だ」と話した。(野口憲太)
インフルほどの差異はない新型コロナ
インフルエンザウイルスは、塩基配列の違いやワクチンの効き方の違いで、「型」や「亜型」というグループに分類される。 新型コロナウイルスには、現状ではそこまでの差はない。 「クレード」の違いもインフルエンザに比べれば小さく、大きな単一のグループの中の差と言える。 (asahi = 3-2-21)
コロナワクチン「ノーベル賞級」 専門家が称賛する理由
記事コピー (2-26-21)
接種率世界一のイスラエル 見えてきたワクチン後の世界
新型コロナウイルスをめぐり、人口あたりのワクチン接種が世界一のイスラエルで、その効果を示す研究結果が次々と報告されている。 「ワクチン後の世界」を占うデータは信用できるのか。 人口約 920 万人のイスラエルでは、すでに 4 割を超える約 440 万人が 1 回の接種を終え、2 回接種済みの人も 300 万人を超えた。 高齢者優先で始まった接種は、16 歳以上の全住民に対象が拡大された。 日本でも接種が始まった米製薬大手ファイザーとドイツのバイオ企業ビオンテックが開発したワクチンが使われている。
国内で接種を担う保健機構「クラリット」はワクチン接種による発症の予防効果を報告した。 接種済みと未接種の 60 万人ずつの集団を比べ、接種済みの集団はウイルス感染による発症が 94% 少なかった。 重症化するケースも 92% 低下した。 こうした効果は、70 歳以上の高齢者も含め、年齢に関わらず確認できたという。 ファイザーが米国などで実施した約 4 万人を対象とした臨床試験(治験)での発症の予防効果は 95%。 誰も接種しなければ 100 人が発症すると仮定した場合、接種すれば発症者は 5 人に抑えられる効果を意味する。 イスラエルでの報告によれば、現実世界の 100 万人単位でも同程度の効果を確認できたことになる。
別の保健機構「マカビ」は、このワクチンにウイルスへの感染予防にも高い効果があると発表した。 2 回目の接種から 1 週間を経た約 60 万人のうち、感染が確認されたのは 608 人(約 0.1%)で、未接種の 60 万人と比べると感染を防ぐ効果が 95% と推計された。 ワクチンには他人への感染を防ぐ効果もあるのか。 ファイザーの治験結果ではこの点が明らかになっていないが、イスラエルで研究が出始めている。
イスラエルで多くの PCR 検査を担う企業「MyHeritage」の研究者らの研究によると、従来は PCR 検査で陽性となった人のウイルス量に高齢者と若年者で違いはなかったが、高齢者へのワクチン接種が進んだ 1 月下旬以降、高齢者からのウイルス検出量に顕著な低下がみられた。 また、テクニオン・イスラエル工科大学の研究者らも、ワクチン接種から 12 - 28 日後のウイルス量が、未接種者と比べて大きく減少していたとの論文を発表している。 これらの論文はまだ専門家による査読を経ていない。
ワクチンの副反応についても、データが集まっている。 保健省の 1 月末時点でのまとめでは、1 回目接種で副反応を訴えたのは約 270 万人中 6,575 人 (0.24%)、2 回目接種では約 130 万人中 3,592 人 (0.27%) だった。 副反応の大多数は、接種部位の痛みや頭痛、倦怠感などの軽い症状だった。 アレルギー反応があったのは 100 万人中 34 - 60 人で、重いアレルギー反応「アナフィラキシー」が起きたのは 1.4 人、呼吸器障害を発症したのは 2.9 人だった。 神経障害を訴えたのは 100 万人中 70 - 104 人だった。 その大半はピリピリするしびれの症状。顔面神経まひは同 1 - 11 人だった。 保健省はこうした副反応の結果を受け、従来の接種方針に変わりはないとしている。
イスラエルでは国民皆保険のもと、個人の医療情報は出生時からデータ化され、一元管理されている。 デジタル化が進む充実した医療制度は貴重なビッグデータを生み、ワクチン接種の効果をリアルタイムで分析する能力を支えている。 一連の研究報告について、ヘブライ大のハガイ・レビン教授(疫学)は「ワクチンの効果を示す非常にいい結果が出ているが、断定しがたい部分も残っている」と話す。 イスラエルでも、ワクチンを受けるべきかは論争となってきた。 「明確に反ワクチンという人は少数で、多くはためらいを感じているのだろう。 人々の心配を無視せず、新しいワクチンで、不確定要素もあることを認め、丁寧に説明する必要がある。」と話す。 (エルサレム = 高野遼)
集団免疫の効果は?
接種が進む国からのワクチンの効果の報告について、鈴木貞夫・名古屋市立大教授(公衆衛生学)は「どんなグループを比較しているか、他の影響はないかを注意しないといけない」と指摘。 その上で、「治験で有効性が高いとわかっているワクチンなので、現実の世界でもおそらく効果は高い」と話す。 インフルエンザのワクチンの発症予防効果は 20 - 60% とされる。 それだけにファイザーが新型コロナワクチンの効果を 95% とする治験結果を公表すると世界が驚いた。 その後、この結果などをもとに各国・地域の政府は次々と承認している。
治験はワクチン開発の最終段階に、人で効果や安全性を調べる試験だ。 数万人を対象とし、本物のワクチンと偽薬を打つ人をくじなどで無作為に分け、比較する。 一方、イスラエルでの調査対象は 100 万人単位だが、ワクチンを打ったかどうかは個人の判断などで決まっていて、無作為に分けられたわけではない。 鈴木さんは「科学的根拠に基づく最も信頼できるデータが得られるのは治験だが、現実社会での効果をみるにはイスラエルの研究者らが採っているような方法しかない。 感染者の減少や発症率の低下がワクチンの効果なのか、ロックダウン(都市封鎖)によるものかを分けられないが、今のところ妥当性がある」と話す。
イスラエルでもいまだに得られていないのが、「集団免疫」についてのデータだ。 ワクチンに大きな期待がかかるのは、感染者を減らすだけではなく、集団免疫で社会の感染を収束に導くかもしれないからだ。 集団免疫について、子どもの感染症に詳しい新潟大大学院の斎藤昭彦教授は「免疫を持った人が増えることで、免疫をまだ持っていない人まで守られるワクチンの『間接効果』」と説明する。
ワクチン接種した人の発症や重症化などを予防するのは「直接効果」だが、その結果、免疫を持つ人が増えることで、ウイルスに対する社会全体の抵抗力が強まる。 集団免疫ができれば、ワクチン接種ができないことがある高齢者や妊婦、別の病気の人などの感染を防ぐ効果がある。 集団免疫の獲得に必要な接種率は、病原体ごとの感染力の指標から計算できる。 感染力が強いはしか(麻疹)では人口の 95% 程度、ポリオでは 80% ほど。 新型コロナでは 60 - 70% ほどとする研究もあるが、さらに高い割合が必要との指摘もある。
世界では1980年に根絶宣言が出された天然痘や、ほぼ排除を達成しつつあるポリオ、日本でもはしかで集団免疫が達成されたと考えられている。 一方、日本では特定の年齢層の男性で接種率が低い風疹、ワクチンの効果がそれほど持続しない百日ぜきなどで集団免疫が実現しない。 斎藤さんは、集団免疫にはワクチン効果の持続期間や、ワクチンが効かない変異が出てくるかどうかが重要な要素になると指摘。 「ワクチン接種率が必要な割合を超えた後も感染の連鎖はすぐになくならず、ゆっくり収束していく。 しばらくは、マスク着用や物理的な距離を保つ地道な対策は続ける必要があるだろう。」と話す。 (合田禄、野口憲太、asahi = 2-24-21)
【イスラエルのワクチン接種で報告されたデータ】
- 保健機構クラリット
発症を防ぐ効果 94%- 保健機構マカビ(2 回目の接種から 1 週間後)
感染を予防する効果 95%- イスラエル保健省(2 回目接種から 2 週間後)
死亡を防ぐ効果 99%
重症化を防ぐ効果 99%
感染を防ぐ効果 96%
コロナ死亡例 98.9% 減少 ファイザー製 2 度接種で - イスラエル
【イスタンブール】 イスラエル保健省は 20 日、新型コロナウイルスによる死亡例が米ファイザー社製のワクチンを 2 度接種することにより、98.9% 減少したとする調査結果を発表した。 現地メディアが伝えた。 保健省の調査は 2 月中旬の時点で、1 月末までに 2 度目の接種を終えた人々と、ワクチン未接種の人々を比較した結果という。 発症率全体については 95.8% 低下した。 イスラエルではこれより先、国民が加入する保健維持機構 (HMO) がワクチンについて高い有効性が認められることを明らかにしていたが、保健省としてもこれを確認した形だ。 (jiji = 2-21-21)
なぜマイナス 75 度必要? 振動 NG? コロナワクチン
新型コロナウイルスのワクチンについて、医療従事者への先行接種が始まった。 「mRNA ワクチン」という新しいタイプだ。 超低温での保存が必要とされており、インフルエンザワクチンなどと比べ、取り扱いには注意が必要だ。 なぜこうした性質があるのか。専門家に聞いた。
もっと高い温度でも保存可能になる?
米製薬大手ファイザーのワクチンは零下 75 度、米バイオ企業モデルナのワクチンは零下 20 度での保存が必要とされている。 どちらにも、ウイルスの遺伝情報の一部が「mRNA」という成分として含まれている。 接種すると、その情報をもとに体内でウイルスのたんぱく質がつくられる。 これによって免疫細胞を活性化させ、感染に備えるしくみだ。
RNA ワクチンに詳しい国立医薬品食品衛生研究所遺伝子医薬部の井上貴雄部長によると、超低温での保存が必要なのは、この遺伝情報をもつ成分「mRNA」の化学構造によるところが大きい。 mRNA は「リボヌクレオチド」という物質が、鎖のようにたくさんつながってできている。 だが、構造の特徴から、つなぎ目近くで化学反応が起きやすく、鎖が切れてしまいがちだ。 これが「RNA は不安定」ということにつながる。
mRNA は私たちの体の中でも普段から働いている。 DNA から情報を写し取り、活動するのに必要なたんぱく質をつくる橋渡しをする。 化学反応を起こしてすぐ消えてしまう性質は、必要なくなったら、たんぱく質を作るのをやめるのに都合がよいが、ワクチンの材料としてはやっかいな面だ。 そこで、保存の際に低い温度が必要になる。 化学反応は一般的に温度が高いほうが起こりやすく、10 度下がると反応の速さが半分になるといわれている。 低い温度に保てば、こうした反応を抑えられると考えられている。
では、なぜ同じ mRNA ワクチンなのに、零下 75 度と零下 20 度の保存温度の違いが生まれるのか。井上さんは、同じように凍った状態でも温度によって物質が受ける影響が変わるため、「基本的には、それぞれの製剤に適した温度に設定されていると考えられる」と話す。 mRNA を細胞に取り込ませやすくするため、ワクチンでは mRNA を脂質の粒子で包んだものを接種する。 この脂質の粒子の成分の違いが影響している可能性があるという。
こうした温度の問題は mRNA ワクチンの課題だと受け取られてきた。 ただ、新型コロナウイルスのワクチンではないものの、同じタイプのワクチンでは 4 度で保存可能な製品も開発されており、ヒトでの安全性や有効性を確かめる臨床研究に進んでいるものもあるという。 井上さんは「今後はもっと高い温度で保存可能なものもでてくるだろう」と期待する。 実際、コロナワクチンも、より高い温度で保存可能になる可能性がある。 ファイザーは 19 日、零下 25 度 - 零下 15 度での安定性試験のデータを米国の規制当局に提出し、この温度で 2 週間の保管を認めるよう申請したと発表した。 認められれば、一般的な医薬品用の冷凍庫でも保存ができるようになる。
バイク便や自転車では運べない?
mRNA ワクチンの取り扱いの注意点は温度だけではない。 運ぶ際の振動にも注意が必要とされており、バイク便や自転車で運ぶのは避けるよう厚生労働省が各自治体に求めている。 井上さんによると、これは、mRNA を包む脂質の粒子の問題が大きい。 溶液中にこの粒子が均一に散らばっているのが理想だが、振動によって粒子が集まり、塊ができてしまうことが考えられるという。 塊になると、体内での取り込みがうまく進まなくなり、ワクチンの効果が薄くなる可能性がある。 車での運搬を想定した揺れに対する検証はされているというが、激しい振動は避けた方がよさそうだ。
万が一、保存中に想定より高い温度や激しい振動にさらされたら、ワクチンの効き目にどんな問題があるのだろうか。 井上さんは「特に温度が上がった場合、有効性が落ちて十分な免疫ができないことが考えられる」と話す。 温度が上がって mRNA が分解されてしまうと、作られるウイルス由来のたんぱく質も減って、効果がでづらくなることはあり得るという。
ファイザー、モデルナのワクチンは共に、有効性が 90% を超えるとされている。 60% 程度とされるインフルエンザワクチンと比べても、高い値だ。 この結果について、井上さんは「mRNA ワクチンの実用化は今回が初めての例。 二つの mRNA ワクチンの両方でこれほどの効果が出て、専門家としても想定以上だった。 この結果から、なぜこれほどの効果が得られたのかという考察や検証が始まりつつある。」と話す。
コロナ禍で広く使われたのを機に、mRNA ワクチンの用途は、他の感染症にも広がるかもしれない。 井上さんは「どのような課題があるか、今後わかってくる部分もあるだろう」としつつ「従来のワクチンに比べ、作るのが簡単で早い。 新興感染症などの緊急性がある場合では優先的に開発されるようになるのでは」と話す。 (杉浦奈実、asahi = 2-21-21)