�����ōH��@�B�̐��Y��P�ނ���L�a�H�ƁA�����ɏW��w�i
�s�̎Z������k���A��������Ɍo�c����
�L�a�H�Ƃ͊C�O�̍H��@�B�̐����E�̔��̐����ĕ҂���B�@�����ł̍H��@�B���Y���~�߁A���Y�͓��{�ɏW���B�@����A�W�A�ł̔̔��̓C���h�l�V�A�ɏW�A2020 �N 3 ���ɃV���K�|�[���̔��q��Ђ𐴎Z����B�@����A�č��ƃC���h�Ŕ̔����_�̐V�݂��������Ă���B�@�s�̎Z������k�����A��������Ɍo�c�������Ĕz������B�@�����q��Ђ͖L�a�i�V�Áj�����i�V�Îs�j�B�@11 �N�ɉғ����A�ꕔ�̕��i�͌��n��������B���A�����ԕ��i�p�𒆐S�ɍH��@�B�Y���Ă����B
�������l����ғ����� 2 �{�ɍ����B�@�����Ē����ȊO���璲�B���镔�i�͊łɂ��A���{��蒲�B�R�X�g���������i������̎Z�����������B�@�����œ��q��Ђ͓V�Îs���ňړ]���A�����Ă����H���ԋp�����B�@����͊O�������p���A�̔��E�ێ�ƁA�H��@�B�̃��C��������Ӌ@��̒lj�������G���W�j�A�����O�ɓ����B�@���n�ł̂��ߍׂ����Ή��͈ێ�����B
�V���K�|�[���̔���Ђ̓n�[�h�f�B�X�N�쓮���u (HDD) ���i�̉��H�@�Ȃǂ�����グ�̒��S�������B�@�������ω����A�̎Z�������������߃C���h�l�V�A�̔��q��Ђɋ@�\���W��B�@�L�a�H�Ƃ����ӂȎ����ԗp�H��@�B�𒆐S�ɁA�C���h�l�V�A���瓌��A�W�A�S��̎s���[�@�肷��B�@�č��ƃC���h�Ŕ̔����_�̐V�݂���������̂��A�����ԕ��i���H�̎s��J�_�����B�@���Ђ͔��㍂�c�Ɨ��v���� 19 �N 3 ������ 4.6% ���� 22 �N 3 ������ 6.5% �ɐL�����j�B�@�̐��̍ĕ҂ɂ��A19 �N 3 �����̔��㍂ 223 ���~���̔����߂����߂�H��@�B���Ƃ̎��v�����P����B (NewSwitch = 8-21-19)
�Β��ő� 4 �e�A���{��Ƃ��g�\���@���Y�ڊNj}�s�b�`
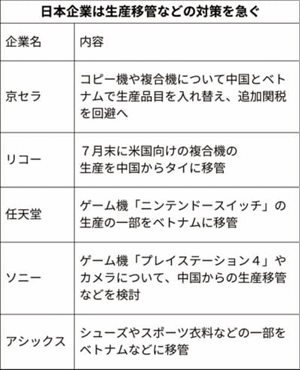
�č��� 1 ���A�������i�̂قڂ��ׂĂɒlj��ł��ۂ��� 4 �e�̐��ق� 9 �� 1 ���ɔ�������ƕ\�������B�@�Ώەi�ڂ̓X�}�[�g�t�H����Q�[���@�A�ߗ��i�ȂǍL�͈͂ɋy�сA�����ɐ��Y���_�������{��Ƃւ̉e�����������Ȃ��B�@�e�Ђ͌x�������߂Ă���A���Y�ڊǂȂǂ̓������}�s�b�`�Ői�݂������B�@�lj��ł���Ƃ̓����ӗ~�Ȃǂ��₵�A���E�i�C�̌���������i�Ƌ��߂��˂Ȃ��ƌ��O���鐺���オ��B
�u�x�g�i���H��ƒ����H��Ő��Y�����ւ���B�v�@���Z���̒J�{�G�v�В��́A�č����� 4 �e�����\������� 2 ���ɊJ�������Z��ł����\�������B�@�ڊǔ�p�͍ő�Ő��\���~���x�������ށB
���Ђ͑� 4 �e�̑ΏۂƂȂ�R�s�[�@�╡���@�ɂ��Č��݂͒����ŕč������A�x�g�i���ʼn��B���������ꂼ�ꐶ�Y���Ă���B�@���H��̏o�א�����ւ��A��������̏o�ו��ɑ���lj��ł̔�����}����B�@2019 �N 3 �����̕����@�֘A�̔��㍂�͖� 3,750 ���~�ŁA�����č������� 2 �����߂��͎s�ꂾ�B
�č�����������lj��ł̑� 4 �e�́A�č����A�����钆�����i�̖� 3 �牭�h���i�� 32 ���~�j���� 9 ������ 10% �̊ł���悹�����B�@�g�����v�đ哝�̂� 1 ���A�u�i�K�I�Ɉ����グ��\��������B�@25% �ȏ�����蓾��B�v�Əq�ׂ��B
6 �����̕Ē���]��k�ő� 4 �e�̔����͂���������ꂽ���̂́A�t�������c���s���ɏI���A�g�����v�哝�̂��Ăы��d��ɑł��ďo���`���B�@�� 4 �e�̑Ώۂ̓X�}�z��p�\�R���A�ߋ�Ȃǂ̏�������܂߁A���L���i�ڂɋy�ԁB�@6 �����̕Ē���k�ł�������ْ͋��ɘa�̃��[�h���L���������A�����̓��{��Ƃ͌x�����ɂ߂��ɃT�v���C�`�F�[���i�����ԁj�̌������Ȃǂɓ����Ă����B
���R�[�� 7 �����A�č������̕����@�̐��Y�𒆍��E�[�Z������^�C�Ɉڂ����B�@����A�^�C����͓��{�≢�B�����̐��Y�𒆍��ֈڊǂ�������Ō������Ă���B�@�V���[�v����������^�C�ւ̈ڊǂ�i�߂Ă���Œ����B�@�C�V���͎�̓Q�[���@�u�j���e���h�[�X�C�b�`�v�̑唼�𒆍��Ő��Y���Ă��邪�A���łɃx�g�i���ňꕔ�̐��Y�ڊǂ��n�߂��B�@����͏����A���Y�ʂ������グ����j���B
�\�j�[���ƒ�p�Q�[���@�u�v���C�X�e�[�V���� 4�v��J�����Ȃǂ��e������\��������B�@���Y�n�̕ύX�≿�i�]�łƂ����������͎��O�ɐi�߂Ă���A�܂��Ĕ��f����Ƃ݂���B�@7 �����̌��Z������ł͑� 4 �e����������Ă��A�u�����̉c�Ɨ��v�ւ̉e���� 2 �P�^���~�ɗ}�������i�����������s�����j�v�Ɛ������Ă���B�@�����ł̐��Y�䗦�������m�[�g�p�\�R���B�@�V���[�v�͎q��Ђ̃_�C�i�u�b�N�i�����E�]���j�������őS�ʂY���Ă���B�@�� 4 �e�����������A��p�ɂ���e��Ђ̍��C�i�z���n�C�j�����H�ƃO���[�v�̋��_��A�V���[�v�̃x�g�i���V�H��ւ̈ڊǂ���������Ƃ����B�@�č������͑S�̂� 1 �����x�̂��悤���B
����A�lj��ł̉e���ڎȂ��Ă��A�Ē��̖f�Ր푈���i�C���̂��̂��₵���˂Ȃ��ƌ��O���鐺�͑����B�@�Ⴆ�X�}�z�s�ꂾ�B�@18 �N�ȍ~�A�s��̖O�a���ȂǂŒ����̃X�}�z���v���������A���{�������݂����H��@�B�̎s�����������Ă���B�@���{�H��@�B�H�Ɖ�ɂ��ƁA19 �N 6 ���̒P���x�[�X�̎��z�͍D�s���̖ڈ��ƂȂ� 1 �牭�~�� 32 �J���Ԃ�Ɋ������B�@�H��@�B�ƊE�ł͎�����ʐM�K�i�u5G�v�ȂǂŃX�}�z���v�̉Ɋ��҂��鐺�������������̂́A�� 4 �e�̔����Łu�s���̉̒x���X�Ȃ鈫����S�z���Ă���i�q��t���C�X���쏊�j�v�Ƃ̐����オ��B
�^���C�Ȃǂ��� 4 �e�̑ΏۂƂȂ�A�V�b�N�X�B�@�L�c�N�l�В��́u�ł��̂��̂ɂ��e���͌y�����B�@�ނ���A�Ē��̌o�ϐ������݉����邱�Ƃ����O���Ă���B�v�Ƙb���B�@�Ē����C���A��Ƃ̓����ӗ~�����ڂ݂���B�@�p�i�\�j�b�N�͌ڋq��Ƃ̐ݔ������̗}���ŁA���Y�ݔ��ɑg�ݍ��܂�郂�[�^�[��Z���T�[�Ȃǂ̔̔��������B�@�� 4 �e�̔����œ���������ɗ₦���މ\��������Ƃ݂�B�@20 �N 3 �����̉c�Ɨ��v�\�z�ɂ��ẮA�����_�ŕĒ����C�� 100 ���~�̃}�C�i�X�v���ɂȂ�ƐD�荞�ݍς݂��B )nikkei = 8-4-19)
���{�d�Y�A�������㍂�� 2 �{���ɁA�����J��������
�y�k�� = �����c�r��z ���{�d�Y�� 20 ���A�k���s�Œ������Ƃ̐헪��������J�����B�@�Ē��Η����������A���E���̃T�v���C�`�F�[���i�����ԁj�Ɉ��e�����o�錜�O�����܂�Ȃ��A�g�{�_�V�В��́u�����͔��ɑ厖�Ȏs��ŁA�����𑱂��Ă����v�Ƌ����B�@2021 �N 3 �����ɒ������Ƃ̔��㍂�� 19 �N 3 ������ 2.3 �{�܂ő��₷�v��𖾂炩�ɂ����B�@19 �N 3 �����̒������Ƃ̔��㍂�� 3,547 ���~�ŁA���㍂�S�̂ɐ�߂�䗦�� 23%%�B�@�g�{�В��́u�����s��̐����͂��ꂩ��������v�Ɣ��f���A21 �N 3 �����ɂ� 8 �牭�~�܂ň����グ�āA���㍂�S�̂ɐ�߂�䗦�� 40% �܂ō��߂�B
��̓I�ɂ́A������ʐM�K�i�u5G�v�A�����Ԃ̓d�����Ǝ������A���{�b�g�̗��p�g��A�Ɠd���i�̏ȃG�l���A�_�Ɨp�����̎������� 5 �̒������Ƃ炦�Ď��Ƃ�L���B�@���ꂼ��̕���ɂ��Ă̓����z�Ȃǂ̏ڍׂ͖��炩�ɂ��Ȃ������B�@5G ����ł̓X�}�[�g�t�H�������̃J�����֘A���i��ݔ������̃A���e�i�Ȃǂɗ͂�����B�@�����ԕ���ł͓d�C������ (EV) �����̋쓮�V�X�e���𒆍����L�����ԑ��A�L�B�D�ԏW�c�ɔ[�����n�߂��Ɩ��炩�ɂ��A���̈��L�����j�����������B
������ƂƂ̎���𑝂₷���߁A�����ł̌����J���̃X�s�[�h�� 5 �{�ɍ��߂�B�@�g�{�В��́u�X�s�[�h�ł͒�����搶�ɂ��Ă����v�Ƌ��������B�@���n�o�c�������琬���A�����e�n�ɒu���������J�����_�̊g�[���i�߂�B�@��̓I�ɂ́A�K�ߕ��i�V�[�E�W���s���j�ō��w�������͂�����V�s�s�\�z�u�Y���V��v��蟐��Ȑ����ł̓��{�b�g��L��o�ύ\�z�u��ш�H�v�Ƃ̘A�g�ɗ͂�����B�@�L�B��d�c�Ȃǂł͎����ԕ���A�L���Ȑ[�Z���ł͒ʐM����A�]�h�ȑh�B�A�싞�ł̓X�}�[�g�V�e�B�[�ɗ͂�����B
�g�����v�Đ����͒����̃n�C�e�N����̐����Ɋ�@���������Ă���A5G ����ł͒����ʐM�@����A�؈Z�p�i�t�@�[�E�F�C�j�̔r���ɓ����B�@�Ē��Η��̌���������������A���{�d�Y�̋��C�̒����헪�ɉe����^����\�������肻�����B (nikkei = 6-20-19)
�V���[�v�A�č������m�[�g�p�\�R�����������琶�Y�ڊǂ�
�Չ���В����\���A�lj��łȂ�
�V���[�v�̑Ր�������В��� 27 ���A���{�o�ϐV���Ȃǂ̎�ނɉ����A�č��̒����ɑ��鐧�يŁu�� 4 �e�v�̑ΏۂƂȂ�m�[�g�p�\�R���ɂ��āA�������瓌��A�W�A���Y�ڊǂ���l���𖾂炩�ɂ����B�@�Վ��́uASEAN �i����A�W�A�����A���j�ɂ��������Y�ł��鋒�_�͂�������v�ƌ��A�����@��f�W�^���T�C�l�[�W�����Ȃǂ̑�^�f�B�X�v���[���ڊǂ���������B
�č��̑Β��ő� 4 �e�͍ő� 25% �̊ł��ۂ����e��6�����ȍ~�ɔ�������錩�ʂ����B�@�V���[�v�q��Ђ̃_�C�i�u�b�N�i�����E�]���j���肪����m�[�g�p�\�R���͍Y�B�s�̎��ЍH��𒆐S�ɒ����őS�ʂY���Ă��邪�A�� 4 �e�����������A��p��x�g�i���Ȃǂɂ���V���[�v��e��Ђ̍��C�����H�ƃO���[�v�̋��_�ւ̈ڊǂ���������B�@�u�S�̂� 1 �����x���č������i�Վ��j�v�Ƃ����B
�� 4 �e�����������A�����@�͍]�h�Ȃ̎��ЍH��ō�������ł����E���ʋ@��Y���Ă��邪�č������ɂ��Ă̓^�C�H��Ɉڂ����j���B�@���l�ɍL�������Ȃǂ̑�^�f�B�X�v���[�����͍��C�̒����H��Ő��Y���Ă��邪�A���Ђ̃��L�V�R�H��Ɉڊǂ�����j���B�@����A�Վ��̓V���[�v�̕��i�������ŏI���i�̔���グ�̒��Łu�����Ő��Y����č������� 3.8% �����Ȃ��v�ƌ��A�e���͌y���ł��邱�Ƃ����������B�@�Y�����鐻�i�̐��Y�ڊǂ�v���ɐi�߁A�����ɑ��ăR�X�g�����b�g�����ăV�F�A�g��ɂȂ���B
�܂��č��ɂ�鎖����̒����E�؈Z�p�i�t�@�[�E�F�C�j�ւ̕��i�����֎~�K���ɂ��āA�V���[�v�͌��݁A�K���̑ΏۂɂȂ邩�̒�����i�߂Ă���B�@���{�����ł��t�@�[�E�F�C���X�}�[�g�t�H���i�X�}�z�j�̔��������Ȃǂ̓����������Ă��邪�A�Վ��͂��������������u�`�����X�ɂ��Ȃ�v�Əq�ׂ��B�@��������g�ѓd�b��g�їp���[�^�[�ȂǂŃV�F�A�g���ڎw���B
�܂��Վ��͓����A���g�̐i�ނɂ��Ă����y�����B�@���N 6 ���ɍ��C�����H�Ƃ̓����ɕ��A�\��B�@�u�i�����̔C�����������߁j 2021 �N�x�܂ł̓V���[�v�̉�E���p������v�ƌ�����B�@�В��E�ɂ��Ắu�K���Ȑl��������������p�������v�Ƃ��A20 �N�x�ȍ~�̌������������B�@��C�́u�ł���Γ��{�l����I�т����v�Ƃ��A��������L���Г��O������҂���B
�܂���p�҈琬�̎��g�݂���������B�@�Վ��ƁA�쑺�����E�Γc���v�����В��� 3 �l�����߂Ă��鋤�� CEO �i�ō��o�c�ӔC�ҁj�ɂ��ẮA���N 7 �����猠�����g�傷����j���B�@����܂ł� 2 �疜�~�ȉ����������ٌ����� 1 ���~�ȉ��܂ň����グ��B�@���̋��� CEO �̒S������ɂ��Ă��Վ����g�́u�Ɛт��B���ł���A�֗^���Ȃ��v�Ƃ����B�@���d�v�Ȍo�c���f������ CEO �ɔC���邱�ƂŁA��p�҂Ƃ��Ă̓K�������ɂ߂�B (nikkei = 5-27-19)
���@���@��
�V���[�v�A�č����������@���Y�@��������^�C�Ɉڊǂ�
�����@��肪�č��������i�̐��Y�𒆍�����ڊǂ��铮�����L�����Ă����B�@�V���[�v�͍��Ĉȍ~�A�č������̕����@���Y���^�C�Ɉڂ����j���B�@���Z�����x�g�i���ւ̈ڊǂ���������B�@���{�������E�V�F�A��ʂ��߂镡���@�̓g�����v�Đ����ɂ�钆���ւ̐��يŁu�� 4 �e�v�̑ΏۂƂȂ����B�@�ƊE��ʂ̃��R�[���ڊǂ����߂Ă���A��������̓������������������B
�č��̑Β��Łu�� 4 �e�v�͍ő� 25% �̊ł��ۂ����e�ŁA6 �����ȍ~�ɔ�������錩�ʂ����B�@�Ėf�Փ��v�ɂ��ƁA�����@�� 52% �i�A���z�x�[�X�j�𒆍�����߂�B�@�V���[�v�͌��݁A�č������̕����@�̑唼���]�h�Ȃ̍H��Ő��Y����B�@�����̈�����\�ȏ㒆�ʋ@����肪���钆�j���_�����A�� 4 �e�����������Εč������̓^�C�����ɒi�K�I�ɐ��Y���ڂ����j���B�@�Ώۂ͓��Ђ̐��E�̔��̖� 2 ���ɂ�����N 10 �����Ƃ݂���B�@�^�C�ւ̈ڊǂł́A���n�̐l���𑝂₵�V���Ȑݔ������͂��Ȃ����悤�B�@���Ђ̕����@�֘A���Ƃ̔��㍂�� 2018 �N�x�ɖ� 3,200 ���~�ƑS�̂� 1 �������߂�B
���Z���͕č������̃R�s�[�@�╡���@�̐��Y�𒆍�����x�g�i���ɐ�ւ��錟���ɓ������B�@���݂͒����E�L�B�ƃx�g�i���k���� 2 ���_�ŁA�č������̓x�g�i���Ɉڂ��������B�@���Ђ̕����@�֘A���Ƃ� 18 �N�x�̔��㍂�͖� 3,750 ���~�ŕč����� 25% ���߂�B�@�ڊǂ͔��N���x������Ƃ݂��A�Ē��f�Ր푈�̉e�������ɂߔ��f����B
�� IDC �̒����ɂ��ƁA�I�t�B�X�Ŏg���� A3 ���[�U�[�����@�� 18 �N�̐��E�V�F�A�i�䐔�x�[�X�j�̓��R�[���� 17% �Ŏ�ʁB�@���Z���� 5 �ʁA�V���[�v�� 6 �ʂɂ���B�@�ă[���b�N�X�E�x�m�[���b�N�X�A�L���m���A�R�j�J�~�m���^���܂ޓ��{���ȂǏ�� 6 �ЂŃV�F�A�� 8 �������߂�B�@�x�m�[���b�N�X��L���m�����č������𒆍�����A�o���Ă���A�e�Ђ͂���܂Œ����𐢊E�s��Ɍ������������_�Ƃ��Ă����B�@��ʂ̃��R�[�͒����Ő��Y����č������̐��i�̑S�ʂ��^�C�Ɉڂ��B ���R�[�ɑ����A�V���[�v�Ƌ��Z�����������瓌��A�W�A�ɕč������̐��Y���ڂ��A���E�I�ȕ����@�̗A�o��n�Ƃ��Ă̒����̈ʒu�Â��ɉA�肪�o�邱�ƂɂȂ肻�����B (nikkei = 5-23-19)
���{��ƁA�E�E������i�Ɓ@���Y�⒲�B��
�č��̒lj��ň����グ�̉e���͓��{��Ƃɂ��L����B�@����̑Ώۂ͎����ԕ��i��Ɠd�A�d�q���i�̈ꕔ�Ȃǂ��B�@�e�Ђ̋Ɛтւ̕��S���d���Ȃ�A���Y�⒲�B�̖ʂŒ������瑼���ɃV�t�g���铮������i�Ɛi�݂������B
�Z�F�d�C�H�Ƃ͒����Ŏ����ԗp�g�ݓd���i���C���n�[�l�X�j��֘A���i�Y���č��ɗA�o����B�@���Ђ͕Ē��f�Ր푈���A��N���璆�����琶�Y���ڂ��Ă����B�@�ł� 25% �ɂȂ�ƔN 25 ���~�̃R�X�g���ŁA�e���͊� 10% �� 2 �{���B�@��㎡�В��� 10 ���̌��Z�L�҉�Łu�������Y�̈ꕔ���t�B���s����x�g�i���A���L�V�R�ȂǂɈڂ��v�ƁA�ڊǂ���Ώۂ��L����l�����������B
�������쏊�͎����ԃ����v�̓d�q��Ȃǂ��Ώې��i�ŁA�ł� 25% �ɂȂ�ƔN 14 ���~�̃R�X�g���ɂȂ肻���B�@���{�Ⓦ��A�W�A�ɐ��Y���ڂ����Ƃ����������B�@�x�m�t�C�����z�[���f�B���O�X�̓f�W�^���J�����̕t���i�̈ꕔ���ň����グ�̑ΏۂƂȂ�B�@�������璲�B���ĕč��ɗA�o���Ă���A����̑[�u�Ő����~�̃R�X�g���̌��ʂ��B�@���쌒���В��́u�i���B�n��̕ύX���j�������Ă���v�Ƃ����B
����A���i���[�J�[�͉��i�]�ł������ɋ��ߌ��𑱂��Ă���B�@�ŏI���i�̒l�グ�ɂȂ���Ύ��v��₦���܂��鋰�������B�@�g���^�����Ԃ̊����́u�č��̑Β��ł� 25& �ɂȂ�A�Ē��̎����Ԏs��̗₦���݂͔������Ȃ��v�ƕs��������B
�����ɂ��č��ւ̕[�u�̗]�g���y�ԁB�@�ۍg�͕č����q��ЂŁA�������ۂ����哤�Ȃǂւ̊ł̉e���Ŏs�������������B�@��A�̕Ē��f�Ր푈�̉e���� 10 �N 3 ������ 200 �� - 300 ���~�K�͂̌��������������B�@�p�i�\�j�b�N�͕Ē��Ԃ̊ň����グ�Ƃ��̗]�g�̎��̂�����ŁA�u18 �N�x�� 400 ���~���x�̌��v�v�f���������B�i�~�c���a�햱���s�����j�v�@19 �N�x�͂���� 100 ���~���x�̌��v��z�肷��B (nikkei = 5-11-19)
�C�V���u�X�C�b�`�v�����ց@���̖{�i�̔��A�}���I���F��
�C�V���̉ƒ�p�Q�[���@�u�j���e���h�[�X�C�b�`�v���A�����{�y�Ŕ̔�����錩�ʂ��ƂȂ����B�@�㗝�X�ƂȂ钆���� IT ���e���Z���g�̐\�����A���n�̐��{�@�ւ��F�߂��B�@�C�V���͉ߋ��ɒ����ŏ��K�͂Ȕ̔����s���Ă������A�v���Ԃ�̍ĎQ���ƂȂ�B
�e���Z���g���{�Ђ�u���L���Ȃ̕������s���� 18 ���A�X�C�b�`�{�̂ƃX�C�b�`�����u�X�[�p�[�}���I�v�̃\�t�g�̔̔����������ƌ��\�����B�@24 ���܂ňӌ�����̊��Ԃ�����A�����ɔF�߂��錩�ʂ����B�@�����S�y�Ŕ̔��ł���̂���A���������Ȃǂɂ��Ă͖��炩�ɂȂ��Ă��Ȃ��B�@�C�V���́u�j���e���h�[ DS�v�Ȃǂ̃Q�[���@�����n�@�l��ʂ��Ĕ̔����Ă������������邪�A���K�͂ȃr�W�l�X�ɂƂǂ܂��Ă����B�@�����̓Q�[���̓��e�Ȃǂɂ��ċK�����������B�@���n�̑��Ƒg�ނ��ƂŁA�̔����X���[�Y�ɐi�߂�_��������B (�������Aasahi = 4-19-19)
�g�{���ƁA��C�ŃG���^���w�Z�@�V�쌀�̌|�l���u�t�h��
�g�{���Ƃ� 3 �� 29 ���A�G���^�[�e�C�������g�Y�Ƃ̐l�ނ��琬����w�Z�𗈔N 3 ���ɒ����E��C�ɗ����グ��Ɣ��\�����B�@���Ђ����ӂƂ���R���f�B�[�║�䌀�Ɍg���l�ނ���Ă�ړI�ŁA�����̖��c���f�B�A���A�ؐl�����O���[�v (CMC) �Ƌ����Őݗ��B�@�g�{�V�쌀�̌|�l���X�^�b�t���A�u�t���Ƃ��Ĕh������\��Ƃ����B�@�g�{���Ƃ͍����Ƀ^�����g�{�����uNSC�v�������A�C�O�ɗ{���@�ւ�����̂͏��߂āB�@������ 50 - 100 �l���x�̐��k���W���A���҂≹���E�Ɩ��̋Z�p�҂ȂǂɈ�Ă�B�@�����́A�_���T�[��̎�Ƃ������p�t�H�[�}�[�A�f��E�A�j���̋Z�p�҂Ȃǂɂ��Ώۂ��L������j���B
CMC �͒����{�y�A���`�A��p�ȂǂɌ������f���e���r�ԑg�̐���A�f��ق̉^�c�Ȃǂ���L���肪���Ă���B�@�����ł̓G���^���Y�Ƃ̐l�C�����܂��Ă������A�u���������l�͂�������̂ɁA�{������@�ւ����Ȃ��B�@���Ђ̌����쌻��Ŏ��H�I�Ȍ��C�����Ă��������B�i�z�C�E�c�[�E�g�[�}�X�ō����s�ӔC�ҁj�v�Ƃ����B�@���Ɛ�������ł���悤�A�f��ق⌀��A�����ǂȂǂ̋��_���A�W�A�n��Ő������Ă����l���B�@�g�{���Ƃ̐����p���E�C�O�헪�{�����́u�w�Z�^�c�����łȂ��A���݂��̎����f�B�A�������R���e���c�����i�߂����v�Ƙb���B (�v�ۓc�Н�Aasahi = 4-2-19)
�\�j�[�A�����̃X�}�z�H�ꐶ�Y�I���@�̔����ő̐�������
�\�j�[�� 3 �����ɒ����̃X�}�[�g�t�H���i�X�}�z�j�H��̐��Y���I������B�@���Y�䐔�Ȃǂ͖��炩�ɂ��Ă��Ȃ��B�@�X�}�z���Ƃ͓��ƂƂ̋��������Ŕ̔��䐔�̌����ŐԎ��Ɋׂ��Ă���B�@�X�}�z�̐��Y���_���^�C�� 1 �J���ɏW�����ăR�X�g���팸���A�����Ƃ̎��v���P��}��B
�k���ɂ���H��̐��Y�� 3 �����ɏI�����A�Ŗ��Ȃǂ̎葱�����o�ĕ����錩�ʂ��B�@1995 �N�ɉғ����n�߂��k���H��͒����ŗB��̃X�}�z�H��B�@�]�ƈ����͔���\���� 1 ��l�K�͂Ƃ݂���B�@���������̐l����̏㏸�ŁA�����R�X�g�����S�ɂȂ��Ă���B�@���n�̔̔��䐔���������钆�A���Y�I�������߂����悤���B�@�u�G�N�X�y���A�v�u�����h��W�J����\�j�[�̃X�}�z���Ƃ͒��ؐ��Ƃ̋��������Ȃǂ��Ĕ̔����������B�@���߂̐��E�V�F�A�� 1% �ɂ������Ȃ����悤�B�@2019 �N 3 ������ 950 ���~�̐Ԏ���������ł���B (nikkei = 3-28-19)
�p�i�\�j�b�N�A3 �N�� 1 ���~��ڎw�������̎��Ɛ헪�@�u�����ŏ��ĂȂ��Ə����͖����v
�p�i�\�j�b�N�́A3 �� 14 - 17 ���� 4 ���ԁA�����E��C�̏�C�V���۔������S (SNIEC) �ŊJ�Â��ꂽ�A�W�A�ő�K�͂̉Ɠd���uAWE 2019�i�����Ɠd�y����d�q������j�v�ɏo�W�B�@�����s������ɊJ������ IoT �Ɠd�Ȃǂ�W�������B�@����O���ɂ́A��C�s���ŋL�҉���s���A�p�i�\�j�b�N �A�v���C�A���X�ЎВ��̖{�ԓN�N�����A�����ɂ����鎖�Ɛ헪�Ȃǂɂ��Đ��������B
�����E�k���A�W�A�Ђ�ݗ��A�����ł̐������p�i�\�j�b�N����������
�{�ԎВ��́A4 �� 1 ���t���ŁA�V�݂��钆���E�k���A�W�A�Ђ̎В��ɁA���炪�A�C���邱�ƂɐG��Ȃ���A��������g���Ď��Ɛ헪��������Ă݂����B�@�����E�k���A�W�A�Ђ́A���n�哱�̑̐��Ƃ��A���J���p�j�[�̎P���ɃX�}�[�g���C�t�Ɠd���ƕ��A�Z����Ԏ��ƕ��A�R�[���h�`�F�[���i�����j���ƕ��A��p���ƕ���V�݁B �A�v���C�A���X�ЎP���̗�M�f�o�C�X���ƕ����ڊǁB�@�����E�k���A�W�A�ɂ����āA�Ɠd���Ƃ������r�W�l�X���s�����ƂɂȂ�B
�{�ԎВ��́A�u�V�J���p�j�[�̎��Ɨ̈�́A400 �����i�� 7,000 ���~�j���̔��㍂�����A3 �N��ɂ� 600 �����i1 ���~�j�K�͂́w���炵�A�b�v�f�[�g��Ɓx�ɂȂ邱�Ƃ�ڎw���B�@�V�J���p�j�[�ł́A�����̂��Ƃ͒����Ō��߂�A�Ƃ����|���V�[������ɐ����i�߁A���q�l�̂��炵���l�E���炵��ԂɊւ��̈��S������B�@�В��̒É�i�p�i�\�j�b�N��\������В��̒É��G���j�́A�w�����ŏ��ĂȂ��ƃp�i�\�j�b�N�̏����͖����x�ƌ���Ă���A�����ł̎��Ƃ�傫�����������A���E���̃p�i�\�j�b�N���������鑶�݂ɂȂ�B�@���������ɑ��čU�߂Ă����A�������琢�E���ւƍU�߂Ă����B�v�Ƃ����B
���݃p�i�\�j�b�N�́A�Ɠd�ȊO�̎��Ƃ��܂߂�ƁA�����S�y�Ŗ� 600 �����i1 ���~�j�A��������̗A�o���܂߂�ƁA1,250 �����i2 ���~�j���鎖�Ƃ��s���Ă���A������̔��A�J���A�f�U�C�����܂߁A88 �̋��_�������A6 ���l���Ζ��B �u���̋K�͂́A���{�������ő�ɂȂ�v�Ƃ����B
�܂��A�{�ԎВ��́A�p�i�\�j�b�N���A���N�ɓn���āA�����Ƌ������т������邱�Ƃ������B�@2018 �N�́A�p�i�\�j�b�N���n�� 100 ���N���}�����̂Ɠ����ɁA�p�i�\�j�b�N�̑n�Ǝ҂ł��鏼���K�V�����ƁA���������Ƃ̒��ډ�k�ɂ��A���Ђ������ɐi�o����ƂƂ��ɁA�Z�p�w�����s�����Ƃ����肵�Ă���A40 �N�ڂ̐ߖڂ��}�������ƂɌ��y�B�@�u���̂Ƃ��̉�k�őn�Ǝ҂́A�w���ꂩ��̓A�W�A�̎���ł���x�ƌ��A�����ɂ�����ߑ㉻�ւ̋��͂�����B�@1987 �N�A���{�̑���ƂƂ��ẮA��㏉�߂āA�k���Ƀe���r�̃u���E���ǍH������݂��A�p�i�\�j�b�N�̒����ł̎��Ƃ��X�^�[�g�����B�v�Əq�ׂ��B
�����Ő�s���� IoT �Ɠd�A�T�v���C�`�F�[���ɂ����@
�p�i�\�j�b�N�� 2015 �N 4 ���ɁAAP ������ݗ����A�Ɠd�̏��i�J������f�U�C���A�}�[�P�e�B���O�܂ł��A�����̃����g�b�v�̑g�D�̐����ňӎv����ł���̐���~���Ă����B�@���̌��ʁA�����s��̃j�[�Y�ɍœK���������i�̓����Ȃǂ��������Ă����Ƃ����B�@���ʂ̂ЂƂƂ��Ă������̂��u�i�m�P�A�h���C���[�v�B�@2018 �N�ɂ́A���������ŔN�� 60 �����̔��B�@�V���i�ł́A���ʂ����߂������Ǝ��̃��[�h�𓋍ڂ�����A�Ǝ��̐Ԃ�{�̃J���[�ɍ̗p�����肵���Ƃ����B
�܂��A���{�ɐ�삯�āA�����s��� IoT �Ɠd���s�̔��B�@���ł� 4 �N���o�߂��Ă��邱�ƂɐG��A�u�A���猒�N�f�[�^�𑪒�ł���g�����́A�X�}�z�ƘA�����A���q�l�̌��N�Â���ɂ��𗧂��ł�����̂Ƃ��āA�����Ńi���o�[�����̎x���Ă���B�@2019 �N 3 ������́A�f�W�^���~���[�ƘA�������V���ȓW�J���X�^�[�g����B�@����A�o�C�^���Z���V���O�œ������N�����j�ɁA�g�����̂���T�j�^���[�E�o�X��Ԃ����łȂ��A���r���O�A�L�b�`���A�v���C�x�[�g�Ƃ�����Ԃɂ����Ă��A���̃\�����[�V�������L���Ă����B�v�Ƃ����B
����ɁA���łɓ��{�œW�J���Ă���Ɠd����яZ��ݔ����������v���b�g�t�H�[���uHOME X�v�����p�����T�[�r�X�𒆍��ł��W�J����p���𖾂炩�ɂ����ق��A���N�ŁA���K�ȋ�Ԃ��f�W�^���v������g�݂Ƃ��āADELOS �Ƌ����ŁA�k���Ƀ��{��ݗ��B�@2019 �N 7 ������A���؎������X�^�[�g����Ƃ����B�@�����ł́A�C���⍁��A�Ɩ��A���A�f���ȂǁA�Ǝ��̎h����ʂ����A���S���Y���J����i�߁A�T�C�o�[��Ԃł̐v���A���A���ȋ�Ԃɗ��Ƃ����ނƂ����B
�u�{�V�E�Ћ�v�Ƃ���������ł́A��B�W�c�����]�f���^�n��ŕ����W�J���� CCRC �ɏ��ނ�[�����A�{�V�{�݂ł̐V������Ă�i�߁A�������̃V���[���[���ł́A�G�C�W�t���[�֘A�̏��i��̌��ł���悤�ɂ����ق��A���]�ȍY�B�s�ɖ{�Ђ�u�����f�x���b�p�[�̍L�F�W�c�ƂƂ��ɁA�ݑ���֘A�̏��ނ⍂��҂���炵�₷����ԂÂ���ŋ��ƁB�@�{�V�Z���a�@�Ȃǂւ̓W�J������ɓ����Ƃ����B
�����s�s�J���v���W�F�N�g�ł́A�u�S�N���N�s�s�v���R���Z�v�g�ɁA�Ћ�\�����[�V�����Ȃǂ̎��g�݂��p�[�g�i�[�ƂƂ��ɊJ�n�B�@���z�ƊE�����ɂ́A���������̕����̃p�[�g�i�[��ƂƋ����ŁA���z��������̃v���n�u�n�E�X���Ƃ�W�J���Ă��邱�Ƃ��������B
����ɁA�p�i�\�j�b�N�ł́A�T�v���C�`�F�[���ւ̎��g�݂ł��A�����s��ł͐����̗]�n������Ƃ݂Ă���B
�{�ԎВ��́A�X�[�p�[�}�[�P�b�g��R���r�j�G���X�X�g�A�ŁA�H�i���₷�u�Ⓚ�E�①�V���[�P�[�X�v�ł́A�����Ńi���o�[ 1 �V�F�A�ł��邱�Ƃ������Ȃ���A�u�A��r���ɒ�������A�Ƃɒ������ɂ͐H�ނ��͂��Ă���Ƃ����A�����̃��C�t�X�^�C���ɂ͋������A�Ő�[�� EC �Љ�ł��钆���ŁA��₷�Ƃ������l�́A����ɈЗ͂����邱�ƂɂȂ邾�낤�B�v
�u�V�N�Ȗ�⋛���A�Y�n����V�N�Ȃ܂܉^��ŁA�ۊǂ��邽�߂̑q�ɂ╨�����A����ɂ͂�������H����~�[�@���X���Ŕ̔�����V���[�P�[�X�A�Ƃɓ͂���܂ł̐��N��z�Ƃ������悤�ɁA�Y�n����H��܂ł̃T�v���C�`�F�[���̂��ׂĂ̒i�K�ɂ����āA�p�i�\�j�b�N�̋Z�p�ƃT�[�r�X���v���ł���B�@�����̐l�X�ɂƂ��āA�H�̈��S���x���鎖�ƂɂȂ�B�v�Ƃ����B
2018 �N 12 ���ɂ́A�M�B�ȏ��S�����ƁA�R�[���h�`�F�[�������V�X�e���̐헪���Ƃɒ���B�@�M�B�Ȃ̊e�������_�ɗⓀ�①�q�ɂ����݂���ق��A�Y�n����H��̈�C�ʊуV�X�e���̍\�z�ɂ���āA���������̔_�Y�i���A���ݕ��̑�s�s�Ɉ��S�ɓ͂��邱�Ƃ��ł���Ƃ����B
�ڎw���̂́u2020 �N�ɊO���n�����Ɠd�u�����h�i���o�[�����v
�p�i�\�j�b�N�́AAWE 2019 �̉��ɂ����āA�O�N�����W���X�y�[�X���g�債�A�V���Ȓ�Ă⒆���������i��W�����Ă݂����B�@�{�ԎВ�����Ŏ������悤�ɁA���{�ɐ�삯�āA�����Ŕ̔����J�n���� IoT �Ɠd�ł́A�O���̖���̏�A����ԂɃg�C���Ōv�������N�f�[�^���A�����I�ɐ��ʑ�̃~���[�ɕ\���B�@�L�b�`���ł͑̒������P���郌�V�s��Ă��s���A�����ŗ①�ɂ̍ɏ��m�F���āA�����{�^���ŐH�ނ������ł���T�[�r�X���f���X�g���[�V�������Ă݂����B
�{�ԎВ��́u���̍\�z�́A�Ɠd��E�A�Z��ݔ��Ȃǂ̎��ƂN�i�߁A�l�b�g���[�N�A�C���^�[�t�F�[�X�A�Z���T�[�ȂǁA���N�E���K�ɂ������Z�p�ɋ��݂����p�i�\�j�b�N�����ł��Ȃ��\�����[�V�����ł���A�w���N���v���b�g�t�H�[�}�[�x�Ƃ��āA���炵��Ԃ��̂��̂��A�A�b�v�f�[�g����������ʂ����v�Ƃ����B�@�g�����́A�֍��ɂ����Z���T�[�ŁA�����������ő̎��b�����v�����A��p�̊����g�����A���m�ŁA�����l�Ȃ�7���ڂ̒l�𑪂邱�Ƃ��ł���Ƃ����B�@�܂��A���ʑ�ɐݒu����f�W�^���~���[�́A2019 �N 3 �����甭������Ƃ����B
����ŁA�i�m�C�[�Z�p���ϋɓI�ɑi�����Ă݂����B�@�p�i�\�j�b�N�u�[�X�ł́A��C����@��w�A�h���C���[�A����@�A�①�ɂƂ������i�m�C�[���ڐ��i��W���B�@����Ɂunanoe LAB�v�̖��̂ŁA�i�C�m�[�̋Z�p�I�ȗD�ʐ��ɂ��Ă����������B
�{�ԎВ��́A�u�i�m�C�[�́A�����e�Ɠd�ɓ��ڂ����ƁA���┧�ɂ��邨����^���邪�A���ꂪ�@��ɓ��ڂ����ƁA��C���̋ۂ�E�C���X��}������ق��APM2.5 �Ɋ܂܂��L�Q�������A�}������B�@����A�葫���a�̃E�C���X�ɂ����ʂ�����Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ����B�@�i�m�C�[�A�i�m�C�[ X �́A����ƒ낾���ł͂Ȃ��A�a�@��w�Z�A�{�V�{�݂ȂNjƖ��p�̋ɍ̗p���ꂽ��A�����Ŕ̔����Ă���W���K�[�����h���[�o�[��g���^�ԂȂǁA�S���E�� 80 �Ԏ�ȏ�ɓ��ڂ���Ă���v�ȂǂƂ����B�@�����e�Ɠd�ł́A�����s�������p�̏�ʃ��f���Ƃ��āuPanasonic Beauty X �V���[�Y�v���B�@������u�[�X���ɓW�����Ă݂����B
�p�i�j�\�b�N�ł́u�V�M�w�v�ƌĂ�鐢�єN�� 32 �����ȏ�� DEWKs ������^�[�Q�b�g�Ɏ��Ƃ�W�J�B�@2020 �N�ɂ́A�O���n�����Ɠd�u�����h�Ƃ��ăi���o�[������ڎw���Ă���B�@�܂��A�A���o�o�⋞���ƘA�g���āAEC �v���b�g�t�H�[�������p�����r�W�l�X���������A�����ɂ�����I�����C���̔��䗦�� 3 �����x�ɂ܂ō��߂�l�����B�@����� AWE 2019 �̓W����A����ɂ��킹�Ď��{�������ʂ��āA�����s��ɂ����āA�t�����l�헪�����Ɏ��Ƃ�W�J����p�i�\�j�b�N�̑��݊����A����ɋ��������Ƃ�����B (��͌����s�ACnet = 3-18-19)
���{���\���邠�̉��ϕi���[�J�[���A�����ł̔���グ���I�ɐL���Ă��� = �������f�B�A
���������ɂ�������{�̉��ϕi�ւ̐M���Ɛl�C�͍����B�@�K�������l�ό��q���Ɠd���i���u�������v�����̂͂��łɉߋ��̘b�����A���ϕi�ɂ��Ă͂Ȃ����l�C�́u���y�Y�v�ł��葱���Ă���B�@�����œ��{�̉��ϕi���[�J�[�������{�y�ł̔̔��ɗ͂������邪�A�����ł��m���x�̍����������ɂƂ��č�N�͑���n�̔N�ɂȂ����悤���B�@�������f�B�A�E�����Ԃ� 12 �����B
�L���́A�������O���[�v�������N 12 �����̘A�����Z�\���A2017 �N 12 �����̌��Z�ŏ��߂Ĕ��㍂�� 1 ���~�̑���˔j�����̂ɑ����A18 �N 12 �������Z�ł����㍂�A�c�Ɨ��v�A�����v���ߋ��ō����L�^�����ƏЉ�B�@���㍂�͑O�N������ 8,9% ���� 1 �� 948 �� 2,500 ���~�ŁA�c�Ɨ��v���� 34.7% ���� 1,083 �� 5,000 ���~�ɒB�����Ɠ`�����B
�����āA���ł����{�ƕ���œ��Ђ̔̔����x���钆���s��̔��㍂�� 1,907 �� 9,900 ���~�ƂȂ�A���{�s��� 4,545 �� 5,800 ���~�ɔ�ׂ�Ƃ܂������ȉ��̋K�͂ł�����̂́A�ΑO�N��ł͓��{�s�ꂪ 9% ���ɂƂǂ܂����̂ɑ��A�����s��͂�����͂邩�ɏ��� 32.3% ���� 3 �{�ȏ�̐L�ї������������Ƃ��Љ�Ă���B
���̂����ŋL���́A���Ђ̒����s��헪�ɂ��ċ߂���p�ɂɕz���ł���Ă���Ǝw�E�B�@���N 1 �� 1 ���ɂ͏�C�Ŗ{�В����́u��������n�V�������v�𗧂��グ�A�����s��̓����ւ̒������C�m�x�[�V�����A�V�Ɩ��̔��W�̐��i���s�����_�Ƃ������ƁA�������Ƃ̐V���ȃ}�l�W�����g�`�[�����n�����A�K�w�ʂ̃u�����h�����AEC �Ǝ��̓X�܂̔��W�Ȃǂ�ڎw�����Ƃ��ē`�����B (���֒��n�ASearChina = 2-13-19)
�Ē��f�Ֆ��C���� �c �@�B��肪�����Ő��Y�g���
���}�U�L�}�U�b�N�͓��{�ւ̗A�o����
�q��t���C�X�A���d���H�@�V�H��
�q��t���C�X���쏊�͒����E��C�ߍx�̐��Y���_�i���R�s�j���ɐV�H������Ă�B�@�����Ԃ̋��^�╔�i�Ȃǂ�������d���H�@�̌��Y�\�͂� 2021 �N�x�Ɍ��ݔ� 4 �{�� 180 ��ɑ��₷�B�@�����s��͗x��ꊴ���Y�����A���Ђ͓��ӂ̐������H�����̍D���������B�@�������ł��d�C������ (EV) ��q��@�A�X�}�[�g�t�H���i�X�}�z�j�����̊g���\�z����B�@�V���K�|�[������̐��Y�ڊǂ�i�߂Ȃ����������荞�ށB
�q��t���C�X�͒����Œ��������������d���H�@�̈ꕔ�Y���Ă����B�@���������g���ĉ��H���郏�C�����d���H�@��A�d�ɂ̌`���]�ʂ���`������d���H�@�̃A�W�A��͋@��𒆍��̐V�H��ɂ܂Ƃ߂�B�@�����Ƀ��C���^�uU �V���[�Y�v��S�ʈڊǂ��A�`����^�uEDAF �V���[�Y�v���ڊǂ���B�@�V�H��̓����z�͖� 40 ���~�B�@�����ʐς͖� 2 �� 5,000 �������[�g����\�肷��B�@���Y�̐��ɉ����A�c�Ƃ�A�t�^�[�T�[�r�X����������B�@�ڋq�̎��ۂ̐v�f�[�^���g���Ď����H����{�݂�AIoT �i���m�̃C���^�[�l�b�g�j�T�[�r�X�����{�݂��V�݂���B
�@�B�ƊE�́A�Ē��f�Ֆ��C�̐��يł𗝗R�ɖk�Č����̐��Y�ڊǂ��i�ވ���A�����̓����g������z�����g�哊���������������B
�u���U�[�H�Ƃ�}�U�L�}�U�b�N�A���Y�E�A�o�g��
�H��@�B��肪�����Ő��Y�\�͂̑�����A�o�̊g��Ɏ��g�ށB�@�u���U�[�H�Ƃ� 2019 �N 11 ���ȍ~�ɐ����s�̍H��Ő��Y���C�������A���Y�\�͂� 4 �����߂�B�@�����̒����ł̎͒�����Ă��邪�A�������I�ɂ͉���ƌ����ށB�@���}�U�L�}�U�b�N�͑�A�s�̍H��̓��{�ւ̗A�o�ʂ� 19 �N�ɂ� 2 �{�ɑ��₷�B�@���{�s�ꂪ�D���ŁA�������Y�����ł͎��v�ɋ������ǂ����Ă��Ȃ���Ԃ����P����B�@���Y���_�A�A�o���_�̑o���ł̒����H��̏d�v�������܂��Ă���B
�u���U�[�͐��Y�q��Ёu�Z��@�B�i�����j�v�ŁA���n�����ɏ��^�}�V�j���O�Z���^�[ (MC) �̎�v 3 �@��Y����B�@�H����ɕ��U����q�ɋ@�\�� 19 �N 11 �������̑q�ɂɏW�A���X�y�[�X���������Y���C���ɓ]������B�@�����z�͔���\�B�@���Ђ͒����ł͎�v�ڋq�̓d�q�@�퐻������T�[�r�X (EMS) �������������ށB�@�����A��������v�ڋq�̎����Ԍ����𒆐S�ɒ������̎��v�͐L�т�ƌ��āA�����H��̐��Y�\�͂����߂�B
���}�U�L�}�U�b�N�͐��Y�q��Ёu�R��n�H�������i�ɔJ�j�v�Ő��Y���鏬�^���l���� (NC) ���Ղ̓��{�ւ̗A�o�ʂ��� 20 ��ɔ{������B�@���������Ƃ𒆐S�Ɏ��D���ȏ�A�����ł̐��Y������������߁A9 ���ɗA�o���n�߂��B�@��������������A�[����Z�k���邽�߁A�A�o�{�������߂��B�@13 �N�ғ��̗ɔJ�H��́A���Y�����Ō��Y�\�͂� 16 �N�� 5 �����ɍ��߂��B
���{�H��@�B�H�Ɖ�i���H��j�ɂ��� 9 ���̍H��@�B���сi�m��l�j�ł́A�������O�N������ 22.0% ���� 189 ���~�� 7 �J���A���̑O�N����B�@���{�͓� 5.6% ���� 644 ���~�ŁA20 �J���A���őO�N���������B (NewSwitch = 11-29-18)
�ɓ����A1,400 ���~�����@�o����̒�����Ƃ��������
�ɓ��������� 2 ���A�o����̒�����Ƃ̊�������Ō����������K�v�ɂȂ�A1,433 ���~�̑����� 2018 �N 9 �����Ԍ��Z�i���ۉ�v��j�Ōv�サ���Ɣ��\�����B�@�ɓ����́A�����ő�̍��L������Ɓu�������M�W�c (CTIC)�v�ɑ��� 15 �N�A�� 1.2 ���~���^�C�̍����Ɛܔ��o���B�@�m�㕗�͂�A�p�����֘A�ŋ�̓I�ȘA�g���n�܂��Ă���B
�ɓ����̔������E�ō������ӔC�� (CFO) �́u���L�n�̂��߁A���{�� 58% �̊���ۗL���Ďs��ɗ��ʂ��銔�����Ȃ��B�@���Z�n�����ɑ���s��]�����������̂��e�����Ă���B�v�Ɗ�������̗��R����������B�@����A19 �N 3 �����ł́A���j�[�E�t�@�~���[�}�[�g�z�[���f�B���O�X�̎q��Љ��ɂ��ĕ]���v 1,412 ���~�ȂǂŁA�ߋ��ō��̏����v 5 �牭�~��\�z���Ă���B (���V��Aasahi = 11-2-18)
�O�@�� (8-11-17)
���{�H���A�����̒������H��@12 ���ғ�
�����������̓��{�H���z�[���f�B���O�X�i���Q�������s�j�� 12 ��1 ���A�Ă����̃^���Ȃǒ������̐V�H��𒆍��]�h�ȓ�ʎs�ʼnғ�������B�@�����ʐς� 1 �� 4,000 �������[�g���A�������z�͖� 30 ���~�B�@�Ă����̃^�����g�����Ȃǂ̐��Y�\�͓͂��Ђ̊C�O�H��ōő�K�͂̔N 2 �� 5,000 �g���Ƃ���B�@�� 50 �l���ٗp����\��B�@���n�@�l�̖{�Ў������⌤���E���w�{�݂����݁B�@�����̎s��ɍ��킹�����i�̊J����i�߁A���v�̊g��ɑΉ�����B (nikkei = 10-28-18)
���d�H�������ŃX�g�[�J�����ݏċp���d�{�݂� 6 ���A����
���d�H�� 11 ���A�����̈��J�C���W�c�iCONCH �O���[�v�j�Ƃ̍��ى�Ђł�����J�C�����H�����A�������������X�g�[�J�����ݏċp���d�{�݂� 6 ���A�������Ɣ��\�����B�@�ݒu�ꏊ�͍]���ȁE�㍂���A���J�ȁE�緌��A�R���ȁE�������A蝐��ȁE�m���A���J�ȁE跎R���A�d�c�s�E�Β����B�@2019 �N 10 ���܂łɏ����[������B
���d�H���Z�p���^���A���{�����ł̎��т����ƂɁA�����̂��ݐ���ɍ��킹�čœK�������B�@���d�H�ɂ��ƁA�X�g�[�J�����ݏċp���d�{�݂� 2016 �N 1 ���̑� 1 ���{�݈ȍ~�A����̘A���Ōv 16 ���ɂȂ����B�@���J�C�����H���͎��{�� 1 �����i�� 16 ���~�j�ŁA�o���䗦�͐��d�H�� 49%�A���J�C���W�c�� 51%�B (�@�����l�ARecordChina = 10-12-18)
��̘V�܁u�F�Ë~���ہv�A�����ő�l�C�@�A���o�o�����W
�u�q��Ăɂ����ƏΊ���v�̊肢�͊C���z�����B�@1597 �N�n�Ƃ̉F�Ë~���ہB�@�Ȗɐ��܂ꂽ���{�L���̘V�܊�Ƃ����܁A�����Œ��ڂ���Ă���B�@���q�����i�ޓ��{�Ŏq�ǂ��������i�̎s�ꂪ�k�����钆�A���N�|�����M�p���A�W�A�ŐV���Ȓn�����J���B
2016 �N 11 ���B�����l�b�g�ʔ̑��̃A���o�o�W�c�����Ђ̃I�����C���V���b�s���O�T�C�g�ŁA�F�Ë~���ۂ̓����p�X�L���P�A���i�u�����̗t���[�V�����v����W�����B�@�ʔ̔ԑg�̌`���œ��{�ƒ��������сA1 ���Ԃ̐�������z�M�B�@���������̈玙���̏����������x�r�[���[�V�����̎g�p������荇���A��Ђ̗��j�⍂���̍H����Љ�ꂽ�B
�������͖� 4 ���l���������A�T�C�g�ւ̃R�����g�� 2 �����ȏ�B�@���̌�A����ɂ킽���čĔz�M���ꂽ�B�@�]���͒����ōL�܂�A�ʔ̂����łȂ��A���{�̃h���b�O�X�g�A�Ŕ������߂钆���l�ό��q���}���B�@�N 30 �� - 40 ���{�̃q�b�g���i�ƂȂ����B (�r�c��ƁAasahi = 10-11-18)
�R�����A�k���ɊC�O 1 ���X�@�u�����h�i���v�_��
���Ô̔��̃R�����i���É��s�j�́A�����E�k���Ɉ�ʋq��Ώۂɂ����C�O 1 ���X�� 9 �����ɊJ�����B�@���z�ȃu�����h�i�����A���Ô̔�����B�@�k�����S���̘H�ʓX�ŕ��u�����h�o�b�O�Ȃ� 1 ��_�������B�@�����ʐς� 414 �������[�g���B�@��ȋq�w�́A������肪 40 ��ȏ�̕x�T�w�A�̔����u�����h�i�ɊS������ 20 ��ȏ�̏�����z�肵�Ă���B
�����͐l���������A�u�����h�i�̎��v���������Ƃ���o�X�����߂��B�@�u���{�̍��i���̓X����ڋq�Ń����[�X�����̒蒅��ڎw�������i�L��j�v�Ƃ����B �R������ 2017 �N 6 ���A�k���Ō��n��Ƃƍ��ى�Ђ�ݗ����ďo�X������i�߂Ă����B�@���N 6 ���ɂ̓^�C�̑������ƍ��ى�Ђ�����A����̓o���R�N�ւ̏o�X��ڎw���B (asahi = 10-2-18)
�����̍H��@�B�u�������v�Ƀu���[�L�A5 �J���A���}�C�i�X
�����ɂ��H��@�B�́u�������v�ɋ}�u���[�L���������Ă���B�@���{�H��@�B�H�Ɖ�i�����E�`�j�� 21 �����\���� 7 ���̎z�i�m��l�j�͒��������� 5 �J���A���őO�N����B�@�S�̂� 13% ���ƍD�������������ɁA�O���� 4 ���� 1 ���߂钆���̕ϒ��͍ۗ��B�@�Ē��̖f�Ֆ��C�ւ̌��O���璆�������ɓ�̑��ޓ������L�����Ă���悤���B
�u����Ƃ��������R�͎v��������Ȃ��B �@���̒ʏ����C�̉e���Œ�����Ƃ̃}�C���h����܂�ł���̂�������Ȃ��B�v�@���H�Ɖ�̔ё��K����i���ŋ@�B��j�͓����̋L�҉�Œ����̌����v�������A����̈��������ɏI�n�����B�@7 ���̍H��@�B�̎��z�� 1,511 ���~�ƑO�N������ 13.1% �����A7 ���Ƃ��ĉߋ��ō����L�^����Ȃǐ���������B�@�O�N��v���X�� 20 �J���A�����B�@������ 674 ���~�� 08 �N�̃��[�}���E�V���b�N�ȍ~ 3 �Ԗڂ̍������ŁA�O���������Ԍ����Ȃǐ��Y�̎�������������ւ̓������v�������Ō����ɐ��ڂ��Ă���B
�B��ϒ����������Ă���̂����������̎z���B�@���E�n��ʂ̎z�Œ����� 205 ���~�ƑO�N������ 8.5% �̃}�C�i�X�ƁA5 �J���A���Ō������������B�@���z�x�[�X�ł� 17 �N 1 ���ȗ� 18 �J���Ԃ�̒ᐅ�����B�@�s���̌����Ƃ���Ă����̂��d�q�@��̎�������T�[�r�X (EMS) �������B�@�X�}�z�̐V�@�퓊�����Ȃǂɑ�ʔ��������邽�߁A���Ƃ��Ɣg���傫���B�u��������͈�ʋ@�B�������������݁A�Ē����C�̉e���Œ����S�̂���܂�ł��Ă���\��������i�ё���j�v�Ƃ̎w�E���o�Ă����B
�����̎����ԃ��[�J�[�������������ł̑��Y�����߂�ȂǁA�H��@�B���[�J�[�͒����̐����Ƃ̐����������Ƃ̌���������Ă��Ȃ��B�@�����A�������{�͐����Ƃ̍��x����ڎw������u�������� 2025�v�̉��A�H��@�B�̓�������i�߂���j��ł��o���Ă���B�@�f�Ֆ��C�����������ɁA���{���[�J�[�ɂ͋t���ƂȂ�������̗��ꂪ��������̂����O���鐺������B
�������ADMG �X���@�̐X��F�В��͕Ē��Փ˂̉e����ے肵�Ȃ�����u���[�}���E�V���b�N��Ɏ�����܂� 2 �N���x�����������Ƃ�����A�̔��̐��̋�����i�߂Ă����v�Ɛg�\���邱�Ƃ��Y��Ȃ��B�@�i�C�̐�s�w�W�Ƃ����H��@�B�́A�ڂ̑O�̕������݂��ł��q���ɔ��f���镗���{�Ƃ�������B�@���ڂ̕ς��ڂ����ɂ߂悤�ƁA�N������N�ɂȂ��Ă���B�i���c�����A�p�c�N�S�Anikkei = 8-21-18)