東京都「地震で危ない街」最新ランキング発表 … 最高ランク 5 と評価された「85 の超危険な街」
地震大国に住む以上、いつ、どこで巨大地震が発生するかわかりません。 一人ひとりが常に「もしものとき」に備えて、準備をしておく必要があるでしょう。 そこで役に立つのが、自治体が公表する防災マップや被害シミュレーション。 今回は東京都が公表した、町丁ごとの『地震危険度』についてみていきます。
30 年以内に 70% で起こる首都直下地震
今後、30 年以内に 70% の確率で起こるとされている首都直下地震。 東京都『首都直下地震等による東京の被害想定』では、東京における被害想定を、震源ごとに行っています。 都内で最大規模の被害が想定されているのは、都心南部直下地震。 震度 6 強以上の範囲は 23 区の約 6 割に上るとされています。
【東京における被害想定】
- 都心南部直下地震 建物被害 : 194,431 棟 死者 : 6,148 人 負傷者 : 93,435 人 避難者 : 約 299 万人 帰宅困難者 : 約 453 万人
- 多摩東部直下地震 建物被害 : 161,516 棟 死者 : 4,986 人 負傷者 : 81,609 人 避難者 : 約 276 万人
- 大正関東地震 建物被害 : 54,962 棟 死者 : 1,777 人 負傷者 : 38,746 人 避難者 : 約 151 万人
- 立川断層帯地震 建物被害 : 51,928 棟 死者 : 1,490 人 負傷者 : 19,229 人 避難者 : 約 59 万人
出所 : 東京都『首都直下地震等による東京の被害想定』より
また懸念されている南海トラフ巨大地震では、東京では揺れの被害はほぼ発生しないとしながらも、東京区部沿岸で約 2 - 2.6m 程度、島しょ地域では式根島で約 28m と、大きな津波が想定されています。 これらはあくまでも想定。 前出の地震被害については、「冬の夕方、風速は 8 メートル/秒」でのシミュレーションであり、東日本大震災のときのように、想定を大きく上回る被害になることも考えられます。
ただひとついえることは、防災・減災対策により、被害は軽減させることができるということ。 前回想定では「死者約 5,100 人、全壊約 11 万棟」と想定していましたが、近年、住宅の耐震化率 92% という状況を考慮して、被害想定を 2 - 3 割ほど減少すると予測。 さらに耐震化率 100% になれば、「死者 1,200 人、全壊約 3.2 万棟」と、さらに 6 割ほど減少できるとしています。 同じように「家具転倒防止対策」が現況 57.3% で想定していますが、それが 75% になれば、死者は約 4 割減、出火防止対策を進めることができれば、現況想定から約 7 割減にできるとしています。
巨大地震が起きたら「東京都で一番危険!」とされた街
また自身の住む地域が、どのような危険があるのか、地震に対してどれほど危険なのか、知ることも対策を講じるうえで重要。 先日、東京都では都内 5,192 町(丁目)ごとに地震による建物倒壊や火災発生の危険性などを評価し、5 段階にランク付けした『地域危険度』を更新しました。 これは同じ揺れの強さに遭遇した場合を想定して算出したもので、「建物倒壊危険度」、「火災危険度」、さらにこれらを合算し、災害活動に必要な空間量、道路整備の状況から、避難や消火・救助活動のしやすさなどを加味して算出した「総合危険度」の 3 種類でランキングしています。
「危険度 5」と評価されたのは 85 の地域。 そのうち 16 カ所と最多が「足立区」。 続いて 15 ヵ所が「墨田区」、13 ヵ所「荒川区」、9 ヵ所「大田区」、8 ヵ所「葛飾区」、6 ヵ所「江東区」、「北区」、5 ヵ所「江戸川区」と、東京東部の地域に集中。 一方で 2 ヵ所「中野区」、1 か所「品川区」、「新宿区」、「杉並区」、「台東区」、「豊島区」と、全体的に危険度が低い地域でも、街や地盤などの状況から、「危険度 5」と評された地域も。
そんななか、都内で最も地震で危険と評価されたのが「荒川区荒川 6 丁目」。 「町屋」駅周辺、都電荒川線と東京メトロ千代田線に囲まれたエリアで、木造住宅の密集地域。 細い路地も多く、「建物倒壊危険度」 20 位、「火災危険度」 2 位、総合では前回 3 位から 1 位へと不名誉のトップへとランクアップしました。 一方前回 1 位の「荒川区町屋 4 丁目」は 2 位に。 前回 11 位の「足立区柳原 2 丁目」は総合 3 位と大きく順位を上げています。
【東京都「地震危険度ランキング」上位 10】
1 位 : 荒川区荒川 6 丁目 (3) / 2 位 : 荒川区町屋 4 丁目 (1) / 3 位 : 足立区柳原 2 丁目 (11) / 4 位 : 足立区千住柳町 (2) / 5 位 : 墨田区京島 2 丁目 (7) / 6 位 : 墨田区墨田 3 丁目 (5) / 7 位 : 足立区千住大川町 (4) / 8 位 : 江東区北砂 4 丁目 (8) / 9 位 : 墨田区押上 3 丁目 (12) / 10 位 : 足立区関原 2 丁目 (20)
出所 : 東京都『地震に関する地域危険度測定調査(第 9 回)』より * (かっこ)内数値は前回調査順位
ただこれらはあくまでも相対的に評価したもので、安全性が向上していても他のエリアの安全性が向上していたら危険度はアップしますし、順位が低いからといって「地震が起きても大丈夫」というわけではありません。あくまでもこれは街の状況を把握するための指標。 その地域に合ったベストな対策を講じることが、防災・減災につながります。 (幻冬舎ゴールドオンライン = 9-29-22)
雨の都心に華が戻る 神宮外苑花火大会

東京の夏の風物詩のひとつ、神宮外苑花火大会が 20 日夜、東京都新宿区で 3 年ぶりに開催された。 雨の中、1 万 2 千発の花火が都心の夜空を彩った。 観覧会場ではコンサートも開かれ、訪れた人たちは光と音楽の祭典を楽しんだ。 主催者によると、全観覧会場のチケットは 18 日時点で完売。 感染防止策として、入場者の検温を実施し、コロナ禍以前まで開放していた会場周辺の一部の観覧スペースは閉鎖された。 (asahi = 8-21-22)
新宿駅地下でエンゼルス・大谷を疑似体験
実況アナもリアルさに太鼓判「本物に近い」
リアル二刀流で、2 年連続 MVP の可能性も十分にあるエンゼルス・大谷翔平。 その迫力あるプレーを日本でも体験できることになった。 ソニーインタラクティブエンタテインメントのゲームソフト「MLB THE SHOW 22」のプロモーションイベントとして、8 月 15 日から 22 日までの 7 日間、JR 新宿駅の東西自由通路、新宿ウォール 456 の超横長の 45.6m の大型 LED ビジョンで、「MLB THE SHOW 22」の大谷翔平キャラクターが、打、投、走で躍動するモーショングラフィック映像を放映する。
その場にいる人は、現実の試合で大谷が叩き出した打球速度、投球速度、走塁速度を体感できる仕組みだ。 打球は 191.5 キロ、投球は 164 キロ、盗塁で走る速度は 31.6 キロに設定された。 今年 4 月 5 日に発売された 22 年度版で表紙を飾った大谷翔平。 ゲームソフトの売りは限りなく本物に近いリアルさだ。 今回からゲームソフトのメインの実況アナウンサーとなったジョン・ブーグ・シアンビーさんは「TV 映像を見ていると勘違いしてしまうほど本物に近い。 選手の体の動き、仕草、表情、こと細かく再現されている。」と舌を巻く。
シアンビーさんの普段の仕事は、鈴木誠也の所属するカブスの実況アナウンサー。 今回、ゲーム用の収録には 200 時間を費やしたそうだ。 「例えばホームランの描写一つとっても、ワールドシリーズの決着をつける満塁本塁打と、大差がついた公式戦でのソロ本塁打では全く違う。 100 万パターンは録音したかな(笑)。 絶叫パターンが多いから、本塁打の録音の日は前もって伝えられていた。 あんな声を出せる回数はリミットがあるから。」と笑顔で振り返る。
「MLB THE SHOW 22」の最大の魅力は疑似体験。 若きベーブ・ルースが本塁打の魅力を世に示した、今は存在しないポログラウンドで「大谷対ルース」を実現させ、楽しむこともできる。 「私も一度は行ってみたかった球場で、夢の対決を疑似体験できるのがすごいところ」とシアンビーさん。 日本のファンも MLB の球場のフィールドに立たなくても、新宿駅の東西自由通路で大谷翔平のパワーとスピードを疑似体験できる。 (奥田秀樹通信員、スポニチ = 8-15-22)
有楽町線に「東陽町」など 3 駅新設へ 豊洲 - 住吉駅間の延伸ルート案
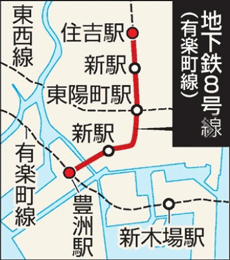
東京メトロ有楽町線の豊洲駅と半蔵門線・都営新宿線の住吉駅を結ぶ延伸事業で、計画区間(約 5.2 キロ)のルート案が明らかになった。 豊洲 - 住吉駅間に三つの駅を新設し、いずれも仮称で(豊洲から順に)、「枝川」、「東陽町」、「千石」としている。 東京都は 21 - 25 日、江東区の小中学校で計 4 回、地元住民向けの説明会を開く。 都の都市計画素案によると、各駅間は区道や都道の地下を使い、東陽町駅は同じ名前の駅がある東西線の地下に新駅を作る。 総事業費は約 2,690 億円。 今回の延伸で臨海部と都東部が結ばれ、利便性の向上と東西線の混雑緩和が期待できるという。 (asahi = 8-4-22)
東急百貨店本店跡に 36 階建て複合ビル 27 年度に完成予定
東急は 21 日、来年 1 月末で営業を終える東急百貨店本店(東京・渋谷)の跡地に、36 階建ての複合ビルを開発すると発表した。 2027 年度の完成予定。 商業店舗や高級ホテルを誘致し、インバウンドの取り込みもめざす。 地上 36 階建てで、高さは約 164 メートル。 中層階には香港、中国などでホテルを展開する「スワイヤー・ホテルズ」が手がけるホテルが入り、高層階は高級賃貸住宅となる予定。 低層階は商業店舗に加え、隣接する複合文化施設「Bunkamura」と接続し、文化・芸術を感じられる空間をつくるとしている。
工事は 23 年度から本格的に着手し、Bunkamura は一部を除き、同年 4 月から 27 年度まで休館する。 東急の高橋和夫社長は「東急百貨店本店として多くのお客様にご利用いただいた計画地で、新たな施設もご愛顧いただけるよう、取り組んでまいります」とコメントを出した。 (松本真弥、asahi = 7-21-22)
京王線をアンダーパスする新道、調布市内に開通 甲州街道 - 品川通りスムーズに

東京都調布市内に 2022 年 8 月 4 日(木)午前 11 時、京王線をアンダーパスする道路が開通します。 道路は「調布都市計画道路 3・4・7 号喜多見国領線」。 甲州街道から品川通りまでの約 580m を結び、幅員は 18 - 24m です。 京王線の国領 - 柴崎間を抜け、品川通り側では野川に沿います。 開通により、並行する狛江通りの交通渋滞が緩和されるとともに、住宅地などの狭隘道路に流入する通過交通が減少するなど、周辺地域の安全性や快適性の向上が図られます。 建設にかかる事業は 2007 (平成 19)年度に開始。 今後は側道も整備される予定です。 (乗りものニュース = 7-14-22)
銀座線や丸ノ内線、8 月から通勤時間帯に減便へ
コロナ禍で利用者減
東京メトロは 7 日、8 月 27 日からダイヤを改定し、銀座線など 4 路線を減便すると発表した。 平日の通勤時間帯も含め、1 時間あたりの運行本数を 1 - 6 本減らす。 コロナ禍の影響で利用者が減り、十分な回復が見込めないことから減便を決めたという。
対象は銀座線、丸ノ内線、東西線、千代田線の 4 路線。平日の通勤時間帯は、おおむね 2 - 3 本の減便となる。 帰宅時間帯も、路線によっては 1 - 3 本ほど少なくなる。 直通運転がある他社路線への影響なども考慮して決めたという。 同社によると、今年 5 月の利用者数は 2019 年の同時期と比べて 26% 減少していた。 同社の担当者は「本数を減らしすぎて混雑にならないよう考慮した」と説明している。 (asahi = 7-7-22)
「電力ひっ迫注意報」きょう午後 6 時解除 きょうまで 4 日連続発令も需給緩和の見通し 経産省
「電力ひっ迫注意報」は、きょうまで 4 日連続で発令されていた。 経済産業省は、4 日間に渡って東京電力管内に発令されていた電力需給ひっ迫注意報を 30 日午後 6 時に解除すると発表した。 十分な予備率を確保できる見込みとなったとしている。
経産省は「ご家庭や職場などにおいて、節電への多大なるご協力をいただきありがとうございました」と述べ、明日以降も熱中症にならないよう引き続き冷房を活用しつつ、無理の無い範囲での節電を呼びかけている。 「注意報」は、電力需給がひっ迫する可能性があることをいち早く周知して節電を促すために今年新設されたもので、今月 27 日からきょうまで、4 日連続で東京電力管内に発令されていた。 (FNN = 6-30-22)
◇ ◇ ◇
政府、初の「電力需給逼迫注意報」発令 27 日の節電呼びかけ
政府は 26 日、東京電力管内の電力需給が 27 日夕に厳しくなるとして、「電力需給逼迫注意報」を初めて出した。 27 日午後 3 - 6 時に節電に協力するよう企業や家庭に呼びかけた。
厳しい暑さにより、電力供給の余裕を示す「予備率」が 5% を下回る見通しのため。 資源エネルギー庁によると、27 日は昼過ぎまでは電力需給にある程度の余裕があるといい、「暑い時間帯には適切に冷房等を活用し、水分補給を行って、熱中症にならないよう十分に注意を」と呼びかけている。 予備率は、安定供給のためには 3% が最低限必要だ。 政府はエリアごとに 5% を下回る見通しの場合は注意報を、3% を下回りそうな場合は警報を出す。 (asahi = 6-26-22)
首都直下地震どう備える? 「4 人家族に必要な備蓄品の量」一覧 高層階に住む人ほど備蓄が必要に
東京都防災会議による首都直下地震の被害の想定では、都心部で急増する高層マンションでのリスクなど、社会環境の変化を反映した。現状の暮らしに応じた備えを呼び掛けている。(佐藤航)
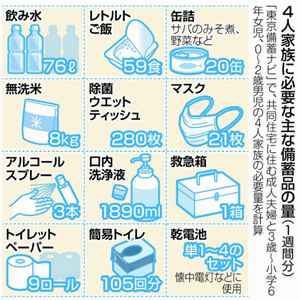
◆ 高層階は「陸の孤島」の恐れ
「地震でエレベーターが止まると(高層階は)『陸の孤島』となってしまう恐れがある。」 沿岸部を中心に高層マンションが立ち並ぶ現状に、都の防災担当者は危機感を抱く。 都内の高さ 45 メートル超の建築物は 2020 年度で 3,558 棟。 わずか 10 年で 1,000 棟以上も増えた。 都内で共同住宅の 6 階以上に住む世帯も同じく 10 年で 3 割以上増え、約 103 万世帯に達している。
災害時にエレベーターが止まった場合、荷物を持って階段を上り下りするのは難しい。 各地で一斉に止まれば点検に時間がかかり、復旧に 1 週間以上かかるケースも想定される。そのため高層階に住む住民ほど、食料や日用品などの備蓄が大事になってくるという。 都はインターネットサイト「東京備蓄ナビ」で、家族の人数や年齢、住まいの種類を入力すると必要な備蓄品や量が分かる情報を提供している。 1 戸建ての 3 日分に対し、マンションなどの共同住宅は 1 週間分が目安。 共同住宅に住む 4 人家族で計算すると、飲み水 76 リットルなど 58 品目ものリストが示された。
都が都民 1 万 5,000 人を対象に実施した 21 年のアンケートでは、食料や水を 1 週間以上備蓄している人は 10% に届かなかった。 担当者は「避難所でなく在宅を希望するなら、より余裕を持った備蓄が必要になる」と説明する。
◆ 通信手段の確保も課題に
通信手段の確保も大きな課題だ。 この 10 年で都内の固定電話加入数は半減した一方、携帯電話契約数はおよそ 3 倍になった。 災害時に通信が集中すると、事業者が回線の逼迫を避けるために通信を規制する可能性は高い。 東京都防災会議地震部会長の平田直・東大名誉教授は「交流サイト (SNS) も非常に制限されることになる」と指摘。 連絡が取れなくなった場合の集合場所を決めるなど、「事前に家族で相談しておくのが大事だ」と呼び掛けた。
◆ 耐震化進めると被害は減少
東京都防災会議の被害想定には、建物の耐震化などの対策によって被害をどのくらい減らせるかとの推計も初めて盛り込んだ。 今回の想定では最悪の場合、揺れにより全壊する建物は 8 万 1,000 棟で、死者は 3,200 人。 1981 年に導入された耐震基準を満たす住宅の割合(耐震化率)を 2020 年時点の 92% から 100% にできれば、全壊建物、死者とも6 割減らせるとした。
火災により焼失する建物は最大で 11 万 8,000 棟、死者は 2,500 人と想定。 これに対し、住宅への消火器や火災報知機の設置を進め、地震の揺れを感知して電気を止める「感震ブレーカー」の設置率を 20 年の 8.3% から 25% に上げると、焼失建物、死者とも 7 割減らせるとした。 家具などの転倒防止対策を適切に行うと死者がどれくらい減るかの推計もした。 今回の被害想定の死者は最悪の場合、240 人。 対策実施率が 20 年の 57% から75% になると、4 割減るとした。 都の担当者は「取り組めば取り組んだだけ効果が出る。 都民 1 人 1 人にはできる対策をしてほしい。」と呼び掛けた。 (加藤益丈、東京新聞 = 5-26-22)
◇ ◇ ◇
首都直下地震、死者 6,100 人を想定 耐震・不燃化進んでも阪神大震災級 都防災会議が 10 年ぶり被害見直し
東京都防災会議地震部会(部会長・平田直東大名誉教授)は 25 日、首都直下地震などの被害想定を 10 年ぶりに見直し、都心南部を震源とするマグニチュード (M) 7.3 の地震が起きると死者約 6,100 人、負傷者約 9 万 3,400 人が出るとの報告書を公表した。 23 区の約 6 割が震度 6 強以上で、江東、江戸川区などは震度 7 になると想定している。(土門哲雄)
◆ 新想定で年明けにも防災計画修正へ
建物の耐震化、不燃化が進み、2012 年想定の東京湾北部地震より死者が約 3,500 人、負傷者は約 5 万 4,200 人少ない。 ただ、依然として死者数は 1995 年の阪神大震災級。 都民の防災意識を高めてもらおうと、防災会議は今回初めて、発生直後からの時間軸で、都民を取り巻く被害のシナリオを掲載した。 平田部会長は取材に「6,000 人超の犠牲はあってはならない。 耐震化などの対策で被害を減らせる。 それぞれの地域がどうなるか、自分の場合の被害想定をしてほしい。」と呼び掛けた。
新想定に基づき、都は来年 1 月下旬に地域防災計画の修正案を公表し、来年度の早期に決定する方針。 防災会議は 5 つの地震で死者数などを算出。 このうち都内で最大の被害となる都心南部直下地震は冬の夕方 6 時に風速毎秒 8 メートルの風が吹いた場合、揺れによる建物倒壊で約 3,200 人、火災で約 2,500 人が亡くなるなどとした。 前回の被害想定から 10 年たち、各地の地震で蓄積した知見、高齢化や単身世帯の増加などを踏まえて見直した。 体が不自由な高齢者や要介護認定者などの「要配慮者」が死者数全体の 6 割超に上ると想定した。
震度 6 強 以上は 23 区の東部と南西部を中心に分布し、震度 7 は約 14 平方キロメートル、6 強 は約 388 平方キロメートル。 江東区は 13.7% が震度 7 で、84.4% が 6 強、江戸川区は 9.6% が震度 7、67.9% が 6強 となり、足立、墨田、大田、品川区は 90% 以上が 6強 になると見込んだ。 帰宅困難者は 453 万人、避難者は最大約 299 万人としている。 揺れや火災などによる建物被害は 19 万 4,400 棟で、前回想定より約 11 万棟減。 停電率は約 12%、断水率は約 26%、エレベーターは約 13 が停止して閉じ込めにつながりうると想定した。 経済被害は約 22 兆円と推計した。 (東京新聞 = 5-25-22)
「第 3 の東名」厚木秦野道路 厚木・伊勢原で工事進行中 国道 246 号の渋滞緩和へ

国道 246 号のバイパス道路「厚木秦野道路」の建設が進んでいます。 この道路は圏央道の圏央厚木 IC/JCT を起点に、伊勢原北 IC を経由し、東名の秦野中井 IC までをつなぐ総延長 29.1km の高規格道路です(未開通 IC はすべて仮称)。 1992 (平成 4)年に基本ルートが決定され、1998 (平成 10)年から各工区で順次事業化が行われてきました。
東名・新東名に並行する「第 3 の東名」として、厚木市・伊勢原市での高速道路・一般道の慢性的な渋滞を緩和する役割を果たします。 それだけでなく、圏央道と東名をつなぐ海老名 JCT がいまだ渋滞多発区間であるため、渋滞を忌避して国道 246 号を利用する車も集中しているため、その交通容量を担う意義もあります。 2022 年現在で未事業化区間は、中間部の厚木北 IC - 伊勢原北 IC と秦野中井 IC - 秦野 IC 付近。 残りの圏央厚木 - 厚木北、伊勢原北 - 秦野中井の 2 区間は、すでに用地買収と一部工事が進んでいます。
4 月 27 日に国土交通省 川崎国道事務所は、2022 年度の事業概要を発表。 厚木秦野道路に関しては、2 工区合計で 53 億円の予算を執行予定で、大半の区間は用地買収や調査設計ですが、厚木地区では圏央厚木 IC 西側の中津川橋の橋脚設置、伊勢原地区では伊勢原大山 IC の南西にある鈴川橋の橋桁設置まで進む予定だとしています。 あわせて、未事業化区間である厚木市内の区間でも、国が資金を貸し付ける「用地国債制度」を活用し、事業化にさきがけて市が独自に用地取得を進めていくとしています。 開通見込みについては、まだ発表されていません。 (乗りものニュース = 5-5-22)
隈研吾氏デザインの文化施設 JR 東、高輪ゲートウェイ駅前再開発

JR 東日本は 21 日、高輪ゲートウェイ駅(東京都港区)前の再開発計画について、建設する高層ビルなど 5 棟の概要を発表した。 建築家の隈研吾氏がデザインした文化施設や、高級ホテルとオフィスが入る商業ビルなどで、2025 年度に全面開業する予定だ。 羽田空港からのアクセスが良く、国内外からの幅広い利用を見込む。 開発の目玉は、らせん状に形作られ、日本の四季を表現したという文化施設。 地上 6 階建てで、音楽や演劇などのイベントが開ける。
駅直結の地上 29 階と 30 階の高層ビルには、外資系高級ホテル「JW マリオット」が入り、オフィスフロアには国内外のグローバル企業の誘致をめざす。 当初、24 年ごろの全面開業を計画していたが、予定地で明治の鉄道遺構「高輪築堤(ちくてい)」が見つかったため、時期を見直したという。 再開発は、車両基地の跡地約 9 万 5 千平方メートル(東京ドーム 2 個分)を活用し、総事業費は約 5,800 億円になる見通しだ。 全面開業後の年間の売上高は 560 億円を見込む。 (松本真弥、asahi = 4-23-22)
虎ノ門のビル、330m で高さ日本一に でも首位の座は数年だけ …
森ビルなどが東京都港区の虎ノ門と麻布台地区で進める再開発事業で、建設中の超高層ビルが高さ 330 メートルに達した。 21 日、現地で上棟式があった。 来年の完成時には大阪市の「あべのハルカス(300 メートル)」を抜いて日本一高いビルになる。 高さ 330 メートルの「A 街区」は 64 階建てで、清水建設が 2019 年 8 月から施工している。 この日は最上部に使われる鉄骨が、クレーンで約 3 分かけてつり上げられた。
日本一は 27 年度に交代か
ビルのオフォス部分の広さは、総貸室面積約 20 万 4 千平方メートルある。 54 - 64 階には高級ホテル「アマン」ブランドの住宅 91 戸ができる。 5 - 6 階には慶応大学病院(東京都新宿区)の予防医療センター(仮称)が入る。 再開発エリアは約 8.1 ヘクタールで、このうち約 2.4 ヘクタールが緑化される。 森ビルの広報担当者は「都心に緑を確保する手段として、ビルを高くし周辺の公開空地を広げた」と説明する。 都内ではほかにも高層ビルが計画されている。 JR 東京駅の北東側には、三菱地所が 2027 年度の完成をめざして高さ 390 メートルの「トーチタワー」を建設している。 高さ日本一の座は再び代わる見通しだ。 (高橋豪、asahi = 4-21-22)
大変身する神宮外苑、東京の歴史見つめた樹木の行方は 伐採か移植か

東京・明治神宮外苑地区でスポーツ施設や高層ビルを新設する再開発が年内にも動き出す。 施設の利便性を高めつつ、歴史と文化を継承し、その質を高めるというコンセプトだ。 だが、開発に伴う樹木の伐採・移植計画があり、地域に慣れ親しんだ人たちの心を揺さぶっている。 神宮外苑といえば、プロ野球ヤクルトが本拠を置く神宮球場や秩父宮ラグビー場、そして国立競技場が立ち並ぶ、まさに国内スポーツの中心地。 そして、聖徳記念絵画館から続くイチョウ並木は、数々の映画やドラマのロケ地にもなってきた。
その並木は保存される予定だが、再開発の事業者がつくった資料によると、外苑内の樹木 971 本が伐採、70 本が移植される見通しだ。一部には枝や幹が腐っているなど状態の悪い木も確認されたとしているが、中央大の石川幹子教授 (73) は「一本一本に人の思いが込められ、物語がある」と警鐘を鳴らす。 どういうことなのか。 石川教授は都市の緑地計画に詳しく、日本イコモス国内委員会の理事。 委員会は文化遺産保存の専門家や団体で構成され、外苑について「公共性・公益性の高い文化遺産。 都は破壊することなく継承していくべきだ。」と提言した。
石川教授は、事業者が都に提出した資料を航空写真と見比べ、写真では分からない低木も現地で確認し、伐採か移植されそうな樹木の本数を調べた。 「小さな木を含めれば、千本近くが伐採や移植されることになります」と話す。 先月、石川教授と現地を歩いた。 幹に亀裂が入ったイチョウもあった。傷んだ大木の移植は 1 本 1 千万円ほどかかるケースもあるという。 計画では伐採分と同じ本数の樹木を植えることになっているが、石川教授が指摘するのが「一本ごとの物語」だ。
外苑が整備されたのは今から 100 年ほど前の 1926 年。 明治天皇をたたえる目的で旧青山練兵場の跡地に人工の森を造り、陸上競技場や野球場なども整備された。 国内初の風致地区にも指定された。 その自然景観を形作る木々は、全国から集められたものだった。 整備費用は当時、多くの企業設立に関わった渋沢栄一が中心の「明治神宮奉賛会」が国民から寄付金を集めたが、樹木も全国から約 3 千本が寄せられた。 石川教授によると、その輸送費が半額にされたという話も残る。
外苑の敷地内にはスダジイやケヤキなどが並び、大人でも腕を回し切れないほど太い幹に成長した大木もある。 歴史を語る木々の扱いは「時間をかけて結論を出すべきだ」と石川教授は話す。 再開発計画の対象地は、明治神宮や日本スポーツ振興センター (JSC) が保有する約 28 ヘクタール。 敷地内の老朽化したスポーツ施設を建て替えるため、民間提案でまちづくりを進める制度を用い、都の都市計画決定をもとに進められる。
再開発は、三井不動産、明治神宮、JSC、伊藤忠商事の 4 者が担い、2036 年に終わる予定。 神宮球場と神宮第二球場を解体してホテル併設の新球場を建設するほか、秩父宮ラグビー場は屋根付き施設に生まれ変わる。 新たな球場とラグビー場の間には災害時の避難場所も確保される。 都の担当者は「歩行者の回遊性がなく広場空間が足りないのが課題だった。 都民に開かれた場所をめざし、にぎわいを呼び込みたい。」 このほか、秩父宮ラグビー場横の伊藤忠商事本社ビルも、今の建物の倍以上となる高さ約 190 メートルのビルに建て替えられる予定だ。
開発に伴い、やはり千本もの樹木が切られるのか。 取りまとめ役の三井不動産は「手続き中の案件なので、事業の詳細に関する回答は控えたい」としつつ、「都と協議し、外苑の歴史的重要性に配慮して対応する。 樹木医の意見を聴きながら木の状態を詳しく調べ、極力保存または移植する。」と説明した。 事業者が都に提出した再開発計画の環境影響評価書案によると、工事完了後は緑の面積の割合を示す緑被率が 16% から 18.7% に増える一方、緑の体積は約 34 万 6 千立方メートルから約 31 万 4 千立方メートルに減る。 伐採分の代わりに若木を多く植えるなどするためだ。開発が周囲の環境に与える影響などについて、都の審議会でも議論が続いている。 (小林太一、asahi = 4-17-22)
JR 東、首都圏運賃 10 円上げへ 来春、駅のバリアフリー化費用に
JR 東日本は 5 日、2023 年 3 月ごろに首都圏の鉄道運賃を 10 円値上げすると発表した。 値上げ分を駅のバリアフリー化を進める費用に充てる。 初乗り運賃は切符の場合、140 円から 150 円に、IC カードは 136 円から 146 円になる。 整備費用を乗客負担とする政府の新料金制度を活用する。 JR 東は 5 日に国土交通省関東運輸局に届け出を提出した。 値上げするのは利用者が多く、運賃が割安に設定されている東京の「電車特定区間」。 10円値上げによる増収効果は毎年約 230 億円という。 通勤定期の場合、1 カ月は 280 円、3 カ月は 790 円、6 カ月は 1,420 円それぞれ値上げする。 (kyodo = 4-5-22)
世帯年収は平均 1,019 万円 人気は 23 区、価格は 5,000 万円超が主流 首都圏で新築マンション買った人あれこれ
株式会社リクルートの住まい領域の調査研究機関である「SUUMO リサーチセンター」が、2021 年に首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)の新築分譲マンションを契約した人を対象とした「首都圏新築マンション契約者動向調査」を発表しました。 同調査によると、物件の購入平均価格は「5,709 万円」で、2001 年調査開始以来、最も高くなりました。 また、物件の平均専有面積は「66.0 平方メートル」で、こちらも 2001 年調査開始以来、最も小さくなったそうです。 2021 年 1 月 - 2021 年 12 月の期間に実施された調査で、集計数は 7,289 件でした。
契約世帯主の平均年齢は「38.8 歳」でした。 なお、ライフステージ別に見ると、夫婦のみ世帯の平均年齢が最も低く、「34.2 歳」でした。 また、既婚世帯を共働き状況別に見ると、共働きをしている方が平均年齢は低く、「36.2 歳」だったそうです。 続いて、「共働き比率」で見ると、全体に占める共働き世帯の割合は「59%」でした。 既婚世帯では「74%」で、2001 年の調査開始以来、最も高くなったそうです。 さらに詳しく見ると、夫婦のみ世帯では「89%」、子どもあり世帯では「68%」、シニアカップル世帯では「39%」だったそうです。
さらに「世帯総年収」で見ると、全体平均は「1,019 万円」で、2008 年以降で最も高くなりました。 なお、ライフステージ別に見ると、シングル世帯以外は平均世帯総年収が 1,000 万円を超えていました。 また、既婚世帯を共働き状況別に見ると、共働きをしている方が平均世帯総年収は高く「1,087 万円」、共働きをしていない世帯では「1,031 万円」だったそうです。
「購入した物件の所在地」を聞いたところ、「東京 23 区」が最も多く 39% でした。 次いで、「神奈川県」が 25% で、2020 年と比べて「神奈川県」が増加、「千葉県」が減少したそうです。 ライフステージ別に見ると、「東京 23 区」の割合がシングル男女世帯では半数を超えており、既婚世帯を共働き状況別に見ると、共働きをしている方が「東京 23 区」の割合がやや高いそうです。 さらに、共働き世帯を総年収別に見ると、総年収 1,000 万円以上の世帯の人の 50% が「東京 23 区」だったそうです。
続いて「物件の購入価格」について聞いたところ、「6,000 万円以上 (36%)」、「5,000 - 6,000 万円未満 (22%)」となり、5,000 万円以上で全体の 57% を占めました。 平均購入価格は「5,709 万円」で、2001 年以降で最も高くなったそうです。 ライフステージ別では、シニアカップル世帯で「6,000 万円以上」が 46% を占め、平均 6,154 万円で最も高いといいます。 また、既婚・共働き世帯を、総年収別に見ると総年収 1,000 万円以上の世帯では「6,000 万円以上」が 64% を占め、平均「6,939 万円」となっているそうです。
「物件の専有面積」については、「70 - 75 平方メートル未満」が最も多く 33% で、「60 - 70 平方メートル未満」が 27% と続きました。 2001 年には 23% だった 70 平方メートル未満の割合が 2021 年は 48% となり、平均専有面積は「66.0 平方メートル」で、2001 年の調査開始以来、最も小さくなったといいます。 また、ライフステージ別に見ると、平均専有面積が最も大きいのは子どもあり世帯で、「72.2 平方メートル」だったそうです。
さらに「ローン借入金額」を聞いたところ、「5,000 万円以上」が 45% を占め、「平均 4,941 万円」となり、2005 年以降で最も高くなったそうです。 ライフステージ別に見ると、夫婦のみ世帯、子どもあり世帯で、ローン借入総額(平均)が 5,000 万円を超えるといいます。 既婚世帯を共働き状況別に見ると、共働きをしている方がローン借入総額(平均)が高く、さらに、共働き世帯を総年収別に見ると、総年収 1,000 万円以上の世帯では、「5,000 万円以上」が 78% を占め、平均で 6,103 万円となっているそうです。 (まいどなニュース = 4-3-22)
東京で桜開花 平年より 4 日早い開花発表

今日 20 日(日)、東京・靖国神社の桜が開花したと発表されました。 平年より 4 日早く、昨年より 6 日遅い開花の発表です。 今年は 17 日(木)に開花発表のあった福岡、18 日(金)の宮崎、19 日(土)の高知と佐賀、20 日(日)の熊本に次いで、全国で 6 番目のソメイヨシノ開花の発表となりました。
東京・靖国神社では 19 日(土)夕方の段階で、軸がのびきっているつぼみが増え、花がほころんできているものも数輪みられました。 今日 20 日(日)は朝から日差しが届き、13 時 22 分の時点で気温は 15.5℃ まで上がったことで、桜はさらに生長して開花しました。 気象庁・気象台では「標本木」と呼ばれる観測対象の木を定めていて、5 - 6 輪以上の花が咲いた状態を開花発表の目安としています。 東京の場合、標本木は東京都千代田区の靖国神社にあります。
桜前線は一歩一歩着実に進む
ウェザーニュース発表の桜開花予想では、今年のソメイヨシノの開花は全国的に平年並みから早い予想となっています。 桜のつぼみは今月前半の暖かさで生長が進んでいます。 週中ごろにかけては極端な暖かさはない予想のため、開花前線はゆっくりと一歩一歩着実に進むことになりそうです。 西日本や東日本では、徐々に桜が開花するところが増えてくるので、ご近所の桜のつぼみに注目してみてください。 (ウェザーニュース = 3-20-20)
〈編者注〉 写真は、前日(19 日)、1 本のソメイヨシノで最初に開花した 1 輪です。 (撮影 : 東京都新宿区)