ホテルや天然温泉 … 羽田新スポット 開業は夏に延期
緊急事態宣言で開業が延期となっている、羽田空港と直結した「羽田エアポートガーデン」は国内最大となる 1,717 室の空港ホテルや飲食店、天然温泉など、先月に開業する予定でした。 しかし、政府の緊急事態宣言を受けて開業が夏に延期されました。 (ANN = 5-4-20)
前 報 (12-11-19)
◇ ◇ ◇
JAL、羽田・成田空港の国際線全ラウンジを閉鎖
日本航空 (JAL) は、新型コロナウイルス感染拡大による運航便数やラウンジ利用者数の減少に伴い、羽田空港・成田空港国際線の全てのラウンジを休業する。 期間は4 月 27 日から 5 月 31 日まで。 羽田空港第 3 ターミナルと成田空港第 2 ターミナル国際線の全てのファーストクラスラウンジ・サクララウンジを閉鎖する。 なお、羽田空港国内線のダイヤモンド・プレミアラウンジとサクララウンジは、南ウイングのみ営業している。 成田空港国内線サクララウンジは閉鎖している。 (柴田勇吾、Traicy = 4-24-20)
緊急事態宣言後の 3 日間 首都圏 JR 定期券利用客 5 割減
緊急事態宣言が出されたあとの今月 10 日までの 3 日間に、首都圏の JR の在来線を定期券で利用した人は、去年の同じ時期と比べて 50% 減っていたことが分かりました。 JR 東日本によりますと、緊急事態宣言が出された翌日の今月 8 日から 10 日までの平日 3 日間に首都圏の在来線を定期券で利用した人は、
▽ 去年の同じ時期と比べて 50%、
▽ 緊急事態宣言が出される前の週と比べて 26%、それぞれ減っていたということです。
また、主要な駅ごとに IC カードなどでの利用者を見てみると、
▽ 東京駅では去年の同じ時期と比べて 85% 減少していたほか、
▽ 新宿駅は 78%、
▽ 渋谷駅は 76%、
▽ 横浜駅と千葉駅、それに大宮駅は 69% と、それぞれ大きく減少していました。
ただ、この主要駅ごとのデータはICカードなど定期券以外の利用者のみが反映されたもので、オフィスワーカーなどが含まれていない可能性が高いということです。
さらに、山手線では今月 10 日までの 3 日間の朝の通勤時間帯で定期券を含むすべての利用者は、
▽ 通常期と比べて 60%、
▽ 緊急事態宣言が出される前の週と比べて 35%、それぞれ減っていました。
一方、緊急事態宣言が出されて初めての週末となった土曜日と日曜日の 2 日間の利用状況を見てみると、
▽ 山手線は 85%、
▽ 新幹線と特急列車は 92%、それぞれ去年の同じ時期と比べて減少していたということです。 (NHK = 4-13-20)
羽田の新飛行ルート、本格運用を開始 くすぶる騒音問題
東京都心の低空を通る羽田空港の新飛行ルートが 3 日、初めて本格的に使われた。 政府は羽田の発着を増やして多くの外国人客を呼び込みたい考えだが、この日は新型コロナウイルスの影響で欠航が相次いだ。 騒音などに対する住民の懸念もくすぶり続ける。 都心低空ルートは、南風が吹く夕方の最大 3 時間使われる。 新宿、渋谷、品川、大井町などの上空を通り、東側のルートは 2 分間隔、西側は 4 分強間隔で着陸する。 3 月 29 日に始まる予定だったが、北風の日が続いたため、北風時に北向きに離陸して荒川沿いを上昇するルートの運用だけが始まっていた。
高度は新宿で約 900 メートル、品川で約 450 メートル、大井町で約 300 メートルとなる。 1 時間あたりの発着数が現在の最大 80 回から 90 回になり、ほかの運用見直しも加えて年最大 3.9 万回増えると試算されている。 住民の最大の懸念は騒音だ。 国土交通省はそうした声を受け、2 月上旬に試験飛行をして騒音を測定。 機体の大きさを踏まえて地点ごとに集計したところ、中小型機を中心に約 2 割の地点で想定より 1 - 3 デシベルほど大きな値が出た。 想定通りが約 6 割で、想定以下は約 2 割だった。 「想定を著しく上回る結果が出てきた場合は、必要に応じてさらなる騒音対策をしていく」としている。
ただ 3 月 27 日には、試験飛行を機に新ルートを問題視するようになったという港区などの住民約 30 人が運用改善を求める要望書を国交省に提出。 「予想を超える騒音に生活の安全と質が脅かされると感じた」などと訴えた。 ほかの市民団体も、署名を集めるなどして見直しを呼びかける方針だ。 新ルートではまた、騒音対策として着陸時に一般的な 3.0 度よりも急な 3.45 度で降りる方法が採用されているが、一部のパイロットや専門家からは「速度が上がり操縦が難しくなる」との声がある。 部品の落下を懸念する住民もいる。
国交省によると、新型コロナウイルスの影響で、羽田の 3 月下旬の発着数は国際線が約 7 割減の約 80 回、国内線が 2 割減の約 800 回になっていたが、赤羽一嘉国交相は「必ず(増便が)必要なときは来る。 助走期間としてしっかりデータを蓄積して分析をする。」とし、予定通りに運用を始めていた。 (贄川俊、asahi = 4-3-20)
◇ ◇ ◇
羽田都心新ルート、これだけある危険な理由
落下物や騒音だけじゃない深刻リスク パイロットには恐怖の空港に
3 月 29 日に始まる夏ダイヤから、羽田空港への進入着陸は南風の時には東京都心上空を使う新ルートに変更される。 国土交通省によれば、新ルートの運用等による発着数の増加は年間 3.9 万回、うち都心上空を進入着陸に使う増加分は 1.1 万回だけで、羽田の発着枠の 2.5% に過ぎないと説明する。 だが、この新ルートは、都心の騒音だけではなく事故のリスク増加など数々の問題点をはらんでいる。 その理由をここで明らかにしたい。
▽ 防ぎきれない経年劣化による落下物
振動が大きくなる進入着陸時における航空機からのパネルや部品、それに上空で自然に出来上った氷塊の落下は、残念ながら現在の技術では防ぐことの出来ない問題である。 国交省は内外の航空会社に整備を強化して落下物が発生しないようにすると言っているが、各航空会社にはそれぞれの整備方式があり、日本の行政機関が指示したり変更したりするのは不可能だ。
一般的に整備は年数や飛行時間ごとに約 4 段階に分かれている。 全てを分解して点検するオーバーホールは約 4 - 5 年に 1 度。 2017 年の秋に関西国際空港を飛び立った KLM オランダ航空が 2 メートルにもなるパネルを落下させ、それが車に衝突して大問題になったが、このような経年劣化による落下物は日常の点検で発見することはほぼ不可能だ。
直近では昨年 12 月 3 日、ボストンの空港に進入中のデルタ航空機がなんと緊急用の脱出シュートを落下させ、一歩間違えば大惨事になるところだった。 日本の航空機も各地に部品等を落下させている。 成田空港周辺では報告されているものだけで数十件ある。 農家のビニールハウスや屋根を直撃した例も少なくない。
▽ 落下物「羽田はゼロ」の真相
国交省は近頃発行した「羽田空港のこれから」というパンフレットの中で、落下物について、近年成田では 21 件あったが羽田ではゼロと宣伝している。 しかしその真相は、これまで羽田への進入ルートは海上であったために落下物が海に落ちていたからに過ぎない。 この論理はおよそ自然科学を無視したもので落下物の頻度は単純に便数に比例するものと考えるべきだろう。 一方、氷塊の落下は多くは車輪を出す際に、その振動で格納部の中で上空で冷やされ氷となったものが落ちてくるもので、直径 10 センチになるものもある。 格納部分にはエアコンが通っていないからだ。
結局、国交省が打ち出した「落下物対策」で唯一目に付くものは、運悪く落下物で被害に遭えば金で補償するというものだけ。 しかもその金は航空会社から保険金として集めたものを使うという。 人が死傷したり、車や家が損傷を受けても運が悪かったと金で解決するという考え方はいかがなものだろうか。
騒音についてはこれまで最大 80 デシベル以上は発生しないと先に触れたパンフレットには書かれていた。 が、1 月 30 日からの「確認フライト」では民放テレビスタッフの計測で 87 デシベルを超えるなど各地で想定より大きな音が観測され、B 滑走路から西へ離陸する航空機からは毎回 90 デシベルを超える騒音が発生していた。 オリンピックを迎える夏の季節には騒音はさらに大きくなる。
▽ 旧香港空港より急角度! 世界のパイロットから異議
計画発表以来、これまで 5 年間の議論で進入は GPS を使った RNAV 進入と ILS (計器着陸装置)による 3 度の角度で行うとされてきた。 ところが去年の 7 月末、実際に最も多く使われる RNAV 進入の角度が 3.45 となった。 パイロットにとって進入角は 0.1 度大きくなるだけで滑走路の見え方は変わる。それが 0.45 度も大きくなると、地面に突っ込んでいく感じで最後の着陸操作が非常に難しくなる。 ちなみに以前世界で着陸が最も難しいとされた(旧)香港空港のホンコンアプローチでも進入角は 3.1 度だった。
着地の時に機首を上げて降下率を少なく、減速する操作をフレアーと呼ぶが、そのフレアーの開始を上空の高い所から行う必要があり、タイミングがずれると尻もち事故やハードランディングにつながる。 また急角度の進入では十分減速できないまま滑走路に接地するためよくバウンドしてしまう。 2019 年 5 月にロシア機がバウンドした後に尻もちし炎上、41 人が亡くなった事故が象徴的だ。
今般の 3.45 度の RNAV 進入の問題点は、私だけでなく世界中のパイロットを組織している IFALPA (国際定期航空操縦士協会)も 1 月 20 日に見解を出し、同様の安全上の懸念と着陸上の注意点を各パイロットへ通知している。 そして 1 月末から始まった乗客を乗せた便での確認フライトで、エアカナダとデルタ航空が安全上の検討が必要と 3.45 度の RNAV 進入を拒否した。 この判断は IFALPA の見解に沿ったもので、極めて妥当なものだ。
▽ パイロットに大きな恐怖
日本では、約 25 年前から、着陸事故をなくすために「スタビライズド・アプローチ(安定的進入)」というポリシーを確立し、今では LCC も含め日本の航空会社は全て運航規定にそれを定めている。 その規定とは、航空機が地上から 1 千フィート(約 300 メートル)の所に到達した時点で降下率が毎分 1 千フィート以内の状態で安定していないと、いったん進入を中止してゴーアラウンド(進入復航)しなければならないというものだ。
この、いわば憲法のような規程は、3 度の進入角を前提として作成された。 3.45 度となると、着陸重量や気象条件によってさらに急角度での進入着陸となるケースも出てくる。 これまで日本のパイロットはこの規定を守り、大きな着陸事故を発生させない努力をしてきたが、それを一瞬に壊す可能性がある。 国交省も、そのような運航規程違反を黙認するのだとすれば、断じて許すことはできない。
国交省は、急角度の進入は稚内や広島、それに米国のサンディエゴで行われていると主張している。 が、そもそも稚内や広島での一部の進入は VOR と呼ばれる古いタイプのもので、RNAV 進入と比較すること自体無理がある。 加えて、サンディエゴでは大型機は飛行しておらず、降下角 3 度の有視界飛行で降りているのが実情だ。
日本の夏は近年 6 月から 9 月まで気温が 35 度を超える猛暑日が多い。 そうなると標準大気状態で設定されている 3.45 度の角度は 3.7 度を超えるようになる。 その理由は、気温が上がり空気密度が低下することにより、航空機の実高度が高くなるためだ。 その結果、最終降下地点からの角度は非常に大きくなる。 パイロットは大きな恐怖心を抱くことになるだろう。
そして突然出された 3.45 度の RNAV 進入は、関係者によると、実は横田空域を米軍機が飛行するため A 滑走路への最終降下地点 (FAF) を 3,800 フィート以上という条件がつけられたために発生したもの。 騒音対策というのは虚偽の説明なのである。 都心上空で 2 次被害も伴う墜落事故が発生する可能性にも言及しておく。 近年のハイテク機は通常運航ではパイロットにとって便利な反面、トラブルが起きると、時にパイロットがパニックになったりそれを制御できずに墜落事故を起こしたりする例がある。
最新鋭のボーイング 737MAX の一連の墜落事故の原因は、センサーからの誤ったシグナルで操縦系統が暴走したことによるものだ。 2 件の事故がいずれも離陸直後に起きたことを考えれば、B 滑走路を西側に離陸して川崎コンビナート上空を飛行するルートで、仮に同様のことが起きたら大惨事になるだろう。
▽ 成田と羽田の棲み分け議論ないまま
歴史を振り返れば、地権者や反対する市民との壮絶な紛争の末に建設された成田空港に 1978 年、国際線の全てが移ったことにより、国際線は成田、国内線は羽田という棲み分けができた。 これは国会でも長い時間かけて議論された結果としての我が国の「航空政策」だった。
しかし 2010 年、国内線の需要増加に合わせて羽田の沖合いに D 滑走路が建設されると発着枠が増え、当初はソウルやグアムといった近距離国際線のチャーター便が成田から帰ってきた。 そしていつの間にか定期便にまで広がり、気が付くと米国西海岸やハワイ路線も戻ってきていた。 今日ではニューヨーク、ワシントン等の米国東部とを結ぶ便や欧州直行便など長距離国際線までもが当然のように羽田に戻ってきている。 つまり、羽田と成田の棲み分けをどうするのかといった「航空政策」無しに、ずるずると場当り的に羽田重視の行政が進行していると言えよう。
世界の大都市の空港で、いったん郊外に新設された国際空港から、市街地が近くて便利だからといって長距離国際線を中心とした主力路線が戻ってくるなどという例は聞いたことがない。 (杉江弘 = 元日本航空機長、kyodo = 3-2-20)
◇ ◇ ◇
2 分に 1 度の大轟音「羽田新ルート」でタワマンに下落リスク
東京都心の上空を行き来する羽田空港の新ルートの運用が 3 月 29 日から始まる。 不動産コンサルタントの長嶋修氏は「住宅街に轟音が響けば、不動産価格に影響が出る恐れがある。 例えば上階ほど価値が高いタワーマンションの価格は、試算で最大 26% の下落リスクがある」と指摘する。
■ 新宿・渋谷・品川など東京都心にジェット音が鳴り響く
「結構うるさいね。」 「こんなに低空とは思わなかった。」
筆者は東京渋谷区・代官山に住んでいるが、2 月に行われた試験飛行で、金属と空気の摩擦音やジェット音を伴って次々と飛来する大型旅客機を見上げつつ、街を行き交う人がこんな感想を漏らしているのを複数見かけた。
3 月 29 日から、羽田空港に新空路が設定される。 訪日外国人の増加や 2020 年 7 月に控える東京オリンピック・パラリンピックへの対応、首都圏の国際競争力強化などを目的として深夜・早朝時間帯を除きフル稼働している羽田空港の発着便を増やすべく、旅客機は埼玉県上空で左旋回した後、高度を下げながら新宿・渋谷・目黒・港・品川・大田区といった東京都心上空を抜け羽田空港に着陸する。
「松濤」、「青山」、「広尾」、「代官山」、「白金」、「御殿山」といった、東京都心の閑静な高級住宅街やタワーマンションの数百メートル上空を大型旅客機が飛来することとなる。 ルート下には、上皇・上皇后ご夫妻の仮住まい先となる「高輪皇族邸」もある。 計画では都心部上空を着陸体制で、300 - 900 メートルの低空飛行で通過。 着陸時間帯は 15 時から 19 時(南風運用時)のうち 3 時間程度に限定されるものの、この間は発着数が最大 90 回、2 分に 1 回といった、通勤ラッシュ時の JR 山手線より多いペースで大型旅客機が続々と飛来する。
これに先立ち、国土交通省は 2 日から 12 日にかけて旅客機の定期便がこの空路を飛ぶ「飛行確認」を行い、ルート周辺で測定した騒音のデータの分析を進めている。
■ "騒音" が不動産価格に与える影響は決まっていない
これによる懸念は大きく 2 つだ。 まずは「旅客機からの落下物」。 人口密集地帯である都心部に機体の一部などが落下すれば、その影響は計り知れない。 国交省は「各エアラインには注意喚起を促す」としているものの、現実に飛行機から部品が落ちてきたといった実例は、ある。 もう 1 つは「騒音」。 一般に、線路や高速道路・工場など騒音や振動・臭いを発するいわゆる「嫌悪施設」の影響を受ける不動産は、その価値が一定程度下落する。 例えば閑静な住宅街の真ん中にいきなり騒音を放つ工場ができれば、その影響は甚大だろう。 だからこそ都市計画法ではその用途を主に「商業系」、「工業系」、「住宅系」の 3 つに分類し、土地利用を制限している。
ところが今回のように、上空からの飛行機騒音や落下物の可能性は、都市計画には織り込まれていない。 さらに、新空路の下には、閑静な高級住宅街や高級タワーマンションが多数存在する。 一般論として「ゴミ焼却施設」や「下水処理場」、「葬儀場」、「火葬場」、「刑務所」、「火薬類の貯蔵所」、「危険物を取り扱ったり悪臭・騒音・震動などを発生させたりする工場」、「高圧線鉄塔」、「墓地」、「ガソリンスタンド」などが嫌悪施設に該当するとされるが、明確な定義はない。 不動産取引を規定する「宅地建物取引業法」では、「相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるもの」に関して説明義務を課しているだけだ。
したがって、こうした嫌悪施設から具体的に何メートルの距離にあった場合、どの程度の騒音の場合に、どの程度資産価格に影響があるといった基準もなく、どの程度の状況なら説明するかといったさじ加減は、不動産各社にゆだねられているのが実情だ。
■ マンション 40 階なら 120 メートル分騒音に近づく
今回のケースでは、駅周辺や繁華街など商業系地域で、従前から一定の騒音が発生している地域のみならず、松濤・青山・広尾・代官山・白金・御殿山といった、都心を代表する高級住宅街でこうした騒音が毎日発生する。 またタワーマンションは「眺望が良い」といった観点から、一般に上階に行けば行くほど資産価格が高い。 ところが、上空から騒音が発せられるとなると、話は変わってくる。 1F あたりの高さが 3 メートルと換算すると、30F は 90 メートル、40F なら 120 メートル分、音源に近づく。 港区には 47F 建てのタワーマンションもある。
具体的にどのくらいうるさくなるか。 国交省の想定では、渋谷駅周辺が高度 600m で最大 74dB (デシベル)、五反田・品川駅周辺が高度 450m で 76dB、大井町駅周辺は高度 300m で 80dB だ。 70dB といえば、「電車の車内」、「掃除機の音」、「騒々しい事務所の中」と等しい。 80dB では「地下鉄の車内」、「ボウリング場」、「交通量の多い道路」、「機械工場の音」と同等であり会話がかき消されるほどの騒音だ。
■ 1 億円のタワマンが 7,500 万円程度になる計算に
では、資産価格はどのくらい下がる可能性があるだろうか? ところがわが国には、騒音が資産価格に与える影響に関し明確な基準はなく、裏付けとなるデータも存在しない。 そこで海外事例を参照してみる。 アメリカのコンサルティング会社が 1994 年に米連邦航空局に提出した報告書によれば、ロサンゼルス国際空港北部における、飛行機騒音による不動産価格は、1dB 上昇するごとに 1.33% ずつ下落していた。
このデータを用い、環境省が定める「環境基準(生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準)」の 55dB をベースとして試算すると、現状は環境基準程度の騒音状態である代官山や白金あたりの資産価格は最大 25%、現在 60dB 程度の大井町駅周辺では最大 26% の資産価格下落の可能性がある。 1 億円のタワーマンションは 7,500 万円程度になる計算だ。 タワーマンションの高層階で、サッシの防音等級がそれほど高くない場合には、下落率はさらに高くなるかもしれない。
こうした懸念に対して国交省は「航空機の飛行と不動産価値の変動との間に直接的な因果関係を見出すことは難しい」と回答をしつつ、各地で説明会を開催するなどのアクションを起こしてきた。 筆者はいくつかの説明会に参加したが、とある会場では、担当者に猛然と抗議する地域住民の姿がみられた。 複数の反対運動を行う会が結成され、HP や街頭活動を通じて見直しを訴えている。 (長嶋修・不動産コンサルタント、President = 2-20-20)
◇ ◇ ◇
羽田新ルート、着陸方法に問題 元パイロットらが会見、撤回要求
東京都心を通過する羽田空港の新飛行ルートを巡り、導入に反対する住民グループの代表大村究さんと元日航機長杉江弘さんが 13 日、東京都内の日本外国特派員協会で記者会見した。 2 人は新たに採用される着陸方法の危険性や、発着回数を増やす効果が乏しいことを指摘。 ルートの撤回を訴えた。 国土交通省は、騒音軽減のため航空機の「降下角度」を引き上げる対策を打ち出している。 杉江さんは、尻もち事故を誘発しかねない角度だとして「安全に着陸させる操縦の難易度が増し、羽田は世界一着陸が難しい空港になる」と話した。 (kyodo = 2-13-20)
◇ ◇ ◇
デルタ、都心ルート運用見合わせ 羽田降下「通常より急角度」
東京都心を通過する羽田空港の新飛行ルートに関し、米航空大手のデルタ航空が、新たに採用された着陸方法の「安全性が社内で確認できていない」として、2 日に始まった「実機飛行確認」での運用を見合わせていることが 5 日、同社への取材で分かった。 都心ルートでは、飛行高度を上げ騒音を軽減する目的で、航空機が高度を下げていく際の「降下角度」を従来の 3.0 度から 3.5 度に引き上げた。 デルタは「通常よりも急角度」と見合わせの理由を挙げている。 3 月 29 日の都心ルートの正式運用までには社内の事前準備を終えたいとしている。 (kyodo = 2-5-20)
◇ ◇ ◇
羽田新ルートの試験飛行開始 都心の低空、騒音に懸念も
3 月 29 日から運用が始まる羽田空港の新飛行ルートで、実際に乗客のいる旅客機で東京都心の低空を通る試験飛行が 2 日午後に初めてあった。 試験飛行は管制手順の確認や騒音の影響を測ることが目的。 3 月 11 日までに計 7 日間程度おこなう予定だ。 政府は今年までに訪日外国人客を年間 4 千万人に増やす目標を掲げる。 新ルートによって 1 時間当たりの発着数が 10 回増えて最大 90 回になり、そのほかの運用改善と合わせて、早朝・深夜を除く国際線の発着数は現在の最大年 6 万回から 9 万 9 千回に増える。
新ルートは、新宿駅付近で高さ約 1 千メートル、恵比寿駅付近で約 700 メートル、大井町駅付近で約 300 メートル上空を飛ぶ。 大井町駅周辺では、掃除機に相当する最大 76 - 80 デシベルの騒音がすることになり、ルート周辺の住民には騒音への懸念が根強くある。 2 日の試験飛行は、午後 4 時 20 分ごろから約 1 時間 40 分実施した。 大井町駅付近では、多くの歩行者が「ゴォーッ」という低い音をさせながら近づく飛行機に気づき、足を止めて真上を覆うように通過する様子を見上げていた。 (asahi = 2-2-20)
前 報 (11-16-19)
東京駅と上野駅、先週末は利用者激減 平年の 2 割以下
新型コロナウイルスの感染拡大で、首都圏に初めて不要不急の外出自粛が要請された週末の主要駅の利用状況を JR 東日本が 30 日発表した。 28 日の東京駅と上野駅の利用者数は前年の同時期に比べ 18% と激減。 新宿駅は 24%、渋谷駅でも 26% と大幅に減った。 3 連休だった前週末の 21 - 22 日は東京駅が前年比 48%、上野駅 59%、新宿駅 65%、渋谷駅 67% で、1 週間でさらに半分以下になったことになる。 (asahi = 3-30-20)
横浜北西線が開通 東名 - 横浜港のアクセス向上 神奈川
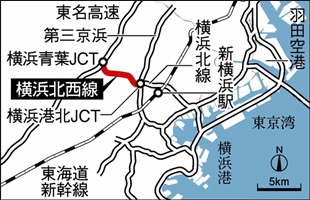
東名高速道路と第三京浜道路を結ぶ首都高「横浜北西線(約 7.1 キロ)」が 22 日午後 4 時に開通する。 東名高速から横浜港まで高速道路にのったまま行けるようになり、物流の効率化などにつながると期待されている。
横浜北西線は、東名高速の横浜青葉ジャンクション(JCT、横浜市青葉区)と第三京浜の横浜港北 JCT (同市都筑区)を結ぶ。 全体の 6 割弱の 4.1 キロがトンネルだ。 路線名は「高速神奈川 7 号横浜北西線」。 横浜港北 JCT と生麦 JCT (同市鶴見区)を結ぶ「横浜北線(2017 年 3 月開通、約 8.2 キロ)」と接続し、これで東名高速と横浜港が高速道路で直結される。 東名高速から横浜港までの所要時間は、これまでの約 60 - 40 分から約 20 分に短縮され、並行する保土ケ谷バイパスの混雑緩和も期待できるという。
通行料金(普通車で ETC 利用の場合)は、横浜青葉 JCT から横浜港北 JCT まで 400 円。 東名高速と連続利用した場合の横浜青葉 JCT からみなとみらいまでが 880 円、晴海までが 1,510 円など。 首都高速道路と横浜市が 12 2年度に事業着手。 当初は 22 年 3 月末までに開通する予定だったが、約 2 年前倒しされた。 総事業費は約 2,600 億円。 通行量は 1 日平均 4 万 1 千台分を見込む。 市などは「東名高速から、新横浜や羽田空港、横浜港へのアクセスが改善され、国際競争力の向上や物流効率化につながる」と期待する。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、22 日に予定されていた開通式典は中止された。 開通前の横浜北西線など約 16 キロを走る 2 月 29 日のファンランや、3 月 8 日の一般公開イベントも取りやめになった。 (武井宏之、asahi = 3-22-20)
JR 原宿駅の新しい駅舎 きょうから利用開始

東京オリンピック・パラリンピックに向けて建設が進められていた JR 山手線・原宿駅の新しい駅舎が完成し、21 日から利用が始まりました。 一方、都内で最も古い木造駅舎として親しまれた建物は役割を終え、96 年の歴史に幕を下ろしました。 原宿駅は、大正 13 年に建てられた都内に残る最も古い木造駅舎ですが、耐火性能が不十分などとして解体されることが決まり、21 日未明の最終電車で最後の営業となりました。 そして、21 日午前 1 時 10 分すぎ、原宿駅の駅員らが 1 列に並ぶと、「96 年間ありがとうございました」とあいさつし、駅のシャッターが閉められました。
21 日の始発からは、隣接する新しい駅舎で営業が始まり、午前 4 時 10 分に駅のシャッターが開けられると、早速、駅舎の中に入って写真を撮ったり記念に入場券を購入したりする鉄道ファンの姿が見られました。 新しい駅舎は鉄筋 2 階建てで、延べ床面積は前の駅舎のおよそ 4 倍に広がっているほか、壁はガラス張りで明るく開放的な空間になっています。 これまで 1 つだったホームは外回りと内回りで 2 つに分けられ、午前中から多くの人が利用していましたが、人の流れはスムーズで、混雑は見られませんでした。
原宿に友人と遊びに来たという 18 歳の女子高校生は、「前の駅舎も好きでしたが、新しい駅舎はガラス張りでとても明るいし、改札の中も広くて利用しやすかったです」と話していました。 新駅舎の特徴は、
- 新しい駅舎は、木造駅舎に隣接する場所に建てられ、鉄筋の 2 階建てで延べ床面積はこれまでのおよそ 4 倍と広くなっています。
- 新駅舎のデザインは、周辺の明治神宮や代々木体育館などとの調和をコンセプトに「主張しすぎないベージュ」を基調とし、ガラス張りで開放感がある空間となっています。
- 1 階部分は改札とコンコースで、出入り口は、竹下通り側と表参道側のほかに新たに明治神宮側にも設けられます。
- また、エレベーターを増やし、車いすの人も利用しやすい多機能トイレが整備されたほか、ベビー休憩室も新たに設置されています。
- このほか、1 階にコンビニエンスストア、2 階に東京を中心に展開するコーヒー店がオープンします。
- 一方、これまで 1 つだったホームは、外回りと内回りでそれぞれ専用ホームとなり、混雑の緩和が見込めるということです。
原宿駅舎の歴史と特徴
原宿駅は明治 39 年に開業し、関東大震災の翌年の大正 13 年に 2 代目となる木造駅舎が建てられました。 太平洋戦争では、昭和 20 年 5 月の「山の手空襲」で、青山通りや表参道などが焼け野原となる中、原宿駅は奇跡的に焼失を免れ、100 年近くにわたって利用されてきました。 2 階建ての駅舎は、ヨーロッパの「ハーフティンバー様式」と呼ばれる柱やはりが建物の外に露出するデザインが取り入れられ、白い外壁や屋根の 8 角形のせん塔の風見鶏が特徴です。
しかし、東京オリンピック・パラリンピックを前に、多くの利用客が見込まれる中、駅が老朽化しているとして、JR 東日本は、4 年前の平成 28 年に駅舎の建て替えを発表しました。 その後、駅舎の保存を要望する地元住民などの声を受け、JR 東日本は協議の場を設けて対応を検討してきましたが、去年 11 月、耐火性能の問題などから保存は難しいと判断し、解体することを決めました。 木造駅舎は、東京オリンピック・パラリンピック後に解体されますが、耐火基準を満たした材料で再現した建物が近くに建てられる予定です。 (NHK = 3-21-20)
◇ ◇ ◇
JR 原宿駅の新駅舎を公開 都内最古の木造駅舎は解体へ
JR山手線・原宿駅(東京都渋谷区)の新しい駅舎の建設現場が 29 日、報道公開された。 新駅舎は 3 月 21 日から使い始め、都内に現存する最古の木造駅舎とされる現駅舎は、五輪・パラリンピック大会終了後に解体される予定だ。 新駅舎は、現駅舎から渋谷寄りの線路とホーム上に2階建てで建設される。 床面積は現駅舎の約 4 倍で、1 階にコンビニ、2 階にカフェができる。 改札内のコンコースは両側ともガラス張りで、開放的な雰囲気になっている。
新たに外回り専用のホームが設けられ、現在のホームは内回り専用となる。 出入り口は現在の竹下口と表参道口(東口)に加え、明治神宮側に西口ができる。 1924 (大正 13)年に完成した現駅舎は、屋根上にある小さな尖塔が印象的な欧風のデザインで知られる。 JR 東日本によると、法律が定める耐火性能を保てないため、取り壊すことになった。 跡地の再開発では、外壁のデザインなどを再現した建物に建て替えるという。 (細沢礼輝、asahi = 1-29-20)
東京・靖国神社で桜開花 雨の中の開花宣言 観測史上最も早い記録

今日 3 月 14 日(土)、気象庁は東京・靖国神社にある桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。 平年より 12 日早く、昨年より 7 日早い開花で、統計開始以来最も早い開花日となりました。 東京の桜は 8 年連続で平年(3 月 26 日)よりも早く咲きました。 2002 年・2013 年に記録していた最早日(3 月 16 日)を 7 年ぶりに更新したことになります。
今週、東京では 3 月 9 日(月)から 5 日連続で最高気温が 15℃ を超え、11 日(水)には 20℃ 超えの暖かさとなり、つぼみの生長が進みました。 気象庁では「標本木」と呼ばれる観測対象の木を定めていて、5 - 6 輪以上の花が咲いた状態を開花発表の目安としています。
昨日昼過ぎの観測時には 2 輪程度の花が開いていたものの発表は見送りとなり、その後今朝までに他のつぼみも開花したものとみられます。 今日の靖国神社は朝から冷たい雨が降っていて、東京都心の 13 時 40 分の気温は 2.6 ℃ しかありませんでした。
今週末からは寒の戻りがあるものの、来週後半には再び暖かくなるため順調に開花が進んで、3 月下旬には見頃を迎える所が多くなります。 靖国神社など東京都心周辺では、来週後半からは見頃となるところが多くなる予想です。 (ウェザーニュース = 3-14-20)
東京ディズニーリゾートが休園へ 3月15日まで
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、東京ディズニーランドとディズニーシーを 29 日から 3 月 15 日まで臨時休園する、と運営会社のオリエンタルランドが 28 日に発表した。 併設の商業施設イクスピアリも休む一方で、ホテルは営業を続ける。 3 月 16 日以降の対応は今後検討する。 チケットを既に購入している人に対しては返金したり有効期限を延長したりする。 詳細はホームページで案内している。 政府がスポーツや文化イベントを 2 週間自粛するよう要請したことに対応する。 (asahi = 2-28-20)
宮下パーク、6 月 18 日開業、渋谷のファッション・グルメ体現 90 店
三井不動産は 2 月 27 日、公園・商業施設・ホテルの複合施設「MIYASHITA PARK」を 6 月 18 日開業すると発表した。 開発コンセプトは、「あたらしい刺激や話題」と「快適さや居心地のよさ」の異なる 2 つの要素がボーダレスに混ざり合い、訪れるたびに新しいヒト・モノ・体験・文化に出会える場所。 公園・商業施設・ホテルが一体となった新しい形のミクストユース型施設が、文化の発信・交流拠点を目指す。
<公園・商業施設・ホテルが一体に>

商業施設(名称未定)は、渋谷区立宮下公園や周辺エリアと親和性の高い、ラグジュアリーブランド、ストリートブランド、横丁、クラブ、シェアオフィスといった多様な価値観やカルチャー性の高い店舗構成とした。 日本初出店の 7 店舗、商業施設初出店の 32 店舗、計 90 店がそろう。 南街区1階は、日本の古きよき横丁文化をさらに発信する「渋谷横丁」。 2、3 階には公園のアクティビティと親和性の高いスポーツブランド、カルチャーブランドを配置した。
原宿エリアやキャットストリートと繋がる北街区 1、2 階には、多くの高感度なファッションブランドをそろえた。 個性豊かな全長約 330m の渋谷の新たな「ストリート」として、常に様々な情報を発信していく。
■ 渋谷のファッション・グルメ体現する 90 店登場
国内直営店最大となる「adidas Brand Center」、初心者からプロまで幅広い層に人気の老舗スケートボード専門店「instant skateboards」などのスポーツ・アウトドアブランド、ヨガ、トレーニングなど芝生広場を使ったワークアウトを提案する「GRIT NATION」、スポーツ好きが集まる高タンパク・低カロリー食レストランの「筋肉食堂」などが出店する。
また、南街区 3 階の「FOOD HALL」には、コカ・コーラボトラーズジャパンが新しい「コカ・コーラ」の魅力を発信する「VALUME」、「タコベル」、「パンダエクスプレス」といったテイクアウトしやすいカジュアルなファーストフード店舗が集結する。
公園内には「スターバックスコーヒー」も出店し、買物目的だけでなく、さまざまな来園者がより快適な時間を過ごせるような場を提供する。 南街区 1 階には、三井不動産の法人向け多拠点型シェアオフィス「ワークスタイリング」が入居し、「憩い」と「働く」の、オンとオフの新しい距離感を提案するという。
■ ラグジュアリー、食、ナイトエンタメまで展開
さらに、明治通りに面する北街区1階には、世界初となる「LOUIS VUITTON」のメンズフラッグシップストア、2 フロアでフルコレクションを展開する「GUCCI」、「BALENCIAGA」、「PRADA」などの世界を代表するブランドが路面店を登場させる。
カルチャーを代表するショップとして、渋谷エリアを拠点にダンススタジオを展開する「En STUDIO」、「MIYASHITA PARK」の BGM セレクションも行う「Face Records」、新しいアートプラットフォームの「Sai」、セレクト書籍やカメラをはじめとしたさまざまなワークショップを展開する「天狼院カフェ SHIBUYA」がオープンする。
渋谷駅側となる南街区2階エリアには、雑貨、ファッション、食、サービス、カフェ、お土産ショップなど、小さな店舗が多数集積したマーケットを展開。 オリジナルの「キットカット」を作れる日本初の体験型店舗の「キットカット ショコラトリー」、関東初上陸のステーショナリー専門店「HIGHTIDE STORE MIYASHITA PARK」、商業施設初出店となるアクセサリーショップ「gram contemporary」、ガラスのアクセサリーショップ「HARIO Lampwork Factory」、メンズヘアケアブランド「DENIS MADE IN TOKYO」などがそろう。
■ 日本初出店レストラン、人気カフェもオープン
北街区・南街区ともに、4 階の公園へのアクセス動線となる場所には、様々なカフェ・飲食店舗を配置した。 「渋谷の新しい待ち合わせ場所」がコンセプトの「パンとエスプレッソとまちあわせ」、ライフスタイルブランド MAISON KITSUNE が展開する「CAFE KITSUNE」、シドニーから日本へ初進出するライスバーガーショップ「GOJIMA」などテイクアウトフードやドリンクが充実した、様々なカフェ・飲食店舗を集積した。
イベントなどを通してたくさんの人々が集まる芝生ひろばへのアクセスに便利な北街区 3 階は、渋谷エリアで人気の「ミヤシタ 成ル」、「青山 シャンウェイ」、渋谷初の醸造所付きワインダイニング「渋谷ワイナリー」、日本初出店となるサンセバスチャンの人気店「GRAN SOL TOKYO」などがオープンする。
インバウンド観光客や渋谷の来街者に、夜の滞在も楽しめるナイトエンターテインメントコンテンツも充実。 ホテルの直下に位置する北街区 1、2、3 階では、cafe & music bar・art gallery・club が一体となったカルチャーハブステーション「or」、南街区 1 階には、全長約 100m の空間に多彩な飲食店やスナックなど 19 店舗が並び、様々なコラボ企画やイベントを行う「渋谷横丁」を構えた。 (流通ニュース = 2-27-20)