「災害弱者」どう守る? 「江東 5 区」大規模水害時 人口の 9 割避難
都東部の 5 区(墨田、江東、足立、葛飾、江戸川)でつくる「江東 5 区広域避難推進協議会」が 22 日に公表した大規模水害時の避難計画では、人口の 9 割以上の 250 万人の域外への広域避難を打ち出した。 避難場所の確保は難題で、さらに 2 週間以上浸水する地域にとり残されるかもしれない高齢者ら「災害弱者」を守る課題も。 協議会は、災害時に地域住民同士で助け合う「共助」の必要性を訴える。
「親戚や知人ら行き先を住民自らが確保してもらうことで 250 万人の域外避難が可能になる。 過去の災害レベルをはるかに超えた災害では、行政で対処しきれないことを理解してもらいたい。」 協議会のアドバイザーを務める東京大学大学院の片田敏孝特任教授は協議会後の会見で強調した。
計画では、荒川流域で 3 日間の積算流域平均雨量がおおむね 500 ミリを超える恐れがある場合などには、住民が隣県を含む域外に自主的に避難してもらうことを明記した。 250 万人の住むエリアの水没が想定されるのに、公的な避難先の確保が見込めないためだ。 避難先がない場合の緊急の対策として、建物上階に移動する「垂直避難」も記した。 ただ、浸水が長引けば、避難者の居場所の把握が難しく、救助が遅れる恐れもある。
7 月の西日本豪雨では広島、岡山を中心に被害は広域にわたり、230 人近くの犠牲者を出した。 多くは独居の高齢者で避難を促されても自宅にとどまり続けた人もいた。 片田氏は「行動が困難な人たちを域外に全員逃すのは無理だろう」と指摘し、「域内にとどまらざるをえない場合の対処を進めたい」と語った。
協議会では今後、計画の課題を洗い出しながら、域内の住民に避難計画の周知を図っていく。 座長を務める江戸川区の多田正見区長は、「計画が有効に生かされるには、住民が計画をいかに理解し、行動に移せるかにかかっている」と述べ、行政主導ではなく、災害に対する住民の意識改革を求めた。 (神野光伸、加藤健太、東京新聞 = 8-23-18)
大塚家具、3 年連続赤字へ 黒字予想一転、大型店不振
大塚家具は 7 日夜、2018 年 12 月期の業績予想を下方修正し、最終的なもうけを示す純損益が 34 億円の赤字(前年は 72 億円の赤字)になりそうだと発表した。 2 月時点の予想(13 億円の黒字)を 48 億円下回り、一転して 3 年連続の赤字に陥る見通しとなった。 大塚久美子社長は 17 年 12 月期決算を発表した 2 月の記者会見で「法人販売とインターネット通販で攻勢をかけ、18 年度は黒字化させる」と収益改善に向けた決意を示したが、稼ぐ力が回復していないことが鮮明になった。 久美子氏の経営責任が問われるのは必至だ。
18 年 12 月期の売上高は従来予想を 80 億円下回る 376 億円(前年は 410 億円)、2 億円の黒字を見込んでいた営業損益も一転して 51 億円の赤字へと大幅に下方修正した。 営業赤字幅はほぼ前年並みの水準にとどまる見通しだ。 10 年前の評価のままだったすべての在庫を評価し直し、18 年 4 - 6 月期に 10 億円の評価損を計上することが響く。 1 株当たり 10 円を予定していた 18 年 12 月期末の配当は「事業の抜本的な立て直しを急務として、現在新たな計画を策定中」であることを理由に、未定とした。
店舗売上高は 7 月まで 12 カ月間前年割れが続く。 とくに新築まとめ買いの需要への依存度が高い大型店の不振が目立ち、こうした店の入店客数は前年同期比 2 ケタのマイナスになっているという。 低価格路線を進めるニトリなどとの競争激化に加え、「お家騒動」によるブランドイメージ悪化の影響も尾を引いている。 大塚家具は 3 日、18 年 12 月期の業績予想を下方修正する見通しだと発表していた。 10 日に予定していた 18 年 6 月中間決算の発表は 14 日に延期している。 (牛尾梓、asahi = 8-7-18)
◇ ◇ ◇
大塚家具、身売りへ 提携先の TKP 軸に最終調整
経営不振が続く大塚家具が自力での再建が困難な状況に陥り、身売り交渉を進めていることがわかった。 昨年 11 月に資本・業務提携した第 3 位株主の貸し会議室大手、ティーケーピー (TKP) が増資を引き受け、経営権を握る方向で最終調整に入った。 今月中旬までに買い手企業を決める方針だ。 取引銀行は家電量販大手ヨドバシカメラによる子会社化を提案しており、交渉の行方には流動的な面も残る。
大塚家具は 6 月以降、家電量販店や百貨店など複数の流通大手のほか、企業再生ファンドなどに支援を打診してきた。 その中から、大塚家具に 6% 強を出資する TKP が第三者割当増資により過半の株式を取得する案が有力となった。 中国の高級家具メーカーからの出資受け入れも一時、検討されたという。
TKP は、売り場の縮小によって生じた大塚家具の店舗の空きスペースを借りて、会議室やイベント会場に変えるなどの提携関係にある。 会議室などに置く家具を自社で製造・販売する事業も手がけており、大塚家具を傘下に収めれば相乗効果が発揮できるとみて買収に名乗りを上げた。 (牛尾梓、asahi = 8-4-18)
成田空港の旅客数、初の 2,000 万人超え 18 年上期、訪日客 868 万人
成田国際空港会社 (NAA) が 7 月 26 日に発表した 2018 年上期(1 - 6 月)の運用状況速報値によると、旅客数は前年同期比 4% 増の 2,061 万 4,967 人で、上期としては初めて 2,000 万人を突破し、2014 年以来 5 期連続で過去最高を記録した。 国際線と国内線を合わせた総発着回数は 1% 増の 12 万 4,931 回で、3 期連続で前年を上回り、過去最高を更新した。 貨物量は 3% 増の 111 万 8,881 トン、給油量は 1% 減の 220 万 3,883 キロリットルだった。
旅客数は国際線が 6% 増の 1,710 万 8,818 人で、このうち日本人は 2% 増の 655 万 1,681 人、外国人が 13% 増の 868 万 7,073 人、通過客が 10% 減の 187 万 64 人となった。 また、国内線の旅客数は 5% 減の 350 万 6,149 人となった。 外国人旅客数は、中国や韓国など、おもにアジア圏からの訪日需要が増加。 5 期連続で最高値を更新し、800 万人を初めて突破した。 発着回数は国際線全体では 3% 増の 9 万 9,630 回。 このうち国際旅客便は 3% 増の 8 万 6,160 回、国際貨物便は 4% 増の 1 万 2,150 回だった。 一方、国内線全体は 5% 減の 2 万 5,301 回だった。
同時に発表した、2018 年 6 月の運用状況速報値によると、国際線と国内線を合わせた総発着回数は前年同月比 1% 増の 2 万 688 回で、3 年 3 カ月連続で前年を上回った。 総旅客数は 7% 増の 344 万 7,039 人で、5 カ月連続で前年を上回り、それぞれ 6 月の過去最高を記録した。 貨物量は 6% 減の 17 万 8,607 トン。 給油量は 3% 減の 35 万 8,157 キロリットルだった。
発着回数は、国際線全体では前年同月比 3% 増の 1 万 6,606 回で、3 年 1 カ月連続で前年を上回った。 このうち国際旅客便は 4% 増の 1 万 4,497 回で、1 年 4 カ月連続で前年を上回った。 国際貨物便は 9% 減の 1,896 回で、1 年 3 カ月ぶりに前年を下回った。 一方、国内線全体は 6% 減の 4,082 回で、6 カ月連続で前年を下回った。
旅客数は、国際線が 10% 増の 289 万 4,379 人で、このうち日本人は 3% 増の 104 万 5,518 人、外国人が 21% 増の 146 万 5,661 人、通過客が 3% 減の 38 万 3,200 人となった。 また、国内線の旅客数は 6% 減の 55 万 2,66 0人となった。 外国人旅客は、5 年 5 カ月連続で前年を上回り、6 月の過去最高を記録。 国内線旅客は 6 カ月連続で前年を下回った。 (Yusuke Kohase、AviationWire = 7-27-18)
◇ ◇ ◇
成田空港に定期便、100 社到達 フィジーへ直行便復活
成田空港(千葉県)に 3 日、フィジーの航空会社「フィジー・エアウェイズ」が就航した。 成田空港に定期便を乗り入れる航空会社は 100 社に到達。 開港した 40 年前の 3 倍で、近年は格安航空会社 (LCC) の新規就航も相次ぐ。 フィジー・エアウェイズは 9 年ぶりの再就航で週 3 日、直行便を運航する。 初日の 3 日夜には、成田空港で記念セレモニーがあり、関係者が就航を祝った。
成田国際空港会社 (NAA) の荒川武・取締役営業部門長は「フィジーは美しい海とサンゴ礁に囲まれた、世界有数のリゾート地。 直行便の復活を心待ちにしていたので、うれしい。」と歓迎した。 成田空港に定期便を乗り入れる航空会社は 1978 年 5 月の開港時、日本航空やフランス国営航空など 34 社だった。 次第に増え、90 年には 50 社を超えた。
増加する大きな契機となったのは 2002 年、2 本目の滑走路の運用開始だ。 年間の発着容量は 13 万 5 千回から 20 万回に拡大し、モンゴルやウズベキスタンなどからの新規乗り入れが実現した。 さらに追い風となっているのが LCC だ。 08 年に海外、12 年に国内の LCC が就航。 現在、18 社に増えている。 NAA は 13 年にエアライン事業部を設け、営業も積極的に展開してきた。
ただ、中国や東南アジアの都市への就航については、多くの拡大余地があるという。 アジア方面を結ぶ便数は韓国・仁川空港の 4 割にとどまる。 NAA の担当者は「成長しているアジアの航空需要を取り込むことが課題だ」と指摘する。 成田空港は現在、海外 118 都市、国内 19 都市を結ぶ。 NAA は今年度中に海外 130 都市以上、国内 20 都市以上と結ぶことを目標に掲げている。 (黒川和久、asahi = 7-4-18)
LCC 台頭・ハブ拠点競争 … 成田空港、40 年目の転換点
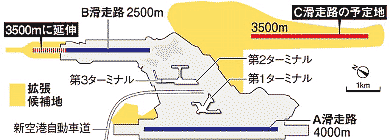
成田空港が 20 日、開港 40 年を迎えた。 激しい反対闘争を経て開港した「日本の玄関」。 羽田空港の国際化、格安航空会社 (LCC) の台頭、関西空港の躍進、アジアのライバル空港とのハブ(拠点)競争 - -。 時代の変化に、どう対応していくのか。
5 月の大型連休。 成田空港の LCC 専用の第 3 ターミナルは、スーツケースを持つ人でごった返した。 家族 4 人で韓国へ向かうという千葉県柏市のバレエ講師池谷玲子さん (36) は「LCC は新幹線に乗るような感覚。 飛行機代を抑えられ、ホテルや食事にお金をかけられる。」と話した。 成田空港に海外の LCC が初めて就航したのは 2008 年(国内の LCC は 12 年)。 現在は国内外 17 社が乗り入れ、運航便数は全旅客便の 3 割を超える。 空港を運営する成田国際空港会社 (NAA) は今年 4 月、第 3 ターミナルの増築を発表。 4 年後に完成予定で、現在の 2 倍となる年間 1,500 万人の LCC 利用客の受け入れが可能になる。
1978 年 5 月に開港し、翌年の旅客数は年間 895 万人だった。 02 年に 3 千万人を突破。 02 年にできた 2 本目の滑走路は 09 年に延伸され、発着容量が拡大。 米同時多発テロや東日本大震災の影響で旅客は一時落ち込んだが、17 年には初めて 4 千万人を超えた。 そして 40 年となる今年、成田空港は大きな転換点を迎えた。 3 本目の滑走路となる C 滑走路新設などの機能強化策について、地元の 9 市町や千葉県が 3 月に合意したのだ。 (黒川和久 石山英明 北見英城、伊藤嘉孝、asahi = 5-20-18)
日本橋 首都高地下化 3,200 億円 運営会社 2,400 億円
国の重要文化財「日本橋(東京都中央区)」の上空を覆う首都高速道路の地下化計画で、国土交通省や都、首都高の運営会社などは 18 日、総事業費を 3,200 億円とし、このうち 2,400 億円を首都高会社が負担するなどとした費用分担案で大筋合意した。 2020 年東京五輪・パラリンピック後に着工し、完成まで 10 - 20 年かかる見通し。
国交省や都によると、都は 320 億円、中央区は 80 億円を負担。 残る 400 億円は、日本橋地区の再開発を計画する民間事業者が担う。 工事区間は 1.8 キロで、地下トンネル部分は江戸橋ジャンクション (JCT) 付近から JR 山手線付近までの 1.2 キロ。 首都高会社は 2,400 億円のうち、老朽化した道路の更新費から 1 千億円、国や都が拠出した出資金の返還先送りなどで 1 千億円を確保する。 事業費は当初、4 千億 - 5 千億円と見込まれたが、既存の地下道路の活用などで圧縮した。
日本橋を覆う部分の首都高は 1963 年に完成。 地元では景観改善のため高架の撤去を求める声が強く、国交省と都は昨年 7 月、地下化の検討で合意した。 小池百合子知事は「景観確保の一つの象徴になる」と歓迎。 中央区の矢田美英区長は「具体化すべく積極的に取り組んでいく」とコメントした。 (東京新聞 = 7-19-8)
◇ ◇ ◇
日本橋の上の首都高が地下へ 1.2 キロのルート案決定

国指定重要文化財の日本橋(東京都中央区)の上を走る首都高速道路の地下移設について、国土交通省などの検討会は 22 日、神田橋ジャンクション (JCT) - 江戸橋 JCT 間の一部の約 1.2 キロメートルを地下化するルート案を決めた。 都市計画法に基づく手続きを経れば正式決定となる。 現在、神田橋 JCT - 江戸橋 JCT 間は、日本橋や日本橋川をふさぐように高架がかかっている。 ルート案ではこの高架を撤去。 かわりに新たにトンネルを約 700 メートル掘り、バイパスとして付近に元々ある八重洲線の地下部分約 500 メートルとつなげる。
もっとも、地下には上下水道、電力、通信、ガスなどのインフラ施設が網の目のように張り巡らされ、半蔵門線、銀座線、浅草線といった地下鉄も走る。 最も深くて地表から二十数メートルを、障害物を避けながら川沿いを掘り進める。 難工事になり、事業費は数千億円に達するとみられる。 周辺では民間事業者による大規模再開発が目白押し。 首都高の地下化で景観がよくなり、レジャーや移動などで日本橋川を活用できるようになれば事業者にメリットは大きい。
検討会では、夏までに事業費を見積もり、民間事業者や東京都とどう費用を分担するか検討する。 工事開始は 2020 年の東京五輪以降で、完成まで 20 年前後かかる見込みだ。 初代日本橋は江戸幕府が 1603 年につくった。 1964 年の東京五輪に向けて首都高を建設する際、日本橋の上に高架化。 その後、地元住民らが地下化を要望した。 国交省は昨年 11 月、民間の再開発との相乗効果が見込まれるなどとして、地下化の検討を始めた。 (石山英明、asahi = 8-22-18)
前 報 (7-21-17)
全都道府県の木材使用、新国立競技場が 4 割完成

2020 年東京五輪・パラリンピックのメイン会場となる新国立競技場(東京都新宿区)の工事現場が 18 日、報道陣に公開された。 6 万 8,000 人を収容する観客席では屋根の設置作業が始まり、19 年 11 月末の完成予定に向けて着々と工事が進んでいる。
日本スポーツ振興センター (JSC) によると、工事は全工程の約 4 割まで達し、順調に進んでいるという。 観客席部分はほぼ完成し、屋根の土台となる鉄骨を組む作業も終えた。 新国立は、「国産木材を利用した世界に誇れるナショナルスタジアム」を基本理念に掲げており、全都道府県の木材が使われる。 (yomiuri = 7-18-18)
前 報 (12-22-15)
オークラ東京本館、1 泊平均 7 万円 19 年 9 月開業
最上位ブランド「都内最高水準」
ホテルオークラは 25 日、建て替え工事中の旗艦施設「ホテルオークラ東京」の本館(東京・港)の概要を発表した。 2019 年春としていた開業時期は同年 9 月上旬となる。 最上位ブランドの客室は、1 泊 1 室の平均宿泊料が従来比 3.5 倍の 7 万円と「都内最高水準(荻田敏宏社長)」を見込む。 外資の進出も続くなか、20 年東京五輪などで来日する富裕層を取り込み、知名度を高める。
施設名は「The Okura Tokyo (ジ・オークラ・トウキョウ、日本語名 = オークラ東京)」に決めた。 オフィスも併設する高層棟「オークラ プレステージタワー(高さ約 188 メートル、地上 41 階建て)」と、ホテル施設に特化した中層棟の「オークラ ヘリテージウイング(75 メートル、17 階建て)」の 2 棟を建設する。 庭園も配置する。 客室は高層棟の 28 - 40 階に 368 室(標準で 50 平方メートル)、中層棟の 6 - 17 階に 140 室(同 60 平方メートル)と計 508 室を備える。 旧本館時代が約 400 室だったので、3 割ほど増える。 最も狭い客室でも約 50 平方メートルと従来比で 1.7 倍となる。
中層棟の客室は新設する最上位ブランド「オークラ ヘリテージ」と位置づけ、間口が 8 メートル以上と一般的な高級ホテルより広げる。 客室単価は平均 7 万円と都内トップクラスを想定する。 高層棟は既存の「オークラ プレステージ」ブランドで、1 室 4 万 5 千 - 5 万円を見込む。 高層棟でリビングなどを併設するスイートルームは室内階段で行き来する 2 層タイプも用意する。 宴会場や婚礼施設、フィットネス・スパ施設も高層棟に置く。
1962 年に開業した旧本館は老朽化などに伴い、15 年 8 月末に惜しまれながら閉館した。 格式ある旧本館ロビーの装飾品はできるだけ新本館に移す。 旧本館の象徴の照明具「オークラ・ランターン」は高層棟のメインロビーで使う。 ホテルオークラ東京は帝国ホテル、ホテルニューオータニとともに「ご三家」と呼ばれる老舗名門ホテル。 約 1,100 億円を投じるオークラの本館建て替えは「第 2 の創業(ホテルオークラ東京の池田正己社長)」と位置づける社運をかけたプロジェクトだ。
ただ都心では国内勢だけでなく外資のホテルも増え、集客競争が激しくなっている。 森トラストはマリオット・インターナショナルの最高級グレード「エディション」を誘致し、20 年に虎ノ門と銀座で開く。 イタリアのブルガリホテルも 22 年に八重洲に進出する。 世界的な顧客基盤や知名度、単価などで外資の後じんを拝する日系ホテルに勝ち目はあるのか。 好例が JR 東京駅近くのパレスホテル東京(東京・千代田)だ。 09 年に旧施設を閉鎖して建て替え、12 年に再開業した。
単価は 17 年度に約 5 万 2 千円と旧施設時代の 2.2 倍になった。 稼働率も上がった。 「フォーブス・トラベルガイド」のホテル部門で、日系ホテル初の「5 つ星」の格付けを 16 年に獲得、3 年連続で維持している。 客室を 389 室から 290 室に減らして 1 室の面積を 45 平方メートル以上に広げ、サービスの質も高めて単価上昇につなげた。
オークラはご三家の中でも海外施設が多く、荻田氏は「現地トップクラスのブランド力の施設が多く、認知度は高まっている」と海外からの集客に自信を示す。 オークラの旧本館は 1964 年の東京五輪の際も海外客を迎えた。 今回も日本のホテルのもてなしを知ってもらう絶好の機会だ。 オークラは「日本の季節感を感じられる料理や装飾で外資にない特徴を出せる(池田氏)」とはじく。 一流ホテルが設備やサービスを磨くことは東京の都市としての競争力を高めることにもつながりそうだ。 (大林広樹、nikkei = 6-25-18)
前 報 (8-26-15)
ディズニーシー、3 割拡張し新エリア アナ雪の世界再現
東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは 14 日、東京ディズニーシー (TDS) を約 3 3割拡張し、映画「アナと雪の女王」など三つの映画の世界を再現した新たなエリアをつくると発表した。 2022 年度の開業をめざす。 投資額は約 2,500 億円で、追加投資としては過去最高という。 訪日外国人ら新たなファンを呼び込むと同時に、混雑を和らげる狙いだ。 現在、TDS は 49 ヘクタール。隣接する平面駐車場の敷地 14 ヘクタールを新エリアにする。
新エリアのテーマは「魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界」。 「アナ雪」のほか、「塔の上のラプンツェル」、「ピーター・パン」の世界を再現する。 それぞれに新アトラクションをつくり、475 室のホテルも建てる。 東京ディズニーリゾートの年間入園者数は、14 年度に過去最高の 3,137 万人に達した後、3 千万人超を維持している。 人気のアトラクションの待ち時間は 2 時間を超えることもあり、混雑解消が課題になっていた。 記者会見した加賀見俊夫会長は「インパクトのある投資で、パークの魅力を高めていく」と話した。 (筒井竜平、asahi = 6-14-18)
◇ ◇ ◇
東京ディズニーリゾート、パーク拡張へ 混雑緩和狙う
東京ディズニーリゾート(千葉県浦安市)を運営するオリエンタルランドは 15 日、開園 35 周年を迎え、パークを拡張する方針を正式に表明した。 時期や規模など、具体的な内容は未定という。 同社の加賀見俊夫会長兼最高経営責任者 (CEO) が「パークの拡張について検討をしている」とコメントした。 隣接する平面駐車場を立体駐車場にして、空いた敷地を新たなエリアとして活用することを検討している。 立体駐車場の完成は 2019 年度の予定で、拡張はそれ以降になる。
拡張の狙いは、訪日外国人を含む新たなファンの獲得と混雑の解消だ。 17 年度の入園者数は 3,010 万人。5 年連続で年間 3 千万人を超えており、混雑緩和が課題となっている。 19 年には東京ディズニーシーに新アトラクション「ソアリン(仮称)」が、20 年には東京ディズニーランドに「美女と野獣エリア(同)」を中心とした複数の施設ができる。 その後も両パークの開発を進めるという。 (asahi = 4-15-18)
◇ ◇ ◇
TDL、15 日に開園 35 周年 … 混雑解消が課題
キャラクターのアトラクションやグッズが幅広い人気を集め、東京ディズニーシー (TDS) と合わせた累計入場者は 7 億 2,000 万人。 近年は外国人客も増えており、混雑解消が課題だ。
TDL の開園は 1983 年 4 月。翌年度、年間入場者が 1,000 万人を突破し、その後もアトラクションやショーを次々と打ち出した。 TDS との合計で 2014 年度、過去最高の 3,137 万人となった。ここ数年は中国や東南アジアからの来園者が急増している。 一方、休日は人気アトラクションの待ち時間が 2 - 3 時間に達するなど混雑が激化。 2000 年に導入した「ファストパス(時間指定整理券)」に加え、ネットで待ち時間がわかるサービスも始めたが、解消にはつながっていない。 (yomiuri = 4-14-18)
◇ ◇ ◇
東京ディズニーリゾート、3 割拡張へ 2020 年代前半
テーマパーク運営のオリエンタルランドが、東京ディズニーリゾート(千葉県浦安市、TDR)を拡張する計画があることがわかった。 約 100 ヘクタールの敷地を、2020 年代前半に約 3 割広げる計画。 投資額は数千億円にのぼるとみられる。競争が激しいテーマパーク業界で、日本人に加えて訪日外国人を引きつける狙いがある。 現在、1983 年開業の東京ディズニーランドと、01 年に開業した東京ディズニーシーを合わせて約 100 ヘクタール。 隣接する平面駐車場を立体駐車場にするなどして、空いた敷地をテーマパークの新たなエリアとして活用することを検討している。
19 年度には立体駐車場が建設される予定で、新エリアはその後の着工になりそうだ。 全体の面積は現在の 1.3 倍ほどに広がるという。 現在、混雑が常態化しており、その解消も狙う。 TDR の 16 年度の入園者数は約 3 千万人で 2 年連続で減少。 一方で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市)は、16 年度(約 1,460 万人)までに 3 年連続で過去最高を更新している。 国内でのテーマパーク間の競争に勝ち抜き、今後も増えることが見込まれる訪日外国人の取り込みを狙う。 (asahi = 11-30-17)
新宿駅南口で「ルミネアグリマルシェ」 定期開催へ

JR 新宿駅ミライナタワー改札外(「NEWoMan」 2 階エントランス前)で 6 月 15 日より、「ルミネアグリマルシェ」が開催される。 ルミネ(渋谷区)が「食のライフバリュー」を提案する「ルミネアグリプロジェクト」活動の一環として 5 月に初開催。 この反響を受け今後の定期開催が決定したという。 6 月はサクランボやブロッコリーなどの旬の果物や野菜のほか、ピクルスやドライフルーツ、オリーブオイルなどの加工品が並ぶ。
同プロジェクトのパートナーで、出店も行うジャパン・アグリゲート(品川区)の今井さんは「産地直送でダイレクトに仕入れるのが強み。 鮮度が高くおいしい野菜や果物をたくさんの方に味わってもらいたい。」と話す。 東京野菜普及協会(大田区)は人気の「ココトマト」をはじめ、ズッキーニや葉付き大根などをそろえる。 五六八市場(秋田県)の「お薦め」は「みず」という山菜。 シャキッとした歯触りとトロッとする食感が味わえる。 その他、原生林(長野県)の一株なめこや、甲斐国物語(山梨県)の「甲斐国レーズンサンド」などを生産者が紹介、解説する。
ドライフルーツを出店するフード・インサイト(北区)の藤巻さんは「ドライフルーツが他とは全然違うと言われる。 マルシェとしては珍しいほどアクセスが良いため通いやすい。」と話す。 ルミネの担当、東島さんは「このプロジェクトは、首都圏で暮らす方々に日本のこだわりの野菜や果物を提供することで食に対する価値観を醸成していくのが目標。 2 回目の開催を終え、リピーターのお客さまが増えてきている。 今後も継続的に開催したい。」と意欲を見せる。
「売られている野菜や果物の背景のストーリーを聞くことで興味が湧いたり、愛着が生まれたりするなど、食を見直すきっかけとなれば。 今後も、生産者とのコミュニケーションを通じてお客さまへ食のライフバリューを伝えていきたい。」とも。 開催時間は、平日 = 13 時 - 20 時、土曜・日曜 = 11 時 - 18 時。 今月 24 日まで。 次回開催は 7 月 13 日 - 22 日。 (中村真司、新宿経済新聞 = 6-13-18)

シャンシャン、12 日に 1 歳 すくすく 28 キロに成長
東京・上野動物園のメスのジャイアントパンダ、シャンシャン(香香)が、12 日で 1 歳になる。 上野で産声をあげ、順調に育ったのは 1988 年のユウユウ(悠悠)以来、30 年ぶりだ。 その愛らしい姿に人だかりは絶えず、地元・上野の街はなおも沸いている。 誕生日を前にした 11 日朝、報道陣に公開されたシャンシャンはこの日初めて設置されたハンモックに興味津々の様子で、体を沈めて揺らすなど、活発に遊んでいた。
ふだんから木に登ったり水浴びしたりと、自由気ままに動き回るシャンシャン。木の上で寝ていることもあり、「外敵に襲われないための本能が表れてきた」と副園長の渡部浩文さんは話す。 飼育員や多くのファンに見守られながら、シャンシャンはすくすくと育ってきた。 生後 2 日目で 147 グラムだった体重は、今月 5 日で 28.2 キロに。 母親シンシン(真真)の 4 分の 1 ほどになった。 主な栄養源は母乳だが、先月は小さく切ったリンゴを歯で削るように食べ、タケノコもかじるなど、1 歳半 - 2 歳で迎える親離れに向けて少しずつ離乳が進んでいる。 (西村奈緒美、asahi = 6-11-18)
初 報 (12-20-17)
バスない港区の高級住宅街、相乗りタクシー実験
東京都港区は区内の白金と白金台で、高齢者などを対象とした「相乗りタクシー」のモニター実験を 6 月から始める。 両地域は都内屈指の高級住宅街として知られるが、幅の狭い道路が多いために区のコミュニティーバスのルートから外れ、高齢化率も区全体の平均を上回っていることから、実験エリアに選ばれた。 3 か月間の実験で利用状況を分析し、本格運用を検討する。
区は今回の実験で、両地域の 70 歳以上の住民や妊婦、障害者などの 4 人 1 組計 100 組の参加者を区のホームページなどで募集している。 参加者 1 組につき、23 区などの初乗り運賃 410 円(1.052 キロ・メートル以内)分の利用券 30 枚を配布。 参加者は 6 月 1 日から 3 か月間、買い物や通院などの際、券を使って最低 2 人以上でタクシーを利用する。 地域外に出てもよいが、初乗り運賃からの超過分は各自が分担して支払う。 スマートフォンを振るだけで運転手に位置情報を発信し、呼び寄せる無料アプリも活用する。 区はこうした実験で集めた利用区間や利用頻度、参加者の声などを分析し、導入の可否を決める。
港区は、区施設や商業施設、病院などを回るコミュニティーバスを赤坂や麻布、青山などで計 8 ルート運行している。 運賃は 1 回 100 円。 しかし、白金と白金台は古くから住宅などが密集し、区内の他地域に比べて道路の再開発が進んでいない。 そのため、車同士のすれ違いが困難な狭い道が目立ち、高台に位置して坂道も多いことから、コミュニティーバスのルートからは外れていた。
両地域は高齢者も多い。 4 月 1 日現在の 65 歳以上の人口割合は、白金が 18.3%、白金台が 19.9% で、区全体の割合 (17.1%) を上回る。 白金地域の無職女性 (73) は「都などのバスが走る幹線道路まで 10 分かけて歩いており、荷物が多いと大変。 安くて気軽に使える交通手段を整備してほしい。」と話す。 両地域は約 1 キロ四方のエリアにあり、区は両地域内で 4 人で相乗りタクシーを使って移動すると、片道の利用料金がコミュニティーバスとほぼ同額の 100 円程度になると想定している。 区地域交通課の担当者は「コミュニティーバスに代わる地域の足として期待できる。 多くの人に実験に参加してほしい。」とする。 (yomiuri = 4-24-18)
JR 京葉線、幕張新都心に新駅 イオンモールが半額負担
千葉市美浜区の幕張新都心に、JR 京葉線の新駅が 2024 年度にも開業する見通しとなった。 千葉県、千葉市、地元企業のイオンモールでつくる協議会と JR 東日本が 20 日、新駅設置の基本協定を結んだと発表した。
新駅の場所は、新習志野 - 海浜幕張間 3.4 キロのほぼ中間が想定されている。 JR 東は今年度中に概略設計に着手し、駅舎の規格や工法を決める予定。 駅舎の建設費約 130 億円の半分をイオンモールが負担し、残りを県と千葉市、JR 東が同額ずつ分担する。 幕張新都心では大規模マンション群やオフィスビルなどの開発が進み、県は 1991 年、JR 東に新駅設置を要請していた。 13 年に大型商業施設「イオンモール幕張新都心」が開業し、20 年東京五輪・パラリンピックでは幕張メッセでも競技が実施されることが決まっている。 (熊井洋美、asahi = 4-20-18)
JR 八王子駅前にオーパ出店へ 食品重視、テーマは自然
JR 八王子駅南口(東京都八王子市)に建設中の複合ビルに今秋、商業施設「(仮称)八王子オーパ」が出店することになった。 駅とペデストリアンデッキで直結し、6 階まである東側部分に食品や衣料品など約 40 店舗が入る予定。 運営会社の担当者は「地元の人にとって居心地のいい空間にしたい」と話している。施設を運営するイオン系のショッピングセンター開発運営会社「OPA」が発表した。 同社によると、売り場面積は約 6,200 平方メートルで、都市に住みながら自然を楽しむことなどがコンセプト。 1、2 階に生鮮品を含む食品専門店やカフェなどの飲食店、3、4 階にアパレルや雑貨店、5、6 階に美容院やフィットネス施設などが入るという。 ビルは地上 26 階建て。 JR 貨物と住友不動産が共同で開発し、今秋、完成予定だ。 西側の 1 - 26 階には計約 200 戸の分譲マンションも入るという。 オーパは東北から九州に約 10 店舗あり、多摩地域では京王線聖蹟桜ケ丘駅(多摩市)の前にも店を構えている。 (川見能人、asahi = 4-10-18)
新宿駅の東西、行き来しやすくなる? 40 年代へ再整備
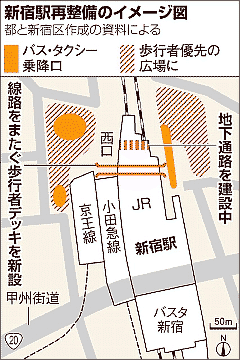
乗降客数が世界一とされる新宿駅やその周辺の再整備方針を東京都と新宿区がまとめた。 2040 年代までの実現を目指すもので、駅の東西をつなぐ歩行者通路の新設や乗り換え通路の拡張などを盛り込んだ。 都や区、鉄道会社などが今後、費用や工期、整備手法を本格的に検討する。 都と区が、国土交通省や鉄道会社の担当者らも加わった検討委員会の案を受けて、先月に「新宿の拠点再整備方針」として決めた。 40 年代の新宿駅の将来像を「人々の多様な活動にあふれ、交流・連携・挑戦が生まれる場所」と位置づけ、周辺を「車中心から人中心のまち」に変えることを目標にしている。
具体的には南北方向に走る JR の線路をまたぎ、東口と西口を結ぶ歩行者専用デッキを新設する。 現状では不便な東西の行き来をしやすくするため、20 年の東京五輪・パラリンピック開催に向けて東西を結ぶ地下通路が建設中だが、さらにデッキも設置する考えだ。 また、駅ビル内も増改築を繰り返してきたため、乗り換え通路が狭く段差も多い。 このため、通路を拡充してバリアフリー化を図ったり、JR と小田急・京王各線のホームを結ぶ通路を新しくつくったりする。
駅構内だけでなく駅前も変え、歩行者優先の広場を目指す。 都によると、新宿駅の乗降客の大半が出発地 - 駅や駅 - 目的地の間を徒歩で動いているが、東口、西口とも駅前広場の面積の 5 割を車道が占め、歩道は 2 - 3 割という。 これを変え、多くの歩行者が行き交ってにぎわいを生む空間に作り替える考えだ。 さらに、1960 年代以降に建ち、老朽化した百貨店ビルの建て替えも視野に、大規模なオフィスやホテル、会議場などの機能も備えるとしている。
都によると、新宿駅は JR、小田急、京王、東京メトロ、都営地下鉄など 7 路線が乗り入れ、乗降客数は 1 日 350 万人。 国内最大級のバスターミナル「バスタ新宿」も隣接する。 路線の増加にあわせて駅や周辺商業施設の増築が続き、歩きづらい複雑な構造になった経緯がある。 今後は再整備方針をもとに行政と鉄道会社が協議し、都市計画の決定など必要な手続きを進める。 都都市整備局は「採算に見合う事業とみるかは各社の判断。 費用や工期などを含め、本格的に検討する。」と話す。 20 年度の一部事業着手を目指している。 (伊藤あずさ、岡雄一郎、asahi = 4-8-18)