国内生産の成功モデルとして "ショールーム" 化する島根富士通
2015 年度下期からは Windows 10 に最適化、IoT を活用した生産革新の模索も
島根県出雲市の島根富士通は、国内のノート PC 生産拠点としては国内最大規模を誇る。 その島根富士通が、国内生産拠点の成功モデルとして、業界内外から注目されている。
2014 年度に同工場を訪れた人は国内外を含め 4,000 人を超えたという。 「今年(2015 年) 7 月も、多い日には、4、5 組の訪問があった」と、島根富士通の宇佐美隆一社長は語る。 一方で、Windows 10 搭載 PC の生産開始に向けた準備も 8 月中には完了。 9 月以降、生産を開始する予定だという。 また、富士通が持つセンサー技術を活用した新たな生産革新の取り組みも開始し、これまでにない先進的な改革手法にも踏み込む。 島根富士通の宇佐美隆一社長に、同社の取り組みについて聞いた。
島根富士通は、出雲縁結び空港から車で約 20 分。 のどかな田園風景の中、植栽で「Fujitsu」と描かれた丘の高台に位置する。 山陰自動車道の斐川インターチェンジからもすぐの場所であり、物流にも適した場所だ。 同社は、1990 年に操業を開始。 当初は、FM TOWNS などのデスクトップ PC の生産も行なっていたが、1995 年にはノート PC の生産に特化。 2013 年には、PC の累計生産台数が 3,000 万台に達している。
2011 年には、島根富士通の所在地である斐川町が出雲市に編入したこともあり、「出雲モデル」として、国内生産であることを強調したマーケティングも開始している。 その島根富士通が、長年に渡って打ち出しているのが、「人と機械の強調生産」である。
同社・宇佐美隆一社長は、「モノづくりは人づくりが基本姿勢。 ロケットに例えれば、人がメインエンジンとなり、サブエンジンとして機械化やロボット化、IoT の活用などがある」とする。 品質マインド教育、専門教育、認定制度などを通じて人材育成を進める一方、機械化による安定品質の確保、ヒューマンエラー防止のための工夫などに力を注ぎ、「品質は工程で造り込む」という姿勢を打ち出している。
組み立て工程では、デジタルピッキング方式により、部品の間違えや取り忘れを防止。 異常発生時には定位置でコンベアが停止し、すぐに異常が確認できるようにしているほか、ネジ締め不良をなくすために、種類、和、傷、角度などを管理する仕組みを導入している。 角度を管理する治具は「すいちょくん」と呼ばれており、同社で考案したものだ。 さらに、自動ラベル貼り付け機により正確な位置にラベルを貼付。VST (ビジュアル・サウンドテスター)ではカメラとマイクを使い、画質やスピーカー音、ラベル位置やキーボード文字を自動で確認する。 こうした工程での工夫は随所で行なわれている。
同社の経営理念は、「人は仕事で成長し、社会に貢献する」としており、人を中心としたモノづくりを基本姿勢に置いていることが分かる。 社内では技能を高めるための教育を強化する一方、開発部門がある神奈川県川崎市の川崎工場と連携して、社内留学制度を実施。 開発に関する知識やノウハウを修得する一方で、製現場からの意見を開発現場に反映しやすい環境を構築。 これによって、製造品質を高めることにも繋がっている。 ここでも、開発拠点と製造拠点が、同じ日本国内にある強みが発揮されていると言えよう。
年間 4,000 人の来場を誇るショールーム?
ここにきて、島根富士通は、国内生産の成功モデルとして、国内外から注目を集めている。 昨今の円安基調の中で、国内生産への回帰を模索する製造企業が増加しているということも背景にあるが、かつての円高時代にも国内生産を維持した競争力の高さ、それに伴う生産革新の数々の実績、そして、富士通が展開するモノづくり支援サービス「ものづくり革新隊」のショールームとしての役割を担っている点も見逃せない。
「昨年(2014 年) 1 年間で、4,000 人を超える見学があった。 日本の製造業を始め、海外からの訪問も多い。 中には製造業以外の業界からの見学もある。 デジタル家電や IT の国内生産拠点が減少していること、そして、富士通が提案するモノづくりに関するツールやノウハウを活用している実践の場であることも、見学が多いことの背景にある。」と、島根富士通の宇佐美社長は語る。
富士通のものづくり革新隊とは、富士通が持つ長年のノウハウ、ツール、人材を結集し、モノづくりの全ての領域において、総合的に支援するサービスだ。 島根富士通では、富士通グループが提供している 3 次元データを用いた製品シミュレーション「VPS」や、作業現場をシミュレーションして効率的な生産ラインを構築する「GP4」などを採用。 デジタルピッキングシステムなどの生産設備による効率化の追求の実績などにも注目が集まる。
「黒物と言われる領域において、1 台ずつ異なる製品を製造できること、PC とタブレットの混流ラインを構築していること、そして、日本からの輸出を継続し続けていたことに対する関心も高い」という。 また、人材育成に関わる実績などについても質問が多く、「海外生産拠点をどうやって指導するか、あるいは、地域活性化にどう貢献するかといった点でも注目されている」という。 さらに、島根富士通では、双腕ロボットを始めとするロボットの制御技術でも工夫を凝らしており、まさに富士通グループにおける生産革新のショールーム的な役割を果たしていると言えよう。
なぜ国内生産を維持し続けたのか?
島根富士通が、国内生産を堅持できた背景には、いくつかの理由がある。 1 つは、日本のユーザーに対するメリットを追求し続けてきた点だ。 特に企業ユーザーにおいては、それぞれの要求に合わせた製品作りが求められており、柔軟にカスタマイズ対応をする必要がある。 富士通では営業部門が獲得した受注案件を、島根富士通でもすぐ対応できる体制を構築。 生産ラインの中で、1 台ずつ仕様が異なる PC を組み立てることができる。 また、ユーザー企業が個別に行ないたい設定情報やソフトウェアについても、生産ライン上で、セキュリティ環境を維持した格好でインストールすることを可能としている。
「1 台ずつ仕様が異なる製品でも生産できる体制を構築している点、そして、製造現場の要望を開発現場にフィードバックし、開発現場の意向に沿ったモノづくり体制を構築できるのは、国内生産ならではの強み。 品質の高い製品を、安定した形で生産し、短納期で供給できる。」という。
また、混流ラインを構築しており、現在、稼働しているラインの半分でノート PC とタブレットを混流させた生産が可能だ。 需要の変動に合わせて、生産品目を柔軟に変更できる点も島根富士通の特徴の 1 つとなる。 さらに、島根富士通では、デスクトップ PC を生産する富士通アイソテックと、事業継続における協力体制の構築にも取り組んでおり、実際に、東日本大震災が発生した際には、島根富士通でデスクトップ PC の生産を行なった経緯もある。 つまり、デスクトップ PC の生産も可能な拠点になっているというわけだ。
かつては、アジアの生産拠点とコスト競争力の差が関心を集めていたが、今では円安の影響や、アジアでの人件費の高騰などを背景に、コスト競争力の話題はほとんどでていない。 場合によっては、日本での生産の方がコストメリットが高い場合もある。 島根富士通は、かつての円高の時期や、アジアの豊富な労働力が脅威とされていた時期においても、品質や納期、柔軟なカスタマイズ対応といった付加価値によって、コストの差を埋め、メリットを追求し続けてきた。 これは、富士通グループ全体として目指したビジネススタイルであったとも言え、そこに国内生産を維持し続けることができた要因がある。
さらに、島根富士通自身の努力も見逃せない。 島根富士通では、基板実装工程を持っているが、これによって、開発部門と連携した最適な基板の製造を行ない、現在では、1 台の基板から、メインボードとサブボードを加えて、2 台分の基板を一度に生産することができる。 さらに検査工程などの自動化を促進。 柔軟性と効率化、品質強化といったことに繋げている。 これも富士通の PC 事業における競争力を高めるための下支えとなっている。
現在は、島根富士通で生産する PC やタブレット以外の基板の生産も行なっており、例えば、兵庫県の富士通周辺機で生産されているスマートフォンの実装基板の生産も島根富士通で行なっているという。 島根富士通では、トヨタ生産方式 (TPS) をベースとした「富士通生産方式 (FJPS)」を採用。 これにより、富士通の製品に最適化したモノづくり環境を構築しているが、島根富士通はその先進的取り組み事例の 1 つになると言っていい。
そのほか、島根富士通では富士通のノート PC の生産だけでなく、部品のリペア事業や、ものづくり受託サービスや富士通グループの製品管理、他社から受託した製品管理のヘルプサービスなどにも乗り出している。 こうしたことも島根富士通の競争力を発揮し、事業基盤を強固なものにすることに繋がっている。
Windows 10 に対応した生産体制の構築も
島根富士通では、2015 年度の取り組みの中で、これまでの人材教育の強化を進める一方、生産インフラの強化に取り組む姿勢を示す。 1 つは、ロボットなどの活用強化だ。 基板実装ラインにおける検査工程において、ロボットを活用した自動化を加速するほか、「PC 組み立て工程においても、機械化できるところは機械化したい」とする。
基板の検査工程においては、機械と目視による検査を行なうとともに、基板から実装部を分割する作業などを自動化しており、1 人が基板をセットすれば、検査と分割、トレーへのセットを自動で行なえる環境を構築している。 これを完全自動化する仕組みを既に構築しており、これを複数のラインに導入。 さらなる作業の効率化を図る考えだ。
また、梱包工程においても、ダンボールで成形する緩衝材を組み立て方式とし、ロボットでこれを行なう仕組みを採用し始めた。 これは緩衝材の改良と、独自に開発したロボットによって実現したもので、従来は組み上がった形で入庫していたために、嵩が増し、物流費用や在庫コストがかかっていたものを、降りたたんだ状態で物流、在庫ができるため、大幅なコスト削減に繋がったという。 こうした取り組み以外にも、今後は組み立てラインにおけるロボット導入を検討していくという。
2 つ目は、モノづくりそのものの向上だ。 例えば、基板生産はこれまではあらかじめ設定された生産計画に基づいた生産を行なってきたが、2015 年 4 月からは、PC の組み立てライン側の生産量に基づいて、そこからの指示で基板生産を行なう仕組みへと変更。 基板生産から組み立てまでを一気通貫で生産コントロールできるようになった。 これにより、基板の完成品在庫は半減したという。
実は、Windows 10 の生産が開始されると、OS のインストールにかかる時間が、Windows 8.1 に比べて、約 1.2 倍長くなるという。 つまり、従来の生産の仕組みのままだと少なくとも 2 割ほど、インストール作業を行なう棚を増やす必要がある。 こうした部分においても、場所を増やさずに効率的に作業が行なえる仕組みの構築に乗り出すという。 「Windows 10 を搭載した PC の生産に向けた新たなラインは、8 月下旬には構築する考えであり、Windows 10 の生産に最適化したものになる」とする。
3 つ目は、物流を巻き込んだサプライチェーン全体の見直しだ。 これまでの生産現場だけの改革に留まらず、物流と一体化したサプライチェーン全体の見直しによって、コスト削減に繋げていく考えだという。 これまでにもダイレクトシップの取り組みを開始するなど、物流現場との連携を図っていたが、こうした取り組みをさらに一歩進めることになる。 そして、最後に IoT を活用した生産現場の改革だ。 富士通では、さまざまなセンサー機器を独自に開発しているが、それらを社内活用して、作業者や部品などに取り付けて、生産現場におけるさまざまなデータを取得。 より効率的な作業環境の実現を目指す考えだ。
「これまでは作業者の様子をビデオで撮影して、そこから改善点を見つけ出すといった方法を採用していたが、センサーデータからは、それ以上にさまざまなデータを取得することができると予想される。 過去にはできなかった生産現場の改革が行なえるのではないと期待している。」という。 島根富士通では、下期からセンサー機器を活用した作業データの取得を開始する予定で、来年度以降の改善に結びつけることになりそうだ。 これも、富士通グループにおける生産現場のショールームとしての役割を果たすことに繋がるものだ。
タブレット生産の比率は 2 割に上昇
現在、島根富士通では、タブレットの生産比率が約 2 割を占めている。 「今後の流れを考えると、タブレットの比重はますます高まっていくだろう。 それに向けて柔軟に変更できる体制を構築することが必要になる。 さらに、カスタマイズにも対応できる体制の強化も進めたい。(島根富士通・宇佐美社長)」とする。
Windows XP のサポート終了に伴う特需がピークを迎えた 2014 年 4 月以降、PC の生産台数は市場全体で大きく減少しているが、そうした需要の変化に対しても、付加価値の高い製品づくりで、国内生産ならではの競争力を発揮しているのが島根富士通の特徴だと言えよう。 Windows 10 が登場しても、その需要動向が読みにくいという状況にあるのも事実。 そうした中で、いかに競争力を発揮し、国内生産を維持するのか。 これからも島根富士通の改革への挑戦が続くことになる。 (大河原克行、PC Watch = 8-12-15)
企業と政府がタッグを組む「地方創生」とは 中村ブレイス
いまや一大ムーブメントとなりつつある「地方創生」。 一体どんな施策で、企業はどのように取り組めばいいのでしょうか? 地方創生をけん引する平将明内閣府副大臣と、島根県の石見銀山の麓で義手・義足を製造し、若者たちが集まる会社・中村ブレイスの中村敏郎社長に、行政と民間それぞれの立場から見た地方創生について聞きました。
人口 400 人の過疎の町でベビーラッシュが起こる
- - まず、中村ブレイスの事業内容についてお教えください。
中村社長 : 手や足を失った人の義手・義足、腰や膝を痛めた人のコルセットなどを作っています。 ぜひ副大臣にも実物を見て触っていただきたいのですが ・・・。
平副大臣 : 質感がリアルで、まるで本物のようです。 これだけ精巧なものを地方で作られているのは、世界が驚愕するようなことだと思います。
- - ここまで精巧な製品をつくるからこそ、今、中村ブレイスには世界中からお客さんや技術を学びたいという若者たちが集まっています。 ところで、中村ブレイスがあるところは、石見銀山の麓の小さな町ですよね。
中村 : はい。 島根県の中央部に位置する石見地区です。 石見銀山が 8 年前に世界遺産登録され、歴史のある街ではありますが、日本一僻地ではないかというような場所に位置しております。
- - 実はその過疎の町で考えられないような不思議な現象が起きています。
中村 : 石見は人口 400 人の町で、私も含めた 65 歳以上の高齢者率が約 40% なんです。 数年前は少子化も危惧していましたが、世界遺産に登録されてから特にこの 2 - 3 年間、文化を持った地域として非常に人々の関心が高くなっています。 当社の社員だけでなく、ぜひこの銀山の町に住んでみたいと I ターン、U ターンする人が増えてきました。 そして、夢のようですが、この 1 年半でなんと 14 人の子どもが生まれようとしており、ちょっとしたベビーラッシュになっています。
- - そこには中村さんが 20 年以上かけてこの町の活性化に取り組まれてきた背景がありますよね?
中村 : 20 代のときに私は京都とアメリカで修業して、石見に帰ってきました。 自宅の納屋で創業したときは、この町に帰っても何もできないだろうと周囲から見られていたと思います。 でも、一人ひとり社員を養成するしかない。 それには 10 - 20 年かかるだろうけれど、気長にやるしかないと夢を追い求めてやってきました。 しかし若い力とは恐ろしいもので、障害をお持ちのお客さんが非常に喜んでくれる表情を見て、若者たちがすごく自信を持ち、力を発揮してくれるようになったんです。
- - 中村ブレイスの地方を元気にしていく姿を見ていると、今回の地方創生は、これまでの地方再生、ふるさと活性化というものとは少し違うのではないかという気がしています。 ぜひ、これまでとどう違うのか平副大臣にご説明願いたいのですが。
平 : 地方を元気にする政策というと、今までは地方に公共事業を持ってきたり、交付金や地方交付税をばらまいたりということが多かったのですが、もうそういう古いタイプの政策はやめましょう、と。 いわゆる過疎地など交通的な条件不利地でも、自分たちの地域の価値を再発見し、自分たちの力で活性化している地域はたくさんあります。 今回の地方創生は、国からああしろ、こうしろという形ではなく、地域から巻き上がってくる活動を応援して、こういう元気にする方法があるんだ、といういわゆるベストプラクティスを日本中の人に知ってもらい、自主的にプランを作ってもらおう、ということなんです。
平副大臣自身が各地を回り地方創生の本当の意味を説いている
- - そうすると、自分たちのアイデアで新しいことに挑戦しようとする取り組みに対して、政府は予算をつける形ですか。
平 : 基本的には地方でアイデアを出してくださいと。 その担い手は中村ブレイスさんのような中核となる企業や、市役所、大学、金融機関などです。 今までのようなミニ東京をたくさん整備していこうとか、とにかく東京とつながり東京を経由して海外とつながろうという考えはまったくありません。 地域からの直グローバル化のような分散型にする。 条件不利地も、条件が不利だということが 1 つの魅力になるわけですよね。 観光でも、こんなに遠くまで来たというのが 1 つの価値になります。
1,800 の地域があれば、1,800 通りの地方創生策があると思いますし、霞が関で考えても出てこないようなアイデアがたくさん出てくるでしょう。 それをたくさん見せていただいて、広く全国に知ってもらうための活動をしていきます。
その中で要望があれば、霞が関の人間を地方に派遣したり、霞が関の各省庁にコンシェルジュという、県の担当者を置いたりしましたので、その担当者が各県の対応を一手に引き受けます。 他にも情報面ではビッグデータをできるだけ自治体に提供していきたいと思っています。 また、財政面でも先進的な事例には応援する。 自治体の総合戦略を作成するための費用は出します。 財政、人材、情報の 3 つの面から応援していきたい。
地方がまず自信を取り戻してほしい
- - 中村さんはなぜ石見に戻って創業しようと思われたのでしょうか?
中村 : 私は 20 代のときにアメリカのカリフォルニアにある、世界的に有名な義手の会社で修業させていただきました。 シリコンバレーの入り口の街で、オレンジ畑の中に立派な工場が建っていたのですが、そこから世界に義手を発信しているのを目の当たりにして、目からウロコが落ちるような衝撃を受けました。 それまでは医療器具の製作は大都市でないとできないと思っていたんです。 でも、ここで作った製品が世界に立派に広まっている。 それを見たときに、どんなところで作ってもいいんだと思いました。
若くして京都、そして米国で経験を積んだことが、中村社長の人生を大きく変えた
私の産まれた石見の町は当時すでにゴーストタウン化していましたが、300 - 400 年前は日本中が注目するドル箱の銀山だったわけです。 我が町には大変な財産があることをみんな忘れてしまっていた。 そういう特性をバックボーンとしてやっていけば、銀山の街から医療器具の会社を生み出せるのではないかと思ったんです。
- - 平副大臣、最大の問題はもしかしたら、地方の人たちが自信を失っていることなのではないでしょうか?
平 : バブル崩壊後景気が低迷しました。 少子高齢化が進み、財政再建もしなければならない。 新興国含め、国際競争は激しくなる。 そうした中で日本全体が自信を失っていたというのはあると思います。 ですが、今これだけアジアが豊かになってくると、実はピンチがチャンスにもなる。 我々が知らないところで、自信を喪失して思考停止になっている間に、世界は様変わりをしている。 例えばこれから農業、漁業、畜産などの一次産業も高付加価値と合わせて輸出を目指したり、観光業も海外の人にたくさん来てもらったり、新たな需要を地方が主体的に生み出す環境ができてきたと思うんです。
海外の観光客が日本に来る場合のビザの問題、検疫の問題、関税の問題などの環境の整備は国がしなくてはなりません。 今まで儲からない、斜陽だと思っていた産業が実は成長産業であって、その企業が最大限活躍できる環境を作っていきます。 それが政府の役割だろうと思います。 中村ブレイスの地方を元気にしていく姿を見ていると、今回の地方創生は、これまでの地方再生、ふるさと活性化というものとは少し違うのではないかという気がしています。
環境の変化はビジネスチャンスだと捉えよう
- - ぜひ、これまでとどう違うのか平副大臣にご説明願いたいのですが。 ここから先の地方創生というのは、予算面では新しい取り組みが始まるのでしょうか?
平 : まずは地方に魅力的な仕事があるかどうかが非常に大事です。 若い人たちが地方に戻って結婚し、出産し、子育てができる環境をつくる。 これまで地方にはやりがいや適正な報酬を得られる仕事がなかった。 それで、中村ブレイスさんのようなベンチャー企業や、オンリーワンの技術を持つ企業が頑張ってくれることが地方創生になると思うんです。
政府は補助金を出し、それが終わったら政策も終わりという失敗をこれまで繰り返してきました。 今回、地方の皆さんにお願いしているのは、持続可能な計画、そして結果重視ということです。 KPI の指標をちゃんと持ってください。 PDCA サイクルを回してください。 民間では当たり前のことですが、これを自治体も頭に入れてくださいねと。 さらに経済の流れが検証できるビッグデータを活用して、継続して検証を行う環境を整備しようとしています。
- - 地方創生を成功させるには地方に人が集まって来ないとダメですよね。
中村 : 私は若いときは、東京や海外で大いに頑張ってもらいたいと思います。 東京の良さ、世界の良さを知ってほしい。 それは素直な私たちの気持ちです。 だけど、また自分の産まれ育った町のことが気になって、あるいは自分が大学で学んだことが地方で実践できると気づいたならば、そのときは勇気をもってふるさとに帰ってほしい。 地方の良さは、空気がよくて自然が豊かですよということだけではなくて、発想の原点もまたあるかもしれません。 そういう地方と都市部のお互いにとって素晴らしい循環が生まれることが大事なのではないかと思います。
- - 平副大臣、ご自身もご実家が中小企業を経営されています。 その立場から見て、日本の中小企業は今後どうなっていくとお考えですか?
平 : 中小企業の強さは、経営者一人ひとりが命がけでやってるということなんですよね。 なので、潰れそうで潰れない。 まさに強靭なんです。 ただ、じゃあ今の延長線上に未来があるかというと、それは違うと思うんです。 中小企業がもともと持っている強さに加えて、今起こっている環境の変化をまさにビジネスチャンスとらえて新たな挑戦をしてほしい。
ここ 10 年、20 年の中小企業政策は、金融危機やバブル崩壊があったので、金融を支える、資金繰りを支える政策にほぼ尽きると思うんです。 でもそうではなくて、日本は一次産業も儲かる。 自動車や電気製品の輸出だけではなくて、観光業も儲かる。 さまざまな地方発の起業も起きていく。 そういうふうに、あらゆる分野で儲かる可能性がある。
その環境は国が整えていきます。 何とかヒルズで起業することばかりがカッコイイのではなくて、これからは地方で起業するのがクールだと。 バブル崩壊、東日本大震災を経て新たな価値観が生まれてきたと思うので、ぜひ地方での起業という大きなトレンドを応援できたらいいなと思います。 (構成 : 尾越まり恵、日経ビジネス = 6-4-15)
松江城、なぜいま国宝に? この夏の官報に載ることで指定
松江城が、天守としては 63 年ぶりに国宝に指定されることになりました。 本に古い様式の天守と紹介されていましたが、なぜ、今になって国宝に指定されるのでしょうか。(愛知県会社員男性 53 歳)
■ 同時代史料の再発見が決め手に
国宝は、文化庁の報告をもとに、国の文化審議会が「重要文化財のうち製作が極めて優れ、かつ文化史的意義が特に深い」と認めた建造物や美術工芸品のこです。 正式には、文部科学大臣の諮問を受けて文化審議会が答申。 松江城はこの夏の官報に載ることで指定されます。 現在、国宝建造物は 221 件。 国宝天守は姫路(兵庫県)、彦根(滋賀県)、犬山(愛知県)、松本(長野県)の 4 城です。
15 日に答申された松江城は、戦前の「国宝保存法」では国宝でしたが、戦後の「文化財保護法」で重要文化財となりました。 文化庁によると、当時、国宝から漏れた理由は分からないとのことです。 今回の国宝化の決め手となったのは、築城年を裏付ける祈祷(きとう)札の再発見でした。 松江城は、関ケ原の合戦後に月山富田(がっさんとだ)城に入城した堀尾吉晴が、現在の松江市中心部に築いた平山城です。 築城は江戸時代半ばの書物から、大坂冬の陣の 3 年前の 1611 (慶長 16)年とされてきましたが、同時代の史料がなく、確定していませんでした。
城の完成時に奉納されたとみられる祈祷札 2 枚には、「慶長十六」の墨書きがあり、戦前に研究者が天守で確認していましたが、その後は行方不明でした。 市は築城 400 年の 2011 年、懸賞金 500 万円をかけて祈祷札の調査に乗り出しました。 翌 12 年、二の丸にある松江神社で市職員が発見。 城の穴蔵でも札が打ち付けられた釘穴が見つかり、通説だった築城年が裏付けられました。 また、近年の研究で、四重 5 階の天守の 2 階以下に月山富田城の部材を再利用したこと、2 階分の「通し柱」を複数配置することで構造を安定させたことなど、松江城独自の工法が次々と明らかにされました。
明治期の廃城令で多くの天守が取り壊されるなか、地元の有力者が買い戻して保存した松江城。 改修への補助など国の支援は重文と大きな変わりはありませんが、国宝化は市民の悲願でした。 10 年には、市民が国宝化を求める約 13 万人分の署名を集めました。 祈祷札発見のきっかけも、「神社に棟札がある」という市民の一報だったそうです。 国宝化の裏には、研究を後押しした市民の思いがあったといえるでしょう。
■ にぎわう城下町、地元の若者が活躍
初夏の城下町は連日、多くの観光客でにぎわい、早くも「国宝効果」に沸いている。 お祝いムードに一役買うのは、地元のために活動してきた「娘」、「武者」たちだ。 「正方形のが鉄砲狭間(ざま)、長方形のが弓狭間です。」 白い着物姿の渡辺由佳子さん (25) が説明すると、観光客が城壁の小穴に目をやった。 松江城を指定管理する NPO 法人「松江ツーリズム研究会」が催す城下めぐりツアーだ。 大坂に豊臣秀頼がいた時代に築城され、籠城(ろうじょう)用の井戸や石落としといった、実戦を意識した造りが見どころになっている。
渡辺さんはツアーガイド「ちどり娘」。 千鳥が羽を広げたような破風(はふ)にちなんだ城の別名・千鳥城が由来だ。 20 - 30 代の女性 7 人がはかまや着物、夏は浴衣姿で案内する。 3 年前の結成当初からのメンバー、谷夏海さん (27) は「何で国宝じゃないのとよく聞かれました」と振り返る。 4 年前、大阪から U ターンした。 以前は誰が建てた城なのかすら知らなかったが、築城 400 年のイベントに関わるうち、魅力にとりつかれた。
「国宝化をきっかけに、期待以上の感動を与えられるよう、市民全体で盛り上げていきたい。」 天守をバックに観光客の記念撮影に応じるのは、「まつえ若武者隊」の出雲修理さん。 築城 400 年のイベントで結成。 その後も、隊員 4 人が仕事のない週末を利用し、JR 松江駅などで活動を続けてきた。 「正体」は秘密。 「長年の夢だった国宝化の発表はうれしかったんじゃ」と話すなど、徹底したキャラクター設定が人気だ。
松江市観光文化課によると、昨年の松江城の登閣者数は約 38 万人。 出雲大社の「平成の大遷宮」の効果もあって、3 年前までの年間 20 万人台から伸びたが、反動が心配されていた。 それだけに国宝化はうれしいニュース。 土日の登閣者数は 2 週連続で、決定前の約 1.8 倍の約 3,700 人に増えた。 出雲さんは「改めて来られる方もいて、うれしいやら。 この機会にまた楽しんでもらえたらうれしいでござる。」 (松江総局・小早川遥平、asahi = 6-1-15)
観客「ゼロ」なら終了 … 島根の劇団、前代未聞の "365 日公演" に挑戦「東京に行かなくても役者はできる」
今年 1 月 1 日から年末まで前代未聞の「365 日公演」に挑戦している劇団がある。 しかも、のどかな田園風景が広がる島根県雲南市を会場にしており、一人も観客がいなければ「即終了」というかなり過酷な条件付き。 団員はスタッフも含めてわずか 9 人しかおらず、気力や体力、団結力なども要求される。 これまでに公演回数は 100 回を超えたが、いまだに挑戦は継続中だ。 「いずれは満席にしたい」との夢を抱きながら、最終公演日とされる大みそかの 12 月 31 日まで舞台に立ち続けることができるのか -。
観客 3 人も … 劇団員らもぎりぎり
「こんなに良い天気なのに、わざわざ演劇を見にきてくれてありがとうございます。 天気の日は、日に当たった方がいいです。」 4 月下旬、前代未聞の挑戦をしている「劇団ハタチ族」の公演。 こんな自虐的なあいさつで始まると、客席から笑いが起きた。 拠点となる「チェリヴァホール(雲南市、465 席)」には、10 回目という常連客を含めて観客は 15 人が集まり、何とか課題をクリア。 翌日以降も継続することが決まった。
「開演前になってもお客さんの姿がなかったら、『大丈夫だろうか』と気になります。 連日のプレッシャーは相当なものです。」と劇団代表の西藤将人さん (31) は話す。 今年の元日から始まった挑戦は、他団体の公演日を除いてすべて実施。 これまでに 100 回超の公演を行ってきた。 観客がわずか 3 人しか入らなかったときもあったが、開始から 4 カ月が過ぎてようやく安定してきたという。
劇団メンバーは、ほとんどが地元・雲南市在住。 20 - 30 代が中心で、俳優 6 人とスタッフ 3 人という小さな劇団だ。 もちろん劇団の仕事だけでは生活ができないから、多くが別の仕事を持ちながらけいこや公演に臨んでいる。 西藤さんも「ぎりぎりのところで役者を回しています」と説明する。
「五輪も W 杯もない」平成 27 年に挑戦
西藤さんは鳥取県米子市出身。 雲南市の創作市民演劇に参加したのがきっかけで平成 25 年に「劇団ハタチ族」を立ち上げた。 「それまでは、東京に行かないと役者として大成しないと思っていました。 でも、市民演劇のメンバーと劇を作るなかで、成長できるかどうかは自分次第だと分かりました。」と劇団立ち上げ当時の意気込みを振り返る。
あるとき、東京の劇団員から毎日異なる公演を 1 カ月間にわたって行ったとのエピソードを聞き、この無謀とも思える挑戦が思い浮かんだという。 「雲南市で毎日、演劇が見られない環境を寂しく感じていました。 毎日、演目を変えることはできませんが、それに近いことをやりたくなりました。(西藤さん)」 団員らに相談したところ、「あっいいよ」、「面白そうだね」 … などと好意的な反応が返ってきた。 約 1 年半の準備期間を経て、今年 1 月からの実施を決めた。 「平成 27 年は、オリンピックも(サッカーの)ワールドカップもありませんから …。 演劇を見にきてくれる人もいるでしょう。」と西藤さんは笑顔を見せた。
「大みそかには満席に …」の夢を抱き
公演では、一人劇やコント、落語をアレンジしたものなど 3 - 4 日ごとに演目を変えている。 取材当日の演目は、演劇の楽しみ方を観客に伝える「演劇入門。」 俳優がトイレに行く姿をユーモラスなスローモーションで再現したり、発声練習で「愛してる」などとまったく恋愛感情がない相手に向かって連呼したり … コミカルなシーンの連続に、客席から笑いがわき起こる。 「むちゃなことかもしれないが、全力でやるしかない。」 「毎日頑張る時間があるのは、すてきなこと。」 脚本は西藤さんが手がけたが、俳優たちが語るセリフには説得力さえも感じられる。
公演を見た島根県出雲市の会社員、須田祐司さん (39) は「苦労しながら作っているのが伝わってくる」と話す。 同市の別の会社員の男性 (39) も「全力で笑えるところが良い。 同じ演目でも、会場の雰囲気や役者の状態で違う内容に見える。」と、繰り返し訪れる魅力を語った。 客席には、鹿児島県からわざわざ車で訪れたという観客も。 「演劇が目的でやってきました。 これから出雲大社(出雲市)に行きます。」と笑顔を見せた。 「良かった」、「元気をもらった」という観客らの喜ぶ声は、劇団員らの糧にもなっている。
あの手この手の集客戦略に奔走しながら、年末の最終公演に向けて舞台に立ち続ける劇団員ら。 西藤さんは「大みそかに大ホールを満席にしたい。 年末にただやり終えたというだけでなく、雲南市の演劇にプラスになる成果を残したい。」と意気込んでいる。 (坂田弘幸、sankei = 5-25-15)
ソニー辞め、島根の離島へ 教育通じ過疎に挑む
「教育魅力化特命官」。 4 月 1 日、岩本悠 (35) は全国で類を見ない新設職を島根県庁で授かった。 魅力ある教育を通じて地域を支える人材を増やす戦略を練り、実践する。 「新天地という思いはありません。」 岩本はこう話し、新たな挑戦の舞台に上がった。
■ 「よそ者」に重責託す
岩本は東京都出身。 島根県の生え抜き職員でもない。 大学卒で入ったのはソニーだった。 なぜ「よそ者」の岩本に県は重責を託すのか。 統廃合の淵にあった離島の高校を、全国から生徒が集まる人気校に育てた手腕が買われたのだ。 沖合約 60 キロメートル先の隠岐諸島。 2006 年末に岩本は海士(あま)町にある県立隠岐島前(どうぜん)高校にいた。 「暗いし、ボロいな。」 廃校寸前の校舎も備品も古かった。 ソニー人事部で働き、この町の中学校に出前授業の講師として招かれた縁で「島の高校を立て直してほしい」と依頼されたのだ。
岩本は何度も異なる文化や環境に飛び込んできた。 20 歳のころに 1 年間休学してアジア、中東、アフリカを転々とした。 観光名所に目もくれず、非政府組織 (NGO) などで働き、現地の暮らしを目に焼き付けた。 その体験記を自費出版し、印税を投じてアフガニスタンに小学校を建てた。 岩本に明確な勝算があったわけではない。 「海士町を無人島にしたくない。 人口減を食い止めるために教育改革が必要だ。」 こう訴える町長の山内道雄 (76) や職員らの熱意にほだされた。 ソニーを辞め、「高校魅力化プロデューサー」という肩書を得て移住した。
町民の誰もが岩本を歓待したわけではない。 最初は「どうせそのうち本土へ帰るんだろ」というような冷たい視線を浴びた。 高校の教師からも「人手が足りないのに仕事を増やさないでほしいと愚痴られた」という。 岩本は改革の実例作りに専念した。 ターゲットにしたのは硬直的なカリキュラム。 受験対策コースや地域活性策を考えるコースなど、過疎化が進む「課題先進地域」であることを逆手に取り、新発想の授業を組み込んでいった。 決まり切った答えを示すのではなく、高齢化や福祉などの課題を自ら設定し、生徒らに考える習慣を根付かせる内容だった。
■ 「島留学」人呼ぶ
念頭にあったのは「教育の魅力を高めること、現場に専念すること。」 岩本は仕組みを変えようとするたびに、関係機関に出向き、了承を取り付けた。 町長の山内は「実行力に驚いた。 制度にとらわれない柔軟な発想力がある。」と評する。 「島留学。」 これが岩本の最大のヒットだろう。 全国各地で説明会を開き、島前高校のユニークな取り組みを紹介。 多様性を取り入れるために 10 年から寮や下宿で島外から生徒を受け入れることにしたのだ。 豊かな自然の中で高水準の授業が受けられると評判が広がり、都会から島にやってくる留学生は増えていった。
島前高校の入学者数は直近のピークである 1991 年の 83 人から 2008 年には 28 人と 3 分の 1 まで減っていた。 だが、教育改革の成果が色濃く表れた 12 年には 1 学年あたりのクラス数は 2 つに増え、完全に右肩上がりの軌道に乗った。 岩本がこの春に海士町を離れ、島根県庁での仕事に就いたのは単純に達成感を味わったからではない。 「8 年間にわたる改革を離島だから、小さい高校だからできたという特殊事例にしたくない。」 県内にはほかにも過疎地がある。 「改革を持続させるために県全体のシステムを進化させたい」というのだ。
本はこの 10 年間、髪形を変えていない。 丸刈りだ。 「シャンプーいらずで楽」と笑うが「髪の毛で顔が隠れない。 ごまかしがきかず、人に誠実に向き合える気がする。」との思いがある。 「地域での教育を通じて日本をよくしたい。」 柔和なまなざしに、おっとりとした口調。 岩本はいつも気負いのない自然体なのだ。 = 敬称略 (若杉朋子、nikkei = 5-23-15)
データで見る夫の家事分担率 1 位は島根、最下位は …
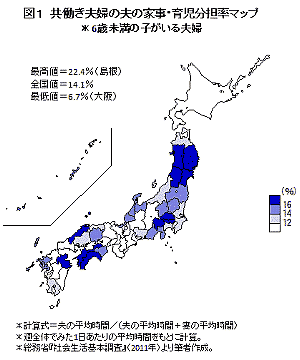
武蔵野大学講師の舞田敏彦さんが、統計データを使って子育てや教育にまつわる疑問を解説します。 今回は「夫の家事・育児分担率」について。 日本の共働き夫婦の家事・育児分担率は、0 歳の子どもがいる家庭でも「夫 15%、妻 85%」。 欧米諸国の夫の分担率が 30 - 40% なのに比べるとまだまだ低いのが現状です。 また地域別に見ると、夫の分担率 1 位は島根県で、東京・東北・四国の夫の分担率も高いのが特徴。 逆に近畿地方では、軒並み低くなっています。
■ 1 - 2 歳の子どもがいる夫の分担率は、日曜日で 26%
総務省の「社会生活基本調査」という資料に、主な生活行動の平均時間(1 日当たり)が掲載されています。 私は、共働き夫婦の家事・育児の平均時間を調べました。 曜日ならびに末子の年齢別の数値を採取し、それを基に夫の家事・育児分担率を計算してみました。 週全体の 1 日当たりの平均時間は、0 歳の乳児がいる共働き世帯では、夫が 92 分、妻が 527 分となっています。 よって夫の分担率は、92/(92 + 527) = 14.9% と算出されます。 「夫 15 : 妻 85」ですか、思ったより低いですね …。
その後、イヤイヤ期の 1 - 2 歳ではちょっと上がり、その後は子どもが大きくなるにつれ低下していきます。 曜日別に見ると、平日よりも土日の分担率が高くなっています。 日曜で見ると、1 - 2 歳の子がいる夫婦では、夫の分担率は 26.1%、およそ 4 分の 1 です。 これが全国の平均像ですが、どのような印象を持たれたでしょうか。 「全然低いじゃん」と思われたかもしれませんが、夫婦とも正社員の世帯で見たら、値はもっと高くなるでしょう。 全国のデュアル世帯の母集団では、夫が正規雇用、妻が非正規雇用(パート等)の世帯が多いことに留意してください。
■ 地域別で見ると、東北・四国が高くて近畿圏が低い
次に、地域別のデータを見てみましょう。 私は鹿児島の出身ですが、中学時代の家庭科教師(女性)が「男は厨房に立つべからず」と、堂々と生徒の前で言い放っていたのを覚えています。 これを人に話すと「鹿児島っていう土地柄じゃないの」と言われますが、そうなのでしょうか。 幼い子ども(6 歳未満の子)がいる共働き世帯の夫の家事・育児分担率を都道府県別に計算し、地図にしてみました。 12% 未満、12% 以上 14% 未満、14% 以上 16% 未満、16% 以上という 4 つの階級を設け、それぞれの県を濃淡で塗り分けた図です。
全国値は 14.1% ですが、県別に見ると、22.4% から 6.7% まで幅広く分布しています。 トップは島根ですが、この県は、子育て期の女性の正社員率も 1 位です。 三世代世帯が多いという条件もあるでしょうが、共働き先進県として注目されます。 東北や四国も、夫の分担率が比較的高いですね。 首都の東京も濃い色になっています。
なお、近畿地方は見事に真っ白になっています。 最下位の大阪をはじめ、どの県も夫の分担率は 1 割ほどです。 冒頭で紹介したパパさんが「忙しさによって『夫 1 : 妻 9』くらいになる」と言っていましたが、近畿圏では常時こういう状態であることになります。 なお、県別の児童虐待の発生率では、近畿地方は値が高い傾向にありました。 「家事をしない夫 → 妻の不満・イライラ → 虐待」 … こんな因果関係が存在しないかどうか、ちょっとばかり不安に思います。
■ 欧米諸国では「分担率 3 - 4 割」が当たり前
それはさておき、国際的な視野で見れば、日本国内の地域比較など「どんぐりの背比べ」です。 他の先進国では、夫の家事分担率は 3 - 4 割というのがザラ。 「社会生活基本調査(2011 年)」の国際統計から、夫の家事・家族ケアの分担率を計算すると、アメリカは 40.0%、スウェーデンは 38.3%、ドイツは 35.3%、フランスは 33.0%、イギリスは 32.8% です(6 歳以下の子がいる共働き夫婦)。 日本は 18.5% であり、大きく引き離されています。
まあこれは、わが国の男性の仕事時間がメチャクチャ長いことによるでしょう。 日本は「男は仕事、女は家事」という役割差が最も大きい社会です。 ですが、子育て期の男性の家事分担意識が低いということはなく、むしろ現実は逆です。
どの年齢層でも女性より男性で率が高く、若年層ではその差が大きくなっています。 20 - 30 代の男性では、6 割以上が「男性も家事・育児を行って当然」と考えているではありませんか。 近年のジェンダー・フリー教育の効果かどうかは分かりませんが、共働き世帯の夫の家事・育児分担率が高まる素地はできているようです。 これに仕事時間の短縮という条件が加われば、男性の家庭進出はかなり促進され、ひいては女性の社会進出も大きく進展することでしょう。 (nikkei = 3-27-15)
舞田 敏彦 さん 1976 年生まれ。 東京学芸大学大学院博士課程修了。 博士(教育学)。 武蔵野大学、杏林大学兼任講師。 専攻は教育社会学、社会病理学、社会統計学。 著書に『教育の使命と実態(武蔵野大学出版会)』、『教職教養らくらくマスター(実務教育出版)』など。 近著は『平均年収の真実 31 の統計から年収と格差社会を図解 【データえっせい】(impress QuickBooks)』。