�u�I�g���v�A�u���v�����Ō����ł����@�������茾�_����
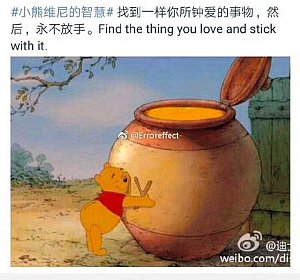
�������Y�}�̏K�ߕ��i�V�[�`���s���j�w���������Ǝ�Ȃ̔C����P�p���A�K���̒����������\�ɂ��錛�@�����Ă����������Ƃ�����A�������ő��������Έӌ��ɑ��錾�_�K���������Ă���B�@����ŁA���ǂ͘A���A���f�B�A���g���ĉ����̐��������A�s�[�����Ă���B
�C���P�p�Ă����\���ꂽ��A������ SNS ��ł́u���͔��v�A�u�s���Ӂv�A�u�I�g���v�Ȃǂ̌��t���S�������ł��Ȃ��Ȃ����B�@1 ���܂łɂ��������L�[���[�h���̂͌����ł���悤�ɂ͂Ȃ������A���@������ᔻ������e�̑����͍폜����Ă���B�@���܂̃v�[������K���Ɍ����āA�I���i���́j�������Ǝ�����Ȃ��G�������Ȃ��܂܂��B�@�ꕔ�̖���h�� SNS �A�J�E���g�͏������݂����Ă��Ȃ��Ă���������A������ᔻ�����l�̏������݂� 1 �T�ԋ֎~����Ȃǂ̋K���������Ă���B (�k�� = ���^����Aasahi = 3-3-18)
������ SNS �Łu�f�B�Y�j�[�v���֎~���[�h��
�����͂ǂ��Ɍ��������Ƃ��Ă���̂ł��傤�� �c�B�@�����A�����͌��@���������č��Ǝ�Ȃ̔C����P�p����\��ł��B�@�܂�A�����Ǝ�Ȃ̏K�ߕ����ɂ��u�ƍِ����v�̉\�����łĂ����킯�ł��B�@�s�������܂钆�A�����̃C���^�[�l�b�g���{�����u�f�B�Y�j�[�v��u�r�܂���v�Ƃ������V���ȋ֎~���[�h�𒆍��Ńc�C�b�^�[�� Weibo ��A������ LINE �� WeChat ����폜���͂��߂��悤�ł��B�@China Digital Times �Ƃ������������̃j���[�X�𒆐S�ɓ`����p��T�C�g���֎~���[�h���Љ�Ă���̂ŁA�����������ďЉ�܂��傤�B
- �uThe Emperor's Dream�v : 1947 �N���J�� 35 ���ڂ̃A�j���[�V�����l�`���f��ŁA�ё����鋤�Y�}�ɔs��A��p�ɓ������Ӊ��`��������B
- Disney �i�f�B�Y�j�[�j : 2013 �N�ɒ����̃l�b�g���[�U�[���K�ߕ����Ǝ�Ȃ��u���܂̃v�[����v�ɂ������肾�ƒ����������Ƃ������ŁA�u�v�[����v�͔��̐��h��������Ă��܂��B�@�������֎~���u�f�B�Y�j�[�v�Ƃ������t�ɂ܂ŋy�ԂƂ� �c�B
- roll up + sleeves �i�r�܂��� + ���j : �K�ߕ����Ǝ�Ȃ��V�N�̈��A�Łu13 ������l�X�����ʂ̖ړI�Ɍ������A�}�Ɛl�X�����ɑ��������グ�Ċ撣�����A������́u�����v�𐬌������邱�Ƃ��ł���v�ƃX�s�[�`�������Ƃ��炫�Ă��܂��B
- Chinese Emperor stock �i�����c�銔���j : China Digital TImes �ɂ��ƁA���Ǝ�Ȃ̔C���P�p�̔��\�̂��ƁA�����̊����s��́u�c��v�Ƃ������t�̂������������������ł��B
- oppose Qing, restore Ming �i���������j : �������ɔ�����l�����̃X���[�K���B
- personality cult �i�l���q�j : ���Ў�`�I�w���҂��ǂ�����ė�q��^���Ȃ��������������C���[�W����������Ɍ��y�B
- the wheel of history �i���j�̗ցj : �@���╶���Ƃ������A���Ԃ��J��Ԃ���Ă���悤�Ɍ�����p��ŁA�����̎��R���̐����ւ̔��̐��I�ȕ����̒��Ŏg���܂��B
- �uDream of Returning to the Great Qing�v : 2006 �N�ɒ����ŏo�ł��ꂽ Jin Zi ���ɂ�钘���^�C�g���B
- change the law �i�ϖ@�j : �C���P�p�����ƂɌ��y�B
- �uBig River, Big Sea 1949�v : 2009 �N�ɑ�p�ŏo�ł��ꂽ�{�̃^�C�g���B�@�������{���댯�����Ă���B
�����͐V���ɒlj����ꂽ�֎~���[�h�̐��X�ł����āAChina Digital Times �ɍs���A���ɂ����������˂錵�����̃��[�h�����邱�Ƃ��ł��܂��B�@����ɂ��Ă��A���`�ƁA�ŋߏ�C�Ƀe�[�}�p�[�N���I�[�v������������̃f�B�Y�j�[�͂��̌���ɕs���������Ă���ł��傤�ˁB�@���������A�����̍��z�ł���M�d�ȃR�~���j�P�[�V�����c�[���ł����� WeChat �Łu�f�B�Y�j�[�v�ƌ����Ȃ�������A�ǂ�����ėF�������u�f�B�Y�j�[�s�����v�ƗU���̂ł��傤�B�@�Ƃ������A�f�B�Y�j�[�Ɍ��炸�A���Ƃ肷��̂ɂ���ȂɌ��t�ɋC�����Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�Đ����Â炢�Ȃ� �c�B
���Ȃ݂ɁA���̋L���͒����l�̗F�����̉ƂŎ��M���Ă����̂Łu�ȂA���������ƂɂȂ��Ă����v�ƌ�������A�u�֎~�p�ꂾ������Ȃ��AWeChat ���Ȃ���ɂ����Ȃ邱�Ƃ����邵�A�l�b�g����C��������B�@�ق�Ƃ��ɈӖ��s���B�v�ƕ���ʂĂ��l�q�ł����B�@���́u�l�b�g����C������v�ɂ͎������S���ӂł��B�@���N�A�k���œ}���J����Ă��������ɏ�C�ɐ����ԑ؍݂��܂������A�����T�C�g�ȊO�قƂ�ǂȂ��炸�A���{�����͂���ƁA�ق� 100 �p�[�Z���g�̊m���ŃG�O���G���T�C�g�ɂȂ����ău�`�ꂻ���ɂȂ�܂�������� �c�B (Matt Novak�AGizmodo = 3-2-18)
�u���܂̃v�[����v���O�[�O�����֎~�A�����̌��{�V�X�e��
�����̃I�����C���l���� 7 �� 3,100 ���l�ɒB�������A�C���^�[�l�b�g�̗��p�͋ɓx�ɐ�������Ă���A�Ⴆ�O�[�O���A�t�F�C�X�u�b�N�A���[�`���[�u�A�j���[���[�N�E�^�C���Y�ȂǂɃA�N�Z�X���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�@1989 �N�̓V����L��ɂ�����w���̍R�c�s���Ɋւ���͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ��B�@�u���܂̃v�[����v�ł����A�֎~����Ă�������������B�@����������قǖc��ȃR���e���c�̊C�����邱�Ƃ��ł���̂́A���E�ő�̌��{�V�X�e�����\�z���Ă��邩��ł���B
���̃V�X�e���́A�����̃O���[�g�t�@�C�A�E�I�[���i�u�h�Β���v�j�Ƃ����A�����ɂ��Ƃ������ŌĂ�Ă���B�@����͐��{�̊Ď����ƃe�N�m���W�[��Ƃ�ʐM��ƂƂ̋�����Ƃł���A����������Ƃ͍��Ƃ̃��[�������{���邱�Ƃ�]�V�Ȃ�����Ă���B�@���̗��Q�͒����̊O�܂Ŋg�債�A���̓ƍٍ��Ƃ��͕�ł����{�̂悤�ɂȂ��Ă���B
��}�ƍق̒����ɂ����Č��������{�͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ����A�K�ߕ����Ǝ�Ȃ̉��ł̓I�����C���ɑ�����ߕt�����܂��܂����i������Ă���A���Ƀm�[�x���ܕ��a��ҁA���Ŕg���̎����i2017 �N�j�̂悤�Ȑ����I�ɔ����ȏo�������N�����������̑O��͂����ł���B�@���� 17 �N�̑� 19 �Y�}���ɐ旧���āA�����̓��b�c�A�b�v�̃��b�Z���W���[�T�[�r�X���Ւf���n�߁A�O���[�g�t�@�C�A�E�I�[�����I���i�Ƃ��Ĉ�ʂɎg�p����Ă��鉼�z�v���C�x�[�g�l�b�g���[�N (VPN) �ɑ�������܂���g�勭�������B
�����́u�T�C�o�[�匠�v���m�ۂ��邱�ƁA���邢�͒����̃C���^�[�l�b�g���O���̉ߓx�̉e������ی삷�邱�Ƃ́A�K��Ȃ����R�ƔF�߂Ă���ڕW�̈�ł���B�@�I�����C���̎��R�𐧌����悤�Ƃ���ŋ߂̓����Ƃ��ẮA�\�[�V�������f�B�A�ɓ����œ��e����\�͂��قƂ�ǖ���������A�A�v���X�g�A�̃I�[�i�[�Ɍڋq���w�������A�v�����ǂ̂悤�Ɏg�p���邩�ɑ��ĐӔC�킹��A�����āA�I�����C���|�[�^���Ƀj���[�X�̒�~���`���t����Ȃǂ̎{����B�@���܂̃v�[����̈ꎞ�I�ȋ֎~�́A�u���K�[�炪�K��Ȃ����̖���L�����N�^�[�̂��܂���Ƃ��ĕ`������Ɏ��{���ꂽ�B
����A�����{�y�ʼnc�Ƃ������O����Ƃ́A���̒n��łȂ�s���ȉ���ƌ��Ȃ���邱�Ƃ��������s������̗p���邱�Ƃ��������Ă���B�@�A�b�v���̓p�X���[�h�ŕی삳�ꂽ���А��i�Ƀo�b�N�h�A�i�Z�L�����e�B�[�ی���I��閧�̗����j��݂���悤�ɕĐ��{����v�����ꂽ�Ƃ��͂���Ɋ��R�ƒ�R�������A�����ł̓A�v����ق��č폜���A�������ǂ̗v���ɉ����`�Ō��n�̃f�[�^�Z���^�[�����݂����B�@�������i��c�̂ł��鍑�� NGO �t���[�_���E�n�E�X�ɂ��ƁA�����������ׂĂ̋A���Ƃ��āA�����ɂ�����I�����C����̎��R�͒n����ōŒ�̐����ƂȂ��Ă���B
�����̓E�F�u����Ɍ������������Ă����킯�ł͂Ȃ��B�@1994 �N�ɃE�F�u�������ɓ������ꂽ�Ƃ��͔�r�I���R���F�߂��Ă���A���Ă̒m���𗘗p���Čo�ς����v����J������̉����ł���ƌ��Ȃ���Ă����B�@�E�F�u�̗��p���g�債�čL�����y���钆�ŁA���ǂ͐�̎w���ҁA�������̔����A���Ȃ킿�u�����J����n�G������v�ɋ������̂ł���B
2000 �N����u�����v�v��̓����ɂ���āA�O���[�g�t�@�C�A�E�I�[���̊�Ղ��z���ꂽ�B�@����́A�f�[�^�x�[�X����g�����Ď��V�X�e���ł���A�����S���̋L�^�ɃA�N�Z�X���Ē����̈��S�ۏ�@�ւƐڑ����邱�Ƃ��ł���B�@���݁A�������{�͌��{�����{���邽�߂ɏ��Ȃ��Ƃ� 5 ���l�̐E�����ٗp���Ă���A���ǂ��F�߂Ȃ��E�F�u�T�C�g���֎~���A�L�Q�ƌ��Ȃ����R���e���c���t�B���^�[�Ŕr������悤�����G���W���ɋ����Ă���B�@�܂��A�吨�̃\�[�V�������f�B�A����v�����e���͂��s�g���Ă���A���鐄��ɂ��ƁA�N�� 5 �����̐e���{�R�����g�𓊍e���Ă���Ƃ����B
����I�Ȗ��́A���Nj@�ւ��A��Ƃ��\������R���e���c�ɑ��ă��[�U�[���쐬�����R���e���c�ɂ��Ă������A��Ƒ��ɐӔC�킹�Ă��邱�Ƃł���B�@����́A���Ƃ����ׂĂ̕@�ւɑ��鋖�F���������Ă��鍑�ɂ����Ď��Ȍ��{�����シ���Ƃ���i�� 1 �ł���B�@�����s�ꂪ�قƂ�Ǔ������ꂽ��Ԃɂ��钆�ŁA�����̋���e�N�m���W�[��ƁA���Ȃ킿�e���Z���g�E�z�[���f�B���O�X�i���u�j�ƃA���o�o�E�O���[�v�E�z�[���f�B���O�͔��W�𐋂��A���̉ߒ��Œ����̋��z�[�Ŏ҂ւƐL���オ�����B�@����A���̐����̓����Ƃ��āA���{�ɔ������c���c�̃O���[�g�t�@�C�A�E�h�b�g�E�I���O���A���Ɠ�����������邽�߂̃~���[�T�C�g�ƃu���E�U�[���쐬���Ă���B
�_��
�قƂ�ǂ̍������炩�̌`�ŃT�C�o�[�������ۂ��Ă���B�@�Ⴆ�A�w�C�g����������E�F�u�T�C�g�̋֎~�Ȃǂł���B�@�������{�̎咣�́A14 ���l�̐l���̔����ȏオ�I�����C���ڑ�����Ă���ɂ����āA�������������͎�Ƃ��ĎЉ�̒������ێ����A���Ƃ̈��S����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ă���Ƃ������̂ł���B�@�^���҂̓O�[�O����t�F�C�X�u�b�N�̂悤�Ȋ�Ƃ��j���[�X�̗���ɗJ�����ׂ��e�����y�ڂ��Ă��邩�炱���A���Ƃ����̋K���ɐϋɓI�Ȗ�����S���Ă���Ǝ咣����B
����ɑ��Ĕᔻ�҂́A�����̃O���[�g�t�@�C�A�E�I�[���́A�C���^�[�l�b�g����}�ƍقւ̔��Έӌ����L�߂�\���ɑ��钆���̔�Q�ϑz�f���Ă���ƌ����B�@�����Ē����̃A�v���[�`�͌��_�̎��R��W���邾���łȂ��A�o�ϓI�ɂ��������ƂȂ�B�@�Ȃ��Ȃ�A����̓C�m�x�[�V������W�Q���A�d�v�ȃA�C�f�A�̌�����j�Q���A��Ƃ��g�p����T�[�r�X�i�Ⴆ�O�[�O���E�N���E�h�Ȃǁj�ւ̃A�N�Z�X���Ւf���邩��ł���Ƃ���B�@�w�p�����҂����́A�S���E�Ŋw���⋳���炪���ʂ����L��������i�Ƃ��ė��p���Ă���O�[�O���E�X�J���[�𗘗p�ł��Ȃ��B
����Ɏ�����L����A�������V�A�⑼�̎����悤�Ȏv�z�I�X���̍��X�������̑O��P���A���̍�����S���E�̃I�����C����Ƃɐ������ۂ����Ƃɐ��������ꍇ�́A�C���^�[�l�b�g�̑n�݂̔w��ɂ���r�W�����A���Ȃ킿���E�K�͂ł̎��R舒B�ȏ������Ƃ����r�W�������傫�ȃ_���[�W����\��������A�Ɣᔻ�҂�͊뜜���Ă���B (Lulu Yilun Chen & David Ramli�ABloomberg = 2-26-18)
�����A���o�o�A�ܗւ��f�W�^�����@�����ł��ꕔ���{��
���� IT ���̈����b�b�W�c�i�A���o�o�O���[�v�j���A�f�W�^���Z�p�Ōܗւ̉^�c�R�X�g�팸��A�t�@���g��Ɏ��g�ށB�@�����܂����Ŏg����o�ϓI�ȉ^�c�V�X�e�����쐬�B�@���Ђ̓d�q�������f���R���e���c�z�M�Ńt�@���𑝂₷�B�@�����i�s�����`�����j�~�G�ܗւ̉��ɐݒu�����Z�p�W����ŁA��X�I�Ȕ��\����J�����B
�u�����ł͖� 200 �l�ȏ�̎Ј����^�c���w��ł���B�@2020 �N�̓����ܗւł͐��ʂ������邾�낤�B�v�@�؍��E�]�����]�ˁi�J���k���j�s�ɂ���~�G�ܗւ̕X�㋣�Z���B�@���̓�����t�߂̈ꓙ�n�ɂ��铯�Ђ̓W����� 10 ���A�n�_�i�W���b�N�}�[�j����L�҉�����B�@�A���o�o�ɂ��f�W�^�����̎��g�݂͍���̕����~�G�ܗւŏ������A20 �N�̓����ܗւł͈ꕔ�����{�B�@22 �N�̖k���~�G�ܗւł̂��ׂĂ̎�����ڎw���B
�A���o�o�͕ăR�J�E�R�[����p�i�\�j�b�N�A�g���^�����ԂȂǂƕ��у��[���h���C�h�I�����s�b�N�p�[�g�i�[�߂�B�@1 �Ǝ� 1 �Ќ���ŁA���E���ŌܗւƗ��߂Ď��Ђ� PR �ł���B�@�A���o�o�̊��Ԃ� 17 - 28 �N�ŁA���ӂ̃N���E�h�E�R���s���[�e�B���O�Ɠd�q��������ΏۋƎ킾�B�@���ۃI�����s�b�N�ψ��� (IOC) �����Ɋ��҂���̂́A�A���o�o�����l�b�g��Ƀf�[�^��ۑ�����N���E�h�Z�p���B�@�ܗւ̉^�c�V�X�e���͑��Ƃɍ���A�o�����`������ɂ��������B�@�����ŃA���o�o�̓N���E�h���g���A�����܂����ōė��p�ł���V�X�e�����\�z�B�J�Òn�����S����R�X�g��������_�����B
����ɃN���E�h�ɏW�߂��r�b�O�f�[�^�͂��Ċ��p�B�@�J�Òn�̐l�̗����\�����������悢���S�K����҂݂����A�H���␇���A�x���̏ȂǑI��̃g���[�j���O�̌������ő剻����Ƃ������@�\���������A�V�X�e���̎������コ����B�@���Z�f���̔z�M��A�����𒆐S�� 5 ���l���g�����Ђ̃l�b�g�ʔ̂�ʂ����ܗւ̃O�b�Y�̔��ŁA�t�@���w�̊g����S���B�@���������Z�p�͂��ׂ� 22 �N�̖k�����ł̓�������������B�@�旧�������ł̓A���o�o�̗��s���i�̔��T�C�g�����p���Đ��S���l�̒����l�ɖK�����Ă��炤�ق��A�����ɓ��{�̃u�����h�⏤�i�荞�ޘb��i�߂Ă���B
�u�f�W�^�����̎���A�A���o�o�̎w������̂����ꂵ���v���B�v�@IOC �̃o�b�n��͋L�҉�ł������}�����B�@���̃R�X�g���J�Òn�ɂƂ�d���ɂȂ��Ă������A�l�C�̒���Ƃ������ܗւ̌p�����ɋ^�╄���t�����ɂ��āA�A���o�o�� IT �ʼn����@����Ă���邩�炾�B�@����A�����ȊO�ł̑��݊��������A���o�o�ɂƂ��āA���Ђ̋Z�p�����ۑg�D�� IOC �ɍ̗p���ꂽ��`���ʂ͑傫���B
�����A�l�b�g��ɍ\�z���ꂽ�ܗւ̃V�X�e���́A������e���I��̏��ȂNj@���������������Ƃ���T�d�ȉ^�c�����߂���B�@���Њ����́u�A���o�o�͂��ꂼ��̎s��̃��[���ɏ]���ăN���E�h���^�c���Ă���B�@IOC ����T�[�r�X�̈��S���͐M������Ă���v�Ǝ咣����B (�]�� = ���c���V�Aasahi = 2-19-18)
�������l�b�g�̌��_�K�������A�|���m��S�V�b�v��O��r����
�������{���~�j�u���O�^�c��Ђɑ��A���U�̏����폜���A���[�U�[�̓��e�� 6 �����ԕۑ�����悤�w�������B�@�������ƌݗ��ԐM���ٌ��� (Cyberspace Administration of China : CAC) �́A�~�j�u���O�̓M�����u����|���m�����������U�̏����g�U���Ă���A���̂悤�ȍs�ׂɊւ�铊�e���Ď��E�폜����d�g�݂� 3 �� 1 ���܂łɍ��悤�ʒB�����B�@�u�~�j�u���O�̉^�c��Ƃ�͎Љ��`�̉��l�ς���ʂɍL�߂邱�Ƃɂ��A�o�ϔ��W�𐄐i���������S���ׂ����v�� CAC �͐����Ŏ咣�����B
����͒����ő�̃~�j�u���O�T�[�r�X�� "�����Ńc�C�b�^�[" �Ƃ��Ă��u�V�Q�����i�ȉ��A�E�F�C�{�[�j�v�ɑ��A�ꕔ�̊�Ƃ�L���l�炪�t�F�C�N�A�J�E���g���g���ăt�H�����[����s���ɑ��₵���^��������Ƃ��āA����̃T�[�r�X���~����悤�������B�@�u��Ƃ�G���^�[�e�C�����g�ƊE�̊W�҂ɂ���ă����L���O���s�����삳��Ă����B�@����Ɋ֘A���Ă����̃u���b�N�}�[�P�b�g���o���Ă����B�v�ƃE�F�C�{�[�͔F�߂Ă����B
���ǂ́u�Ԉ�������_�ւ̗U���v��u�킢���ȓ��e�v�A�u�������ʁv���������Ƃ��Ă���B�@��~�𖽂���ꂽ�T�[�r�X�ɂ͘b��̃��[�h��������z�b�g�E�T�[�`���܂܂�Ă����B�@�܂��A�L���l�̃S�V�b�v���L�߂��Ƃ��ăA�J�E���g�������悤������ꂽ���̃~�j�u���O�^�c��Ђ�����B�@�u�X�^�[�̎������Ɋւ��鉺�i�ȉ�����S�V�b�v���g�U���邱�Ƃ̓l�b�g���[�N�̒�����傫�������A�����̌�����N�Q����s�ׂ��v�Ɠ��ǂ͎w�E�����B
�����ł̓l�b�g��̓��e�̊Ǘ��ӔC���^�c��Ђ��������[���� 2000 �N�ɓ�������A��Ƃ̑����͈�@�R���e���c�������y�ю蓮�ŊĎ�����d�g�݂������B�@�܂��A���̃��[���̈�тƂ��āA��Ƃ�̓~�j�u���O�̃A�J�E���g�J�݂ɂ�����A���p�҂�̎������擾����悤���߂��Ă����B�@���p�҂̓T�[�r�X���p�J�n���ɁA�����ƍ������ʔԍ���g�ѓd�b�ԍ��̒�o�����߂���B
�e���Z���g���^�c���� WeChat �͂��łɂ���ɉ����Ă��邽�߁A���{�̂��n�t�����`�ŁAWeChat �� ID �����{�֘A�̃T�[�r�X�ŗ��p�\�ɂȂ��Ă���B�@����ŁA����̖��߂̓E�F�C�{�[�ɓ���˂����邱�ƂɂȂ�B�@�E�F�C�{�[�͍�N�̑� 3 �l�������_�� 3 �� 7,600 ���l�̌��ԃA�N�e�B�u���[�U�[�����A���E�ő�̃~�j�u���O�T�[�r�X���B�@�������A�E�F�C�{�[�͌��݁AWeChat �Ƃ̐킢�ɋ�킵�Ă���A���テ�[�U�[������������̂͊ԈႢ�Ȃ����낤�B (Emma Woollacott�AForbes = 2-5-18)
������ iClound �É_�@�A�b�v���A������Ƃɉ^�c�ڊ�
�ăA�b�v���� 2 ��������N���E�h�T�[�r�X�̒����ł̉^�c�𒆍���ƂɈڊǂ��邱�Ƃ����߁A�u�v���C�o�V�[���N�Q�����v�ȂǂƗ��p�҂����O�����߂Ă���B�@�����ɂ́A�l�b�g���[�N�̉^�c�҂ɑ��āA�ƍߑ{���ւ̎x���E���͂��`���Â���@�������邩�炾�B
�A�b�v���͎��Ђ̃X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�^�[���A�p�\�R���Ȃǂ�ʂ��A������ʐ^�A����Ȃǂ��l�b�g��ɕۑ��ł���uiCloud �i�A�C�N���E�h�j�v�Ƃ����T�[�r�X�𐢊E�ōs���Ă���B�@�A�b�v���� 2 �� 28 ������A�����ł̃T�[�r�X��n����ƂɈڊǂ���B�@������ 2017 �N�Ɏ{�s�����l�b�g���S�@�ŁA�����ŏW�߂��f�[�^�������̃T�[�o�[�ɕۑ�����悤�`���Â������߂��B�@����ɂ���āAiCloud �̐ݒ�ŁA���p�����u�����v�ɂ��Ă���l�̃f�[�^�́A���ׂĒ��������ɕۑ������B
�����̗��p�҂����O���Ă���̂́A�T�[�r�X���n����ƂɈڊǂ���邱�ƂŁA����l�b�g��ɕۑ������f�[�^���������{�ɒ���邩������Ȃ��Ƃ����_���B�@�l�b�g���S�@�́A�l�b�g���[�N�̉^�c�҂ɔƍߑ{���ւ̎x���E���͂Ȃǂ��`���Â��Ă���B (�k�� = ���c���V�A�T���t�����V�X�R = �{�n�䂤�Aasahi = 1-17-18)
�����A2017 �N�� 12 �� 8,000 ���́u�L�Q�v�T�C�g��� = �V�؎�
�m��C�n �������{�� 2017 �N�ɕ������u�L�Q�v�T�C�g�� 12 �� 8,000 ���ɏ�邱�Ƃ��킩�����B�@�V�؎Ђ� 8 ���A���{���\�f�[�^����ɕ��B�@�ɂ��ƁA3,090 �����̈�@�o�ŕ��� 2017 �N�ɉ�������A1,900 �l���Y���ɏ����ꂽ�Ƃ����B�@�������{�́u�Љ�̈��萫�v���ێ����邽�߂̎{��̈�Ƃ��āA�C���^�[�l�b�g�E�R���e���c�ɑ���K�����������Ă���B�@�܂��w��̐��E�ɂ�����K�������̈�Ƃ��āA�C�O���f�B�A�ɑ��A�`�x�b�g���p�A1989 �N�̓V���厖���ȂǂɊւ�������f�ڂ����@�������Ȃǂւ̃A�N�Z�X���~���Ă���B (Reuters = 1-9-18)
"�l�b�g����" �����̒������u���E�C���^�[�l�b�g���v�@�T�C�o�[��Ԃ̎哱���_��
�y�k�� = �����R�́z �������c�V�؎ВʐM�ɂ��ƁA���]�ȋˋ��s�G���� 3 ���A�u�� 4 �E�C���^�[�l�b�g���v���J�������B�@�K�ߕ����Ǝ�Ȃ͏j�ꃁ�b�Z�[�W�Łu���E�̃C���^�[�l�b�g�Ǘ��V�X�e���̕ϊv�͏d�v�Ȏ����ɓ���A�w�T�C�o�[��ԉ^�������́x�̍\�z�͍��ێЉ�̍L�͂ȋ��ʔF���ɂȂ��Ă���v�Ǝ咣�����B�@�����̓C���^�[�l�b�g�̋K����啝�ɋ����� "�l�b�g������" ��i�߂����ŁA���ۓI�ȃT�C�o�[��Ԃ̎哱�������낤�Ƃ��Ă���B
�K���́A���Z�p�̔��W�͌o�ς�Љ���W���铮�͂ƂȂ����Łu�e���̎匠����S�A���W���v�ɑ����̒���������炵�Ă���v�Əq�ׁA�������T�C�o�[�U���̔�Q�҂Ƃ̗�����ɂ��܂�����Łu�T�C�o�[�匠�v�̑��d��i�����B�@�������ǂ́A�l�b�g��̌��_���̐��ւ̋��ЂƂȂ邱�Ƃ��x�����āu�T�C�o�[��Ԏ匠�v�Ȃ�T�O��W�Ԃ��A���N�ɓ���u�T�C�o�[�Z�L�����e�B�[�@�v��u�l�b�g�j���[�X���T�[�r�X�Ǘ��K��v�ȂNjK���⌟�{�̍����ƂȂ�@�߂����X�Ɛ����B�@�܂����t�[�E�W���p���ȂLjꕔ�|�[�^���T�C�g�̌����@�\���g���Ȃ�������A�����̓��{���f�B�A�̃T�C�g���{���ł��Ȃ������肷��ȂǁA�l�b�g��� "��" ����w���łȂ��̂ɂ��Ă���B
�V�؎Ђɂ��ƁA�C���^�[�l�b�g���ɂ͉����i= �����Ɍ˂̉���)�W�J�E�����Ǐ햱�ψ����o�Ȃ����ق��A80 �J���ȏ�̐��{��\����֘A��Ƃ̊������ 1,500 �l���Q�������B�@�������Ď�v���̍������ƌo�c�҂�̏o�Ȃ͏����ɂƂǂ܂����B (sankei = 12-3-17)
�����u�l�b�g�̍c��v�A�d��ȋK���ᔽ�̗e�^�Ŏ�蒲��
�������Y�}�̒����K�������ψ���� 21 ���A���f�B�A�Ǘ���}�̐�`�H�������}������`���̘D���i= �̂̐l�̑ւ��ɉΕj�E�O���������u�d��ȋK���ᔽ�v�Ŏ�蒲�ׂĂ���Ɣ��\�����B�@�D���͌������l�b�g�K����i�߂����ƂȂǂ���A�l�b�g���p�҂̊Ԃł́u�C���^�[�l�b�g�̍c��v�ٖ̈��ŌĂ�Ă����B�@�D���͍��c�V�؎ВʐM�̕��В��Ȃǂ��o�āA�C���^�[�l�b�g�Ǘ�������u���ƃC���^�[�l�b�g���ٌ����v�̎�C�Ȃǂ��C�B�@����̏ڂ����e�^���e�͕s�������A10 ���̓}�����o�ăX�^�[�g���� 2 ���ڂ̏K�ߕ��i�V�[�`���s���j�w�������������������s��i�߂�p����N���ɂ����`���B (�k�� = �������Aasahi = 11-22-17)
�A���o�o�u�Ɛg�̓��v�Z�[���A����z 2.8 ���~��
�y��C = �����q�A�������z �����C���^�[�l�b�g�ʔ̍ő��A�A���o�o�W�c�� 11 ���A��K�͂ȁu�Ɛg�̓��v�Z�[�����J���A����z�� 1,682 �����i�� 2 �� 8 �牭�~�j��˔j�����B�@2016 �N�� 24 ���Ԃł̎��т͖� 1,200 �����������B�@����̐���オ�肾���łȂ��A�u�A���o�o�E�G�t�F�N�g�v�͌l�����Z�p�v�V�̕��i��傫���ς��Ă���B�@�u�Ɛg�̓��v�Z�[���͖��N 11 �� 11 ���ɊJ�ÁB�@�P�g�҂�A�z������u1�v�����Ԃ��Ƃ�R���Ƃ��Ă���B�@11 �� 1 ������A���o�o�Ɠ����悤�ȃZ�[������|����l�b�g�ʔ� 2 �ʁA�����W�c�������A������z�� 1 �牭����˔j�����Ɣ��\�����B
�ȒP�ɃX�}�[�g�t�H���i�X�}�z�j�Ŕ��������ς܂����钆���B�@�u�Ɛg�̓��v�Z�[���̑O�ɁA�����ɓ��{�o�ϐV����C�x�ǂŏ{�̏�C�K�j�ƃA�C�X�A�����A�X�^�[�o�b�N�X�̃R�[�q�[�Ȃ� 230 �����𒍕����Ă݂��B�@�� 30 ����A��z�����R���r�j�G���X�X�g�A��X�^�o�ɕ���Ŕ����������ƃR�[�q�[�������B�@���� 10 ����A�A���o�o���o�����鐶�N�H�i�x���`���[�uᴔn�i�t�[�}�[�j�N���v�̑�z�����͂��Ă��ꂽ�J�j�͐������܂܂ŁA�R�[�q�[���M���B�@�x�����̓A���o�o�̃X�}�z���ρu�A���y�C�v�B�@�萔���̓t�[�}�[���Ȃ��A�����ƃR�[�q�[�� 16 �����B
�������� 1 ���P�ʂł������ł���X�}�z���ς͋N�ƉƂ����̃A�C�f�A���}�l�^�C�Y�i�������j�ł���d�v�Ȋ�ՁB�@�V�����T�[�r�X��Z�p�ނӉ��킾�B�@���]�Ԃ�P�ȂǃV�F�A�r�W�l�X�ޏz�����A�x���`���[��Ƃւ̓����z�� 12 �N�� 460 �������� 16 �N�� 1,300 �����ɑ������B
�����u�A���o�o�E�G�t�F�N�g�v�͗e�͂Ȃ������^�X�܂��쒀����B�@6 ���A�ɔJ�ȑ�A�ŘV�ܕS�ݓX�A�V���E�S�݂����������A�u�W�q���u�v�����������ʁA���͂̓X�����ǂ��悤�ɕ��u���ԂɃV���b�^�[�X�Ɖ������B�@�l�b�g�ʔ̖̂� 6 ���͌��͎��X�܂̔���グ�������Ƃ����B�@�S�ݓX�Ȃ� 16 �N�ɂ͏��Ȃ��Ƃ� 70 �̑�^�X�����B�@�`�F�[���W�J���鏬���X�܂̌ٗp�҂� 245 ���l�� 12 �N�ɔ�ׂ�� 8 ���l�������B�@���J���t�[���Ȃǂ��Ă̏����g���Ō�̉��A���N����܂Ńl�b�g�ɒD������B (nikkei = 11-11-17)
���� E �R�}�[�X 2 �ʂ̕x���A�Ȃ� 24 �u�l�b�g�̏����v
������ E �R�}�[�X�s��ŃA���o�o�Ɏ����� 2 �ʂ� JD.com �i��������j�𗦂���̂́A43 �̃��`���[�h�E���E���B�@�ނ� 24 �̍Ȃ̃i���V�[�E�`�����́AJD �� "�`�[�t�E�t�@�b�V�����E�A�h�o�C�U�[" �߁A���Ђ̕x�T�w�����r�W�l�X�ɐ[���ւ���Ă���Ƃ����B�@���`�̃��O�W���A���[���f�B�A�uHong Kong Tattler�v���`�����B�@��l�����������̂� 2015 �N�̂��ƂŁA����ȗ��`������ JD �̎��Ɛ헪�Ɋւ��A�h�o�C�X���s���Ă����B�@Tattler �ɂ��� JD �͒����̕x�T�w�����}�[�P�b�g�ŁA�}�����𐋂��Ă���Ƃ����B
JD �̓t�@�b�V�����ƊE�ւ̓����������������Ă���A���N�ɓ��� 3 �� 9,700 ���h���i�� 450 ���~�j�� E �R�}�[�X�T�C�g�uFarfetch�v�ɏo�������B�@���� 2 �N�œ��Ђ̓j���[���[�N��~���m�A�����h���A�k�����C�Ńt�@�b�V�����V���[���J�Â��A�V���ƕ��́uJD �t�@�b�V�����v���J�݂����B�@JD �t�@�b�V������ 2017 �N�A�A���}�[�j��X�����t�X�L�[�A�[�j�X�Ƃ��������ۓI�u�����h�� E �R�}�[�X�̔����J�n�����B
�`�����͒����� SNS �E�̃X�^�[�ŁA���N�O�Ƀ~���N�e�B�[����ɂ����ޏ��̉摜���l�b�g�Ɋg�U���A"�~���N�e�B�[�o����" �Ƃ̃j�b�N�l�[���ŌĂ��悤�ɂȂ����B�@�ŋ߂͊e���� JD �t�@�b�V�����̃C�x���g�̊���ɂ��Ȃ��Ă���B�@�ޏ��� JD �O���[�v�P���̃x���`���[�L���s�^�� TQ Capital �̖����߁A���E�Ƃ̊Ԃɂ͍�N�A�������܂ꂽ���肾�� Tattler �͓`�����B�@���E�̎��Y�z���t�H�[�u�X�� 98 ���h���i1.1 ���~�j�Ɛ��肵�A���E�� E �R�}�[�X�ƊE�ōł��x�T�Ȑl���̈�l�Ƃ��Ă���B
JD �̔��s������ 15.8% �̓��E���ۗL���A�č��̃E�H���}�[�g�� 10.1%�A�e���Z���g�� 18.1% ��ۗL���Ă���B�@���E�͉�Ђ̊����c������ 80% ���x�z���ɒu���B�@�x�T�w�}�[�P�b�g�� JD �̋����� Secoo Holding �� 9 ���Ƀj���[���[�N�،�������� IPO ���ʂ����A1 �� 1,000 ���h���i�� 124 ���~�j�B�����B�@Secoo �ɂ� IDG �L���s�^���⒆�������ی��炪�����𒍂��ł���B (Russell Flannery�AForbes = 10-8-17)
���� �l�b�g��� 3 �� ���u���K���s�\���v�Ŕ���
�������ǂ́A�����ł̃c�C�b�^�[�� LINE �Ȃǂɂ��ăf�}��|���m�Ȃǂ̕s�K�ȏ�\���ɋK������Ă��Ȃ��Ƃ��ăC���^�[�l�b�g��� 3 �Ђɔ������Ȃ��s���������������Ɣ��\�� 10 ���̋��Y�}�����T���l�b�g��̌��_���������߂Ă��܂��B�@�����̖k���Ɠ암�E�L���Ȃ̃C���^�[�l�b�g�Ǘ����ǂ́A25 ���A�����Ńc�C�b�^�[�́u�E�F�C�{�[�v�ƒ����� LINE �́u�E�F�C�V���v�A����ɍő��̌����T�C�g�u�o�C�h�D�v�̌f�������ꂼ��^�c����l�b�g��� 3 �Ђɑ��āA���Ƃ� 6 ���Ɏ{�s���ꂽ�C���^�[�l�b�g���S�@�Ɉᔽ�����Ƃ��āA�������Ȃ��s���������������Ɣ��\���܂����B
���\�� 3 �Ђ����p�҂����M����f�}��|���m�A�e���ȂǂɊւ�������\���ɋK�����Ȃ������Ƃ��Ă��ē��ǂ́A�e�ЂɊǗ��ӔC���ʂ����悤���߂��Ƃ��Ă��܂��B�@�����ł͓��ǂ��V����e���r�̓��e���K�����Ă��邱�Ƃ������āA�l�b�g�オ�����Ȃ��ӌ��\���̏�ƂȂ��Ă��܂����A�������݂����{�⋤�Y�}�ɂƂ��ēs���̈������e�ƌ��Ȃ����Ύ��X�ƍ폜����Ă��܂��B�@����A��� 3 �Ђ������������ƂŃC���^�[�l�b�g�e�Ђ��A����A���p�҂̔��M���e�𐧌����铮�������߂邱�Ƃ��\�z����Ă��āA10 �� 18 ���Ɏn�܂� 5 �N�� 1 �x�̋��Y�}�����T���������ǂ̓l�b�g��̌��_���������߂�p���m�ɂ��Ă��܂��B (NHK = 9-26-17)
���@���@��
���� �l�b�g�������݂Ɏ����o�^�`����
�������{�̓C���^�[�l�b�g��̃R�����g�̏������݂ɂ��āA���p�҂Ɏ����̓o�^���`���Â��邱�ƂȂǂ荞�V���ȋK��\���A�l�b�g�̊Ǘ�������i�߂�p����N���ɂ��Ă��܂��B�@�������{�́A�C���^�[�l�b�g�̃j���[�X�T�C�g�⓮��z�M�T�C�g�A�g�ѓd�b�̃A�v���Ȃǂł̃R�����g�̏������݂ɂ��āA���Ƃ� 10 ������{�s����V���ȋK��� 25 ���ɔ��\���܂����B
����ɂ��܂��ƁA���p�҂͂���܂łǂ���C���^�[�l�b�g��œ����ŏ������݂��ł�����̂́A�T�C�g��A�v���̉^�c��ЂɎ��O�Ɏ�����o�^���邱�Ƃ��`���Â����܂��B�@�܂��^�c��Ђɂ́A�������݂̓��e����@���Ɣ��f���ꂽ�ꍇ�A�������݂��ł��Ȃ��Ȃ�悤�ɂ���Ȃǂ̑[�u����邱�Ƃ����߂Ă��܂��B�@�����ł͑����̐l�X���l�b�g��ňӌ��\������j���[�X�ւ̕]�_���q�ׂ��肵�Ă��܂����A���{�ɓs���̈������e���������܂��P�[�X������A�������{�Ƃ��Ă͖�肪����Ɣ��f�����ꍇ�Ɍl����肵�A���₩�ɑΉ��ł���d�g�݂𐮂���_��������ƌ����A�l�b�g�̊Ǘ�������i�߂�p����N���ɂ��Ă��܂��B (NHK = 8-26-17)
���@���@��
�������ǁ@�l�b�g��� 3 �Ђ��@�u���M�v�A�u�����v�A�u�S�x�v�C���^�[�l�b�g���S�@�ᔽ�̋^��
�}���O�Ɍ��_�K������
�����̍��ƃC���^�[�l�b�g���ٌ����� 11 ���A������ LINE �́u���M�v�⒆���Ńc�C�b�^�[�́u�����v�A�����l�b�g�����T�C�g�u�S�x�v�̌f����ΏۂɁA�C���^�[�l�b�g���S�@�ᔽ�̋^���ŁA�^�c���̃l�b�g��� 3 �Ђ����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B�@���ٌ����́u�e����f�}�A�|���m�ȂǍ��ƁE�����̈��S��Љ���Ȃ������L�߂郆�[�U�[�����݂��A�Ǘ��`����ӂ��Ă���v�Ǝw�E�����B�@�����ł͏H�̒������Y�}����O�ɁA�l�b�g��̌��_�K������������Ă���B (�k���E���{�Ӗ�Asankei = 8-11-17)
�����Ń��t�[�������g�p�s�\�Ɂ@�l�b�g�Ǘ����i����
������ 22 ���܂łɁA�u���t�[�W���p���v�̃l�b�g�����@�\���g���Ȃ��Ȃ��Ă���B�@�����ł͕ăO�[�O���ւ̐ڑ��͎Ւf����Ă��邪�A���t�[�W���p���̌����̓O�[�O���̋@�\���g���Ă���B�@���̂��߁A�O�[�O���ւ̐ڑ��́u�������v�ɂȂ��Ă���Ƃ���A�����̃l�b�g�Ǘ����ǂ� 10 ���̋��Y�}����O�ɁA�Ǘ������i�ɂ��Ă���Ƃ݂���B�@���t�[�W���p���́u�����������猟���T�[�r�X�����p�ł��Ȃ���c�����Ă��邪�A�T�[�r�X�̕s���g���u���ł͂Ȃ��v�Ƃ��Ă���B (�k�� = ���c���V�Aasahi = 9-22-17)
�����������l�喳�l�G���A�ŏ��̃C���^�[�l�b�g�ڑ�������
�C�Ȃɂ�������i�t�t�V���j���R�ی����̍���B���ی�X�e�[�V������ 8 �� 29 ���ߌ�A�q���ʐM�Œ�X�e�[�V�����������ɃI�[�v�������B�@����������āA�����͒����ɂ�����l�喳�l�G���A�̂Ȃ��ŁA�ŏ��ɃC���^�[�l�b�g�̐ڑ��������������G���A�ƂȂ����B
�����̓����S����Łu�����������v�Ƃ����Ӗ��ŁA�C�ȓ쐼���̋ʎ��`�x�b�g�������B���ɂ���A���̖ʐς� 4.5 �������L�����[�g���A�����Ō��ݍő�K�͂��ւ閳�l�G���A���B�@�G���A���ɂ͐������̊Ȗ쐶�̓��A�����W�܂��Ă���A��Ŋ뜜��̃`���[��ی삷�邱�Ƃ�ړI�ɏ��߂Ē����ɐ݂���ꂽ���Ƌ����R�ی��ł���A�����̐������l����ی삷�邽�߂ɐ݂���ꂽ 11 �J���̊j�S�G���A�̈�ł�����B
���N�ɂ킽��A�]���̒ʐM�l�b�g���[�N�̕~�݂͉����ł̎���������A�쐶���A���̕ی��Ƃ�W�J�����ł��ʐM�ʂł̐��������B�@�������A�q���ʐM�Œ�X�e�[�V�����I�[�v����́A����B���ی�X�e�[�V�����̎��� 500 ���[�g������ 1 �L�����[�g���͈̔͂ŃC���^�[�l�b�g�ւ̐ڑ����\�ƂȂ�A�q���e���r�≓�u�r�f�I�ʐM�Ȃǂ����p�\�ƂȂ�B
�������Ƌ����R�ی��Ǘ��ǐX�ь����Ǖ��ǒ��̗����C���́A�u�q���ʐM�Z�p�Ɋ�Â��C���^�[�l�b�g�`���A���ʃV�X�e���������G���A���̕s����A��T�A�ܓ����A�����͂Ƃ����� 4 �����̕ی�X�e�[�V�����A�y�ѕی��̊e�o������Əd�v�ϑ��X�|�b�g�Ɏ��X���������\�肾�B�@���̐搔�N�ԂŁA�����̊e�ی�X�e�[�V�����őS�ʓI�ȃR�l�N�e�B�r�e�B�����������A���h�~��~���Ȃǂ̓���Ɩ��ɂ�葽���̃T�|�[�g��Z�p�ʂł̃T�|�[�g�����҂ł���v�Ƃ����B
���N 7 �� 7 ���ɂ̓|�[�����h�N���N�t�ŊJ�Â��ꂽ�� 41 �E��Y�ψ����c�ŁA���������E���R��Y�Ƃ��ēo�^����A�������ɂ͐��E���R��Y�[���̗��j�ɖ�������B (�����E�l���� = 8-31-17)
���������i EC �T�C�g Xiu.com �n�ƎҁA���A�̋^���őߕ�
�m��C�n �����A���i�����������̓d�q����� (EC) �T�C�g�uXIU.com �i���G�ԁj�v�̑n�Ǝ҂ł���I���������A4 �� 3,800 �����i6,567 ���h���j�����̖��A���̋^���őߕ߂��ꂽ�B�@���c�p�����`���C�i�E�f�C���[�� 21 ���A�Ŋ֓��ǂ̘b�Ƃ��ĕ��B�@�I���̓C���h�l�V�A�Őg�����S������A�����ɑ��҂��ꂽ�B�@�ېł�邽�߁A���Ăōw�����������ߗ��i���l�̉ו����č��`�o�R�Ŗ{���Ɏ����������Ƃ����^����������Ă���B
Xiu.com �� 20 ���ɐ����\���A���Ђ̈ꕔ�Ј������A�Ɋւ�������Ƃ�F�߂��B�@�c�Ƃ͕���ʂ�p�����Ă���Ƃ����B�@�I���͍�N 5 ���A���A�̌��^����������������ɒ������o�����Ă���A���یY���x�@�@�\�i�C���^�[�|�[���j�́u�Ԏ�z���v�ƌĂ�鍑�ێ�z���s���đߕ߂��w���B�@������{�A�C���h�l�V�A�x�@�������̐g�����m�ۂ��Ă����B (Reuters = 8-21-17)
�����ŃC���^�[�l�b�g�ٔ����J�� �_���͐v���ȉ���
�C���^�[�l�b�g�̕��y�ɔ����đ�������l�b�g�ʔ̂⒘�쌠���߂���g���u���ɑΏ����悤�ƁA�����ł́A�����҂��ٔ����ɏo�삵�Ȃ��Ă��R�����ł���C���^�[�l�b�g�ٔ�����V���ɊJ�݂��A���ǂ́A�v���ȕ����̉����ɂȂ���ƃA�s�[�����Ă��܂��B�@�������c�̐V�؎ВʐM�Ȃǂɂ��܂��ƁA�����Ńl�b�g�ʔ̍ő��́u�A���o�o�v�Ȃǂ��{�Ђ�u�����]�ȍY�B�ŁA18 ���A�V���ɃC���^�[�l�b�g�ٔ������J�݂���܂����B
���̍ٔ����́A�l�b�g�ʔ̂�l�b�g���Z�A����Ƀl�b�g��ɓ��e���ꂽ���Ђ�f�����߂��钘�쌠�̃g���u���ȂǁA�C���^�[�l�b�g�Ɋւ�閯���ƍs���̍ٔ��̐R�����s���܂��B�@18 ���͏�����Ƃ��A�݂�����̏�������@�Ƀl�b�g��Ō��J���ꂽ�Ƃ��āA�����̑�� IT ��Ƃ�i�����ٔ��̐R�����e���r�d�b�ōs���A���̗l�q���n�����f�B�A�Ɍ��J����܂����B
�C���^�[�l�b�g�ٔ����ł̍ٔ��́A�l�b�g��Ŏ葱����R�����s�����߁A���n���f�B�A�́A��Q�����l���������ꂽ���Ƃ�i����ꍇ�ł���p���������ނƓ`���Ă��܂��B�@�����ł́A�l�b�g�ʔ̂Ȃǂ̕��y�ɔ����ăC���^�[�l�b�g�Ɋւ��g���u�������������Ă���A���ǂ́A�V���ȍٔ����̒a�����v���ȕ����̉����ɂȂ���ƃA�s�[�����Ă��܂��B (NHK = 8-19-17)
�t�F�C�X�u�b�N�A�����Ŏʐ^���L�A�v���@�Ď���
�y�V���R���o���[ = �����Y��Y�z �ăt�F�C�X�u�b�N������Ƃ�ʂ��Ђ����Ɏʐ^���L�A�v���𒆍��Œ��n�߂��ƕĎ��j���[���[�N�E�^�C���Y�����B�@�ăO�[�O���� 3 �������璆���Ŗ����|��A�v���̒��n�߂Ă���B�@�������Y�}���H�̓}���Ɍ����l�b�g�K������������Ȃ��A�ăl�b�g���ɂƂ��Č��n�ł̖{�i�I�ȃT�[�r�X�W�J�͕s�\�ɋ߂��B�@�����A�������̔����T�[�r�X��ʂ��A�����i�o�̑������肾���ł���낤�Ƃ��Ă���B
�����ł͐ڑ��ꏊ���B���\�t�g�̗��p����A���`�ȂLjꕔ�n������� 2009 �N����t�F�C�X�u�b�N�͗��p�ł��Ȃ��B�@���ЎP���̃C���X�^�O������ 14 �N�ȍ~�Ւf����Ă���B�@�P���̑Θb�A�v���A���b�c�A�b�v�� 7 ���ȍ~�A�ʐ^�⓮�悪����ɂ�����Ԃɂ����A���p�҂͌����Ă���B�@�����A�Đi�o��ڎw���}�[�N�E�U�b�J�[�o�[�O�ō��o�c�ӔC�� (CEO) �͒�������w�K���A�J��Ԃ��K�����Ċw���ƌ𗬂���ȂǏH�g�𑗂��Ă����B�@�������{���v�����鎩�匟�{�ɑΉ�����\�t�g���J�����Ă���ƌ����Ă���B
�����ł͔����{�^���Ȃǂ������܂邽�߁A�\�[�V�����ȃT�[�r�X�̗��p�Ɏ��������B�@�����̌ڋq�f�[�^�������f�[�^�Z���^�[�͒��������ɐݒu���邱�Ƃ����߂Ă���B�@�A�b�v���͂���ɏ]���A�f�[�^�Z���^�[�̐ݒu�����߂��B (nikkei = 8-13-17)
�����l�b�g��Ə�� 100 �� ���グ���� 1 ��������
�X�}�[�g�t�H���̕��y�Ńl�b�g�ʔ̂�d�q���ςƂ������T�[�r�X���}���Ɋg�債�Ă��钆���ŁA�C���^�[�l�b�g�֘A��Ə�� 100 �Ђ̔���グ�̍��v���A���N���߂� 1 ���l�����̑��������Ƃ��킩��܂����B�@������ IT ���������H�Ə�Ȃ̔��\�ɂ��܂��ƁA�C���^�[�l�b�g�֘A��Ə�� 100 �Ђ̔���グ�̍��v�����N�A1 �� 700 ���l�����i���悻 18 ���~�j�ɒB���܂����B�@����͑O�̔N�� 46.8% ����A���߂� 1 ���l�����̑����܂����B
�����ł̓X�}�[�g�t�H���̕��y�ɔ����A�l�b�g�ʔ̂�d�q���ρA����Ƀl�b�g�ɂ��z�ԃT�[�r�X�Ȃǂ��}���ɍL�܂��Ă��܂��B�@��ʂɂ̓l�b�g�ʔ̍ő��́u�A���o�o�v��ASNS ��d�q���σT�[�r�X�����u�e���Z���g�v�Ƃ�������Ƃ�����A�ˁA��� 5 �Ђ̔���グ���S�̂̔����ȏ���߂Ă��܂��B�@����������Ƃ́A�����郂�m���C���^�[�l�b�g�ƂȂ� IoT ��AAI = �l�H�m�\�̊J�����ϋɓI�ɐi�߂Ă��āA���\�ɂ��܂��ƁA��[����ւ̓������O�̔N�ɔ�ׂ� 30% �߂��L�т܂����B
�挎�ɂ͌����T�C�g���^�c���锄��グ 3 �ʂ́u�S�x�v�ƃ}�C�N���\�t�g�Ђ������^�]�̋Z�p�Œ�g����Ɣ��\���Ă��āA����̓T�[�r�X�����łȂ���[����ł�������Ƃ̑��݊�����w�������Ƃ��\�z����܂��B (NHK = 8-4-17)