�������s�̔��z�⏕��v���~�A���t���H�����A7 �����{�J�n�� �c �\�Z 1.7 ���~�m��
���{�� 25 ���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��őŌ����Ă���ό��Ƃ���H�ƌ����̎��v���N��ɂ��āA7 �����{������{������j���ł߂��B�@�������s�̑���̕⏕����H�X�Ŏg����N�[�|�����ȂǂɌv�� 1.7 ���~�̗\�Z���m�ۂ��Ă���A�Ɛт̉ɂȂ���B
���N��́uGO TO �L�����y�[���v�Ƃ̖��̂ŁA�������s�̑���z�⏕�i1 ��������ő� 2 ���~�j����ق��A�y�Y���X�ȂǂŎg����N�[�|�����s����B�@���H�X�����̃v���~�A���t���H�����̔��s��A�C�x���g�`�P�b�g�̊����Ȃǂ����{����\�肾�B�@���{�� 25 ���ɋً}���Ԑ錾��S�ʓI�ɉ������A��{�I�Ώ����j�ŁA�O�o���l�� 7 �������܂łɒi�K�I�Ɋɘa����v��荞�ތ��ʂ����B�@����A���Ǝ҂◘�p�҂Ɏ��m���A�ċx�݂̗��s�V�[�Y���ɍ��킹�Ď��{�ł���悤������i�߂�B (yomiuri = 5-25-20)
�ً}���Ԑ錾�����Łu���₩�ɗv���ɘa�v�@���r�m���
�Â��K�͂�o�Z���A�i�K�I�Ɋɘa�@�s�̃��[�h�}�b�v�ڍ�
�����s�� 22 ���A�V�^�R���i�E�C���X�Ή��ɔ����x�Ƃ�Z�k�c�Ƃ̗v���̊ɘa�s���� 3 �i�K�Ŏ��������s�́u���[�h�}�b�v�v�̏ڍׂ\�����B�@�ŏ��́u�X�e�b�v 1�v�ł́A�����ق���p�فA�}���فA�ϋq�ȕ������̂����̈�ق␅�j��Ȃǂ̉^���{�݂��ɘa����ق��A���H�X�̉c�Ǝ��Ԃ͌��s�̌ߌ�8������ߌ� 10 ���܂łɉ�������B�@���r�S���q�m���� 22 ���̋L�҉�Łu���ً̋}���Ԑ錾�����������A���₩�ɃX�e�b�v 1 �ɓ����Ă����v�Ɩ����B�@���ɍ��� 25 ���ɐ錾�̉����f�����ꍇ�A26 ���ߑO 0 ���Ɋɘa���J�n���錩�ʂ��ł��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B
����A�������X�N�������Ƃ����ڑ҂����H�X��C�u�n�E�X�A�J���I�P�X��X�|�[�c�W���Ȃǂ͊ɘa�̂߂ǂ������Ă��Ȃ��B�@�s�͊����̑� 2 �g�ւ̔����Ƃ��āA�x�ƂȂǂ��ėv�����鐔�l�����u�����A���[�g�v��������j���B�@�A���[�g���������ꂽ�ۂ͂����̃��C���{�[�u���b�W��ԐF�ɓ_������Ƃ����B
�s�� 15 ���A���[�h�}�b�v�̍��q�����\�B�@�V���Ȋ����҂� 1 �� 20 �l�����i1 �T�ԕ��ρj�ɂȂ�ȂǎO�̐��l������A�v����i�K�I�Ɋɘa������j�������Ă����B�@�s���ł͊����Ґ��͌����X���ɂ���A21 ���Ɋm�F���ꂽ�����҂� 11 �l�������B�@�����ً}���Ԑ錾�̉������������Ă��� 25 ���ȍ~�̊ɘa�������ށB�@22 ���ɔ��\�������[�h�}�b�v�̏ڍהłł́A�u�X�e�b�v 1�v�̑ΏۂɁA����܂Ŏ����Ă��������ق�}���قɉ����A�̈�ق␅�j��A�{�E�����O��i��������ϋq�Ȃ͎g�p��~�j�Ȃǂ荞�ށB
�u�X�e�b�v 2�v�͊w�K�m�⌀��A�f��فA���Ǝ{�݂ȂǁA�u�X�e�b�v 3�v�ɂ̓l�b�g�J�t�F�▟��i���A�p�`���R�X��Q�[���Z���^�[�Ȃǂ�����B�@�C�x���g�̎Q���l�����i�K�I�ɒ��A50 �l�i�X�e�b�v 1�j�A100 �l�i�X�e�b�v 2�j�A��l�i�X�e�b�v 3�j�Ƃ���B�@�Z�k�c�Ƃ�v�����Ă�����H�X�ɂ��ẮA�X�e�b�v 1 �̒i�K�Ō��s��� 2 ���Ԓx���ߌ� 10 ���܂łɉc�Ǝ��Ԃ���������B�@��ނ��������܂Œł���悤�ɂ���B�@�X�e�b�v 3 �̒i�K�ł́A�c�Ǝ��Ԃ��ߑO 0 ���܂ʼn����B
�s�����Z�ł́u���U�o�Z�v�����A�i�K�I�ɍĊJ���Ă����B�@�X�e�b�v 1 �͓o�Z���T�� 1 ��A�ݍZ�� 2 ���Ԓ��x�Ƒz��B�@�w�Z�ƃI�����C���ł̎��Ƃ̑g�ݍ��킹��ڎw���B�@���̌�́u�T 2 - 3 ���v�A�u�T 3 - 4���v�ƒi�K�I�ɓo�Z�𑝂₵�A�ݍZ���Ԃ��u�����v�A�u1���v�Ɖ����Ă����B�@�o�Z���̑̉������A���ƒ��͐��k���m�̋����� 1 - 2 ���[�g���قNJm�ۂ���Ƃ���������Ƃ�Ƃ����B�@���r�m���� 22 ���A�w�Ɂu�����g��̏����Ȃ���A����ƌo�ςƂ������Ƃ��l���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�Əq�ׂ��B
�x�Ɨv���̊ɘa�X�e�b�v���Ƃ̎�ȑΏێ{��
�X�e�b�v 1 : �����فA���p�فA�}���فA��w�⏬���w�Z�Ȃǁi���U�o�Z�Ȃǁj�A* �̈�فA* ���j��
�X�e�b�v 2 : �����ԋ��K���A�w�K�m�A����A�f��فA���|��A�W���
�X�e�b�v 3 : �l�b�g�J�t�F�A����i���A�}�[�W�����X�A�Q�[���Z���^�[�A�p�`���R�X�A�V���n
�@�@�@�@�@�@�@* �͊ϋq�ȕ����͎g�p��~
�����n��ōL����ɘa
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ً}���Ԑ錾���������ꂽ�e�n�ł́A�o�ϊ����̍ĊJ�Ɍ������������L�����Ă���B�@���{�͂܂� 14 ���� 39 ���Ő錾�����������B�@������āA�������͊w�Z��f��فA���Ǝ{�݂Ȃǂɏo���Ă����x�Ɨv�������������B�@�܂��������≮����܂ވ��H�X�ɂ��Ă��A�c�Ǝ��Ԃ̒Z�k�v��������߂��B�@���m���� 15 ������i�K�I�ɋx�Ɨv�����������A19 ���ɂ̓v�[����{�E�����O��ɂ��Ă����������B
21 ���ɐ錾���������ꂽ���A���s�A���ɂ� 3 �{�����A��y�{�݂Ȃǂւ̋x�Ɨv����啝�ɉ������邱�Ƃ����߂Ă���B�@����łǂ̒n��ł��A�����̍Ċg��ւ̌��O�͍������B�@����܂łɃN���X�^�[�i�����ҏW�c�j�������������C�u�n�E�X��ڋq���X�ɂ��ẮA�����∤�m�A�ߋE�̊e�{�������������x�Ƃ����߂Ă���B (asahi = 5-22-20)
�����s�̋x�Ɗɘa�A���� 1 �� 20 �l�����Ȃǂ����
�V�^�R���i�E�C���X�Ή��ً̋}���Ԑ錾�ɔ����x�Ƃ�c�ƒZ�k�v���ɂ��āA�����s�� 15 ���A�V���Ȋ����҂� 1 �T�ԕ��ς� 1 �� 20 �l�����ɂȂ邱�ƂȂǂ���ɁA�i�K�I�Ɋɘa������j���ł߂��B�@���� 21 ���ɂ��S���Ő錾����������\���������Ă��邪�A�s�͑� 2 �g�ɔ����č������͊ɘa���Ȃ����j���Ƃ����B�@���r�S���q�m�����u���[�h�}�b�v�v�Ƃ��āA15 ���ߌ�ɋL�҉���J���Ĕ��\����B
�s�W�҂ɂ��ƁA�s���x�Ɨv����O�o���l���ɘa����w�W�Ƃ��ėp����̂́A�� �V���Ȋ����Ґ��A�� �����o�H���s���Ȑl�̊����A�� �T�P�ʂ̑����䗦�A�� �d�NJ��Ґ��A�� ���@���Ґ��A�� PCR �����̗z�����A�� ��f���k�����ł̑��k���� - - �� 7 ���ځB�@�����o�H���s���Ȑl�̊����ɂ��ẮA50% �����Ȃǂ̖ڈ���݂����B
�ɘa�ɓ��݂���ꍇ�A�i�K�I�Ȏ��{�[�u�Ƃ��Ă܂��͔����ق���p�فA�}���ق�Ώۂɂ���B�@���̌�u�N���X�^�[�i�����ҏW�c�j�����Ȃ� 3 ���ɂȂ�ɂ����{�݁v�ƂȂ錀��̍ĊJ��A���H�X�̉c�Ǝ��ԒZ�k�̈ꕔ���ɘa������Ƃ����B�@�����g��́u�� 2 �g�v�ւ̔����Ƃ��ẮA�w�W�Ƃ��Ďg�������l�� 1 ���ڂł��ɘa�̖ڈ������ꍇ�Ɂu�����A���[�g�v�����A�s���ɑ��Čx�����Ăт�����B�@���̌�A�V���Ȋ����҂� 1 �T�ԕ��ς� 1 �� 50 �l�ȏ�A�����o�H�s���Ȋ����� 50% �ɂȂ�Ȃǂ���A�O�o���l��x�Ƃ��Ăїv������B
�s�́u�� 2 �g�v�ɑ���̐������ɂ����y�B�@�V�^�R���i�O�����g�[������APCR �Z���^�[�̐ݒu���x�������肷��Ƃ����B�@���r�m���� 15 �����A�w�ɑ��u�������������������g���h�~���Ă������Ƃ��s���ɂƂ��Ă��A�����̌o�ςɂƂ��Ă����{�o�ςɂƂ��Ă��d�v�B�@�܂���������Ԃɂ���Ƃ����ӎ������L�������B�v�Ƙb�����B (asahi = 5-15-20)
39 ���ً̋}���Ԑ錾���������F�@���Q�u�����t�������v
���{��14���A�V�^�R���i�E�C���X�Ή��̓��ʑ[�u�@�Ɋ�Â��ً}���Ԑ錾�ɂ��āA�����g��Ɉ��̎��~�߂��������Ă��� 39 ���̉����@�Ɋ�Â�����ψ���Ɏ��₵�A���F���ꂽ�B�@�����A���Q���ɂ��Ă͐V���ɏW�c�������N�����Ƃ��āu�����t�������v�Ƃ���B�@���{�͎���ς̌����܂��A������̑��{���ʼn����𐳎��Ɍ��߂�B
�V�^�R���i�Ή���S�����鐼���N���o�ύĐ����͎���ς̖`���A39 ���́u�������Ó��Ɣ��f�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���v�Əq�ׁA���������߂��B�@39 ���́A�d�_�I�ɑ���u����Ƃ��Ďw�肵�� 13 �́u����x���s���{���v�̂����A���A�ΐ�A�A���m�A������ 5 ���Ɠ���x���ȊO�� 34 ���B�@�����ߌ� 0 ���������A���������L�Ғc�̎�ނɁu����Ăǂ��菳�F���ꂽ�v�Ɠ������B�@��Ë@�ւ� 20 �l���x�̏W�c���������炩�ɂȂ����Ƃ������Q���͎���ςŋc�_����A�����o�H��O�꒲�����A���ɕ���u�����t�������i�������j�v�ŏ��F���ꂽ�Ƃ����B
����ςɐ旧���ĊJ���ꂽ���{�̐��Ɖ�c�ł́A�������M�����J�������u�ً}���Ԃ̉����̍l������������ꂽ�n��̊�����̂�����A�����ĕی����̑̐������A��Ò̐��̊m�ۂȂǂ��c�_�������������v�Ƃ������B�@�������͎Љ�o�ϊ�����i�K�I�ɍĊJ���Ă������߂̎w�j���A81 �̋ƊE�c�̂� 14 �����Ɍ��\���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ����B �W�҂ɂ��ƁA���Ɖ�c�ł́A�ꕔ������������Ȃǂ̃��X�N�ɉ������Ή����K�v���Ƃ��āA�s���{���� 3 �敪����l���������ꂽ�B�@���s�́u����x���v�ɉ����A�u�����g�咍�Ӂv�A�u�����ώ@�v��������B
�u�����g�咍�Ӂv�͓���x���̔������x�̐V�K�����Ґ��ȂǂŊY�����邩�f��������ŁA�s���{�������܂����s�v�s�}�̈ړ���A������ 3 ��������邱�ƂȂǂ����߂�B�@�C�x���g���m�������l�����߂�Ƃ��Ă���B�@�u�����ώ@�v�͐V�K�����҂������x���Ă��u�����g�咍�Ӂv�̊�ɂ͒B���Ă��Ȃ��ꍇ�ŁA��r�I���K�͂ȃC�x���g�̊J�Â��\�Ƃ̍l�����������B�@�u�����g�咍�Ӂv�Ɓu�����ώ@�v�͊e�n�̒m�������f����Ƃ����B
���{��14���ߌ�A����ς̌������Č��߂������𐼑���������ŕ���B�@���̌�A���{�W�O���L�҉���A�����f�������R�Ȃǂ��������B�@���{���ł̐�������͉��ƂȂ�\�肾�B�@�����̍����́A���� 2 �T�ԂŐV�K�����Ґ��������X���ɂ���A�u���� 1 �T�Ԃ̐V�K�����Ґ����l�� 10 ���l������ 0.5 �l�ȉ��v�ȂǂƂ�����̂́A�K�B�̊�Ƃ͂����A��Ò̐��ɗ]�T�����邩�� PCR �����̊g�[�ȂNJe�n��𑍍̏��I�ɔ��f����������B
�Ăъ������}�g�傷�钛�����݂���ꍇ�́A���߂ċً}���Ԃ�錾����l���B�@�����A��̓I�Ȑ��l��͎������A���߂̐V�K�����Ґ���A�����o�H�s���҂̊����Ȃǂ����Ƃɔ��f��������Œ��������B�@���{�͂܂��A39 ���Ő錾�������Ă��A��K�͂ȃC�x���g�̊J�Â�ڋq�����H�X�̗��p�A�錾���p������ 8 �s���{���Ƃ̕s�v�s�}�̉����̎��l�͈����������߂�B
���������₳��Ȃ������k�C���A�����A�_�ސ�A��ʁA��t�A���A���s�A���ɂ� 8 �s���{���͈��������A5 �� 31 ���܂łƂ��Ă���錾���ێ�����B�@��t�⋞�s�͊����Ґ��͌����Ă��邪�A�d������œ����A���Ƃ̂Ȃ��肪�����A�l�̈ړ��������Ɣ��f�����B (asahi = 5-14-20)
����x���ȊO�� 34 �� "�錾�ꊇ����" ����
���{�́A�S���ɏo���Ă���ً}���Ԑ錾�ɂ��āA�u����x���s���{���v�ȊO�� 34 ���ŁA���T 14 ���Ɉꊇ���ĉ������邱�Ƃ��������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B�@�����̐��{�W�҂ɂ��܂��ƁA�u����x���s���{���v�ȊO�� 34 ���̑����ŁA�V�K�����Ґ��̐L�т��}������Ă��邱�ƂȂǂ���A�������܂ł̐錾�̊�����҂����A14 ���Ɉꊇ���ĉ������邱�Ƃ��������Ă���Ƃ������Ƃł��B
�����A�x�R���ȂǐV�K�����҂��ˑR�A������������A14 ���ɊJ�����Ɖ�c�̈ӌ����ӂ܂��čŏI���f���܂��B�@�܂��A13 �́u����x���s���{���v�ł��A�V�K�����҂����Ȃ����͉����ł��邩�������܂��B�@��K�͂ȉ����ɂ��Đ��{���ɂ́A�o�ςւ̉e�����l�����āA�ϋɓI�Ȉӌ����������A�ړ��Ȃǂ̎��l�̓������ɂނ��Ƃ����O���A�T�d�Ȑ�������܂��B (���e�� = 5-11-20)
���{�����l�����֓Ǝ�� �c �z�����Ȃ� 3 ����
���{�̋g���m���m���� 5 ���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g������O�o���l��x�Ɨv���Ȃǂ���������ۂ̓Ǝ��̊�\�����B�@�d�NJ��҂������a���̎g�p���� 60% �����ƂȂ�ȂǎO�̐��l�������A7 ���ԘA���Ŗ������A15 ���ɒi�K�I�ȗv�����������߂���j���B
�{�́A���� 4 ���ɋً}���Ԑ錾�� 5 �����܂ʼn������A�����܂� 13 �s���{�������������u����x���s���{���v�Ƃ������Ƃ��A�{���ւ̊O�o���l�⎖�Ǝ҂ւ̋x�Ɨv���Ȃǂ̑[�u�������Ƃ��Čp������B�@�Ǝ���́A�����g��ɂ���Õ����h�����Ƃ��ŗD��Ƃ��A�o�ϊ����ĊJ�̓����T��u�o���헪�v�ƕ{�͈ʒu�Â��Ă���B�@�g���m���́u�����ǂ�}�����݂Ȃ���A�o�ϊ��������X�ɍĊJ���A�������Ă������Ƃ��d�v���v�Əq�ׂ��B
��́A�q1�r �����o�H���s���ȐV�K�����Ґ��� 10 �l�����A�q2�r PCR ���������ɑ��銴���Ґ��̊����������u�z�����v�� 7% �����A�q3�r �d�NJ��҂̕a���g�p���� 60% �����ŁA���ꂼ�� 7 ���A���Ŗ������K�v������B�@�q1�r �� �q2�r �͂��ꂼ��̓��̒��� 7 ���Ԃ̕��ρi�ړ����ρj�Ŕ��f����B�@4 �����݂ŁA�q1�r �� 7.29 �l�A�q2�r �� 4.5%�A�q3�r�� 33% �ƁA�S�ĉ�����Ă���B�@8 ������ 14 ���܂ł̌��ʂŌ��肵�A������� 16 ���ɉ�������\��������B
����A�v������������Ă��A�x�����̊ɂ݂ȂǂŊ������g�傷��u�� 2 �g�v�����邱�Ƃ����O�����B�@���̂��߁A�{�͍Ăђi�K�I�ɋx�Ɨv���������������B�@7 ���Ԃ̈ړ����ς��A�� �����o�H�s���҂��O�T��葝�����A��萔�ȏ�ƂȂ�A�� �z������ 7% �ȏ� - - �ƂȂ�A�ΏۂƂ���B�@�{�́A������� 7 �����疈���̐��l���z�[���y�[�W�Ōf�ځB�@�������J���邱�ƂŁA�{���Ɋ�@�ӎ��〈�ʂ������L���Ă��炢�₷���悤�ɂ���B
�g���m���́A�x�Ɨv������������ΏۋƎ�ɂ��āu����܂ŃN���X�^�[�i�����W�c�j������������̐ڋq�����Ƃ�A���C�u�n�E�X�ɂ��Ă͐T�d�ɔ��f�������v�Əq�ׁA������Ă������ɉ������Ȃ��l�����������B�@����ȊO�̋Ǝ�́u��{�I�ɉ����̕����ɂȂ�v�Əq�ׂ��B�@�g���m���� 1 ���A�u�����o���헪�������Ȃ��̂Ȃ�A����̒m������������v�Ƃ��āA���l�ʼn��������߂�u��ヂ�f���v����邱�Ƃ�\�����Ă����B (yomiuri = 5-5-20)
������l�̓����A���h�����̓I�����C���@�V���������l��
�V�^�R���i�E�C���X�̑���������鐭�{�̐��Ɖ�c�i���� = �e�c�����E���������nj��������j�� 4 ���A�����̍L������I�ɖh�����߂́u�V���������l���v�̋�̗�����\�����B�@���퐶���̂Ȃ��ŁA���̐����l����S�����邱�ƂŁA�V�^�R���i�����łȂ��A�ق��̊����ǂ̍L������h�����Ƃ��ł��A�������g�����łȂ��Ƒ���F�l��̖�����邱�ƂɂȂ���A�Ƃ��Ă���B�@�S���͈ȉ��̂Ƃ���B (asahi = 5-4-20)
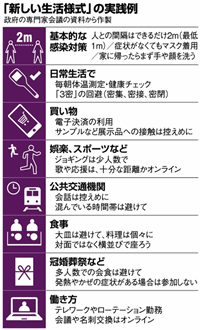
��l�ЂƂ�̊�{�I������
�����h�~�� 3 �̊�{ : �@ �g�̓I�����̊m�ہA�A �}�X�N�̒��p�A�B ���
- �l�Ƃ̊Ԋu�́A�ł��邾�� 2 ���[�g���i�Œ� 1 ���[�g���j��
- �V�тɂ����Ȃ牮����艮�O��I��
- ��b������ۂ́A�\�Ȍ���^���ʂ������
- �O�o���A�����ɂ���Ƃ����b������Ƃ��́A�ǏȂ��Ă��}�X�N�𒅗p
- �ƂɋA������܂������B�ł��邾�������ɒ��ւ���A�V�����[�𗁂т�
- ��� 30 �b���x�����Đ��Ƃ�������Œ��J�ɐi��w���Ŗ�̎g�p���j
* ����҂⎝�a�̂���悤�ȏd�lj����X�N�̍����l�Ɖ�ۂɂ́A�̒��Ǘ�����茵�d�ɂ���
�ړ��Ɋւ��銴����
- ���������s���Ă���n�悩��̈ړ��A���������s���Ă���n��ւ̈ړ��͍T����
- �A�Ȃ◷�s�͂Ђ����߂ɁA�o���͂�ނȂ��ꍇ��
- ���ǂ����Ƃ��̂��߁A�N�Ƃǂ��ʼn�������������ɂ���
- �n��̊����ɒ��ӂ���
���퐶�����c�ޏ�ł̊�{�I�����l��
- �܂߂Ɏ�A��w����
- �����G�`�P�b�g�̓O��
- ���܂߂Ɋ��C
- �g�̓I�����̊m��
- �u3 ���v�̉���i���W�A���ځA���j
- �����̉�����A���N�`�F�b�N�@���M�܂��͂����̏Ǐ���ꍇ�̓�����������ŗ×{
���퐶���̊e��ʕʂ̐����l��
������
- �ʔ̂����p
- 1 �l�܂��͏��l���ł��������Ԃ�
- �d�q���ς̗��p
- �v������Ăđf�����ς܂�
- �T���v���ȂǓW���i�ւ̐ڐG�͍T���߂�
- ���W�ɕ��ԂƂ��́A�O��ɃX�y�[�X
��y�A�X�|�[�c�Ȃ�
- �����͂��������ԁA�ꏊ��I��
- �g����K�͎���œ�������p
- �W���M���O�͏��l����
- ����Ⴄ�Ƃ��͋������Ƃ�}�i�[
- �\�𗘗p���Ă�������
- ���������ł̒����͖��p
- �̂≞���́A�\���ȋ������I�����C��
������ʋ@�ւ̗��p
- ��b�͍T���߂�
- ����ł��鎞�ԑт͔�����
- �k���⎩�]�Ԃ����p����
�H��
- �����A���o�O�A�f���o���[��
- ���O��ԂŋC�����悭
- ��M�͔����āA�����͌X��
- �Ζʂł͂Ȃ������тō��낤
- �����ɏW���A������ׂ�͍T���߂�
- ���ށA�O���X�₨���傱�̉��݂͔�����
�������ՂȂǂ̐e���s��
- ���l���ł̉�H�͔�����
- ���M�₩���̏Ǐ���ꍇ�͎Q�����Ȃ�
�������̐V�����X�^�C��
- �e�����[�N��[�e�[�V������
- �����ʋł�������
- �I�t�B�X�͂Ђ�т��
- ��c�̓I�����C��
- ���h�����̓I�����C��
- �Ζʂł̑ł����킹�͊��C�ƃ}�X�N
�}���ق�����̍ĊJ�A���{���e�F�@34 ���ł̓C�x���g��
���{�� 4 ���A��{�I�Ώ����j�̉���ɔ����A�S���̓s���{���m���ɁA�C�x���g�̊J�Â�c�Ǝ��l�̗v�����ɘa����ۂ̖ڈ��Ȃǂ�ʒm�����B�@�d�_�I�ȑK�v�� 13 �́u����x���s���{���v�ł��A�}���ق≮�O�����̍ĊJ��e�F�B�@�S���t��ł̓��b�J�[���[���ł̐ڐG�������Ƃ����������A���l�v���̊ɘa���܂߂Ĕ��f����悤���߂��B�@����ȊO�� 34 ���ł̓C�x���g�̊J�Â�F�߂�B�@�z�肷��͍̂ő� 50 �l���x�ŁA�̏���Ȃ����t��⒃��A��O�C�x���g�ȂǁB�@�W�c�������N���Ă��Ȃ������f��فA�S�ݓX�A�w�K�m�Ȃǂ��ĊJ�ł���Ƃ����B�@������������Ǒ���u���Ă��邱�Ƃ��O�B (asahi = 5-4-20)
���@���@��
����x���s���{���Łu���p�قȂǍĊJ�\�Ɂv�@�o����
�����N���o�ύ����E�Đ����� 3 ���A�V�^�R���i�E�C���X�̏d�_�I�ȑK�v�ȁu����x���s���{���v�ł����p�ق�}���قȂǂ͍ĊJ�ł���悤�ɂ���Əq�ׂ��B�@���ꐧ���ȂNJ����h�~��̓O��������Ƃ�����j���B�@�����̋L�҉�� NHK �ԑg�Ŗ��炩�ɂ����B�@����x���s���{���ōĊJ�\�ȗ�Ƃ��Č�������p�فA�����فA�}���ق��������B �l�Ɛl�Ƃ̋�����u���Ȃǂ̑[�u����ꐧ����O��Ɂu���̂��Ƃ͔F�߂Ă����̂ł͂Ȃ����v�Ƙb�����B�@����x���s���{���ł͂Ȃ��n��ɂ��ẮA���ɘa�����[�u���Ƃ�l�����������B (nikkei = 5-3-20)
������Ǝx���Ɋ����t�@���h�o�����@�����o�ύĐ���
�V�^�R���i�E�C���X���S�����鐼���N���E�o�ύĐ����� 3 ���A�S���̒n����s�Ƌ��͂��A�����t�@���h��ʂ���������ƌ����̐V���Ȏx�����ł��o���l���𖾂炩�ɂ����B�@�ő� 200 ���~�̋��t����A�����q�E���S�ۂ̗Z�������ł͕s�������Ƃ̍Č����x���邽�߁A�o�����܂߂��x�����p�ӂ���B
���{���o������u�n��o�ϊ������x���@�\ (REVIC)�v���A�n��̒��j��Ƃ��x���邽�߂ɒn��ƍ���Ă���t�@���h�����p�B�@��N�̑䕗��Q�̍ۂ� 1 �s 13 �������ɗ����グ�����z 31 ���~�̃t�@���h��A�����{���J��F�{�n�k�̍ۂɍ�����t�@���h���A�V�^�R���i�ɂ��o�c�������x���ł���悤�ɂ���B�@���̑��̒n��ł́A�n��ƐV���ȃt�@���h�̗����グ������B�@�x���̏ڂ������e��K�͍͂���l�߂�B
�������� 3 ���̋L�҉�ŁA���\�X�K�͂œW�J�����ƂȂǂ����Ƃ𑱂��邽�߂ɂ́A�ő� 200 ���~�̎��������t���Ȃǂɉ������x���K�v�Ɛ����B�@REVIC ������ 1 ���~�̐��{�ۏؘg��O���Ɂu�K�v�ł���A����𑝂₷���Ƃ��l����v�Əq�ׂ��B (�R�{�m�O�Aasahi = 5-3-20)
�o�ϊ����ĊJ�̍l�����A4 ���Ɏ����ӌ��@�����o�ύĐ���
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ً}���Ԑ錾���߂���A�V�^�R���i���S�����鐼���N���o�ύĐ����� 2 ���A�錾�̉��������߂� 4 ���ɍ��킹�A�o�ϊ����̍ĊJ�Ɍ�������{�I�ȍl�����������ӌ��𖾂炩�ɂ����B�@�܂��A�����h�~�̑�������ɁA�����҂̏��Ȃ��n��ȂǂŐ�s���Čo�ϊ����̎��l�ɘa��i�߂Ă����l�����������B
�������� 2 ���A�����s�̏��r�S���q�m���A���{�̋g���m���m���Ƃ̃e���r��c�ɎQ���B�@�g���m���́u�ڕW���Ȃ��܂܋ً}���Ԑ錾�����������ƕs���ɂȂ�v�Ƃ��āA�{�Ƃ��ċx�Ɨv���ƊO�o���l������������݂���l�����������B�@���̏�Łu�����o���헪�A�q�ϓI�Ȃ��̂������Ȃ�]�����A�����łȂ��Ȃ�A�n�����������d����Ƃ������`�ɂ��Ăق����v�Ƃ��v�]�����B
����A���r�m���́A�x�Ɨv����O�o���l�̉����ɂ��āu�s�Ƃ��Ă̏o���헪���������Ă��������v�Ƃ��A�u�s�ɂ��Ă͂܂��i�����Ґ����j���������Ă��Ȃ��v�ƐT�d�Ȏp�����������B
�������́A4 ���ɐ��Ɖ�c���{�I�Ώ����j������ψ�����J���Đ錾�̉��������߂�Ƃ��A�u���̍ہA�o�ϊ����ĊJ�ɂ��Ă̊�{�I�ȍl���́A���Ƃ̊F���܂�������������Ȃ��炨�����������v�Əq�ׂ��B�@�܂��w�Z�̍ĊJ������̎g�p�Ȃǂɂ��Ă��u�i���Ƃ���j�ɘa���Ă������Ƃ����������͏o����Ă���v�Ɛ����B�@�ɘa�ɂ���Ċ����̍Ċg��������N�����Ȃ����߁A�ڐG�@������炷�Ȃǂ́u�V���������l���v�̋�̗�������l�����������B
�e���r��c��A�������͋L�҉�ŁA�u���߂Ď��l�p�������肢����킯�Ȃ̂ŁA���̌�̌o�ύĊJ�Ɍ������l��������ƂƋc�_���Ă���v�ƌ�����B�@���̏�ŁA4 ���Ɏ����o�ϊ����ĊJ�̍l�����܂��A�ƊE�c�̂ȂǂɁu����I�ȃK�C�h���C���v������Ă��炢�A���Ƃ�̏��F�čĊJ����菇���������Ă���Ɩ��炩�ɂ����B
����ɁA�d�_�I�ɑ��i�߂�K�v������Ƃ��Č��� 13 �s���{�����w�肳��Ă���u����x���s���{���v�ɂ��āu���������A�i�l�Ƃ́j 8 ���ڐG�팸�����肢����v�Ƃ������A����ȊO�̒n��́u7 ���ȍ~�́i�����̎��l�́j�����ɂ܂��Ă������A���̍ہA���Ǝ҂̊F�����f���Ȃ���ł���悤�Șg�g�݂�����Ă��������v�Ɣ����B�@�x�����x���̒Ⴂ�n��ł͌o�ϊ����̎��l�ɘa�ɔ����āA�u8 ���팸�v�̖ڕW���ɘa���Ă������Ƃ����������B (�R�{�m�O�A���˗C���A�X���T��Aasahi = 5-2-20)
�������͊ɂ₩�A������V���������l�����@���Ɖ�c
�V�^�R���i�E�C���X�̑���������鐭�{�̐��Ɖ�c�i���� = �e�c�����E���������nj��������j�� 1 ���A����̕��͂܂������܂Ƃ߂��B�@�����̐V�K�����҂͌����X���ɓ]���Ă�����̂́A�Ăъ������L����Έ�Ñ̐����N�����邨���ꂪ����Ǝw�E�B�@���ʂ͊O�o�̎��l�Ȃǂ̑�𑱂���K�v������Ƃ����B�@���Ɖ�c�� 4 ���ɂ��A�e�n�̊����ȂǁA���ڂ������͂����߂Ď����A����̑Ή�������B�@���{�͂���܂��A�������Ɋ�{�I�Ώ����j������ψ�����J���A�ً}���Ԑ錾�̉���������e�Ȃǂɂ��Đ����Ɍ��߂���j���B
1 ���̒ɂ��ƁA�錾�ɂ��O�o��c�Ƃ̎��l�Ȃǂɂ��A�S���̗v�����҂͔����I�ȑ����i�I�[�o�[�V���[�g�j��Ƃ�A�V���Ȋ����Ґ��͌����X���ɓ]���Ă���B�@�������A���́u�����̑��x�v�́A3 �����{���琶�������ǎ҂́u�}���̑��x�v�ɔ�ׂ�Ɗɂ₩�ɂ݂���A�Ǝw�E�����B�@�l�o�̌����Ȃǂ����ƂɎZ�o�����u�ڐG�p�x�v�ɂ��Ă��A�ڕW�Ƃ��� 8 ������B�����Ă��Ȃ��n�悪�������ƕ��͂����B
����A������̑������Ƃ�O��ɁA����́A�@ �����̏��������n��A�A �V���Ȋ����Ґ�������I�ƂȂ����n��̓�����݂��Ă����A�Ǝw�E�B�@�@ �̒n��ł͐V���Ȋ����Ґ�����萅���ɉ�����܂ł́A�O�o���l�Ȃǂ̑K�v�ŁA�A �̒n��ł��A3 ���i���E���W�E���ځj�̉����e�����[�N�ȂNJ����g���h���Ƃ������A�V�^�R���i�̗��s��ɍL����n�߂��u�V���������l���v�̕��y�����߂���Ƃ����B
�O�o���l�Ȃǂ̑�����߂邩�ǂ����́A�u�����̏v�Ɓu��Ò̐��v�̓�̗v�f�܂��Ĕ��f����Ƃ����B�@�����̏͐V���Ȋ����Ґ��Ȃǂ��\���ɗ}�����Ă��邱�ƂȂǂ����������A��̓I�Ȑ��l�Ȃǂɂ͌��y���Ȃ������B�@�ق��ɁA�s�����w�E����Ă��� PCR �������v���Ɏ��{�ł��邱�Ƃ������Ƃ����B�@��Ò̐��͊��҂̎����̒����A�y�ǎ҂̏h���{�݂̊m�ۂȂǕa��ɉ������Ή����\�ȑ̐����\�z�ł��Ă��邱�ƂȂǂ��K�v�Ƃ��Ă���B
�w�Z�ɂ��ẮA�����h�~�̑�Ȃǂ��Ƃ��������ŁA�����ĊJ�̂�������������Ă����K�v�����w�E�����B�@�܂��A�����̊O�o���l�ɂ�鎙���s�҂�A�c�Ǝ��l�ɂ��|�Y�A���ƁA���E�Ȃǂւ̑�ɕK�v�Ȏx�����u���Ă����K�v������Ƃ����B�@�L�҉�ŁA�������߂���g�E�n���Ë@�\���i�@�\�������́A��𑱂�����Ԃɂ��āu�����m�Ɍ�����悤�ȃE�C���X�ł͂Ȃ��B�@1 �N�Ƃ����N�Ƃ��͎c�O�Ȃ���N�������Ȃ��B�v�Əq�ׂ��B (�y��C��Aasahi = 5-1-20)
���@���@��
1 ���ɐ��{�̐��Ɖ�c���܂Ƃ߂��͐V�^�R���i�E�C���X�̐V���Ȋ����҂͌����Ă���Ƃ����A�������ڎw�����قǂł͂Ȃ��A��Ñ̐����N�����Ă���Ǝw�E�����B�@�����̑Ή��𔗂���Ȃ��A�������X�N������ 3 ��������A�ڐG�@������炵���u�V���Ȑ����l���v�̒蒅���Ăт������B
�����Ҍ��u�ɂ₩�Ɍ�����v
���Ɖ�c�� 1 ���ߌ�ɊJ�����L�҉�B�@���g�Ε������́u�����Ґ��͌������Ă��邪�A���̃X�s�[�h�͉�X�̊��҂���܂łɂ͎���Ȃ������v�ƌ�����B�@�ً}���Ԑ錾����� 4 �� 11 ���ɑS���̐V���Ȋ����Ґ��� 700 �l�߂��ɂȂ������A�ŋ߂� 200 �l�قǂ̓�������B�@���̓����\�����́u�I�[�o�[�V���[�g�i�����I�Ȋ��ґ����j��Ƃ�A�V�K�����Ґ��������X���ɓ]����Ƃ������̐��ʂ�����͂��߂Ă���v�ƕ]�������B
�����A1 ���ɐ��\�l������ 3 ����{ - ���{�ɔ�ׂ�ƁA�܂������B�@�����y�[�X���u�}���̃y�[�X�ɔ�ׂ�Ɗɂ₩�Ɍ�����v�ƒ͎w�E���A�u��s�s������l���ړ��������ƂŁA�n���Ɋ������g�債���v�ƕ��͂����B�@�S�����ς�茸���̃X�s�[�h�����������ł��A�a�@�╟���{�݂ł̏W�c������ƒ���ł̊����������Ȃ��Ă��邱�ƂŁA�}���ɂ͌����Ă��Ȃ��Ƃ����B
�������g�債�Ă��邩���݂�d�v�Ȏw�W�̈���u�����Đ��Y���v���B������1�l�����l�Ɋ��������邩�������l�ŁA1 ���傫����Η��s�͊g�債�A�������Ǝ������Ă����B�@�S���� 2.0 �i3 �� 25 �����_�j�A������ 2.6 �i3 �� 14 �����_�j���������A4 �� 10 �����_�ł͑S���� 0.7�A������ 0.5 �܂ʼn��������B
�����J���ȃN���X�^�[���ǂɎQ�����鐼�Y���E�k�C���勳���i���_�u�w�j�́A1 ����������̂͑S�����������ً}���Ԑ錾���o��O�� 4 �� 1 �����낾�����Ɛ����B�@���̂����ŁA�u1 �����邾���ł͊����Ґ����\���Ɍ��炷���Ƃɂ͑���Ȃ��B�@�S���I�ɂ݂�ƁA8 ���̐ڐG�@��̍팸�ŋ��߂Ă��������ɂ͒B���Ă��Ȃ��B�v�Ǝw�E�B�@�ڕW�Ƃ��� 0.5 �ȉ��ɂȂ邱�Ƃ��m�F���Ă����K�v������Ƃ����B
��Ì���A���S�͑���
�����APCR �����̌����������A�Ƃ��ɗ��s�n��Ŋ����҂�c��������Ă��Ȃ��Ƃ̎w�E������B�@���g�������Łu��X�͊����̎��Ԃ̈ꕔ��c�����Ă���ɉ߂��Ȃ��v�ƔF�߂������ŁA�傫���͌����X���ƊԈႢ�Ȃ����f�ł���Ƌ��������B�@�錾�̉������f�ŏd�v�Ȃ�����̗v�f����Ì���̕N�����B�@���҂͕��� 2 - 3 �T�ԓ��@����B�@���ɐl�H�ċz�킪�K�v�ȏd�NJ��҂̓��@�͒���������B�@�d�Ăȏ�Ԃ��ƁA��ÃX�^�b�t�̐l�����K�v�ŁA24 ���ԑ̐��̏W���I�Ȏ��Â������B
�S���I�ɐl�H�ċz�킪�K�v�Ȋ��҂͂��� 1 �J���� 3 �{���ɑ����Ė� 280 �l�A�l�H�S�x���K�v�Ȋ��҂��� 2.5 �{�ɑ����Ė� 50 �l�ɂȂ��Ă���B�@�V�K�����Ґ��������Ă��A��Ë@�ււ̕��ׂ͊ɂ₩�ɂ�����������Ȃ��B�@��ŁA��c�̃I�u�U�[�o�[�߂铌���s����a�@�̍������j�E�����ǃZ���^�[���́u���Ґ��������Ă��d�Ǐd�Ă̊��҂ł��Ȃ�a�������܂��Ă���B�@�y�ǎ҂ɂ��d�ĂɂȂ�l������B�@�i��Ì���́j���S�͑����Ă���B�v�Ƙb�����B (asahi = 5-2-20)
���Ɖ�c�̏��͂ƒ̍��q
�E �����_�Ŕ����I�ȑ����i�I�[�o�[�V���[�g�j��Ƃ�A�V�K�����Ґ��͌����X��
�E ��s�s������l���ړ����A�n���Ŋ������g��
�E �V�K�����҂������Ă��A��Ì���̕N�������͊ɂ₩�ɂ�����������Ȃ�
�E ��́u�������������n��v�Ɓu�V�K�����Ґ�������I�ƂȂ����n��v�ŋ敪��
�E �V�K�����Ґ�������I�ƂȂ����n����A3 ���̉�����A�e�����[�N�⎞���o�Ȃǂ́u�V���������l���v�Œ����̑Ή����K�v
���{�A�x�Ɨv����i�K�����ց@�u���͏o���헪���Ȃ��v
���{�̋g���m���m���� 1 ���A�V�^�R���i�E�C���X�ɑΉ�������ʑ[�u�@�Ɋ�Â��x�ƂƊO�o���l�̗v���ɂ��āA���������ɂ߂A���� 15 ���ɂ��i�K�I�ȉ������n�߂�l�����L�Ғc�Ɏ������B�@���{�� 4 ���ɔ��\����V�����Ώ����j���m�F���A���{�Ƌ��c������ōŏI���f����B
�x�Ƃ̓J���I�P�{�b�N�X��X�|�[�c�N���u�A�i�C�g�N���u�Ȃǂɑ��Đ挎 14 ���ɗv���B�@�ǂ̋Ǝ킩��������n�߂邩�́A����l�߂�B�@���҂̓��@�x�b�h�̗��p�Ȃǂ��w�W�Ƃ���Ǝ��̊�����肵����ŁA��������ꍇ�ɉ���������j���B�@�g���m���͂���܂Łu�o�ς����S�Ɏ~�߂�ƍ��x�͓|�Y�A���ƎҁA�����Ŏ����閽���K���o�Ă���v�Ǝ咣�B�@1 �����u�o���헪���Ȃ����̍��̕��j�͑��肾�B�@�������Ȃ��Ȃ�A��ヂ�f������낤�ƌ��߂��B�v�Əq�ׂ��B
���{�ً͋}���Ԑ錾�̊����� 1 �J�����x����������j�ŁA�Ή��͐����ɂȂ肻�����B�@�g���m���Ƒ����݂����낦����s�̏����Y�s���́u���[�@�̌����͓s���{���m���ƂȂ��Ă���v�Ǝw�E�����B�@���������A�{���ŐV���Ɋm�F����銴���Ґ��͗��������Ă��邪�A�x�Ɖ����Ȃǂɓ��ݐ����ꍇ�͍Ăё�������\��������B (�X���T��A�{���R���Aasahi = 5-1-20)
�V�^�R���i�u�o�ϕ��������ɗ}�����߂�v�@�Ȋw�҂���
�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŊO�o�֎~�⎩�l�����������A���ǂ�����āu�����v��i�߂Ă����� - -�B�@�e���ɔ����������f�ɁA�C�X���G���̒����ȃR���s���[�^�[�Ȋw�҂���̃A�C�f�A����Ă���B�@�_���̃^�C�g���́u�o�ϕ����������ɁA�V�^�R���i�E�C���X��H���~�߂��邩�B�v�@�������X�N�̒Ⴂ��҂������ɉ�����A����҂͂Ȃ�ׂ�����u���𑱂��� - -�B�@����Ȑ헪���������邽�߂̓Ǝ��̌v�Z���@��҂ݏo�����̂��A�_���̃~�\���Ƃ����B
�������̂̓w�u���C��̃A���m���E�V���V���A�����B�@�Ԃ̎����^�]�Z�p�Ő��E�̃g�b�v�𑖂�u���[�r���A�C�v�̑n�Ǝ҂ŁACEO �ł�����l�����B�@���Ђ� 2017 �N�A�ăC���e���� 153 ���h���i1.7 ���~�j�Ŕ������ꂽ���Ƃł��傫�Șb��ƂȂ����B�@����̒�Ă̑_���ɂ��āA�r�f�I�d�b�Ŗ{�l�Ɏ�ނ����B
- - �R���s���[�^�[�Ȋw�҂Ȃ̂ɁA�Ȃ������Ǒ�̘_�����o�����Ƃɂ����̂ł����B
�u�����ǂ̐��Ƃ����g�ނׂ��e�[�}���ƕ��ʂ͎v���܂���ˁB�@�����A����̃E�C���X�́w������Ȃ����Ɓx����������B�@�u�w�I�ȉ�͂�����̂ł��B�@�����̃s�[�N�͂��ŁA�{���̊����Ґ������l�Ȃ̂��́A�N���m��Ȃ��B�@�����O�o�֎~�������Ή����N���邩�́A�u�w�I�Ȍv�Z�ł͂Ȃ��Ȃ�������܂���B�v
�u�����ŃR���s���[�^�[�Ȋw�̏o�Ԃł��B�@�s�m��ȗv�f�̒��ŁA�v�Z�ɂ���čň��̃P�[�X������邽�߂̏������o���͓̂��ӕ���ł��B�v
- - ���ł��鎩���^�]�Z�p�̊J���ɂ��ʂ���l�����ł����B
�u���̒ʂ�ł��B�@�����^�]�̏ꍇ�A���S���Ɨ����̃o�����X����ɖ���܂��B�@���̂̉\�����[���ɂ������Ȃ�A�Ԃɏ��Ȃ�������B�@�ł��l�Ԃ͐����̂��߂ɎԂɏ��܂��B�@���̂̉\�����\���Ɍ��炵�A�����Ԃ������ɑ��点�邩�B�@����A���̔��z�����p�����킯�ł��B�@����������āA�����ƉƂɂ������Ă���킯�ɂ͂����܂���B�v
- - ��̓I�ɂǂ�Ȓ�ĂȂ̂ł����B
�u�܂��Љ�� 2 �̃O���[�v�ɕ����܂��B�@�w�����X�N�x�� 67 �Έȏ�⎝�a�����l�����B�@�w��X�N�x�͂���ȊO�̐l�����ł��B�@�����āw��X�N�x�̃O���[�v�����A�O�o�֎~�߂��������܂��B�v
�u���ʂ̐����ɖ߂�����҂����ɂ͏��X�Ɋ����͍L�܂�܂����A�����͏d�ǂɂ͎���܂���B�@�������T�Ԃ��琔�J����A�\���Ȑl�����E�C���X�ւ̖Ɖu���l�����A�������L����ɂ������Ɣ��f�����A����҂Ȃǁw�����X�N�x�̐l�������O�o���Ă����S���ƌ�����ł��傤�B�@�� 1 �N����̃��N�`���J���܂ł̑Ή���Ƃ��Ă͗L���Ȑ헪���ƍl���Ă��܂��B�v
- - ���N�ȎႢ�l�����ł��A��������Ώd�lj����鋰�ꂪ����킯�ł���ˁB
�u���̎��A�W�����Î� (ICU) �̃x�b�h������������Έ�Õ����h���邩���v�Z�����̂��A����̘_���̍ł��厖�ȕ����ł��B�@�C�^���A��X�y�C���ł́A�����̎��҂���Õ���ɂ���Đ��܂�Ă��܂��B�@�����҂��o�Ă��A�\���ȃx�b�h���Ƃ���ɉ������l�H�ċz��A��ÃX�^�b�t������Ζ��͋~����̂ł��B�v
�u�Ⴂ�l�����̒v�����͔��ɒႢ���Ƃ��������Ă��܂��B�@�����A����ł��������|���Ƃ����l�ɖ������ĊO�o�͋������܂���B�@�����܂ŁA�w��X�N�x�̃O���[�v�ɊO�o�����o���Ƃ������z�ł��B�v
- - �����ɂ́A����҂Ǝ�҂��ꏏ�ɏZ��ł���P�[�X������܂��B
�u������z��ς݂ł��B�@�C�X���G���̏ꍇ�A�������̃P�[�X�̂����A�����͕ʋ��̑I�����\�ł��B�@�c��̔����͌����I�ɓ���̂ŁA���̐l�����͑S�����O�o�֎~�𑱂���w�����X�N�x�ɕ��ނ��܂����B�v
- - ���ۂɌv�Z������ƁA�ǂ��Ȃ�܂������B
�u�C�X���G���̗�Ő������܂��傤�B�@150 ���l�́w�����X�N�x�̐l�����͎���u���𑱂��A750 ���l�́w��X�N�x�O���[�v���Љ�ɖ߂�܂��B�@���݂̃C�X���G���ł̊����܂���ƁA10 ���l������ 15 ���� ICU �x�b�h������ΑΉ��ł���v�Z�ɂȂ�܂��i��̘_���ł� 10 ���l������ 20 ���ƎZ�o�j�B�@���݂� 10 ���l������ 6 ���Ȃ̂ŁA���{�̓w�͂ɂ���Ď����\�Ȑ����ł��B�v
- - �����ǂ̐��Ƃ���݂Ă��A�����͂̂���A�C�f�A�Ȃ̂ł��傤���B
�u�C�X���G���{�̂��ƂɁA�O�o��������̏o���헪����邽�߂ɐݒu���ꂽ�ψ������A�����g�b�v�߂Ă��܂��B�@�ψ���琭�{�ɂ��̃A�C�f�A���Ă����Ƃ���A�����Ɍ����Ē�����i�߂邱�ƂɂȂ����B�@���Ƃ̈ӌ������܂������f���Ǝv���Ă��܂��B�v
- - ���̎�@�͑����ɂ��K�p�ł���̂ł����B
�u���{�ł��A���Ƃ��Γ����ŃT���v�����O���������{����AICU �x�b�h�ɂ��Ɖ����̗]�T������ΊO�o�֎~�������ł��邩���v�Z�ł��܂��B�@5 ��l�̖������������A�\���ɐM���ł��鐔�l�������܂��B�v
�u���݂͊e���������S�̂ɊO�o���l�𑣂��A�����̃s�[�N���Ȃ��炩�ɂ���헪���Ƃ��Ă��܂��B�@�������A����ł͌o�ς��₪�Ĕj�]���Ă��܂��B�@����҂͂Ȃ�ׂ��Ƃɂ��Ă��炢�A���̑��̐l�����̊������X�N�ɑς����邾���̈�ÑԐ��𐮂�����Ōo�ϊ������ĊJ������̂́A�����I�ȍl�����ł��B�v
��
��ތ�A�V���V���A�����͒lj��œ�̘_���\�����B�@����҂�u�����X�N�v�̐l�̊O�o�𐧌����Ă��Ȃ��A�u��X�N�v�̐l�����Ƃ̐ڐG��������ꂸ�Ɋ�������\���Ȃǂ��l���������f�����\�z�B�@��茻���ɑ������v�Z��i�߂Ă���B
�C�X���G�������̊����f�[�^�����ɂ���ƁA�u��X�N�v�w�̒v���� 0.01 - 0.02% �ɑ��A�u�����X�N�v�w�̒v������ 2.2% �Ɛ��肳���B�@�V���V���A�����́u�܂�œ�̕ʂ̕a�C�ɒ��ʂ��Ă���悤���B�@��҂炪�o�ς����������A�M�d�Ȉ�Î����́w�����X�N�x�̐l�����ɏW��������d�g�݂��K�v���B�v�Ƃ��Ă���B�@�_���͈ȉ��̃E�F�u�T�C�g�Ɍ��J����Ă���B�@https://medium.com/ @amnon.shashua (�G���T���� = �����1�Aasahi = 5-1-20)
�q�ҎҒ��r ��L�̐��������ƂɁA�����̔N��ʊ����Ґ�������ƁA��ҋy�ь��𐢑�̔䗦�������A�����I�ɂ͏�L�̉�͂͐������A���A�����ł��������ʂ������Ă���悤�Ɋ����܂��B�@�����A����҈�Î{�݂̃N���X�^�[���d���̂��������Ă���̂������ŁA��ɕ�����Ƃ���A���͂ōs���ł���l�ƁA�����łȂ��l�i��b���������l���܂ށj���A���ꂼ��ɕʌ̑Ή�������̂��A�ł��]�܂�������ł͂Ȃ����ƕM�҂ɂ͎v���܂��B
�ً}���Ԑ錾�A���������Œ����@�S�s���{����Ώ�
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɔ����ً}���Ԑ錾�ɂ��āA���{�͑S�s���{����Ώۂ� 5 �� 6 ���܂ł̊�����������������Œ����ɓ������B�@�������Ԃɂ��Ă� 1 �J�����x�ɂ���Ă���������Ă���B�@���{�W�O�� 4 �� 29 ���̎Q�@�\�Z�ψ���ŁA��������}�̘@�u������ً}���Ԑ錾�� 5 �� 6 ���ɏI�����邩�ǂ�������A�u�ˑR�������͑����Ă���낤�Ǝv���v�ƌ�����B�@���\�����ɂ��Ắu���O�ł���Α�ςȍ��������邩������Ȃ��v�Əq�ׁA���O�ɕ�������ł��o���l�����ɂ��܂����B
1 ���ɂ͐��{�̐��Ɖ�c���\�肳��Ă���B�@�͐��Ƃ���̈ӌ����������ŁA�����ȓ��ɉ�������Ώۋ�����ԂȂǂ��ŏI���f������j���B�@���{��t���S���m����͑S�s���{����Ώۋ��Ƃ��Đ錾���Ԃ���������悤���߂Ă���A���@�����́u���d���Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƌ�����B�@���ɂ���ċx�Ƃ̗v���Ȃǂ̐����ɋ����t����Ă����サ�Ă���B�@�V�^�R���i�E�C���X���S�����鐼���N���o�ύĐ����� 4 �� 29 ���̋L�҉�ŁA30 ���ɑS���m����ƃe���r��c���J���ӌ���\���B�@�����ɂً͋}���Ԑ錾��S���Ɋg�債�Ă��� 2 �T�Ԃ��}���A�O�o���l���ʂ����ɂ߂�f�[�^���o�Ă���Ǝw�E�����B (asahi = 4-29-20)