只見線 11 年ぶり全線再開 ローカル線、廃線回避の条件は
福島県と新潟県を結ぶ JR 只見線(会津若松 - 小出)が 1 日、11 年ぶりに全線で運転を再開した。 2011 年の豪雨で不通となった只見 - 会津川口が復旧した。 ローカル線は毎年のように豪雨や地震で被災し、そのまま廃線に追い込まれるケースもある。 復旧と廃線を分けるポイントは。
只見線は 11 年 7 月の新潟・福島豪雨の直撃を受け、鉄橋 3 本が流失した。 復旧区間の被災前(09 年度)の収支は 3 億 2,900 万円の赤字。 JR 東日本は廃線とバス転換を地元に提案した。 沿線自治体による本腰の支援が流れを変えた。 復旧コスト約 90 億円は 3 分の 2 を地元が負担する。 最大半分は国が補助し、年約 3 億円が見込まれる施設の維持管理費も会津の 17 市町村が最大 6,300 万円を受け持ち、残りは県が負担する。
運行と施設の維持管理を分担する上下分離の手法を JR 東日本が導入するのは初めて。 災害復旧には熱意だけでなく、自治体によるコスト負担の本気度がカギを握る。 三重県松阪市から津市山間部を結ぶ JR 名松線(松阪 - 伊勢奥津)は、09 年の台風被害で全線運休となった。 JR 東海は当初バス転換も検討したが、津市が約 7 億 5 千万円をかけて川へ注ぐ水路を整備し、三重県は約 4 億 7 千万円をかけて土砂災害を防ぐ治山で協力。 16 年 3 月の全線運転再開にこぎつけた。
三重県知事(当時)に初当選後すぐ、決断を迫られた鈴木英敬・現内閣府政務官は「全線再開に向けて重い腰を上げてもらうには地方も負担しないといけない、と腹をくくった」と振り返る。 1 日 1 キロメートルあたりの乗車人数を示す輸送密度は 287 人(19 年度)と低迷が続くが、JR 東海の金子慎社長は「(廃線やバス転換などの)予定は当面ない」と断言する。
日高線(鵡川 - 様似)や岩泉線は被災をきっかけに廃線に追い込まれた。 一方、東北地方を直撃した 8 月の豪雨で被災した奥羽本線の不通区間は運転再開が決まり、磐越西線も来春の運転再開へ準備を急いでいる。 奥羽本線は貨物の幹線で、磐越西線も東日本大震災後には迂回ルートとして活用された。 震災で寸断された気仙沼線、大船渡線はバス高速輸送システム (BRT) に転換して生き残った。 17 年の九州北部豪雨で運休となった日田彦山線も、一部一般道を走る「BRT ひこぼしライン」として 23 年夏の再開を目指している。 病院や学校の近くに駅を設け、利便性を上げる。
20 年の九州豪雨で被災した肥薩線は八代(熊本県八代市) - 吉松(鹿児島県湧水町)の約 87 キロメートルが不通となったままだ。 235 億円程度と試算された復旧コストのうち、政府は橋梁の架け直しや河岸のかさ上げなどを公共工事として肩代わりし、JR 九州の負担を約 76 億円に抑える案を示した。 国や JR も交えた検討会議での議論も 3月から始まっている。
八代 - 人吉の利用客数は豪雨災害前の 19 年度、1987 年度と比べて 81% 減少していた。 19 年度は約 6 億円の営業赤字だった。 議論の終着駅は見えない。 (黒滝啓介、小山隆司、近藤康介、nikkei = 10-1-22)
函館線を貨物線として維持、国が協議へ 北海道や JR と 旅客と分離
国土交通省は、北海道新幹線札幌延伸で JR 北海道から分離される函館線の函館 - 長万部間(約 148 キロ)を貨物路線として維持するため、北海道と JR 貨物、JR 北との 4 者協議を始める。 函館線の同区間について、沿線自治体の多くは旅客路線としては大部分を廃線・バス転換したい意向だ。 ただ同区間は北海道と本州を結ぶ貨物の大動脈で、貨物網が寸断される可能性がある。 国は農産品などの物流維持のため、異例の調整に乗り出す。
北海道新幹線は 2030 年度に札幌まで延伸される予定で、並行在来線の函館線(函館 - 小樽、約 288 キロ)の存廃が協議されている。 すでに長万部 - 小樽間(約 140 キロ)は沿線自治体が廃止・バス転換を受け入れた。 函館 - 長万部間は 8 月末、約 1 年 4 カ月ぶりに沿線自治体の協議会が開かれ、新幹線に連絡する函館 - 新函館北斗間(約 18 キロ)のみを第三セクターで存続させたいとの意見が目立ち、大部分の廃線が確実となった。
ただ、函館 - 長万部間は十勝地方などの農産物や本州からの様々な生活用品を運ぶ貨物の大動脈。 国交省は「このままでは北海道と本州を結ぶ重要な貨物輸送が途切れる可能性がある(貨物鉄道政策室)」として、並行在来線の沿線協議とは別に、道や JR 2 社と協議の場を設けることにした。
貨物網寸断、国内経済全体に影響も
今後の協議では、道などが出資する第三セクターが線路を保有し、JR 貨物が列車を運行する「上下分離方式」を軸に検討されるとみられる。 今後、旅客路線の存廃協議の方向性が固まり次第、具体策の検討に入る。 旅客路線としては大部分が使われなくなるため、貨物路線として線路を維持するには費用負担が課題になる。 JR や道などの負担割合のほか、旅客輸送をやめたあとの収益確保などの課題が議論されそうだ。
国が中心となって貨物線の存続を検討する異例の対応をとるのは、道南地域の鉄路は北海道と本州を結ぶ貨物輸送の「玄関口」にあたり、寸断されれば道内だけでなく、国内の経済全体に大きな影響を与えるためだ。 JR 貨物が道外に運ぶ荷物は農産品が約 5 割を占める。 道外に出荷されるタマネギの約 6 割、ジャガイモやコメの約 4 割を運ぶ。 本州から道内には宅配便や書籍、生活用品などを運んでいる。
船舶では鉄道のように大量の貨物を運べず、港湾からのトラック輸送も人手不足の折、ドライバーの確保が難しくなっている。 鉄道物流をめぐっては、国交省の有識者会議が 7 月に貨物専用新幹線の導入を提唱。 JR 貨物と JR 各社などが実現に向けて検討する予定だが、札幌延伸が予定される 30 年度には間に合わないという見方が強い。
専用車両の開発に時間がかかるほか、旅客需要の多い仙台以南の新幹線は本数が多く、その合間に貨物新幹線を混在して走らせることは難しいというダイヤ編成上の問題もある。 国交省は「現状では鉄道貨物に代わる手段がない。」とみている。 道も、5 月にまとめた物流に関する報告書で「取引条件に応じて輸送手段が合理的に選択され、現在の輸送体制が形成されており、トラック、鉄道、船舶、航空機の手段はいずれも欠くことができない」とし、貨物網を維持する重要性を訴えている。 (編集委員・堀篭俊材、新田哲史、asahi = 9-12-22)
JR 東日本、鉄道人員 4,000 人縮小へ 不動産などに再配置
- JR 東日本は鉄道事業の社員数を約 1 割縮小
- 在宅勤務の定着などでコロナ前回復見込めず
- 人員は不動産や流通などの成長分野に再配置
JR 東日本は鉄道事業の社員数を約 1 割縮小する。 新規採用を抑え、2025 - 30 年に山手線などで導入するワンマン運転や保守作業のデジタル化で約 4,000 人を減らす。 新型コロナウイルス禍で減少した通勤客は回復が鈍い。 鉄道の人員は不動産や流通などの成長分野へ回す方針で、コロナ後の需要の変化をにらんだ人材の再配置の動きが本格化してきた。
深沢祐二社長が日本経済新聞の取材で明らかにした。 JR 東で現在、鉄道事業の運営に必要な人員は約 3 万 4,000 人(連結従業員数は約 7 万 1,000 人)。 今後の目標として 3 万人未満に減らす方針を示した。 早期退職などは募らず、定年退職などの自然減や非鉄道事業への配置転換で対応する。 コロナ禍後に鉄道事業の大幅な人員縮小の動きが明らかになるのは大手で初めてになる。
コロナ禍の長期化で鉄道の需要は回復が遅れている。 JR 東の 22 年 4 - 6 月期の運輸収入はコロナ前の 19 年同期に比べて 7 割の水準にとどまる。 深沢社長は在宅勤務の定着などで定期券の収入や新幹線の出張客は「コロナ前に戻ることはない」と語る。 28 年 3 月期に鉄道事業の営業費用を 20 年 3 月期比 1,000 億円減らす目標を掲げ、700 億円まで削減のめどがついた。 主要駅の「みどりの窓口」は 20 年比 2 割減らしたほか、首都圏ではワンマン運転の拡大や線路などの保守作業のデジタル化を加速している。 赤字の地方路線でもバスへの転換などを検討してコストを減らす。
JR 東は人口減も見据えて商業施設の「ルミネ」や東京都港区の高輪ゲートウェイ駅周辺の再開発など非鉄道からの収益を増やす方針だ。 連結売上高の 6 割強を占める鉄道事業の比率を将来は 5 割程度まで下げる計画だ。 鉄道事業の従業員の学び直しなどを支援して再配置するほか、副業なども促進する。 運輸業界では日本航空がビジネス需要が戻らないとみて、約 3,000 人の従業員を主力の航空事業から格安航空会社 (LCC) やマイル事業などの非航空分野にシフトする方針を決めている。 (nikkei = 8-31-22)
アンテナ消え、隣県と同じ放送に? 地方のテレビに何が起きるのか
テレビの放送波を全ての家へ届けるのをやめ、一部はネット回線経由で見てもらう。 番組は終日、隣の県と同じ - -。 将来、地方のテレビはそんなふうになるかもしれない。 地方の放送局の経営が厳しくなるのを見込んで、今の仕組みを変えられるようにしてはと国の有識者会議が提言したのだ。 地方局の実情と、提言が示唆する将来像を探った。
「全国あまねく受信」維持の重い負担
東シナ海に面した長崎県西海(さいかい)市。 九州本土から三つの橋で海を渡った西端、かつて海底炭鉱で栄えた崎戸(さきと)地区の丘の上に、地上デジタル放送を送信する「ミニサテライト局」と呼ばれる崎戸東中継局の鉄柱が立っている。 ミニサテ局は出力 0.05 ワット以下で、出力の大きな送信所の電波が直接届かない地域に中継している。 NHK と民放合わせて全国に約 3,300 局。 多くは 1 カ所に複数の中継局が「同居」している。 崎戸東中継局では NHK 総合と E テレ、民放 4 局の計 6 局がこの鉄柱から、崎戸地区の一部にあたる直下の数十軒に放送波を届けている。
放送法は NHK に、放送が全国あまねく受信できるようにする義務を定め、民放には努力義務として課している。 そのため、人口減が進む地域でも、放送局は全ての住民が放送波を受信できるよう維持してきた。 その負担は大きい。 日本民間放送連盟(民放連)が全国の加盟 127 社に調査したところ、小規模な中継局の 1 年当たりの維持費(建て替え費用含む)は全国合計で約 71 億円、さらに小さなミニサテ局も約 10 億円で、計約 81 億円かかる。 だが、これらの送信所でカバーする世帯は全国の 3% に満たない。
入り組んだ地形が続く長崎県はミニサテ局も多く、民放 2 局と FM ラジオ局 1 社は、各局の負担を減らすため、中継局の維持管理会社を 1989 年に設立。 91 年には後発の 2 局も出資に加わった。 台風の常襲地帯でもあり、停電が起きれば民放各社と NHK が分担し、発電機を車に積んで駆けつけ、電源を確保して放送を維持することが毎年のように起こるという。 こうした負担を軽減するため、総務省の有識者会議「デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会」は昨年 11 月から制度の見直しを議論してきた。 7 月末にまとめた提言では、将来は光ファイバーなどの高速インターネット網で代替するよう検討を求めた。
国の検討会が提言したのは、ネット回線での代替だけではありません。 記事の後半では、地方局のかたちを一変させるかもしれない「マス排」、「放送対象地域」の見直しについて読み解きます。
ある地方局幹部は「費用対効果の差が広がる一方の地域では、正直ミニサテ局をブロードバンドに置き換えられるならそうしたい」と提案を歓迎する。 一方で「局がどうネット配信の仕組みをつくり、その負担をどうするか。 そこがまだ見えない。」とも漏らす。 西海市では今春までに、全域の主要道路に光回線が敷設された。 ただ、家に引き込むには各戸で工事や利用料を払わなければならない。 住民の宮津柳二郎さん (83) は「テレビはよく見ようばってん、住民の負担になるようなことは困るですよね」と話した。
「マスター」更新、多額の費用
ミニサテ局などの中継局と並んで多額の投資を迫られるのが、放送局の心臓部にあたる「マスター」と呼ばれる送出設備だ。 地方局ではいま、地デジ化後初めての更新期を迎えている。 一式更新するのに、地方局のもので 5 億 - 7 億円、キー局は 20 億 - 30 億円ほどかかるとされる。 全国 114 の地方局平均で、売上高 52 億円、平均営業損益 1 億円の黒字(いずれも 2020 年度)という経営規模には重くのしかかる。
NHK 放送文化研究所の調査(20 年)で、10 - 20 代の約半数がほとんどテレビを見ないことが明らかになるなど、若者を中心にテレビ離れが進む中、特に地方局は苦境にある。 人口が減れば地方経済が冷え込み、CM 売り上げの減少となって跳ね返る。 一方で人口は減っても住民がいる限りは放送を届けなければならず、その設備を維持する負担が人口に比例して減るわけではない。
ある地方局の社員は「今後 10 年間売り上げを保てるかどうか、誰も予言できない」と漏らす。 CM 収入がコロナ前の水準に戻っていない上、今年から来年にかけて中継局やマスター設備などの更新が迫り、数十億円単位の投資がのしかかる見通しだという。 総務省の有識者会議はこうした地方局の現状を踏まえ、経営を圧迫する要因を減らし、番組制作に注力できるよう、様々な提言をした。 ミニサテ局のネット回線代替などと並び、高額なマスター設備を念頭に、複数の放送事業者が共同で設備を使えるようにすることも提案した。
提言は設備投資軽減策にとどまらず、地方局の経営の選択肢を広げるため、既存の様々な放送制度の見直しにも言及している。 その一つが、放送に多様性や地域性をもたせるために、一つの持ち株会社の傘下に入れる放送事業者の放送地域が計 12 都道府県以下になるよう制限している「マスメディア集中排除原則」の上限撤廃。 地方経済が落ち込み、地方局の地元株主が株を手放すことも想定される中、持ち株会社は系列局への出資比率を引き上げやすくなる。
県境またいで同じ放送?
また放送法に基づく「基幹放送普及計画」で定められた「放送対象地域」の拡大も提言した。 現行の計画では放送事業者が放送できる地域を、関東は 7 都県、近畿は 6 府県、中京は 3 県を一つの単位とし、ほかの大半は 1 道県を 1 地域と位置づけており、民放の各系列局は 3 大都市圏のほかはほぼ県単位で開局し、全国にネットワークを広げてきた。 今回の提言は、県境を越えて同じ放送ができるようにすることとしている。 実現すれば、放送エリアや資本関係などの既存の枠組みが、大きく変わる可能性もある。
これら提言に盛り込まれた内容は、いずれも民放キー局側の要望と重なる。 ただ、キー局と地方局の認識がかみ合っているわけではない。 県域を越えて同じ放送ができるようになった場合、県ごとに番組や CM を切り替えられなくなるのが前提だ。 九州のある民放幹部は「経営の選択肢が増えるのはありがたい」としつつ、「時間帯にもよるが、番組のブロック化によって視聴率が伸びないのは経験済み。 終日隣県と同じ放送をすれば、スポンサーの商圏や予算とのミスマッチが起こり、CM を出しにくくなる。」と疑問視する。 「今後も放送を続けていくには固定費を削減するしかない。」 (伊藤宏樹、野城千穂、平賀拓史、asahi = 8-26-22)
山手線も「客足戻った駅/さらに減少の駅」明暗 JR 東日本の 2021 年度「駅別乗車人員」出る
JR 東日本は 2022 年 8 月 1 日(月)、2021 年度の 1 日平均の駅別乗車人員ランキングを発表しました。 トップ 7 は前年度と変わらず、新宿・池袋・横浜・東京・渋谷・品川・大宮の順番。 乗車人員 1 位の新宿駅は、1 日平均 52.2 万人が利用していました。 なお、コロナ禍の影響下にあった 2020 年度からは 9.5% 増加となっています。 ちなみにコロナ禍前の 2018 年度は 1 日平均 78.9 万人の実績があったので、それと比べると今もまだまだ少ない数です。
前年度比で比較すると、コロナ禍の緩和をうけ全体的に 5% 周辺の増加がみられ、新宿・池袋・渋谷・高田馬場・吉祥寺といった繁華街の駅は 8 - 10% の大きな伸びを示しています。 対照的なのが品川・田町・浜松町・新橋・大崎といったビジネス街で、数少ない 4 - 5% 周辺の「減少」となっています。 テレワークへの移行が進んだことで、通勤利用の減少が顕著に表れたとみられます。 前年度比で変化なし・微減となったのは他に、有楽町・神田・飯田橋・大井町などがあります。
ちなみに、1 日平均乗車人員がもっとも少ない駅は、4 年連続で JR 飯山線の平滝駅(長野県栄村)。定期利用 1 名、一般利用 1 名の計 2 名です。ただ、「計測対象となっていない駅」もあり、JR 山田線の区界駅は 2017 年度まで最下位でしたが、現在は数値が出ていません。 新幹線では東北・上越新幹線の東京駅が 1 日平均 3.2 万人で最多。 最少は、いわて沼宮内駅で 1 日平均 38 人という数字になっています。 (乗りものニュース = 8-1-22)
◇ ◇ ◇
JR 東のローカル線、35 路線 66 区間すべて赤字 収支を初公表
JR 東日本は 28 日、管内を走るローカル線の路線ごとの収支を初めて公表した。 対象となった 35 路線 66 区間すべてが赤字だった。 利用者の減少に歯止めがかからず、JR 東は廃線も含め、今後の路線維持のあり方について沿線の自治体と協議を進めたい考えだ。 公表したのは、2019 年度に 1 キロあたりの 1 日の平均利用者数(輸送密度)が 2 千人未満だった区間。 東北地方や新潟県を走る路線が多く、19、20 年度の収支を公表した。
公表された資料によると、最も赤字額が大きかったのは新潟県と山形県を走る羽越線村上 - 鶴岡で、19 年度は 49 億円、20 年度は 53 億円だった。 費用に対する収入の割合を示す「収支率」は、19 年度は千葉県の久留里線久留里 - 上総亀山が 0.6%と 最も低く、20 年度は宮城県と山形県を走る陸羽東線鳴子温泉 - 最上が 0.5% と最も低かった。 20 年度については、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあったとみられる。
ローカル線をめぐっては、JR 西日本や北海道、四国、九州がすでに収支を公表しており、いずれも厳しい経営状況にあることが示されている。 今月 25 日には、国土交通省の有識者検討会議がローカル線のあり方について提言をまとめ、輸送密度が 1 千人未満などの条件を満たせば見直しの対象となるとの考えを示した。 今後、路線の維持をめぐり JR 各社や自治体との協議が進むとみられるが、存続を求める自治体側の反発も予想される。(小川崇、松本真弥、asahi = 7-28-22)
| 赤字の総額 | 対象の路線区数 | |
|---|---|---|
| JR 東日本 | 693億円 | 35路線66区間 |
| JR 西日本 | 248億円 | 17路線30区間 |
| JR 九州 | 53億円 | 14路線20区間 |
| JR 北海道 | 458億円 | 13路線22区間 |
| JR 四国 | 131億円 | 8路線18区間 |
* 各社の 2019 年度の公表ベース。 在来線のみ。 JR 東日本、西日本、九州は 1 キロあたり 1 日の平均乗客数(輸送密度)が 2 千人未満の路線区が対象。 JR 北海道、四国は全路線区。 JR 東海は非公表。
ローカル線、平均乗客「1 千人未満」で見直し 国交省会議が目安示す
赤字が続く JR 各社のローカル線のあり方について国土交通省の有識者会議が 25 日、提言をまとめた。 1 キロあたりの 1 日平均乗客数(輸送密度)が「1 千人未満」などの条件を満たせば見直しの対象になる。 廃止は前提とせず、存続やバスへの転換などに向けた会社と自治体の協議を促す。
国の会議が見直しの具体的な条件を示すのは国鉄民営化後では初めて。 1 千人未満の線区は JR 東海を除く JR 5 社で 61 路線 100 区間にのぼる。 特急や貨物列車が走る一部区間を除くなど、1 千人未満でもすぐに対象にはしない。 広域な自治体間での調整が必要なことなども協議入りの条件とした。 結果的に鉄道をやめてバス転換するところも出てくる可能性がある。
地方の人口減や自動車の普及などで JR 各社は多くの赤字ローカル線を抱える。 コロナ禍で都市部の乗客も減り経営は厳しい。 会社側としては不採算路線のバス転換などを進めていきたい考えだ。 存続を求める自治体側の反発は根強く、これまでは協議することも難しかった。 提言では見直しの目安を輸送密度 1 千人未満などとした。 輸送密度は 1980 年代に旧運輸省が国鉄再建法に基づく廃線検討の参考にした指標だ。 バス転換の目安は当時 4 千人だった。
JR 西日本などは近年、2 千人を目安に不採算路線を公表している。 今回の 1 千人未満などの条件は、会社側の従来の目安より人数が少なく、自治体にも一定の配慮をしたかっこうだ。 隣接する駅間の 1 時間あたりの乗客が最大 500 人(一方向)を超える場合は対象から除く。 通勤や通学の利用者が多い路線を守る考え方だ。 県庁所在地をつなぐ特急列車が走る区間や、災害時に貨物列車が物資の輸送を担うところも維持する。 普段の乗客が常に 50 人を下回るなど、極端に利用が少ない路線は積極的にバス転換を検討することにも言及した。
国は鉄道会社や自治体の求めに応じて「特定線区再構築協議会(仮称)」を設置できる。 協議開始から 3 年以内に結論を出す。 「廃線ありき」などの前提は置かない。 これまでの「地域公共交通活性化再生法」では自治体の主導を想定していたが、新しい協議会では国が積極的に関わる。 路線を維持しやすくするため、既存の制度とは別に、柔軟に運賃を決められる新たな仕組みもつくるという。
鉄道からの転換を促す支援策も用意する。 バス導入の実証実験にかかる費用や、バス高速輸送システム (BRT) の専用道の整備などに財政支援が受けられる。 国交省はこうした内容を、今夏の概算要求に盛り込む方針だ。 今回の提言にあたり、国は見直し対象となる区間のデータは出していない。 JR 北海道、東日本、西日本、四国、九州の 5 社が今年までに公表した資料によると、1 千人未満の区間は全体の約 4 分の 1 にあたる 100 ある。 コロナ禍の影響が本格化する前の数字で、現在はさらに増えている可能性もある。 JR 東日本は近く、路線ごとの収支を発表する予定だ。 (松本真弥、高木真也、asahi = 7-25-22)
JR 北、留萌線の 23 年 3 月廃止提案 一部は 3 年存続 続くバス転換
JR 北海道は 21 日、廃止・バス転換方針の留萌線(深川 - 留萌、50.1 キロ)について、石狩沼田 - 留萌を 2023 年 3 月末で廃止し、深川 - 石狩沼田はその 3 年後の 26 年 3 月末で廃止する案を沿線 4 市町(留萌市、深川市、沼田町、秩父別町)に示した。 自治体の一部に部分存続を求める強い声があり、廃止時期をずらした。 提案通りになれば、JR 北が廃止方針の全 5 線区がバス転換される。
今回の案は、JR 北と 4 市町の首長らが秩父別町で開いた会議で示された。 4 市町は JR の案を持ち帰り、住民に説明したうえで賛否を判断する。 会議は冒頭を除き非公開。 終了後取材に応じた山下貴史・深川市長や JR 北の萩原国彦常務によると、JR 側は深川 - 石狩沼田の 26 年までの運行費用負担を自治体に求めないと提案。 代替バス運行費や、廃線後の地域振興の支援金を自治体に支払う方針も示した。
首長からは「これまでの話し合いを踏まえた提案だ(深川市の山下市長)」、「ずいぶん JR に譲歩してもらった(秩父別町の渋谷信人町長)」と評価する声も出たが、存続を強く求めていた沼田町の横山茂町長は「厳しい提案。 存続を願っていたので残念だ。」と語った。 ただ、沼田町内には「地域振興のための 3 年の猶予をもらえた」との捉え方もあり、この案で決着する可能性がある。
JR 北の萩原常務は「一番重要なのは全線の廃止・バス転換に同意してもらえるかどうかだ。 方向性が定まらない状態が続くのは経営に厳しい」と語った。 一部を 3 年間存続させるのは、代替バスの準備期間や、利用する高校生への影響を考慮したためという。 留萌線廃止では、留萌市が 20 年に容認を表明したが、3 市町は深川 - 石狩沼田は通学・通院の利用が多いとして存続を求めていた。 JR 北は、部分存続でも年約 3 億円の赤字で、折り返し駅の整備費にも約 4 千万円が必要としていた。 今回の提案では、これらの費用は JR 側が負担する。
留萌線は JR 北が廃止・バス転換方針を表明した 5 線区の一つ。 12 駅あり、上り 7 本、下り 7 本が運行している。 1 キロあたりの 1 日の平均乗客数を示す「輸送密度」は 19 年度が 137 人、20、21 年度は 90 人と低迷。 21 年度は 2,900 万円の収入に対し 6 億 3,500 万円の経費がかかり、営業赤字は約 6 億円だった。 JR 北は 2016 年 11 月、営業路線の約半分にあたる 10 路線 13 線区を「単独では維持困難」と公表。 特に留萌線を含む 5 線区は利用者が極端に少ないため、廃止とバス転換を求めていた。 5 線区のうち 3 線区はすでに廃止され、根室線の富良野―新得間も沿線 4 市町村が 1 月、バス転換に向けた協議入りを決めた。
他の 8 線区は、住民や自治体と利用促進やコスト削減に取り組みながら存続させる。 JR 北と自治体の費用負担については今後議論されることになる。 (新田哲史、本田大次郎、asahi = 7-21-22)
復旧しても赤字 … 豪雨後の鉄道、再建難航 地方路線の維持は可能か
九州を襲った豪雨で断絶した鉄路の再建が難航している。 採算割れが長年続く JR 肥薩線は、2 年前の豪雨直撃で今も大半が運休したまま。 地元自治体は再建を望むが費用は膨大で、復旧しても赤字運営からの脱却は見通せない。 細る一方の地方で鉄路の維持は可能なのか。 鉄路を諦めた地域ではさらなる衰退への懸念も広がる。(長妻昭明、豊島鉄博、加藤裕則)
SL も走る観光の「生命線」
熊本豪雨から 2 年が経った今月初め、肥薩線の被災現場を訪れた。 つぶれた線路や鉄橋を覆う土砂から、新緑が芽吹いていた。 熊本県南部の八代市と鹿児島県霧島市を結ぶ肥薩線は明治期に開通し、日本三大急流の球磨川沿いを走る観光列車「SL 人吉」は長年、鉄道ファンを魅了してきた。 だが、2020 年 7 月の豪雨で球磨川があふれ、国の近代化産業遺産群に指定された橋梁など約 450 カ所が被災。総延長の 7 割にあたる八代(熊本) - 吉松(鹿児島)の 86.8 キロで運休が続く。
熊本県や沿線自治体は、流失した鉄路の再建を観光再生の「生命線」と位置付けて復旧を熱望する。 だが JR 九州は今年 3 月、復旧費を約 235 億円と試算し、「経験したことがない数字」と強調するなど再建に慎重な姿勢を示している。 鉄路再建をめざす県は、復旧費の減額と国からの財政支援で JR 九州の負担を圧縮し、再建への道筋を付けようと躍起だ。
国は 5 月、肥薩線と並行して走る道路の復旧とセットにしたり、他の補助金と組み合わせたりすることで、JR 九州の負担を最大 210 億円圧縮し、25 億円に減額できると提示。 自治体が設備や土地を保有し、鉄道会社が列車を運行する「上下分離方式」を採ることなどを条件とした。 肥薩線に接続し、豪雨で被災した第三セクター・くま川鉄道の復旧時も上下分離方式を採用し、復旧費を国と沿線自治体が負担することで 25 年度に全線開通する予定だ。 肥薩線の沿線自治体や県は、上下分離方式を「将来にわたって鉄道運行を支える仕組み」と位置づけ、国は JR 九州に対し、再建への働きかけを強める。
沿線住民は 70 年で 8 割減
だが、被災区間は豪雨前の 19 年度に約 9 億円の営業赤字を計上。 被災区間のうち熊本県内の八代 - 人吉駅(同県人吉市)間は 1 日平均の利用者が同年は 414 人で、ピーク時の 1987 年から 8 割減った。 さらに 2020 年以降、コロナ禍が経営を直撃した JR 九州は、採算性を重視する姿勢を強める。 沿線の熊本県球磨村の人口もこの 70 年ほどで 8 割近く減り、地域の利用者減が反転する見通しは立っていない。
肥薩線の復旧を望むのは主に人吉駅前の旅館など恩恵を受ける観光業関係者の一部にとどまり、地元では必ずしも鉄路再建の機運は高まっていない。 通勤や通学、買い物など暮らしの足を支えるのは車で、ひしゃげたままの線路を横目に住民の多くは「肥薩線が復旧しても乗ることはない」と口をそろえる。
「バス」転換受け入れた地域は
地域が先細りを続けるなかで、鉄路の再建は現実的なのか。 豪雨災害を機に別の道を歩む地域もある。 熊本豪雨の 3 年前、福岡県の山あいを走る JR 日田彦山線を、九州北部豪雨が襲った。 北九州市と大分県日田市を結ぶ路線の 4 割超の約 29 キロが不通になった。 6 月下旬、不通区間のほぼ中央に位置する筑前岩屋駅(福岡県東峰村)は、5 年前の豪雨で土砂が流れこんだ線路がはがされ、砂利で覆われていた。 今後、アスファルトで舗装される予定だ。
かつて駅舎から南北に延びていた約 14.1 キロの線路は来夏、バス高速輸送システム (BRT) の専用道路に変わる。 JR 九州が 26 億円を投じて整備し、12 カ所の鉄道駅は「バス停」になる。 筑前岩屋駅近くに住む女性 (36) は「電車がなくなるのは残念だけど、交通手段さえ残れば、バスでも構わない」と割り切る。 豪雨災害の後、沿線の 3 市町村も、肥薩線の沿線自治体と同じように「鉄道での復旧」を望んだ。 中でも最小の東峰村は「車を使わない子どもや高齢者の足であり観光資源としても重要」として、最後まで鉄路存続にこだわった。
だがここでも、当初 70 億円と試算された復旧費とともに、鉄路復旧後に赤字を見込む JR 九州の慎重姿勢が阻んだ。 福岡県による地域振興の基金創設などと引き換えに、村長として BRT への転換を受け入れた渋谷博昭さん (72) は「苦渋の決断だった」と振り返る。 赤字路線、豪雨被害、多額の復旧費 - -。 日田彦山線と肥薩線の課題は、多くの部分で重なる。 渋谷さんは「災害のたびに全国の赤字路線が維持できなくなれば、過疎地域の衰退はさらに拍車がかかる」と懸念する。
JR 社長「国や県と協議」
JR 九州の古宮洋二社長 (59) は 6 月末、朝日新聞のインタビューに応じ、肥薩線の「鉄道での復旧」について、慎重に検討していく姿勢を示した。 肥薩線は、JR 九州の中でも最も美しい風景を持っている。 だが、2 年前の豪雨で駅舎もホームも路線の多くが流され、視察に入った現地で衝撃を受けた。 復旧には莫大な費用がかかるが、沿線の人口は今後も減っていく。 もともと通勤・通学の利用は少なく、観光客向けの週末中心の運行をしてきた。
赤字路線でもあり、復旧しても乗客増が望めないなか、従来の運行を続けるのは非常につらい。 この先も鉄道としての役目があるのかどうか、地元と話し合いたい。 車やバスなど利用実態に合わせた乗り物の姿がある。 (上下分離方式など)地元負担の議論はありがたいが、どこまで出してもらえるのか。 コロナ禍で収入が減り、社員のボーナスも減らしている。 肥薩線のあり方は、補助などもみながら国と熊本県との協議の場で判断していきたい。(談) (asahi = 7-18-22)
ローカル線、東北 19 路線で利用低迷 JR 東が年内に収支公表
JR 東日本は、利用者の少ないローカル線の区間別の収支を年内に公表する。 客観的なデータを基に地方自治体と協議を始め、鉄路に限らない地方交通の形を探る構え。 廃線を警戒する沿線自治体は多く、調整は難航が予想される。 深沢祐二社長が 5 月の定例記者会見で「比較しやすい一つの(公表)基準」と言及したのが、1 日 1 キロ当たりの利用者を示す平均通過人員(輸送密度) 2,000 人を下回る区間だ。 既に収支を開示した JR 西日本は、路線維持が困難とされるこの基準を採用した。
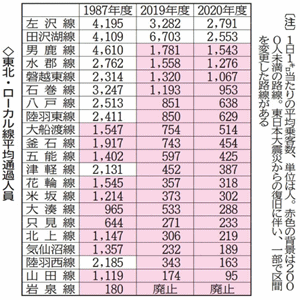
JR 東は 2 月、地方交通網に関する国土交通省の有識者検討会で、2,000 人未満の路線数を示した。 収支が明らかになる線区とは異なる部分もあるが、共通する傾向が読み取れる。 資料によると、2,000 人未満の路線は国鉄が民営化した 1987 年度の 13 から、2019 年度は 24 にほぼ倍増。 新型コロナウイルス禍の 20 年度は 26 に増えた。 東北に関係する路線は表の通り。 19、20 年度いずれも 19 (廃止された岩泉線を含む)が該当した。
新型コロナの影響が少ない 19 年度との比較で、民営化時に 1,357 人だった気仙沼線(前谷地 - 気仙沼)は 2 割弱の 232 人に落ち込んだ。 東日本大震災で被災し、バス高速輸送システム (BRT) を導入した。 2,411 人から 850 人に減った陸羽東線(小牛田 - 新庄)など、東北の 15 路線(岩泉線を含む)が 1,000 人にも満たず経営は厳しいとみられる。
JR 東は公表後、各自治体との協議を通じ、(1) 路線を維持する、(2) BRT を含むバス輸送に転換する、(3) 運行と施設保有を分ける「上下分離方式」を採用する - などの方向性を探る見通しだ。 鉄道各社が収支を公表する背景には、新型コロナ流行で受けた大きな打撃がある。 JR 東では収益の柱だった首都圏の在来線や新幹線の利用者が減り、東北・上信越の線区の赤字を穴埋めする「内部補助構造」が成り立ちにくくなった。
国交省の検討会が沿線の人口減やコロナ感染の状況を踏まえ、地方交通網の再構築策を 7 月までにまとめる動きに合わせて議論を活性化する狙いもある。 深沢社長は「地方交通について各自治体と話してきたが、具体的に協議する場がつくりにくかった。 国の取り組みと並行し、私どものデータを出すことが議論を深める上で必要と考えた。」と述べた。
各県知事、廃線に危機感
ローカル線の区間別収支を開示する JR 東日本の方針を巡り、東北各県の知事は廃線への不安や交通網の在り方を地域と共に協議する必要性に言及した。 「路線の廃止につながるのでないかと、危機感を持たざるを得ない。」 山形県の吉村美栄子知事は 5 月 18 日の定例記者会見で懸念をにじませた。 「県民にとって鉄道は重要な足」と述べ、改めて市町村などと活用法を考えていく意向を示した。
宮城県の村井嘉浩知事は同月 23 日の定例記者会見で、路線の存廃をはじめとする将来の方向性に関し「民間企業であり、経営判断があっていい」と JR 東に理解を示しつつ、「しっかりと地域やわれわれとも話をして進めてほしい」と求めた。 東北 6 県を含む 28 道府県の知事は同月 11 日、黒字路線の収益を赤字路線に振り向けるルールの創設を通じ、鉄道ローカル線の維持を求める緊急提言を国土交通省に提出した。
提言では「ローカル線の廃止は住民の通勤、通学、通院などへの影響が強く危惧される」と強調。 代替交通では運行継続に補助金が必要だったり、慢性的な人手不足に陥ったりする課題があると指摘し「結果として地域の公共交通を失いかねない」と訴えた。 (河北新報 = 6-5-22)
愛知企業、外国人実習生の働く意欲向上へ工夫重ねる
外国人と共生
愛知県の外国人技能実習生数は都道府県別で全国最多の 3 万 4,900 人と全体の 1 割を占める。 自動車産業を中心に製造業が集積しているほか農業が盛んで、安定した雇用を求めて集まっている。 人手不足が深刻化する中、受け入れ側の実習生への依存度も高まっている。 だが、ここにきて他都市や海外との競争で求心力は低下傾向にある。
「少子高齢化や若者の流出で、日本人を雇いたくても雇えない」
菊やキャベツを生産する農事組合法人、アツミ・シーサイドフローラル(愛知県田原市)。 従業員約 20 人のうち、15 人が外国人技能実習生などの外国人が占める理由を福田督代表理事はこう説明する。 1995 年から実習生の受け入れを始め、「今では外国人の実習生に支えられています(福田氏)」という。 インドネシアから来日したアストリ・プラティウィさんは「文化に憧れて日本に来た。 寮も整備されていて、とても働きやすい。」と頭に巻くスカーフ「ヒジャブ」から笑顔をのぞかせる。
「彼らなしでは回らない」 実習生 10 年で 3 倍超に
法務省の在留外国人統計(2021 年 6 月末)によると、全国の外国人技能実習生は 35 万 4,100 人に上り、この 10 年で 3 倍以上に増えた。 名古屋市や豊田市を中心に愛知も同じ 3 倍以上の 3 万 4,900 人となり、東京都の 1 万 1,800 人、大阪府の 1 万 7,700 人と比べても突出して多い。 愛知県内でトヨタ自動車向けに部品を製造しているある企業では従業員 10 人のうち、7 人が技能実習生だ。 工場で働く外国人実習生の男性(20 代)は「できるだけ長く日本で働きたい」と話し、代表を務める男性は「彼らなしでは仕事が回らない」と打ち明ける。
別のトヨタ系中小サプライヤーの社長はコロナの影響で実習生が入国できず「人手不足で生産が追いつかない会社もあるのでは」と話す。 愛知の 15 - 64 歳の生産年齢人口は 45 年には 380 万人に減り、ピークだった 1995 年比で 23% 減の水準になる。 企業や愛知県は女性の活躍推進などを進め、人材の確保に努めるが、新たな労働力として外国人が期待されているのは事実だ。 だが、働き手としての外国人が今後も日本や愛知県を選ぶかどうかは不透明だ。 送り手国の事情が変わりつつあるからだ。
中国は 16 年まで技能実習生の最大の送り手だったが、経済発展に伴い日本行きを希望する実習生は減った。 13 年には中国人技能実習生の数は減少に転じ、21 年 6 月末時点の実習生数は 5 万 5,000 人と、13 年 6 月末の半分の水準まで減った。 さらに、今後は中国国内で人口減少が想定され、外国人労働者の受け入れ国となる可能性が高い。 16 年に中国を抜き国籍別の実習生数で最多となったベトナムでは「最近は韓国行きを希望する人が増えている(愛知県で実習生の受け入れを支援するベトナム人男性)」という。
韓国では自国民と外国人労働者を同水準の待遇で受け入れる「雇用許可制」が定着。 韓国の最低賃金は時給 880 円と、日本(愛知県の最低賃金は 955 円)と近い水準まで上昇しており、就労先としての人気が高まっているという。
他国事例も参考に 企業は独自の誘致策
さらに、国内の受け入れ体制のほころびも目立ち始めている。 愛知では技能実習生に対する違法行為が相次いでいる。 厚生労働省は 21 年、技能実習生を企業などに仲介している団体「アジア共栄事業協同組合(一宮市)」に対して、監理団体の許可を取り消した。 監理団体の義務となっている受け入れ企業の監査をしなかったり、第三者に名義貸しして監査させたりしていた。 愛知県労働組合総連合には 21 年、「暴言暴力」や「解雇強制帰国」などの相談が 91 件、SNS (交流サイト)を通じて寄せられた。
技能実習制度は日本で働き、帰国後に学んだことを母国で生かしてもらう制度だ。 ただ、企業は技術を伝える一方で、実質的に実習生を労働力として想定している。 違法行為が続くようであれば、外国人が日本や愛知を見限ることで働き手を失い、企業の目算が狂うことにもなりかねない。 このため、企業側が実習生に選ばれるための工夫を始める事例もある。 アツミ・シーサイドフローラルでは実習生が自ら効率的な仕事のやり方を考え採用された結果、効果が出れば、臨時手当を出す仕組みを整えた。 帝人子会社の帝人フロンティア(大阪市)は送り出し機関への手数料を自社で負担し始めた。
ニッセイ基礎研究所の金明中主任研究員は「まずは(実習生を仲介する)悪質なブローカーを排除しなければならない。 その上で、韓国が導入した雇用許可制や他国の事例を参考に、外国人労働者の本格的な受け入れ制度を検討する必要があるのでは。」と指摘する。 名古屋出入国在留管理局で 21 年 3 月、施設に収容中だったスリランカ人女性のウィシュマ・サンダマリさんが亡くなり、入管の人権意識の低さが指摘された。 違法行為は論外だが、企業や自治体を含めて主体的にかかわることが重要だ。 外国人の受け入れ環境を整え、協力して働いていく。 中部の競争力を保つにはそれが必須になる。 (nikkei = 2-8-22)