インターネットが「文化資本の格差」拡大させる訳
アクセスの平等は「皆が上手に使える」ではない
問題は「学ぶ意欲はあるが貧しくて学べない優秀な若者をどうするか」ではなく、「文化的貧困のために、学ぶ意欲のない若者が大勢いる現状をどうするか」です。
GAFA の強さの秘密を明かし、その危険性を警告した書籍 『the four GAFA 四騎士が創り変えた世界』 は日本だけで 15 5万部のベストセラーになり、「読者が選ぶビジネス書グランプリ 2019 総合第 1 位」、「ビジネス書大賞 2019 読者賞」の 2 冠を達成、日本に GAFA という言葉を定着させた。
その著者スコット・ギャロウェイ教授の最新作『GAFA next stage?四騎士 + X の次なる支配戦略』が刊行され、発売 3 日で 6 万部のベストセラーになっている。 本書では、コロナ禍でますます肥大化した GAFA とこの 4 社に匹敵する権威を持つようになる「+ X」の巨大テック企業が再び、世界をどのように創り変えていくかを予言している。
ここでは「インターネットの平等性が、逆説的に格差を拡大している」と指摘する作家・ジャーナリストの佐々木俊尚氏に、その見解を聞いた。
GAFA の過剰な富の収奪
ビッグテックには、過剰に富を集めてしまっているという問題があります。 GAFA は従業員がとても少ない企業です。 アップルは、大半がアップルストアの店員ですから、高い収入を得ているのはごく一部の人だけです。 特にアメリカは、富める 1% とその他 99% の格差がどんどん開いています。 トマ・ピケティが『21 世紀の資本』で言ったように、巨大企業から徴税して分配しなければ、格差はなくなりません。
しかし、彼らはタックスヘイブンに逃げてしまい、きちんと税金を納めていません。 日本では、アマゾンが消費税を納めていなかったことが問題視されましたが、そもそも GAFA は、ヨーロッパでほとんど税金を逃れていました。 『GAFA next stage』では、業績がいいときには「成功者が多くを得るのはアメリカンドリームそのものだ」と言っているのに、業績が悪くなると、一変して社会主義的救済を求めるのはどういうことだという痛烈な批判が展開されています。
リーマンショックでも今回のコロナでも、大企業の救済が行われています。 もちろん国家としても大企業を潰すわけにいかないというところはありますが、民意は納得できませんよね。 金銭的な格差だけでなく、メリトクラシー(能力のある人々による支配)という問題が指摘されています。 成功者は、それが自分の能力だと過信してしまいますが、現実には能力だけでなく、運や育ちの良さから、文化的・教育的な環境が左右されているわけです。 でも、そこは忘れられています。 マイケル・サンデルが『実力も運のうち』で述べたとおりです。
日本でも、国立大学の初年度の費用は、入学金と学費をあわせて 100 万円近くになります。 これ以上格差が広がると、社会の活力がなくなっていくのは明らかです。 アメリカ社会は、流動性が極めて落ちています。 実力主義が極度にまで達すると、大学入試でも単に学力が高いだけでなく、高校時代にボランティアをやっていたというような、「人間力」などの基準を求められることになります。 このような課外活動は、アルバイトで学費を稼いでいるような学生には難しい。 そうなると、豊かな家の子どもでなければいい大学に行くのはきわめて困難になっています。
なにより、文化的素養がないと、貧困から抜け出せなくなります。 貧困とは文化的貧困です。 人材流動性を高めるためには、あらゆる人が一定の水準の教育を受けられるようにしなければなりませんが、日本もアメリカもそうはなっていません。
インターネットの「平等」が格差を生む
途上国には、学ぶ意欲はあるが、お金や PC がないという子どもがたくさんいます。 一方、日本は、学ぶ意欲さえあれば、奨学金などが準備されています。 しかし、問題は、学ぶ意欲のない子どもです。 アフリカにも、意欲がない子どもはたくさんいて、麻薬の密売人などになってしまうケースもあります。 日本でも貧困から抜け出せない若者の多くは、学ぶ意欲がありません。
ですから、問題は「学ぶ意欲はあるが貧しくて学べない優秀な若者をどうするか」ではなく、「文化的貧困のために、学ぶ意欲のない若者が大勢いる現状をどうするか」ということになります。 単に E ラーニングなど、インターネットで道を開くだけでは解決にはなりません。 インターネットは自分で情報を取りに行かなければならない世界ですから、結局は、リテラシーの高い人でなければいい情報を得られません。
日本は、識字率は 100% ですが、読解力のない人が多いとわかっています。 誰もが読めるはずの国語の質問を、実は、中高生の 3 割が読めていないのです。 そういう子どもたちに、E ラーニングで大学を目指そうと言っても難しい話です。 また、いろいろな援助や給付金制度がありますが、当事者がそれを知らないということも少なくありません。 身の回りには、パチンコやゲームに没頭する人ばかりで、そういう情報を教えてくれる人がおらず、役所に出向くという発想もない - - 文化的に貧困であるというのは、そういうことなのです。
さらに、インターネットでは、人間関係の格差も生まれます。 SNS で誰をフォローしているかによって違いが出て、なかには陰謀論に染まってしまう人もいます。 インターネットは平等ですが、平等であるがゆえに、たちまち格差化する。 これは人間社会の宿命でもありますね。 それをテクノロジーで乗り越えられるのかは、まだわかりません。 GAFA の存在と同じで、今後はテックを利用できる人とできない人で、格差はどんどん広がるでしょう。
最近は、15 歳ぐらいでデビューするシンガーが増えています。 かつては下積み時代が必要でしたが、今は、自宅で自分で録音して、ユーチューブに公開できます。 優秀な人はあっという間に開花して、どんどん優秀になってゆく。自由であるからこそ、本質的な格差が見えてきたと言えるでしょう。
「望遠鏡的博愛」だけでは解決しない
ここで本書に 1 つ異論があります。 著者のギャロウェイ氏は、動画サービスの企業のうち、ユーチューブは、プライバシーのデータを集めているからよくないという意味で「赤の動画サイト」、一方で、お金を払った人にサービスを提供するネットフリックスは「青の動画サイト」と分けています。 しかし、貧困層から見れば、広告がついていようが、データを収集されていようが、ネットフリックスに月額料金を支払うより、ユーチューブで無料で見られるほうがいいわけで、そのほうが民主的だと言えるのです。
もちろん、常に自由を愛している人にとっては、「プライバシーデータを集めるなんてけしからん」ということになります。 しかし、たとえ企業に誘導されていても、それで文化的生活が維持できるならいいという考えもありえます。 明日の食事にも苦労しているシングルマザーが、せめて子どもに、ユーチューブで好きな動画を見せたいという場合はどうでしょう。 そう考えると、本書を書くほどのギャロウェイ氏であっても、まだまだ貧困層への眼差しが足りないように僕は感じます。
格差と言っても、アメリカと日本は違います。 日本には、アメリカほどの金持ちはいません。 中間層はまだいますが、アンダークラスと言われる層が、急激に落ちていっているというイメージですね。 アンダークラスとは、もともと中間層の下のほうにいた人たちで、シングルマザーなど、非正規になって年収 200 万円以下になった人々です。 生産年齢人口の 3 割ぐらいいますが、あまり可視化されていません。
昭和の頃は、抑圧があって息苦しい社会でしたが、黙々と働いていれば生活が安定する時代でした。 工場の隅で黙々とガラスを磨くなどの単純労働をしている人の姿もありました。 地味に生活していれば、コミュニケーション能力がなくても、家を建てられたわけです。 でも今は、みんなが高度な仕事を求められるようになり、どうしてもこぼれ落ちる人がいます。 こぼれ落ちると結婚もできず、家も持てません。 コミュニケーション能力が低い人は、どう食べていけばいいのかわからないですよね。
本来は、そういうところをテクノロジーで救うことが期待されます。 しかし、得てして「地球温暖化」など大きな話になってしまい、ややもすると「それを言っていればカッコいい」という、金持ちの道楽と化すわけです。 イギリスの小説家チャールズ・ディケンズは、「望遠鏡的博愛」という言葉を残しています。 近くの問題に目をつぶり、遠くの対象を救おうとする態度のことです。 それ自体が悪いとは言いませんが、「SDGs」と言うなら、日本国内に起きている目の前の貧困を見ないでどうするのかと思いますね。 (佐々木俊尚、東洋経済 = 1-20-22)
87 市区町村、人口減脱す 交流深め外国人定住
データで読む地域再生
2020 年国勢調査で人口が増えた市区町村は 324 にとどまる。 高齢化の進展に加え、若年層の都市部への流出や出生率低迷で多くが人口減にあえぐ。 そうした中、外国人や子育て世代に照準を絞った施策などを展開し、新たな住民の呼び込みに成功した地域がある。 劣勢に歯止めをかけ 5 年前の減少から増加に転じた市区町村は 87 あった。 総務省が 6 月末に発表した国勢調査速報で都道府県として人口が増えたのは東京圏(東京、神奈川、千葉、埼玉)ほか、愛知、滋賀、大阪、福岡、沖縄の 9 都府県(15 年の前回比)。 38 道府県は減少し、福島、茨城、群馬、山梨、長野を除きマイナス幅が広がった。
全国 1,741 市区町村のうち人口増の自治体をみると 6 割が 9都府県内。一方、38 道府県でも中核となる都市圏を中心に 131 あった。 人口減を脱した市区町村は 9 都府県が 40。 38 道府県が 47 だった。 共に過疎に指定される北海道占冠村(8% 増)、北海道赤井川村(4% 増)は、海外からスキーリゾートとして注目された機を生かして外国人の定着に力を注ぎ、人口減少から脱却した。 占冠村は 1990 年以来、赤井川村は 95 年以来の人口増となった。
占冠村では 2017 年、フランス系の「クラブメッド北海道トマム」が開業し、外国人が急増(18 年末時点で 42 カ国・地域 393 人)した。 村は入れ替わりの激しい外国人従業員に土地への愛着を持ってもらおうと愛好者が多いボルダリング設備を開設。 無料教室などを通じて住民との交流を深めることに注力した。 利便性を高めるため、役場窓口と診療所に多言語の音声翻訳機も常備。 新型コロナウイルスの感染拡大で外国人従業員は減少傾向にあるが、なお 200 人前後が定住する。 赤井川村でも外国人従業員の生活支援に注力し、感染対策などを説明するパンフレットを英語で配布した。
幅広い支援で移住者を呼び込み 1985 年以来の人口増につなげたのは北海道鶴居村(1% 増、過疎)。 2017 年から酪農家が従業員住宅を建設する場合に 1 棟当たり 100 万 - 150 万円を補助する制度を始め 29 戸を整備した。 従業員住宅に入らない移住者にも住宅新築時に最大 150 万円、空き家購入の場合は最大 110 万円を補助する。 補助金の総額はこれまで 1 億 4,000 万円。 担当者は「主力産業が活性化した上、増えた従業員も村内で消費を増やす」と効果を強調する。
茨城県阿見町(2% 増)、岡山県早島町(2% 増)も、それぞれ 05 年以来、10 年以来の人口増に転じた。 住宅地開発に合わせ小学校入学を迎える児童へのランドセル贈呈や子育てのしやすさなどを訴え、若い世代を呼び込んだ。 一方、大都市圏以外でも人口が増え続けている自治体もある。 山梨県昭和町(7% 増)は 1971 年の町制施行以来、人口増を維持する。 2020 年には 2 万人を突破した。
中央自動車道へのアクセスの良さから企業立地が相次いだことを受け、12 の区画整理事業を推進。 住宅地整備のほか大型商業施設も誘致し、住民を呼び込んだ。 担当者は「多額の資金を投じたが、活性化で元はとった」と話す。 東京など限られた地域への人口集中が加速する中、流れにあらがうのは簡単なことではない。 それでも機を捉え的確な施策を打ち出せば活力を取り戻せる可能性がある。 (asahi = 7-17-21)
利用低迷の芸備線、JR 西日本が地元と存廃視野に協議へ
JR 西日本は 8 日、広島県北部と岡山県を結ぶ芸備線(159 キロ)の利用減などの課題を洗い出すため、一部の沿線自治体に協議を申し入れたと発表した。 今後の話し合いの内容によっては、一部廃止も視野に検討する可能性がある。 コロナ禍による収益悪化を受け、採算が悪いローカル線の見直しが加速しそうだ。
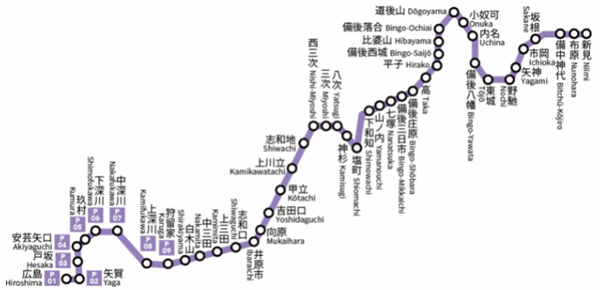
芸備線は、備中神代駅(岡山県新見市)と広島駅(広島市)を結ぶローカル線。 競合する高速道路の整備もあって利用低迷が目立つ。 同社によると、庄原市内と新見市の沿線駅では計 14 駅のうち、2019 年度の 1 日あたりの乗車人員が 10 人を切る駅が 10 カ所にのぼり、0.5 人未満の駅も山ノ内や道後山、備後八幡駅など四つあった。 両市を合わせた人口は 1990 年の約 9 万 3 千人から 19 年は約 6 万 8 千人にまで減った。 備中神代駅 - 備後庄原駅(庄原市)の平均通過人員は 90 年の 12% に落ち込んでいるという。
このため同社は 7 月にも、両市などと沿線地域の利用状況や鉄道以外も含む公共交通の状況などを整理し始める。 広島県にも追って申し入れる見通し。 協議には必要に応じて、地元の交通事業者にも加わってもらう考えだ。
同社が利用データなどをもとに自治体に具体的な議論の場を申し入れるのは初めて。 平島道孝支・岡山支社長は 8 日の会見で、「(検討対象の区間は)特に利用が少ない状態が続き、コロナ禍により課題が鮮明になっている」と説明した。 現状や課題について共通認識を持つための場」で「存続、廃止は議論対象でない」としたうえ、将来的な廃止の可能性も「今からの議論でコメントできる状況にない」と話した。
申し入れを受けた岡山県の伊原木隆太知事は 8 日、「芸備線は地域住民の日常的な移動手段。 沿線自治体と連携しながら対応を検討してまいります。」とのコメントを出した。 蔵原潮・広島支社長は同じく同日の会見で、「決まったものはない」、「廃止ありきではない」と繰り返し強調し、「鉄道利用が減り、地域ニーズに応えられていないのが問題と考え、申し入れをした」と話した。 対象区域を絞ったことについて蔵原支社長は、「距離が長く、区間で事情が異なる。 人口減少や少子高齢化が進み、ご利用が長年減っている区域を対象にした。」と述べた。
一方で利用促進策も検討する考えを示したが、人口減が続く地域で利用者を増やすのは難しい状況だ。 将来的には鉄道以外の公共交通の導入も検討せざるを得ないとみられる。(松田史朗、高橋孝二)
JR 西は以前から、採算が悪化しているローカル線の見直しを進めてきた。 最近では 2018 年に広島県と島根県を結ぶ三江線(108 キロ)を廃止した。 路線廃止となれば、地域の利用者の生活や経済への影響が大きく、地元自治体などとの協議を重ねて慎重に判断せざるを得ない。 このため、同社は新幹線や近畿圏都市部の在来線などの利益を回す形で、ローカル線を維持してきた。
だがコロナ禍で業績が急落し、余裕がなくなりつつある。 長谷川一明社長は 4 月の会見で、路線見直しを加速させる可能性に言及。 「かねてローカル線は利用状況に応じたあるべき姿を模索してきた。 コロナでより鮮明な、喫緊の課題になってきた」と述べた。 同社によると今回の芸備線のほかに、福井県と京都府を結ぶ小浜線や、京都市から山陰地方に延びる山陰線などについても、一部沿線自治体とともに利用状況などの検証を進めている。 いずれも利用者が少なく、駅の無人化やバスなど鉄道以外への切り替えも視野に検討が進むとみられる。
ローカル線以外でもコスト削減を急ぐ。 10 月には、来春に計画していたダイヤ改定の一部を前倒しして、130 本規模の減便を実施する予定だ。都心部でも京都線の高槻 - 京都駅間、神戸線の須磨 - 西明石駅間などが対象になる見込みだ。 同社の 21 年 3 月期決算は、純損益が 2,332 億円の赤字(前年は 893 億円の黒字)となり、過去最大の赤字だった。 (筒井竜平、asahi = 6-8-21)
鉄道はビジネスかボランティアか コロナで露呈した矛盾
コロナ禍で人の移動が減り、鉄道会社の経営が悪化している。 今後は不採算路線の減便や廃止に向けた検討が進む見込みだ。 民間企業が公共交通を担うことの限界が露呈したようにも見える。 鉄道はビジネスとして持続可能なのか。 交通経済学が専門の宇都宮浄人・関西大学教授に聞いた。
- - 鉄道会社は採算が悪い地方路線の見直しを進めています。 どう見ますか。
「鉄道は極めて公益性が高いインフラだ。 なくなれば人の動きが減り、地域が衰退する。 ただ社会全体として望ましいかは別にして、民間企業が不採算路線から撤退するのは合理的選択だ。 インフラの維持を民間に丸投げするのは無理がある。 鉄道は設備維持にかかる固定費が重い一方、地域に与える影響も大きく、自由競争を重視する市場原理では社会全体の最適は導かれない、というのが経済学の常識だ。」
- - それでも多くの路線は、今も鉄道会社の負担で維持されています。
「例えば JR 西日本でいうと、近畿圏のラッシュ時の運賃と新幹線の運賃による利益で、地方の路線を支えている構図だ。 地方路線の維持は、いわばボランティア。 鉄道会社の使命感に依存している。 全く持続可能性のない仕組みだ。」 「インフラ維持を民間企業に押しつけてきたという意味で、国も自治体も沿線住民も無責任だったと言える。 新聞を含めたマスメディアも、企業に使命感を強制するような伝え方が多い。 公的使命を負わせるのであれば、それだけの資源を公的に負担するべきだ。」
「本質的に赤字」の道路 特殊な日本の鉄道事情
- - 鉄道への公的支援はハードルが高い一方で、同じ交通インフラである道路には多額の税金が使われています。
「多くの人が認識できていない事実だ。 膨大な税金を使って道路を整備しても、車が走るのに運賃はとらない。 だから費用は回収できず、本質的には赤字だ。 だが道路の話になると採算感覚が薄れてしまう。」 「日本では法的に、道路は公共事業で、鉄道は民間事業。 列車や線路は企業のビジネスツールという位置づけで、『あなたがもうけたいなら、整備してください』という考え方だ。 鉄道事業単体で利益を出すことが前提となっており、日本ならではの位置づけになっている。」
- - なぜ「日本ならでは」なのですか。
「日本は、私鉄と呼ばれる民間の鉄道事業者が利益を生み出せた世界的に希少な事例だからだ。 車が普及する前の 20 世紀初頭までは、海外でも鉄道がビジネスとして興隆した時期はあった。 ただ現代においてインフラ管理も含めた鉄道事業を民間が担い、利益を出すモデルを形成できているのは日本だけだ。」
- - なぜ日本では利益を生み出せたのですか。
「1960 年代の高度経済成長期に、ほかの先進国では見られない速度で人口が増えた。 その結果、都市化が進み、地価はほぼ右肩あがりだった。 私鉄会社は沿線で不動産事業を展開すれば、人が住み着き、地価も上がって投資額が回収できた。 それどころか利益が出た。」 「人口密度が高いことや、車の普及が欧州より遅れたことも、鉄道事業にプラスだった。 こういう極めてまれな条件下で、日本の鉄道会社は海外の研究者が驚くような収益をあげた。 旧国鉄が分割民営化された後は、JR 東日本や JR 西日本なども黒字経営を続けてきた。」
- - 海外は違うのですか。
「欧州では鉄道の赤字は当然で、線路などの設備を民間が保有するなど考えられないことだ。 もともと日本の旧国鉄と同じように国の事業として鉄道は運行されていた。 20 世紀半ばには車の普及によって斜陽となり、日本のように私鉄が育つこともなかった。」 「国有の鉄道事業は長年非効率なままだったが、70 年代後半以降に英サッチャー政権、米レーガン政権が誕生し、市場原理を重視する新自由主義的な考え方が広がった。そこで出てきたのが、『上下分離』という手法だ。」
「車一辺倒」欧米で見直し
- - 線路などの設備の維持管理を国や自治体が担い、運行を民間が担う方法ですね。
「そうだ。 欧州は道路と同じようにインフラは公的に管理し、その上を走るサービス提供は民間に委ねていくことにした。 80年代後半にスウェーデンの国鉄が上下分離したのを皮切りに、今では各国に広く浸透している。」
- - 日本では、設備も民間が保有する「上下一体」の方式が一般的です。
「例えるなら、バス会社が道路や信号を全部自分で整備してもビジネスとして成り立つような状況だったと言える。 ただ以前から地方路線は重荷になっており、それがコロナ禍で鮮明になっている。」
- - 今後はどうするべきでしょうか。
「民間で負担しきれないところは上下分離を進めるべきだ。 ただ旧国鉄を分割民営化した経緯があるので、鉄道を公的に支えることは『後退』に見える側面があり、国などからの抵抗感は根強い。 ではどうするのか、他の手段を見いだせないまま、民間に依存し続けているのが現状だ。 それでは持たない。」 「欧州では、上下分離しても運行事業者が見つからない場合、行政が公共サービスとして支援することを前提に、民間企業と契約して効率的な運行を促す手法が確立されている。 運行部分まで公的支援をする点で上下分離よりも踏み込んだ手法で、PSO (パブリック・サービス・オブリゲーション、公共サービス義務)と呼ばれる。」
- - 不採算の路線は上下分離し、もうかる路線はこれまで通りとなると、鉄道会社は「いいとこ取り」にも見えます。
「鉄道会社がひとつの民間企業である以上、利益を求めるのは当然で、不採算の路線を抱え続ける方がナンセンスだ。 民間で成り立つ地域は、今のまま民間に任せればいい。 それでこそより良いサービスになるし、より効率的な運営ができる。」
- - 鉄道のあり方が改めて問われそうです。
「脱炭素の観点からも見直しが必要だ。 欧州では鉄道を含む公共交通への再投資が、脱炭素に向けた重要施策に位置づけられている。 圧倒的な道路大国の米国でさえ、バイデン政権が今春発表したインフラ投資計画で、鉄道に多額の資金が投じられることになっている。」 「欧米では車一辺倒の社会を変える動きが活発化しており、すでに日本は半周遅れの状況だ。 コロナ禍の影響で、鉄道が抱える課題を直視せざるを得なくなっており、今が本気で議論するべきタイミングだ。」 (聞き手・筒井竜平、asahi = 6-1-21)
☆
〈宇都宮浄人(うつのみや・きよひと)〉 1960 年、兵庫県西宮市生まれ。 京都大経済学部を卒業後、84 年に日本銀行入行。 金融研究所歴史研究課長などを歴任し、2011 年から関西大経済学部教授。 専門は交通経済学。著書に「鉄道復権」など。
地方都市の鉄道も「上下分離」 支援なしでは厳しい経営
列車の運行を鉄道会社、線路といった維持管理は自治体などが担う「上下分離方式」の導入が相次いでいる。 維持管理の負担を減らす仕組みで、過疎地で採り入れるケースが多かったが、コロナ禍による鉄道会社の業績悪化などで自治体の支援が必要となった地方都市の路線にも拡大。 規模にかかわらず、鉄道はあり方そのものの見直しを迫られつつある。 (神山純一)
「鉄道があるから、生活できる。 なくなったら本当に不便になる。」 3 月末、滋賀県東近江市にある近江鉄道八日市駅で電車を降りた同市内のパート女性 (66) は話した。 週 3 日、掃除の仕事で同県彦根市内の駅に通うが、車が運転できないため、鉄道が欠かせないという。
乗車人員は 50 年前に比べて 6 割減
県東部を走る近江鉄道(彦根市)は、営業距離が約 60 キロ。 沿線には企業や高校、大学も多い。 しかし昨年末、沿線自治体が施設を保有し、同社が運行を担う「上下分離」に 2024 年度から移行すると決めた。 服部敏紀・構造改革推進部部長は「JR との接続をよくするなど利便性の改善に取り組んだが、黒字見通しが立たなかった」と説明する。 鉄道部門は 1994 年度から 27 年連続の営業赤字の見込み。 18 年度の乗車人員は約 483 万人で 50 年前に比べて6割減った。 人件費を削減し、駅の大半を無人化するなどコスト削減を加速。 06 年と 08 年には、大企業の工場前に駅を設けて通勤客を増やし、電車に自転車を持ち込めるようにして観光客にアピールしたが、赤字脱却できなかった。
運賃を値上げしようにも、並走する JR 西日本に比べてもともと割高で、これ以上は難しいという。 県に相談して、19 年に沿線 10 市町などと協議の場を設置。 鉄道を廃止してバスに替える検討もされたが、輸送力のある鉄道のコストの安さから存続に。 現在、年間約 6 億円の設備投資と修繕費用がかかるが、上下分離後の金額を精査しなおし、県と沿線 10 市町で半分ずつ負担する予定だ。 同社は「負担の大きい維持管理費用がなくなれば『攻めの経営』をめざせる(服部部長)」とし、ラッシュ時間帯の増便の検討やバスとの接続の改善などを進める方針という。
三毛猫の「たま駅長」で知られる和歌山電鉄(和歌山市)も、和歌山市・県などに上下分離への移行を求めている。 06 年に南海電鉄貴志川線(14.3 キロ)を引き継いだ。 鉄道設備の更新費用は県や地元自治体から一部補助を受けるが、17 年度から赤字が続く。 コロナ禍で 20 年度は売上高が 3 - 4 割程度減り、さらに業績が厳しくなる見通しだ。 礒野省吾専務は「コロナ禍で経営はもうもたない。 このままでは鉄道をなくすしかなくなる。」と危機感を語る。 県、市などとの協議入りを急ぎたい考えだ。
国土交通省によると、コロナ禍の影響を受けた中小の鉄道会社の 19 年度決算は、95 社のうち 8 割近い 74 社が経常赤字となった。 上下分離は、これまで鳥取県東部の 19.2 キロを走る若桜(わかさ)鉄道(若桜町)や、京都府から兵庫県北部にかけて総延長 114 キロを結ぶ京都丹後鉄道(京都府宮津市)など利用減の激しい過疎地で導入されてきたが、より広い地域で事業維持の手法として使われそうだ。
大手の鉄道会社でも路線のあり方を見直し始めた。 コロナ禍で経営が厳しい JR 西日本の長谷川一明社長は今月 14 日の会見で、「かねてよりローカル線は利用状況に応じたあるべき姿を模索してきた。 コロナでより鮮明な、喫緊の課題になってきた。」と発言。 路線廃止も含めた議論を自治体に呼びかける方針だ。 同社は 18 年に広島県と島根県を結ぶ三江線を廃止している。 JR 四国の西牧世博(つぐひろ)社長も 3 月末の会見で赤字路線の存廃にふれ、「5 年以内に廃止はないと思うが議論は別。 なるべく早く始めたい。」と述べた。 今後、鉄道事業をどのような姿で残していくのか。各社は岐路に立たされている。
地方路線の現状は? 専門家に聞く
鉄道の運行と施設保有を分ける「上下分離方式」の導入を模索する鉄道会社が増えている。 それはなぜなのか。 行政や鉄道会社で長年、まちづくりと交通政策に携わってきた一般社団法人グローカル交流推進機構の土井勉理事長 (70) に、地方路線の現状や経営の立て直しに向けて必要なことを聞いた。
- - なぜ、上下分離方式を導入する鉄道会社が増えているのでしょうか
「人口が増加した時代の鉄道会社は、沿線開発を進めて住宅を広げ、通勤通学の利用客を増やすことができた。 しかし近年は、地方の県庁所在地に拠点を置くような鉄道会社でも沿線人口が縮小した。 収入が減ったため、線路や駅舎の修繕費用をまかなうことが厳しくなってきた。」 「コロナ禍による在宅勤務の普及など、生活様式の変化も打撃だ。 地方を走る鉄道は、通勤や通学の利用客の比重が高い傾向にあるからだ。 地域鉄道で黒字を出せる会社は全国で 3 割程度と限られ、自治体が鉄道を存続させるためにお金を含めて支援をする必要性が高まっている。」
- - 自治体が民間の鉄道会社を支援しなければならないのでしょうか
「経営が悪化してから上下分離しても、鉄道の利便性を上げるための投資にお金を回せない。 これでは不便な鉄道を残すだけになり、地域のためにならない。 自治体が支援して、列車の本数を増やしたり、観光客を呼び込むキャンペーンを打ったりと、利用者拡大のための経営的な余力を持たせることが重要だ。」
- - 費用負担の大きい鉄道ではなく、バスなどほかの移動手段に替えてもよいのではないですか
「近江鉄道(滋賀県彦根市)の場合、利用客の約 3 分の 2 が通勤通学客で、朝夕のラッシュ帯の大量輸送は、バスでは代替できない。 利用客が少ないからといって廃線を進めれば、街の中心地である駅がなくなり、活気が失われる。 さらに人口が減る悪循環に陥るだろう。」
- - 財政負担に対して、自治体には抵抗感もありそうです
「鉄道がなくなれば、通勤や通学、病院通いや買い物などで利用する人々の移動を行政が支えなければならないが、その負担額は上下分離の拠出額よりも大きくなる。 鉄道を生かしたまちづくりなど、地域の活力に寄与させる仕組みをつくることが大事になる。」 「負担をしても投資回収するつもりで、駅前の活性化に取り組むべきだ。 駅の利用客が増えれば駅前の資産価値が上がり、自治体の固定資産税が増え、財政が潤う可能性もある。」
- - 上下分離に移行した後の鉄道会社に求められることは何ですか
「自治体の支援を受けるだけで終わってしまえば、沿線住民からの視線は厳しいものになる。 社員が沿線の全世帯を回り、顔なじみの関係になることが重要だ。 ダイヤの要望をすくい上げるなどして、利便性の高い鉄道に変えていく必要がある。」 (聞き手・神山純一、asahi = 4-18-21)
集落で最後の 1 人、浮かぶ「消滅」 もう目指さぬ人口増
1 億 2,427 万 1,318 人。 総務省が 8 月 5 日に発表した今年 1 月 1 日時点の日本人の数である。 前年から 50 万 5,046 人減り、減少幅は 1968 年の調査開始以来、最大となった。 中核市規模の都市が丸々消えた勘定になる。 社会の中軸となる 15 - 64 歳のいわゆる「生産年齢人口」は日本人全体の 6 割を切り、過去最低を更新した。 東京、神奈川、沖縄以外の道府県がすべて人口減少の坂道を下っているなか、地図から消えようとしている地区は全国にある。
そんな里の一つ、徳島県つるぎ町の旧一宇(いちう)村にある十家(といえ)集落を昨冬、訪ねた。 最後の 3 キロは車が通れず、山道を歩くしかない。 老いた両親から畑を引き継ぐため集落に戻ってきた上家(かみけ)敏一さん (62) は、数年前からここに 1 人で住んでいる。 父は亡くなり、足を痛めた母親が弟とともにふもとに下り、高齢住民たちも次々と去った。
コロナ禍を経た最近の様子を電話で尋ねると、こう話した。 「1 カ月間、誰とも話さず、寂しい時もあるが、コロナに感染する心配はない。 こういう状況だと 1 人がええでよ。」 一宇村は 15 年前、2 町と合併してつるぎ町になった。 戦後の最盛期には 8 千人近い住民がいたが、現在は 700 人余。 現在残る 32 集落のうち、半数以上の 19 集落で、いずれ住民がゼロになるとみられている。
総務省などによる昨年の調査によると、「いずれ」または「10 年以内」に無居住化の恐れがあると自治体が答えた集落は全国で 3197 に上った。 徳島県だけで 267 集落が消える。 6 年前、「消滅」という言葉が列島を揺さぶった。 世界に先駆けて急激な人口減少と少子高齢化に直面している日本は、いわば「限界先進国」状態です。 人が消える現実を見据え、どう縮んでいくのか。正面から考えます。
増田寛也元総務相が座長を務める日本創成会議が、急激な人口減少が予測される 896 自治体を「消滅可能性都市」と位置づけたためだ。 全国の市区町村の約半数が該当し、慌てて対策を立てたが、それでも各地で集落は消え続ける。
「平成の大合併が、追い打ち」
2002 年のサッカーワールドカップ日韓大会で、カメルーン代表のキャンプ地になった大分県の旧中津江村にある宮原地区に、西ヤス子さん (85) はたった 1 人で住んでいる。 「あと 10 年もすれば、誰もおらんごとになる。 家近くのお社、天満宮さんの手入れをする人がいなくなるのだけが気がかりだねえ。」 数年前に同世代の女性が老人ホームに入居し、1 人になった。 自分がいなくなれば、この集落は閉じる。 旧中津江村で自治会長をつとめる津江良治さん (73) は、衰退の理由に心当たりがある。 「平成の大合併が、追い打ちをかけたんです。」
「村の終わり」を前提に準備
大分県の旧中津江村が近隣の日田市と合併したのは、15 年前のことだった。 合併時に 1,312 人だった人口は、今年 7 月末現在で 731 人と半分近くまで減った。 高齢化率は 50% を超え、合併後に消滅した集落もある。 「村役場は市役所の出先になって何もできなくなった」と自治会長の津江良治さん (73) は言う。 50 人以上いた役場の職員は出先である振興局の 10 人ほどに。 以前はすぐ対応してくれた住民の要望も、今では「本庁に確認します」と言われる。
一昨年、住民全員がメンバーの自治組織「中津江むらづくり役場」を作った。 合併前の村を復活させ、高齢化と人口減少にあらがう目的かと思ったら、事務局長の永瀬英治さん (58) は予想外のことを口にした。 「狙いは、村をいかにソフトランディングさせるかです。」 中心部にある事務所を開放し、死亡後の行政手続きやエンディングノートの付け方、葬儀の段取りなどを講習する。 他の地域のように、移住者による人口増は目的にしていない。
刻々と近づく村の終わりを待つだけでは、と問うと津江さんは答えた。 「だって若い人にマッチングする働き口も買い物する場所もないですから。 今いる人たちが穏やかに暮らすことを考えた方がいい。」 人を増やす努力をしても、もう遅い。 人口減の最前線にいる人々の多くは、そう気付いている。 「以前は駄目だった時のことを考えてはいけない雰囲気があった。 だが今は後退してでも大切なものを守る方法を考えなければ。」
住民がいなくなった「無住集落」を研究する金沢大学の林直樹准教授は説く。 「以前の過疎は恵まれていた。 局所的に人が減っても国の経済は膨張し、地方へお金が流れたから。 真に厳しいのは、日本全体で人が減るこれからです。」
いまや日本は「消滅可能性国家」
国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、2045 年に日本の総人口は 1 億 642 万人となり、15 年から約 16% 減少するが、4 割以上人口が減る市区町村は 688 自治体、約 41% にも上る。 若者を中心に大都市へ人口が流出し、地方の出生数を押し下げる構図は変わっていない。 それでも、人口減を前提にした地域づくりは自治体の首長にとって難題だ。 「我がまちは縮小します」と選挙で公言するのは難しい。
そんな中、「人口増をめざしても意味がない」と主張しているのが、愛知県新城(しんしろ)市の穂積亮次市長 (67) だ。 05 年の国勢調査で約 5 万 2 千人だった人口は、10 年間で 5 千人減った。 県内の市で唯一、「消滅可能性都市」に挙げられた。 穂積氏は 17 年の市長選で「人口の V 字回復」を主張する対立候補を批判して 4 選を果たした。 「いずれは日本全国で減っていくのだから、自治体間の人口の奪い合いにしかならない。」
新城市では人口減少を見越し、公共施設の廃止と統合も検討している。 今年 1 月、シンポジウムで市民の意見を聞いたところ、「残してほしい」との意見が出た一方で、施設の廃止を認める声も上がった。 穂積氏は人口減をジェットコースターに例える。 同市のように人口が減り始めた自治体はコースターの先頭で、後部の首都圏はまだカタカタと上っている。
「ある瞬間、最後尾の東京も含めて国全体が猛スピードで落下する。 その前に地方分権を進め、地域に合った方策を自立的に立てられるようにしてほしい。」 例えば新城市では、現役世代が減る分、高齢者の年金収入を域内で循環させ、その資金によって若者の起業を支える仕組みを作ることなどを考えている。 同市のように自治体が独自のプランを立てて人口減少に向き合いやすくするには、分権を進め、財源や権限を地方に移すのが効果的だ。 地方分散型の国土作りは、首都圏への人口流出を抑えることにもつながる。
日本創成会議が 6 年前に提言したのも、やはり東京一極集中の解消だった。 だが、その後も状況は改善しておらず、18、19 年の東京圏への転入者は転出者を約 14 万人上回った。 その東京ですら、推計では 10 年後から人口減少が始まる。 同会議メンバーの一人、明治大の加藤久和教授は言う。 「出生率が高い地方から、低い首都圏への人口流出を食い止められず、いまや日本全体が『消滅可能性国家』になっています。」 人口減少という後退戦にどう立ち向かうか。 各地の「消滅可能性」地域のみならず、この国のあり方そのものが問われている。 (菅原普、上田学、宮沢崇志)
<視点>
地方分散、やったふりでは変わらない
新型コロナウイルスの感染拡大は、わずか数カ月で人々の生活を非日常にたたき込んだ。 一方、人口減少は 10 年単位で日本社会の土台をむしばんでいく。 感染症と闘う間も、その時計は決して止まらない。 現在の日本は、親となる世代が減ることで「縮小再生産」に陥っており、昨年は 50 万人の日本人が消えた。 人口推計は非情なほど精度が高く、今後出生率が回復したとしても、少なくとも半世紀は人口が減り続けることが避けられない。
多くの自治体にとって消滅は絵空事でなく、インフラの縮減を前提に地域づくりを考えざるを得ない。 他方、東京では高齢者の絶対数が増え、医療介護分野で空前の人手不足が起きる。 危機はコロナ禍でさらに深まるだろう。 景気後退が続けば、子を持つ余裕のない人が増える。 感染予防で国家間の往来は細り、外国人労働力の導入はより難しくなる。 これからの日本は、二正面作戦を強いられる。 人の減少と高齢化に耐えうる柔軟な国の仕組みを築く一方で、将来の人口減を緩やかにするため、社会のあり方自体を変える必要がある。
そのための鍵となる言葉が「分散」だ。 戦後日本は東京にヒトとカネを集めて経済成長を成し遂げたが、全国から若者を呼び寄せることで地方の縮減が進み、少子化を加速させた。 東京は人口を吸い込むブラックホールとも言われる。 コロナは、そんな人口密集社会の脆弱性を浮き彫りにした。 テレワークの進展でビジネス面でも地方分散が現実味を帯びている。 これは、極端な東京一極集中を改める転機になる。
人口減少と少子高齢化は、北朝鮮情勢と並ぶ日本の国難だと宣言し、安倍晋三首相が衆院を解散したのは 3 年前。 今年 7 月 15 日に開かれた地方創生の会議で、安倍首相は再び述べた。「集中から分散へ。 日本列島の姿を今回の感染症は根本から変えていく。 その大きなきっかけにしなければ。」 看板を掲げるだけでは、何も変わらない。 今後数十年、人口減と高齢化に耐えながら、現在のような社会の活力をどう保つか。 ポストコロナに向かい、この国が抱えた重い宿題である。 (編集委員・真鍋弘樹、asahi = 8-27-20)