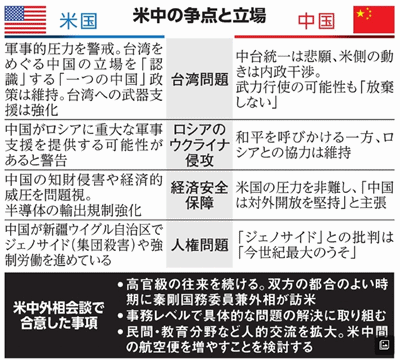中国がトランプ政権に報復措置、石炭など追加関税 対立激化の懸念も
中国政府は 10 日、米国から輸入する石炭や液化天然ガス (LNG)、大型自動車など 80 品目に 10 - 15% の追加関税を発動した。 国営中央テレビ (CCTV) 傘下のメディアが伝えた。 合成麻薬の米国への流入を不満としてトランプ米政権が全中国製品に 10% の追加関税を課したことへの報復措置。 日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、今回、追加関税の対象となる品目の米国からの輸入額は 140 億ドル(約 2 兆 1 千億円)規模で、米国からの輸入総額 1,643 億ドルの 8.5% にとどまる。 エネルギーや自動車など米国の主要な輸出品を狙ってはいるものの、以前に比べれば中国側の出方は抑制的だ。
第 1 次トランプ政権時の 2018 年、米国が「不公正な貿易慣行」を理由に産業機械など 340 億ドル相当の中国製品に 25% の制裁関税の「第 1 弾」を課した際には、中国も大豆など同額の米国製品に同率の追加関税をかけて対抗。 その後、関税の応酬となり米中対立は激化した。
今回、追加関税の対象範囲を米国より限定的にとどめると同時に、中国は「率先して貿易紛争を引き起こすことはせず、対話と協議を通じて問題を解決することを望んでいる(中国商務省の何詠前報道官)」と対話姿勢を崩していない。 中国経済は不動産不況が主因となり内需が低迷し、外需への依存度が高まっており、経済を傷める「関税合戦」の先鋭化は望んでいない。
ただ、「一方的な行為に対しては、我々の権利と利益を断固守るために必要な措置は必ずとる(同省)」とも強調する。 トランプ氏は習近平(シーチンピン)国家主席との首脳協議について「急がない」と述べている。 また、「中国と合意できなければ、関税はとても大きなものになる」とさらなる引き上げもちらつかせる。 トランプ氏は対中 60% 関税も主張しており、米国の出方によっては第 1 次トランプ政権時のような関税の応酬となるおそれもある。 (北京・鈴木友里子、asahi = 2-10-25)
中国、重要鉱物を対米禁輸 ガリウム、アンチモン … 半導体規制に対抗
中国商務省は 3 日、高性能半導体に使われるガリウムなどの重要鉱物について、米国への輸出を原則禁止すると発表した。 米商務省が前日、中国向け先端半導体の輸出規制を強めたことを受け、ただちに対抗措置に出た。 中国が生産シェア 9 割以上を握るガリウムをはじめ、半導体や電気自動車 (EV) に欠かせない重要原料の輸出が止まれば、米国内外に幅広い影響が出る可能性がある。
中国商務省はガリウムやゲルマニウム、アンチモンなどの重要鉱物について、今後は原則として米国への輸出を認めないとした。 「輸出管理法」に基づき、軍事にも転用できる軍民両用品の輸出管理を強めるとしている。 第三国を経由した輸出も禁じる。 EV 向け電池の材料となる黒鉛の対米輸出も、利用者と使い道の審査を厳しくする。 半導体の輸出規制を強める米国に対抗するため、中国は昨年 8 月にガリウムとゲルマニウムの、同 12 月には黒鉛の輸出をそれぞれ許可制にした。 今回、米国が半導体輸出規制をさらに強めたことを受け、一段と踏み込んだ措置をとる。
中国商務省は「米国は輸出管理措置を乱用し、関連製品の対中輸出を制限し、多くの中国企業を制裁リストに含めて企業の合法的な権利と利益を害した」と批判した。 米地質調査所によると、2023 年の世界の生産量のうち、中国はガリウムで 9 割以上、アンチモンでは 5 割を占める。 対米輸出が止まれば米国のサプライチェーン(供給網)への影響は必至だ。 第三国経由での輸出も禁じられることで、日本などにも影響が及ぶ可能性がある。 米政府は 2 日、先端半導体の輸出規制を強化。 規制対象となる企業リスト「エンティティーリスト」に、中国の半導体関連企業など新たに 140 社を加えたと発表していた。
先端半導体の製造装置やソフトウェアの輸出規制を強めたほか、高速でデータ処理ができる「広帯域幅メモリー」でも新規制を打ち出した。 米国の対中規制は外国企業も対象としている。 次世代軍事システムや人工知能 (AI) に使える先端半導体について、中国での開発を遅らせる狙いがある。 (北京・鈴木友里子、サンフランシスコ・五十嵐大介、asahi = 12-3-24)
米政府、中国製 EV 「関税 100%」は 27 日から 4 倍に引き上げ
米政府は 27 日から、中国から輸入する電気自動車 (EV) にかける制裁関税を、従来の 4 倍の 100% に引き上げる。 EV 用充電池も従来の 7.5% から 25% に、鉄鋼・アルミニウムは 0 - 7.5% を 25% に、それぞれ同日から引き上げる。 補助金に支えられた中国の安すぎる製品の流入を阻み、国内産業や労働者を守るための措置という。
米通商代表部 (USTR) が 13 日、発表した。 これらの輸入品の関税引き上げは本来は 8 月 1 日に始めるはずだったが、中国製品を輸入している米産業界との調整に時間がかかり、引き上げ時期を延期していた。 米政府はこのほか、半導体の関税は 2025 年 1 月から、一部の重要鉱物の関税は 26 年の 1 月から、それぞれ税率を引き上げる方針だ。 いずれも重要物資として米政府が過度の中国依存を問題視しており、調達先の多様化をめざしている。 (ワシントン・榊原謙、asahi = 9-14-24)
カナダ、中国製 EV に追加関税 100% 米欧に追随、中国は反発
カナダ政府は 26 日、中国製の電気自動車 (EV) に 100% の追加関税を課すと発表した。 トルドー首相は会見で、中国製 EV は不公平な政府補助を受けているとして「カナダの重要な産業の安全を脅かし、勤勉な労働者を追い出している」と批判。 「これに対処するために行動を起こす」と主張した。 10 月から現在の 6.1% の関税に上乗せする。 また、中国からの鉄鋼とアルミニウム製品にも 25% の追加関税を課すという。
中国製 EV については、米国が 5 月に関税を 25% から 100% に引き上げる方針を発表したほか、欧州連合 (EU) も最大 36.3% の追加関税を課す予定で、カナダも追随する。 欧米各国は、中国製 EV が政府の巨額支援によって過剰生産されていると主張している。 安価な EV が自国に大量に輸入されれば、自国の産業や雇用が打撃を受けるとの危機感がある。
カナダでは、とくにオンタリオ州は米国の「自動車の街」デトロイトに近く、自動車産業が集積している。 また、カナダ財務省によると、鉄鋼とアルミ産業には 13 万人以上の労働者がいるという。 カナダ政府の発表に対し中国商務省は 27 日、「強い不満を抱いており、断固として反対する。 中国はカナダの誤ったやり方を直ちに是正するよう求める。 中国は中国企業の正当な権利と利益を断固として守るため、あらゆる必要な措置をとる」などとする報道官談話を発表した。 (ニューヨーク・真海喬生、asahi = 8-27-24)
米中関係に改善の余地なし、台湾や南シナ海で対立 - 中国学会が懸念
11 月の米大統領選を控え、中国の学会で米国との 2 国間関係が激動期にあるとの見方が強まっている。 長期的な関係改善について懐疑的な考えすらある。 週末に北京で開催された清華大学主催のフォーラムでパネリストらは、米中間の緊張が台湾や南シナ海を巡る紛争でも高まり得ると述べた。 清華大学戦略・安全研究センターの達巍主任は 7 日、「2 国間関係を安定させるのはもう限界かもしれない」と指摘。 根本的な不信感が非常に強く、「もしこのままの軌道をたどれば、われわれは徐々に別の危機やある種の対立へと向かっていくことになると思う」と語った。
米大統領選を争うバイデン大統領とトランプ前大統領はいずれも、対中強硬姿勢を有権者にアピール。 米国の雇用を守るとし、貿易関税の強化をちらつかせている。 バイデン大統領と中国の習近平国家主席が昨年 11 月にサンフランシスコ近郊で会談し、米中関係はいったん安定したが、南シナ海での中国の威嚇的な行動と、中国からの安価な輸出の急増が新たな緊張をもたらしている。 清華大学国際関係研究院の閻学通院長は先週、今回のフォーラムが始まる前の記者会見で、米大統領選のキャンペーンも一因となり「今から 2025 年前半にかけて、22国間関係は改善するよりも悪化する可能性の方が大きい」との予想を示した。
中国と米国は地政学やテクノロジー、貿易などの問題を巡り衝突を続けている。 カーネギー国際平和財団のダグラス・パール研究員は、南シナ海が米中関係の最も危険な部分に変わるかもしれないと警告した。 中国とフィリピンは南シナ海の南沙(英語名スプラトリー)諸島付近で衝突。 フィリピン軍西部方面隊のトーレス司令官によれば、南沙諸島アユンギン礁(英語名セカンド・トーマス礁)の軍事拠点に物資を補給していた先月中旬、中国海警局の職員が作業用のゴムボートに「不法」に乗り込み、ボートにあった銃器を押収・分解した。
中国海警局が銃器を「略奪」、南シナ海での衝突時 - フィリピン軍
パール研究員はアユンギン礁を巡る「争いは対立する立場をどう扱うかについてのメカニズムや理解が欠けているため、米中衝突の危険性が南シナ海でより高くなる可能性があることを示している」とフォーラムでパネリストとして発言した。 (Bloomberg = 7-8-24)
◇ ◇ ◇
米テキサス州知事、台湾と経済協力趣意書に署名 - 半導体分野など想定
台湾を訪問中の米テキサス州のアボット知事は7日、郭智輝経済部長(経済相)と会談し、経済協力に関する趣意書に署名した。 アボット知事は半導体とエネルギー、電気自動車(EV)製造を含む重要産業分野に双方が協力できる機会が存在すると強調した。 「テキサス州でも米国でも、われわれは強い台湾が世界全体の将来にとって重要だと理解している」と署名式で発言。テキサス州が台湾に代表事務所を開設することも明らかにした。同州が今世紀に入り海外拠点を新たに設けるのは、メキシコ以外では初めて。 アボット氏はこれに先立ち、台湾の頼清徳総統とも会談した。 (Yian Lee、Bloomberg = 7-7-24)
米国で TikTok 「禁止」法案、成立 違憲訴訟起きる可能性も
中国系企業が運営する動画投稿アプリ「TikTok (ティックトック)」の全米での利用禁止につながる法案が 24 日、成立した。前日に米議会上院で可決された法案に、バイデン大統領が 24 日署名し、成立させた。 米国で 1.7 億人が利用するとされる人気アプリだけに、是非をめぐって激しい論議を呼びそうだ。 610 億ドル(約 9.4 兆円)規模のウクライナ支援などが柱の法案に、TikTok に関する規定も盛り込まれた。 下院では可決済みで、上院でも 23 日賛成、79 票、反対 18 票の賛成多数で可決された。
米国では、TikTok のアプリを通じて、米国の情報が中国に漏れたり、中国共産党の宣伝がまんえんしたりするといった懸念が、党派を超えて広がっている。 この法律は、TikTok の親会社の中国企業バイトダンスに対して、最長で年以内に TikTok の米国事業を非中国企業に売却するよう求める。 応じなければ米国でのアプリ配信をできないようにする。 事実上の利用禁止となる。 一方で、TikTok の利用者は、若者を中心に 1.7 億人に及ぶとされる。 芸術表現の発表の場として使う人に加え、700 万の中小企業や個人事業主らが事業の PR などに使っているともされ、今回の法律に対する利用者からの風当たりは強い。
米国憲法修正第 1 条が定める「表現の自由」に抵触しかねず、違憲訴訟が起こされる可能性も大きい。 TikTok 側が提訴し、この法律に抵抗するのはほぼ確実だ。 米紙ニューヨーク・タイムズは、TikTok 事業を買い取るにしても、数百億ドル規模の資金が必要になるとの見方を報じた。 グーグルやメタ(旧フェイスブック)など資金力がある米テック大手による買収は反トラスト法(独占禁止法)が壁になりそうで、この法律が想定するようなバイトダンスからの事業の切り離しも容易ではない。 (ワシントン・榊原謙、asahi = 4-25-24)
米中、新たな経済対話枠組み合意 「バランスある成長」軸に協議継続
米財務省は 6 日、中国との間で、両国や世界の経済の「バランスのとれた成長」に向け、集中的に議論することで合意したと発表した。 電気自動車 (EV) をめぐる対立をはじめ、両国間では経済分野の難題が多く残るが、経済の「バランス」をキーワードに、議論を継続することで一致した。 3 - 9 日の日程で中国を訪問しているイエレン米財務長官と、中国の何立峰(ホーリーフォン)副首相が 5、6 両日に協議したうえで合意した。
今回の会談でイエレン氏は、中国の EV や充電池、太陽光パネルの「過剰生産」を、「懸念される問題」だと一貫して訴えてきた。 中国政府からの巨額補助金を背景にした EV などの「つくりすぎ」が、各国の産業や世界経済に悪影響を及ぼしていると指摘。 訪中前から「中国に必要な対応をとらせる」と語り、今回の会談でも改善を求めたとみられる。 一方、国営新華社通信は 6 日、中国は米国に対して、「生産能力の問題に十分な返答をした」と報じた。 中国はむしろ、北米で組み立てられた EV を税優遇する米国の政策こそ「不公平」だと不満を募らせる。 3 月には世界貿易機関 (WTO) への提訴にも踏み切り、対決色を強めている。
今回、両国が打ち出した新たな対話の枠組みは、「国内経済と世界経済のバランスのとれた成長に関する交流(イエレン氏)」という互いに一定の合意を得やすい土俵で、議論を前に進める狙い。 米国としては、この枠組みを使い、引き続き過剰生産の問題を議論したい考えとみられる。
両氏の直接会談は、昨年 7 月から数えて 3 回目。 今回の会談は 2 日間にわたり、両氏は夕食や昼食をともにしたほか、5 日夜には船遊びもしたという。 イエレン氏は中国に厳しい姿勢をとるバイデン政権の中では、「融和派」とみなされる。 トランプ前政権がかかけ、バイデン政権も維持する対中制裁関税に反対してきた経緯もある。 今回の新たな対話の枠組みに中国が同意したのは、イエレン氏のそうした姿勢を中国側が一定評価したことの反映ともいえそうだ。
ただ、イエレン氏の融和姿勢が際立ちすぎれば、中国に厳しい姿勢をとり、11 月の大統領選で返り咲きをめざす共和党のトランプ前大統領に政権攻撃の材料を与えかねない。 中国に対する「弱腰」イメージは大統領選では大きなマイナス材料で、再選を狙うバイデン大統領の足をひっぱりかねないリスクがある。 イエレン氏の今回の訪中は 3 - 9 日の日程。 8 日には北京で、劉鶴前副首相や中国人民銀行(中央銀行)の潘功勝総裁と会談する。 同日には記者会見も開き、訪中の意義などを総括する方向だ。 (ワシントン・榊原謙、北京・ 西山明宏、asahi = 4-6-24)
米中の軍当局、海洋での衝突防止へ協議 対話再開の動きの一つに
米中両政府は 3 - 4 日、米ハワイで、海洋における偶発的な衝突を防ぐための軍当局の協議を開いた。 米インド太平洋軍が 5 日、発表した。 米中間の軍事海洋協議協定 (MMCA) に基づく作業部会で、一時は滞った国防当局間の対話の再開の動きの一つとなった。
米中の軍当局者が過去数年における安全に関わる事例を見直し、航行や飛行の安全性をめぐって協議した。 MMCA は 1998 年に米中間で締結された。 作業部会の開催は、2021 年 12 月にオンラインで開かれて以来となった。 米中の国防当局間の協議は、中国が 2022 年のペロシ米下院議長(当時)の訪台に反発して滞ったが、23 年 11 月の米中首脳会談で再開に合意していた。 (asahi = 4-6-24)
中国の偵察気球、米ネットサービス使い位置データを本国に送信 米当局
米当局者は 29 日までに、今年初めに米本土を横断した中国の偵察気球が米国のインターネットサービスを使用して、飛行と位置に関するデータを中国に定期的に短時間送信していたことを米情報機関が突き止めたと明らかにした。 気球のインターネットサービスへの接続は、米国が領空を飛ぶ気球を追跡し、気球についての情報を集めるのに役立った方法の一つだという。
CNN は使用されたインターネットサービスのプロバイダーを特定することはできなかった。 CNN は以前、当局者の話として、米本土を横断していた気球は中国と通信することが可能だったと報じていた。 偵察気球が中国にデータを送るのに米インターネットサービスを使用していたことについては、米 NBC テレビが最初に報じた。 当局者によると、このインターネット接続は機密情報の送信には使われなかったという。 気球は画像やその他のデータを含む情報を保存していた。 2 月に撃墜された後、米国はこれらの情報について調査できるようになった。
この件について、連邦捜査局 (FBI) と国家情報長官室はコメントをしなかった。 CNN は在ワシントンの中国大使館に問い合わせている。 気球については、中国は気象観測のためのもので、風に飛ばされてコースを外れたと主張し続けている。 CNN は以前、気球は中国軍による大規模な偵察活動の一環だと米国はみていると報じていた。 米当局によると、気球を使った監視活動は近年、少なくとも 5 大陸で 20 回超行われたという。 また、中国共産党の指導部は気球に米本土上空を横断させる意図はなく、気球運用担当者を懲戒処分としたと米情報機関内では考えられていると CNN は報じていた。 (CNN =12-30-23)
米、中国へのハイテク投資規制を発表 軍事的脅威に対処
【ワシントン = 坂本一之】 バイデン米政権は 9 日、中国が半導体や人工知能 (AI) など最先端技術の能力を高め米国の安全保障上の脅威となることを防ぐため中国企業への投資規制を講じると発表した。 米企業の投資が中国の「軍事的優位性」の確立につながることを阻止する。 投資規制は、半導体と AI に加え量子技術が対象で、特定取引の禁止や政府への届け出を義務付ける。 中国が民間技術を活用して中国軍の能力強化を図っていることから、技術開発資金が中国に流入することを押さえ込む。
バイデン大統領が「懸念国での特定の国家安全保障技術・製品に対する米国投資」の大統領令を出し、米国に安全保障上の脅威を与える懸念国・地域として中国本土とともに香港とマカオを指定した。 投資規制は意見公募を実施し、詳細な規則を定めた上で施行する。 バイデン氏は議会に送った投資規制に関する書簡で、最先端技術を通した中国の「軍事、インテリジェンス(諜報)、監視、サイバー」における脅威を指摘し、「米国の投資が脅威を悪化させる危険性がある」と訴えた。 (sankei = 8-10-23)
米兵 2 人、中国に国防機密を提供か 沖縄配備のレーダーシステム図も
米司法省は 3 日、金銭と引き換えに中国に国防情報を提供したとして、米海軍の兵士 2 人をスパイ法違反などの罪で起訴したと発表した。 海軍の艦艇の写真や動画のほか、沖縄に配備されたレーダーシステムの設計図なども提供していたという。 同省によると、強襲揚陸艦「エセックス」の乗員だったジンチャオ(別名パトリック)・ウェイ被告 (22) は 2022 年 2 月以降、賄賂と引き換えに、エセックスや他の海軍艦船に関する機密情報を中国の情報将校に提供したとされる。
ウェイ被告は機械修理などに携わる下士官で、艦船の武器や推進力、海水淡水化システムなど国防上の機密情報へのアクセスが認められていた。 情報将校の要請に応じ、エセックスの写真や動画のほか、他の艦船の位置情報も送信し、引き換えに数千ドル(数十万円)を受け取ったとされる。 また、輸出規制がかけられた機密性の高い内容を含む技術や機械のマニュアル類も複数提供し、5 千ドル(約 71 万円)を受け取ったという。
これとは別件で、カリフォルニア州の海軍基地に勤務していた下士官ウェンヘン・ザオ被告 (26) は 21 年 8 月 - 23 年 5 月、海事経済学者を装った中国軍将校に、インド太平洋地域での大規模な米軍演習の非公開の作戦計画や、沖縄の米軍基地に配備されたレーダーシステムの電気系統図や設計図を送ったとされる。 同省によると、中国軍将校はザオ被告に対して自分は海事経済学者だと偽り、投資判断のために情報が欲しいと要望。 情報提供の対価として約 1 万 4,866 ドル(約 212 万円)を支払ったという。
有罪となった場合、ウェイ被告は終身刑、ザオ被告は禁錮 20 年となる可能性がある。 米司法省は声明で「今後も中国からの脅威に対抗するため、また中国を助けて我々の法を破り国家安全保障を脅かす者たちを抑止するため、あらゆる手段を駆使していく」としている。 (ワシントン = 下司佳代子、asahi = 8-4-23)
半導体「中国包囲網」に日本も参加 報復の懸念、ビジネスに障壁も
中国の半導体の製造能力を抑え込もうとする米国主導の包囲網に、日本が加わった。 米国が最初に輸出規制の強化に動いた昨年 10 月以降、中国では工場建設が止まるなどし、日本企業も先端品向けの製造装置の売り上げが減るなどの影響が出た。 これに反発する中国からの報復措置も懸念されている。
旧世代「レガシー半導体」の装置は輸出可能
新たに輸出規制が強化されるのは、成膜装置 11 品目、露光装置 4 品目などの計 23 品目。 日本の経済産業省幹部は「日本の強みを踏まえて選定したものだ」とする。 日本には、製造装置の分野で世界有数の技術を持ち、高いシェアを誇る企業が多い。 例えば、東京エレクトロンの「コータ・デベロッパ」と呼ばれる装置はシェアが 80% 以上。 一部の検査装置でシェア 100% を持つニッチ企業も国内にある。 こうした高性能の製造装置が手に入らなければ、中国がスーパーコンピューターや人工知能 (AI) に使われるような先端半導体をつくることが難しくなる。 ドローン兵器に使われるなど半導体の軍事転用を防ぐことが目的だが、高性能のスマートフォンなど民間の製品にも影響が出る可能性がある。
一方、自動車や家電に使われるような旧世代の「レガシー半導体」の製造装置は対象ではなく、普通に輸出ができる。 日本の半導体製造装置産業にとって、中国は最大の輸出先だ。 財務省の貿易統計によると、2022 年の日本から世界への半導体製造装置の輸出額は 4 兆 652 億円。 うち 3 割強が中国向けで台湾や韓国、米国を上回る。 それでも規制を強化するのは、昨年 10 月に一足早く対中規制を打ち出した米国の協力要請に歩調を合わせる必要があったからだ。
日本と同じく、協力を要請されていたオランダ政府も 9 月 1 日から、先端半導体の製造装置に対する新たな輸出規制を導入する。 同国には半導体製造に欠かせない露光装置で高いシェアを持つ ASML がある。 政府が装置の最終的な利用者や用途などを確認し、許可を出すかどうか判断する。 日本、オランダとも特定の国を名指ししていないが、中国が念頭にある。 オランダの情報機関は 22 年の年次報告書で、中国が半導体などの高度な技術を求め、オランダはターゲットになるなどとし、「オランダの経済安保にとって最大の脅威」と警戒感を強めていた。(冨名腰隆、ベルリン = 寺西和男)
国内企業「影響は限定的」 米の動き見越す
規制の強化は、これまで自由にできていた民間の取引に制限がかかることを意味する。 巨大市場である中国でのビジネス機会が減る半導体業界からは懸念も出ている。 米半導体工業会 (SIA) は 17 日の声明で更なる米国の規制に警戒感を示すとともに、「中国による継続的でエスカレートする報復を促すリスクがある」と警告した。 日本半導体製造装置協会の渡部潔・専務理事も「ルールには当然従うが、どれくらい待たされるかわからない状況は困る」と語る。 輸出の手続きに時間や人手がかかるようになれば、ビジネスの障壁になりかねないためだ。
昨年 10 月以降の米国の規制で、中国国内では最先端の半導体工場の新設が止まり、そこに納入されるはずだった日本製の製造装置の需要もなくなったという。 半導体製造装置メーカーの Kokusai Electric は「投資の抑制で、先端品向けの装置はほぼチャンスがなくなってしまった(広報)」と話す。 一方、今回の日本の規制強化でさらに大きな影響を受けるというメーカーは少ない。 米国の動きを見越して中国でのビジネスを慎重に進めてきた国内関係企業もあり、対象となる約 10 社のうち、取材に応じた7社が「影響は限定的」などと回答した。
また、中国では先端半導体から「レガシー半導体」へ投資を転換する動きもあり、この分野の装置は日本への引き合いも強いままだ。 東京エレクトロンの川本弘・執行役員は 5 月の決算会見で「先端品でない分野は(中国の)取引先からの意欲が非常に高い」と述べた。 半導体の基板を洗浄する装置で世界 1 位の Screen ホールディングス(京都市)は売上高に占める中国の割合は今年度、10% ほど増える見込みだ。 日本と同様、米国に規制の歩調を合わせるオランダの ASML のピーター・ウェニンク最高経営責任者 (CEO) も 19 日の決算会見で、今回の規制が「長期的なシナリオに重大な影響を与えるとは考えていない」としている。
ただ、中長期的には中国による国産化が進んで日本の製造装置のシェアが奪われたり、対日感情の悪化でビジネスがやりづらくなったりするリスクはある。 半導体製造装置も手がける電機大手の幹部は「中国でビジネスをするのに、今は非常に微妙な段階だと言える。 経済安全保障は今後、ますます厳しい状況になるだろう。」とみている。 (中村建太、杉山歩、asahi = 7-22-23)
中国「ガリウムとゲルマニウム」輸出規制の衝撃 半導体として優れた特性、外資に広がる懸念
中国商務省と海関総署(税関)は 7 月 3 日、国家安全保障と国益の保護を目的に、希少金属のガリウムおよびゲルマニウムの関連製品を輸出管理の対象に加えると発表した。 具体的には金属ガリウム、酸化ガリウム、窒化ガリウムなどを含むガリウム関連 8 品目と、金属ゲルマニウム、リン化ゲルマニウム亜鉛などを含むゲルマニウム関連 6 品目について、関連当局の許可を得なければ中国から輸出できなくなる。
輸出規制の施行は 8 月 1 日から
ガリウムは主にアルミニウム精錬の副産物、ゲルマニウムは褐炭や亜鉛精錬の副産物として抽出され、中国の生産量は前者が世界の約 9 割、後者が約 7 割を占めている。 現時点の需要量は大きくないが、半導体として優れた特性を持つことから、将来は(電気自動車用パワー半導体など)高性能半導体向けの用途拡大が期待されている。 今回の輸出規制は 8 月 1 日から施行される。 これに対して、アメリカの半導体材料メーカーの AXT は即座に声明を発表。 同社の中国子会社がガリウムおよびゲルマニウム関連製品の輸出許可の申請手続きを直ちに開始し、「顧客に及ぼす潜在的な混乱を最小限に抑えられるよう努める」と述べた。
「輸出許可申請に対する中国当局の対応が、どの程度厳しいものになるかに注目している。 とりわけ(事実上の禁輸措置である)『原則不許可』のポリシーをとるかどうかを懸念している。」 財新記者の取材に応じたある日系メーカーの担当者は、そう不安を隠さなかった。 (訳注 : アメリカ政府は 2022 年 10 月に先端半導体技術の対中輸出管理を強化した際、原則不許可の方針をとった。 中国政府がその報復措置として、同様の対応を取る可能性が指摘されている。)
サプライチェーンに影響不可避か
「希少金属に関しては、国家戦略上や重要資源としての考慮から、世界の多くの国々が特別な保護政策をとっている。 輸出管理の強化は、その常套手段のひとつだ。」 国際貿易の実務に詳しいキング・アンド・ウッド・マレソンズ法律事務所の劉新宇シニアパートナーは、財新記者の取材に対してそう解説し、次のように続けた。 「長期的に見て、今回の輸出管理強化は半導体など関連産業のサプライチェーンに直接的、間接的な影響を与える可能性が高い。 そのような前提で、企業は対応策をしっかりと練るべきだ。」 (杜知航、財新/東洋経済 = 7-11-23)
イエレン氏、習近平氏側近と面会重ねる 首脳会談実現へ「対話継続」
訪中している米国のイエレン財務長官が、李強(リーチアン)首相はじめ中国側の要人と面会を重ねている。 冷え込む両国関係の修復へ、双方とも「対話の継続」という低めのハードルを設定し、それを慎重にこなしている状態だ。 個別の難題の解決はまだ遠いが、秋の首脳会談の実現に向けた重要なプロセスが続く。 イエレン氏は 8 日、新たに副首相になった何立峰(ホーリーフォン)氏と北京市内で会談した。 何氏は習近平(シーチンピン)国家主席の側近の一人で経済政策の司令塔役とされる。
イエレン氏は会談で、「特定の経済的慣行に懸念があるならば、直接それは伝えるべきだし、そうするつもりだ」と述べ、率直な対話を呼びかけた。 昨年の米中間の貿易実績が過去最高だったことを引き合いに、「両国の企業が貿易や投資をする余地は大きい」との期待も述べ、米中経済の「切り離し」は改めて否定した。 前日には指導部ナンバー 2 の李首相や何氏の前任の劉鶴(リウホー)前副首相らも、イエレン氏と相次いで会談。 トランプ前政権時代の対中制裁関税の解除を訴えるなど、「対中穏健派」とみられるイエレン氏を、中国側も一定の期待をもって迎えたようだ。
根深い対立を抱える米中の関係は 2 月に米本土に飛来した中国の気球を米軍が撃墜した問題で、更に緊張。 4 カ月遅れで先月訪中したブリンケン国務長官に、中国側は米中関係が国交正常化以降「最も低迷している」との認識を示した。 中国政府関係者は「気球の件で政権上層部は、米国は話が通じない相手だという認識を持った」と明かす。 ブリンケン氏の帰国後もバイデン大統領が習氏について「独裁者」と発言するなど、両国の関係は悪材料に事欠かない。
それだけに、米戦略国際問題研究所 (CSIS) のイラリア・マゾッコ氏は「今回の訪中は『プロセス』で、意思疎通と交流の再構築をめざした。 イエレン氏は目に見える成果を求めて中国に行ったわけではない。」とみる。 世界経済は前年から減速感を強める。 両国の意思疎通の目詰まりは、金融危機などが起きればそれ自体が大きなリスクになる。 経済が回復軌道に乗り切らない中国にとっても、米国との対話の促進には利点がある。
だが具体的な難題の解決は、なお遠い。 米側は今月以降、半導体製造装置に関わる新たな対中規制を、日本やオランダと共に発動。 中国側もレアメタルの禁輸などで対抗する方針で、事態はエスカレートするばかりだ。 軍事分野の対話も止まったままだ。 それでも国務長官に続けて財務長官の訪中も実現し、両国の対話路線はひとまずは続きそうだ。 レモンド商務長官らも訪中を検討しており、秦剛(チンカン)国務委員兼外相の「適切な時期」の訪米でも双方は合意している。
CSIS のマゾッコ氏は、「イエレン氏の訪中が成功と評価されるかどうかは、今後、米中の高官の往来が実現し、最終的に両首脳の直接会談が開かれるかどうかにかかっている」と語る。 (ワシントン = 榊原謙、北京 = 西山明宏、斎藤徳彦、asahi = 7-8-23)
中国の気球「情報収集できず」 米国製の機器も搭載 米紙報道
中国の気球が米本土上空に飛来し米軍が撃墜した問題をめぐり、複数の米メディアは 29 日までに、気球が米国製の機器を搭載していたと報じた。 バイデン米政権は、気球が機密情報の収集を目的としていたとする一方、米本土上空での情報収集はできなかった、との見方を示した。 米紙ウォールストリート・ジャーナルは 28 日、米当局者の話として、分析の結果、中国の気球が米国製の機器を搭載していたことがわかった、と伝えた。 米国製の機器の一部はオンラインで購入可能なものだった。 その他に中国製のセンサーや、写真や動画などを集めて中国に送信するための機器も含まれていた。
米国防総省のライダー報道官は 29 日の会見で、気球が米国製の機器を搭載していたかどうかについてコメントしなかった。 ライダー氏は気球について、「情報収集能力を持っていた」と改めて指摘。 ただ、米国は気球の情報収集を防ぐ措置を取ったとし、「米国の上空では情報を収集しなかったと判断している」と述べた。 中国はこれまで、気球は気象観測など民用のものだったと主張し、気球を撃墜した米国に反発。 米中間のハイレベルの対話が滞る原因となった。
米側は気球の残骸を回収し、米連邦捜査局 (FBI) で解析してきた。 ただ、詳しい調査結果はこれまで公表していない。 今月 18 - 19 日にはブリンケン米国務長官が気球問題を受けて延期されていた中国訪問を行うなど、米中間の対話を再開を目指してきた。 バイデン米大統領は今月 20 日、中国の習近平(シーチンピン)国家主席を「独裁者」と呼び、「習氏が非常に腹を立てたのは、気球がそこにあったことを知らなかったからだ」と発言。 中国側の反発を招いていた。 (ワシントン = 清宮涼、asahi = 6-30-23)
◇ ◇ ◇
中国の偵察気球、本土へデータを即時送信か 米報道
【ワシントン = 中村亮】 米 NBC テレビは 3 日、2月に米本土へ飛来した中国の偵察気球がデータをリアルタイムで中国本土に送っていたと報じた。 野党・共和党はバイデン政権の対応が後手に回ったとして追及を強める構えだ。 NBC テレビによると、偵察気球は米本土の軍事基地の上空に飛来し、兵器システムや基地にいる人々の通信から得られる電気信号を通じて情報を集めていた。 米国防総省は機密情報が漏れないよう対策を講じたと説明していたが、中国は情報を集められたという。
国防総省のシン副報道官は 3 日の記者会見で中国の情報収集に関し「我々が講じた対策によって中国は(偵察気球を通じ)付加価値をほとんど得られなかった」と指摘し、従来の見解を堅持した。 情報をリアルタイムで中国本土に送っていたかどうかは現時点で確認しないと説明した。 上院軍事委員会のロジャー・ウィッカー筆頭理事(共和党)は 3 日の声明で「バイデン政権は受け入れがたい誤りをしたことが明白になった」と批判した。 「この件に関する全ての情報を見つけ出す監視の取り組みを断念しない」と強調し、政権に情報提供を求めていく方針を示した。
共和党では米軍が偵察気球をもっと早く撃墜すべきだったとの見方があり、バイデン大統領を批判する声が根強い。 気球は西部モンタナ州を飛行して米本土を移動し、米軍は南部サウスカロライナ州の沖合で撃墜した。 政権は撃墜して生じる残骸が広範囲に落下し、市民に被害が出るリスクを排除できないとして撃墜を遅らせていた。 (nikkei = 4-4-23)
米国務長官、習近平氏と会談 衝突回避へ「対話活性化」では一致か
中国の習近平(シーチンピン)国家主席は 19 日、北京を訪問中のブリンケン米国務長官と約 30 分間にわたり面会した。 訪中した米国務長官と面会するのは約 6 年ぶり。 台湾問題などで米国と根深い対立を抱え、米中関係について国交正常化以来「最も低迷している」との認識を示す中国側だが、対話を続けるとの意思は示した。 ブリンケン氏は 19 日の記者会見で、中国側と「関係を安定化させる必要性で合意した」と述べた。
習氏は面会の冒頭、ブリンケン氏が 18 - 19 日に秦剛(チンカン)国務委員兼外相や王毅(ワンイー)政治局員と長時間にわたって会談したことに触れ、「双方はいくつかの具体的な問題で進展を遂げ、共通認識に達した。 これは良いことだ。」と話した。 今回のブリンケン氏の訪中が「中米関係の安定のため積極的な役割を多く果たすことを希望する」とも語った。
習氏は長机の奥に座り、ブリンケン氏ら米側と王氏ら中国側とが左右に向かい合って並んだ。 双方が対等の形で座る従来の外交儀礼とは異なる形だ。 米国務省によると、この習氏の発言に対し、ブリンケン氏は「バイデン大統領は、米中には関係を管理する義務と責任があると信じ、私に訪中を指示した。 それは米中や世界にとっての利益だ。」と述べた。
習氏「中国は米国に取って代わることはしない」
中国側の発表によると、習氏はその後、「国際社会は両国の衝突を望んでいない」、「大国間の競争は時代の流れに合わない。 中国は米国に取って代わることはしない。」と述べ、中国を締め付けるかのような厳しい対中政策をやめるよう、米側に促した。 中国の外交部門トップの王氏とブリンケン氏との 19 日の会談は、約 3 時間に及んだ。 米国務省によると「率直で生産的な議論」がなされた。 台湾問題をめぐり王氏は「永遠に中国の核心的利益の中の核心だ」と指摘した。 米側に「台湾独立に明確に反対しなければならない」と要求した。 ブリンケン氏は 19 日の記者会見で、中国の台湾海峡での「挑発的な行為」に懸念が高まっていると指摘。 「米国は台湾独立を支持していない」と述べ、台湾政策に変わりはない、と改めて伝えた。
米中首脳会談の見通しは
バイデン米政権が 2022 年 10 月に決めた半導体の対中輸出規制をめぐっても協議がなされた。 ブリンケン氏は会見で、「中国を経済的に封じ込めようとはしていない」と強調した。 中国側は不信感を強めており、王氏はブリンケン氏との会談で「米国側が、誤った対中認識から、誤った対中政策を進めた」と批判した。 今回の訪中では、米中首脳の直接会談の調整についても取り上げられた可能性がある。 11 月に米国のサンフランシスコで開くアジア太平洋経済協力会議 (APEC) 首脳会議などの機会にあわせ、首脳会談による局面の打開が図られるかが今後の焦点だ。
ブリンケン氏の訪中は、22 年 11 月、バイデン政権で初めての米中首脳会談で取り決めた合意事項だった。 ブリンケン氏は 23 年 2 月の訪中を予定していたが、米本土に中国の気球が飛来した問題を受け、一度は延期に追い込まれた。 その後、米中高官による対話は滞っていた。 ブリンケン氏は 19 日の記者会見で、習氏と「重要な会話をした」と振り返った。 また、「直接の関与が、競争が紛争に発展しないようにする最善の方法だ」と中国側に繰り返し伝えた、という。
訪中した米国務長官が習氏と面会するのは、17 年 9 月のティラーソン国務長官(当時)以来となる。 18 年にはポンペオ国務長官(当時)が訪中したが、習氏との会合は設定されなかった。 当時、トランプ政権下で、米中の貿易摩擦が激化していたことが背景にあったとみられる。 米中関係の改善がみられないにもかかわらず、習氏がブリンケン氏との面会に応じたことで、中国側も米中関係の安定化に向け、一定の意欲を示したことになる。
米中が具体的な成果と位置づけたのが、政府や民間での米中交流の促進だ。 秦剛(チンカン)国務委員兼外相の「適切な時期」の訪米で合意し、事務方でも、米中間の懸案について協議を進めることを新たに決めた。 民間の交流を増やすため、米中間の航空便を増やすことを検討することでも一致した。 習氏がこうした進展について「良いことだ」と表現したのに対し、米側も、今回の訪中で、米中の関係改善に向けて「進展があった(国務省高官)」と評価している。 台湾問題や経済問題などの課題をめぐる米中の隔たりは依然大きいが、今後、首脳間を含む米中のハイレベル対話の再開につながる可能性がある。 (北京 = 清宮涼、斎藤徳彦、asahi = 6-19-23)