�����́u�]���r��Ɓv���v�A�S��������L��Ƃ�
�m���`�n �����͍��N�A��剻�����������L��Ƃ̉��v�����������悤�Ƃ��Ă���B�@��s�Ⓤ���Ƃ́A10 ���̒������Y�}����Ɏ��Y���p�Ȃǂ��s����\���Ɋ��҂��Ă���B�@�����A�������{�������v�ɖ��Ԏ��{�͕s�����Ə��サ�Ă���ɂ�������炸�A���̖����͌���ꂽ���̂ɂȂ�\���������ƁA�������{�̌v��ɏڂ��������̊W�͖������B
�ނ�ɂ��A�������{�́A�ꋫ�ɂ��������L��Ƃ̂�����K�͂Ȃ��̂̋~�ςɂ́A�����l���ی��⒆�����M�̂悤�Ȏ����͂̂��鍑�L��Ƃɗ�����Z���傫���B�@�����l�����挎�A���������ԗ��ʐM�i�������ʁA�`���C�i�E���j�R���j�ɂ�� 120 ���h���i�� 1.3 ���~�j�̑����̈ꕔ�����������ƂW�͗�Ƃ��ċ������B�@���L��Ɖ��v�ɂ����閯�Ԏ��{�̖���������I�ɂȂ�A�^�ɔ��{�I�ȉ��v�Ƃ�����̂��^�₪�c�邱�ƂɂȂ邾�낤�B�@��S�I�Ȍo�ϐ����ڕW��B�����A���L��Ƃ̍����y�����邽�߁A�����͓����v�̃X�s�[�h�𑁂߂����l�����B
�u���s�̃��f���ł́A���҂̍D���Ȋ�Ƃ��A�s���Ȋ�Ƃ��ꕔ���L���邱�ƂɂȂ�B�v�@�����w�E����̂́A�i�e�B�N�V�X�̃A�W�A�E�����m�n��S���̃`�[�t�G�R�m�~�X�g�A�A���V�A�E�K���V�A�E�w���������B�@�u����������A����͑���A���L��Ƃ̂������ŗ��v�Ƒ����̓���ւ����s���Ă���悤�Ȃ��̂��B�v�@�W�ɂ��ƁA�����l���́A���͔��d�f�x���b�p�[���̎P���ɂ��钆���O���V�\���L�����i�ƌ������Ƃ����B
���Ԏ��{�����L��Ƃɒ������邢����u�������L���v�̌��ɋ������Ă����ƂɂƂ��Ă��A���Ԏ��{�̖����͋ɂ߂ďd�v���ƁA���W�͎w�E����B�@���̂悤�Ȋ�Ƃ̂Ȃ��ɂ́A��������d�Ԃ⒆���D���H�ƏW�c�A�����j���Ȃǂ��܂܂�Ă���B�@�����l���ƒ������M�̓R�����g�v���ɉ��Ȃ������B�@���L��Ƃ́A���Z����ی��A�G�l���M�[�A�ʐM�Ɏ���܂ŁA�����̎�v�Y�Ƃ��x�z���Ă���B�@�������B���e�ՂȂ��Ƃ�����A�����O�ɂ����铊���ɂ����āA���L��Ƃ͖��Ԃ̃��C�o����Ƃ𗽉킵�����Ă���B
���������L��Ƃ̎��v�͖͂��Ԋ�Ƃɋy���A�����̋�s��������s�Ǎ��ōő�̊������߂Ă���͍̂��L��Ƃł���B�@���L�ʐM��Ђ̃`���C�i�E���j�R���̎������B�́A2015 �N�̐��{�v��ɃA�E�g���C����������Ă����������L���ւ̊��҂����߂��B�@���j�R���̑����ɂ́A�A���o�o�E�O���[�v�E�z�[���f�B���O�⓫�u�T�ҁi�e���Z���g�E�z�[���f�B���O�X�j�ȂǁA������ IT �����܂� 14 �̓����Ƃ��Q�����A�s��Ɋ��}���ꂽ�B
�����A�������{�����{�Ǝx�z���Ă�т�ɂ�����Ȃ��A�����l���͌��ǁA���j�R���̊��� 10.6& ���擾�B�@����͔���ɏo���ꂽ�����S�̂� 3 ���� 1 �߂��ɑ�������B�@�����l�����܂ސV���������Ƃɂ́A15 ����c�����̂��� 3 ���^����ꂽ�B
�u���L��Ɖ��v�𐬌�������ɂ́A����������Ƃ̏��L�����A�����ۗL�ƃK�o�i���X�̗��ʂɂ����Đ^�ɑ��l������邱�Ƃ��K�v���v�ƌ��̂́A�k���ɋ��_��u���A�����̍��Ɣ��W���v�ψ��� (NDRC) �▯�Ԋ�ƂƎd��������ٌ�m���B�@�u�����A�����B������͍̂���낤�B�@���L��Ƃ̂قƂ�ǂɂ��āA���Ԋ�Ƃɂ͓�������C���Z���e�B�u���Ȃ����炾�B�v�ƁA���ٌ̕�m�͐T�d����v������ł��邽�߁A�����ł���������B�@�u���������āA��{�I�ɂ͂��鍑�L��Ƃ̃L���b�V�����g���āA�ʂ̍��L��Ƃ���݂����点�悤�Ƃ��邱�ƂɂȂ邾�낤�B�v�@NDRC �ƍ����@���L���Y�ēǗ��ψ���́A���C�^�[�̃R�����g�v���ɉ����Ȃ������B
�����{���B�ւ̏�����
�Ƃ͂����A���Ԏ��{�͈ˑR�Ƃ��đ傫�Ȗ�����S�����Ƃ����҂���Ă���B�@���N��i�ƌ������\�z�����O�����ړ������Ăэ��ނ��߁A�����͐挎�A�C�O�����Ƃւ̋K��������Ɋɘa����Ɣ��\�����B�@���̂Ȃ��ɂ́A��s�A�ی��A�،��Ƃ������A����܂ŊO�����̎��{�Q���K��������A�����s��ւ̐i�o��ڎw���C�O��Ƃ��s��������Ă���������܂܂�Ă���B
�����̋��Y�}����O���ɒu����s�W�҂́A���̌�̍��L��Ɖ��v�̔g���P�Ȃ�^�C�A�b�v�ȏ�̂��̂ɂȂ邱�ƂɊ��҂���B�@�i���{�ɂ́j�s�v�Ŋ����ɕ]������Ă��邪�A���ԓ����Ƃɂ́A���L����������Ȃ牿�l���o�鏬�����Y�̔��p���܂܂�邩������Ȃ��Ƃ݂����������B�@���Y�}���́u�ƂĂ��d�v�ȓ]���_�ƂȂ�v�ƁA�����K���E�X�^�����[�̒�������ӔC�҃E�F�C�E�X���E�N���X�`�����\�����͍��������c�ŁA���L��Ƃ̔��p���邢�͎��Ƃ̕����Ɨ��̉\���ɂ��Ă����q�ׂ��B
�u����������������ƂɍD�@�ݏo���v�Ɠ����͌�����B�@�����������āA���͒����l���̂悤�Ȋ�ƂɗL���ƂȂ��Ă���B�@�W�ɂ��ƁA���ɒ����l�����o������\�������������O���V�\���́A�� 15 ���h���̑������������Ă���Ƃ����B�@���ɒ����O���V�\���̎��{���B�ɖ������グ��̂́A��͂荑�L��Ƃ̉\��������A���ԓ����Ƃ���͔M���S�͌����Ȃ��ƁA�W�� 1 �l�͌����B
�u�������L���v�̎��̃��E���h�ɐϋɓI�ɎQ������v�ƁA�����l���� �k������͐挎�A���Z���\��ł����q�ׂ��B�@�����A�ꕔ�̍������L����Ƃ����Ԏ��{���Ăъ閣�͂Ɍ��������ŁA���������i������v�̈�[��S�����Ƃ��閯�ԓ����Ƃ̂Ȃ��ɂ́A���v�ȏ�̂��̂��l������҂��o�Ă��邾�낤�B�@�u�����ł́A���������������l���Ă��Ă͂���Ă����Ȃ��v�ƁA���j�R���̑����ɎQ����������l�����Ƃ͘b���B�@�u���̐���ւ̎x�����������߁A�����������v�ɎQ������K�v������B�v (Julie Zhu�ASumeet Chatterjee�BReuters = 9-25-17)
�����̑ΊO�����K���A���ڂɏo��\��
�m���`�n �������{�́A������Ƃɂ��C�O�̃z�e����X�|�[�c�N���u�Ȃǂ̔����̂����A�u���I�v�Ƃ݂Ȃ����Č��ɑ��ċ��d�I�ȑԓx����邱�Ƃ𐳎��ɕ\�������B�@�v���̐���ɂ���ĕs�Ǎ����ςݏオ�邱�Ƃւ̌��O���A���̈������ɂȂ����Ƃ̌������o�Ă���B�@���̉\���͂��邾�낤�B�@��������̋K�������́A���{�I�Ȗ����������Ă���B�@����́A�����ł̗��v��������A��芈�C�̂���C�O��Ƃ̔����ɂ���ĕ₤�悤��Ƃɔ��鍑���́u�c�݁v�̖�肾�B
18 ���ɔ��\���ꂽ�����}����́A�M�S�ȊC�O�����Œm������M�ی��W�c���A���B�W�c�i�����_�E�O���[�v�j�A�������ہA�C�q�W�c�iHNA �O���[�v�j�Ȃǂ̊�Ƃɑ��Ĉ��͂����߂Ă����A�������{�̂��̐��J���̓������A����Ƃ��Ė��m�ɂ������̂��B�@����̋K�������ɂ��A�]�O����̕ێ�I�ȃ|�W�V�����ɖ߂邱�ƂɂȂ�B�@������Ƃɂ��C�O�����́A�傫�ȃj���[�X�ƂȂ�����˔�Ȕ����Œ��ڂ���Ă͂�����̂́A���A�f�ՊJ����c (UNCTAD) �ɂ��ƁA2016 �N�̑ΊO�����̓X�g�b�N�x�[�X�� 1 �� 3,000 ���h���i142 ���~�j�ɉ߂��Ȃ��B
�ΊO�����z�͓��N�A�ߋ��ō��� 1,830 ���h���ɒB�������A���������Y (GDP) �� 2% �ȉ��ɂƂǂ܂��Ă���B�@�������Z�V�X�e���� 7 �������łقړ��z�̐M�p���^�ݏo���Ă���B�@���ւ̌��O����肴������邱�Ƃ��������A������Ƃɂ�鍇���Ɣ��� (M & A) �́A�V�X�e�~�b�N�E���X�N�������炵�Ă��Ȃ��B�@�����̑ΊO�������ߏ��ɂƂǂ܂�w�i�ɂ́A2 �̗��j�I���R������B�@�܂��A���{�K���ɂ��A��Ƃ͌_������O�ɑ����̃n�[�h�������z����K�v���������B�@���ɁA�}���Ȍo�ϐ����ɂ��A���������̕������v�������������B
�����A���ړ����͊O���̋��͂ȓ���ɂȂ邽�߁A�������{�����̏ɖ��������A�K�����ǂ͔F�v����啝�Ɋɘa�B�ΊO�����������������B�@�������A����ɂ̓��x�����ł͂Ȃ��v�����������B�@�����Ŏ������B���e�Ղł��邱�Ƃ̕���p�� 1 �́A�ߏ�ȓ����]�͂��B�@���c�֘A��Ƃ����������B���Ď蓖���莟��ɐV�s��ɎQ�����A���v���̒ቺ���������B�@���j���Ƃŗ��v���グ���Ȃ��Ȃ��������̒�����Ɗ����́A���̕���ŗ��v���҂����Ƃ���悤�ɂȂ����B�@���@�ɑ�������ƌo�c�҂�����A���{�����́u�{�����̂Ăċ��\�ɑ������v�ƕ]�����B
���̌o�c�҂́A�����Ȃ��ƂɁA�����̉��i������ĊC�O�Ŏ��Ɗg���}�낤�Ƃ����B�@�Ⴆ�A���]�ԃV�F�A�����O�̃X�^�[�g�A�b�v��ƁA�����P�� (ofo) �▀�q�P�� (Mobike) �́A�����̎s�X�n���͕�r�W�l�X�ň�t�ɂȂ�̂����āA��荂�����i�ݒ肪�ł��鉢�B��č��̓s�s�ŋ}���ɑ����z���Ă���B�@����́A���M�ی��ɂ��ăj���[���[�N�̍����z�e���u�E�H���h�[�t�E�A�X�g���A�v�̔����ɂ����Ă͂܂�ƌ��ĊԈႢ�Ȃ����낤�B�@�����̏h���ƊE�́A�����n�̖ڂ��悤�ȋ����ɂ��炳��Ă���B
�C�O�����ɁA�����̕ۏ͂Ȃ��B�@�����A��߂�����͕̂s���N���B�@��Ƃ��獑�O�Ŏ������������@���D���A�������{�͋����͂Ȃ����ƂɂȂ�B�@����͍ŏI�I�ɁA���������P����̂ł͂Ȃ��A���������錋�ʂɂȂ邾�낤�B (Pete Sweeney�AReuters = 8-22-17)
���@���@��
�������{�A��Ƃ̊C�O�������K���@�������o�j�~��
���` : �������{�� 18 ���A������Ƃɂ��C�O�������K��������j�𖾂炩�ɂ����B�@�C�O�ւ̎������o�Ɏ��~�߂������邱�Ƃ�_���Ă���B�@�K���̑Ώۂ́A�s���Y�A�z�e���A��y�Y�Ƃ�X�|�[�c�N���u�ȂǁB�@����番��ւ̒�����Ƃɂ�铊���͋ߔN�������A��N�͍ō��������L�^���Ă����B
�����A���������Ȃɂ��ƍ��N�ɓ����Č������A�㔼���ł� 46% �����B����A�K���̑ΏۂƂ�������ł� 80% �ȏ�̗������݂��������B�@�C�O�����ɐϋɓI�Ȉꕔ�̒�����Ƃ͓����֘A�@�K�̈ᔽ�s�ׂ��w�E����A���ǂ̒����ΏۂɂȂ��Ă���Ƃ������B�@���ǂɂ����ߕt�����A��ƏW�c�u��A���B�O���[�v�v�͌�y�Y�ƕ���ւ̐i�o�̏k����]�V�Ȃ����ꂽ�Ƃ������B (CNN = 8-19-17)
���@���@��
�������瓦���邨���@�������ߖ�N�A���`�h���̋��P��
�������炨���������A�l�����̉������i��ł���B�@�o�ς̕ϒ�������A�����̓��ǂ͂Ȃ�ӂ�\�킸�������߂�\�����B�@20 �N�O�A�Ԋ҂��ꂽ����̍��`�̒ʉ݊�@�Œm�����������щz���邨���̗���̕|���B�@����́u�x���̑卑�v�ɂȂ�������������Y�܂��Ă���B
�� �����Y�܂��u���R�ȃ}�l�[�v
7 �� 1 ���A���`�������ɕԊ҂���� 20 ���N�̋L�O���T���A���`���̉�c��ŊJ���ꂽ�B�@�u�����̌��͂ւ̒���͐�ɋ����Ȃ��B�v�@�����̏K�ߕ��i�V�[�`���s���j���Ǝ�Ȃ͂����i�����B�@��������̓Ɨ����߂����ꕔ�̓������A�������������`���B�@�̐�����邽�߂ɗ͂ʼn���������p���́A�ʉݖh�q�ł��ς��Ȃ��B
�������A�������z���ē������}�l�[�ɑR���邷�ׂ��w�̂́A20 �N�O�̒ʉ݊�@�������B�@�Ԋҗ����� 1997 �N 7 �� 2 ���A���@�̍U���ɂ��^�C�̒ʉ݃o�[�c�̖\�������������ɃA�W�A�ʉ݊�@���n�܂����B�@���`�͉p���A���n�̎��ォ��A���Z�Z���^�[�ƈʒu�Â����A�����ƊO�������Ԗf�Ղ̒��p�n�������B�@������~���ɐi�߂邽�ߑh����������肳���悤�ƁA1 �ăh���� 7.8 ���`�h���ɌŒ肵�Ă����B
�A�W�A�e�����������Œʉ݂̑Εăh�������艺�������Ƃ���A���̌Œ葊�ꂪ�u�����v�ƌ����đ_����B�@97 �N 10 ���A���@���敨�s��Ŗ{�i�I�ɍ��`�h���藁�т����̂��B�@�ʉݓ��ǂ̍��`���Z�Ǘ��� (HKMA) �́A�L�x�ȊO�ݏ����̕ăh�����āA���`�h���������Ȃ�̂�H���~�߂悤�Ƃ����B�@���@���s��Ŕ��邽�߂̍��`�h���B���ɂ������悤�ƁA��s�Ԃł�����݂��肷������������グ���B
�����A�����㏸�̕���p�Ōi�C���₦���݁A���`���͖\�������B�@������������ē��@�͊��̐敨�����藁�т��A���`�h���Ɗ��̗����ŗ��v���������p���Ƃ����B�@HKMA �� 98 �N 8 ���A�O�ݏ����ō��`�����s��̃n���Z���w���\�����̌����Ɛ敨���x����u�O�㖢���v�̑�ɏo��B�@HKMA �̔C�u���i�W���Z�t�E�����j���فi�����j�́u���@�������ɍ��`�s�ꂩ�狎��܂ő[�u�𑱂���v�ƕ\���B�@���ʁA���@�͓P�ނɒǂ����܂ꂽ�B
���́u���`�h���h�q��v�𒆍��͌�������B�@������s�A�����l����s�̑Ց����i�^�C�V�A�������j���ق� 97 �N 10 ���A���`���̎�ނɑ��A�u�K�v������A���邢�͍��`����̗v��������A�������{�͍��`�h�����x����p�ӂ�����v�ƌ��������Ă���B�@�����A�����͓����ړI�ŗ������邨�����������������Ă������߁A��@�Ɋׂ������̍��̂悤�ɓ����o�����������������Ȃ��A�ʉ݊�@�̔g�y��Ƃꂽ�B
�A�W�A�e�����������Œʉ݂�艺���Ă���A�����̗A�o�ɂƂ��ĕs���ȏ��������A98 �N 3 ���̑S���l����\���̋L�҉�ŁA���O��i�`���[�����`�[�j�́u���͐艺���Ȃ��v�Ƌ��������B�@���炦�錈�f���������ƂŁA�l�����̕]���͍��܂����B�@�������ʉ݊�@�œ������P�́A���{�K���̏d�v���������B�@�����̋��Z�@�֊����ɂ��ƁA�l����s�� 90 �N�㔼�A2000 �N�܂łɍ����O�̂����̈ړ������S���R������\�z�������Ă����B�@�O������̎���������C�O�ւ̎����o���ɐ�����݂��Ȃ���Ԃ��B
����ȍ\�z�́A�A�W�A�ʉ݊�@�Ő�����B�@10 �N��� 08 �N 12 ���A�������{���f�Ռ��ςɐl�������g����悤�ɂ�����j�����߁A�l�����́u���ۉ��v�ɏ��o���B�@���[�}���E�V���b�N�ŕăh����ɑ̐����h�炢�����ɁA�l�����𐢊E�ʉ݂ɉ����グ��u��]�v�������B�@����ł����`�̌o���͏d���A�����̎��R�ȗ����͐����𑱂����B
�� ����ɂ߂�u�l�����h�q��v
20 �N�O�́u���P�v�́A���������ɉe�𗎂Ƃ��B�@���N 6 �����{�A�����̕ی������M�ی��W�c�̌�����i�E�[�V�A�I�z�C�j��ǂ��A�s�����ƕ��ꂽ�B�@�ăj���[���[�N�ɂ��鍂���z�e���̃E�H���h���t�E�A�X�g���A��� 20 ���h���i�� 2,2000 ���~�j�Ŕ���������Ђ��B�@���͌��ō��w�����������i�g���V�A�I�s���j���̑��ƌ�����������Ƃ���A���Њ����ɂ͐̂̎w���҂̎q������B�@�����s�Ő��G���������K�w�������u�����̐e���̒����ɓ��ݐ����v�Ƃ݂��Ă���B�@�����ɁA���M�̊O���ւ̓������A��������̎������o����������Ӑ}��������B
�����̋�s�ē��ǂ� 6 �����{�A�h�C�c��s�̕M������ɂȂ����q����̊C�q�W�c��A���Ẳf��ق���ɓ��ꂽ�s���Y�̑�A���B�W�c�ȂǐϋɓI�ɊO���œ��������Ƃ̕��ׂ�悤��s�Ɏw�������A�Ƃ̕��o���B�@���ǂ���N�ɂȂ��Ă���̂́A�����ɒ~�ς���Ă����������O���ɓ����n�߂Ă��邩�炾�B
�l������ 16 �N 10 ���A���ےʉ݊�� (IMF) �̓��ʈ����o���� (SDR) ���\������ʉ݂ɂȂ�A�ăh����[���A�~�Ȃǂƕ��ԍ��ےʉ݂̒��ԓ�����ʂ������B�@�����A���̒ʉ݂ƈ���Ċ��S�ϓ�����ł͂Ȃ��B�@SDR �ʉ݂ƂȂ�̂��T���A�l����s�� 15 �N�āA�l��������̊�l���Z�o������@��ς����B�@�ł��邾���s��̑���ɍ��킹�悤�Ƃ������ʂƂ݂��邪�A�ˑR�̕ύX���������߁A�l�����̑h������� 3 ���� 5% �߂������A�s��ɏՌ���^�����B
��������ɁA�����̈��萬���ւ̌��O�����o�����B�@�ꕔ�̊�Ƃ͋��z�̂������g���ĊC�O���Y�����A��������Ӑ}�I�ɂ����������o���Ă����Ƃ�������B�@�l����s�̒ʉݐ���ψ��߂��]�i��i���C�����e�B���j���́u���{�����̏͌������B�@���{�͉\�Ȍ���ē����߂�K�v������B�v�ƌ���B�@20 �N�O�ƈقȂ�u���Ȃ�G�v�Ɛ키�u�l�����h�q��v�͍�����ɂ߂Ă���B�@�s�[�N���� 4 ���h���������O�ݏ����Ō����x�������A�O�ݏ����͂ǂ�ǂ�A17 �N 1 ���ɂ� 3 ���h�����������B�O�ݏ����̒ꂪ������A�s��Łu����ȏ�A�����x�����Ȃ��v�ƌ����A�ʉ݊�@�ɂȂ��肩�˂Ȃ��B
�l����s�̎�����i�`���E�V�A�I�`�������j���ق� 3 ���A�u���s���s�\����������������P����K�v������v�Əq�ׁA���{���o�̕������߂�\�������B�@�N������͋�s�̑����K���ŊC�O�������K���������Ƃ��Ă������A�O������Ҕ������� 4 ���ɓP��B�@5 ��������́A�����ɂȂ�ɂ����悤�Ɍ��̊�l�̎Z�o���@�ɐV���ɕύX���������B�@17 �N�㔼���̋��Z�������ΊO���ړ����͑O�N�������甼���B����͈ꍠ����������߂������A���ǂ͌x���������Ă��Ȃ��B
���Z�s�ꂪ�����B�Ȓ����ł́A�s����̂Ȃ��������s���Y�Ɗ��ɗ��ꍞ�݁A����̉ߔM�������Ă����B�@�s���Y�J�������͓��ǂ��K�������߂Ă���̂ɂ�������炸�A�㔼���͑O�N������ 8.5% ���ƍ����L�т�ۂ����B�@15 �N�ɑ�\�����N��������C�����w�������肶��Ə㏸�𑱂��Ă���B�@�K���Ǝ�Ȃ� 7 �� 15 ���̑S�����Z�H���c�ŁA�u�����Ɏ��{�̏o��������R������v�Əq�ׂ��B�@�����A���S���R���̎����͎����Ȃ������B�@���`���P������@�̑O�ɕ`���Ă����A�����̏o���肪���S�Ɏ��R�ɂȂ�o�ς́A���܂����̓����������Ă��Ȃ��B (���` = ���c���V)
��
�� �u���v�̍��ۉ��A�����̍������v�����@�쑺���{�s�ꌤ�����V�j�A�t�F���[�E�֎u�Y��
�����̓A�W�A�ʉ݊�@�ŁA����A�W�A�e����K�ڂɐl������艺�����A���������ێ����A�n��̌o�ϑ卑�ɖ��o���B�@�� 10 �N��̕č������Z��@�≢�B�̍���@���ɂ́A��K�͂Ȍi�C���ʂ��Đ�����f���������A�O���[�o���Ȍo�ϑ卑�ɂȂ����B�@�����̐l�������܂߂ăA�W�A�e���̒ʉ݂́A��{�I�ɒʉ݊�@�ȍ~���h���ɘA�����Ă����B�@�����A�ߔN�͍��`�h���������A�W�A�ʉ݂��A�l�����ɘA������X����������B
�Ƃ�킯 2015 �N�Ĉȍ~�A�l�������h���ɑ��Ēl�����肷��悤�ɂȂ�ƁA�؍��A��p�A�C���h�l�V�A�A�^�C�A�}���[�V�A�A�V���K�|�[���A�t�B���s���Ȃǂ̒ʉ݂��ꏏ�ɉ��������B�@�s��Ŕ���ꂽ���Ƃɉ����āA�������i�Ƃ̗A�o�����͂��ӎ������e�n�̓��ǂ��A���n�ʉ݂��ăh��������������\��������B
��@�̂��тɑ��݊������߂Ă������������A�ʉ݊�@�ɖ|�M���ꂽ�A�W�A�̍��X�̎p�����āA���{�̈ړ��̎��R���͒x�ꂽ�B�@���̏����ƂȂ鍑���̋��Z�@�ւ̉��v�͂��܂��������B�@�i�C��̃c�P�ō��L��Ƃ�u�e�̋�s�v�Ƃ�����s�����ȗZ���@�ւȂǂ̎؋����c���ł���B�@�����̐l���������ۉ����Ă������ǂ����́A�����̋��Z���v�̐i�W�ɂ������Ă���B (������ = �ҏW�ψ��E�g���j�q�Aasahi = 7-23-17)
�i�����ɂ��痧�����A�C�O�}�l�[�Ăэ��݂ɗ�␅
�m�k��/���`�n �����́A�i�t����胀�[�f�B�[�Y�E�C���x�X�^�[�Y�E�T�[�r�X���� 30 �N�Ԃ�ɓ����̊i�t�����������������Ƃɂ��āA�s�K�Ȏ�@�Ɋ�Â��Ă���Ƃ��Ĉ�ɕt�����Ƃ��Ă���B�@���������̂悤�Ȕ����́A�����̊����E���s��ɊC�O�}�l�[���Ăэ������Ƃ���Ȃ��ŁA�����������Ɍ����Ă��邩�ɂ��Ē������q���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�@���ɕ�����Ă���B�@�i�����ɂ��A�����̍����ɂ����ĐV���Ȏ��������o�����킯�ł͂Ȃ��B�@�������A����ɂ�蓯���̌o�ό��ʂ��Ɍ��ʓI�Ɉًc�������A��X�I�ɐ�`���ꂽ���v�̌��ʂɋ^���悵�A�O���l�����Ƃ̌��O�����܂����Ɛ��Ƃ͎w�E����B
���[�f�B�[�Y�� 24 ���ɒ����i�����\���Ă��琔���Ԍ�A���������Ȃ����������͕s�K�Ȏ�@�Ɋ�Â��Ă���A�����o�ς̖����֒��������A���v�̎��g�݂��ߏ��]�����Ă���Ƃ̐������o���܂ŁA�������c���f�B�A�́A�i�����ɂ��ĕ邱�Ƃ͂Ȃ������B�@���[�f�B�[�Y�ɂ�钆�����̊i�����͖� 30 �N�Ԃ�B�@����܂ł́uAA3�v����uA1�v�� 1 �i�K�����������B�@���[�f�B�[�Y���ǎ҂� 26 ���A�������c��オ�����}�����Ȃ�����A�����i�̈������������蓾��ƌ�����B
�������������� MSCI �V�������w���ɂ����钆�����̗̍p��ڎw���A�O���l�����ƂɌ������N��i�̍��s��J�����v�悷�钆���ɑ��āA�C�O�̕]���Ɠ����������߂鐺�͑������肾�B�@���[�f�B�[�Y�ƒ������������ɑ��قȂ錩��������̂ł���A����́A�����̃��X�N�]���ɕK�v�ȏ��ɃA�N�Z�X���邤���ŁA�O���l�����ʂ��鍢���������x�f���o���Ă���\��������B�@�u�����ł́i���j�A�N�Z�X���x���́A�������B���Ђǂ��K�v�Ƃ��鍑�Ƃ͑�Ⴂ���v�ƁA�ʂ̊i�t����Ђ̃A�i���X�g�͐_�o���Ȗ��ł��邽�ߓ����ł��̂悤�Ɍ�����B
�u�������B�͒����ł͂��܂���ł͂Ȃ��B�@�����Ȃ⒆���l����s�i������s�j�̉���x���͂��܂��܂��B�@���ǎ҂ɃA�N�Z�X�ł��邩�ǂ����́A�i�t����Ђ��z���W�ɍ��E�����B�v�@�����ȂƐl����́A�t�@�N�X�ł̃R�����g�v���ɒ����ɉ��Ȃ������B�@20 �J���E�n�� (G20) �̊ē��ǂō\��������Z���藝���� (FSB) �͂��傤�Ǎ����A��������v�ȋ��Z�f�[�^����Ȃ����߁A�V���h�[�o���L���O�i�e�̋��Z�A���I�Z����M�����[���A�m���o���N����̎����Ȃǁj�ɂ���Đ��E�����ʂ�����Z���X�N�Ɋւ�����̍쐬�ɒx�ꂪ�����Ă���Ƃ��āA������ᔻ�����B
���C�ɂ��Ȃ����Z�s����
�����v�̑唼�͋��z�ȍ������~�v�[�����玑�����B����Ă���A�����͓��ʁA���ۊi�t���̏d�v�����d�������ɍςޗ]�T������B�@�܂��A�ꕔ�̃g���[�_�[�͑����Ȃ�Ƃ����ǂ̎x�����������Ƃ݂Ă�����̂́A�����̋��Z�s����i�������C�ɂ��Ă��Ȃ���������B
�l������ 25 ���A�Εăh���� 2 �J���Ԃ荂�l��t�����B�@���[�f�B�[�Y�ɂ��i�������A�ʉ݂̋������֎����邽�ߎ�v���L��s���x�������ƃg���[�_�[�̈ꕔ�͎w�E�B�@���� 26 ���A��i�Ə㏸�����B�@�����̊����s��� 25 ���A�}�������B�@��C�Ɛ[�Z���s��ɏ�ꂷ��L�͊�� 300 �����ō\������� CSI300 �w���́A2016 �N 8 ���ȗ��̑啝�㏸�ƂȂ����B�@�����ł����{�哱�̔������������Ƃ݂��Ă���B
���S�z���p����
���[�f�B�[�Y�͒����̊i�t�����������������R�Ƃ��āA�����̍����������A�����̐����ڕW��B�����邽�ߐ��{���h����Ɉˑ��������邱�Ƃ��\�z����邱�Ƃ��������B�@�����͍����͔F�߂����A���X�N�͊Ǘ��\���Ƃ��Ă���B�@�O���l�����Ƃ͂��łɍ�������D�荞�ݍς݂̂��߁A�����{�y�̍��s��ɑ���S�ɉe�����y�ڂ��\���͒Ⴂ�ƁABNP �p���o�E�C���x�X�g�����g�E�p�[�g�i�[�Y�̃W�����V�������E�T���{�[���͎w�E�B�@�u�������\���������Ɨǂ��������������ƌ����A������v�ƃT���{�[���B�@�u���ɕ��G�ŁA�d�����Ă��邱�Ƃ�����B�@�\�z�͂ǂ�������ł͂Ȃ��B�v
�i�����ɂ���āA�����̍��L��Ƃ����������̎����Ƃ��Ďg���Ă����C�O����̎����R�X�g����i�ƍ����Ȃ�\�������邾���łȂ��A�ꕔ�̊O���t�@���h�͒������Y�̃|�[�g�t�H���I�g�ݓ���ɑ���������\��������B�@�u�i���[�f�B�[�Y���j�����̎���𗝉����Ă���Ƃ͎v��Ȃ��B�v�@�������̂͒����̃V���N�^���N�A�������یo�ό𗬃Z���^�[ (CCEE) �̃`�[�t�G�R�m�~�X�g�㗝�ł��� Xu Hongcai �����B�@�u���N�̒����̌o�ϐ����\�z�͍�N���ǂ��B�@�o�ς͈��肵�A���サ�Ă���B�@�i���[�f�B�[�Y�́j�n�����{�̍��ɂ��ĐS�z���Ă��邪�A���̂悤�ȕK�v�͂Ȃ��B�v (Elias Glenn�AUmesh Desai�AReuters = 5-29-17)
�����̊i�����A���{�̃o�u�������z�N�@���ʂ��o�Ϗ�
�ꕔ�̃G�R�m�~�X�g�͈ȑO����A���������{�Ɠ����^�������ǂ鋰�ꂪ����ƌx�����Ă��� - - �܂�ߏ�Z���Ɍ㉟�����ꂽ�D�i�C�̌�ɒ�����Ɍ������A���̌��ǂɋꂵ�ނƂ������Ƃ��B
�Ċi�t����胀�[�f�B�[�Y�� 24 ���A�����̒������i�t�����uA1�v�Ɉ��������A���Ȃ��Ƃ�����ł͗����̊i�t���͓������ɂȂ����B�@�����́A25 �N�O�ɕs���Y�o�u��������Z�@�ւ̔j�]��@�Ɏ���o�u��������o���������{�Ɠ��l�̖��ɒ��ʂ��A�Ή��Ɏ��g��ł���B�@�������i�t�������{�Ɠ������x���Ɉ���������ꂽ���Ƃ́A���������{�̂悤�Ȍo�ς̒��������Ƃ�邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����s�����Ȃ܂܂ł��邱�Ƃ�z�N�������B
���{�͑� 2 ������}���Ɍo�ς������A1990 �N��ɂ͌o�ϗ͍͂ō����ɒB���A���������Ő��E��̌o�ϑ卑�ɂȂ鐨���������B�@�����A�����͂܂��ё���̒��N�ɂ킽��o�ϐ���̎��s���痧������r��ɂ������B�@���������o�ς� 2001 �N�ɐ��E�f�Ջ@�� (WTO) �ɉ���������A�}�����ɓ]�����B�@21 ���I�ɓ���Ɠ��{��ǂ������Đ��E��2�̌o�ϑ卑�ƂȂ�A�g�b�v�̍���č��Ƒ����܂łɂȂ����B
���[�f�B�[�Y�Ȃǂ��w�E���Ă��钆���o�ς��߂��錜�O�́A���{�� 1990 �N�㏉�߂ɒ��ʂ������Ƌ����镔��������B�@�����̐����̌������ƂȂ��Ă����̂́A�����̓��{�Ɠ����������̐ݔ��������B�@�ݔ������������̔N�Ԑ������ɐ�߂�䗦�́A1990 �N�� 3 ���� 1 ���� 2010 �N�ɂ͂قڔ����Ɋg�債���B
�s���Y���i���}�����A���̃e���|�����ю�����I�t�B�X���ݗ��̏㏸�����͂邩�ɏ����Ă��邱�Ƃ́A���݂̒����� 1980 �N�㖖�̓��{�Ƃ̋��ʓ_�� 1 ���B�@���{�̃o�u���̃s�[�N���ɂ́A�����̏Z��p�s���Y���i�� 1 �N�Ԃ� 69% �����ˏオ�����B�@���������̕s���Y���@�Ƃ͊Ԃ��Ȃ��M���̑㉿���x�������ƂɂȂ����B�@1990 �N�㏉�߂ɂ͓y�n���i�� 15 �N�A���̉������J�n�����̂��B
�s���Y�o�u���̕���́A�K�����s�\�����������{�̋��Z�V�X�e���̐Ǝ㐫��I�悵���B�@����́A���݂̒����ɂ��d�Ȃ荇������ 1 �̌��O�ł���B�@���{���{�͏Z����Z����� 7 �Ђ��~�ς��邽�߂ɑ��z�̌��I�����𒍓������B�@�܂��A�s���Y���i�̍����Ɉˑ������o�c���s���Ă������S�ݓX�������ȂLjꕔ��Ƃ͎�����|�Y�����B
���̏́A�����̈ꕔ��s���e�̋�s�𗘗p���ĉ�v��̑�����s���A�\���ȏ��J���Ȃ��ɕs���Y�Z�����g�債�Ă��邱�Ƃ��v���N��������B�@�����̕s���Y�s��͉ߋ� 2 - 3 �N�̊ԕs�����������A�����ɗ��čĂы}�����n�߂Ă���B�@�k���̕s���Y���i�͍��N����܂ł� 16% �l�オ�肵�Ă���B
���ɂ��ގ��_�͂���B�@1990 �N����ɂ͓��{�̐l���� 15 - 20 �N��ɂ͌������n�߂邱�Ƃ��͂����肵�Ă����B�@���ۂɂ��̒ʂ�ɂȂ��Ă���B�@����Ɛl�������̌��ʂ��́A����҂��Ƃ̃��[�h�𒾑������B�@����Ɠ��l�ɁA���A�̗\���ł͒����̐l���͍������ 15 �N��� 2030 �N�㏉�߂ɂ̓s�[�N�ɒB���A���̌�ɂ͋}������ƌ����܂�Ă���B
���݁A�����̌o�ϓ��v�͂ǂ̒��x���Ă���̂��B�@����̌o�ϓ��v���݂�ƁA���{�̏͒������[���Ȃ悤���B�@2017 �N�� 1 �l�����ɓ��{�o�ς̎����������� 2.2% �Ɣ�r�I�͋����������A����ł������� 6.9% ������傫��������Ă���B�@���{�̍������A�������͂邩�ɐ[���Ȃ܂܂��B�@���ی��ϋ�s (BIS) �ɂ��A2016 �N�� 3 �l���������_�ŁA�����̔���Z����i���{�A��ƁA�ƌv�j�̍��c���̑��������Y (GDP) ��� 256% �ɏ㏸�������A���{�� 373% �Ɠr�����Ȃ��K�͂ł���B
����̍��c���F���ق͍ŋ߁A���������{��葊�ΓI�ɗL���ȓ_�����邱�Ƃ�F�߂��B�@�u80 �N��x���ɓ��{�͊��ɐ��n������i���ƂȂ�A�������� 6.5% ��傫�������A�l���������͂قڃ[���ɂȂ��Ă����B�@��������ł͐l���͂܂������𑱂��Ă���A�s�s���͍����i��ł���v�ƁA���c���̓E�H�[���E�X�g���[�g�E�W���[�i�� (WSJ) �������ŊJ�Â����C�x���g�uCEO �J�E���V���v�ŏq�ׂ��B
����ł��A���{�������������|�I�ɗD�ʂȂ̂́A���{�����łɖL���ȍ����Ƃ������Ƃ��������v���B�@����ɂ��A2015 �N�ɓ��{�� 1 �l������ GDP �� 3 �� 4,524 �h���ŁA������ 8,069 �h���� 4 �{���ɒB���Ă���B�@�����̎w���҂͑����̍\���I���ɗ����������Ă�����̂́A�������L���Ȑ�i���̒��ԓ��������ɂ͂܂��܂���͒����A�����̓w�͂�v����B (Andrew Peaple and Peter Landers�AThe Wall Street Journal = 5-25-17)
�s���Y�A�l�b�g���Z �c �����o�u���Ăс@�K���Ń}�l�[�×�
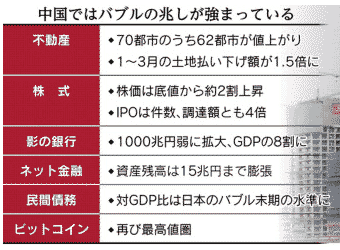
��C�̏Z��A�N���� 20 �{���@�Ő����̓�������
�ʉ݁E�l�����̋}����h�����߂ɊC�O�����Ȃǂ̋K�������߂������ŁA�����ɂ��ӂꂽ�}�l�[���s���Y�s���C���^�[�l�b�g���Z�ȂǂɏW�����A�o�u�����O���Ăы��܂��Ă���B�@�����̉ߔM�ő����̌i�C�͎��������Ă��锼�ʁA�S�z�Ȃǎ����A�����}�����A�o����x���������鋰����o�Ă����B�@�c��ރo�u���͒����o�ς̈���Ȃ��g���v���ɂȂ肩�˂Ȃ��B
��C�s�x�O�̏����R���B�@�H��Ȃǂ��_�݂���s�ւȒn�悾���A��C�s�������������y�n�� 3 �����̗��D���i�� 1 �������[�g�������� 3 �� 6 �猳�i�� 58 ���~�j�B�@1 �ؓ�����͉~���Z�Ŗ� 190 ���~�ƁA�����E���c�J�Ȃǂƕς��Ȃ��B�@�Z���́u�}���V���������Ă�� 1 �������[�g�������� 5 �����v�Ɖ\����B�@�쑺���{�s�ꌤ�����ɂ��ƁA2015 �N�̏�C�̐V�z�Z��i�͕��ϔN���� 20.8 �{���B�@�����J���e�C�ɂ��� 1990 �N�̓����� 18.1 �{�B
�����̑�s�s�̏Z��͂��łɃo�u�����̓��������鍂���̉Ԃ����A��C�ł� 15 �N���瑫���܂ł���� 4 ���l�オ�肵���B�@�k����L���Ȑ[�Z�������l�ŁA���N 3 ���͎�v 70 �s�s�̂��� 62 �s�s�ŏZ��i���㏸�B�@1 - 3 ���� 300 �s�s�̓y�n���������z�� 1 �N�O�� 5 �������B�@�l�オ����҂����������������A����ɉ��i�������グ�Ă���B
���ǂ̖ڂ��͂��Ȃ��u�e�̋�s�i�V���h�[�o���L���O�j�v�����ĔR���n�߂��B�@�C���^�[�l�b�g��ʂ��Čl���������������Ƃ肷��u�s�A�E�c�[�E�s�A (P2P) ���Z�v�̎c���� 4 ������ 9,500 �������ƁA1 �N�O�� 1.7 �{�ɖc��B�@��ƂȂǂ���s��ʂ��ė]�莑����݂��o���u�ϑ��Z���v�� 13 ������˔j�B�@1 �N�O��� 2 �������A�ꕔ�͉^�p�悪�s�����ȓ������i�i�������i�j�ɗ����B�@�ϑ��Z���◝�����i�ȂNj��`�́u�e�̋�s�v�� 16 �N���� 60 ������ƁA���������Y (GDP) �� 8 ���̋K�͂��B
�x�C���E�A���h�E�J���p�j�[������\�̊ؔ������́u���{�K���ŊC�O����������Ȃ�A�����ւ̊җ����N���Ă���v�Ƃ����B�@�������{�͕ė��グ�ɔ����}���Ȍ����⎑�����o��h�����ƁA16 �N�����玑�{�K���̋����ɓ����A500 ���h���i�� 5 �� 6 �疜�~�j���C�O M & A �i�����E�����j�ȂǂɎ�����A�҂������������B�@�����͏]���A�������܂��������̂��Ƃ�𐧌����Ă������A�o������i�ƍi��ꂽ�}�l�[�������ɂ��ӂꂽ�B
15 �N�Ăɉ��i�}���ɏP��ꂽ�����s��ɂ������������߂��Ă���B�@�� 3,200 �Ђ� 16 �N 12 �������Z�̍��v�����v�͑O�̊��ɔ�� 5% ���������̂ɑ��A�����̏�C�����w���� 16 �N���߂̒�l���� 2 ���߂��㏸�����B�@1 - 4 ���̐V�K�������J (IPO) �� 167 �Ђ� 1 �N�O�� 4 �{�ɖc��B�@�x���`���[������ 1 - 3 ���� 535 ������ 3 �l�����Ԃ�ɑ����B�@�V�F�A�T�C�N���� ofo �� 3 ���A4 �� 5 �疜�h���B���A����Ȃ���]���z�� 10 ���h�����u���j�R�[���v�ɒ��ԓ��肵���B�@���z�ʉ݃r�b�g�R�C���̌����ĉ��i�� 9 �猳�O��ƍō��l���Ő��ڂ���B
�����l����s�i������s�j�̎����쑍�ق́u�ߓx�̗������̓C���t����o�u�����N�����v�ƌx������B�@�����Ƃ��A�������{�������u�[���ɉ�t���Ă���ʂ������B�@������ 1 - 3 ���̍������x�� 1,551 �����̐Ԏ��B�@1 - 3 ���̐Ԏ��� 1,995 �N�ȗ� 22 �N�Ԃ肾�B�@�H�̋��Y�}�����T���A���{���i�C�����肳���悤�ƃC���t���������������Ă���B�@1 - 3 ���̎�v���@ 25 �Ђ̃V���x���J�[�̔̔��䐔�͑O�N������ 98% �������B�@1 - 3 �����ς̉��������͑O�N������ 7.4% �㏸�ƁA16 �N�ʔN�� 1.4% ��������}���]���Ă���B
�����ł̉ߏ蓊���́A�o����x�̈����Ƃ�������p�������炵�Ă���B�@���m�ɉ����A�m�I���Y����Ȃǂ��܂߂��f�ՁE�T�[�r�X���x�̍����� 1 - 3 ���� 187 ���h���ƁA�O�N������ 64% �������B�l�����ł͐Ԏ����L�^���� 14 �N 1 - 3 ���ȗ��A3 �N�Ԃ�̒ᐅ�����B�@���������̊g��œS�z�Ȃǂ̗A�����{���A�f�Ս����� 25% ���������߂��B�@�������x�� 16 �N�܂� 2 �N�A���̐Ԏ��ŁA�f�ՁE�T�[�r�X���x�ƍ��킹���o����x�̍����� 16 �N 10 - 12 ���ɑO�N������ 86% ���� 118 ���h���B�@�o�퍕���̌����������\��������A�ʉ݁E���̐M�F��h�邪�����ꂪ����B
�����o�ς� 6% ��㔼�̐�����ۂ��A���Z�s��Ɉ��S�����Y���B�@����ŁA�����̋��Z�@�ւ��������ԍ��� GDP �� 200% ���Ɠ��{�̃o�u���������݂��B�@�x�������߂�l����͋��Z������������ߋC���ɉ^�c���n�߂����A�Ѝ̔��s�����⒆�~���������Ƃ������e�������łɏo�Ă���B�@���@�̉ߔM�����܂��}�����߂Ȃ���A�݂��|��̋}���ȂǁA���E���Ăђ������X�N���ӎ�����W�J���������𑝂��B (��C = ���E�ˁA�k�� = ���c���Anikkei = 5-6-17)
�����l����A�I�݂ȍٗʓI�����g�Ń��X�N�}����
�m�k���n �����l����s�i������s�j�͋���������K���ē̖ʂŎ���̍ٗʗ]�n���I�݂ɋ�g���A�������Z�V�X�e���̃��X�N�}����i�߂Ă���B�@���傫�ȑ_���́A�����I�ɋɂ߂ďd�v�ȏH�̋��Y�}�S����\����O�ɁA�o�ς�Љ�̈�����m�ۂ��邱�Ƃ��B�@�����̊W�҂����炩�ɂ����B�@�����Ɋւ��ẮA�ύX����ꍇ�ɍ����@�̏��F���K�v�Ȑ�������̑���Ɏs�꒲�߂����ϋɓI�Ɋ��p���A�^�C�����[�Ō��ʓI�ȋ����`����ڎw���B�@����A�K���ēł͋�s�̃��X�N�����Y�̒~�ς�_���E�������邽�߂̎�@���������A���̓��ǂƂ̊Ԃɖ��C���N���Ȃ��悤�H�v���Ă���B
�����͍��A���@�o�u����X�N�̑傫���Z����}�����݂Ȃ���A�}���ȋ��Z�������߂Ōo�ςɑŌ���^����͔̂�����K�v������Ƃ�����������ɍ����|�����Ă��邪�A�l����͂�������������ʂ��đΉ��\�͂����߂Ă���`���B�@���鐭��A�h�o�C�U�[�́u�����͑傫�ȃV�X�e�~�b�N���X�N�ɒ��ʂ��Ă���A2017 �N�͂����̃��X�N�𐧌䂷�邽�߂̑厖�ȔN���B�@�l����͋K���ʂ̋@�\���g�����A�i���X�N����ɂ����āj�D�z�I�Ȗ�����w��������B�v�Ǝw�E�����B
�l����� 1 ���ɒ����ݏo�t�@�V���e�B�[ (MLF) �����A2 ���ɏ�ݑݏo�t�@�V���e�B�[ (SLF) �����ƃ��o�[�X���|���������ꂼ������グ���B�@����� 3 �� 16 ���ɂ͒Z���s��̋��������߂ɗU���B�@�G�R�m�~�X�g�́A�č��̗��グ�ɑΉ����Ď������o�Ɏ��~�߂������A�l�����̈����}�����Ǝ~�߂��B�@������A����肪�������ɑ��z�̍����������ƃZ�N�^�[�Ɉ��e�����y�ڂ����˂Ȃ���������̈����グ����T���A�����̎s����������߂ɗU��������Z���傫���A�Ƃ����̂����l���̐���A�h�o�C�U�[�̌����Ă��B
2 �l�ڂ̃A�h�o�C�U�[�́u�����o�ς̊�{�I���͂��������P���Ă�����̂́A�������߂��}���߂���Ɩ�肪�N���Ă����������Ȃ��v�Əq�ׂ��B�@�l����̓Ɨ����͂܂����������̒���ɔ�ׂ�Ǝキ�A�������������l�����̐����Ɋւ���ŏI�I�Ȕ������͂Ȃ��B�@���Z����ƒʉݐ���̑傫�ȕ������͋��Y�}�w���������肵�Ă���B
������Ƃ��Ă̊�����
�l����͒��炭���ق߂�����쎁�̉��ŁA���܂��܂ȉ��v���哱���Ă����B�@�����I�ȖڕW�͋�s�̎����R�X�g���s��̌���Ɉς˂镔����傫�����āA�����z���̌����������߁A�o�ς����������ˑ�����E�p�����邱�Ƃɂ���B�@2015 �N�ɂ͊����}����ɁA��s�A�ی��A�،��̋K�����ǂ� 1 �ɂ܂Ƃ߂�u�X�[�p�[�ē@�ցv�̍\�z�����サ�����A�����S���҂�W�Ȓ��̊Ԃł͂��܂��ɋK���̌n�̔��{�I�Ȍ��������ǂ̂悤�ɐi�߂Ă��������ӂ͐������Ă��Ȃ��B
�ʂ̃A�h�o�C�U�[�́u���{�I�Ȍ��������߁X�s��ꂻ���ɂ͂Ȃ��B�@�Ȃ��Ȃ炳�܂��܂ȗ��Q�W��l���A�Ȓ����m�̂�����݂�����ł��邩�炾�B�v�Ɛ��������B�@�����Ől����́u�}�N���v���[�f���X�]�� (MAP)�v���r���𗁂тĂ���B�@MAP �͍�N��������A�e��s�̎��Y�̎��⎑�{�A���������Y�䗦�Ȃǂ��w�W�Ɋ�Â��Ďl�������Ƃɐ��ѕ]�����鐧�x�B�@��̓I�ȕ]�����ڂ͌��\����Ă��Ȃ����A�W�҂̘b�ł͑� 1�E�l�������痝�����i (WMP) ��Ώۂɉ������Ƃ݂���B
�����菤�Ƌ�s�́u���Z���X�N�𐧌䂷�邽�߂ɂ́A�قȂ����@�ւ�����ɓ������̋K���̌n�ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@�l����s���ʉ����ʂ◬�����̊Ď��ƃV�X�e�~�b�N���X�N�̐���Ƃ����g����^�����Ă���_�܂���A���X�N������̒��S�ɐ�����̂͗��ɂ��Ȃ��Ă���B�v�Ƙb�����B�@2 �l�ڂ̃A�h�o�C�U�[�́u�����̋��Z��������������ꂪ����B�ꂽ���X�N���������݂���ȏ�A�l���₪ MAP �̉��ŋK���@�\�����߂�K�v������v�Ǝ咣���Ă���B (Kevin Yao�AReuters = 4-14-17)
�u���E�̍H��v�ŕ����ڎw�������@�x�g�i���̒nj��ɑR�p��
�����͂��Đ��E�̍H�ꂾ�����B�@2011 �N�ɂ͕č����A���E�ő�̐����i���Y���ɂȂ����B�@�H��͏����������グ��G���W���ɂȂ�A�����̍��� 1 �l������� GDP �� 2013 �N�܂ł� 10 �N�ԂŔ{�������B�@�����A�����͌o�ϐ�������̃T�X�e�i�r���e�B���m�ۂ��邽�߁A2011 �N���납�獑�������T�[�r�X�Z�N�^�[�ւ̓������d������悤�ɂȂ����B
�����Ē����͍��A���E�̍H��̃|�W�V���������߂����Ƃ��Ă���B�@���̓����́A�����̍ő�̃��C�o���ƂȂ����x�g�i���ɑR������̂��B�@���{�n�V���N�^���N�̒������یo�ό𗬃Z���^�[�ɂ��ƁA�����ւ̊C�O���ړ����͍��N 15% �������A�L�ї��͑O�N�� 4.1% ���錩���݂��B�@�C�O���{�ւ̊J������ƁA�C�O����̓����葱���̐v�������A���ړ����̐L�тɂȂ������Ƃ����B�@�����̉p�����f�B�A�̃`���C�i�f�C���[�́u�V�ޗ��A�V�Z�p���삪�����̑������������Ă���v�ƕ����B
�����͎��{���o��H���~�߂�K�v�����邪�A���{���o�̑����́A�����������ߑ��Ő���������ƍl���Ă��钆����Ƃɂ����̂��B�@���{���o�� 2015 �N�� 1 ���h���i�� 114 ���~�j�ɒB���A2016 �N�����قǕς��Ȃ��Ƃ݂��Ă���B�@�V���K�|�[���̃��[�f�B�[�Y�\�u�����̃}���[�E�f�B�����́uFDI �i���ړ����j�����z���� FDI ���o�z�������������z�́A���� 2 �N�ԃ}�C�i�X�������A�O�ݏ����������炵�Ă���v�Əq�ׂ��B
�`���C�i�f�C���[�ɂ��ƁA��N�̊C�O����̑Β������� 1,180 ���h���i�� 13 �� 5,000 ���~�j�ŁA������ GDP �� 2% �ɂ��y�Ȃ��B����A�x�g�i���ւ̊C�O���ړ����z�� GDP �䗦�͒����A�C���h�A�C���h�l�V�A������ 6% �ŁA�����̉Ƌ�[�J�[����t�H�b�N�X�R����T���X���d�q�Ƃ�������Ƃ��x�g�i���ɓ������Ă���B�@���E�̍H��Ƃ��đ��݊������߂�x�g�i���́A�N�� 6% �߂��o�ϐ������������Ă���B
�G���N�g���j�N�X����ŋ}�L�̃x�g�i��
�x�g�i���͂���܂ňߗނ�Ԃ̕��i�����ȂǁA��t�����l�̍�Ƃ�S���Ă����̂ɑ��A������PC�̂悤�ȍ��t�����l���i�̐�����S���Ă����B�@�������A�x�g�i�������� 5 �N�œd�q���i�̐������_�ɕϖe������B�@�ăV���N�^���N�Œ����r�W�l�X�����̃X�R�b�g�E�P�l�f�B�́u�����Њ�Ƃ͐̂̂悤�ɒ����ւ̓����ӗ~�������Ă��炸�A�����𑼂̏ꏊ�Ɉڂ����Ƃ��Ă���v�Ǝw�E�����B
���E�̍H��̃|�W�V�����̕�����ڎw�������ɑ����A�x�g�i���̓����͂�芈�������邩������Ȃ��B�@�z�[�`�~���s�ݏZ�̃R���T���^���g�́u����ł̓x�g�i�����U�v���Ă���̂́A�����o�����[�`�F�[���̉����ɂ���Ǝ킾�B�@�܂�A�x�g�i���̐����͂܂����ꂩ�炾�B�v�Əq�ׂ��B (Ralph Jennings�AForbes = 3-7-17)