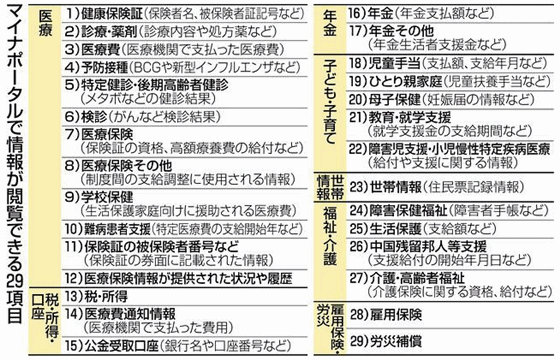対面で本人確認、IC チップ活用義務化へ 精巧な偽造免許証に対策
警察庁は 4 日、金融機関などの窓口で対面して預貯金口座を開設する際は原則、マイナンバーカードや運転免許証などにある IC チップでの「本人確認」を義務化する方針を決めた。 偽造品による本人確認を防ぐのが狙い。 5 日から 2026 年 1 月 3 日まで意見を公募したうえで犯罪収益移転防止法の施行規則を改正し、27年4月1日の実施を目指す。 警察庁によると、現在は運転免許証などの提示で本人かどうかを確認している。 ただ、近年は精巧に偽造された免許証を使って不正に口座が開設され、特殊詐欺などに悪用されるケースが出ている。 こうした事件の摘発は 24 年に 67 件あった。
非対面は既に決定
こういった偽造品の悪用を防ぐため、警察庁は IC チップの読み取りによる本人確認に限定したい考えだ。 マイナンバーカードなどを持っていない人については、住民票の写しなどでの本人確認も認める。 その場合、金融機関など事業者側から送られる書類は転送不要に設定される。 警察庁の楠芳伸長官は 4 日、定例の記者会見で「匿名・流動型犯罪グループによる預貯金口座などの悪用を防止し、特殊詐欺などの被害の防止につながると期待している」と述べた。 非対面での本人確認を原則 IC チップで行うことは既に決まっており、27 年 4 月から実施される。 (板倉大地、asahi = 12-4-25)
マイナ免許、9 月にシステム改善 マイナ更新時も免許情報を引き継ぎ
今年 3 月に始まったマイナンバーカードと運転免許証が一体化された「マイナ免許証」にシステム上の問題点が浮上しており、警察庁が改善に乗り出す方針を固めた。 マイナ免許証に一体化した後にマイナカードの更新期限を迎えて更新の手続きをした場合、免許情報が新しいカードに引き継がれず、再び運転免許センターなどを訪れて一体化する必要があった。 そこで、警察庁は、マイナカードを更新した場合でも免許情報が引き継がれるようにシステムを改善する。
一体化の手続きは 3 月 24 日に始まり、警察庁によると、マイナ免許証の保有者は 6 月末で 86 万 8,188 人。 うち 7 割近くが通常の運転免許証との 2 枚持ちだった。 システムが改善されれば、マイナカードを更新する際にも免許情報が自動的に引き継がれるようになる。 8 月 9 日までパブリックコメントを行い、9 月 1 日からの実施を目指す。 警察庁は、システムを改善するまでは、マイナンバーカードの更新後に一体化の手続きをしてほしいと呼びかけている。 (板倉大地、asahi = 7-11-25)
マイナ保険証に代わる資格確認書、普及進まず 75 歳以上全員に送付へ
マイナンバーカードと健康保険証が一体化したマイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、75 歳以上の高齢者らを対象に、従来の健康保険証と同じように利用できる「資格確認書」が自動的に配られることになった。 厚生労働省が 3 日の審議会に方針を示し、了承された。 これまでは新たに 75 歳になったり、転居したりするなど、健康保険の資格情報に変更があった人を対象に 7 月まで配布予定だったが、対象を拡大して来年 7 月末まで使えるようにする。
健康保険証は昨年 12 月に新規発行が停止。 資格確認書はマイナ保険証に本格移行する際に導入された。 資格確認書は事実上、従来の保険証と変わらない。 75 歳以上の高齢者らが入る後期高齢者医療制度の保険証の有効期限は 1 年間。 毎年 7 月末に一斉に期限を迎えるため、厚労省は、資格確認書の交付を求める申請が自治体の窓口に殺到する恐れがあるとみて、配布期間を事実上延長した。 75 歳以上のマイナ保険証の利用率がほかの年代に比べて低いため対象者も広げ、75 歳以上のすべての人に資格確認書を交付することにしたという。
75 歳未満に対しては、マイナカードを持っていない人やマイナカードを持っているが保険証としての登録をしていない人に対して、資格確認書が送られる。 従来の保険証の有効期限が切れる前に、加入する健康保険から送られる。 有効期限は 5 年以内で、加入先の健康保険が決める。 (足立菜摘、asahi = 4-3-25)
マイナ免許取得、8 日間で 12 万人 オンライン講習利用は 300 人
マイナンバーカードと運転免許証の一体化の手続きが始まった 3 月 24 - 31 日に「マイナ免許証」を取得した人は、全国で 11 万 7,589 人だった。 警察庁が 3 日に発表した。 免許証の保有者は 2023 年末時点で約 8,186 万人おり、マイナ免許証の取得はこのうち 0.1% だった。 マイナ免許証は運転免許センターなどで手続き可能で、従来の免許証を持ち続けることも、両方を所有することもできる。 3 月末までの 8 日間に取得した人のうち、4 割近くがマイナ免許証のみを選んだ。
8 日間で免許証の更新をした人は全体で約 45 万人おり、うち 9 万人ほどがマイナ免許証にしたという。 マイナ免許証を持っていれば、免許証の更新時に講習をオンラインで受講できる。 ただ、更新よりも前に一体化の手続きを終えていなければならないため、8 日間でオンライン講習を受けた人は 322 人にとどまった。 (板倉大地、asahi = 4-3-25)
◇ ◇ ◇
マイナ免許手続き開始 マイナ更新で免許情報引き継がれず、秋に修正
マイナンバーカードに運転免許証の情報を入れて一体化する手続きが、24 日に全国で始まった。 一体化は希望者が対象で、運転免許センターなどでできる。従来の免許証を持ち続けることも、両方を所有することも可能だ。 警察庁によると、一体化の手続きでは、マイナカードの IC チップに免許情報を記録する。 「マイナ免許証」を持っていれば、免許更新時の講習をオンラインで受講できるという。
ただ、マイナカードの更新期限が近い人は注意する必要がある。 現在のシステムでは、マイナカードと運転免許証の一体化の手続きをした後に、マイナカードを更新したら新しくカードが発行されるが、そのカードには免許情報が引き継がれない。そのためマイナカード更新後に再び一体化の手続きが必要になる。 マイナカードの更新時に自動的に免許情報が引き継がれるように、今秋ごろまでにシステムを改修するという。 警察庁は「マイナカードの有効期限が近い人は、更新してから免許証と一体化させてほしい」と呼びかけている。 (板倉大地、asahi = 3-24-25)
◇ ◇ ◇
マイナと免許証の一体化、24 日開始 22・23 日はシステム停止に
マイナンバーカードと運転免許証を一体化する手続きが、24 日から全国で可能になる。 警察庁のシステムを新たな「マイナ免許証」へ移行する作業に伴い、22 - 23 日は全国で免許の更新などの手続きができなくなる。 全国的にシステムを止めるのは1969 年の運用開始以降で初めて。 警察庁によると、一体化は運転免許センターなどで 24 日の開業時から可能だ。 希望者を対象にしており、従来の免許証を持ち続けることも、両方を所有することもできる。
免許の更新時に一体化する場合の手数料は従来より 400 円安い 2,100 円で、更新時以外では 1,500 円。 新たに免許を取得する際にマイナ免許証を選んだ場合は、従来より 500 円安い 1,550 円だ。
レンタカー利用にはアプリ有効
マイナ免許証を取得する際に自治体側から警察への情報提供に同意すれば、住所変更時に必要だった警察への届け出が不要になる。 また、マイナ免許証を持っていれば、免許更新時の講習をオンラインで受講できるようになる。 12 日には、マイナ免許証をスマートフォンで読み取り、免許証の情報をスマホ画面に表示させるアプリがリリースされた。 マイナ免許証の表面には免許証の情報が記載されていないため、レンタカーなどで提示する際などにはアプリが有効だという。 (板倉大地、asahi = 3-17-25)
マイナ保険証のアプリに不備 不同意なのに医療情報提供 最大 73 件
「マイナ保険証」を使った医療情報の提供について、本人が同意していないのに医療機関に情報が漏れる事案が最大 73 件起きたと、厚生労働省などが 22 日発表した。 訪問診療や訪問看護で医療従事者がスマートフォンで使うアプリにプログラムの不備があったという。 漏れた情報は、過去の処方薬に関する調剤日や薬品名、調剤量などで、最大 37 人分の計 73 件。
マイナ保険証は、医療機関や薬局での受付時、カードリーダーに暗証番号を入力するなどして患者の保険資格が確認できる。 患者が画面で「同意する」ボタンを押せば、患者の過去の診療情報や薬剤情報などが医療機関や薬局に提供される。 アプリを特定の手順で操作した際、情報提供に「不同意」と入力したはずが、薬剤情報だけ「同意」扱いとなるプログラムのミスがあったという。 アプリが稼働し始めた昨年 10 月当初から不備があり、今月 20 日に解消されたという。
情報を管理する社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会(いずれも厚労省の外郭団体)は、今回の問題を個人情報保護委員会に報告した。 同意していないにもかかわらず薬剤情報が照会された可能性のある 37 人に、おわびと経緯の説明をする予定。 また、アプリ開発会社の富士通と連携して原因究明と再発防止に取り組むとしている。 (吉備彩日、asahi = 1-22-25)
従来の保険証、発行停止に マイナ保険証へ本格移行 利用率低いまま
従来の健康保険証の新規発行が 2 日から停止された。 マイナンバーカ>従来の保険証、発行停止に マイナ保険証へ本格移行 利用率低いままードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」への移行を踏まえた対応。 今後の医療機関の受診では、マイナ保険証の有無などで留意すべき点もある。 一方、マイナ保険証の利用率は低迷しており、厚生労働省などが普及に取り組んでいる。
三つのケース、留意すべきこととは …
従来の健康保険証は、2 日以降は新規発行されない。 だが、発行済みの健康保険証は、有効期限が切れるまでこれまで通りに使える。 有効期限が示されていない保険証が使用できるのは 2025 年 12 月 1 日までだ。 マイナ保険証を持っていない人らには、従来の保険証の期限が切れる前に「資格確認書」が自動的に送られてくる。 従来の健康保険証と同じように利用できる。 マイナ保険証を持っている場合で、12 月 2 日 - 25 年 7 月 31 日の間に 75 歳になる人と、同じ期間に公的医療保険の資格情報が変更となった 75 歳以上の人についても、資格確認書が自動的に送付される。
相次いだ問題 …
マイナ保険証をめぐっては、これまで問題が相次いだ。 23 年 5 月にマイナ保険証に別人の情報がひもづけられていた事例が発覚。 政府が 1 億 6 千万件分のデータを点検した結果、判明した情報のひもづけ誤りは、9,223 件。 窓口で負担割合が違って表示されるトラブルも 2 万 1,574 件が確認された。 いったん 10 割を請求される例もあった。 マイナ保険証のひもづけ誤りについて、政府は、保険者(会社の健康保険組合など)が、データ入力を誤ったことなどが原因と分析。 負担割合が違って表示されるトラブルもシステムの仕様などによって起きたものだとわかった。
いずれの問題も、事務処理のマニュアルを作成して保険者に周知したり、定期的に誤りをチェックする仕組みを導入したりするなどの防止策がとられている。 ただ、利用者は大きく増えていない。 マイナカード保有者(約 9,400 万人)の約 8 割にあたる約 7,600 万人が、マイナ保険証としての利用を登録済み。 だが今年 10 月時点の利用率は 15.67%。 1 年前の 4% 台と比較すると増えているが、いまだ一部に限られている状況だ。
厚労省が 8 月、マイナカード保有者 2 千人に実施したマイナ保険証に関するインターネット上のアンケートでは、39.5% の人が「個人情報がまとまって管理されることが不安だ」と回答。 38.4% が「持ち歩いて紛失してしまわないか心配だ」と答えた。 厚労省はマイナ保険証の普及に向けた取り組みを続けている。 ホームページ などで使い方やメリットを紹介している。 (吉備彩日、asahi = 12-2-24)
マイナ保険証対応の義務化は適法、医師らの訴えを退ける 東京地裁
医師らが患者を診療する際、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」への対応を義務づけられるのは違法だとして、医師や歯科医師ら 1,415 人が国を相手取り、義務がないことの確認などを求めた訴訟で、東京地裁(岡田幸人裁判長)は 28 日、請求を棄却する判決を言い渡した。 国は健康保険法に基づく規則を改正し、2023 年 4 月から医療機関に対し、マイナ保険証を使った保険資格の確認に応じることや、確認のためのオンラインシステムに関わる機器の導入などを義務づけた。 原告側は、機器導入に多大なコストがかかり、医療機関の廃業のおそれにつながるなどと訴えた。
判決は、マイナ保険証への対応の義務化について「制度運営の効率化や、正確なデータに基づいたより良い医療のためと認められる」と指摘。 義務化によって医療機関に経済的な負担が生じても「事業継続を困難にするとはいえず、医療活動の自由に重大な制限を課すものではない」として訴えを退けた。 政府は紙の保険証からマイナ保険証への移行を進めており、12 月 2 日には現行の健康保険証の新規発行が停止される。 (米田優人、asahi = 11-28-24)
偽造マイナカード見抜くアプリ開発 デジ庁、8 月下旬にも提供開始
偽造されたマイナンバーカードで本人になりすまし、携帯ショップでスマートフォンをだまし取られる事件などが相次いだことを受け、デジタル庁が偽造を見抜くためのスマホ用アプリを開発した。 8 月下旬から一般向けに提供を始める予定。 マイナカードの IC チップを読み取ると、券面にある顔写真や氏名などの情報がスマホ上に表示される仕組み。 携帯電話の契約や金融機関の口座開設時の利用を想定しており、お店側は表示された情報で本人確認できる。 スマホ内に個人情報は保存されない。
河野太郎デジタル相は 1 日、アプリの実証実験をしている東京都渋谷区内の三井住友銀行の店舗を視察し、「チップの読み取りが早くスムーズだった。 利用者に負担をかけずに安全性が高まる.。」と話した。 全国で偽造マイナカードによる事件が起きており、政府は 6 月の犯罪対策閣僚会議で、対面時の本人確認の際に身分証の IC チップ読み取りを義務づける方針を示した。 デジタル庁は、運転免許証の IC 読み取りアプリの開発も検討しているという。 (神野勇人、asahi = 8-1-24)
避難先で薬が分からない 災害時モードで情報確認 能登地震で活用
少子高齢化、人材不足、創薬の遅れ - -。 医療をめぐる様々な課題の解決策として「医療 DX」の活用が始まっている。 その先にはどのような将来像が描かれているのか。 1 月 1 日に起きた能登半島地震。 今回の災害では、医療 DX の一つ「災害時モード」が初めて長期的に運用された。 避難生活を送る高齢者らが、ふだん使っている薬の名前がすぐにわからない例もあった。 災害時モードを使うことで、こうした患者の過去の診療や薬の情報などを避難先の医療機関や薬局は参照することができ、適切な医療につながった。
石川県七尾市でクリニックを営む日本医師会の佐原博之常任理事は 1 月 4 日から診察を始めた。 電気は使え、電子カルテなどのシステムも稼働していた。 だが、能登北部から避難した患者の中には、保険証やお薬手帳を持っていない人もいた。 そこで、診療や処方薬の情報を閲覧できる「オンライン資格確認システム」の災害時モードを活用。 患者の名前や生年月日などの基本情報を入力することで、過去の薬の情報を確認できた。 佐原さんは「今回のような多くの人が避難せざるを得ないような災害では、すごく役に立った」と話す。
金沢市の城北診療所では 1 月、避難中の患者約 160 人を診察した。 患者の 1 - 2 割ほどは保険証を持っていなかった。 「保険証がないけどどうしよう」と不安がる人もいたが、災害時モードで情報を確認できることを伝えると、安心してもらえたという。 厚生労働省によると、石川県や近隣県の医療機関で情報が閲覧された回数は、のべ約 3 万 2,600 件(5 月 2 日で運用終了)。 主にかかりつけではない医療機関で診察を受けた患者への薬の処方時に活用されたという。 石川県薬剤師会の中森慶滋会長は「多くの人は『高血圧の薬』や『白い錠剤』と覚えている。 災害時モードで、服薬履歴を正確に得ることができ、現場はとても助かった」と話す。
光回線断絶で利用できず
過去にどんな医療行為を受け、どんな薬を処方されたのか。 こうした患者の基本的な医療情報はオンライン資格確認システムに登録される。 9 割以上の医療機関が光回線などでこのシステムに接続している。 患者が、健康保険証とマイナンバーカードが一体化した「マイナ保険証」で同意すれば、医療機関や薬局は端末で患者の過去の診療・薬剤情報を閲覧し、より効率的な医療を提供できる。 だが、災害時には手ぶらで避難し、患者がマイナ保険証をもっていないこともある。 システムを災害時モードに切り替えることで、患者の名前や生年月日など基本情報のみで情報にアクセスできる。
課題もある。 光回線で医療機関にひもづいた端末を使う必要があり、避難所など端末がない場所や臨時診療所では情報を閲覧できない。 佐原さんによると、七尾市内の一部地域では、光回線の断絶によりシステムを利用できなかった医療機関もあったという。 厚労省によると、訪問診療で利用できるように、光回線を必要としない携帯端末での運用が 4 月から始まっている。 ただ、その場で確認できるのは保険資格のみで、医療情報は見られないという。 大規模停電時の活用や施設同士での連携のあり方も検討課題となっている。
また、閲覧できる情報は、診療報酬明細書(レセプト)をもとにしているため、最新の薬剤情報の反映までに 1 - 2 カ月ほどかかる。 直近で薬を変えたり追加したりした場合は、古い情報しか見られない。 「電子処方箋(せん)」ならばリアルタイムで情報が反映される。 政府は、2025 年 3 月末までにほぼすべての医療機関での導入を目指しているが、活用は進んでいない。 厚労省によると、6 月 9 時点で、全国の約 2 万 1 千施設の薬局で電子処方箋システムが導入されている。 薬局での導入率は 36% であるのに対し、薬を処方する側の病院では全国でわずか 131 施設(導入率 1.6%)、医科クリニックは 2,469 施設(同 3.0%)、歯科クリニックは 90 施設(同 0.1%)の導入にとどまっている。 (吉備彩日、後藤一也、asahi = 7-8-24)
ネットで本人確認、マイナカード使いやすく 利用情報が国に? 懸念も
デジタル庁は 21 日、スマートフォンとマイナンバーカードを使い本人確認をする無料の「デジタル認証アプリ」を 24 日から提供すると発表した。 マイナシステムでの本人確認を企業のオンラインサービスでも使いやすくし、コスト削減やマイナカードの利用拡大を図る。 一方で個人の利用状況を国が把握することにつながるとの指摘もある。 マイナカードを使ったスマホでの本人確認では、企業側でシステムの開発や検証をする必要があることが普及の障害になっていた。 今回のアプリと連携するだけで、企業側は本人確認機能を利用できるようになる。 月内にも横浜市の子育て応援アプリや三菱 UFJ 銀行の口座開設アプリへ導入されるという。
21 日に会見した河野太郎デジタル相は、アプリ提供によって「開発コストを抑えた形で本人確認をすることができるようになる」と話した。 ただ、個人によるサービスの利用状況が政府によって把握される恐れもある。 認証アプリが利用されると、総務省などが所管する地方公共団体情報システム機構 (J-LIS) に照会が行われる。 デジタル政策に詳しい国立情報学研究所の佐藤一郎教授は、「政府はマイナカードを持つ個人がどんな手続きをしたのかなどを把握できる」と指摘する。
デジ庁が今年 1 - 2 月に実施したパブリックコメントでも、「個人が官民の各種サービスを利用した履歴が蓄積し、一元管理されてしまう」、「情報漏洩のリスク(が)上がる」といった反対意見が寄せられた。 デジ庁は「個人情報保護法も踏まえ、厳格なアクセス制御、暗号化などのセキュリティー対策を講じる」としている。 また河野氏は 21 日、デジタル社会の実現に向けた重点計画を改定し、政府と自治体が共同で運用するシステム「ガバメントクラウド」への移行支援といった政策を進めるため、デジ庁職員の数を今の約 1.5 倍の 1,500 人規模に増やす計画も明らかにした。 (上地兼太郎、asahi = 6-21-24)
マイナカード、来春にも iPhone で利用可 かざすだけで読み取り
米アップルは日本時間 30 日、来年春にも iPhone (アイフォーン)でマイナンバーカードの機能が使えるようにすると発表した。 物理的なカードを持たなくても、コンビニで証明書交付などが受けられるようになる。 岸田文雄首相が同日午前、アップルのティム・クック最高経営責任者 (CEO) とテレビ形式で会談、合意した。 使い方は、iPhone 向けのアプリ「ウォレット」を開き、マイナカードを選んでサイドボタンをダブルクリック。 顔認証機能「フェース ID」で認証した後、コンビニや病院などの非接触読み取り機にかざせば利用できる。
米国では免許証も iPhone に
マイナカードは券面として iPhone 上で目で見ることができるが、利用者がいつ、どこで、どのような個人情報を共有したかなどの履歴は暗号化され、端末上だけで保存される。 端末を紛失した場合は、「探す」アプリで位置を特定できるほか、遠隔で端末上のデータを消去することもできるとしている。 日本では、昨年 5 月からグーグルのアンドロイド端末でマイナカードの機能が使えるようになっており、アップルの対応が注目されていた。
アップルによると、iPhone のウォレット機能への身分証の導入は米国外では初。 米国では 2022 年からアリゾナやマサチューセッツなど 4 州で導入されていた。 米国では iPhone のカメラ機能で免許証をスキャンすればウォレットに登録できるが、日本のマイナカードの導入方法は未定という。 (サンフランシスコ・五十嵐大介、asahi = 5-30-24)
マイナの国民健康保険関連「情報古く使えない」 220 万人に影響
マイナンバーシステムで、児童手当や介護保険申請などの手続きを簡略化する機能が活用されていない。 15 日に公表された会計検査院の全国調査によると、2022 年度に半数以上の自治体が活用したのは 1,258 機能のうち 33 機能 (3%) だけだった。 住民側には、本来なくなるはずだった負担が生じ続けている。 なかでも、検査院が「非常に大きな影響が出ている」と指摘したのが、会社の退職などに伴い、自治体に届け出る国民健康保険の切り替え手続きだ。
詳細を調べた 451 自治体の大半でマイナシステムの機能が使われず、22 年度は約 220 万人が、証明書などの提出を求められていた。 国はシステムで前職の情報が得られ、証明書はいらなくなるとしてきたが、自治体が活用しようとしたところ、最新の情報に更新されておらず使えなかったという。 背景には、健保の新規加入や資格喪失の情報を会社側でサーバーに登録する作業に時間がかかるという実情がある。 検査院によると、健保のうち 1 - 2 割が、情報登録を終えるまでに 2 週間以上かかっていた。
ほかに、公営住宅の家賃を決める際、システムが使えれば、申請者は有料の課税証明書の取得負担が不要になるのに、113 自治体ではシステムが全く使われていなかった。 年間 31 万件(22 年度)の手続きで課税証明書が必要になっていた。 身体障害者らが使用する車の自動車税が減税される制度では、11 県で約 5 万件(同)の申請があったがシステムの利用は0件だった。自治体には「システムに申請に必要な情報が不足している」との声があり、省略されるはずの身体障害者手帳などの提出が必要になっていた。 (吉備彩日、座小田英史、asahi = 5-15-24)
マイナ保険証 誤った情報登録、新たに 545 件発覚 計 9 千件超に
マイナンバーカードと健康保険証が一体化した「マイナ保険証」をめぐり、情報のひもづけミスが新たに 545 件確認されたことがわかった。 厚生労働省が 26 日までに公表した。 別人の情報が誤登録されるトラブルなどを受けた一連の点検作業で発覚したひもづけミスは計 9 千件を超えた。 昨年からの点検作業では、マイナンバーにひもづけられた健康保険証の情報や、口座情報などに誤りがないかを確認。
健康保険証については追加的内容として、1.6 億件分のデータを住民基本台帳と照合した。 その結果、ひもづけミスが新たに 545 件判明し、重複を除いた総数は 9,223 件となった。 同省はひもづけミスへの対策を実施。 情報の新たな登録や、転居や転職などでの変更の際、ミスがないかを自動的に確認できるシステムを 5 月 7 日から稼働させるという。 同省は、電子カルテや電子処方箋(せん)の整備などの医療 DX (デジタル化)を進めている。
マイナ保険証もその一環で、昨年 4 月に医療機関に対し、対応するシステムの導入を原則義務化。 現行の健康保険証は今年 12 月 2 日から新規の発行を停止する。 ただ、マイナ保険証の3月時点の利用率は 5.47% にとどまっている。 政府はマイナ保険証の利用促進に向け、患者に呼びかけたり、医療機関を財政的に支援したりしている。 (吉備彩日、asahi = 4-26-24)
マイナンバーで証明書、また誤交付 総務省が富士通側に行政指導
昨年相次いだマイナンバーカードを使ったコンビニでの別人の証明書の誤交付問題で、総務省は 16 日、新たに高松市で 1 件の誤交付があったと発表した。 システムを開発した富士通側に、原因究明と再発防止を求める行政指導をした。 総務省によると、今月 4 日、高松市内のコンビニで、別人の証明書が交付されたことに申請者本人が気づいた。 また証明書の交付をつかさどる国全体のシステム上でもエラー表示が出て、トラブルが発覚したという。
システムを開発した富士通の子会社「富士通 Japan」は昨年、別人の証明書を交付するトラブルを 15 件起こした。 このため昨秋までに、同社のシステムを導入している全国 123 自治体に対し、修正プログラムを提供して点検を終えた。 ただ高松市は、同社のシステムを導入したのが今年 1 月からで、修正プログラムの提供から漏れていた。
総務省は、再発防止策を着実に実行すると報告したのに誤交付が再発している現状は、「全社的な監督体制やリスク管理態勢、品質確保に向けた取り組みに著しく問題がある」と指摘。 今後、さらに問題を起こした場合には「追加的な措置を求める可能性がある」と釘を刺した。 これまでは口頭レベルでの指導だったが、今回は一歩踏み込んだ「文書」での指導とし、来月 15 日までの報告を求めている。 富士通側は「深くおわび申し上げるとともに、全力を挙げて再発防止に努める」と謝罪した。 (上地兼太郎、asahi = 4-16-24)
マイナ保険証利用低迷 厚労相、職員に「朝メールで利用呼びかけて」
「日々のメールでも、マイナ保険証の利用を呼びかけて。」 利用が低迷するマイナンバーカードと健康保険証を一体化した「マイナ保険証」について、武見敬三厚生労働相は 29 日、省内放送で職員に積極的に利用するよう求めた。 マイナ保険証の普及を促す立場の同省職員らが入る共済組合の利用率も昨年 11 月時点で 4.88% と低調。 大臣自ら職員をせき立てた形だ。
動画メッセージは 29 日正午ごろに放送された。 武見氏は職員らが入る共済組合の利用率を「低すぎると言わざるを得ない」と指摘。 マイナ保険証を利用することで医療費を 20 円節約できるなどとメリットを強調した上で、管理職に「定例の会議や打ち合わせ、日々送られる朝メールなどで、マイナ保険証の意義・メリットについて案内いただき、積極的に利用を呼びかけていただければ」と強調した。
背景には、マイナ保険証を「医療のデジタル化へのパスポート」と自ら国民に再三訴えながら、普及しないことへの焦りがある。 マイナ保険証への移行は今年 12 月 2 日。 利用率は昨年 4 月に 6.3% だったのが同 12 月は 4.29% まで低迷。 国家公務員の昨年 11 月の利用率も 4.36% と伸び悩んでいる。
都道府県別の利用率も公表 最も高いのは …
利用率を高めようと、厚労省もさまざまな策を講じてきた。 2023 年度補正予算では217億円を使い、昨年10月時点に比べて利用率が向上した医療機関に支援金を出すようにした。6月の診療報酬改定でも、ポスター掲示やウェブサイトで利用を呼びかける医療機関に報酬を上乗せする加算を新設した。 29 日には都道府県別の利用率も公表。 最も高い鹿児島県 (8.44%) と最低の沖縄県 (2.31%) でばらつきがあり、医療機関への調査とあわせて分析したところ、受付での呼びかけを「保険証を見せてください」から「マイナカードはお持ちですか」に変えた施設が多い県で利用率が高い傾向があった、などと明らかにした。
2 月に実施した別のウェブ調査では、マイナカードを保有する 3 千人のうち、マイナ保険証を使ったことがある人が 23.3% いたことから、「受付での呼びかけ次第では、もっと利用が進む余地がある」とみる。 こうした取り組みが功を奏したのか、1 月の利用率は4.6% といったん下げ止まった。 同省は今後も、カードリーダーの画面表示をわかりやすくするといった改修もして、利用の呼びかけを続けるとしている。 (吉備彩日、asahi = 2-29-24)
〈編者注〉 マイナ保険証の利用低迷がニュースになること自体を変に感じます。 あと数カ月すれば今手持ちの保険証は使えなくなるし、マイナ保険証以外の選択肢はありません。 今徹底すべきことは、入力ミスを根絶ささせること、そして、もっと利用価値の高いアプリを増やすことでしょう。 どういうアプリを入れて欲しいのか、聞いてみたらどうでしょうか。
「マイナ保険証」の賛否 若年層と高齢層の結果をそれぞれみると …
マイナンバー制度を巡るトラブルを受け、政府が 6 月から実施した総点検の内容が 12 月 12 日に公表されました。 同日、岸田文雄首相は、現行の健康保険証を来年秋をめどに原則廃止する考えを示しました。 マイナ保険証としてマイナンバーカードと一体化する方針を変更することはありませんでした。 その後の 16、17 日に実施した朝日新聞社の全国世論調査(電話)で、この方針の賛否を尋ねたところ、岸田首相の考えとは異なる結果でした。
政府は 22 日に、現行の健康保険証を来年 12 月で廃止することを決めましたが、調査時点で廃止方針の時期は「来年秋めど」のため、以下、これを前提として聞いた調査の結果を振り返ります。 今回の調査で、健康保険証を来年秋に原則廃止し、マイナ保険証としてマイナンバーカードと一体化する方針を聞いたところ、全体では「反対」 55% が「賛成」 38% を上回りました。
年代別にみると、18 - 29 歳では「賛成」 49%、「反対」 36% とほぼ割れていましたが、70 歳以上では「賛成」が 28% と少なく、「反対」が 66% でした。 若年層ほど賛成が多く、高齢層ほど反対が多いという傾向でした。 若年層ほどマイナ保険証への一体化の不安より利便性を重視しているのかもしれません。 男女別でみると、男性は「賛成」 44%、「反対」 52%。 女性は「賛成」 32%、「反対」 58% でした。 女性の方が抵抗がやや強いようです。
マイナンバー制度を巡るトラブルが相次ぎ、国民の不安や反発が出ていた今年 5 - 8 月に実施した調査で、同じ質問を計 4 回聞いています。 全体の結果はすべて、「反対」が「賛成」を上回っています。 今回の調査に向けて質問を練っていた 12 月上旬時点では、自民党の派閥の政治資金を巡る裏金疑惑が連日ニュースで大きく取り上げられていました。 このため、裏金疑惑に注目が集まり、マイナンバーを巡る出来事への関心がかすみ、賛否を示さない「その他・答えない」という回答が増えるのでないかと、記者は心配していました。
しかし、「その他・答えない」の回答割合は 5 - 8 月調査とほぼ同じ。 さらに賛否の割合もほぼ同じ傾向でした。 マイナ保険証への一体化に、国民の間で根強い不安や反発があることが改めてわかりました。 今回の調査で、マイナンバー制度をどの程度信頼しているかも 4 択で質問しています。 結果は「あまり」 38% と「全く」 18% を合わせた「信頼していない」が計 56% に対し、「大いに」 3% と「ある程度」 39% を合わせた「信頼している」が計 42% でした。
「信頼していない」層で、マイナ保険証に一体化することに「反対」は 81% にも上ります。 マイナンバー制度への不信感から、マイナ保険証への一体化に反対している人が多いことがうかがえます。 政府は 12 月 12 日までに、マイナンバーにひもづける健康保険証や公金受取口座など延べ 8,200 万件のデータの大半の点検を終え、ミスは計 8,351 件見つかったとしています。 誤登録の合計は 1 万 5,907 件となりました。
岸田首相はマイナンバー制度への批判が拡大していた今年夏、来年秋の健康保険証の廃止方針をいったん留保しました。 そして、制度への信頼回復が廃止の前提と繰り返し説明してきました。 今回の調査をみると、岸田首相が言う「信頼回復」とは距離があるように思います。 「聞く力」をアピールする岸田首相は、こんな世論をどう受け止めているのでしょう。 (寺本大蔵、asahi = 12-26-23)
〈編者注〉 もともと、マイナンバーは脱税防止の為に始められたと認識しています。 確定申告書にマイナンバーを書き込むだけですから、カードを持つ必要はありません。 顔写真付きのカードは身元確認に使えるとのことで、カードを持たせることになったのでしょう。 これまで、身元確認の為に一般には保険証が使われていますが、顔写真もない印刷物は、簡単に偽造もされるでしょうし、今後も保険証をめぐるトラブルが益々増えることが明らかです。 即ち、現行の保険証カードは、遅かれ早かれ無くなる運命です。 そこで、マイナカードに肩代わりさせようとするのは、むしろ自然な流れでしょう。 今のところマイナンバーのトラブルは誤入力によるものであり、システムそのものに欠陥があるとは思われません。
紙の保険証、来年 12 月 1 日に原則廃止へ マイナ保険証の移行めぐり
マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」への移行をめぐり、政府は現行の保険証を来年 12 月 1 日で廃止する方針を固めた。 翌 2 日以降、新規発行はできなくなる。 複数の政府関係者が明らかにした。 今年 6 月初旬に成立したマイナンバー法などの改正法で、現行の紙などの保険証は 2024 年 12 月 8 日までに廃止すると定められている。 政府は来年秋をめどに廃止の日を調整してきたが、自治体や医療機関などの準備に余裕を持たせるため、12 月まで割り込ませることにした。 今後、政令で正式に定める。
来年 12 月の廃止後も経過措置として、有効期限が残っている保険証は最長 1 年間使うことができる。 マイナンバーカードを持っていない人や、持っていてもカードを保険証として登録していない人には、保険証の代わりとして「資格確認書」が自治体などから送られる。 マイナ保険証は過去の薬剤情報が一覧できるなどのメリットがあるが、情報が他人に閲覧されるなどのトラブルが相次ぎ、利用率が低迷している。 政府は 23 年度補正予算で、マイナ保険証の利用率が上がった医療機関に配る支援金制度を盛り込むなど、普及に努めている。
政府は当初、今月 12 日の「マイナンバー情報総点検本部」で、岸田文雄首相がトラブルの点検結果の報告と合わせて廃止の日程を示すことを検討していた。 だが、内閣支持率が低迷する中、官邸内では世論の反発が根強い保険証の廃止を明言することに慎重な意見もあり、日程を具体的に言及しなかった。 (吉備彩日、小手川太朗、asahi = 12-21-23)
◇ ◇ ◇
ドタバタで決まった保険証の廃止表明 マイナ信頼回復、どこまで検討
岸田文雄首相は 12 日に開かれたマイナンバー情報総点検本部で、来年秋に紙の健康保険証を廃止する方針を表明した。 岸田文雄首相が紙の健康保険証の廃止を 12 日の総点検本部で明言するのか。 調整は直前まで続いた。 複数の政府関係者は、当初は廃止判断を先送りする方針だったと明かす。
もともとマイナンバー制度への批判が拡大したこの夏、保険証廃止への反発を懸念した官邸幹部らは、廃止時期の大幅な延期を検討していた。 これに、制度をめぐる国会答弁を担ってきた河野太郎デジタル相や、加藤勝信厚生労働相(当時)が周囲に辞任も示唆するなどして抗議。 首相は 8 月上旬、廃止時期の最終判断を秋以降に先送りすると表明することで事態を収めた。
今回も、世論の反発を懸念した官邸側が、先送りの方針をデジタル庁に伝えた。 報告を受けた河野氏は 11 日午前、「総理と直接話して説得する」と反発。 デジタル庁幹部が官邸を訪れて首相周辺と協議し、具体的な日付を示さずに廃止を明言することで決着した。 ドタバタで固まった今回の廃止表明。 首相が廃止の前提としてきた「信頼回復」をめぐり、政府内で十分な検討がされたのかは不透明だ。 (小手川太朗、asahi = 12-12-23)
〈編者注〉 大半の国民にとって、マイナカードは、健康保険証として使うくらいでしょう。 本人確認も出来ない現在の保険証にくらべると、マイナカードが良いに決まっています。 機能性と使いやすさを今後も追及していくことが、政府に課せられます。
マイナ保険証の利用率、10 月時点で 4.49% 6 カ月連続で低下
マイナンバーカードを使った「マイナ保険証」の利用率の低下が止まらない。 厚生労働省は 13 日、10 月時点の利用率が 4.49% だったと明らかにした。ピークだった 4 月の 6.3% から 6 カ月連続で低下した。 医療機関や薬局で、患者の健康保険証の資格をオンラインで確認するシステムは、4 月に原則義務化。 これを受け、医療機関がこのシステムを利用した件数は伸び続け、10 月で 1 億 7,334 万件となった。
一方で、患者のマイナ保険証の利用は低迷。 このシステムでマイナ保険証を読み込んだ件数は、5 月の 853 万件をピークに減少。 8 月以降は再び増加傾向に転じたが、10 月時点で 779 万件、利用率は 5% 弱の低水準にとどまる。 利用が伸び悩む背景には、窓口での負担割合の誤表示をはじめ、相次ぐトラブルなどがあるとみられる。
利用促進関連、補正予算案に 887 億円
こうした状況を踏まえ、政府は「マイナ保険証、1 度つかってみませんか」と題したキャンペーンを展開している。 13 日にはマイナ保険証を積極的に活用する東京慈恵会医科大学付属病院(東京都港区)を武見敬三厚労相と河野太郎デジタル相が視察した。 病院側から「最初の導入の時はなかなか難しくて、覚えていただくのが大変だが、そこを 1 回サポートすると、その後は非常に楽になる」との説明を受けると、武見氏は「一度仕組みを作っていただくと、確実により効果的に使えるようになって、デジタル化の本領が発揮されるという一つの見本」と述べた。
政府は 10 日に閣議決定した今年度補正予算案にマイナ保険証の利用を促進する関連費用として計 887 億円を計上。 利用率が増えた医療機関などに支援金を支払うなどして、来年秋の健康保険証の廃止に向けて、利用率を浮上させたい考え。 だが、野党は「こんな状況ではとても来年の秋の廃止はできない」などと反発している。 (吉備彩日、藤谷和広、asahi = 11-13-23)
マイナ保険証、医療機関向けの補助制度新設へ 河野デジ相が表明
河野太郎デジタル相は 17 日、利用が低迷する「マイナ保険証」を普及させるため、医療機関向けの補助金を新設する考えを明らかにした。 政府が月内にもまとめる経済対策にも盛り込む考えだ。視察先の千葉市で記者団に明かした。
マイナ保険証は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する。 河野氏は、病院や薬局の事務職員がカード読み取り装置の使い方を覚えたり、患者に案内したりする負担がハードルになっているとして、「経済対策の中で、負担を乗り越えられるようなしっかりとした支援を盛り込んでいきたい」と述べた。 補助の対象や内容は今後、厚生労働省とデジタル庁で検討するという。 政府は来秋に現行の健康保険証を原則廃止して、マイナ保険証に統合させる予定だが、相次ぐトラブルなどが原因で利用者が伸びず、8 月時点で 4.7% にとどまっている。 (小手川太朗、asahi = 10-18-23)
「マイナ保険証」の利用率は 5% 弱 4 カ月連続減少 厚労省は危機感
患者の資格情報をオンラインで確認する医療機関での「マイナ保険証」の利用率が 8 月は 4.7% にとどまり、4 カ月連続で下がっていることがわかった。 厚生労働省が 29 日公表した。 健康保険証の廃止が来年秋に迫る中、相次ぐトラブルなどで利用が広がらず、同省は危機感を募らせている。 マイナ保険証の利用率は、医療保険の加入情報などをオンラインで確認する際、従来の保険証ではなくマイナ保険証が使われた割合。 医療機関にオンライン資格確認のシステム導入が原則義務化された今年 4 月には 6.3% まで上昇したが、その後はじわじわ下がり、8 月時点で 4.7% だった。 利用件数も、ピークだった 5 月の 853 万件から 734 万件まで減少した。
交付されたマイナンバーカードのうち、保険証としての利用登録されたのは約 6,900 万枚。 医療機関や薬局では、86% (9 月 24 日時点)の施設でマイナ保険証が扱える状態になっている。 利用の低迷について、武見敬三厚労相は 29 日の閣議後会見で、「極めて重要な課題と受け止めている」と危機感を示した。 利用が進まない理由については、▽ 情報のひもづけの誤りを受けた国民の不安、▽ 医療現場におけるトラブルマイナ保険証を利用するメリットがあまり知られていない、といったことが関係しているとの認識を示し、「課題を一つ一つ解決し、国民が安心してマイナ保険証を利用できる環境を整備することを徹底する」と述べた。 (吉備彩日、asahi = 9-29-23)
マイナ保険証持たない全員に資格確認書交付へ 最長 5 年有効の方針
健康保険証の廃止めぐり政府案
来年秋の健康保険証の廃止をめぐり、政府が新たに打ち出す対策案の内容がわかった。 マイナンバーカードの「マイナ保険証」を持たない人には申請がなくても全員に資格確認書を交付し、その有効期間も最長 5 年に延長するのが軸。 岸田文雄首相が 4 日に記者会見し、こうした措置を講じて国民の不安解消を図り、当面は廃止方針を維持する考えを表明する方向だ。 対策案では、保険証の廃止によって保険診療が受けられなくなる事態を避けるため、資格確認書の運用を大幅に見直す。
資格確認書は原則、本人の申請に基づいて交付され、有効期間も「1 年を限度」にするとされてきた。 ただ、これでは申請漏れなどが生じるとして、マイナ保険証のない人には、健康保険組合などの各保険者が本人の申請がなくても「プッシュ型」で交付するように改める。 有効期間も「5 年以内」とし、この範囲内で各保険者が決める仕組みにする。 現行の保険証と同様の扱いにするのが狙いで、保険証の有効期限が 1、2 年の国民健康保険などでは、今と同期間になる見通し。
このほか、現行ではいったんマイナ保険証の利用登録をした後は解除できないルールも改め、希望者には解除を認めて資格確認書を選べるようにする案も検討している。 岸田首相は 3 日、視察先の群馬県で、翌 4 日に関係閣僚からマイナンバーをめぐる総点検の実施状況や対応方針について報告を受けるとした上、「その内容も踏まえて、デジタル化に向けた決意と、その前提となるマイナンバーカードに対する国民の信頼回復のための対策について、明日の夕刻会見を開き、私から説明をしたい」と述べた。
政府は現在、マイナンバー制度の総点検を実施中で、今年秋までに完了する目標を掲げている。 政府はこの結果も踏まえて、保険証の廃止時期を慎重に判断する考えだ。 来年秋に保険証を廃止し、マイナ保険証に移行する方針に関しては、相次ぐトラブルを受けて与党内からも延期を求める声がある一方、延期には新たな法改正が必要で政府内でも慎重論が根強く、意見が割れている。 (asahi = 8-3-23)
〈編者注〉 「マイナンバー」を必要とする第一の理由が「脱税防止」であり、その次が「健康保険の不正利用防止」であるとすれば、顔写真も無い現在の健康保険証の存続はありえません。 であれば、マイナカードの普及啓発時点で、なぜ政府は最初に「健康保険証がマイナカードに取って代わる」ことを伝えなかったのか? 何とも理解に苦しみます。 実際に医療機関の窓口に置いてある小さな装置の下にカードを置き、(私の場合は)登録した 4 桁数字のパスワードを入力するだけで、保険証確認が済むわけですから、何も難しいわけではありません。
正直、高齢者の大半はこれだけの使用なのです。 その他、いろいろな付加機能、それも「マイナポイントのおまけ」までつけて、更にそれを煽ったばかりに、むしろそれが「難しさ」をイメージさせてしまったのではないかと思われます。 いろいろな付加価値は、それを使いたい人が使えばいいわけです。 繰り返しますが、マイナカードに尻込みする高齢者には「健康保険証の代わりとしてマイナカードを利用して欲しい」と伝えればいいだけだったはずです。
マイナカード、暗証番号なしで交付へ 認知症や高齢者の声受け
マイナンバーカードの申請の際に必要な暗証番号について、松本総務大臣は、高齢者や認知症の患者から「設定が難しい」などという声が出ていることを受けて、ことし 11 月にも暗証番号を設定しなくてもカードの申請や交付ができるようにする方針を明らかにしました。 現在、マイナンバーカードを申請する際には、専用サイト「マイナポータル」にログインするための 4 桁の暗証番号を設定する必要がありますが、認知症の患者や高齢者などから「設定や、その後の管理が難しい」などという声が出ています。
これを受けて松本総務大臣は 4 日の閣議のあとの記者会見で、ことし 11 月にも、暗証番号を設定しなくてもマイナンバーカードの申請や交付ができるようにする方針を明らかにしました。 総務省によりますと、暗証番号を設定せずにカードが交付された場合は、「マイナポータル」などの利用はできなくなるということですが、健康保険証と一体化すれば、顔認証や目視で本人確認を行い、保険証として使うことができるということです。 松本大臣は「できるかぎり多くの方にカードを取得してもらえるようこうした取り組みによって環境整備を着実に進めていきたい」と述べました。 (NHK = 7-5-23)
セルフレジで酒たばこ買えます マイナカードで年齢確認、政府実験へ
コンビニ大手などが加盟する日本フランチャイズチェーン協会は 27 日、マイナンバーカードの情報を読み込んで、スマートフォンで年齢確認ができるアプリを開発すると発表した。 デジタル庁と共同で実証実験を進める協定も締結した。 年齢確認が必要な酒やたばこをセルフレジでも買いやすくすることで、店舗の省人化につなげるねらいだ。 マイナカードの普及を進める河野太郎デジタル相は締結式後、記者団に「日常的にマイナカードを使ってもらえることになり、(カードへの)敷居が低くなる」と話した。
開発するアプリは、あらかじめマイナンバーカードの生年月日や顔写真などの情報を読み込んでおき、アプリ上に表示されたバーコードをレジでスキャンすると年齢認証ができる仕組みを想定している。 20 歳未満への販売が禁じられている酒やたばこを、店員が対面しなくても販売できるようになる。 ローソンなどの一部店舗では、マイナカードを専用の機械で読み取って年齢確認をする実証実験が始まっている。 (小手川太朗、asahi = 6-27-23)