�u�E�B���J�[�̍��}�o���Ȃ��v�A���R���S�����[�X�g
���{�����ԘA�� (JAF) ���s������ʃ}�i�[�Ɋւ��钲���ŁA���R���͉E���܂�Ԑ��ύX�̎��Ɂu�����w����i�E�B���J�[�j�̍��}���o���Ȃ��Ԃ��ł������s���{���v�Ƃ����s���_�Ȍ��ʂ��o���B�@����܂ł����O�h���C�o�[��ό��q����̔ᔻ���A���x�͍��}�̓O����Ăт����Ă������A���P�̕K�v�������t����ꂽ�`�ɂȂ����B
������ 6 ���� JAF �̃z�[���y�[�W�Ŏ��{�B�@�S���� 6 �� 5 ��l���������A�i���R�j�������Z�҂� 970 �l���������B�@�u�E�B���J�[���o�����ɎԐ��ύX��E���܂���Ԃ������v�Ƃ̐ݖ�ɑ��A�u�ƂĂ��v���v�Ɠ����������� 53.2%�A�u���v���v�� 37.8% �ŁA���v���� 91.0% ���S���Ńg�b�v�������B�@���ɁA�u�ƂĂ��v���v�͑S������ (29.4%) ��傫���������B�@���x�̓h���C�o�[�ɍ��}��O�ꂵ�悤�ƁA2005 �N�Ɂu�� ���}�v�̘H�ʕ\�������A���N 2 �����݂Ō��� 28 �J���ɂ܂ő������B�@�t�ƏH�̑S����ʈ��S�^���ł��u���}�̓O��v�����̏d�_�ڕW�̈�ɋ����Ď����܂���������Ă���B�@�����A�����̎��g�݂͎�������ł��Ȃ����B (�g������Aasahi = 8-2-16)
���@���@��
�^�]�}�i�[����� "�ǂ�" �͓̂�����!�@�����Ƃ� "����" �̂� �c
���悢��ċx�݃V�[�Y�������������B�@���i�͉^�]�����Ȃ��Ƃ��������Ƒ��ƈꏏ�Ƀh���C�u�ʼn��o���v�悵�Ă���l�������B�@�����Ō����������̂��^�]�}�i�[���B�@JAF�i��ʎВc�@�l���{�����ԘA���j�� 6 �� 15 �� - 30 ���ɂ����čs������ʃ}�i�[�Ɋւ��钲���i�L���� 6 �� 4,677 ���j�����ƂɁA�^�]�҂��C��t�������_�ɂ��Ă������Ă݂��B
�܂��u���Z����s���{���̌�ʃ}�i�[�v���Ă����˂��Ƃ���A�ł��}�i�[���悢�ƍl���Ă��錧�͓������������B�@�u�����v�A�u�ƂĂ������v�Ɖ����l�ɂ��āA�ł����Ȃ� 16.8%�B�@�����Ŋ�茧 (18.1%)�A���茧 (19.0%)�A�_�ސ쌧 (19.0%)�A�R���� (19.4%) �Ƒ����Ă����B�@�������͑��҂̌�ʃ}�i�[�Ɋւ��āA�قڑS�Ă̐ݖ�ɂ����ă}�i�[���u�����Ǝv��Ȃ��v�Ƃ������������ϒl�������Ă����B�@���Ȃ݂ɁA�����s�� 20.7% �ŁA�R�����Ɏ��� 6 �ʂɂ��Ă���B�@�����s���̉^�]�Ƃ����ƃn�[�h����������ۂ����邪�A�h���C�o�[�̑����̓}�i�[����^�]��S�����Ă���悤���B
���̈���A�u�ƂĂ������v�A�u�����v�̉��ł����������̂́A���쌧�� 80.8%�B�@�����ē����� (73.5%)�A��錧 (67.2%) �������B�@���Ɂu�����Ȋ��荞�݂�����Ԃ������v�Ƃ����ݖ�Ɋւ��āA���� 3 ���́u�ƂĂ��v���v�Ƃ��������ς������Ă����B�@����̃A���P�[�g�Ŗ��炩�ɂȂ����̂́A����炾���ł͂Ȃ��B�@���g�͏\���ɋC��t���Ă������ł��A���҂���݂�Ƃ��̉^�]�}�i�[�͕s�\���ł���Ƃ����P�[�X�������Ă����̂��B
�����ł́A�u�E�B���J�[���o�����ɉE�܍��܂�����Ԃ������v�A�u�M�����ɕς��O�ɔ��M����Ԃ������v�ȂǁA��̓I�ȃV�`���G�[�V��������A�u�ƂĂ��v���v�A�u���v���v�A�u���܂�v��Ȃ��v�A�u�܂������v��Ȃ��v�ʼn��Ă�������B�@���̒��ŁA�����Ƃ������̐l���u�ƂĂ��v���v�Ɖ����̂��A�u�M���@�̂Ȃ����f�����ŁA���s�҂��n�낤�Ƃ��Ă���̂Ɉꎞ��~���Ȃ��Ԃ������v�Ƃ����ݖ�B�@�S�̂� 43.7% ���u�ƂĂ��v���v�ƉB�@�u���v�� (42.5%)�v�ƕ�����ƁA���� 86.2% �̐l���ꎞ��~�ɂ��āu�}�i�[�������v�Ɗ����Ă��邱�Ƃ����������B
���̐ݖ�Ɋւ��Ēn��ʂɂ݂�ƁA������ (52.4%)�A��ʌ� (51.6%)�A���쌧 (51.1%)�A���ꌧ (50.0%) �Ɓu�ƂĂ��v���v���������Ă��錧���������B�@�������A���g�̌�ʃ}�i�[��₤�u�M���@�̂Ȃ������_�ŁA���s�҂����f������n�낤�Ƃ��Ă���ꍇ�ɂ́A�Ԃ͈ꎞ��~���Ȃ���Ȃ�܂���B�@���̂��Ƃ����Ȃ��͒m���Ă��܂����B�v�Ƃ����ݖ�ł́A���[�����u�m���Ă���A�s���Ɉڂ��Ă���v�������l�́A�S�̂� 70.7% �Ƒ��������B�@���g�̔F���ƁA���肩��̂���Ƃł͑傫�Ȋu���肪����悤���B
�܂��A�ߔN�́u�����X�}�z�v�ȂǃX�}�z�̃}�i�[���w�E������ʂ����������A���������X���͂��̒����ɂ��\��Ă���B�@�u�^�]���Ɍg�ѓd�b�i�X�}�z���܂ށj���g�p���Ă���h���C�o�[�������v�Ƃ����ݖ�ł́A�u�ƂĂ��v���v���S�̂� 37.0% �������B�@�ʘb��[���̑��ɁA�X�}�z���i�r�Ƃ��Ďg�p������A�a�؏��⌻�n�̏��ׂ���Ɖ^�]���ł��g�������Ȃ��ʂ͑��X���邪�A�������^�]���̌g�ѓd�b��X�}�z�̎g�p�͓��H��ʖ@�ᔽ���B�@�}�i�[�ȑO�̖��ł��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����̒����ŁA�S�̂ɖ₤�u���Ȃ��͎v�����������A��ʃ}�i�[���ӎ����ĉ^�]���Ă��܂����v�Ƃ����ݖ�ł́A�u�ƂĂ��ӎ����Ă���v�� 45.1%�A�u���ӎ����Ă���v�� 52.3% �������B�@��ʃ}�i�[���ӎ����Ă���h���C�o�[�͑����悤�����A���҂��猩���ꍇ�ɂ͂��̃}�i�[�͌����ď\���Ƃ͂����Ȃ��悤���B�@�v���Ԃ�̃h���C�u�͋C�������g���A��ʃ}�i�[�����낻���ɂȂ邱�Ƃ����邩������Ȃ��B�@�������A���ꂪ����@�ᔽ�⎖�̂ɂ��Ȃ��肩�˂Ȃ��B�@�^�]�O�Ɍ�ʃ��[�����������Ƌ��ɁA���Җڐ��ɗ����Č�ʃ}�i�[���l����K�v�����肻�����B (�����^�[�Adot. = 7-30-16)
�g���^�V�u86�v�͎�҂̃N���}������~�߂��邩

8 �� 1 ���A�g���^������ "�̂���" �̃X�|�[�c�J�[���f�r���[����B�@�u86�i�n�`���N�j�v���}�C�i�[�`�F���W���A����^�Ƃ��Ĕ̔������̂��i�g���^�Г��ł͊������f����O���^�ƌĂԁj�B�@86 �͕x�m�d�H�Ɓi�X�o���j�Ƌ����J���������^�X�|�[�c�J�[�B
2012 �N�ɔ�������Ĉȍ~�A���E�Ŗ� 16 �����̔����Ă���B�@�ߍ��Ȃ��ƂŒm����ƃj�����u���N�����N�̃��[�X�ł̒m�������i�J���ɐ������Ă���A12 �N�ɂ͓� 24 ���ԑϋv���[�X�ŃN���X�D�����ʂ����ȂǁA�����Ƃ��Ƀg���^�̃��[�^�X�|�[�c���ے�����Ԃ��B
����� 86 ���^�[�Q�b�g�Ƃ��Ė��m�ɑł��o���Ă���̂���N�w���B�@���̔w�i�ɂ���̂��A�g���^�̋���Ȋ�@���ł���B�@2000 �N��A�g���^�͎Ԏ�W�J�̊g���̔��䐔�̑�����D�悷�邪�]��A���[�U�[�ɂƂ��Ă� "���͂���ԂÂ���" �������Ȃ�ɂȂ����B�@���̌��ʁA��҂̃N���}����������N�����Ă��܂����A�Ƃ����������B�@�̔��䐔�̐��グ����v���ւ̃C���p�N�g���傫���Ȃ��X�|�[�c�J�[�ɒ��͂���̂͂��̂��߂��B
�u�����Ԃ�D�悵�Ă������Ƃ��A��҂̃N���}����̗v���ɂȂ��Ă���B�@�Ⴂ�l�Ƀ��N���N���Ă��炦��Ԃ���邱�Ƃ��A����������ԎY�Ƃ��ێ����Ă�����ŕK�v���B�i����G�p�ꖱ�j�v�@���ۂɁA�f�[�^�ɂ���N�w����̎x�����@���ɕ\��Ă���B�@���������́A86 �̓o���҂��]��ł����A���Ắu�ԍD���̎�ҁv�ł��� 40 - 50 �オ��ȍw���w�ł��������A���X�ɁA�w���N��������Ă䂫�A�u�ǂ̐�����قڋϓ��B�@���߂ł� 20 �オ�ł��w������悤�ɂȂ��Ă����B�i���c�N��`�[�t�G���W�j�A�j�v�Ƃ����B�@86 �� "�����Ԏ�" �ł���A�}�c�_�E���[�h�\�X�^�[�̍w���w�� 40 - 50 ��ʼnߔ������߂邱�Ƃ��l����ƁA���̎�N�w�̎��v����������Ă���Ƃ����Ă悢�B
CM �d���Ŏ�҂��͂�����
�g���^�́A����̌���^�������_�@�ɁA�X�Ȃ��N�w�̈͂����݂�_���Ă���B�@�܂��A�̑����@�������ƕς����B�@�������f���̑O���^�ł́A�̑��\�Z�̒��S�̓C�x���g�Ɋ����ꂽ���A�u����^�ł́A�t�@���w���L���邱�Ƃ�ړI�ɁA�e���r CM ���X�I�ɓW�J����B�i���c CE�j�v�@�u����A86�B�v���R�s�[�ɁA����Ԃ����̃V���v���ȉf����A�V�t�g�`�F���W���鏗���̎���f�����f���ȂǁA��蕝�L�������ԍD�����ӎ����� CM ���B
�܂��A�ʂ̑_��������B�@����^���s��ɓ��������ƁA���ʂ̑O���^�����ÎԎs��ւƗ����B�@�����ƑO���^�̒��Îԉ��i�͉�����A����N�w�ɂƂ��Ď��L���₷�����i�ɂȂ�̂��B�@���ۂɁA�O�Ⴊ����B�@86 �̖��̂̌����ł�����A1980 �N��Ɉꐢ���r�����g���^�̃J���[�����r���E�X�v�����^�[�g���m���A�u���f���`�F���W�̍ۂɒ��ÎԎs�ꂪ�g�債�����߁A����̍L����ɂȂ������v�ƃg���^�W�҂͌����B�@�����Ƃ��A����^�͕W�����f���̉��i�� 262 ���~�ƁA�O���^�̓����f������ 20 ���~�㏸���Ă���B�@���\���l����Βl�グ�ł͂Ȃ��A�Ƒ��c CE �͂������A�V�Ԕ̔��ł̂���Ȃ��N�w�V�t�g�ւ̃l�b�N�ɂȂ�\���͔ے�ł��Ȃ��B
���C�o�����X�|�[�c�J�[�ɔM����
�������N�A86 ����������Ȃ��āA���Y�X�|�[�c�J�[�s��S�̂�����オ��������Ă���B�@86 �����O�N�� 11 �N�ɂ͎s��S�̂Ŗ� 1 ����ł��������A�� 12 �N�ɂ� 86 ���ʂ� 3.5 ����ɋ}�㏸���A2015 �N�ł��� 2 ����Ɛ��ڂ��Ă���B�i��ʎВc�@�l���{�����Ԕ̔�����A����̃f�[�^�����ƂɕҏW���W�v�j
�n�C�G���h�w��ΏۂƂ��������X�|�[�c�J�[�ł́A���Y�� GT-R 17 �N���f���� 7 ���ɔ������ꂽ�ق��A�z���_�� �m�r�w �̐V���f�����A�N���ɍ����Ŕ̔������B�@����ȊO�ɂ��A���[�h�X�^�[�̐V���f����A�y�����ԃX�|�[�c�J�[�ł̓z���_ S660�A�_�C�n�c�E�R�y���Ȃǂ���������A�e�Ђ̃��C���i�b�v�͒����ɍL�����Ă����B
�X�|�[�c�J�[�����łȂ��A�X�|�[�c�d�l�̎Ԏ���g�債�Ă���B�@�g���^�͕��ʎԂ̊e�Ԏ�ɁAG's �Ƃ������̂ŁA��葖�s���\��Nj������O���[�h��ݒ肵�A�R���o�ϐ��ȊO�̑i���|�C���g��ł��o���B�@�X�|�[�c�J�[��蒅������ɂ�����A���c CE �́u�i�C�ϓ��Ȃǂ������Ă��A��ɊJ����r���ł�߂Ȃ����ƁB�@�����ď����ł��������疈�N�A�b�v�f�[�g���Ă������Ƃ�����v���B�@�͂����āA�X�|�[�c�J�[�͎�҂̃N���}����𑫎~�߂ł��邩�B�@���Ȃ��Ƃ��A���ʂ͎s��̒�グ�����҂ł��������B (�R�{�P�ADiamond online = 8-1-16)
�R����A�ԓ�������g���b�N��?�@�ܗ։����d�l���ڌ���

���I�f�W���l�C���ܗւ̊J�����ԋ߂ɍT���� 1 ���AJR �R����� 1 �Ґ������{��\�I����������鑕���ɗl�ς�肵�A����n�߂��B�@26 �� - 9 �� 15 ���̓p�������s�b�N�d�l�ɂȂ�B�@�ԗ��u�����!�@�j�b�|��! ���v�͗���g���b�N��v�[����͂������ɂȂ�A���Â��ԓ��̕ǂɂ͑I��̎ʐ^������B�@���{�I�����s�b�N�ψ���Ɠ��{�p�������s�b�N�ψ���ɋ��͂����� 15 �Ђ̎��g�݂��B�@���I�ɂ��邩�̂悤�ȕ��͋C���y���݂I����������āA�� JR �����{�̍L��S���ҁB�@�����u�I��̓��[��������Ċ撣��B�@�݂Ȃ�����ԓ��ł͋������đ���Ȃ��ł��������ˁB�v (asahi = 8-1-16)
���s�҂����G�A�o�b�O�@�C���v���b�T�A���Y�Ԃŏ�����
�x�m�d�H�Ƃ́A�S�ʉ��ǂ��č��H����o����͎ԁu�X�o�� �C���v���b�T�v�����\�����B�@���̎��Ƀ{���l�b�g��Ŗc��݁A���s�҂����G�A�o�b�O�����Y�Ԃŏ����ڂ���B�@�����u���[�L�Ȃǂ̉^�]�x���V�X�e���u�A�C�T�C�g�v�Ƃ��킹�A�S�O���[�h�ŕW�������ɂ���B�@�Z�_���ƃn�b�`�o�b�N������A�r�C�ʂ� 1.6 ���b�g���� 2 ���b�g���B�@���i�͖���B (asahi = 7-26-16)
���j�A�A���� 3 ���~�Z���ց@JR ���C�A�J�ƑO�|��������
JR ���C�����݂�i�߂郊�j�A�����V�����̑��܂ł̑S���J�Ƃ�O�|�����邽�߁A���{�� 20 ���A���Ђɑ��Č��ݎ������x�����邵���݂ɂ��āA�����}�̕���ȂǂŐ��������B�@JR ���C�͗Z���̎����O��ɁA�J�ƑO�|���Ɍ����������ɓ���B
�������Z�@�ւȂǂ���W�߂������������Œ����ɑ݂��t����u�������Z���v�̂����݂��g���AJR ���C�� 3 ���~�K�̗͂Z�����s���B�@�����̕��S���y���Ȃ�A�v����H�����͂₭�i�߂邱�Ƃ��ł���Ƃ����B�@JR ���C�́A���É� - ���� 2045 �N�̊J�Ƃ��v�悵�Ă��邪�A�ő��� 37 �N�̊J�Ƃ��߂����B�@���{�����͋߂����\����o�ϑ�ɁA���j�A�����V�����̌��ݑO�|���荞�ށB�@�܂��A��ʃC���t��������Ɨ��s���@�l�u�S�����݁E�^�A�{�ݐ����x���@�\�v��ʂ��č��̂�����݂���悤�A�H�̗Վ�����ɖ@���̉����Ă��o���B (���邢 ��Òq�`�A�S�����K�Aasahi = 7-21-16)
�O�@�� (12-12-14)
�z���_���d��y�ގg��� HV ���[�^�[�@���E���A�����ˑ��Ȃ���
�m�����n �z���_�Ƒ哯����|�� 12 ���A���A�A�[�X�i��y�ށj�̈��ł���W�X�v���V�E���Ȃǂ̏d��y�ނ���؎g��Ȃ��M�ԉ��H�l�I�W�������n�C�u���b�h�� (HV) �p�쓮���[�^�[�ɐ��E�ŏ��߂Ď��p�������Ɣ��\�����B�@�z���_�͓����[�^�[�����H���\�\��̐V�^�~�j�o���u�t���[�h�v�ɍ̗p����B
�d��y�ނ͑啔���𒆍�����̗A���ɗ����Ă���A�ߋ��ɂ͐����I�Ȗ��ʼn��i���㏸�����苟������~����Ȃǂ��A���Y�ɉe�����o�邨���ꂪ�������B�@���̂��߁A�g�p�ʂ̍팸���������߂��Ă����B�@���Ђɂ��ƁA���[�^�[�ɏd��y�ނ��g���Ă��Ȃ��Ă��A�g���N�A�o�́A�ϔM���Ƃ��������\�͏]���i�Ɠ������x����B�����Ă���A�R�X�g���팸�ł���Ƃ����B (Reuters = 7-12-16)
��B��w�A�h�R���ADeNA�A�����s�� 4 �ҁA���L�����p�X���Ŏ����^�]�o�X�T�[�r�X�� 2018 �N�����ɊJ�n
��B��w�� NTT �h�R���A�f�B�[�E�G�k�E�G�[�i�ȉ� DeNA�j�A�����s�� 4 �҂́A��B��w�ɓs�L�����p�X���Ŏ����^�]�o�X�T�[�r�X�����p�����A2018 �N�x�����ɊJ�n����B�@4 �҂� 7 �� 8 ���A���T�[�r�X������ړI�Ƃ����u�X�}�[�g���r���e�B���i�R���\�[�V�A���v�̐ݗ��ɍ��ӂ����Ɣ��\�����B�@���R���\�[�V�A���ł́A�ԗ��̃n���h����A�N�Z���A�u���[�L���^�]�肪���삹���ɑ��鎩���^�]�ɕK�v�ȑ��s�Z�p�A�ʐM�l�b�g���[�N��l�H�m�\�����p�������S�E�֗��ȃT�[�r�X�̋Z�p�J������؎����Ȃǂ�i�߁A�����^�]�o�X�T�[�r�X�̑������p����ڎw���B
��̓I�ȋZ�p�J���́A���ʂ��̈��������_�̓��H�ɐݒu�����Z���T�[�ɂ���Ďԗ��J��������F���ł��Ȃ��Ԃ�l���@�m���Ďԗ��Ɖ��u�Ď��Z���^�[�ɓ`���Ĉ��S���m�ۂ���u�H�Ԋԋ����Z�p�v�A�o�X�ԓ��̃T�C�l�[�W��ʂ��ĉ^����ړI�n�ւ̍s�����Ȃǂ��ē�����u�����G�[�W�F���g�Z�p�v�A��~���\���Ɋ�Â��čœK���[�g�ʼn^�s�����ԒZ�k��}��u�^�s�ǐ��Z�p�v�ȂǁB
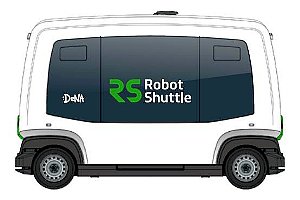
��B��w�ɓs�L�����p�X�́A�ʐ� 275 �w�N�^�[���̎��L�n�B�@�L�����p�X���̓��H�ɂ͍��M��������A�o�X���p�ԁA2 �֎ԁA���]�ԁA���s�҂ȂǑ����̉������������߁A�����ɋ߂����ł̋Z�p�̊m���E�m�E�n�E�̒~�ς��\�Ƃ���B�@�ԗ��͕� EASY MILE �Ђ� EZ10 ���L�͂�������ł͂Ȃ��Ƃ����B�@4 �҂́A���R���\�[�V�A����ʂ��ē����Z�p�E�m�E�n�E�����p���邱�ƂŁA�l�������E����Љ�ɂ�����^�]��s���A�n��ɂ���ʂ̋����s���Ȃǂ̎Љ�I�ۑ�̉����Ɍ����čv���������l���B (�����K�AITpro = 7-11-16)
���@���@��
DeNA�A���l�^�]�o�X���^�s�ց@��t�̌���
�Q�[�����̃f�B�[�E�G�k�E�G�[�� 7 ���A���l�^�]�o�X�� 8 �������t�s���l��̖L�������ő��点��Ɣ��\�����B�@�����̓C�I�����[�����Ǘ����ϑ�����Ă���A�אڂ��铯�Ђ̃V���b�s���O���[���̗��X�q�̗��p�������ށB�@���l�^�]�o�X���g������ʃV�X�e���́A���{���Ƃ����B
��g��̃t�����X�̎����ԃ��[�J�[�A�C�[�W�[�}�C�����J�������d���̎����^�]�ԗ��uEZ10�v���g���B�@�ő� 12 �l����Ԃł��A�J������Z���T�[�AGPS �̈ʒu�����g���āA���炩���ߌ��߂�ꂽ���[�g�𑖂�B�@���͂ɏ�Q��������ƕ��������ꍇ�A�����I�Ɍ���������A��Ԃ����肵�Ď��̂�h���Ƃ����B�@���݁A���{�����ł́A�������������^�]�ԗ��̑��s�́A���L�n�݂̂ŔF�߂��Ă���B�@�f�B�[�E�G�k�E�G�[�͍���A�����{�݂�e�[�}�p�[�N�A�H��ȂǂŎg����ƌ�����ł���B (asahi = 7-7-16)
�؍����ǁA���Y�̃��R�[��������~�ɕs���@�R���̕��j
���Y�����Ԃ̃f�B�[�[���Ԃɂ��āA�؍����Ȃ��r�K�X���u�ɕs��������Ƃ��Ċ؍����ł̃��R�[���i����E�����C���j�Ȃǂ̏����𖽂������ŁA���҂̖@�쓬���������Ă���B�@���Y�̑i�������\�E���s���ٔ����� 4 ���t�ŏ����̈ꎞ��~��F�߁A���Ȃ��s���Ƃ��ă\�E�����قɍR��������j�����߂��B�@�����̂����[�t�ς݂̉ے����������A���R�[���ƑΏێԂ̔̔���~�A�F�؎������̎��s���ꎞ��~���ꂽ�B�@���Y���͔̔��������ɍĊJ����l���͂Ȃ��Ƃ����B
���Y��؍����Ȃɂ��ƁA�����܂ŏ������ꎞ�I�ɗP�\����[�u�ŁA�s���͂Ȃ��Ƃ�����Y�̎咣��F�߂����̂ł͂Ȃ��Ƃ����B�@���Y�͈ꎞ��~�ɂ��āu�W�����Ȃ̂ŃR�����g�͍T����v�Ƃ����B�@���̖��ł́A6 ���Ɋ؍����Ȃ����Y�̃f�B�[�[���ԁu�L���V���J�C�v�̔r�K�X���u�ɕs�����������Ƃ��čs�������\���A�؍����Y�ƎВ����Y�����������B�@���Y�́u�����Ȃ�s�����Ȃ��v�Ǝ咣�B�@�s���̔F���s���Ƃ��A�����̎������Ȃǂ����߂čٔ����ɒ�i���Ă����B (asahi = 7-7-16)
���@���@��
�؍����Y�̏����A�ꎞ��~�F�߂�@�\�E���s���ٔ���
���Y�����Ԃ��؍��Ŕ̔�����f�B�[�[���Ԃɂ��āA�؍����Ȃ��r�K�X���u�ɕs��������Ƃ��ă��R�[���i����E�����C���j�Ȃǂ̏����𖽂������ŁA�\�E���s���ٔ����������̈ꎞ��~��F�߂��B�@���Y�� 6 �����炩�ɂ����B (asahi = 7-7-16)
���@���@��
�u�s���v���f�s���A�؍����Y����i�@�r�K�X���u�߂���
���Y�����Ԃ� 24 ���A�؍��Ŕ̔�����f�B�[�[���Ԃɔr�K�X�̕s�����������ƔF�肵���؍����Ȃ̔��f��s���Ƃ��āA���n�@�l�̊؍����Y���\�E���s���ٔ����ɓ��Ȃ��i�����Ɩ��炩�ɂ����B�@��i�� 23 ���t�B (asahi = 6-25-16)
���@���@��
�؍����ȁA�؍����Y�Ƀ��R�[�����߁@���Y�͕s���ے�
�؍����Ȃ����Y�����Ԃ̃f�B�[�[���ԁu�L���V���J�C�v�̔r�o�K�X�ጸ���u�ɕs�������������Ǝw�E���Ă������ŁA���Ȃ� 7 ���A�A���̔����Ă����u�؍����Y�v�ɑ��A���R�[���i����E�����C���j�𖽂����B�@���Y���͓��Ȃɑ��s����ے肵�����̂́A�ނ���ꂽ�B
���Ȃ� 7 ���t�ŁA�؍����Y����C���ۑS�@�Ɉᔽ�����Ƃ��āA���łɔ̔����ꂽ 824 ��̃��R�[�����߂ɉ����A�V�Ԃ̔̔���~��ے��� 3.4 ���E�H���i�� 3,100 ���~�j���Ȃ����B�@�܂��A�؍����Y�Ɠ��ЎВ��@�ᔽ�̗e�^�Ń\�E�������n���ɌY�����������B�@�u�L���V���J�C�v�͓��Y�����Ԃ��p���Ő������A�؍����Y���A���̔������X�|�[�c�p���ړI�� (SUV) �ŁA�u�f���A���X�v�̊C�O���B�@�L���V���J�C�ɓ��ڂ���Ă������f�_���� (NOx) �̔r�o�ʂ����炷�u�r�o�K�X�ďz���u�v�����ɂ��ꂽ�B (�\�E�� = �����O�Aasahi = 6-7-16)
�㔼���ɍł����ꂽ�Ԃ̓v���E�X�@�O�N�����̂ق� 2 �{��
���N�㔼���i1 - 6 ���j�ɓ��{�ōł����ꂽ�����Ԃ́A�g���^�����Ԃ̃n�C�u���b�h�� (HV) �u�v���E�X�v�������B�@�O�N�����̂ق� 2 �{�� 14 �� 2,562 ������B�@��N���ɐV�^������o����Ă���A�[�Ԃ܂ōő吔�J���҂��Ƃ����l�C�Ԃ�ŁA�u�����h�͂̍��������߂Č��������B�@���{�����Ԕ̔�����A����ƑS���y�����ԋ���A��� 6 ���A���\�����B
2 �ʂ̓z���_�̌y�����ԁuN-BOX �i�O�N������ 10.3% ���� 9 �� 5,991 ��j�v�A3 �ʂ̓g���^�̏��^ HV �u�A�N�A�i�� 26.3% ���� 8 �� 9,409 ��j�v�������B�@��� 10 �Ԏ�̂����A�y�����Ԃ� HV ���f��������Ԏ킪 9 �Ԏ���߂Ă���A��R��E���^�Ԏu���������Ă���B�@�R��s�������������O�H�����Ԃ�X�Y�L�̌y�����Ԃ́A�傫���̔��䐔�����炵���B�@�O�H�����狟�����ē��Y�����Ԃ�����u�f�C�Y�v�� 9 �ʁi�� 41.2% ���� 5 �� 1,370 ��j�B�@�X�Y�L�́u�A���g�v�� 7 �ʁi�� 8.2% ���� 5 �� 5,736 ��j���ō��������B (asahi = 7-6-16)
���ؗ�ԁu�l�G���v�̗\��A�ō����X�C�[�g�� 76 �{

JR �����{�� 5 ���A���ؐQ���ԁu�g�����X�C�[�g�l�G���v�̑� 1 ���i2017 �N 5 - 6 ���o�����j�̗\��\�����B�@�v 187 �����ɑ��� 1,234 ���̉��傪����A�������� 6.6 �{�������B�@���I�҂ɂ� 7 �����{�ɘA��������B�@���Ђɂ��ƁA����҂� 20 - 90 ��ƕ��L���A�֓����ݏZ�҂� 7 �����߁A�؍��⒆������̉�����������B�@�ō��{���́A�^�s������ 5 �� 1 ���ɏ��w���o�����ē����┟�ق���� 3 �� 4 ���̃R�[�X�̂����A�ō����́u�l�G���X�C�[�g�i2 �l���p�� 1 �l 95 ���~�j�v�� 76 �{�������B
�y�c�N�Y�В��́u���O�W���A���[�ȗ����y���݂����l�������Ă���B�@�o�����Ƃ��Ĕ��ɑ����̐l�ɐ\�����ݒ������B�v�Ƙb�����B�@���ؐQ���Ԃ̐�삯�ƂȂ��� JR ��B�́u�ȂȂ��v�͑� 1 ���i13 �N 10 - 12 ���j�̔{���� 7.3 �{���������A�� 9 ���i16 �N 10 �� - 17 �N 2 ���j�� 24.1 �{�ƂȂ�A�D�����ێ����Ă���B (�������Aasahi = 7-5-16)
�O�@�� (6-3-14)
- 5 �� 12 �� - 7 �� 2 ���Ԃ̋L���A����đr�� -
 |
 |
| (5-18-16) | (5-23-16) |
 |
 |
| (6-7-16) | (6-16-16) |
 |
 |
| (6-18-16) | (6-18-16) |
�����̗�ԁu�n�C�p�[���[�v�v�A���̌��J�����@���� 187 �L��
���X�x�K�X : �����̒�������ԁu�n�C�p�[���[�v�v�̊J����i�߂�ĐV����ƃn�C�p�[���[�v�E������ 11 ���A�ă��X�x�K�X�ō������s�Z�p���e�X�g���鏉�̌��J�������s�����B�@�S�|�̍��g�݂łł����ԗ��� 2.5G �̉����x�Ő��H��𑖂�A������ 187 �L���ɓ��B�B�@���̎R�ɓ˂�����Ő���ɓy�ڂ���������グ���B�@�� 1.9 �b�ԂŎ����͏I�������B�@�n�C�p�[���[�v�E�����̋����n�ƎҁA�u���[�K���E�o���u���[�K�����͎����I����A�u���ׂĂ��܂��������v�Ɩ��������ȗl�q�������B
�n�C�p�[���[�v�̍\�z�́A�ăe�X���o�c�҂̃C�[�����E�}�X�N���� 2013 �N�ɑł��o�����B�@�����`���[�u���ŏ�q���悹���J�v�Z���コ���A���� 1,120 �L�������x����������Ƃ����d�g�݁B�@�}�X�N���͂��̃A�C�f�A�����J���A�����̐V����Ƃ��Z�p�J���������Ă���B�@�n�C�p�[���[�v�E�����́A���ԉF����ЃX�y�[�X X �̐��i�H�w�Z�p�҂������o���u���[�K������x���`���[�L���s�^���X�g�̃V���[�r���E�s�V�F�o�[���� 2014 �N�ɑn�݂����B�@����܂ł� 8,000 ���h���i�� 87 ���~�j�̎������W�߁A�]�ƈ��� 150 �l�����B
����̎����Ɏg�������O���H�͔��N�O�Ƀ��X�x�K�X�k���̍����ɕ~�݂����B�@�����͑吨�̕w��]�ƈ��A�W�҂Ȃǂ��l�߂����Ď����̗l�q����������B�@�ԗ��͐��䎺����G���W�j�A������B�@�J�E���g�_�E�����s���đS�]�ƈ�����H���痣�ꂳ���A���H�� 7,000 �{���g�̓d���𗬂��ċN���������B�@����͎����p�̐��H������Ɋg������v��ŁA���a 3.3 ���[�g���̃`���[�u�ň͂S�� 1.5 �L���̕��^�O�������ݗ\��B�@���̒��ɃJ�v�Z���コ���A�𑖍s������B�@�J�v�Z���̒��̏�q�͍q��@�Ɠ����ŁA�ŏ��̉����������d�͂������Ȃ��Ƃ����B�@�N���ɂ̓V�X�e�����t���ғ���������Ԃł̎�����\�肵�Ă���B
�n�C�p�[���[�v�E�����̌v��ł́A2019 �N�܂łɉݕ���Ԃ̉^�s���J�n���A21 �N�܂łɗ��q��Ԃ̉^�s�J�n��ڎw���B (Heather Kelly�ACNN = 5-12-16)
�g���^�A�����Z�A�����͉~���� 5 �N�Ԃ�啝���v��\�z�@�O���͉ߋ��ō����X�V
�g���^�����Ԃ� 11 ���A2016 �N 3 �����A�����Z�\�����B�@�ŏI���v���O���� 6.4% ���� 2 �� 3,126 ���~�ƂȂ�Ȃǔ��㍂�A���v�Ƃ��ߋ��ō����X�V���đ������v�Ƃ����B�@�����������i17 �N 3 �����j�͍ŏI���v�� 35.1% ���� 1 �� 5,000 ���~�������ނȂǁA�������v��\�z�����B�@���v���Z�́A�����{��k�Ђ̉e���Ō��Y���� 12 �N 3 �����ȗ��A5 �N�Ԃ�B�@���㍂�� 6.7% ���� 26 �� 5,000 ���~�A�c�Ɨ��v�� 40.4% ���� 1 �� 7,000 ���~��\�z���Ă���B
�������v�͉~�����i��ŊC�O�ŋ�킷��Ƃ̗\�z���x�[�X�Ɍ��������ς������B�@�Г��̈בփ��[�g�� 1 �h�� = 105 �~�A1 ���[�� = 120 �~�ƌ��݈ȏ�̐����̉~���őz�肵���B�@�������̗\�z�ɂ͌F�{�n�k�̉e���͐D�荞��ł��Ȃ��Ƃ��Ă���A����Ƀ}�C�i�X�v���������\��������B�@16 �N 3 �����͔��㍂�� 4.3% ���� 28 �� 4,031 ���~�A�c�Ɨ��v�� 3.8% ���� 2 �� 8,539 ���~�B�@�c�Ɨ��v�A�ŏI���v�� 3 �N�A���ʼnߋ��ō��ƂȂ����B (sankei = 5-11-16)
��B�̍������A25 ���Ԃ�S�������@�ꕔ�ő��x�K������
��������F�{�̌��
�L���R�s�[ (4-17-16 �` 5-10-16)
GW �� JR ��q�A�k�C���ɐV�������ʁ@��B�͒n�k���e��
�i�q�A�q��A�������H�̊e�Ђ� 9 ���A�S�[���f���E�B�[�N���ԁi4 �� 28 �� - 5 �� 8 ���j�̗��p�\�����B�@JR ���q 6 �Ђɂ��ƁA��v 46 ��Ԃ̐V�����A���}�A�}�s�̏�q�́A�O�N�̓����Ԃ��� 1.2 ���l���� 1,141.6 ���l�B�@�k�C���V�����̊J�ƌ��ʂŁAJR �k�C���͏�q�� 17% ���������AJR ��B�͌F�{�n�k�̉e���őO�N�� 92% �������B�@���� 4 �Ђ͓� 99 - 101% �̕��ɂ����܂����B
�����q��e�Ђ̗��q���́A���������O�N�� 2.1% ���� 310 �� 9,612 �l�A���ې��͓� 14.4% ���� 65 �� 6,944 �l�������B�@�����т̗ǂ����e�������Ƃ����B�@�F�{��`�����ւ̗��q���͑S����őO�N�� 1 �����A���{�q��� 2 �������������A��B���ʑS�̂ł͑O�N���݂������B�@���ې��̓n���C��O�A���Ȃǃ��]�[�g�n���l�C�������B�@�������H 4 �Ђɂ��ƁA10 �L���ȏ�̏a�� 274 �������B�@��N��� 22 ��ߋ� 5 �N�ōŏ��Ƃ����B�@3 ���Ɋ։z���̓����W�����N�V��������t�߂Ŕ������� 70.2 �L�����Œ��������B (asahi = 5-9-16)
�������H�a�� 2 �����Ԃ����_�Ɂ@���[�X�g 3 �͓����Ɛ�
���y��ʏȂ� 28 ���A�S���̍������H�� 2015 �N�ɏa�ɂ���ė��p�҂����ʂɂ������Ԃ͑S��Ԃ� 2 �����Ԃɏ��A�N�� 10 ���l���̘J���͂������Ă���Ƃ��鎎�Z�\�����B�@�ł��������傫��������Ԃ͍�N�ɑ��������������̊C�V���W�����N�V���� (JCT) - ���l���c�������B�@�����Ώۂ͎�s�����ƍ�_�����������A�S���̍������H�̑S 2,632 ��ԁB�@���[�X�g 10 �̂����A6 ��Ԃ𓌖���������߂��B�@�ʍs�䐔��J�[�i�r�Ȃǂ��瓾�����x�Ȃǂ͂����B�@�ł��a���Ђǂ������C�V�� JCT - ���l���c�̏����ł́A�N�� 134 �����Ԃ̑����ƂȂ����B (asahi = 4-29-16)
| �@ ������� | �i�C�V�� JCT - ���l���c�j | 134 |
| �A ������� | �i������� - �����j | 126 |
| �B �������� | �i���l���c - �C�V�� JCT�j | 107 |
| �C ������� | �i���z - ����ˁj | 101 |
| �D ������� | �i���{�R�� JCT - ��ˁj | 100 |
| �E ������� | �i�`�쒆�� - ���j | 90 |
| �F �������� | �i�����r�c - ��ˁj | 85 |
| �G �������� | �i�T�R JCT - �鎭�j | 84 |
| �H �������� | �i�L�� - ���H���S�j | 82 |
| �I ������� | �i�匎 - ��쌴�j | 80 |
�������� GS �A�����ց@16 ��ԁA���N�x�܂łɃ[��
���y��ʏȂ́A�S���̍������H�� 150 �L���ȏ㋋���ł��Ȃ��K�\�����X�^���h (GS) ��Ԃ̉����ɏ��o���B�@�S 9 �H�� 16 ��ԂŁAETC ���ڎԂ���ʓ��ɍ~��Ďw�� GS �ŋ������Ă��lj������������Ȃ��u�H�O�����T�[�r�X�v�Ȃǂ�i�߁A���N�x�܂łɃ[���ɂ���B�@�����Ȃɂ��ƁA�������H�ł̔R����� 1 �����ςŖ� 40 ���A�N�Ԗ� 1 �� 5 �猏�������Ă���B�@���� 16 ���� 150 �L�����̋�Ԃ� 100 �L�������̋�ԂƔ�ׁA�R����̔������� 1.8 �{�ƍ����B (���r�ꕽ�Aasahi = 4-28-16)
�g���^�A�ʎY�^�̔R���d�r�ԁ@19 �N�ɂ������̌v��@�u�~���C�v��菬�^�A500 ���~��
�g���^�����Ԃ��A���f�ő���R���d�r�� (FCV) �̗ʎY�^���A2019 �N�ɂ�����o���v��𗧂ĂĂ��邱�Ƃ����������B�@���s�́u�~���C�v��� 100 ���~�ȏ���� 500 ���~��㔼�Ƃ���������B�@�����ܗւ����� 20 �N���߂ǂɁAFCV �𐢊E�ŔN�� 3 ����ȏ㔄�邱�Ƃ��߂����B (asahi = 4-28-16)
�H�c���č��֘g�A�S���� 4�E���q 2�@�����Ȃ��z����
���y��ʏȂ́A���čq����ŕē��ǂƍ��ӂ����H�c��`����̕č��ւ̔����g�̔z�����A�S���{��A 4 �ցi�����j�A���{�q�� 2 �ւƂ�����j�����߂��B�@�S����̂��� 1 �֕��́A�[��E�����i�ߌ� 10 �����痂�ߑO 7 ���j�̔����g�ƂȂ�B�@26 ���ɔ��\����B�@���ӂł́A���đo���̍q���ЂɁA���ꂼ�ꒋ�� 5 �ցA�[��E���� 1 �ւ�������U�����B�����Ȃ́A���ݐ[��E�����g�ʼn^�q���Ă���S����Ɠ��q�� 2 �ւ����A�܂����ԂɈڂ��B�@�c��� 2 �֕��́A��������S����ɔz������B�@���I�x���ōČ��������q�́A���N 3 �����܂ŐV�����H���̏A�q����������Ă��邽�߂��B (asahi = 4-26-16)
���@���@��
�H�c��`����̕č��ցA���ւœ��č��Ӂ@���Ԃ̔����ւ�
���ė����{�� 18 ���A�H�c��`����̕č��ւ��A���݂� 1 �� 8 �ցi�����j���� 12 �ւɑ��₷���Ƃō��ӂ����B�@���̂��� 10 �ւ́A����܂ŔF�߂��Ă��Ȃ��������ԁi�ߑO 6 �� - �ߌ� 11 ���j�̔����ւƂȂ�B�@���N 10 �����{�ɂ��A�j���[���[�N�ȂǕē��C�݂ւ̘H�����������錩�ʂ����B�@16 �����瓌���ŊJ����Ă����A���{�ƕč��̍q��������������B�@���� 10 �ւƐ[��E�����i�����ߌ� 11 �� - ���ߑO 6 ���j 2 �ւ́A���{�ƕč��̍q���Ђɔ������z�������B�@���Ă̍��ӂ́A�[��̏o���ւ��F�߂�ꂽ 2009 �N�ȗ����B
���Ԃ̔����ւł́A�j���[���[�N��V�J�S�Ȃǂ̘H�����������������B�@�s�S�ɋ߂��H�c�𒋊Ԃɔ�������j���[���[�N�ւȂǂ́A�r�W�l�X�q�̐l�C���W�߂������B�@�������Ə��p���n���̐l�ɂ��A�֗��ɂȂ�B�@���݁A�H�c����̕č��ւ͐[��ɏo������ 8 �ւ����ŁA�A�q��̓��T���[���X�A�T���t�����V�X�R�A�z�m�����̂݁B�@�ē��C�݂ւ̘H���́A�[��ɏo������Ɠ������[��ɂȂ邽�߁A�q���Ђ͗��p�҂����Ȃ��Ƃ݂āA�^�q�����Ђ͌��݂͂Ȃ������B�@���ӂ��A�[��E�����ւ̓z�m���������� 2 �ւƂȂ肻�����B
�H�c�� 14 �N�t�ɒ��Ԃ̔������� 40 �֕������A���ې��ɏ[�Ă��邱�ƂɂȂ����B�@����܂ʼnp���A�h�C�c�A�����A�V���K�|�[���Ȃ� 10 �J���̘H���Ɍv 31 �֕�������U��ꂽ�B�@�����A�č��Ƃ́A���c��`������H���𑽂��^�q���Ă���f���^�q������ȂǁA������q���Ă����B (�啽�v�Aasahi = 2-18-16)
���@���@��
�H�c�� NY �ցA�H�ɂ�����?�@���V�ݏ�����Č���
�H�c��`�𒋊Ԃɏo������č��ւ��A���̏H����V���ɔ�Ԃ悤�ɂȂ�̂��B�@���̂䂭�������܂���{�ƕč��̌����A9 �����瓌���ŊJ�����B�@���ӂł���A�j���[���[�N��V�J�S�H�����V�݂����B
�r�W�l�X�q�͂������A�n����`������p���q�ɂƂ��Ă��֗��ɂȂ肻�����B�@�H�c����̕č��ւ́A���܂͐[��̏o���ւ����Ȃ��A�A�q��̓��T���[���X�A�T���t�����V�X�R�A�z�m�����݂̂��B�@�����g�Ƃ��āA�[��E�����i�����Ƃ��Čߌ� 11 �� - ���ߑO 6 ���j�� 8 �ցi�����j�����蓖�Ă��Ă��邽�߂��B�@���Ă̍q����ł́A���{���͒��� 10 �ցA�[��E���� 2 �ւ��A���ĘH���ɏ[�Ă邱�Ƃ��Ă�����j���B
���ӂ��Ē��Ԃ̕ւ������ł���A����܂łȂ������j���[���[�N�ȂǕē����ւ̕ւ���Ԍ��ʂ����B�@���c���s�S�ɋ߂������ɁA�r�W�l�X�Ŏg���l�͕֗��ɂȂ�B�@�܂��A���Ԃɑ����̒n����`������p���q�ɂƂ��Ă��A���̑I�����͑����������B�@����ŁA�[��̏o���ւ͑啝�Ɍ���B�@���c�̕č��ււ̉e���Ȃǂɂ��z���������߂ŁA�������g�ŁA�A�W�A�̊i���q���Ђ�U�v����˂炢������B
��N 12 ���ɁA6 �N�Ԃ�ɊJ���ꂽ�������ł͍��ӂ������������A�킸�� 2 �J���ōĊJ�ɂ����������B�@������̌��ŁA���ӂł���\�������܂����Ɠ��ē��ǂ����f�������߂ŁA�q��ƊE�ł�����Ō�������Ƃ̌��������܂��Ă���B (�啽�v�Aasahi = 2-8-16)
���@���@��
�H�c�̕Ē��s�ցA�[��E�����͌��֒�Ăց@���čq�����
2 �� 9 ������ĊJ�\��̉H�c��`���߂�����ē��NJԂ̌��ŁA���y��ʏȂ͐[��E�����i�ߌ� 11 �� - ���ߑO 6 ���j�̔����ɂ��āA���ĊԂ̒���ւ����݂� 1 ���ő� 8 �ցi�����j���� 2 �ւɌ��炷��Ă����邱�Ƃ��킩�����B�@���܂͂Ȃ����ԕւ� 10 �ւƂ�����j�ŁA�v 12 �ւƂȂ�B�@�����Ȃ́A���Ăɂ��ꂼ�ꒋ�� 5 �ցA�[��E���� 1 �ւ���z��������j���B�@���ӂł�����H�ɂ��A����܂łȂ������j���[���[�N��V�J�S�ւ̘H�����������錩�ʂ����B
�ăf���^�q��͕č����ŁA�u�i�H�c�̒��ԕւ���������Ɓj���c��`�̎�v�H�����p�~�ɒǂ����܂��v�Ɣ���\���B�@���{�x�Ђ̊������u�i�k�ĂƓ���A�W�A�́j���p���Ȃǂŗ�����������v�Ǝw�E����B�@�����A�ƊE���ɂ́A�f���^���ē��ǂɂł��邾�������̘g�̔z�������߂Ă���Ƃ̌���������B�@���ē��ǂ̌��������ł́A�[��E�����̔����g����ς݂����\�����c��B (�啽�v�Aasahi = 1-24-16)
�g���^�A���E�̔���ʕԂ�炫�@15 �N�x�AVW �͎���
�g���^�����Ԃ� 26 �����\���� 2015 �N�x�̃O���[�v���E�̔��䐔�́A�O�N�x�� 0.7% ���̖� 1,009 ���䂾�����B�@�ƃt�H���N�X���[�Q�� (VW) ������A�N�x�Ƃ��Ă� 2 �N�Ԃ�Ɏ�ʂɕԂ�炢���B�@�g���^�͐L�єY���AVW �̔̔����A��N�ɖ��炩�ɂȂ����r�K�X�s�����̉e���Ŏ����B�@���ʂ��ċt�]�����B�@�g���^�O���[�v�i�_�C�n�c�H�ƁA���쎩���Ԋ܂ށj�̐��E�̔����O�N�x����������̂� 4 �N�Ԃ�B�@�g���^�{�̂́A�k�Ă⒆�����D��������������A�W�A�ȂǂŐU��킸�A�O�N�x���݂������B�@�_�C�n�c�́A�����̌y�����Ԑň����グ�̉e���łP���]�茸�����B
����A14 �N�x�Ɏ�ʂɗ����� VW �O���[�v�́A�r�K�X�s�����̉e���� 15 �N�x�� 2.3% ���̖� 995 ����ɂƂǂ܂����B�@�g���^�́A���ړx��������N�i1 - 12 ���j�̎��т� 15 �N�܂� 4 �N�A���Ő��E��ʂ𑱂���B�@�����A���N�͗\�f�������Ȃ����B�@VW �͍��N�ɓ����Ē����≢�B�Ő���Ԃ��A1 - 3 ���̐��E�̔����g���^��� 5 ����������B�@�g���^�͈��m���|�̔������̂̉e���� 2 ���ɖ� 9 ����̌��Y�ɂȂ����̂ɑ����A4 ���ɂ͌F�{�n�k�̉e���� 8 ���䋭�ɂ̂ڂ錩�ʂ��B�@�g���^�����Y�̒x������܂łɔ҉�ł��邩���A����̎�ʑ��������E����v���ɂȂ肻�����B (�����Ȏq�Aasahi = 4-26-16)
�O�@�� (7-28-15)
�g���^�̐��Y�A25 ������i�K�I�ĊJ�@10 ������ɉe��
�F�{�n�k�̉e���ō������Y�̑唼���Ƃ߂Ă���g���^�����Ԃ� 20 ���A25 ������i�K�I�ɍĊJ����Ɣ��\�����B�@��Ђł���Ȃ��Ȃ������i�̑���Y�ɁA�߂ǂ��������߁B�@28 �����_�ōĊJ�ł��Ȃ��ꕔ�H��ł̐��Y�ĊJ�̎����� 27 ���ɉ��߂Ĕ��f����B�@���Y�ւ̉e���͍��v 10 ������x�Ƃ݂���B
�g���^�͓��k�����B�ɂ����Ă̑S���̎ԗ��g�ݗ��čH��Ő��Y���Ƃ߂���A22 ���� 23 ���ɂ̓O���[�v��Ђ̋��_���܂ލ��� 15 �H��Ńg���^�Ԃ̐��Y���~����B�@�F�{�n�k�ł́A�g���^�n�̕��i���A�C�V�����@�̌F�{�s�ɂ���q��Ђ̍H�ꂪ��Ђ��A�h�A��G���W���̕��i�̋�������~�B�@�A�C�V���́A�ق��̍H��ł̑���Y�Ȃǂ�i�߂Ă���B (asahi = 4-20-16)
���@���@��
�g���^�̍����H��A�唼�x�~�ց@�F�{�n�k�ŕ��i������
�F�{���Ȃǂő����n�k���A�g���^�����Ԃ� 17 ���A�����e�n�ɂ���g���^�Ԃ̑g�ݗ��čH��ŁA���T�̉ғ���i�K�I�ɒ�~����Ɣ��\�����B�@���i�̋��������Ă���̂������B�@22 ���܂łɍ����H��̑唼�Ő��Y���C���������~�܂邱�ƂɂȂ�B�@���T�ȍ~�̉ғ��́A���i�̋������݂� 20 �����߂ǂɔ��f����B
�F�{�n�k�ł́A�g���^�����Ԍn���i���A�C�V�����@�̌F�{�s�̎q��Ђ���ЁB�@14 ���̔������ォ��H��̉ғ����~�߂Ă���A�����̂߂ǂ������Ă��Ȃ��B�@���̉e���ŁA�G���W�����i�Ȃǂ̋������~�܂�A���������ɂ���g���^�����ԋ�B�� 3 �H����A�P�U���܂ő��Ƃ������킹���B�@�g���^�����Ԃ� 19 ���ȍ~�A���C�Ⓦ�k�n���Ȃǂɂ���ق��̍H��ł��A���i�̍ɂ��Ȃ��Ȃ������Y���C���������~�߂Ă����B�@�A�C�V�����@�́A�[����ւ̉e����}���邽�߁A���i���ق��̍H��ő���Y������j���B (asahi = 4-17-16)