エコかるた児童夢中、省エネ学ぶ コウノトリ紙芝居の読み聞かせも
福井市の円山なごみ児童クラブで 28 日、福井新聞社が作製した「みらい・つなぐ・ふくいエコかるた」の大会が開かれた。 児童が札を取り合いながら、環境保全や省エネなどの大切さを学んでいた。 円山地区で読み聞かせを行っているボランティアの北野禎輝さん (75) が企画。 円山小と森田小の児童 21 人が参加した。 「ペットボトル飲んだらかかさずリサイクル」など、エコをテーマにした「あ」から「わ」まで 44 種類の読み札が読まれると、児童らは「はい!」と勢いよく札に手を伸ばしていた。 若松蓮斗君 (7) は「環境に関心を持った。 かるたの絵札も見やすくてよかった。」と意識を高めていた。
北野さんは「エコや自然の大切さを知ってもらいたい。 楽しみながら学ぶのが一番。」と話した。 このほか 1970 年に越前市(旧武生市)に飛来したくちばしの折れたコウノトリ「コウちゃん」を題材にした紙芝居「とんだとんだ! コウノトリ」の読み聞かせもあった。 三木家和珠さん (8) が読み上げる命のリレーの物語に児童は熱心に聞き入っていた。 エコかるたは福井新聞社の「みらい・つなぐ・ふくい」プロジェクトの一環として作製。 読み札と絵札のデータは「みらい・つなぐ・ふくい」のホームページからダウンロードできる。 (福井新聞 = 7-30-15)
地球温暖化防止へ協定 喜多方市と中野区が締結
喜多方市と東京都中野区は 22 日、同市が森林間伐で取得した二酸化炭素 (CO2) の排出権を同区が 5 年にわたり購入する内容を盛り込んだ「地球温暖化防止のための森林整備等に関する協定」を締結した。 同市が管理する公有林間伐で残った森林の育成を促進し CO2 吸収を高め、削減目標を定める企業・団体に排出権を販売する「喜多方市 J-VER 制度」を利用し、売買を行う。
同区は平成 27 年度、CO2 を 50 トン分買い入れ、区内のイベント開催により発生した分と相殺するという。 締結式は市役所で行われた。 山口信也市長と田中大輔区長が契約内容を確認し、握手を交わした。 2 自治体は 21 年の「里・まち連携事業宣言」により、観光、経済、環境交流を推進してきた。 (福島民報 = 7-23-15)
温室ガス、13 年度比 26% の削減目標 政府が正式決定
政府は 17 日、地球温暖化対策推進本部(本部長・安倍晋三首相)を開き、2030 年度の温室効果ガス排出量を「13 年度比 26% 減(05 年度比 25.4% 減)」とする削減目標を正式決定した。 午後にも国連の気候変動枠組み条約事務局に提出する。
削減目標は、6 月 2 日に政府案を了承。 安倍首相がドイツの主要 7 カ国首脳会議(G7 サミット)で各国に説明していた。 その後約 1 カ月間、一般から意見募集を行い、1,982 件が寄せられたが、細かな文言の修正はあったものの政府案通りに決めた。 削減目標は、16 日に経済産業省が正式に決めた 30 年度時点の電源に占める原発や再生エネルギー、火力発電などの割合に加え、省エネ対策や森林による二酸化炭素の吸収分、フロン対策を積み上げた。 日本が支援して途上国で温暖化対策をした分を日本の削減分にする「二国間クレジット制度」は含めなかった。 (asahi = 7-17-15)
ビルのエネルギー、太陽光で完全自給 大成建設が成功
大成建設は、ビルで使うエネルギーを、外壁と屋上の太陽光発電でまかなう実験が成功したと発表した。 人のいる所だけを照らす照明などで、同じ規模のビルと比べエネルギー消費量を 75% 減らした。 建設費を減らし、2020 年までの実用化をめざす。
1 年間の実験に使ったのは、横浜市の技術センターに建てた 3 階建ての研究棟だ。 外壁の半分の面積には太陽光発電をする薄い膜を張り、発電する。 屋上には太陽光パネルを設置した。 循環する冷水を使った冷房や効率的な照明や空調を組み合わせたことで、太陽光発電だけでエネルギーをまかなうことができた。 屋外や広い屋上などに置くような大型設備は不要で、中小型のビルでも実用化できるとみている。 ただ、建設費は通常の 1.5 - 2 倍だ。 電気代などは減らせるため、大成は通常の 1.2 倍ぐらいまで建設費を抑えられれば普及するとみている。 (下山祐治、asahi = 7-9-15)
東芝、再エネから水素を製造し、運搬、利用、北海道で実証実験
東芝は 7 月 3 日、再生可能エネルギー由来の電力で水素を製造し、燃料電池の燃料に活用する実証実験を北海道で開始すると発表した。 北海道の釧路市、白糠町と連携し、5 年間(2015 - 2019 年度)にわたり、水素の製造・貯蔵・運搬・利用までのサプライチェーンを構築する。 同実証実験は、環境省が公募した「平成 27 年度地域連携・低炭素水素技術実証事業」に同社の提案が採択されたもの。 提案内容の名称は、「小水力由来の再エネ水素の導入拡大と北海道の地域特性に適した水素活用モデルの構築実証」。
白糠町にある庶路ダムに小水力発電所を建設し、そこで発電した電気を使い水電解水素製造装置で水素を製造する。 製造した水素をトレーラーで貯蔵・運搬し、酪農家や温水プールなどの多様な施設に設置する燃料電池や燃料電池自動車 (FCV) の燃料として利用する。 寒冷地域である北海道では熱利用が多いため、燃料電池で供給する電気、お湯の両方を最大限に活用する。 同社は、北海道が設置した「北海道水素イノベーション推進協議会」と連携し、北海道内における水素社会の推進に取り組んでいる。 (金子憲治、日経テクノロジー = 7-6-15)
太陽光発電プロペラ機、ハワイ到着 … 5 日間かけ
【ロサンゼルス = 加藤賢治】 太陽電池だけを動力源に初の世界一周を目指している、スイスの太陽光発電プロペラ機「ソーラー・インパルス 2」が 3 日朝(日本時間 4 日未明)、米ハワイ州オアフ島の空港に到着した。
県営名古屋空港からハワイまでの飛行距離は約 7,200 キロ。 飛行時間は約 118 時間とほぼ 5 日間に上り、単独飛行の記録を更新した。 太平洋上を飛行する今回のルートは緊急時の着陸場所がなく、最大の難関とされていた。 同機は今年 3 月にアラブ首長国連邦 (UAE) を出発。 悪天候のため県営名古屋空港に緊急着陸し、その後、日本時間 6 月 29 日未明にハワイに向けて同空港を離陸した。 次のフライトでは、米西部アリゾナ州フェニックスを目指す。 (yomiuri = 7-4-15)
夏の節電、1 日からスタート 家庭での対策は
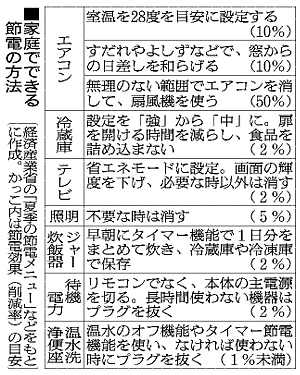
1 日、沖縄を除く全国で夏の節電期間がスタートした。 政府はこの夏、どれだけ節電するかの数値目標を設けず、家庭や企業で無理のない範囲での節電を呼びかけている。 もともと原発に依存する割合が高かった関西電力の管内はこの夏も原発が動いていないため、電力需給が厳しいと見込まれる。 大阪市の地下街では 1 日朝、関電幹部や自治体関係者らが、家庭のエアコンを 28 度を目安に設定するなどの節電を呼びかけた。
節電期間は 9 月 30 日まで。 関電はこの夏のピーク時で、2010 年夏のピーク時の 10% 分(310 万キロワット)の節電を見込んでいる。 他の電力会社から電力を融通してもらうなどして、必要最低限の供給余力を確保できるとしている。 (asahi = 7-1-15)
老朽設備の省エネ対策、エネマネ事業者の活用で補助金を支給
国からエネマネ事業者に採択されたイオンディライトは、補助金を活用したエネルギー管理支援サービスの提供を開始した。 工場・事業場などに対して省エネ設備・システムの導入をサポートし、設備導入費用の一部を補助する。
イオングループの総合ファシリティマネジメント会社であるイオンディライトは、同社を幹事社とするコンソーシアムを構築し、経済産業省と資源エネルギー庁の外郭団体である環境共創イニシアチブ (SII) が 2015 年 4 月に行った「平成 27 年度エネルギー使用合理化等事業者支援補助金に係るエネルギー管理支援サービス事業者(エネマネ事業者)登録のための公募」に応募し、エネマネ事業者に採択された。 これを受け同補助金を活用したエネルギー管理支援サービスの提供を開始した。
同補助金は、事業者が計画した省エネに関する取り組みのうち「技術の先端性」、「省エネ効果」および「費用対効果」を踏まえ政策的意義が高いと認められる設備・システム更新を支援する制度だ。 工場・事業場などにおける省エネ設備の導入や電力需要のピークを抑制する設備の導入について、エネマネ事業者と連携してエネルギーマネジメントシステム (EMS) を導入する事業者に対して費用の一部を補助する。
老朽化した設備などを、省エネ効果の高い設備にリニューアルすることで、ランニングコストの低減と CO2 排出の削減が図れる。 その一方で大きなコストが掛かるため、新設備の導入を決断するには省エネ効果の裏付けが必要となる。 イオンディライトおよびコンソーシアム事業者のエイ・ジー・サービスでは、省エネルギーの効果管理を行うとともに、補助金を活用した設備の改修を提案していく。
イオンディライトは、エネルギーソリューションを重要な事業領域と位置付けている。 これまでも LED や BEMS (ビルディングエナジーマネジメントシステム)の導入に加え、設備管理事業で培ってきた各種設備の管理・運営ノウハウや省エネ対策を生かした独自のエネルギー管理支援サービスを展開してきた。 2012 年 4 月には中小規模ビルの省エネ・電力抑制を担う「BEMS アグリゲータ」として登録されおり、これまでに約 600 件の BEMS の提供をして中小規模ビルの省エネ・電力需要の抑制に貢献している。
今回のエネマネ事業者採択を機に、同社ではさまざまな用途の施設に向けて、照明、熱源、空調、冷凍冷蔵といった主要な設備の高効率化を図り、さらなる省エネ化を推進する。 今後は ICT 技術活用した独自の設備管理プラットフォームを構築し、施設のエリア管理やスマートコミュニティ化を通じて省エネに貢献するとしている。 (長町基、スマートジャパン = 6-25-15)
中部電力、次世代電力計を全域設置へ 880 万台を順次
中部電力は 22 日、通信機能つきの次世代電力計「スマートメーター」を、管内全域で 2022 年度末までに導入すると発表した。 来月以降、今のメーターの交換時期などに合わせて、家庭や事業所などに計約 880 万台を順次設置する。
スマートメーターは、電力会社がインターネットを通じて電気の使用量などを 30 分ごとに把握できる。 発電・送電設備の運用を効率化して省エネにつなげる効果が期待され、電力大手各社が導入を進めている。 中部電は昨年秋から今年春にかけて、愛知県春日井市など 6 市の約 1 万 2,500 世帯で導入。 運用に問題がなかったため、全域に普及させることにした。 すべての交換には 800 億円ほどかかる見通しだ。 16 年度は 63 億円かかる一方で、毎月の検針作業が不要となり、7 億円のコスト削減効果も見込まれるという。 (asahi = 6-23-15)
世界最大級の蓄電設備、福岡の発電所に 日本ガイシ受注
日本ガイシは 22 日、九州電力が豊前火力発電所(福岡県豊前市)の敷地内につくる大規模な蓄電施設用の電池を受注したと発表した。 2015 年度中に運転を始める予定で、「世界最大級の蓄電池設備になる見通し」としている。
設置するのは、新たに開発したコンテナ型の「ナトリウム硫黄 (NaS) 電池」で、出力は 5 万キロワット。 一般家庭約 3 万戸が 1 日に使う電力量に相当する 30 万キロワット時程度をためることができる。 九電は太陽光発電など再生可能エネルギーの受け入れ余地を広げることを狙い、国が公募した実証実験に参加する。 この実験で日本ガイシの NaS 電池を活用する。 (asahi = 6-23-15)
世界の再生エネ 17% 増 新設電源の 6 割占める
2014 年に世界で建設された太陽光や風力など再生可能エネルギーの発電設備容量は 9,700 万キロワットに上り、総容量は 13 年比約 17% 増の 6 億 5,700 万キロワットに達したとの調査結果を、エネルギーの専門家らでつくる「21 世紀の再生可能エネルギーネットワーク(REN21、本部ドイツ)」が 18 日、発表した。 新設された発電設備の約 6 割が再生エネで、成長ぶりは顕著。 REN21 は「昨年、世界の経済成長に伴ってエネルギー消費も増えたが、二酸化炭素排出量は 13 年と変わらなかった。 中国などでの再生可能エネルギーの急拡大がその一因だ。」と分析した。 (kyodo = 6-18-15)
省エネ、サービス業にも目標導入促す 経産省が対策まとめ
経済産業省は 15 日、企業や家庭における省エネ対策をまとめた。 2015 年度にもサービス業に新たな省エネ目標の導入を促すほか、20 年に新設する戸建て住宅の半数でエネルギー消費量をゼロにする計画だ。 政府は 30 年度までに温暖化ガス排出量を 13 年度比で 26% 減らす目標を掲げる。 国際公約の達成に向けて対策の実現に注力する。
同日の総合資源エネルギー調査会(経産相の諮問機関)の専門委員会で報告書の骨子を示し、大筋で了承された。 7 月に開く次回の委員会で報告書を取りまとめる。 柱の一つはエネルギー消費の 6 割を占める企業部門の省エネの徹底だ。 業種ごとに最も省エネが進んだ事業者を基準にした目標を設け、他の事業者に達成を促す制度の拡充を掲げた。
これまで鉄鋼や製紙、石油化学などの重厚長大産業が対象で、現状の産業構造とズレが生じていた。 新たな対象候補と考えるのはエネルギー消費が増えているサービス業だ。 スーパーマーケットや百貨店、コンビニエンスストアなど 6 業種を挙げ、15 年度にも 1 - 2 業種を加える考えだ。 企業の省エネ活動を格付けする仕組みも 16 年度に導入する。 企業を 4 グループに分け、優れた企業を公表し、努力不足の企業に注意文書を配布する。 大企業の大半を含む約 1 万 2,000 社が対象になる方向だ。
家庭部門では「ゼロ・エネルギー・ハウス (ZEH)」の普及を柱に据えた。 ZEH は太陽光発電による売電や蓄電池の利用などを組み合わせ、年間のエネルギー消費量が差し引きでおおむねゼロになる住宅を指す。 骨子には 20 年の新設戸建て住宅の過半を ZEH にすると明記。 オフィスビルや商業施設の新築時に省エネ基準に適合させる義務も盛り込んだ。
日本が掲げた温暖化ガスの削減目標はハードルが高い。 骨子に示した施策は一部で、追加対策が必要。 ただ政府や産業界の一部からは「過度な省エネ対策は企業活動に悪影響を及ぼしかねない」との指摘もあり、一段の省エネ対策には反発も予想される。 (nikkei = 6-15-15)
G7、温室ガス 40 - 70% 減で一致 2050 年目標
ドイツ南部エルマウで開かれた主要 7 カ国首脳会議(G7 サミット)は 8 日、地球温暖化対策で 2050 年までの世界全体の温室効果ガス排出量を 10 年比で「40 - 70% の幅の上方に削減する」という新たな長期目標を盛り込んだ首脳宣言を採択し閉幕した。 ウクライナ危機を巡るロシアの介入や中国の海洋進出を念頭に、力による領土拡大に対処することも確認した。
温暖化対策は、今年末にパリで開かれる国連気候変動枠組み条約締約国会議 (COP21) で、京都議定書に続く新しい枠組みで合意できるかが焦点だ。 首脳宣言は「COP21 で合意を採択する」と強い決意を確認することで、今後の温暖化交渉で途上国側の譲歩を引き出す狙いがある。 また首脳宣言では、「今世紀中に世界経済を「脱炭素化」するため、50 年までの削減目標は「締約国で共有する」とした。 これは、国連の気候変動に関する政府間パネル (IPCC) の最新報告書の内容に沿ったもので、「世界半減、先進国 80% 削減」とした従来の合意から踏み込んだ。
途上国の温暖化対策への資金援助では「20 年までに年間 1 千億ドル」との目標を再確認。 20 年までに温暖化による被害を補償するための保険の仕組みや、アフリカなど途上国での再生可能エネルギーへの支援をうたった。 外交政策では、ロシアと中国に対する G7 としての強いメッセージが盛り込まれた。 ロシアに対しては、昨年 3 月のクリミア半島併合への非難を改めて表明。 対ロシア制裁の期間は「ウクライナ東部の停戦合意の完全履行とウクライナの主権の尊重に明確に関連されるべきだ」とした。
さらに、4 月の G7 外相会合で発した「海洋安全保障の宣言」を支持。 南シナ海での中国による岩礁埋め立てを念頭に「威嚇、強制または武力行使、大規模な埋め立てを含む現状変更を試みるいかなる一方的行動にも強く反対する」と強調した。 この問題に強い関心を寄せる日本や米国の意向が働いたとみられる。
テロ対策では、中東で勢力を増す過激派組織「イスラム国 (IS)」で訓練を受けた外国人戦闘員が母国でテロに走る現状を踏まえ、「国際社会にとって引き続き優先課題」と指摘した。 首脳会議の議論に参加したイラクやアフリカ諸国の首脳と結束してテロに立ち向かう決意を示した。 また、北朝鮮の核開発と拉致問題にも G7 として「強い非難」を表明した。(エルマウ近郊〈ドイツ南部〉=香取啓介、玉川透、asahi = 6-8-15)
再生エネ買い取り、登録制に 経産省が検討
経済産業省は再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)について、電力会社との接続契約を条件とする登録制を導入する方向で検討に入った。 急増する太陽光については抑制策を、普及が遅れる地熱などは事業環境を整備し、再エネ導入の仕組みを抜本的に見直す方針だ。
経産省は月内に開く新エネルギー小委員会で議論を始め、年内にも見直し案をまとめる。 来年の通常国会で「再生可能エネルギー特別措置法」を改正し、早ければ 2017 年の施行を目指す。 再エネはこれまで、政府が認めた設備要件を満たしていれば買い取りを認可してきた。 買い取り価格が高い時期に発電の権利だけを確保し、実際には発電しない「空押さえ」が相次ぎ、計画と実態の隔たりが広がっていた。 (篠健一郎、asahi = 6-8-15)
漂着ペットボトル、大半中韓製 … 日本海側や沖縄
環境省は、漂着ごみの調査・回収事業の一環として、国内7か所の調査地点に流れ着いたペットボトルについて、2010 年度から 5 年にわたってラベルで製造国を区別し集計した。 その結果、日本海側や沖縄では中国や韓国から流れてきたものが大半で、沖縄県石垣市では中国製の割合が 82%、山口県下関市では韓国製の割合が 55% だった。 一方、太平洋側や瀬戸内海に流れ着いたペットボトルは国内製がほとんどで、兵庫県淡路市と茨城県神栖市では、日本のものの割合がそれぞれ 98%、82% だった。
同省海洋環境室は「中国や韓国と連携して漂着ごみを減らすよう努めたい」と話している。 13 年度の漂着ごみの総量は推定 31 万 - 58 万トンで、重量の内訳は、流木など自然のごみが 54%、プラスチック容器や漁網など人工物が 35% だった。 (yomiuri = 6-4-15)
木質バイオマス発電所 : エネ・ビジョンが島根に建設
豊田通商の子会社エネ・ビジョン(名古屋市)が、林業の盛んな島根県江津市で建設していた木質バイオマス発電所が完成し、竣工(しゅんこう)式が 3 日、開かれた。 出力は 1 万 2,700 キロワットで、年間発電量は一般家庭約 2 万 3,000 世帯分に相当。 木質バイオマス発電所としては国内最大級という。 式典には関係者ら約 90 人が出席。 発電所の運営主体でエネ・ビジョンの 100% 出資により設立された「しまね森林発電」の森田孝職務執行者は、「地域に貢献できるよう電力の安定供給に努めたい」とあいさつした。
木質バイオマス発電は、森林に放置された間伐材などをチップ化して燃料に用いる発電。 未利用材を活用でき、環境保全にも有効とされる。 しまね森林発電は、年間約 8 万 3,000 トンの県内産木材チップを燃料として使用し、他に約 3 万 2,000 トンを輸入する。 電力は特定規模電気事業者(新電力)や中国電力などに売る計画で、約 24 億円の収入を見込んでいる。 エネ・ビジョンは松山市でも同規模の木質バイオマス発電所を建設中。 (kyodo = 6-3-15)
前 報 (7-23-14)
前 報 (11-5-13)
温室ガス削減「2030 年に 90 年比 30% 以上を」
低炭素社会を目指す企業のネットワーク「日本気候リーダーズ・パートナーシップ(代表・桜井正光・リコー特別顧問)」は 29 日、2030 年の日本の温室効果ガス削減目標について、1990 年比 30% (05 年比 36%)以上が望ましいとする意見書を公表した。 日本政府の原案では、13 年比 26% (05 年比 25.4%)となっている。
意見書は、理由として「気候変動問題で消極的と見なされると、低炭素技術や人材等の海外展開に悪影響を及ぼす」ことなどを挙げた。 その上で、地方創生にもつながる再生可能エネルギーの潜在力を生かし、家庭や業務部門の省エネ強化などで「より意欲的な削減を目指すことが可能だ」としている。 (石井徹、asahi = 5-31-15)
世界最大水上メガソーラー完成 兵庫の池にパネル 9 千枚
兵庫県加西市の逆池(さかさまいけ)で、世界最大の水上メガソーラーが完成した。 水面に浮かぶ樹脂製の「フロート(浮き)」の上に、縦約 1.7 メートル、横約 1 メートルの太陽光パネルが 9 千枚並ぶ。 発電能力は 2,300 キロワットで、一般家庭 820 世帯分が使う電気を生み出せる。 京セラの関係会社が運営し、電気は関西電力に売る。
各地で大型の太陽光発電所の建設が相次ぎ、陸上は適地が少なくなった。 水上につくると、空間の有効利用に加え、パネルの温度が上がりにくく、発電能力の低下を防ぎやすいという。 京セラは 3 月に同県加東市の 2 カ所でも運転を始めた。 来年 3 月には、千葉県市原市のダム湖でも、発電能力約 1.3 万キロワットの発電所をつくる計画だ。(西村宏治、asahi = 5-26-15)
大成建設、省エネの植物工場用設備を開発
大成建設はスタンレー電気と共同で、発光ダイオード (LED) を使う省エネ型の植物工場用設備を開発した。 スタンレーが培ってきた自動車用ランプのノウハウを生かし、防水性を高めて湿気にも強くした。 耐久性の高さを売りにする。 新開発した製品は、蛍光灯に比べて消費電力を約 6 割減らした。
既に LED を使う植物工場はあるが、2 種類のライトが必要なうえ、ライトが湿気に弱いなどで省エネによるコスト削減効果を思ったほど引き出せないケースがある。 新製品は1種類で済むうえ、耐久性が高い。 両社は 2009 年から植物工場のシステムを共同研究してきた。 工場そのものの建設や栽培方法の指導なども含め、新たに植物工場を立ち上げる企業の需要を取り込む。 (nikkei = 5-22-15)
パナソニック、国内太陽電池工場に約 100 億円を投資
[東京] パナソニック は 18 日、太陽電池の生産能力増強のため、国内工場に約 100 億円の設備投資を実施すると発表した。 太陽電池の生産増強を目的にする設備投資は、2012 年 12 月に稼働を開始したマレーシア工場の建設以来。 これにより、同社の太陽電池の生産能力は現行の年間 900 メガワット (MW) から、2016 年度には 1 ギガワット(ギガは 10 億 = GW)を超える規模になる。
パナソニックの太陽電池の販売量は、2013 年度に 835MW、14 年度に 840MW で、15 年度は 850MW と横ばいの計画だが、このうち、同社の住宅用の太陽電池モジュール製品「HIT」の販売量は、14 年度に 700MW で、15 年度は 800MW と着実に増える見通し。 国内の太陽電池市場は、固定価格買い取り制度の減額で大規模案件(メガソーラー)が縮小傾向だが、パナソニックが注力する住宅用ソーラーは安定。 この中でも、住宅用に特化した HIT は、グループの営業網に乗って堅調に出荷を伸ばしているという。
太陽電池セルは、二色の浜工場(大阪府貝塚市)、島根工場、マレーシア工場の 3 拠点で生産しており、モジュールの組み立ては、二色の浜、滋賀工場(大津市)、マレーシアの 3 カ所で手掛ける。 13 年 9 月に、欧州のモジュール組み立て拠点(ハンガリー工場)を閉鎖して、日本とマレーシアに集約したが、今回、島根と滋賀のライン増強に約 100 億円を充て、年 150MW の能力を追加する。 追加生産は 16 年 3 月から開始し、来期の生産能力は同 1,050MW (1.05GW) に達する見通し。 今後、生産能力のほとんどを HIT の量産に充てる考えという。
パナソニックは 18 年度に住宅関連事業を 2 兆円(14 年度は 1.3 兆円)にする目標で、15 年度の設備投資は 2,800 億円(前年同期は 2,550 億円)に積み増す計画。 今期以降、全社的に投資を拡大しており、東京で記者会見した吉田和弘ソーラービジネスユニット長は「太陽電池事業も投資に転じる」と述べた。 (村井令二、Reuters = 5-18-15)
世界の CO2 排出、初の横ばい 温暖化対策に効果
年々増加する傾向にあった世界全体の二酸化炭素 (CO2) 排出量が、2014 年は 13 年と同じ 323 億トンにとどまったことが国際エネルギー機関 (IEA) のまとめで 16 日、分かった。 世界経済が成長したにもかかわらず、排出量が横ばいで推移したのはデータがある過去 40 年間で初めて。 大気中に蓄積された CO2 濃度は 400ppm を超える危険水準にあり、すぐに地球温暖化が止まるわけではないが、「温暖化対策と経済成長を両立させるのは難しい」とする慎重派の見方を覆し、各国の対策が効果を挙げ始めたことを示す内容だ。 (kyodo = 5-16-15)
代替フロン削減 地球温暖化防止の重要な柱だ
地球温暖化防止には、温室効果の高い代替フロンの排出削減が欠かせない。 実効性ある取り組みを進める必要がある。 代替フロンは、主にエアコンや業務用冷蔵庫の冷媒として使用されている。 オゾン層を破壊する物質として規制された特定フロンに代わり、2000 年代以降、急速に広まった。 代替フロンの温室効果は、二酸化炭素 (CO2) より数千倍も高い。 国内で排出される温室効果ガスのうち、代替フロンの割合は約 2% だが、排出量は増加の一途をたどっている。
政府は、30 年度までに温室効果ガスを 13 年度比で 26% 削減する目標案をまとめた。 原発の活用や省エネに加え、代替フロンの排出削減を柱の一つに据えたのは、当然と言えよう。 重要なのは、CO2 や水など自然冷媒を使った製品の開発と普及を進めることだ。 4 月に施行された「フロン排出抑制法」では、品目ごとに冷媒転換の目標値や時期を設定した。 例えば、食品の冷凍冷蔵用のショーケースについては、25 年度までに 3 割の製品を CO2 冷媒のタイプに転換する。
コンビニエンスストアのローソンは、10 年度から CO2 冷媒のショーケースを導入し、既に約 600 店舗に設置した。 従来のショーケースに比べ、温室効果ガスの排出量が半減したという。 自然冷媒タイプの製品は、フロンを使ったものより割高だ。 環境省は、導入する企業への助成を実施している。昨年度は 55 社に 50 億円を支給した。 需要が増えれば、大量生産により、価格も下がるだろう。
代替フロンの規制強化は、温暖化対策の国際交渉でも重要なテーマとなっている。 日本のメーカーにとって、低価格の自然冷媒製品の開発は、ビジネスチャンスと言える。 環境分野での国際競争力を高めていくことが大切だ。 使用済み製品からの代替フロンの回収も大きな課題である。 廃棄時に全量を回収し、高温で破壊処理すれば、温室効果ガスとして排出されることはない。
現在の回収率は、3 割程度にとどまっている。 多くは製品の使用中に漏洩ろうえいしているとみられる。 フロン排出抑制法は、エアコンや冷蔵機器を保有する企業に定期的な点検を求めている。 漏洩量の多い企業に対しては、政府への報告も義務付けた。 漏洩防止は、重要な温暖化対策である。 着実に進めたい。 (社説、yomiuri = 5-10-15)
暑さに強い農作物開発へ … コメ・野菜で新品種
農林水産省は今年度から、地球温暖化対策として、暑さや水不足に強い農作物を作る研究を強化する。 2019 年度までの 5 年間で、コメや野菜、果物などで 10 種類以上の新品種開発を目指す。 今年度の研究費は 4 億円で、残りの 4 年間も同規模の予算を確保したい考えだ。 研究を委託する研究機関や大学などは、今月中に決定して公表する。
政府は 8 月をめどに温暖化による被害を軽減する国家戦略「適応計画」をまとめる予定で、新品種の開発策もその一部となる見通しだ。 環境省の専門家委員会は、今世紀末には、全国の年平均気温が、20 世紀末より最大 4.4 度上昇するとの予測をまとめている。 今後、国際的に温室効果ガスの削減が進んでも、気温上昇を完全に抑えることは難しいとみられている。 (yomiuri = 5-6-15)
温暖化ガス削減目標、欧米にらみ最後に上積み 政府 26% 目標
政府が 30 日にまとめた 2030 年の温暖化ガス排出削減目標は、政府内の激しい綱引きの末、省エネや森林整備による吸収効果を積み上げ、13 年比で 26% を捻出した。 最優先したのは「欧米に見劣りしない目標」だった。 省エネには巨額の投資が必要となり、実現の可能性は未知数だ。
「05 年に比べて約 3 割削減する環境省サイドの案はどうやっても実現不可能だ。」 水面下の調整が始まった 4 月上旬、経済産業省幹部は政府内の意見の隔たりの大きさを嘆いた。 同時に検討していた 30 年の電源構成案を基にすると、削減目標は「十数 %」というのが経産省の当時の見立てだった。 経産省は環境・外務両省と調整を進め、「13 年比で 20% に乗せる水準」という折衷案が政府内で有力となった。
だが、環境省は巻き返しに動いた。 米国が 05 年比 26 - 28% 削減、欧州連合 (EU) が 1990 年比で少なくとも 40% 削減の目標を既に打ち出した中で、低い目標では国際的に孤立すると恐れたためだ。 環境省は国際エネルギー機関 (IEA) の昨年の試算値をベースに「24% 減」を最低ラインとして論陣を張った。
4 月 18 日東京・新宿の新宿御苑。 安倍晋三首相が主催する「桜を見る会」で首相と同席した望月義夫環境相は「国際的に日本の努力が分かるようにする必要がある」と進言した。 岸田文雄外相が訪独から帰国すると、外務省も大幅削減に傾き、「20% 台半ば」の削減論が政府内で強まった。 国際的に遜色ない水準を望んだのは、6 月に主要 7 カ国 (G7) 首脳会議(サミット)を控えた首相も同じだった。 政府関係者によると、首相は 4 月 20 日、官邸に入った経産省幹部に「諸外国の批判を招かないようにしてくれ」と指示した。
大幅な削減目標を達成するため、経産省はほぼ大枠が固まりつつあった電源構成に手を加えた。 排出量の多い石炭火力の比率を今の 30% から、30 年時点で 26% に減らし、省エネの目標も 2 月時点の試算から 1 割上乗せした。 電源構成の変更と省エネで、21.9% を稼ぎ、将来の森林整備による吸収などの効果と合わせ、26% に乗せた。
見せ方にもこだわった。05 年比では日本は欧米に見劣りするが、13 年比では上回る。 だが、環境省は 05 年比という従来の基準をむやみに変えれば国際的な信用を失うと譲らず、国連に 2 つの削減目標を登録する異例の対応が決まった。 高い削減目標の実現には今後 15 年間で 37 兆円の投資が必要となりハードルは高い。 今回の削減目標を公約すれば結果的に温暖化ガスの排出が少ない原子力発電所の再稼働には追い風との思惑もちらつく。 経産省幹部は「これで 15 年後に原子力が 20% を割ることはなくなった」とつぶやいた。 (nikkei = 5-1-15)
日中韓の環境相会合 共同行動計画を採択へ
中国で開かれている日本と中国、韓国の環境大臣会合は最終日の 30 日、大気汚染対策を中心に今後 5 年間で連携して取り組む共同行動計画を採択することにしていて、新たに技術協力や共同研究の分野で実務者レベルの作業部会を設置することなどが盛り込まれる見通しです。
中国・上海で開かれている日本と中国、韓国の環境大臣会合では、初日の 29 日、望月環境大臣が 2 国間の会談を行い、このうち 3 年ぶりに実現した日中の環境大臣会談では、中国で深刻化し、日本への影響が懸念されている大気汚染物質 PM2.5 などの対策に向けて、都市間連携を強化していくことで一致しました。
そして、最終日の 30 日は 3 か国の大臣の会談が行われ、PM2.5 などの大気汚染対策を中心に今後 5 年間で連携して取り組む共同行動計画を採択することにしています。 共同行動計画には、実効性のある対策を協議するため、大気汚染物質の観測や予測などについての技術協力や、大気汚染物質の排出削減などに向けた共同研究の分野で、新たに 3 か国の実務者レベルの作業部会を設置することなどが盛り込まれる見通しです。 3 か国の環境大臣は日本時間の 30 日午後、会合の成果について記者会見を開くことにしています。 (NHK = 4-30-15)
畜産廃水を資源に 省エネ型の浄化めざす 微生物燃料電池で岐阜大学
岐阜大学流域圏科学研究センターの廣岡佳弥子准教授と市橋修特任助教らの研究グループは、微生物燃料電池という仕組みを使って、豚のふん尿を含む畜産廃水から発電とリンの回収をすることに成功した。 廃水も同時に浄化でき、回収したリンは肥料原料として利用できる。 研究グループによると、微生物燃料電池でリン回収に成功したのは世界初という。 (日本農業新聞 = 4-29-15)
太陽光で発電 → 水素を貯蔵 → 必要な時に発電 東芝が実験
東芝は 20 日、太陽電池で起こした電気で水素を作って貯蔵し、必要なときに再び電気に換える国内初のシステムを川崎市の公共施設で稼働させた。 災害時などは約 300 人分の電気とお湯を約 1 週間供給できる。 充電池などを使う場合に比べ、大量の電気を効率よく保存できるという。 太陽電池が使える日中に水を電気分解し、取り出した水素をタンクにためる。 給水タンクもあるため、水道が止まっても日差しがあれば水素をつくり続けられる。 この水素を使って燃料電池で電気を起こし、発電時に出る熱で、給水タンクの水をお湯にする。
システム一式は長さ 20 フィート(約 6 メートル)のコンテナ三つと、長さ 2 メートルのコンテナ一つに入っており、他の場所で災害が起きたらトラックなどで運ぶこともできる。 川崎の施設は実証実験という位置づけ。 今年 9 月までに自治体や企業向けにシステムの販売を始め、輸出も検討するという。 年 50 台の受注を目指す。(南日慶子、asahi = 4-21-15)
国内最大の太陽光発電所 11万 5千 kw 青森・六ケ所
完成すると国内最大の発電量となる太陽光発電所「ユーラス六ケ所ソーラーパーク」の建設が、青森県六ケ所村で進んでいる。 三菱電機製を中心に 51 万 3,600 枚の太陽電池パネルを使い、発電能力は 11 万 5 千キロワット。 一般家庭約 3 万 8 千世帯が使う電力をまかなえる。 7 月から試運転し、11 月に本格稼働する。 (asahi = 4-17-15)
温室効果ガス : 日本 1.2% 増 13 年度、排出量過去 2 番目 環境省公表
環境省は 14 日、2013 年度の二酸化炭素 (CO2) などの国内の温室効果ガス排出量(確定値)を公表した。 前年度比 1.2% 増の 14 億 800 万トンに上り、1990 年度以降で最多だった 2007 年度(14 億 1,200 万トン)に次ぐ多さだった。 東京電力福島第 1 原発事故後、石炭火力発電の利用が増えたことなどが主な原因という。 (mainichi = 4-14-15)
再生エネ「20% 台前半」 経産省、2030 年電源構成
経済産業省は、2030 年の電源構成(エネルギーミックス)について、太陽光など再生可能エネルギーの割合を 20% 台前半にする方向で検討に入った。 電気料金が上がることの経済的な影響を重く見て、「約 2 割をさらに上回る」としてきた政府の目標をぎりぎり満たす低い水準にとどめる考えだ。
再生エネの比率は、13 年度は水力を中心に 11%。 これを 30 年にはほぼ倍増させる。 太陽光と風力はいまの計約 2% から 10% ほどに伸ばし、大規模ダムが造れない水力や環境影響評価に時間がかかる地熱はほぼ変わらないと見込む。 原発は 20% 前後とし、再生エネ全体を下回る。 建て替えや新増設は想定せず、寿命と定めた運転開始から 40 年を超えて原発を動かす前提にする。
経産省は自民、公明両党や環境省などと調整を進め、4 月末にも電源構成の素案として有識者会議に提示。 5 月中に決定したい考えだ。 安倍晋三首相は 7 日、自民党の調査会から経産省の方針と同様の提言を受け取り、「こうした考え方を基本にしながら進めていきたい」と応じた。 (大津智義、asahi = 4-8-15)
今世紀末の平均気温 4.8 度上昇も 気象庁が報告書
気象庁は、気候変動と見通しをまとめた報告書「異常気象レポート 2014」を公表した。 世界の経済成長に伴って温室効果ガスの排出が増え続けた場合、21 世紀末の世界の年平均気温は 20 世紀末と比べて 2.6 - 4.8 度の範囲で上がると予想した。 気象庁による観測のほか、国内外の研究機関の研究結果をもとにまとめた。 世界の気温は 1891 年以降の統計、日本の気温は 1898 年の統計開始からのデータを分析した。
21 世紀の半ば以降、温室効果ガスの排出量が現在よりも 50% 増える状態が続くと仮定した場合、21 世紀末の日本の年平均気温は 2.5 - 3.5 度上がると予想。 温暖化が進んで空気中の水蒸気の量が増え、年降水量は全国平均で約 100 ミリ増えると見込んでいる。 一方、2013 年までに、世界の年平均気温は 100 年あたり 0.69 度のスピードで上昇。 日本の年平均気温も同様に 1.14 度上昇した。 世界約 1,300 地点、国内 15 地点の年の平均気温と平年値との偏差から長期的な傾向を出した。(土居貴輝、asahi = 4-4-15)
計画中の石炭火力が運転なら、温室ガス排出量 5 - 6% 増
東日本大震災による原発の停止後、各地で建設計画が相次いでいる石炭火力発電所が運転を始めると、二酸化炭素 (CO2) の排出量が 2030 年ごろには少なくとも年間 7,100 万 - 8,900 万トン増加することが朝日新聞の試算で分かった。 日本全体の温室効果ガスの年間排出量を約 5 - 6% 押し上げる量で、地球温暖化防止の努力を帳消しにしかねない。
電力会社の電力供給計画や報道発表、環境省が公開している小規模火力発電所の建設計画などを元に調べたところ、今後 15 年間で新設されたり、置き換わったりする石炭火力は、少なくとも 32 基 1,637 万キロワットに上る。 うち 11 基は 11.25 万キロワット未満の小規模なもので、法律による環境影響評価の対象とならない。 石炭は安くて資源量も豊富だが、発電の際に出る CO2 排出量が、ほかに比べて膨大だ。 1 キロワット時あたり平均 886 グラム、最新鋭の施設でも約 710 グラムと、石油の約 1.3 倍、天然ガスの約 2 倍となっている。
設備利用率を東日本大震災前後の 74 - 76% と仮定し、現状の石炭火力発電所並みの排出量の場合と、実証中の高効率の石炭ガス化複合発電をすべてで導入した場合を試算。 すると、計画通り稼働した場合、CO2 排出量は 15 年後に年間約 7,160 万 - 8,940 万トン増加すると出た。 今後 15 年間で運転開始から 50 年を経過する発電所がすべて廃止されると見込んでも 4,600 万 - 6,400 万トン増加する。
日本が京都議定書の第 1 約束期間(08 - 12 年)の 5 年間で減らした温室効果ガスの量は年平均約 1 億 500 万トンだが、石炭火力で増える見込みの排出量は、その 7 - 9 割にあたる。 (香取啓介、asahi = 3-28-15)