���E���v���X�`�b�N�ʼn������Ă����ƃ����L���O�����J�����
���E�I�ȃv���X�`�b�N���݂̖��Ɏ��g�ފ��c�� Break Free From Plastic ���A�̂� 51 �J���� 7 �� 2,541 �l�̃{�����e�B���Q���������|�����̌��ʔ��������A�v���X�`�b�N���݂̉������ƂȂ郁�[�J�[�̖��O�\���܂����B
�v���X�`�b�N���݉������̉h������g�b�v�̓R�J�E�R�[���ł��B�@�R�J�E�R�[���̃u�����h�}�[�N�����ꂽ�v���X�`�b�N���i�̂��݂́A4 �̑嗤�ɂ܂����� 37 �J���ō��v 1 �� 1,732 �������܂����B�@���̐��́A2 - 4 �ʂ����v�������������������Ƃ̂��ƁB�@�� 2 �ʂ��l�X���ŁA31 �J���ō��v 4,846 �̃v���X�`�b�N���݂��������Ă��܂��B�@�� 3 �ʂ��y�v�V�R�ŁA������ꂽ���݂� 28 �J���ō��v 3,362 �ł��B�@4 �ʈȍ~�ɂ̓����f���[�Y�ƃ��j���[�o�������܂����B�@�g�b�v 5 �̃��[�J�[�͂������������H���̔̔��Ɛ�������͂Ƃ���O���[�o����Ƃł��B
�n�悲�Ƃ̌X��������ƁA�R�J�E�R�[���̓��[���b�p�ƃA�t���J�嗤�� 1 �ʂ��l���B��A�����J�嗤�ƃ��[���V�A�嗤�ł� 2 �ʂƁA���|�I�ȋ������������܂����B�@�܂��A�k�Ăł̓X�^�[�o�b�N�X�� 3 �ʂɂ������ތ����������Ă��܂��B�@�������A��L�̊�Ƃ������ӂ߂���ׂ����Ƃ����킯�ł͂���܂���B�@2019 �N 9 �� 21 ���̃��[���h�N���[���A�b�v�f�[�ɍ��킹�āA���E���ōs��ꂽ���|�����ʼn�����ꂽ�̂� 47 �� 6,423 �̃v���X�`�b�N���݂ɂ́A���� 484 ��ނ��̃u�����h�̃��S���t���Ă��܂����B�@�܂��A�u�����h�������������݂͑S�̂� 43% �ŁA�c��� 57% �͐ӔC�̏��݂����肩�ł͂���܂���B
�������O���[�o����Ƃ������A���̑���u���Ă��Ȃ��킯�ł͂���܂���B�@�v���X�`�b�N���� 1 �ʂ̃R�J�E�R�[���́A2030 �N�܂łɐV�K���Y�����S�Ẵy�b�g�{�g�����A30% �A���R���̌������g�p���ꂽ�uPlantBottle�v�ɒu����������j��ł��o���Ă��܂��B�@�܂��A100% �A���R���̌����łł����uPlantBottle 2.0�v�̐����ɂ�����B�@������͂��ׂẴy�b�g�{�g���������\���̍����f�ނɒu��������l�����Ƃ̂��ƁB�@2 �ʂ̃l�X���� 2025 �N�܂łɂ��ׂẴp�b�P�[�W���ė��p�\�ȑf�ނɂ��邱�Ƃ�ڕW�Ɍf���Ă���A���̍ŏ��̎��g�݂Ƃ��Đ܂�߂ɂ��ł��鎆���p�b�P�[�W�̃L�b�g�J�b�g����{�Ő��Y�J�n���܂����B

�����Ƃ��A�R�J�E�R�[���ƃl�X���̃v���X�`�b�N���݂� 2018 �N�ɔ�ׂđ������Ă���Ƃ������������Ă���A���g�݂̌��ʂ������͓̂��ʐ�ɂȂ肻���ł��B�@Break Free From Plastic �̓��|�[�g�̒��Łu���������Ƃ����́w100% ���T�C�N���\�x������������ɁA���ւ̉e����ጸ���邱�Ƃ��m�܂��B�@�������A���T�C�N�����\�Ȃ��ƂƁA���ۂɃ��T�C�N������邱�Ƃ͕ʂł��B�v�Ǝw�E���A��Ɨ��݂ł͂Ȃ�����҈�l�ЂƂ肪�g���̂ĕ����ƌ��ʂ��邱�Ƃ����߂��Ă��邱�Ƃ��������܂����B (Maria Mendiola�AGigazine = 11-1-19)
�u�E�v���v�ցA�`���b�N�t�����e����J���@����{���
����{������A���x���J���߂��ł���`���b�N�t���̎��e����J�������B�@�H�i����p�i�̗e��́u�E�v���X�`�b�N�v��i�߂������[�J�[�Ȃǂ̎��v����荞�݁A2022 �N�x�� 10 ���~�̔��㍂���߂����B�@���e��̓����ɂ͓Ǝ��̔����t�B������\���Ă��邽�߁A�����C��_�f��ʂ��ɂ����Ƃ����B�@�v�����̓t�B�����ƃ`���b�N�����ŁA�ʏ�̃v���e��Ɣ�ׂĎg�p�ʂ�啝�Ɍ��炵���B�@������Ȃ����ߔp�����₷���A�A���ɂ��֗��Ƃ����B�@���Ђ̒S���҂́u�ۑ����̍����e��Ȃ̂ŁA�����ȗp�r�ŏd�Ă��炦��Ǝv���v�Ƙb���B (asahi = 8-2-19)
�u�E�v���v�A�Ɠd�ł��@�p�i�\�j�b�N����֑f�ނ��J��
�p�i�\�j�b�N�� 8 ���A�①�ɂȂǂ̉Ɠd�Ƀv���X�`�b�N�̑�֕i�ƂȂ�V���������f�ނ��̗p���Ă������j�\�����B�@�V�f�ނ́u�Z�����[�X�t�@�C�o�[�v�ƌĂ��A�����@�ۂ��g�������́B�@�C�m�����̐[�����Ȃǂ����u�E�v���v�̓������Ɠd�ɂ��L�����Ă����B�@�p�i�\�j�b�N�ɂ��ƁA�V�f�ނ̓Z�����[�X�t�@�C�o�[���ƊE�ō������ƂȂ� 55% �ȏ�܂݁A�v���X�`�b�N���鋭�x�����̂������B�@�F�������A���R�ɒ��F�ł���̂����_�ŐF�̂����Ɠd�ɂ��g���₷���ƊE���̑f�ނƂ����B
���Ђ́A���̐V�f�ނ𐔔N���Ƀv���X�`�b�N�̎g�p�ʂ������①�ɂ�|���@�Ȃǂ̉Ɠd�ɍ̗p���邱�Ƃ��߂����B�@�ق��ɂ��A�Z��ނ�ԍڗp�̕��i�ɂ����L���g���A�u�E�v���v���������Ă����l�����B�@�]���̃v���X�`�b�N���R�X�g�������̂��ۑ肾���A���А��i�ɂ��g���Ă��炤���ƂŐ��Y�ʂ��g�債�ăR�X�g�������邱�Ƃ��߂����B�@�v���X�`�b�N���̐H��Ȃǂւ̗̍p�������Ă����Ƃ����B�@�p�v���ɂ��C�m�����Ȃǂ̖�肩��A�Ζ��R���̃v���X�`�b�N�͎g�p�ʂ̍팸�����E�I�ɋ��߂��Ă���B�@�����ł����H�X���v���X�`�b�N���X�g���[��p�~������A�����X���V���b�s���O�o�b�O�����܂ɐ�ւ����肷�铮�����������ł���B (�����Í��Aasahi = 7-9-19)
���W�܁A���N 4 ������L���`�����@��������R���r�j
���k�O���o�ώY�Ƒ��� 15 ���A�X�[�p�[�ȂǂŔz����v���X�`�b�N���̃��W�܂̗L���`�����i�����z�z�̔p�~�j�ɂ��āA���N 4 �� 1 ���̎��{���߂������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�@�ȗ߉�����O���ɊW�Ȓ��ƒ�������ƂƂ��ɁA�`�����̑ΏۂƂȂ郌�W�܂͈̔͂�f�ނȂNj�̓I�Ȍ�����i�߂�B�@���ʋƊE�ł́A���W�܂̗��p�������R���r�j�G���X�X�g�A�Ȃǂ��Ƃ��ɑ��}�ȑ�𔗂�ꂻ�����B
���쌧�y��ł��̓��n�܂�����v 20 �J���E�n�� (G20) �G�l���M�[�E���W�t����B�@�`���̂������Ő��k�o�Y���́u������Η��N 4 �� 1 ���ɊԂɍ����悤���_�����v�ƌ�����B�@�o�Y�Ȃɂ��ƁA�e�����T�C�N���@�̏ȗ߉�����O���ɒu���B�@���@�̏��ǂ͊��A�o�Y�A�����A�����J���A�_�ѐ��Y�� 5 �Ȃɂ܂����邽�߁A������i�߂�B�@�ΏۂƂȂ郌�W�܂̑傫����f�ށA�Ǝ�A������Ƃւ̔z����Ȃǂ��������Ă����B
���W�܂̗L���`�����i�����z�z�̔p�~�j�͓��{���{���挎�܂Ƃ߂��v���̎����z�헪�ɐ��荞�܂ꂽ�B�@���c�`�������͍��� 3 ���A�����ܗցE�p�������s�b�N�O�ɖ@�߂ŋ`��������ӌ���\���B�@�K����@�͍��㌟������Ƃ����B�@�������A15 ���̐��k�o�Y���̕\���ɂ��Ď��O�̒����͂Ȃ������Ƃ����A���ȊW�҂́u���������O�ɒm��Ȃ������͂����B�v�@�����݂͕K������������Ă��Ȃ��B
�����ƊE�͑Ή��𔗂���B�@���X�[�p�[�Ȃǂ͂��łɗL������i�߂Ă��邪�A�R���r�j�ł̓��W�܂���]����q�������A���W�܂̎��ޗ��� 2 - 3 �����x�ƒႢ�B�@���R���r�j�̍L��S���҂́u�X�[�p�[�ƈႢ�A�R���r�j�͂ӂ���Ɨ������ꏊ�B�@�G�R�o�b�O����Ɏ����Ă���q�͏��Ȃ��B�v�Ƙb���B�@�Z�u��-�C���u���� 2030 �N���߂ǂɃ��W�g�p���[���ɂ��A���܂Ȃǂɕς�����j��ł��o���Ă��邪�A�lj��̑Ή��𔗂��邱�ƂɂȂ�B (�K���I�F�A�ɓ��O�B�A�y���V���Aasahi = 6-15-19)
�C�m�v�����ݍ팸�ōs���v��@���{�AG20 �ŕ\��
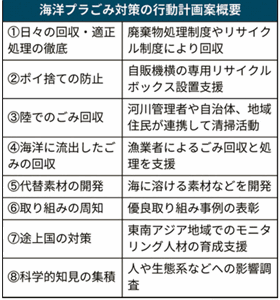
�C�m�v���X�`�b�N���݂̍팸�Ɍ��������{�̍s���v��Ă��킩�����B�@�S�Ẵy�b�g�{�g�����Đ��ȂǗL�����p����悤�x���Ɏ��g�ނق��A�C�ɗ��o���Ă��e���̏��Ȃ��f�ނ̊J���Ȃǂ荞�B�@���{�� 6 ���ɑ��ŊJ�� 20 �J���E�n�� 'G20) ��]��c�ő���c��̒��̈�ɐ�������j�B�@���{����đ����I�Ȏ��g�݂������A�c�_���哱����_��������B
���{���C�m�v���X�`�b�N���݂̍팸�ɍi���ĕ�I�ȑ���܂Ƃ߂�̂͏��߂ĂƂȂ�B�@31 ���Ɏ��@�ŊW�t����c���J���Čv��Ă��m�F����B�@������A�\�Z�[�u�Ȃǂ̌����ɓ���B�@���{�̃y�b�g�{�g���̃��T�C�N�����͉��Ă������Ă���A�����ƊE�̎��g�݂͊������B�@���{�� 100% �̗L�����p�Ɍ����Ēe�݂����邽�߁A�����̔��@�̉��Ƀ��T�C�N���{�b�N�X��ݒu���邱�Ƃ��x������B
�e��̎U����|�C�̂Ă��C�m���݂̖��ɂȂ����Ă���Ƃ̔F������A����ł̉������i�Ɛi�߂�ق��A�{�b�N�X�ɓ������e��̉���p�x���グ��B�@���{�͒n�������̂�W�c�̂ɋ��͂����߂�B�@�����͂͂Ȃ����߁A�⏕���Ȃǂ̗\�Z�[�u�ŗU�����邱�Ƃ��z�肳���B�@�s���v��ɂ͊C�ɗ��o���Ă��e���̏��Ȃ��f�ނ������ŘA�g���ĊJ�����邱�Ƃ����荞�B�@�Ⴆ�A�C���ŕ��������v���X�`�b�N�f�ނ̊J�����z�肳��Ă���B�@�C�m�x�[�V�����ɂ���֑f�ނւ̓]����i�߂�B�@�C�m���݂Ŗ��ɂȂ��Ă��鋙��Ȃǂ��ΏۂɂȂ�B
���̂ق��A�p���������@��C�m�������h�~�@�A���Ɉᔽ���铊���̎����܂��O�ꂷ��B�@���N�u�S�����ݕs�@�����Ď��E�B�[�N�v�𒆐S�Ƃ��č��A�����̂��W���I�ȊĎ��p�g���[�������{���Ă���B�@���������Ď�����������B�@���E�I�Ȏ��g�݂ɍL���邽�ߓr�㍑�ɑ��Ė@�����̎x����A����A�W�A�n��ł̃��j�^�����O�l�ނ̈琬�Ȃǂ��ł��o���B
�C�m�v�����ݖ��͎�v 7 �J�� (G7) �Ȃǐ�i���Ŏ�ɋc�_����Ă����B�@���{�ł̊J�ÂƂȂ� G20 ��]��c��A�t���J�J����c TICAD) �Ŕ��W�r�㍑���������ތ`�ŋ��c���邱�Ƃő�����L����B�@���A�̐��v�ɂ��ƁA�v�����݂͔p���ʂ��N 3 ���g���ɋy�ԁB�@�C�ւ̗��o�͔N 800 �� - 1,200 ���g���Ƃ̎��Z������B (nikkei = 5-30-19)
1 �����[�g�����̐[�C�ɂ��v���X�`�b�N���݁A�L�^�B���̐����Ŕ���
�č��l�̊C��T���ƁA�r�N�^�[�E�x�X�R�{�����j��Ő[���ւ̐����𐬂�������
�Ő[���ł͐V��̉\���̂��鐶���̂ق��A�|���܂�L�����f�B�[�̕�݂����������Ƃ���
������ɂ킽��s���������ł͊C���� 4 ���Ԃ��߂��������������
�����̗l�q�͕ăf�B�X�J�o���[�`�����l���̔ԑg�p�ɎB�e���ꂽ
�����`�[���̓}���A�i�C�a�ɉ����A����܂łɑ吼�m�̃v�G���g���R�C�a��C���h�m�̃W�����C�a�Ȃǂ̒������s����
1960 �N�ɏ��߂ă}���A�i�C�a�̒T�����s�����h���E�E�H���V�������V�L�^�B���̂��j���ɖK�ꂽ
�č��̊C��T���Ƃ� 13 ���A�L�l���������g���đ����m��[�̃}���A�i�C�a�ɂ���`�������W���[�C���i��������j�̐����ɒ��݁A�P�Ɛ����̐V�L�^��B�������Ɣ��\�����B�@�`�������W���[�C���̐[���͐��E�ō��� 1 �� 927 ���[�g���B�@���̊C��ɂ��v���X�`�b�N���݂�����ł����B�@�L�^��B�������͎̂��Y�Ƃ̃r�N�^�[�E�x�X�R�{�� (53)�B�@�������ŕ�����ɂ킽���ă`�������W���[�C���ɐ���A5 �� 1 ���� 1 �� 927 ���[�g���̊C��ɓ��B�����B�@����܂ł̐[�C�����́A�f��ē̃W�F�[���Y�E�L������������ 2012 �N�ɑł����Ă��L�^���ō��������B
�x�X�R�{���͂��̐����ŁA�����̋N����T��肪����ƂȂ蓾��V�� 4 ��������B�@����ɁA�C��Ń|���� 1 ���ƁA�L�����f�B�[�̕�݂����������������Ɠ`���Ă���B�@�}���A�i�C�a�̐[���́A���E�ō���G�x���X�g�̕W��������B�@�`�������W���[�C���ɂ́A�G�r�̂悤�Ȏp����������Ȓ[�r�ނ�A�C��ɂ��ރi�}�R�Ȃǂ��������Ă����B�@�T���`�[���͂������������ɂ��āA�̓��̃v���X�`�b�N�̗ʂׂ錟�����s���ӌ��B
�`�������W���[�C���̐����́A�ăf�B�X�J�o���[�`�����l���̔ԑg�B�e�̈�Ƃ��Ď��{���ꂽ�B�@���ԑg�ł̓}���A�i�C�a�Ȃǐ��E�� 5 ��[�C�̒T�����s���Ă���A����� 8 ���ɁA�܂������̖k�ɊC�̃����C�E�f�B�[�v�ɒ��ށB (CNN = 5-14-19)
�t���[�X���E��̐������ �c�@�����v�������A�g�߂�
�������̐����́A�v���X�`�b�N�Ɏx�����Ă���B�@����ŁA�C�ɗ���o���v���X�`�b�N���݂����O���Ȃǂŗ��čׂ����ӂ������ 5 �~���ȉ��̗��u�}�C�N���v���X�`�b�N�v���A�C�̐��Ԍn�ɉe�����y�ڂ��ƐS�z����Ă���B�@���{�ߊC�̓}�C�N���v���X�`�b�N�́u�z�b�g�X�|�b�g�v�B�@���O���痬�ꒅ���̂ɉ����A���X�̐����̒�������������Ă���B�@���������g����������Ȃ���Ȃ�Ȃ���肾�B
�ăW���[�W�A��́A���{����ő�N 5.7 ���g���̃v���X�`�b�N���݂��C�ɗ��o���Ă���Ɛ��v�B�@���E�� 30 �Ԗڂɑ����Ƃ����B�@��B��̈�ӓĕF�����́u�C�ւ̗��o�����炷���߂ɂ́A�������̐����Ŏg���v���X�`�b�N�̑��ʂ����炷�����Ȃ����낤�v�Ǝw�E����B�@�u�C�ɗ��ꍞ��ł���v���X�`�b�N�́A�X�Ń|�C�̂Ă��ꂽ���̂Ƃ͌���Ȃ��v�Ƙb���̂́A�������Ă��铌�����ȑ�̓�r�חY�������B�@�X���ɂ��邲�ݔ��Ȃǃv���X�`�b�N���i���{���{���ɂȂ��āA�}�C�N���v���X�`�b�N�ݏo�����Ƃ����邩�炾�B
���A���v�� (UNEP) �ɂ��ƁA�����Ԃ̃^�C������ꂽ�Ƃ��ɏo��J�X��A�t���[�X��Z�[�^�[�Ȃǂ̉��w�@�ۂ̕�������Ƃ��ɏo��@�ۂ��݂��}�C�N���v���X�`�b�N�ɂȂ�Ƃ����B�@���X�̐����̂�����Ƃ����H�v�ŁA�X���̃}�C�N���v���X�`�b�N�����炷���Ƃ͂ł���B�@�Ⴆ�v���X�`�b�N���̐�����݁B���x�����_�ȂǂŎ��O���𗁂сA�{���{���ɂȂ肪�����B�@�j�Ђ��r���a�ɗ��ꍞ�݁A���̂܂܉͐삩��C�ւƗ���o�����������B�@�Z��X������A�v���X�`�b�N���̐A�ؔ���A�A�ؔ�����Ɏg���Ă��锭�A�X�`���[�������ă{���{���ɂȂ�A����ɔj�Ђ��U����Ă���P�[�X������ꂽ�B�@���퐻�̐A�ؔ���I������Ƃ����������B
���łɊX���ɏo�Ă��܂��Ă���}�C�N���v���X�`�b�N���C�ɗ����Ȃ����߂ɂł��邱�Ƃ͂Ȃ��̂��B�@�������ȑ�̓�r�����炪�A���|�����̐���ȓ����s���n��̘H��ׂĂ݂�ƁA�ق��̓s�s���v���X�`�b�N���݂����Ȃ��X���ɂ������Ƃ����B�@�u�v���X�`�b�N���݂��ׂ����ӂ���O�ɁA���|�����ʼn�����Ă��܂��̂����ʓI���낤�B�v (���{���Aasahi = 3-24-19)
�����v���A���łɐl�̂Ɂ@�L��������o�@���N�ւ̉e����
�C�ɗ���o���v���X�`�b�N���݂��ӂ��������ȗ��u�}�C�N���v���X�`�b�N�v�B�@�L�Q�ȉ��w�������z�����₷���A���Ԍn�ւ̉e�������O����Ă���B�@�C�̐������̂����łȂ��A���łɐl�Ԃ̕�炵�ɐ[�����荞��ł���B�@�l�Ԃ̌��ɓ�����̂���A�}�C�N���v���X�`�b�N�����o�����Ⴊ�������ł���B
�p�u���l����� 2018 �N�A�p���̃X�[�p�[ 8 �X�Ŕ����Ă���L�ׂ��Ƃ���A���ׂĂ̊L����}�C�N���v���X�`�b�N�����o���ꂽ�Ɣ��\�����B�@���v�Ń��[���L 100 �O���������� 70 ���܂܂�Ă���Ƃ݂���B�@���{�ł������_�H��̍��c�G�d�����炪�A�����p�ŃC���V�⃀�[���L�̈��A�����T�L�C�K�C�Ȃǂ��猟�o���Ă���Ƃ����B
�������������͕̂ă~�l�\�^��̌����`�[���B�@�č���p���A�C�^���A�A�L���[�o�A�C���h�Ȃ� 14 �J�� 159 �J���̐������ׂ��Ƃ���A�C�^���A�ȊO�� 13 �J���̐���������}�C�N���v���X�`�b�N�����o���ꂽ�B�@�����`�[���́u�č��Ȃǐ�i���ł��������o����Ă���A��T�ɏݔ��̖��Ƃ͌����Ȃ��B�@�l�X�ȗv�����W���Ă��������B�v�Ƃ݂Ă���B
�}���[�V�A��t�����X�A�p���Ȃǂ̍��ی����`�[���́A�}���[�V�A�Ŕ̔�����Ă���H���ׂ��B�@���B����{�A�t�����X�Ȃ� 8 �J���Ő������ꂽ���̂���}�C�N���v���X�`�b�N�����o���ꂽ�B�@�����`�[���́u���N�ɉe�����o��ʂł͂Ȃ��������A�̓��ɒ~�ς����̂ň����������ׂĂ����K�v������B�v�Ƙb���Ă���B�@�}�C�N���v���X�`�b�N�͂��łɐl�Ԃ̑̓��Ɏ�荞�܂�Ă���B�@�I�[�X�g���A�̌����`�[�������{�A�p���A�C�^���A�A�I�����_�A�I�[�X�g���A�A�|�[�����h�A�t�B�������h�A���V�A�̌v 8 �l�̑�ւׂ��Ƃ���A���ׂĂ���}�C�N���v���X�`�b�N�����o�����B�@�� 10 �O���������蕽�� 20 �����������B
���������������W���Ă��鉢�B�H�i���S�@�� (EFSA) �́u�}�C�N���v���X�`�b�N�̐l�Ԃ̑̓��ł̋�����Ő��𖾂炩�ɂ���ɂ̓f�[�^���\���łȂ��A�L�Q���ǂ��������y����͎̂����������v�Ƃ̌��������\���Ă���B�@�����A�����_�H��̍��c������̌����ł́A����H�ׂĂ���C���̑̓��Ƀ}�C�N���v���X�`�b�N�������Ƃ݂���L�Q�������~�ς��Ă��邱�Ƃ��������Ă���B (���{���Aasahi = 2-19-19)
�C�m�v�����݂�}���A��������A�W�A�Z�p�x����

�C�m�����ւ̉e�����[��������v���X�`�b�N���݂̔r�o��}�����邽�߁A���Ȃ͗����ȍ~�A��Ȕr�o���ƂȂ��Ă��铌��A�W�A�e���ւ̋Z�p�x���ɏ��o�����Ƃ����߂��B�@�C�ɕY���v�����݂Ȃǂ͂��A���݂̗ʂ̔c����r�o���[�g�̓���ɖ𗧂ĂĂ��炤�B
�x���Ώۂ̓C���h�l�V�A�Ȃ� 2 ���������Ɍ������Ă���B�@���E�̊C�ł͋ߔN�A����E�~�K���A�N�W���Ȃǂ̑̓�����y�b�g�{�g����|���܂����X�ƌ������Ă���B�@�đ�w�����҂�̐��v�i2010 �N�A�ő�l�j�ɂ��ƁA���E�̊C��Y���C�m�v�����݂� 1,275 ���g�����B�@���̓�������ʂɂ݂�ƁA��� 10 �����ɂ̓C���h�l�V�A��x�g�i���ȂǓ���A�W�A 5 ����������A�r�o�ʂ� 3 ���߂����߂�B
���Ȃ͗����ȍ~�A�����C�m����B��ȂǂƘA�g���A�r�o���̓���ɂȂ���Z�p���x���Ώۍ��̐��{�⌤���@�ւȂǂɓ`����B�@��̓I�ɂ́A�v�����݂��̏W���钲���D�⋙�D���g���āA�C��Y�����݂̎�ނ�傫���A�D�ɂ�锭���p�x�Ȃǂ���A���̊C��̃v�����݂̎�ނ�ʂ𐄌v����B�@����A�v�����݂������Ȃǂɂ���ė��A�ו������ꂽ�u�}�C�N���v���X�`�b�N (MP)�v����ʂɌ��o����Ă���B�@�v���X�`�b�N�̔����q���L�⋛�ɋz������A������H�ׂ�Ɛl�̂Ɉ��e�����y�ڂ��\�����w�E����Ă���B
���{�͂���܂ŁA�ŏ� 0.35 �~���E���[�g���܂ł� MP �����ȃl�b�g�ō̏W���A�ގ��╪�z���B�@�C�m�̃v�����݂̗ʂ�r�o���ɂ��āA�����ɔ�ׂĐ��x�̍������ʂ��@���Ă����B�@���ȂȂǂ́A�C��� MP ���̏W�E���͂���Z�p���x���Ώۍ��ɓ`���A���݂̔r�o�ʂ�c�����₷������B
6 ���ɑ��s�ŊJ������v 20 �����E�n�� (G20) ��]��c�ł̓v�����ݑ���e�[�}�ƂȂ�\��ŁA���c������ 1 ���A�u�r�㍑���������������̂�����g�݂�ł��o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƕ\�����Ă����B�@���C���E�����C�m�勳���i�C�m���������w�j�́u�C�m�v�����݂̔�������r�o�ʂ�c�����ė}����ɂȂ��A�e���̊��ւ̈ӎ���ς��邫�������ɂ������v�Ƃ��Ă���B (yomiuri = 3-15-19)
�� �}�C�N���v���X�`�b�N (MP) : 5 �~���E���[�g���ȉ��̔��ׂȃv���X�`�b�N�ŁA�̂Ă�ꂽ���W�܂�y�b�g�{�g���Ȃǂ��C�ɗ��o���A���O����g�Ȃǂōׂ����ӂ��ꂽ���̂Ƃ����B�@�C���̗L�ŕ������z�����鐫�������邱�Ƃ��w�E����Ă���B
���N�W���݂̈����ʃv���X�`�b�N���݁@�[���Ȃ��ݑ�ɃC���h�l�V�A�A�o�X�̃t���[���C�h����
�����E�I�ɖ��ɂȂ��Ă���v���X�`�b�N���݁B�@�����Ɏ����C�m���ݓ������Ƃ�����C���h�l�V�A�ł����̐[������˂����鎖�����N�����B��
�C���h�l�V�A�̃X���E�F�V���i���Z���x�X���j�̓���X���E�F�V�B���J�g�r���ɂ��郏�J�g�r�����������̃J�|�^���̊C�݂� 11 �� 18 ���A1 ���̃N�W���̎��[�����ꒅ�����B�@�n���̋����⍑�������W�҂���Ɋ��ی�c�̃����o�[�Ȃǂ��C�݂Ŏ��[�������Ƃ���A�݂̒������ʂ̃v���X�`�b�N���̂��݂��o�Ă����Ƃ����B
��������邱�ƂȂ��c���ꂽ�݂̒��̃v���X�`�b�N���݂����ڂ��̃N�W���̎����ɊW���Ă��邩�ǂ����́A����̕��s�����������ߓ��肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ������A�Ƃ��Ă���B�@�������C���h�l�V�A�Ȃǂ̓���A�W�A�ł͊C�m�ɓ������ꂽ��ʂ̃v���X�`�b�N�̂��݂��C�m�̊����������łȂ��A�C�m�����̐��Ԍn�ɂ��[���ȉe����^���A�v���X�`�b�N���ݑi�ق̉ۑ�ł��邱�Ƃ��A���̃N�W���̎��[�͕�����Ă���B
���������W�҂Ȃǂɂ��ƃJ�|�^���̊C�݂ɗ��ꒅ�����̂͑̒� 9.5 ���[�g���̃}�b�R�E�N�W���ŁA���݂̈̒����獇�v�Ŗ� 5.9 �L�����̃u���X�`�b�N���݂�������ꂽ�Ƃ����B�@���E���R�ی��� (WWF) �C���h�l�V�A�x���̔��\�ɂ��ƁA���̃}�b�R�E�N�W���݂̈��������ꂽ�̂́A�@ �d���v���X�`�b�N�� 19 �A�A �v���X�`�b�N�J�b�v 115 �A�B �r�j�[���� 25 ���A�C �r�j�[���̃q�� 3.26 �L���O�����A�D �y�b�g�{�g�� 4 �A�E �r�[�`�T���_�� 2 ���̍��v 5.9 �L���Ƃ����B
���E�� 2 �ʂ̊C�m���ݔr�o��
�C���h�l�V�A���{���C�m�̃v���X�`�b�N���݂Ɋւ��Ă͖��̏d�v����F�����đ�ɏ��o���Ă͂���B�@����Ƃ����̂��� NGO �Ȃǂ̒����ŁA���E�̊C�m�ɓ��������v���X�`�b�N���݂͂��̖���������M���ɃC���h�l�V�A�A�t�B���s���A�x�g�i���A�^�C�ƁA�A�W�A�� 5 �J������o���ꂽ���̂ł���Ƃ̒������ʂ�A�C�m������������ 882 ���g���Ɏ����ŃC���h�l�V�A�� 322 ���g���Ƃ����u���E�̃v���X�`�b�N���ݓ����卑�v�ł���Ǝw�E����Ă��邱�Ƃ��w�i�ɂ���B
�����A2018 �N 3 ���ɂ͐��E�I�Ȋό��n�ł���C���h�l�V�A�E�o�����ő�ʂ̃y�b�g�{�g����X�g���[�Ȃǂ̃v���X�`�b�N���݂��Y���C�����_�C�o�[���j���f���� FaceBook �ɃA�b�v����A100 ����ȏ�Đ����ꂽ���̉f���͐��E�̃_�C�o�[�ƂƂ��ɃC���h�l�V�A�l�ɂ��Ռ���^���A���������}���ł���Ƃ̔F�����L�܂����Ƃ���Ă���B�@�� 1 �� 3,500 �̓�����Ȃ�C�m�Q�����ƃC���h�l�V�A�ł͂��݂̉͐�A�C�m����������������O�ɂ���܂ōs���Ă����B�@�������ߔN�̃v���X�`�b�N���݂ɂ�鉘�����̐[��������A���{�� 2025 �N�܂łɊC�m�v���X�`�b�N���݂� 75% �팸���A�ƒ낲�݂� 30% �팸����Ƃ����ڕW���f���ăS�~��ɏ��o�����Ƃ��Ă���B
�C���h�l�V�A�� 2 �̓s�s�W�����������̃X���o���s�� 2018 �N 10 ������A�s���̃o�X�Ƀv���X�`�b�N���݂ŏ�Ԃł������������B�@��q�̓y�b�g�{�g�� 5 ���u���X�`�b�N�J�b�v 10 �����Q���ăo�X�ɏ��� 2 ���ԏ�Ԃł��閳�����ƌ������邱�Ƃ��ł���Ƃ����A�C�f�A���B�@��������v���X�`�b�N���݂͓��s�������ɂ����čĐ��Ǝ҂ɔ���A�������v�̓o�X�^�c�����ɓ��Ă�Ƃ������̂ł���B�@�C���h�l�V�A�S�̂̃v���X�`�b�N���ݑ�݂���������X���o���s�̎��g�݂͂��������ȋK�͂ɉ߂��Ȃ����A�C���h�l�V�A�����^���Ƀv���X�`�b�N���ݑ�ɏ��o�����Ƃ��Ă�����Ƃ��Ă͒��ڂɒl���邾�낤�B (��˒q�F�ANewsWeek = 11-22-18)
�����m�v�����݁@���������u�u�o�q�v�@5 �N�ԂŔ����\�z
�y�u�����b�Z�� ���c�_��z �C�̃v���X�`�b�N���݂�������鋐��ȕ��V���u�� 8 ���A�č��{�y�ƃn���C���̊Ԃ̊C��u�����m���݃x���g�v�Ɍ����A�Đ����T���t�����V�X�R�p���u�o�q�v�����B�@�I�����_�̔�c���g�D (NGO) �u�I�[�V�����E�N���[���A�b�v�v���v��B�@�����m���݃x���g�̃v�����݂� 5 �N�ԂŔ���������\�z���B
���u�͒��� 600 ���[�g���A�[�� 3 ���[�g���� U ���t�F���X�^�B�@���͌��͂Ȃ��A�g�╗�𗘗p���ĊC�ʂV���Ȃ���A���݂𑨂���B�@���݂͐�p�D�ʼn�����A���T�C�N������v�悾�B�@���u�� 10 �����ɕĐ��C�݂��� 2,000 �L�����ꂽ�����m���݃x���g�ɓ������錩�ʂ��Ƃ����B�@�C�m�����͑��u�̉��������邱�Ƃ��ł���ƁA�� NGO �͐������Ă��邪�A������������Ԍn�Ɉ��e����^����Ƃ̌��O������ق��A�v��̎������ɉ��^�I�Ȍ������������B�@�� 2,000 �����[���i25 �� 6,000 ���~�j�̔�p�͊�t���Ƃ̋��^���ł܂��Ȃ����B
�� NGO �Ɖ��Ă̌����@�ւ̋��������ɂ��ƁA�����m���݃x���g�ɂ͐��E�ōł������̃v�����݂��W�ς���B�@���d�� 7 �� 9,000 �g���ŁA���{�̖ʐς� 4 �{�ȏ�� 160 �������L���ɍL�����Ă���B�@�u�C�̐��|�v���Ӗ����邱�� NGO �́A�C�̃v�����ݍ팸��ړI�ɃI�����_�l�̔����ƃ{�C�����E�X���b�g���� 2013 �N�� 18 �Őݗ������B �@�v�����݂ɂ��[���ȊC�m�����ɂ͍��ۓI�ȊS�����܂��Ă���A�팸�Ɍ������e���œ������������Ă���B (mainichi = 9-10-18)
30 ���ŏ_�炩���A�z���Ȃ��Ȃ鎆���X�g���[�@�����Ă݂�
�X�g�����O�X�z�e�������C���^�[�R���`�l���^���i�����s�`��j�� 9 �����猴���A�z�e�����̃��X�g�����ȂǂŎ����̃X�g���[������B�@�J�t�F���E���W�Ŏ����������Ă݂��B�@�ڂ̑O�Ɍ��ꂽ�̂́A���������č��ꂽ�܂������ȃX�g���[�B�@��������Ƃ����d��������A�A�C�X�R�[�q�[�����Ƃ���S�����Ȃ��g�����B�@���� 30 ���قǂ���ƁA�X�g���[�������ď_�炩���Ȃ�A���܂��z���Ȃ��Ȃ����B
���z�e���̃l�C�U���E�N�b�N���x�z�l�́u���{�̃z�e���ł́A���ĂƈقȂ�A�v���X�`�b�N�����u���V�Ȃǂ̏�������߂���B�@�v���X�`�b�N���S�̂��l���Ȃ���x�X�g�ȑI�������Ă��������B�v�Ƙb���B�@�����X�g���[�́A�����ł̓v���X�`�b�N���ɗ�邪�A��l�ЂƂ肪�ӎ����v�����߂��Ă���A�����̏����ȂƂ��납��s����ς��Ă������Ƃ���ł͂Ȃ����Ɗ������B (���c�M��Ayomiuri = 8-25-18)
���@���@��
�v�����X�g���[�������p�~ = �C�m���z���A�ۑ��
�y���V���g���z �č��Ȃǂ̑���ƂŃv���X�`�b�N���X�g���[�̎g�p������߂铮�����������ł���B�@�p�����ꂽ�X�g���[�͊C�m���������A�����̑̓��Ɏ�荞�܂���肪�w�E����Ă����B�@���N�O���琷��オ�鑐�̍��I�Ȕp�~�^������Ƃ������`�����A�p�~�ɂ͉ۑ������B
�����ގ��̃v���X�`�b�N���X�g���[�͊C���Ŕ����ȁu�}�C�N���v���X�`�b�N�v�ɒZ���Ԃŕ�������A�C����N�W���A����ނ����ɂ���B�@2015 �N�ɓ��e���ꂽ�A�������C�K���̕@�����ʂ̃X�g���[�Ђ����o����铮��� 3,000 ����ȏ�Đ�����A�������ĂB�@�C���^�[�l�b�g����čL�܂����u�X�g���[�s�v�v�̔g���A�ăR�[�q�[�`�F�[�����X�^�[�o�b�N�X�͐�T�A�v���X�`�b�N���X�g���[�̎g�p�� 20 �N�܂łɎ���߂�Ɣ��\�B�@�A�����J���q����@���ō���g�p���Ȃ����j�����߂��B
�ǐ����铮���͍L����A�H�i�ƊE���̃j���[�X�T�C�g�́u���̊�Ƃ��w���X�g���[��`�x�����ꂴ��Ȃ��Ȃ�v�Ƃ̌����������B�@�����A��ւ���ޗ��ɂ��ۑ�͂���B�@�͔쉻�\�ȃv���X�`�b�N���X�g���[�͍����ŁA����������ɂ͐�p�̎{�݂��K�v�Ƃ����B�@�����͐����Ɏキ�A���������Ȃ����Ȃ���ɁA�M��₽����`���₷���f�����b�g������B
�̂ɏ�Q�������C�^�[�͕Ď����V���g���E�|�X�g�ւ̊�e�ŁA��Q�҂��X�g���[�Ȃ��Œ��ڔM�����ݕ������߂A�₯�ǂ����邩�A�̂ǂ��l�܂点��댯��������Ǝw�E�B�@�X�g���[�p�~�^�����u��Q�҂̐���������ɂȂ�Ƃ������_���S�����f����Ă��Ȃ��v�Ɣᔻ�����B (jiji = 7-16-18)
�R���^�N�g�A�v�����݂̈�����@�Ẳ����ɔN�� 33 ����
�č��̉����ɗ�����Ă���R���^�N�g�����Y�͔N�ԍő� 33 �����ɒB���� - -�B�@����Ȑ��v��ăA���]�i�B����̌����`�[���� 19 ���A�ĉ��w��Ŕ��\�����B�@�ׂ����ӂ��Ċ������̌����ɂȂ�}�C�N���v���X�`�b�N�𑝂₵�Ă���\��������Ƃ��Ē��ӂ��Ăт����Ă���B�@�����`�[���ɂ��ƁA�č��̃R���^�N�g�����Y�̗��p�҂͖� 4,500 ���l�B�@�قƂ�ǂ��v���X�`�b�N���̃\�t�g�R���^�N�g�����Y���g�p���A���̂����u15 - 20% �̒��p�҂�������g�C���Ɏg�p�ς݃����Y�𗬂��Ă���v���Ƃ��œ˂��~�߂��B�@���̌��ʂ���A�č������ŔN 18 �� - 33 �� 6 �疜���̃����Y�������ɗ�����Ă���Ɛ��������B
�����ɗ����ꂽ�R���^�N�g�����Y�͉���������Ɏ���B�@�`�[���ɂ��ƁA���D 2 �|���h�i�� 900 �O�����j������ 2 �����x�̃����Y��������Ƃ����B�@�ꕔ�̃����Y�͏������ӂ��ꂽ�}�C�N���v���X�`�b�N�ɂȂ�A����������̐ݔ���ʂ蔲���Đ����ɗ��o���邩�A���D�Ɋ܂܂�ď�����̒n���ȂǂŊg�U���Ă���\��������B�@�����A�ڂ������Ԃ͕s���Ƃ����B
�����`�[���́A���[�J�[�ɐ������̂ĕ��̎��m��A���R�E�ŕ��������������̃����Y���J������悤�ɋ��߂Ă���B�@�}�C�N���v���X�`�b�N�ɂ��������͋ߔN�A���E�I�Ȗ��ɂȂ��Ă���B�@�R�[�q�[�`�F�[�����E�ő��̕ăX�^�[�o�b�N�X�́A2020 �N�܂łɐ��E�̑S�X�Ńv���X�`�b�N���X�g���[��p�~����Ɣ��\�B�@���B�ψ���͍��N 5 ���A�t�@�X�g�t�[�h�̗e��Ȃǎg���̂ăv���X�`�b�N���i���K������Ă��������Ɏ����ȂǓ������L�����Ă���B (������Y�Aasahi = 8-22-18)
���}�C�N���v���X�`�b�N�� �̂Ă�ꂽ�v���X�`�b�N�����O���ŗ���Ȃǂ��� 5 �~����菬�������ɂȂ������݁B�@���Ⓓ�̑̓��Ŋm�F����A���Ԍn�ւ̉e�������O�����悤�ɂȂ����B�@�H���A���ɂ��l�Ԃ⑼�̐����ւ̈��e�����o�鋰����w�E����Ă��邪�A�ڂ������Ԃ͂킩���Ă��Ȃ��B
���Ԍn���@���ɂ₳�����v���X�`�b�N�A���i�J�����X
�A���������ɂ���o�C�I�v���X�`�b�N��A���R�E�ŕ��������v���X�`�b�N�̐��Y�����Ɍ������������ڗ����Ă����B�@�v�����݂��C�m�����������N�����A���Ԍn�ւ̉e�������O����Ă��邩�炾�B�@��_���Y�f (CO2) �̔r�o�ʂ����炷�_��������B�@�����ԗp�i�̊J�����肪����~�����[�h�i�����j�� 2014 �N�A�A���Ȃǂ̐��������������Ƃ����o�C�I�v���X�`�b�N���Ƃ𗧂��グ���B�@�O�d�E���h�̃q�m�L�i�Ԕ��ށj��A�É��E�|��̒��t�A���m�E�Ó��̃����R�����g���A���݊k�����������Ă���B
���m����{�s�̍H��ł����ӂ��A�Ζ��R���̃v���X�`�b�N�����������ăy���b�g�ɂ���B�@���^�Ǝ҂ɉ����A���|�p�i��E�b�h�f�b�L�ȂǂɎg���錚�ނƂȂ��Ďs��ɏo���B�@�y���b�g�̐��Y�ʂ� 1 �� 2.4 �g���B�@���R����В��́u�Ζ������ɂ͌��肪����B�@�o�C�I�v���Ȃ� CO2 �̔r�o�ʂ����点��B�v
17 �N 12 ���ɔ̔����n�߂��Ƃ���A���u���̍��܂�ň��������������A�H��̑��݂��v�悵�Ă���B�@�c�����������́u�g�̉��Ƀv���X�`�b�N���i�͂�������B�@�ǂ�ǂ�o�C�I�v���ɒu�����������B�v�@20 �N�܂łɔN�� 10 ���~�̔��㍂���߂����B�@���Ȃ� 14 �N�x�� 8 ���g���������o�C�I�v���̍����o�חʂ� 30 �N�x�� 197 ���g���ɑ��₷�ڕW�𗧂ĂĂ���A�ǂ����ɂȂ��Ă���Ƃ����B
�o�C�I�v���́A�������������Ă���n����������}����Ă���B�@�~�����[�h�͍���A�{�i�I�ɎO�d�E�K���s�̖Џ@�|�i�������������j���g���\��ŁA�|�̕����s�� NPO �@�l�u�K�|��v����d�����B�@���u�|�т�����c�̂ŁA���̂���|�͖��N�� 6 ��{�B�|�Y�ɂ��ēy����ǍނƂ��Ĕ̔����Ă����B�@�K�|��̎���d�M�E�������� (68) �́u�����|�̏����ɍ����Ă���l�͑����B�@�L�����p�ɂȂ���ꂵ���B�v�Ƙb���B�i���邢�Aasahi = 8-9-18)
�ꌩ���ꂢ�ȓ����`�A�ɏ����݂̋��Ё@�L�̑̓����猟�o
�g���₩�ȓ����`�B�@�ꌩ���ꂢ�ȊC�ʂɂ��A���╗�̉e���ł��݂����܂��p������B�@���|�D���������ƁA�����X�y�[�X�̓y�b�g�{�g���ȂǂŖ��܂����B�@���A�ӂ��ď������Ȃ����v���X�`�b�N���݂����E�̊C���������Ă���B�@�u�}�C�N���v���X�`�b�N�v�ƌĂ�A��ʓI�ɒ��a 5 �~���ȉ��̂��̂��w���B�@�y�b�g�{�g���̔j�ЁA�ߕ��̉��w�@�ہA�v���X�`�b�N���i�̌����u���W���y���b�g�v�ȂǗl�X�Ȏ�ނ�����A���ォ����ʂ��A�C�֗����B
�����_�H��̍��c�G�d�����́A����v�����N�g�������ݍ��ݏ����ǂ���������A���w�����������̑̓��ɒ~�ς��ꂽ�肷��\�����w�E����B�@�R�`���̊C�݂ō̎悳�ꂽ�T���v���ɂ͐F���傫�����l�X�ȃ}�C�N���v���X�`�b�N���܂܂�A�����p�ō̎悵�������T�L�C�K�C�̑̓�������A�@�ۏ�̃}�C�N���v���X�`�b�N�����������B
�v���X�`�b�N���݂����炷�����͎n�܂��Ă���A6 ���ɃJ�i�_�ŊJ���ꂽ��v 7 �J����]��c�iG7 �T�~�b�g�j�ł́A�g���̂ăv���X�`�b�N�̎g�p�팸�Ȃǂ��f����u�C�m�v���X�`�b�N���́v���̑����ꂽ�B�@�������A���{�ƕč��͏������������Ă���B
����ŁA�č��̃R�[�q�[�`�F�[�����E�X�^�[�o�b�N�X�� 7 �� 9 ���A2020 �N�܂łɐ��E�̑S�X�Ńv���X�`�b�N���X�g���[�̒���߂�Ɣ��\�����B�@���c�����́u��Ƃ��ẮA�v���X�`�b�N�̍ė��p��A���R�̒��ŕ�������鐻�i�̊J���Ȃǂ��l������B�@�������A��ԑ�Ȃ͎̂g�p�ʂ����炵�A�w����߂�x���Ƃł��B�v�Ƙb���B (�|�R���Aasahi = 7-31-18)
�L�ɔ����v���X�`�b�N���q���~�ρ@����E���Ԗ��ő�ʂɁA�����p��
�n���K�͂̊C�m���������ɂȂ��Ă���v���X�`�b�N�̔������q�u�}�C�N���v���X�`�b�N�v���A�����p�≫�ꌧ�E���Ԗ����̊C�݂̓L�̒��ɑ�ʂɒ~�ς��Ă��邱�Ƃ𓌋��_�H��̍��c�G�d������̃O���[�v�� 18 ���܂łɊm�F�����B
�O���[�v�͉ߋ��ɓ����p�̃J�^�N�`�C���V���猩���Ă��邪�A�L�͊C�O�Ō��o�Ⴊ���邾���������Ƃ����B�@�����̑̓��Ɏ�荞�܂�₷�����a 0.02 - 0.08 �~���̂��������ȗ��q�������u�L�̐�����Ԍn�ւ̉e�����ڂ������ׂ�K�v������v�Ƃ��Ă���B�@2015 - 17 �N�ɓ����s�Ɛ��s�̓����p�Ń����T�L�C�K�C�ȂǁA���Ԗ����ł̓C�\�n�}�O���̑̓��ׂ��B (kyodo =6-18-18)
�j�㏉�̑����m���j���f�ցA���`���Ƃ̒��� ��ւ́u�v�����݁v
�t�����X�l�̃x���E���R���g���� (51) �� 5 ���A��t�E���q�̊C�݂���T���t�����V�X�R�܂ŁA�����m�� 9,000 �L�����j���ʼn��f����`���ɔ�э��B�@�����m���j���œn��l�ގj�㏉�̈̋Ƃ�B������ɂ́A���R���g����͑�g�ƑΛ����邾���łȂ��A�T����N���Q�A����ɂ́u�����m���݃x���g�v�̒����j���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�@�X�^�[�g���琔�S���[�g���́A���R���g����̑��q�Ɩ����ꏏ�ɉj���Ŗ`���̎n�܂���j�����B�@���̌� 2 �l�݂͊ɖ߂�A�W�܂��� 70 �l�̎x���҂�e���A�F�l��ƕ��i�����킵���B
�`���Ƃł�������ی슈���Ƃł����郋�R���g����́A����̒����ʂ��ĊC�m�����ƃv���X�`�b�N�����ɑ���l�X�̊S�����߂����ƍl���Ă���B�@�ނ̃T�|�[�g�`�[���́A6 - 8 ����������Ƃ݂��闷�̍Œ��ɐ������̎�����\�肵�Ă���B�@�r���A�ł�����ɂȂ�Ƃ݂��Ă���̂��A�n���C�B�ƃJ���t�H���j�A�B�̊Ԃɕ����ԋ���ȁu���݂̉Q�v�̒����j�����Ƃ��B�@���̂��݂̌ł܂�́A�قڃe�L�T�X�B�Ɠ����傫���ŁA���܂荇�����v���X�`�b�N�����Ɋ댯���Ƃ����B�@���C��ł́A�T�|�[�g�`�[�����C���T���v�����̎悵�ă}�C�N���v���X�`�b�N�̒~�ςɂ��Ē�������B
���풆�͑S��20 ���[�g���̃{�[�g�u�f�B�X�J�o�[�v�����펞���s����B�@���R���g����͐H����x�e�A�����������łƂ�A���ɂȂ�ƑO���ɉj���I�����ꏊ�܂Ŗ߂�A�j���n�߂�B
�� �u������Ƃ���Ƀv���X�`�b�N�v
�X�^�[�g���O�A���R���g����� AFP �̃C���^�r���[�ɁA�u�g�̖ʂ��������^���ʂ̕������ɏd�v���B �K���A��Ƀ|�W�e�B�u�Ȃ��Ƃ��l���邩�A��������v�Ă�������K�v������B�v�ƌ�����B�@�u���̒��������ς��ɂ�����̂��Ȃ��ƁA���z�Ɋׂ��Ă��܂��B�����������Ɉ������Ƃ��N����B�v�@���R���g����ɂ��ƁA�ł��炢�̂́A���A�C�ɖ߂�Ƃ����Ƃ����B�@�܂��A���� 4 - 6 ���ԉj������ɂ́u�ǁv�ɂԂ���Ƃ����B�@�u�S�Ƒ́A�����Ēɂ݂⊦���Ȃǎ����̑̂ɋN���邱�Ƃ�藣���悤�w�͂���B�@8 ���Ԃ̂������A���ɂ��čl����̂�������Ɨ\��𗧂ĂĂ���B�@���̒�����ɖZ���������Ă��Ȃ��ƑʖڂȂB�v
���R���g����� 1998 �N�A�吼�m���j���ʼn��f�����B�@�����́u������x�Ƃ��Ȃ��v�Ɛ��������A�����̉ƒ�����Ƃ܂��C�ɖ߂肽���Ǝv���悤�ɂȂ����Ƃ����B�@�u�������c���Ƃ��́A���e�ƕl�ӂ�����Ă��Ă��قƂ�ǃv���X�`�b�N�̂��݂Ȃ�Č��Ȃ������B�@���܂́A�q�ǂ���A��čs���Ƃ�����Ƃ���Ƀv���X�`�b�N�������Ă���B�v�@����̒���ł́A�����̌������̂ɂ��e�����m�F���邽�߁A���ː������̑������g�ɒ�����B (Harumi OZAWA�AAFP = 6-5-18)
���݉����i�ޒn���̊C�@�}���A�i�C�a�̐[�C�Ƀ|���ܕ�
���[ 1 �����[�g�����̐[�C�Ń|���܂̔j�Ђ��݂���ȂǁA�v���X�`�b�N���݂��[�C�ɂ܂œ��B���Ă�����Ԃ��A�C�m�����J���@�\�Ȃǂ̌����O���[�v���܂Ƃ߂��B�@�����҂́A���E���̊C���\�w����C��܂Ńv���X�`�b�N�����ɂ��炳��Ă���A�ƌx�����Ă���B�@�@�\�́A�L�l���������D�u���� 6500�v�Ȃǂ������������ɎB�e�����摜�⓮��̂����A�v���X�`�b�N�Ђ�����ЂȂǂ̂��݂��ʂ������̂̃f�[�^�x�[�X���\�z�B�@�����O���[�v�͂�������p���A�����m�Ȃǂ� 1982 - 2015 �N�ɍs��ꂽ 5,010 ��̐��������̃f�[�^�͂����B
�m�F�ł������݂� 3,524 �A���� 3 ���� 1 ���v���X�`�b�N���݂������B�@���[ 6 �烁�[�g���ȏ�ł͂����������݂������ȏ���߂��B�@�v�����݂� 9 ���̓|���܂�y�b�g�{�g���Ȃǎg���̂Đ��i�������B�@�ł��[���Ō��������̂́A�����m�̃}���A�i�C�a�̐��[ 1 �� 898 ���[�g���̊C��ɂ������|���܂̔j�Ђ������B�@���@�\�n�����ϑ������J���Z���^�[�̐�t���c�E��C�������́u�����牓�����ꂽ�[�C�܂ŁA�������̓��퐶���̉e�����y��ł���B�@�v���X�`�b�N�����̊ϑ���@���m�����A���ۓI�Ȋϑ��l�b�g���[�N������āA���ʓI�ȑΉ�����������Ă������Ƃ��K�v���B�v�Ƃ��Ă���B (�쑺���u�Aasahi = 5-19-18)
�C�X�ɂ���Ėk�ɊC�ɉ^���}�C�N���v���X�`�b�N
��ʂ̃}�C�N���v���X�`�b�N���C�X�ɕߑ�����A�k�ɊC�S��ɉ^��Ă��邱�Ƃ����_�����A���T�f�ڂ����B�@���̐V�m���́A�C�X���}�C�N���v���X�`�b�N�̈ꎞ�I�Ȓ����ɂƂ��ē����Ă��邱�Ƃ������A�C��ϓ��ɂ���ĊC�X�̗Z�����i�ނƑ�ʂ̃}�C�N���v���X�`�b�N���C�m�ɕ��o�����\�������邱�Ƃ𗠕t���Ă���B
����AIlka Peeken �����̌����O���[�v�́A�X���R�A�Ɋ܂܂��}�C�N���v���X�`�b�N�i5 �~�����[�g�������̃v���X�`�b�N�j�̑g���ƊC�X�̕Y���O�Ղ͂��A�C�X�������f����p���āA�C�X�̐����ߒ��Ń}�C�N���v���X�`�b�N���C�X�ɕߑ����ꂽ�C��肵���B�@�C�X�ɕߑ����ꂽ�}�C�N���v���X�`�b�N�̃|���}�[�g���́A�X���R�A�ɂ���ĈقȂ��Ă��邱�Ƃ��������A�C�X�̋N�����悲�ƂɓƎ��̃|���}�[�g�������肳�ꂽ�B�@�܂��APeeken �����́A����̌����ŗp����ꂽ�C�X�����̋N�����A�����W�A���C�~�ƃ��[���V�A�C�~�ɂ���A���̑啔�����A��v�Ȗk�ɊC���� 1 �ł���k�ɉ��f���ɂ���Ėk�ɊC�������ɉ^��Ă������Ƃ��������B
Peeken �����́A�k�ɊC�������ɂ�����}�C�N���v���X�`�b�N�̕��z������܂ōl�����Ă����ȏ�ɕ��G�ł���A�C�X���Z�����ă}�C�N���v���X�`�b�N�����o�����ƁA�����͖k�ɊC�̕\�w����[�w�܂őS�̂ɂ킽���ĕ��z����\��������Ǝ咣���Ă���B (Nature Communications = 4-25-18)