広がる年収差 … 役員報酬は高額化、従業員の年収増は慎重
報酬を 1 億円以上もらう上場企業の役員は 400 人を超え、高額報酬を受けとる役員とその企業の従業員との年収の差は年々広がる。 役員報酬は好業績を反映しやすいが、企業はコスト増につながる従業員の年収アップには慎重なためだ。 役員の巨額報酬への批判もある米国並みに差が開く日本企業も、出てきそうだ。
今年 3 月期の報酬が初めて 10 億円台にのった日産自動車のカルロス・ゴーン社長は、6 月 23 日の株主総会で「役員報酬に相当な投資をしないと、競争力を保つのに必要な人材の採用や確保ができない」と理解を求めた。 従業員の平均年収の約 20 倍にあたる 2 億円超の報酬を得た大手金融会社トップは「社員の給料も業績に連動している。 役員の貢献に報いる仕組みも、企業の収益力を高めるために必要だ。」と話す。 (多田敏男、編集委員・堀篭俊材、ニューヨーク = 畑中徹、asahi = 7-26-15)
リケジョ育成で官民連携 夏休みに職場体験実施
内閣府と経団連は 17 日、「リケジョ」と呼ばれる理工系分野で活躍する女性の増加に向け、中高生や大学生らに理系の専攻や仕事の魅力を知ってもらうイベントを、夏休み中の 7 - 8 月に各地で実施すると発表した。
労働力人口の減少を見据え、政府はリケジョの育成を重要課題に位置付けており、官民連携で進学から就職まで一貫して、女性の理工系選択を支援したい考えだ。 「理工チャレンジ」と銘打った企業の職場見学会は経団連加盟の建設会社や鉄鋼メーカーなど 31 社で実施。 トンネルや防潮堤などの大規模工事の現場見学や、研究開発拠点での研究体験などを予定している。 (福井新聞 = 7-17-15)
「トヨタ社員の夫、過労とパワハラで自殺」 国を提訴
トヨタ自動車の社員だった男性(当時 40)が自殺したのは過労とパワハラによるうつ病が原因だったとして、妻 (44) = 愛知県豊田市 = が 10 日、国を相手取り、労災を認めなかった労働基準監督署の処分取り消しを求める訴えを名古屋地裁に起こした。
訴状によると、男性は 2008 年 4 月からトヨタ三好工場(同県みよし市)で自動車部品の生産ラインを造っていたが、リーマン・ショックの影響による人員削減に伴い、09 年 7 月以降は「残業ゼロ」の方針で業務が過密化。 上司から指導の適正な範囲を超えたパワハラがあったという。 男性は同年秋から妻に「上司から罵声を浴びせられる。 経験したことのないひどい叱られ方をされ、けちょんけちょんに言われる。」と話し、12 月にうつ病と診断され、10 年 1 月に自殺した。
妻は遺族補償給付などを求め豊田労働基準監督署に労災認定を申請。 「業務による心身の負荷が有力な原因とは言えない」として 12 年 10 月に不支給処分となった。 労働保険審査会などに再審査を求めたが、棄却されたという。 夫の死後は看護師として働き、中学 2 年の長女 (14) と 2 人暮らし。 提訴後の会見で「将来、子どもはなぜ父が亡くなったのかと思うだろう。 子どものためにも夫が一生懸命働いたことを認めてもらいたい。」と訴えた。 弁護人は「労基署の調査は不十分で事実が明らかになっていない」と話した。
豊田労基署を所管する愛知労働局は「訴状が届いていないので、コメントは差し控える」、トヨタ広報は「訴訟の詳細を把握する立場にないので、コメントできない」としている。 (asahi = 7-10-15)
深夜残業 → 翌日必ず遅出 勤務間休息ルール始まってます
社員さん、今日の仕事が深夜に及んだら、明日はゆっくり出勤しましょう - -。 前の終業から次の始業までの間に一定の休息を取らせる「勤務間インターバル」の取り組みが、大企業で増え始めた。 極端な働きすぎの防止策だが、多くの企業に広がるには時間がかかりそうだ。 通信大手 KDDI は 7 月から、「8 時間以上の休息確保」ルールを本格的に始めた。 管理職を除く社員約 1 万人が対象。 午前 1 時以降の勤務を原則禁止し、始業時刻の午前 9 時までに 8 時間以上の休息がとれるようにする。 もし 1 時以降も働いたら、次の出勤がその分ずれる。 たとえば午前2時退社なら、翌朝の出勤は 10 時以降だ。
8 時間ギリギリの日が続かないよう、休息が 11 時間を下回った日が 1 カ月に 11 日以上あったら、本人や上司に注意を促す。 KDDI は以前から、設備担当の社員などで休息ルールを適用していた。 今春闘で労働組合の求めに応じ、対象を広げた。 白岩徹・人事部長は「『長時間労働をなくす』という会社の姿勢を強く打ち出したかった」と説明する。
勤務間インターバルについては、欧州連合 (EU) が「11 時間以上の確保」を企業に義務づけている。 日本にはこうした法規制がないため、労組が経営側と話し合って自主ルールとして確保に乗り出している。 KDDI など情報通信産業の労組がつくる情報労連は、今夏までに傘下の 21 組合でルール化した。 働きすぎへの懸念が指摘される外食業界でも、取り組む会社が出てきた。 24 時間営業のレストランを展開するジョイフルは昨春、店長ら従業員に「11 時間以上の休息」をとる仕組みをつくった。 (佐藤秀男、牧内昇平、asahi = 7-8-15)
トヨタ、配偶者手当廃止へ 子ども分を 4 倍増 労使合意
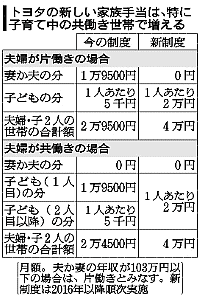
トヨタ自動車の労使は、「家族手当」を大幅に見直すことで大筋合意した。 月額約 2 万円の専業主婦(夫)らの分を廃止する代わりに、子どもの分をおおむね 4 倍に増額する。 来年 1 月以降、段階的に実施する。 女性に就労を促し、子育ても支援する国の政策を先取りする形だ。
トヨタの家族手当は月給の一部で、現在は子ども 1 人あたり月 5 千円が基本だが、新制度では 2 万円に引き上げる。 一方、社員の妻か夫が働いていない場合や、年収が 103 万円以下の場合に払っている分(月 1 万 9,500 円)は打ち切る。 これらにより、子どもが 2 人以上いる社員は手当が増えるが、妻が専業主婦などで子がいない場合は逆に減る。 全体の会社支払額は変わらない見通しだ。
経営側は配偶者の分を 2019 年に完全に打ち切る考え。 しかし、労働組合側は手当が大きく減る社員に配慮して 21 年ごろまで遅らせるよう求めており、労使で協議を続ける。 また、社員の親が高齢で働いていない場合も、新制度の対象にするかなども話し合う。 (友田雄大、asahi = 7-7-15)
ABC マートを書類送検 違法な長時間労働の疑い
東京労働局は 2 日、全国展開する靴の販売店「ABC マート」が、従業員に違法な長時間労働をさせたとして、労働基準法違反の疑いで、運営会社「エービーシー・マート(東京都渋谷区)」の役員ら 3 人と法人としての同社を書類送検した。
いわゆるブラック企業の対策として 4 月に東京、大阪両労働局にできた過重労働撲滅特別対策班による初めての書類送検。 エービーシー・マートは「このような事態に至ったことは誠に遺憾。 現在は法令順守を徹底し、全店舗でこのような問題が生じない体制が確立している。」とのコメントを発表した。 送検された 3 人は、男性取締役と東京都内の店舗の男性店長 2 人。 (河北新報 = 7-2-15)
地方大学を活用した雇用創出・若者定着を後押し
総務省と文部科学省では、今年度から地方創生の取り組みの一環で両省が連携して行っている「地方大学を活用した雇用創出・若者定着」事業の周知と協力を呼び掛けている。
地方大学に進学する学生や、地域産業の担い手となる特定分野の勉強をする学生に対して、地方企業などに就職した場合、返還の全部または一部が免除される奨学金を創設するほか、地域活性化に資する事業を行う大学に補助金を増額。 また、地元産業界と連携した長期インターンシップなどの実践的な職業教育、地域ブランドや地場産業の育成強化など雇用創出・若者定着につながる分野で大学と地元企業の共同研究を推進する事業も行う。 詳細は ⇒。 (日本商工会議所 = 6-25-15)
派遣法改正案、衆院を通過 与党の賛成多数で可決
派遣社員の受け入れ期間の制限を事実上なくす労働者派遣法改正案が 19 日午後の衆院本会議で採決され、与党の賛成多数で可決された。 今後は参議院で審議されることになる。 与野党で激しく対立してきた同法案は成立に近づいた。
改正案は、派遣先の会社が労働組合などの意見を聞いた上で、人を入れかえれば同じ仕事をずっと派遣社員に任せることができるようになる内容。 社員の仕事が派遣に置きかわりかねないとして、一部の野党は「生涯派遣になる法案だ」などと批判している。 法案は 12 日の衆院厚生労働委員会で審議が打ち切られたが、民主などが「丁寧に質疑をすべきだ」と反発。 安倍晋三首相も出席して 19 日午前中に補充的な質疑をした。 採決では民主、維新、共産が反対したが与党の賛成で可決。 本会議にもはかられ、可決した。 (末崎毅、asahi = 6-19-15)
日航 CA、「マタハラ」提訴 … 休職命じられ無給
日本航空の客室乗務員の女性が 16 日、妊娠して地上勤務を希望したのに休職を命じられ、無給となったのは、男女雇用機会均等法が禁じる「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、同社を相手取り、休職命令の無効確認や賃金など約 340 万円の支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。 訴状によると、原告の神野知子さん (40) は、昨年 8 月に妊娠が分かった。 同社に報告し、地上勤務の希望を伝えたが、同 9 月、会社から「地上職のポストがない」と休職を命じられ、無給になったという。
同社によると、妊娠が判明した客室乗務員は、母性保護のため休職させるが、本人が希望し、かつ会社が認めた場合は、地上勤務ができる制度を設けている。 2007 年度までは希望者全員が地上勤務に就くことができたが、業績悪化により、08 年度から「会社が認めた場合」という条件が加わった。 (yomiuri = 6-16-15)
東京圏への移住、女性の方が多い その理由は
地方から東京圏に移り住む人は男性より女性の方が多い - -。 内閣府の分析でこんな傾向が分かった。 地方に女性の働き口が少ないことが背景にあるとみられ、働く場が広がれば「地方は女性にとってより魅力ある場所になる」としている。 内閣府が住民基本台帳などから分析した。 東京圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)で転入と転出の差である転入超過数を見ると 2009 年以降は女性が男性より多く、14 年は女性が約 6 万人、男性が約 4 万 9 千人。 15 - 34 歳がいずれも大半を占めた。
また、東京圏と名古屋圏、大阪圏を除く地方の転出超過数も同じ傾向で、14 年は女性約 5 万 6 千人で、男性約 4 万人だった。 15 - 64 歳の女性就業者は 14 年までの 11 年間に東京圏で 62 万人増え、他地域は 33 万人減った。 ただ、内閣府が今年、全都道府県の 20 - 69 歳の男女 500 人ずつを対象に実施した意識調査では、都市部に住みたいと答えた人で「仕事の機会が充実している」を理由にした女性は 9.8%。 男性の 17.6% より少ない。 一方、地方に住みたいと答え、「近くに親族や知人が多い」を理由にした女性は 20.4% で、男性の 11.4% より多い。
それでも都市部へ移住する女性が多いことについて、内閣府は「必ずしも都市部での仕事にあこがれているわけではなく、就業機会が少ないことなどでやむを得ず都市部で就業している可能性もうかがわれる」と分析。 「地方で女性の就業の場が広がれば女性にとってより魅力ある場所になる」とする。 分析結果は、近く閣議決定される 15 年版男女共同参画白書に盛り込む。(畑山敦子、asahi = 6-11-15)
大学ランク、中国に校数抜かれる アジア、学校別トップは東大
【ロンドン】 英教育誌タイムズ・ハイヤー・エデュケーションは 10 日、中東を含むアジアの今年の大学ランキングを発表した。 東京大が 2013 年の発表開始以来 3 年連続でトップだったが、上位 100 校に入った日本の大学は昨年より 1 校少ない 19 校で、21 校の中国に初めて校数で首位の座を譲った。 13 年に 22 校だった日本は 2 年連続の減少となり、昨年 2 位の中国に逆転を許した。 今回の 19 校も東大や神戸大などを除く 15 校が昨年より順位を下げており、同誌は「中国に対抗するため研究投資を増やさなければならない。 迅速に対処すべきだ。」と指摘している。 (kyodo = 6-11-15)
英語 4 技能、中 3 に全国テスト 文科省「推進プラン」
文部科学省は 5 日、中高生の英語力を上げるための「推進プラン」を発表した。 全国の中学 3 年生を対象に、「聞く・話す・読む・書く」の 4 技能の新しいテストを 2019 年度から導入することが柱。 生徒は苦手な分野を自ら把握して中高での学習に生かし、教員は授業の改善につなげるのが狙いという。
新テストは数年に一度の実施を想定。 具体的な方法は今後、議論する。 毎年 4 月に 2 - 3 教科で実施されている「全国学力調査」の一部として加えることも検討する。 すでに英検などの民間試験を受けている生徒もいるが、義務教育の中学生には無料で受けられ、かつレベルに合ったテストが必要と判断した。 今年 7 月と来年に、中 3 の一部に試行のテストを実施し、方法などを検証して本格導入の参考にする。 (高浜行人、asahi = 6-5-15)
東京圏高齢者 : 移住促進を 25 年、介護人材 90 万人不足
創成会議が提言
産業界や研究者らでつくる有識者団体「日本創成会議・首都圏問題検討分科会(座長・増田寛也元総務相)」は 4 日、東京、神奈川、埼玉、千葉の 1 都 3 県(東京圏)の 2025 年の介護需要が現在(15 年)に比べ 45% 増え、172 万人に上るとの試算を公表した。 全国平均(32% 増)を大きく上回り、他地域に比べ突出している。 入院需要も 21.8% 増加する。
一方で、東京圏は医療・介護の受け入れ能力が全国平均よりも低く、「患者のたらい回し」や「介護施設の奪い合い」が起きる可能性が高いと警鐘を鳴らし、地方移住を促す施策の推進などを提言している。 25 年には団塊の世代が 75 歳以上となる。 国立社会保障・人口問題研究所の推計では、同年の東京圏の 75 歳以上人口は現在より約 175 万人増え、全国の増加数の 3 分の 1 を占める。
創成会議の試算によると、在宅と入所の介護需要は 25 年には埼玉が現在の 51.5% 増、千葉は 49.8% 増、神奈川で 47.7% 増、東京は 37.9% 増。 埼玉、千葉、神奈川の増加幅が際立つ。 入院需要も全国平均の 14.1% 増に対し、▽ 埼玉 24.6% 増、▽ 神奈川 22.5% 増、▽ 千葉 21.9% 増、▽ 東京 19.8% 増となる。 この結果、東京圏では医療や介護の人材が 25 年に約 80 万 - 90 万人不足するという。
試算を踏まえ、創成会議は、東京圏全体で今後の医療や介護の需要・供給見通しを共有することの必要性を指摘。 さらに、40 年には崩壊しかねないとして、高齢者の移住を促すため、移住費用の支援や「お試し移住」の導入などを提案している。 日本創成会議は昨年 5 月に「消滅可能性都市」の一覧を公表している。【阿部亮介、mainichi = 6-4-15】
夏のボーナス、大手平均は 91 万 3,106 円 経団連集計
大手企業の夏のボーナス調査(第 1 回集計)を経団連が 29 日、発表した。 妥結額は平均で昨年夏より 2.43% 多い 91 万 3,106 円。 円安などで企業の業績が良くなったことを受けて 3 年連続のプラスとなり、リーマン・ショック前の 2008 年(93 万 329 円)以来の高い水準だった。
63 社のうち 54 社が製造業で、製造業に限れば、妥結額は 96 万 7,870 円。 自動車は伸び率こそ 0.19% 減だったが金額は 110 万 3,802 円で最多だった。 造船(87 万 2,248 円)、電機(85 万 8,495 円)も多かった。 企業業績の改善とともに、ボーナス額を業績に連動して決める傾向が強まっていることも高い水準になった背景にある。 調査は 20 業種 245 社の大手企業(原則として東証 1 部上場、従業員 500 人以上)が対象。 今回は労使交渉が妥結し、集計できる 63 社(労働組合員数は約 42 万人)分を発表した。 (稲田清英、asahi = 5-30-15)
来春採用「増やす」 4 割超 朝日新聞・主要 100 社調査
企業が、業績回復を背景に採用意欲を高めている。 朝日新聞社が主要 100 社に 2016 年春の新卒採用計画を聞いたところ、前年より「増やす」は 42 社で、「減らす」の 11 社を大きく上回った。 「増やす」の 4 割超えはリーマン・ショック前の 08 年春(41 社)以来。 学生有利の「売り手市場」になったと感じている企業は 64 社に上った。 5 月下旬までの約 1 カ月間、調査した。 「横ばい」は 35 社、「未定」は 12 社で、「増やす」は昨年の 34 社より 8 社多かった。
採用増の動きは、幅広い業界に及んでいる。 すかいらーくは出店増に向けて、前年実績から倍増の 160 人を予定。 新日鉄住金も定年退職者の補充や技術ノウハウを次世代に引き継ぐため、ほぼ倍増の 1,620 人を見込む。 資生堂は研究開発力の強化などのため、前年の約 1.5 倍の 90 人を採用予定だ。 (吉川啓一郎、細見るい、asahi = 5-30-15)
4 月失業率 3.3%、18 年ぶり低水準 個人消費なお低迷
景気の緩やかな回復を映し、雇用や企業の生産活動の改善が続いている。 4 月の完全失業率は 3.3% と前月に比べ 0.1 ポイント低下。 1997 年 4 月以来、18 年ぶりの低水準となった。 企業の採用が活発になり離職者が減った。 IT (情報技術)関連などの生産が増え、鉱工業生産指数は前月比 1% 増となった。 ただ、家計の消費支出はマイナスで、個人消費の本格回復には至っていない。
総務省が 29 日発表した 4 月の失業率は 3 カ月連続で改善した。 未就職の状態で仕事を探している完全失業者数(季節調整値)は 219 万人で、前月に比べ 2 万人減った。 このうち勤め先や事業の都合による離職は 4 万人減の 40 万人となり、2002 年以降で最も少なくなった。 正社員と非正規社員の両方が増え、雇用の質も改善している。 正規社員は前年同月比 6 万人増の 3,294 万人、非正規社員は 30 万人増の 1.939 万人だった。 15 歳から 64 歳の就業率は 72.9% で 0.5 ポイント上昇した。
失業率はリーマン・ショック後の 2009 年 7 月に 5.5% に上昇したが、景気の持ち直しを受けて低下傾向が続いている。 現行の賃金水準で働きたい人がすべて雇用されている「完全雇用」に一段と近づいたとの見方もある。 雇用指標では、同日厚生労働省が発表した 4 月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.17 倍と前月から 0.02 ポイント上昇した。 23 年 1 カ月ぶりの高水準だ。 教育・学習支援業や医療・福祉で求人が増えた。 有効求人倍率が高いほど、求職者は仕事を見つけやすく、企業は採用が難しい。 幅広い業種で、人手不足が続き、賃金も上昇する要因となっている。
雇用改善の背景には企業の生産活動の持ち直しがある。 経済産業省が同日発表した 4 月の鉱工業生産指数(2010 年 = 100、季節調整値)速報値は前月比 1.0% 増の 99.1 となった。 前月を上回るのは 3 カ月ぶり。経産省は「緩やかな持ち直しの動き」との基調判断を据え置いた。中国などアジアで組み立てるスマートフォンの新機種生産を見込み、電子部品・デバイスが 5.2% 増えた。 電気機械は国内向けのエアコンを中心に 6.4% 増加した。
一方、個人消費は低迷から脱し切れていない。 総務省が同日発表した 4 月の家計調査によると、2 人以上世帯の 1 世帯当たり消費支出は 30 万 480 と、物価の動きを除いた実質で前年同月比 1.3% 減った。 減少は 13 カ月連続となる。 住宅リフォームなどの支出が減り「住居」が実質で 20.6% 減り、全を大きく押し下げた。 総務省は「増税前の駆け込み需要で膨らんだリフォーム費の支払いが 4 月にずれ込んだことが影響した」と説明した。 季節要因をならした 4 月の実質消費支出を 3 月比でみても 5.5% 減だった。マイナス幅は縮小傾向にあるが、消費には弱さがある。 (nikkei = 5-29-15)
企業悩ます人手不足・人件費増、高齢者雇用などに活路
[東京] 景気拡大の裏側で深刻化する人手不足と人件費上昇が、非正規比率の高い小売り、外食、サービス産業などの経営を一段と圧迫している。 必要なパート社員やアルバイトを確保するには時給引き上げが避けられない。 出店計画を下方修正するなど経営戦略への影響も目立つ中、各社には高齢者雇用や短時間での雇用などに活路を見いだそうという動きも広がっている。
<出店計画にも影響>
全国に約 3,000 店を展開し、約 9 万人の従業員を抱えるすかいらーく。 2015 年 1 - 3 月期は、人手不足のショックを乗り切り、売上高人件費率が前年同期の 32.7% から 31.7% に低下した。 寺口博取締役は「生産性向上に取り組み、人件費率が低下した」と話す。 同社が取り組んだのは、店舗オペレーションの簡素化や効率的な人員配置などで、こうした細かな対策の積み重ねが奏功した。 しかし、寺口氏は、年間を通して、人件費率が前年を下回るかどうかは、「何とも言えない状況」と慎重な姿勢を崩さない。
小売りや外食、サービス産業は総コストに占める人件費の比率が高く、賃金を引き上げれば、他の産業以上の負担となって企業経営に跳ね返る。 実際に、人手不足の長期化による人件費上昇は、各社の事業計画にも影を落とし始めている。 平和堂は、今期 7 店舗の出店を予定しているが「パートなど人手不足が問題(夏原平和社長)」という。
多くのアルバイトに支えられているコンビニエンスストアも出店計画に狂いが生じている。 セブン-イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマートの大手 3 社の 15 年 2 月期は、期初の出店計画 4,300 店に対し、実際は 3,732 店にとどまった。 ローソンの玉塚元一社長は「地域によっては、人手不足は深刻さを増している」と指摘する。 16 年 2 月期は合計 3,900 店の新規出店を計画しているが、着地は不透明だ。
<人件費増で「お値打ち感」失う>
輸入牛肉価格の上昇に円安が加わって材料コスト高に苦しむ牛丼業界では、深刻な人手不足がビジネスモデルの転換を迫る事態も起きている。 夜間にひとりでオペレーションする「ワンオペ」が問題となったゼンショーホールディングスは、2015 年 3 月期の連結当期損益が上場来初めて赤字となった。 原材料高・人件費増・米国の事業清算などが大きな打撃となった。 「ワンオペ」による深夜営業を休止した店舗については、9 月にはすべて営業再開を計画しており、人件費負担増は今期も続く。
上昇したコストを商品価格に転嫁できれば問題解決は容易だが、それには価格に厳しい消費者の反応が壁になる。 松屋フーズは、昨年 7 月にチルド牛肉を使った「プレミアム牛めし」を発売。 従来の牛めしを順次切り替えるはずだったが、計画は足踏みだ。 緑川源治社長は「生産性が上がる準備が間に合わない」と説明する一方、「牛めしで高い価格は取りにくいかもしれない。 日常食べるものは、お値打ち感と美味しさが必要。」と本音を漏らす。 従来の牛めし 290 円に対して、プレミアム牛めしは 380 円。 想定以上の客離れを引き起こしており、価格設定の難しさを示した格好だ。
<短時間勤務・高齢者など取り込み>
吉野家ホールディングスは今後、高齢者や主婦の雇用を拡大する方針だ。 店舗の労働環境改善を進めるチームを 1 月に立ち上げ、定年退職した高齢者や主婦が働くための職場作りを進めている。 例えば、従来行ってきたような、米が炊きあがった釜を持ち上げるなどの作業は、高齢者や女性には困難になるため、改善できないか検討中だ。
イオンでも、2 - 4 時間の短時間のパートを積極投入する。 「これまで、夕方の繁忙期に人手が足りず、品切れやレジの行列などを起こし、機会損失を生んでいた(岡崎双一イオンリテール社長)」という。 今期は、30 億円をこうした人材確保に充てる。 また、丸井グループでは、コールセンターで事務処理にあたるアルバイト確保が厳しくなりつつあるという。 首都圏では集まりにくい人材をカバーするため、コールセンターを各地に分散させることで、人員不足の解消への取り組みを強化している。 (清水律子、Reuters = 5-22-15)
今春の大卒就職率 96.7%、リーマン前とほぼ同水準
今春卒業した就職希望の大学生のうち、就職した人の割合を示す就職率(4 月 1 日現在)は 96.7% (前年比 2.3 ポイント増)で、4 年連続で改善した。 19 日、文部科学省と厚生労働省が発表した。 リーマン・ショックの影響が表れる前の 2008 年 3 月卒 (96.9%) とほぼ同水準まで回復した。
近畿地方は 97.1% (前年比 3.3 ポイント増)、九州地方は 94.7% (同 3.9 ポイント増)で、ともに調査を始めた 1996 年度以降で最高だった。 中部地方と中国・四国地方も 97.3% と高水準。 文科省の担当者は「景気回復の影響が地方にも及んでいる」とみる。 調査は大学や専門学校などの 6,250 人を抽出して実施した。 大学生のうち就職を希望したのは過去最高の 72.7% (同 1.2 ポイント増)だった。 大卒者数から推計すると就職希望は 41 万 700 人で、そのうち 39 万 7,100 人が就職した計算になる。 (高浜行人、吉川啓一郎、asahi = 5-19-15)
ブラック企業公表、行政指導段階から 厚労省が新基準
違法な長時間労働を繰り返す「ブラック企業」について、塩崎恭久厚生労働相は 15 日の閣議後会見で、企業名を早期に公表する新たな基準を明らかにした。 違法に月 100 時間超の残業をする働き手が一定数いた場合などに、行政指導の段階で公表する。 18 日から実施する。 いまは企業が長時間労働で法律に違反した場合、労働基準監督署が是正を勧告。 それでも従わない悪質な企業に限って、書類送検して社名を原則公表している。 2013 年に公表された件数は 100 件程度という。
新基準では、複数の都道府県に支店や工場を持つ大企業が対象になる。 残業代の未払いといった違法行為があり、時間外や休日に働いた時間が月 100 時間を超える働き手が、1 カ所に 10 人以上いることなどを基準にする。 ただ、年間に 3 カ所以上で違法な長時間労働がなければ公表されないため、公表企業数は限られそうだ。 (asahi = 5-15-15)
「夜間中学」生徒、8 割が外国人 類似の取り組み広がる
中学校を卒業できなかった高齢者や外国人らが通う「夜間中学校」について、文部科学省がどの程度ニーズがあるかを初めて調査し、8 日発表した。 ボランティアたちが運営する似たような取り組みが 154 市区町に広がる一方、夜間中学を置いているのは 8 都府県 25 市区にとどまった。 調査は全国の教育委員会を対象に昨年 5 月 1 日時点の状況を聞いた。
夜間中学は全国に 31 校あり、大阪市や奈良市、東京都世田谷区、千葉県市川市などにある。 生徒 1,849 人のうち、8 割が外国人で、入学理由は「読み書き」や「日本語会話」の習得が 3 割近くと多かった。 一方、全員が中学未修了者で、不登校などでほとんど中学に通わないまま形だけ卒業した既卒生はいなかった。 (高浜行人、asahi = 5-8-15)
就職内定率 7.5%、前年比減 採用解禁後ろ倒し影響か
来春卒業予定の大学生・大学院生の 4 月 1 日時点の就職内定率は 7.5% で、前年同期の 18.5% より 11 ポイント低いとの調査結果を、就職情報会社リクルートキャリアがまとめた。 4 月 28 日に発表した。 同社は「今年から(大手の)採用解禁が 8 月に 4 カ月後ろ倒しになったことが背景にあるのでは」とみている。
就職情報サイト「リクナビ」にモニター登録した民間企業志望の学生 1,892 人が回答した。 内定率の内訳は、文系 6.9% で理系 8.9%、男性 9.7% で女性 4.8%。 地域別では近畿 10.1%、関東 9.2%、中部 5.0% で、その他の地域 2.9% だった。 まだ内定・内々定をもらっていない人に今後の取得の見通しを尋ねたところ、「見通しは立っていない」が 56% で半分以上。 「ある程度取得できる見通し」が 27.1%、「確実に取得できる見通し」が 4.3% で続いた。 (asahi = 5-6-15)
資生堂、11 年ぶりに販売員を正社員採用へ 販売力強化
資生堂は店頭で化粧品の販売を担う「ビューティーコンサルタント (BC)」の正社員採用を、2016 年 4 月から 11 年ぶりに復活させる。 現在約 2 千人いる契約社員にも正社員登用試験を受けてもらい、合格者から順次正社員にする。 BC の意欲を引き出し、販売力を強化するのがねらい。
16 年 4 月には、約 500 人を新たに正社員として採用。 若い世代を多く店頭に配置することで若い客を取り込み、人口減によるパイの奪い合いに備える。 資生堂は長く BC の正社員採用を続けていたが、急成長するドラッグストアにも BC を配置する必要が出てきたことや人件費の削減などを理由に、契約社員の採用に切り替えた。 最後まで正社員採用を続けたデパート担当も、06 年 4 月から契約社員採用となった。 (横枕嘉泰、asahi = 4-28-15)
人材不足の中小、4 割近くに 15 年版中小企業白書
政府は 24 日、2015 年版中小企業白書を閣議決定した。 深刻な人手不足に焦点をあて、人材を確保できていない中小企業が 4 割近くに上ると指摘。 ただその一方で、外部からの人材獲得はコストに見合わないと考えている経営者も多く、必要な人材を柔軟に確保できない中小企業の実態を浮き彫りにした。 売り上げが伸び悩む中小企業では新規顧客の発掘や市場調査を手掛ける人材が不足している。 白書では、経験を積んだ人材などを外部から獲得した企業も 11% にとどまっていると指摘。 人材を外部から得ていない企業の 56% は「コストに見合う効果が期待できない」と答えた。
白書では、研究開発や経営の中核となる人材も不足していると指摘した。 中小企業の人材獲得手段はハローワークや知人・友人の紹介などが多い。 自社ホームページの活用など採用手段を多様にする必要があるとした。 政府は今回、小規模事業者(製造業で従業員 20 人以下)の白書も初めてまとめた。 小売業の事業所数はピーク時の 1981 年から 2012 年までの 31 年間で 50% 減り、製造業は 46% とほぼ半減した。 経営者の高齢化が進み、後継者不足が深刻になっている。 (nikkei = 4-24-15)
ガバナンス・コード導入目前 経営透明化・効率化進むか
金融庁と東京証券取引所による 6 月からの企業統治指針(コーポレートガバナンス・コード)導入が目前です。 狙いは経営の透明化と効率化です。
上場企業は経営計画、持ち合い株保有・取締役選任などの理由の開示、社外取締役拡充や女性活用などの体制整備が求められます。 順守できなければ理由を説明しなければなりません。 すでに企業側には、指針導入に向けた動きが出ています。 経営効率を表す ROE (自己資本利益率)が低水準にとどまっていた半導体商社リョーサンは、ROE 改善を柱とする経営計画と同時に、社外取締役の増員を発表。 高島屋とエイチ・ツー・オーリテイリングは、提携を深めつつ持ち合い株を減らす決断をしました。 (asahi = 4-18-15)
「時給 1,500 円!」 ファストフード店員が賃上げ要求
「時給 1,500 円を常識に!」 ハンバーガーなどファストフード店のパート・アルバイトの賃上げを求めて、働き手や支援者が 15 日、東京・渋谷の渋谷センター街をねり歩いた。
労働組合の首都圏青年ユニオンなどがつくる「ファストフード世界同時アクション・東京実行委員会」が主催。 約 50 人が参加した。 世界 30 カ国以上で同様のイベントが呼びかけられているという。 参加した牛丼チェーンのパート、神奈川県の 30 代男性は時給約 1 千円。 シフトの多い月でも収入は 15 万円ほどで貯金はゼロという。 「まともな生活を送るには時給 1,500 円が必要だ」と話した。 (asahi = 4-15-15)
都心は場所なくて … 公園内に保育園 自治体「窮余の策」
待機児童が全国で最も多い東京都心で、都市公園内に保育園をつくるケースが相次いでいる。 各自治体は「待機児童解消のための窮余の策」とするが、住民からは反発も出ている。 違法との指摘があり、国は公園内に保育園をつくれるようにする国家戦略特区改正案を閣議決定し、追認する方針だ。
「せんせい、まってー。」 東京都の認可を受けた世田谷区野毛 1 丁目のナオミ保育園の分園「りんごの木」。 園舎の前で園児と保育士が追いかけっこをしていた。 よくある保育園の光景だが、遊んでいるところは公園だ。 同園は社会福祉法人が経営。 分園は 2011 年、区立の都市公園・玉川野毛町公園の一角に建てられた。 専用の園庭はなく、外遊びは公園を利用する。 公園には古墳があり、隣の等々力渓谷を含めて緑が多い。
山口節子副園長は「園庭のある保育園より広々と遊べ、保護者の評判がいい。 都内でも敷地に余裕がある公園はあるので、このやり方が進めば待機児童解消につながると思う。」と話す。 同区の待機児童数は 14 年 10 月時点で 1,049 人と全国最多。 前年同期より 217 人増えた。 保育サービスの総定員は 14 年度中に 1,301 人増やしたが、希望者の増加に施設整備が追いつかない状況だ。 (重政紀元、高橋友佳理、asahi = 4-14-15)
◇ ◇ ◇
保育園まだ入れない 新制度始まる、不安な「3 歳の壁」
子育て環境の充実をはかる「子ども・子育て支援新制度」が 1 日、スタート。 待機児童解消のため、受け入れ先を増やすことが柱の一つ。 ただ、認可保育への申し込み数は増加し続けており、入れなかった親たちの異議申し立てが、東京では今年も相次いでいます。 「保育園に入るのは難しいと聞いていたので不安だったけれど、預け先が決まって安心しました。」
昨年 4 月時点の待機児童数が、全国の市区町村で 4 番目に多かった東京都板橋区。 4 月にオープンする認可の小規模保育所「ウィズブック保育園志村坂上(定員 19 人)」に長男の入園が決まった契約社員西澤千恵さん (35) は、ほっと胸をなで下ろした。
■ 「小規模」に補助
板橋区は昨年 4 月以降、2015 年度中に受け入れ可能な認可保育の定員を 689 人増やした。 うち 130 人分が小規模保育所の整備による。 ウィズブック保育園を運営する株式会社アイ・エス・シー(東京都)は今春、都内と名古屋市で計6カ所の小規模保育所をスタート。酒向俊彰専務は「新制度の補助がなければ、これだけの数をつくるのは不可能だった。」
原則 0 - 2 歳児を受け入れる小規模保育所(定員 6 - 19 人)は、新制度で新たに市区町村の認可事業になった。 これまでは「認可外」とされてきたが、基準を満たせば国などの補助金を受けられる。 保育ママなど自宅で子どもを預かる「家庭的保育」や、企業内保育所なども認可の対象に。 待機児童の 8 割を占める 0 - 2 歳児の受け入れ先を増やすためだ。 (田中陽子、伊藤舞虹、asahi = 4-2-15)
◇ ◇ ◇
子供の声を騒音対象から除外 都の改正環境確保条例施行
子供の声を騒音の数値規制の対象から除外した東京都の改正環境確保条例が 1 日、施行された。 都内は保育所の定員超過などで入れない「待機児童」が多く、都は条例改正で、保育所を建設しやすい環境づくりを図る。
改正条例では、保育所や幼稚園、公園での子供の声や足音、拍手などを騒音の数値規制の対象外とする。 その上で、音の種類や頻度、防音対策、関係者同士による話し合いの内容から周辺住民への影響を判断し、必要があれば施設側に措置を取るよう勧告・命令できるとした。 これまでは地域や時間ごとの音量の基準があり、従来は子供の声も対象に含まれていた。 都内を含む各地で保育所を展開する日本保育サービスの荻田和宏社長は「より多くの子供たちが伸び伸びと遊べるようになるという意味でプラスだ」と話している。 (sankei = 4-1-15)
前 報 (10-10-14)
厚労省 : 介護福祉士や保育士の資格を統合
◇ 一本化検討入り 福祉人材の確保に向けて
厚生労働省は少子高齢化と人口減で人手不足が懸念されている福祉人材の確保に向け、介護福祉士や保育士などの資格を一本化する検討に入った。 戦後ベビーブームの「団塊の世代」が全員 75 歳以上になる 2025 年以降を見据えた動きで、介護施設と保育施設などを一つにまとめて運営できるようにすることも考えている。 近く省内に検討チームを発足させ、利点や課題を整理する。
厚労省の推計によると、25 年に必要とされる介護職員の数は約 248 万人で、このままでは約 33 万人不足し、保育士も 17 年度末には約 7 万人足りなくなる。 人口減が進む 40 年には、地方の過疎化が一層深刻化する見通しで、厚労省は介護施設や児童福祉施設などがバラバラに点在している現状では、人手不足で存続できない施設が続出する可能性があるとみている。
ただ、保育士の場合、今後の少子化で大幅に人員を増やせば将来過剰となる。 このため、厚労省は介護施設、保育施設、障害者施設を 1 カ所にまとめられるよう規制を緩和したうえで、介護福祉士や保育士など専門職種で分かれている資格を統合し、1 人の職員が子育てから介護サービスまで提供できるようにする仕組みを検討することにした。
参考にするのが、フィンランドが導入している医療と社会福祉サービスの共通基礎資格(ラヒホイタヤ)だ。 ホームヘルパーや准看護婦、保育士、リハビリ助手など計 10 の中学校卒業レベルの資格を一本化した資格で、福祉や介護に従事する職員を確保する必要性から生まれた。 1 人で複数の分野を掛け持ちできる職員を福祉の現場に配置し、柔軟に対応できるようにしているという。
この資格を持っていると、子育てから介護まで幅広い分野で働くことができ、求人も多いため、生涯仕事を続けることができるという。 厚労省は同様の仕組みを日本で導入すれば、雇用対策にもつながるとみている。 問題になるのは、乳幼児の世話と認知症患者も含めた高齢者のケアでは、求められる技術や知識が大きく異なる点だ。すべて1人でこなすには高い能力が求められ、資格の一本化には、人材をどう育成し確保するかという課題が横たわる。 介護、福祉の現場からは、資格統合に対する反発もあり、同省は時間をかけて検討することにしている。 (中島和哉、mainichi = 4-11-15)