�u������эZ�v�������₷���@�V�������̐��x�Ɉʒu�Â�
9 �N�Ԃ����ʂ����J���L�������Ŋw�ԁu������эZ�v���A�V�������̊w�Z���x�Ƃ��Ĉʒu�Â����邱�Ƃ����܂����B�@��������R�c� 22 ���A���\�������̂ŁA����A�s�����Ȃǂ̋���ψ���A��ы�������₷���Ȃ�Ƃ����B
������эZ�́A���w�Z�ŕs�o�Z�Ȃǂ���������u���P�M���b�v�v�����Ȃǂ̂��߂Ɏs�������ς��P�T�N�قǑO����n�߁A���݂͑S���ɂP�P�R�O�Z����B�����A���x��͕ʁX�̏����w�Z�̂��߁A������������B�Ⴆ�A�w�ԓ��e�������Ԃœ���ւ�����A�p��Ȃǂ̏������ʂ̋��Ȃ��������肷��ɂ́A���������Z�⌤���Z�Ɏw�肳��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B
���\�ł́A2 ��ނ̏�����эZ�����邱�ƂƂ����B�@�Z���� 1 �l�ŁA�����{�ݓ��ɒu���̂���{�́u������ы���w�Z�i���́j�v�ƁA�{�݂�Z���������ʁX�ɂ���u������ь^���E���w�Z�i���́j�v�B�@�������Ȃ��I�������܂߁A�e���ς�����ɉ����Ĕ��f����B (���l�s�l�Aasahi = 12-23-14)
�Ꮚ���Ҍ������t���A6 ��~�lj��x���ց@���{�����ő�
4 ���̏���łɂ��Ꮚ���҂̕��S�����炰�邽�߂ɓ������ꂽ�u�Վ��������t���v�ɂ��āA���{�͗��N�x�ɒlj��� 1 ��x��������j�����߂��B�@���N�H�̐ŗ� 10% �ւ̍Ĉ����グ����������A�y���ŗ�������������ꂽ���߂��B�@�x���z�́A���N�x�� 1 �l 1 ���~��菭�Ȃ� 6 ��~�ƂȂ錩�ʂ����B�@�^�}�ƍŏI�������Č��߂�B
���̋��t���́A����ŗ��� 5% ���� 10% �ɏグ��@���Œ�߂�ꂽ�B�@�x���Ώۂ͌����A�s�������Łi�ϓ����j����ېł̐l�ŁA2 �疜�l�K�͂ɏ��B�@����ł͐H���Ȃǂ̐����K���i�ɂ�������A�������Ⴂ�l�قǕ��S�����傫���B�@���t���́A�y���ŗ��Ȃǂ̒Ꮚ���ґ������܂ł̕��S�ɘa��Ƃ̈ʒu�Â����B�@8% �ւ̐ŗ������グ�ɔ����A4 �����痈�N 9 ���܂ł� 1 �N�����Ƃ��āA���� 1 �l������ 1 ���~�� 1 ��z�邱�Ƃ����܂����B�@�x���z�͑��łɂ��H���i�ւ̎x�o�����������Z���Č��߂��B�@�\�Z�z�͖� 3 �牭�~�B�@�����̎����̂��Ĉȍ~�Ɏx�����n�߂Ă���B (�������O�Y�A�D�c���g�Aasahi = 12-20-14)
�J���g���g�D�� 17.5%�@6 �������_�A�ߋ��Œ���X�V
�S���̘J���g���̐���g�D���i�ٗp�J���҂ɐ�߂�g�����̊����j�����N 6 �������_�� 17.5% �ƂȂ�A�ߋ��Œ���X�V�������Ƃ� 17 ���A�����J���Ȃ̒����ł킩�����B�@�O�N�����Ɣ�ׂ� 0.2 �|�C���g�������āA4 �N�A���Œቺ�����B�@�J���g���������� 2 �� 6 ��l (0.3%) ���� 984 �� 9 ��l�������B (nikkei = 12-17-14)
������s�̎Љ�I�ӔC�A�ō��� 29 �_�@NGO �̓_
���{�� 5 ���s�O���[�v���A�Љ�I�ӔC��������ƍl���ē�����Z�������Ă��邩�A�������ʂ����\����T�C�g�� NGO ���������B�@���ۊ�� 13 �̃e�[�}�ׂ��Ƃ���A���_ 130 �_�ɑ��A�ō��ł��݂��ق� 29 �_�ƌ������]���ɂƂǂ܂����B
�T�C�g�̓t�F�A�E�t�@�C�i���X�E�K�C�h�E�W���p���ihttp://fairfinance.jp�j�B�@�a���҂Ⓤ���Ƃ��A��s�O���[�v���Љ�I�ӔC���ʂ����������r�ł���悤�ɂ��A���̕���ł̋����𑣂��_�����B�@13 �̃e�[�}�́u�C��ϓ��ɔz�����铊�Z�����I��ł��邩�v�A�u��K�͂ȃv���W�F�N�g�ŗZ���������J���Ă��邩�v�ȂǂŁA�v 228 ���ڂׂ��B�@�O�H UFJ �Ƃ݂��فA�O��Z�F�́u�Z����̏]�ƈ��̘J�����ɔz�����Ă��邩�v�Ƃ������ڂ� 5 �_�������B (���c���V�Aasahi = 12-10-14)
0 - 12 �ΑΏہA�S�ݓX�ŋ���̌��T�[�r�X�@�ɐ��O�V�h
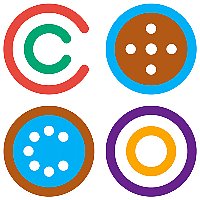
�ɐ��O�V�h�{�X�i�����s�V�h��j���A���N 4 ������ 0 - 12 ��Ώۂɂ�������̌��T�[�r�X�ucocoiku �i�R�R�C�N�j�v���n�߂�B�@�~���[�W�V�����⌚�z�ƁA�f��ē�ɂ��̌��v���O���������{���āA�\���͂�n���͂�g�ɂ��邱�Ƃ�_���ɂ���B�@�ꕔ�̍u���͐e���Q���ł���B�@3 �J���ԂɁA1 ���Ԓ��x�̍u����S 10 ��J���A��u���� 6 �� - 7 ���~�̗\��B (asahi = 12-5-14)
"�����ی����"�A5 �J���A���ʼnߋ��ő��X�V - 10 ���A����Ґ��т�����
�����J���Ȃ� 3 ���A2014 �N 9 �����̔�ی�Ғ����̌��ʂ\�����B�@����ɂ��ƁA9 �����_�̐����ی���т͑O���� 2,123 ���ё��� 161 �� 1,953 ���тƂȂ�A5 �J���A���ʼnߋ��ő����X�V�����B�@�����ی�Ґ��͑O���� 1,757 �l���� 216 �� 4,909 �l�ƁA2 �J���Ԃ�ɑ��������B
���ѕʂɌ���ƁA����Ґ��сi�j���Ƃ� 65 �Έȏ�̐��сA�܂��͂����� 18 �Ζ����̖����҂�����������сj���S�̖̂� 47% �ɓ����� 75 �� 9,114 ���сi�O�� 75 �� 7,118 ����)�Ńg�b�v�B�@�ȉ��A�����鐢�т��܂ނ��̑��̐��т� 28 �� 387 ����(�� 28 �� 981 ����)�A���a�Ґ��т� 26 �� 8,969 ���сi��26�� 9,138 ���сj�A��Q�Ґ��т� 18 �� 6,355 ���сi�� 18 �� 5,844 ���сj�A��q���т� 10 �� 8,507 ���сi�� 10 �� 8,299 ���сj�Ƒ������B (��ؖ{��t�AMyNavi = 12-3-14)
�A���O�A�C���^�[�����M�@��А�����̉��� 3 �J�����
�����Ȃ�A�E�������X�^�[�g���� 12 �������A���N�̏A������͂�����ƈႤ�B�@���̑�w 3 �N������A��А�����̉��ւ����N 3 ���ɂȂ����B�@�Ƃ͂����A���ǂ��l�ނ��~������ƁB�@���������������Ĉ��S�������w���B�@���ƂȂ������ւ�҂Ă�̂�?�@11 �� 29 ���A�s���Ŋ�� 55 �Ђɂ��C���^�[���V�b�v�̍���������������B�@�� 1,500 �l�̊w���������Ɏ����X���Ă����B
�u����B�Ƃ肠���������Ȃ���B�@�����A���͎n�܂��Ă���B�v�@���N���[�g�X�[�c�p�ŎQ�����������w�@�� 3 �N�̏��q�w�� (21) �� 11 ���ɓ����Ă����v�����B�@�F�l�������W�ߎn�߂����炾�B�@���{��������̗v�]���A�o�c�A�͏A�E�����̉��ւ� 3 �J���x�点��w�j�����߂��B�@�w������ɏW�������邽�߂��B�@��Ƃ���А�������J����̂� 3 ���ȍ~�����A�C���^�[���V�b�v�͂ł���B�@���̏��q�w���́u�C���^�[�����������邩��A�����Ԃɂ͏[�Ă��Ȃ��v�Ƙb���B (�����b�q�A����B�A ���l�s�l�Aasahi = 12-1-14)
�w���ۈ� 8.3 ���l���s���@17 �N�x�A���J�ȂȂǐ��v
�ҋ@���������̂��߂̎{�ݐ����͂�����Ɛi�ނ̂��A���O�����܂钲�����ʂ� 28 ���̐��{�̎q�ǂ��E�q��ĉ�c�Ŏ����ꂽ�B�@2017 �N�x�� 0 - 2 �Ύ������̕ۈ�{�݂��� 4 �� 6 ��l���s�����A���w�������̊w���ۈ�i���ی㎙���N���u�j���� 8 �� 3 ��l������Ȃ��Ƃ̓��e���B�@�����͗��N 4 ������n�܂�\��́u�q�ǂ��E�q��Ďx���V���x�v�ɍ��킹�A�����̂̐����v���Z���A���P�[�g�Ȃǂ���A�����J���ȂȂǂ����v�����B
0 - 2 �Ύ������̕ۈ�{�݂́A17 �N�x�Ŗ� 116 ���l���̎��v�������܂ꂽ���A�m�ۂł���͖̂� 111 �� 4 ��l���ɂƂǂ܂����B�@19 �N�x���� 1 �� 1 ��l���̕s���ƂȂ����B�@�m�ۗ\�萔�ɂ͔F�ۈ珊�ɉ����A�����s�̔F�ؕۈ珊�Ȃǎ����̂��Ǝ��ɕ⏕���o���u�F�O�v���܂܂��B�@���{������ 17 �N�x�܂ł� 5 �N�Ԃ� 40 ���l���̎����m�ۂ�ڎw���u�ҋ@���������������v�����v��i�߂Ă���B�@�������J�Ȃ̒S���҂́u���ۂ̕ۈ珊�����́A�s�����̎��ƌv��̑z����������i��ł���v�Ƃ��A�ҋ@���������͉\���Ɛ������Ă���B (���R�֎q�Aasahi = 11-29-14)
���@���@��
�w���ۈ�̑ҋ@���� 9,945 �l�@3 �N�A���ő�
�������ƒ�Ȃǂ̏��w�������ی���߂����w���ۈ�i���ی㎙���N���u�j�� 5 �� 1 �����_�̑ҋ@�����́A9,945 �l�����B�@�O�N��� 1,256 �l (14%) �����A3 �N�A���ő������B�@�����J���Ȃ� 7 ���A���\�����B�@�w���ۈ�̐��� 2 �� 2,084 �J���őO�N��� 602 �J�� (3%) �������B�@���p���������O�N��� 4 �� 7,247 �l (5%) ���� 93 �� 6,452 �l�ŁA�Ƃ��ɉߋ��ō��ƂȂ������A��������v�Ɏ��ꂪ�ǂ����Ă��Ȃ��B�@���{�����͎d���Ǝq��Ă̗����𐄐i���邽�߁A���N�x���� 5 �N�ԂŒ���� 30 ���l�����₵�A�ҋ@����������������j���B (���R�֎q�Aasahi = 11-7-14)
��Q�Ҍٗp�A11 �N�A�����@14 �N�A43.1 ���l�@�O�N�� 5.4% ��
2014 �N�Ɋ�Ƃœ�����Q�҂̐��͑O�N��� 5.4% ���̖� 43 �� 1 ��l�ŁA11 �N�A���ʼnߋ��ō����X�V�����B�@���_��Q�҂� 24.7% ���� 2 �� 7 ��l�ƂȂ�A�L�ї����傫�������B�@���ς̌ٗp���͑O�N�� 0.06 �|�C���g���� 1.82% �ŁA3 �N�A���ʼnߋ��ō����X�V�����B�@�����J���Ȃ��]�ƈ� 50 �l�ȏ�̊�� 8 �� 6,648 �Ђ�Ώۂ� 6 �� 1 �����݂ŏW�v���A���� 26 ���ɔ��\�����B�@�g�̏�Q�҂� 3.1% ���� 31 �� 3 ��l�A�m�I��Q�҂� 8.8% ���� 9 ���l�������B�@����܂ł��g�̂�m�I��Q�҂��ق������͐i��ł������A18 �N����͐��_��Q�҂��ٗp���̎Z��Ɋ܂܂�邽�߁A���肵�Čق���Ƃ������Ă���B
��Q�Ҍٗp���i�@�́A��Ƃɏ]�ƈ��� 2% �ȏ�͏�Q�҂��ق��悤�A�`���Â��Ă���B�@�����B��������Ƃ� 44.7% �i3 �� 8,760 �Ёj�ŁA�O�N��� 2 �|�C���g�オ�����B�@�]�ƈ� 1 ��l�ȏ�̊�� 3,122 �Ђ̕��όٗp���� 2.05% �ƂȂ�A���߂� 2.0% ���������B�@�����J���ȏ�Q�Ҍٗp��ۂ̒S���҂́u��Q�҂��������Ƃɂ��āA��Ƃ̗������[�܂��Ă���B�@���_��Q�҂����Ƃ𒆐S�Ɍق��������łĂ���B�v�Ƙb���B�i����B�Aasahi = 11-26-14)
�����Ǘ��E�u�܂�����ĂȂ��v�@��v 100 �В� 36 ��
���{�����́u2020 �N�܂łɏ����Ǘ��E�� 3 ���ɂ���v�Ƃ̖ڕW���f���邪�A�����o�p��i�߂悤�Ƃ����Ƃ̔Y�݂͏��Ȃ��Ȃ��B�@��v��� 100 �Ђւ̌i�C�A���P�[�g�ʼnۑ���ŕ����ƁA�u�Ǘ��E�ɓK���Ȑl�ނ�����Ă��Ȃ��v�� 36 �Ђōł����������B
�������̐��q�Y�В��́u�ے��A�����ł͈���Ă��Ă��邪�A�䗦�͂܂����Ȃ��v�A�A�T�q�O���[�v�z�[���f�B���O�X (HD) �̐�J���؎В��́u�������̏����̐���ꐔ�Ƃ��đ��₳�Ȃ��Ƃ����Ȃ��v�ƌ��B�@���Ă͏����̗̍p�����Ȃ��A������₪�܂�����Ă��Ȃ����ʂ̔Y�݂�����悤���B�@�u�j���Ј��̈ӎ����v���i��ł��Ȃ��v���A33 �Ђ������B�@ANA HD �̒����L�V��Ȏ��s�����́u�ꕔ�̑g�D��������ŁA�d�v�Ȕ��f������d���������ɔC����̂�����邱�Ƃ�����v�Ƙb���B�@�Ǘ��E�Z�~�i�[�Ȃǂł́u�@������������ɗ^���ĕ]�����ׂ����v�Ɠ`���Ă���Ƃ����B (asahi = 11-24-14)
���@���@��
�j�������A���{ 104 �ʁ@�c���E��Ɗ����A�Ⴂ�����䗦

���E�o�σt�H�[�����iWEF�A�{���E�W���l�[�u�j�� 28 ���A�e���̒j���i���i�W�F���_�[�M���b�v�j�̏��Ȃ����w�������A�����L���O�Ŏ��������� 2014 �N�ł\�����B�@���E 142 �J���̂������{�� 104 �ʁB�@�O�N�������ʂ��グ�����̂̈ˑR�Ƃ��Ēᐅ���ŁA��v 7 �J�� (G7) ���ʼn��ʂ������B
WEF �́A���E�̐����E�l���W�܂�u�_�{�X��c�v����Â��邱�ƂŒm���Ă���B�@�����L���O�́u�E��ւ̐i�o�v�A�u����v�A�u���N�x�����v�A�u�����ւ̎Q���v�� 4 ����Œj���i���̏��Ȃ����w�������A���̕��ϓ_�ő������ʂ����߂�B�@�e���삲�ƂɁA2 - 5 �̗v�f�ׂ�d�g�݂��B�@���{�́u�����ւ̎Q���v�� 129 �ʁA�u�E��ւ̐i�o�v�� 102 �ʂ��������Ƃ����������������B (������Y = �W���l�[�u�A�����T�� �c�G�� = �p���A���э��a�Aasahi = 10-28-14)
���@���@��
�n�� 64 �s�Q���A�l�ރo���N�� = �u��������v����̉�
�����s���̊�����㉟�����悤�ƁA�����̒n����s�� 11 ���̔����Ɍ����ď�����i�߂Ă���u�P�������̊������������n�⓪��̉�i���́j�v�ɁA�S���̒n�� 64 �s���Q�����錩�ʂ��ƂȂ������Ƃ� 23 ���A���������B�@�z��҂̓]�őސE������Ȃ��s�����A�]����̕ʂ̒n��ɏЉ��l�ރo���N�̑n�݂���������������B
�n�⓪��̉�́A��t��s�i��t�s�j�A��z��s�i���ˎs�j�A���M��s�i�����s�j�A�݂��̂���s�i�X�s�j�� 4 �s�̓��悪���N�l�ƂȂ�A���̒n��ɎQ�����Ăъ|���Ă����B�@�S���n����s����ɉ������� 64 �s�S�Ă̎Q�����ł܂������ƂŁA�����̊����o�p��A�d���Ǝq��Ă̗����x���Ȃǂ��߂���S�����x���ŘA�g���i�݂������B (jiji = 10-23-14)
���@���@��
�u�����o�p��Ƃɏ����v�@10 ���߂ǂɐ���܂Ƃ�
���{�W�O�� 12 ���A��Ƃ̏����o�p�ւ̐V���ȏ������x�ȂǁA�����̊���𑣂������ 10 �����߂ǂɂ܂Ƃ߂���j��\�������B�@�s���ŊJ���ꂽ�u�������P���Љ�Ɍ��������ۃV���|�W�E���i���{�A�o�c�A�Ȃǎ�Áj�v�Ō�����B
�͍u���Łu�����̊���𐄐i�����Ƃɂ́A���{���B�ł̎@��̑����}��B�@�V���ɏ����o�p�Ɏ��g�ފ�Ƃɂ͏������s���v�Əq�ׂ��B�@�ҋ@���������ւ̎��g�݂�A�q��Ă���i�����Ă���N�Ƃ��鏗���ɑ���x���ɂ��͂�����l���������A�u10 ���Ɂw�S�Ă̏������P������p�b�P�[�W�x���Ƃ�܂Ƃ߂�v�Əq�ׂ��B�@�́A�V���|�W�E���̃��Z�v�V�����ŁA�����o�p�̗�Ƃ��āu���̓��t�������̊t���𑝂₵�����ʁA�x���������₷���Ƃ��ł����v�Ƃ��������A���̏���U�����B (asahi = 9-13-14)
���@���@��
���{�̍��w�������A3 ���A�J�����@OECD ���Œ�x��
���{�̍��w�������̖� 3 ���͏A�J���Ă��Ȃ����Ƃ� 9 ���A�o�ϋ��͊J���@�\ (OECD) �̋���Ɋւ��钲���ŕ��������B�@���{�����́u�����̊���v���f���Ă��邪�A���� 34 �J�����Œ�x���B�@OECD �̃A���h���A�E�V�����C�q���[����ǒ��́A�\�͂̍����������A�J���邽�߂ɂ́A3 �Ζ����̕ۈ���g�傷�邱�Ƃ��K�v���Ǝw�E����B
OECD �͖��N�A�������̋���V�X�e���ɂ��āA�����x�o�⋳����ʂׂĂ���B�@����́A2012 �N���݂̐������܂Ƃ߂��B�@���{�ł́A��w�ȏ�̊w�ʂ������w���̐��l�i25 - 64 �j�̊����� 26%�B�@34 �܂ł̎�N����� 35% �ŁAOECD ���� (30%) ���������B�@�����A�����̔\�͂́A�Љ�ŏ\����������Ă��Ȃ��B�@���w��j���� 92% ���A�J���Ă���̂ɑ��A�����̏A�J�� 69% �ɂƂǂ܂�AOECD ���� (80%) ����������B�@���w�������̏A�Ɨ����������ɂ́A�X�E�F�[�f����m���E�F�[�ȂǁA�q��Ďx�����[�����Ă���k�����ڗ��B (���������A�͌��c�T��Aasahi = 9-10-14)
���@���@��
���݉�͋��j�[�� 1 - 2 ���ԁ@�����Ǘ��E���A���Ă̍H�v
���邢���������������ދ��j���̗[�� 5 ���B�@�I�����_�E�A���X�e���_���̃o�[�̉��O�̐ȂŁA�d�����I��������̒j�� 8 �l�����C����r�[��������ł����B�@��Ə�������Ђ̓��������̈��݉�B�@�����C���̃O���X���X���Ă����^�}���E�t�F�A�X�^�C�l���� (38) �́A���w���� 2 �l�̎q�ǂ��������e���B�@�u�����̐l���������邵�A�E��ł̈ӎv�a�ʂ��~���ɂȂ�B�@�T�� 1 �炢�A�����ǂ����ł����l���Ă������Ԃ�������������Ȃ��B�v�@����������Ō𗬂�[�߂�u���i�m�j�~���j�P�[�V�����v�͓��{�Ɠ��l�Ƃ�����B
�����A�͂�����Ƃ����Ⴂ������B�@���݉�̎��Ԃ͋��j�̗[���ɂ������� 1 - 2 ���ԁB�@���݂����l�����āA�����̃^�C�~���O�ŋA��B�@�u�[�H�̎��Ԃɂ͉Ƃɖ߂�A�Ƒ��ƐH�ׂ�v�̂����ʔF���ɂȂ��Ă���B�@�����������݉�́u�{�����v�ƌĂ��B�@�����̏A�Ɨ����}���ɍ��߂�Ȃ��ŁA�ƒ�ƐE��𗼗������邽�߂Ɏ��R�ɂł����H�v���B (���э��a�A�������Aasahi = 9-8-14)
���@���@��
�u�ǂڂ���v�m���Ă�?�@�y�؏��q�A���𑊂Ɏʐ^�W PR
�y�؋ƊE�œ��������������u�y�؏��q�i�ǂڂ���j�v���� 34 �l�̎ʐ^��C���^�r���[���܂Ƃ߂��{�u�y�؏��q!�i�����Њ��j�v���A8 ���ɔ��������B�@�j�Љ�̃C���[�W�������y�؋ƊE�����A���q�w����ɋƊE�̖��͂��A�s�[�����ďA�E��ɑI��ł��炤�˂炢�ŁA�{�ɓo�ꂷ�� 4 �l�� 5 ���A���c���G���y��ʑ��ɖ{����n�����B
����ē����Ă��鎭���̑��㖃�D�q���� (30) �́u���̂Â���̊�т��傫���̂ŁA�����������₷�����ɂȂ�B�v�@���c���́u�����������āw�ǂڂ���x�̊�����������܂��v�Ɖ������B�@������œ��������͑S�̂� 3% �ɂ������ 10 ���l�B�@�����Ȃ� 8 ���A������œ��������̐��� 5 �N�ԂŔ{��������s���v����܂Ƃ߂Ă���B�i�R������Aasahi = 9-6-14)
��5 �� ��3 �Łu�p����Ɓv�@�����ܗւɌ����p��͋���
�����I�����s�b�N�̊J�Â����܂�A�p��͂̋�����ڎw���܂��B�@�������������Ȋw��b�́A�c�t�����獂�Z�܂ł̋�����e���߂�w�K�w���v�̂̑S�ʉ����𒆉�����R�c��Ɏ��₵�܂����B�@�p�ꋳ��̃X�^�[�g���A���݂̏��w�Z 5 �N������3�N���ɑO�|�����A�����I�����s�b�N���T���A���H�Ŏg����p��͂̈琬��ڕW�Ƃ��Ă��܂��B�@����ɁA�Љ�̃O���[�o�����̂Ȃ��ŁA�����̗��j����������Ɗw�ԕK�v������Ƃ��āA���Z�ł́u���{�j�v��K�C���ȂƂ��邱�ƂȂǂ����߂Ă��܂��B (TV Asahi = 11-20-14)
���u���Ƃŗ���x�A�b�v���@�S�������Z�����t����
�ʁX�̊w�Z�ōs������Ƃ��e���r��c�V�X�e���ȂǂŌ��ԁu���u���Ɓv��S�������Z�łł���悤�A���t�ɂ����̐��x���ς�錩�ʂ��ɂȂ����B�@���łɈꕔ�œ����i��ł���ʐM�����Z�ł́A���Ƃ̗���x���オ��Ȃǂ̐��ʂ��o�����A�ۑ���݂�ꂽ�B
����s�ɂ��钷�茧���ꍂ�Z�̒ʐM���́A2012 �N�x���牓�u���Ƃ�{�i���������B�@���k�� 800 �l�̂����A�����̖� 60 �l�����p���Ă���B�@�ʐM���͎���w�K�ɂ�郊�|�[�g��o���傾���A������͓o�Z���Ď��Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�ꍂ�͗����̍��Z���u���͍Z�v�Ƃ��ēo�Z��ɂ��Ă������A���͍Z�̋����̕��S�ɂȂ�Ƃ����w�E���������B (���l�s�l�Aasahi = 11-19-14)
�����܂�! �Z�N�n���A�}�^�n���@���k 1 �������u�X�R�̈�p�v
��Q�𖾂��J�ȁA���̖{�i����
�����J���Ȃ� 15 ���A�E��ł̃Z�N�n����A�D�P�E�o�Y�𗝗R�ɕs���Ȉ�������u�}�^�j�e�B�[�n���X�����g�i�}�^�n���j�v�ɂ��āA���̖{�i�����ɏ��o�����Ƃ����߂��B�@���ɔh����p�[�g�ȂǗ��ꂪ�ア�K�ٗp�̏����̔�Q���[���ɂȂ��Ă���Ƃ݂āA�ڂ������Ԃ����݁A�h�~��Â���ɖ𗧂Ă�B�@�e�n�̘J���ǂɕ��� 25 �N�x�Ɋ�ꂽ���k�́A�Z�N�n���֘A�� 6,183 ���A�}�^�n���֘A�� 3,371 ���B�@�����Q���肵�Ă���l�������Ƃ݂��A���J�Ȃ́u�X�R�̈�p�ł͂Ȃ����v�Ƃ݂āA��Q�ׂ�K�v������Ɣ��f�����B
�����͗��N�ɂ����{�\��B�@�������o��������l���܂߁A�Ώۂ�ׂɒ��o����B�@��Q�̋�̓I���e�ɉ����A(1) �ٗp�`�Ԃ���Q�҂̗���A(2) �Ζ���ɐ\���������ǂ����A(3) �Ζ���̑Ή� - �Ȃǂ����j�B�@�K�ٗp�ɂ��ẮA���ق�ق��~�߂ȂǕs���Ȉ������Ă��Ȃ������m�F���A���P���T��B (sankei = 11-16-14)
���@���@��
�}�^�n���A�����Q����̓C����!�@�A�g�����Q�҂���
���{�������u�������P���Љ�v���f���鑫���ŁA�E��ł͔D�P��o�Y�𗝗R�ɂ�����@�ȉ��ق�_��ł���Ȃǂ́u�}�^�j�e�B�[�E�n���X�����g�i�}�^�n���j�v���₦�Ȃ��B�@��Q�ɂ����������������Ȃ���A�����グ�n�߂��B
�� ��i�������u�l�̍Ȃ� �c�v
�_��Ј��Ƃ��ĎG���̕ҏW�����Ă������i�������ׁj���₩���� (37) = �_�ސ쌧 = �͔D�P���A��Ђ̏�i�ɂ���������ꂽ�B�@�u�_��Ј��͎��Z�Ζ����ł��Ȃ��B�@�ǂ����Ă��d���������Ȃ�A�A���o�C�g�ő����邵���Ȃ��B�v�@�u�l�͍Ȃ̔D�P�����������Ƃ��A�����Ɏd�������߂������B�@�N�̒U�߂���͉����l���Ă���̂��B�v�@�ؔ����Y�� 1 �T�ԋx�Ƃ��A��i�͎���ɗ��āA�_��X�V��������߂�悤�ɔ������B�@�u���_�I�ɂ��s����Ȃ̂Ɏd�����D�P���I���𔗂�ꂽ�B�@���������B�v�Ƃӂ�Ԃ�B
���̌�A���Y�����B�@���N�O�ɑ����� 2 �x�ڂ������B�@�u���ɔD�P�����������܂ŋx�܂��Ăق����v�Ɠ`����ƁA�l�������Ɂu�d���ɖ߂�Ȃ�A�D�P�� 9 ��������߂�v�ƌ���ꂽ�B�@�ސE����������Ȃ������B�@�j���ٗp�@��ϓ��@�ł́A�D�P���̏����ɑ��A��Ђ͎��Z�Ζ��⎞���ʋȂǂŔz�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�@�D�P�𗝗R�ɂ������ق�_��ł���A�~�i�Ȃǂ̕s���v�Ȏ�舵�����ւ���B (���э��a�A�ҏW�ψ��E��H�B�F�Aasahi = 10-5-14)
����Ƃ̓~�{�[�i�X 5.78% ���@�ߋ��ō������ɔ���
�o�c�A�� 13 �����\��������Ƃ̓~�̃{�[�i�X�����i�� 1 ��W�v�j�ɂ��ƁA�Ì��z�͕��� 89 �� 3,638 �~�őO�N�~��� 5.78% �������B�@�O�N������̂� 2 �N�A���ŁA���z�͍ő������� 2008 �N�i90 �� 4,885 �~�j�ɔ���B�@20 �Ǝ�A240 �Ёi�����Ƃ��ē��� 1 �����A�]�ƈ� 500 �l�ȏ�j���ΏۂŁA����͎����Ԃ�d�@�Ȃ� 10 �Ǝ� 76 �Ёi���������� 74 �Ёj���B�@10 �Ǝ킷�ׂĂőO�N�������Ă���A�L�ї��� 2 �N�A���� 5% �����B�@�~���ȂǂŋƐт����P���Ă���ق��A�����I�ȃR�X�g���ɂȂ�x�[�X�A�b�v�i�x�A�j���{�[�i�X�ŊҌ����悤�Ƃ���X�����w�i�ɂ���B (asahi = 11-13-14)
�u�v�w�T���v�Ȃ� 5 �ā@�z��ҍT���������Ő��{�Œ�
�����Ɏ�w���т̐ŕ��S���y�����Ă���u�z��ҍT���v�̌��������߂���A���{�Ő�������i�̎���@�ցA��������j�� 7 ���A�����_�ł̑I�������܂Ƃ߂��B�@�V���ȁu�v�w�T���v�ւ̐�ւ��Ȃ� 5 �Ă������A���ꂼ��ۑ���f���āu���J�ȍ����I�c�_���K�v�v�Ƃ����B
�z��ҍT���́A�Ⴆ�Ȃ̔N���� 103 ���~�ȉ��Ȃ�A�v�̎������� 38 ���~�����������ď����ł��v�Z���A�ŕ��S���y������d�g�݂��B�@�Ȃ̔N���� 103 ���~����ƍ���������z���i�K�I�Ɍ���ق��A���̐��x���Q�l�Ɋ�Ƃ��z��Ҏ蓖�̎x��������߂�Ȃǂ��Ă��邱�Ƃ���A��������������}���Ă��܂��u103 ���~�̕ǁv�ɂȂ��Ă���Ƃ̎w�E������A���������c�_����Ă����B
���̓��̉�ł́A�Ő����ӎ������ɓ�������I�ׂ鐧�x�Ƃ��āA�@ �z��ҍT���̔p�~�A�A ���������̓����A�B �z��҂̎����Ɋւ�炸�v�w�̏����T���i�ېŏ����̌��z�j�g�����ɂ���A�C �v�w�̐Ŋz�T���i�[�Ŋz�̌��z�j�g�����ɂ���A�D �V���ȁu�v�w�T���v�ւ̓]���A�� 5 �Ă��������B (�g��[��Y�Aasahi = 11-8-14)
������эZ�A�������x���ց@2016 �N�x�ɂ��J�Z
�����Ȋw���̎���@�ցu��������R�c��v�� 31 ���A������ы���ɂ��Ă̋c�_���Ƃ�܂Ƃ߂��B�@�w�N�̋������R�ɐݒ�ł���u������ы���w�Z�i���́j�v�ƁA�ʁX�̏��w�Z�ƒ��w�Z�����ꂵ���J���L�������Ŋw�ԁu������ь^���E���w�Z�i���́j�v�𐧓x������B�@��������s�撬������ψ���̔��f�Őݒu�ł���悤�ɂ���B
���ȏȂ͂�����A�w�Z����@�Ȃǂ̉����Ă𗈔N�̒ʏ퍑��ɒ�o����B�@�ő��� 2016 �N�x�̊J�Z���߂����B�@�P���^�́u6�E3�v�����������̋`�����炪�傫���]������B�@�@������эZ�͂���܂ŁA�����s�i���ȂNJe�n�̎s�撬���Ȃǂ��Ǝ��� 1,130 �Z��ݒu���Ă����B�@�����߂�s�o�Z�Ƃ��������s������ 1 �Ō�������u�� 1 �M���b�v�v�̉����ɐ��ʂ��������ƕ]�����鐺���������A���x��A�ʁX�̊w�Z�̂��߁A�������o���o���ɔz�u���ꂽ��A������Ȃ��Ɗw�K���e���O�|���ł��Ȃ�������Ƃ������ۑ肪�w�E����Ă����B (���l�s�l�Aasahi = 11-1-14)
�u�����̗F���v���i = �]�ƈ���A�c�Ƒ㖢������ - ���n��
�����Ԃ̎��ԊO�J�����������Ȃ���A�c�Ƒオ�x�����Ȃ������Ƃ��āA���G�X�e�T�����u�����̗F���r���[�e�B�N���j�b�N�v���X�̏]�ƈ��ƌ��]�ƈ��� 2 �l�� 29 ���A���T�����̉^�c��Ёu�s��r���[�e�B�v�ɑ��āA�������̒����v�� 1,015 ���~�����߂�i�ׂ���n�قɋN�������B�@�����́A���X�ŃG�X�e�e�B�V�����Ƃ��ċΖ����� 20 ��̏����]�ƈ��ƁA30 ��̏������]�ƈ��B
�i��Ȃǂɂ��ƁA2 �l�͎n�Ǝ��ԑO�ɓ�������A�^�C���J�[�h�ɏI�Ǝ����Ƃ��đō���������Ɩ����s�����肷��Ȃnj��� 80 ���ԑO��̎c�Ƃ�������ꂽ���A���ԊO���������͎x�����Ȃ������Ƃ����B�@�����̗F���r���[�e�B�N���j�b�N���X���߂����ẮA�G�X�e�e�B�V������̎c�Ƒ������Ɍ��z�����ȂǂƂ��āA���J����ē��� 8 ���ɐ����������s���Ă����B
�L�҉�������]�ƈ��̏����́u���q���܂̂��߂Ɉꐶ�������������A�{���ɘJ�����Ԃ������A�g���S���ڂ�ڂ낾�����B�@��Ђ͎������𗘉v���グ�铹��Ƃ����v���Ă��Ȃ��āA�c�O�B�v�Əq�ׂ��B�@�s��r���[�e�B�̘b : �i�͂��Ă��Ȃ��̂ŏڍׂ͓������Ȃ����A����܂Ő��Ǝw���̉��A�c�Ƒ�ɂ��Ē��Ă����B�@�������Ȃ��܂ܒ�i�Ɏ��������Ƃ͎c�O�B (jiji = 10-29-14)
���@���@��
�G�X�e�ƊE�̌���́@�m���}�� 700 ���~�A�����w����
�ꌩ�₩�ɂ݂���G�X�e�ƊE�ŁA�����Ă��鏗����������u�����v���������ł���B�@�����ԘJ����c�Ƒ㖢�����A�p���n���Ƃ��������������E��ɋ��ʂ���̂́A��������グ�ڕW�̑��݂��B�@�m���}�B���̈��͂̂Ȃ��ŁA���z�́u�����c�Ɓv��������Ȃ��l������B
�� �����Ԃ��Ƃɔ���z����o��
�����u�����v�ɒǂ��Ă����B�@�ŋ߂܂ŁA�u�����̗F���r���[�e�B�N���j�b�N�v�œ����Ă��� 20 �㏗���́A���������ɂȂ�ƁA���̍��̏ő������v���o���B�@�{�p�̉��Ȃǂ�_��Ɩ���S�����A�q�̔���̂̑��k�ɂ̂�A��b���ϕi��h�{�܂�̔������B�@�u�Ƃɂ��������v�̌���ŁA�� 700 ���~�̃m���}���ۂ��ꂽ���Ƃ�����B�@�����̍ŏI���ɂ́A�����Ԃ��Ƃɔ���z���X�V���������x�e���ɓ\����B�@�X������i�ɓd�b�œ{���A�������Ƃ��������B
�m���}�B���̂��߁A���肰�Ȃ��q�ɔ��荞�B�@�{�p�̏I������q�Ɂu���������̂��ق����Ă������ł���?�v�Ǝ��������A�}�b�T�[�W��̂悤�ȓ���łق����B�@�u����A�Ȃ�?�v�Ƌq���S����������A�u����Ŏg���ƌ��ʂ�������ł���v�Ǝ�n���B�@�l�i�́A�������܂Ō���Ȃ��B�@����グ�ڕW�ɓ͂��Ȃ����Ƃ����������B�@��i��������Ɓu���́v�����Ȃ������B�@�����͒f�肫�ꂸ�A25 ���~�̔�����}�b�T�[�W���A�h�{�܂�p�b�N�Ȃǂ������ōw�������B
�В����肪����W���G���[�̔̔�����������B�@����s���������Ɓu���Ȃ������Ă����Łv�ƓX���B�@�u��������ˁv�ƍw�������߂��A�_�C���� 30 ���~�̎w�ւ� 13 ���~�̃l�b�N���X�Ȃǂ��Ј����i�Ŕ������B�@���^�͋ƐтƘA�����A�����Ƃ��Ŋz�ʌ� 25 ���~�قǁB�@�ƒ��̂Ȃ����Z�܂��Łu�����͏\���v�Ɗ����Ă������A�����w���͑������� 20 ���~�ɂ̂ڂ����B
�L���x�ɂ����R�Ɏ�ꂸ�A���ʂĂđގЂ����B�@���܂� IT �̌P���������Ȃ���d����T���B�@���������Ŕ������W���G���[�̎x�����͌� 3 ���~�B�@�܂� 1 �N�ȏ�A�c���Ă���B�@���T�������o�c����u�s��r���[�e�B�v�̑㗝�l�́u����グ�ڕW�͓X�܂ɂ͂��邪�A�l�ɂ͉ۂ��Ă��Ȃ��B�@�����w���͂��邩������Ȃ����A��ЂƂ��Ďw�������������Ă��Ȃ��v�Ƙb���Ă���B
�� �u���|�S�Ŏd���v
�z�e���ɃG�X�e�e�B�V������h�����Ă������s�̃G�X�e��Ђœ����Ă��� 20 �㏗���́A�� 50 �� - 60 ���~�̃m���}���ۂ����Ă����B�@�B������� 1 ���~�̎蓖���ł邪�A�u�����苰�|�S�Ŏd�������Ă����B�v�@�z�e���̏h���q�����Ȃ������́A����グ�[���̂��Ƃ��B�@�����̒���ŁA����グ���ł����Ȃ��]�ƈ����В����猵�������ӂ���A�����o���l�������B�@���킭�āA�{�p�������Ƃɂ��āA1 �� 3 ��~�قǎ����ŕ������Ƃ����x���������B�@�� 11 ���߂��̕X���O�ɂ��\������A�[�� 1 ���܂œ��������Ƃ��������B
���БO�ɖ���Ă����Љ�ی���ܗ^�A�����͂Ȃ��B�@�В��͌ٗp�����������̕s���̗e�^�ō�N�ߕ߂��ꂽ�B�@�����͌������ƁA��ЂɎc�Ƒ�x�����Ȃǂ����߂Ē�i�����B
��錧���̃G�X�e��Ђō��N 6 �����瓭���o�������� (44) �͓����߂��ő̒�������A1 �J�����őސE�����B�@�� 9 ������� 10 ���܂ł̋Ζ��ŁA�T 2 ��A�Ζ���ɐ[�� 0 ���܂ł̗��K���������B�@�c�Ƒ�͂Ȃ������B�@�{�p�̑O��ɂ͎В���ɓd�b�Ŏw�������ł����B�@�u�{�p�̓x�ɐ������グ�邽�߂̃`�F�b�N������̂́A�X�g���X�������B�v
�� �u�o�c�҂͖@�������ӎ��K�v�v
���e�̂��߂̑��g�i��������j��E�тȂǂ��s���G�X�e�T�����͑S���� 1 ���X�Ƃ�������B�@���o�ό������ɂ��ƁA�{�p�����łȂ��A���ϕi�Ȃǂ̕��i�̔��ɏd�_��u�����Ǝ҂������Ă���B�@�D�ǂȃG�X�e���Ǝ҂�F�肷��F�� NPO �@�l���{�G�X�e�e�B�b�N�@�\�� 9 ���A�u�����̗F���v�̗D�ǔF�����������B�@����F���В����J���g���ɓ������]�ƈ��ɑ��A�u�J����@����������Ђ͂Ԃ��v�Ȃǖ@�߈ᔽ��F�߂锭�����������߂��B
���N 3 ���ɂ́A�q�ɑ���4 ���Ԉȏ�����������U�����Ƃ��čs�������������� TBC �ɂ��Ă��A�F�����������B�@���@�\�̍������������ǒ��́u�����₷���T��������������v�Ƃ��������ŁA�u���͍L����傫���A�]�ƈ��̋��^����r�I�����B�@�R�X�g�̉���̂��߁A�c�ƖڕW�������Ȃ�B�@�Œ���̃��[���ł���@�������A�Ƃ����ӎ����o�c�҂ɂ͕K�v���B�v�Ƙb���B (�������Aasahi = 10-10-14)
����ҕی����̌y���k�� = �����������҂͕��S�� - ���@�H������グ�ցE���J�ȕ��j
�����J���Ȃ� 15 ���ɊJ���ꂽ�Љ�ۏ�R�c��i���J���̎���@�ցj�̈�Õی�����ŁA�Ꮚ���ґ�Ƃ��Ď��{���Ă��� 75 �Έȏ�̕ی����y���[�u���k��������j���������B�@�}���ɍ�����i�݈�Ô�c��ޒ��A�L�����S�����߂�K�v������Ɣ��f�����B�@�����̑������𐢑��ΏۂɁA�ی����𑝂₷���Ƃ���Ă����B
2008 �N�ɓ������ꂽ 75 �Έȏオ��������������҈�Ð��x�ł́A���߂ŒᏊ���҂̕ی������ő� 7 ���y������ƋK��B�@���݂͌��ϊɘa�[�u�Ƃ��āA����I�ɗ\�Z���m�ۂ�����ŁA�Ⴆ�ΔN�� 80 ���~�ȉ��̒P�g���т̏ꍇ�� 9 ���y�����Ă���B�q�ǂ��̕}�{����O�ꂽ�l�̕ی����ɂ��Ă����l�ɁA�{�� 5 ���̌y���������[�u�� 9 ���Ɋg�債�Ă���B�@����Ɍ��𐢑�̍������҂ɂ��ی����̕��S�������߂�B�@�ی����͌����ɕی��������|���邱�ƂŌ��܂�B�@���s���x�ł͕ی��������|���錎���̏���� 121 ���~�����A���̏���z�� 145 ���~�܂Ŋg�傷��悤��Ă����B
���J�Ȃ͂��̂ق��A���@���̐H����グ��l�����B�@���s�� 1 �H 640 �~�̂����H�ޔ�Ƃ��� 260 �~�����ȕ��S���Ƃ��A�c��͈�Õی��Řd���Ă���B�@����ōݑ��Â̊��҂͐H�ޔ���łȂ�������p�����S���Ă��邱�Ƃ���A���@���҂̐H��ɂ��Ă�������p�� 200 �~���x�������グ��Ă��������B (jiji = 10-15-14)
�A���A�x�A 2% �ȏ��v���ց@���N�̏t�����j
�J���g���̒����g�D�E�A���� 10 ���A���t���Œ����̌n�S�̂��グ����x�[�X�A�b�v�i�x�A�j�ɂ��āA�u2% �ȏ�v��ڕW�ɗv��������j���ł߂��B�@�x�A�̓���v���� 2 �N�A���B�@��ƋƐт������Ȃ����A�~���Ȃǂŕ����͏オ�葱���A�u1% �ȏ�v�����߂����t��������v��������K�v������Ɣ��f�����B
�A�������� 10 ���A���t���́u��{�\�z�v�����c���A�x�A�����߂邱�ƂŁA�����ނˈ�v�B�@���t���̕��ϒ��グ���i������������܂ށj�� 15 �N�Ԃ�� 2% �������A�����㏸�ɒ��グ�����ǂ������A���������͑O�N����������葱����B�@�l������x�����邽�߁A���N��荂���v�����f����B�@�A���� 17 ���̒������s�ψ���Ő����Ɍ��߂�B (�����G�j�Aasahi = 10-11-14)
�X�Ǔ��ɔF�ۈ珊�I�[�v���ց@���t�A�������܂���
���{�X�ւ��A�X�ǂ̋X�y�[�X��ۈ珊�Ƃ��đ݂��o�����Ƃ��n�߂�B�@���e�Ƃ��āA�������ܒ����X�ǁi�������s�j�̈ꕔ�𗈔N 4 ������F�ۈ珊�ɂ���B�@�X�ǂ͉w�O�̍D���n���������Ƃ���A�ʋΓr���ȂǂɎq��a����j�[�Y�������Ɣ��f�����B
�X�ǂ̃X�y�[�X��ۈ玖�Ƒ��� JP �z�[���f�B���O�X�i���É��s�j�ɑ݂��B�@�������ܒ����X�ǂɊJ���F�ۈ珊�̒���� 60 - 100 �l�ɂȂ�\��B�@���{�X�ւ͂��܁A�X�̗X�ǂł��Ă���d�����Ɩ���n��̋��_�ɏW�A�z���������グ�悤�Ƃ��Ă���B�@����͗X�ǂ̋X�y�[�X�������邽�߁A�n��̎��v���݂Ȃ���ۈ珊�𑝂₵�Ă����Ƃ����B
���݁A�k�C��������ɂ����đS�� 147 �̕ۈ珊���^�c���� JP �z�[���f�B���O�X�̎R���m�В��́u�Z��X�ɂ���ۈ珊�́A�n��̍�����i�ނ� 5 - 10 �N�قǂŃj�[�Y�������肪�����B�@�l���W�܂�w���ӂȂ� 20 - 30 �N�P�ʂŎ��Ƃ𑱂�����v�Ƙb���Ă���B (asahi = 10-10-14)
���@���@��
�������Ȃ��ۈ牀�@�߂��̌����͉����ő卬�G
�ҋ@�����̉����Ɍ����āA�ۈ牀�̑��݂���������s���ŁA����̂Ȃ��Ƃ��낪�����Ă���B�@����̑���ɗ��p��������͑卬�G�ŁA���Ԃ����炵�ė��p����P�[�X���B�@�q�ǂ��̗̑͂Â���Ɍ������Ȃ��V�яꏊ���ǂ��m�ۂ��邩�A����ł͖͍��������Ă���B�@�u�݂�Ȃ��ォ��w����āx����B�v�@���l�s�ߌ���̈��������ŁA�F�ۈ珊�u�r�[���Y�ۈ牀�v�̕ۈ�m�������������B�@�� 40 �l�̉����́u�́[���v�ƕԎ����A��Ăɑ���o�����B (�؉������A��c�a�؎q�Aasahi = 9-17-14)
���@���@��
�ҋ@������ 2 �� 1,371 �l�@4 �N�A�������ł�������
�F�ۈ珊�ɓ���Ȃ��ҋ@������ 4 �� 1 �����_�� 2 �� 1,371 �l�ŁA�O�N��� 1,370 �l�������B�@4 �N�A���̌����ƂȂ�B�@�����J���Ȃ� 12 ���Ɍ��\�����B�@�ҋ@�����[����ڎw����������w�i�ɂ��邪�A���p��]���E���オ��ŁA�ˑR�Ƃ��č������������Ă���B
�F�ۈ珊�̒���� 233 �� 6 ��l�ŁA�O�N��� 4 �� 7 ��l�� (2.0%) �������B�@����A�ۈ珊�𗘗p���鎙�������قړ����̖� 4 �� 7 ��l (2.1%) �����A226 �� 6,813 �l�ƂȂ����B�@���v�����n�߂� 1984 �N�ȍ~�ł́A2001 �N�i�� 183 ���l�j���� 14 �N�A���ʼnߋ��ő����X�V���Ă���B�@���J�Ȃ̒S���҂́u�ۈ珊���g�����d�����v���Ƃǂ܂��Ă������A�����������̂œ����Ă݂悤�Ƃ����l�������Ă���v�Ƃ��A���ݓI�ȕۈ���v���@��N������Ă���Ƃ݂�B (���R�֎q�Aasahi = 9-13-14)
���@���@��
�ۈ牀�̊�ƎQ���A�����̂��j�ށ@�ҋ@��������Ȃ����
�����̂��F����ۈ牀����Ƃ��^�c���悤�Ƃ��Ă��A�����̎s�⒬���u�ǁv��݂��Ă��邱�Ƃ��킩�����B�@���{�� 2000 �N�Ɋ�Ƃɂ��F�ۈ牀���^�c�ł���悤�ɂ����̂ɁA�Љ���@�l�i�Е��j��D�����A��Ƃ̉^�c��F�߂Ă��Ȃ�����������������������肵�Ă����B�@�ۈ痿�̈����F�ۈ牀����]���Ă�����Ȃ��u�ҋ@�����v���A����Ȃ�����ɂȂ��Ă���B
�F�ۈ牀�͖� 2 �� 4 ��J������A�� 9 ���������̂�Е����^�c���A��Ƃ� 2% �ɂƂǂ܂�B�@���{�� 00 �N�A�����̂�Е��Ɍ����Ă����^�c����Ƃɂ��J���������A�F�̏����Ȃǂ͎s�����ɔC���Ă���B�@�����J���Ȃ� 5 ���A���ߎw��s�s�A���j�s�A�ҋ@������ 50 �l�ȏ�̎s�撬�̌v 133 �����̂ɂ��āA��N 10 �����_�̔F�ۈ牀�̉^�c��F�߂�������܂Ƃ߂��B�@��������Ƃɒ����V������ނ����Ƃ���A�����ȏ�� 70 �����̂���ƎQ���ɕǂ�݂��Ă����B (�k��d��Aasahi = 8-3-14)
�O�@�� (5-20-14)
���E�ɒʗp�����w�x���@�X�[�p�[�O���[�o�� 37 �Z�I�o
�����Ȋw�Ȃ� 26 ���A���E�ɒʗp���錤���⋳����s���u�X�[�p�[�O���[�o����w�v��I�сA���\�����B�@���E�̑�w�����L���O�� 100 �ʈȓ���ڎw���u�g�b�v�^�v�ɓ�����⋞�s��A���É���A��B��Ȃ� 13 �Z�A���{�̍��ۋ����͌���ɍv������u�O���[�o���������^�v�ɐ�t��◧���ّ�Ȃ� 24 �Z��I�B�@���� 10 �N�ԁA13 �Z�ɂ͂��ꂼ��P�N�x�ōő� 5 ���~�A24 �Z�ɂ͓� 3 ���~�̎x�������o���B
��N 10 ���ɉp�����厏�u�^�C���Y�E�n�C���[�E�G�f���P�[�V�����v�����\���������L���O�ł́A100 �ʈȓ��͓���i23 �ʁj�Ƌ���i52 �ʁj�̂݁B�@���{�́u100 �ʈȓ��� 10 �Z�v��ڕW�Ɍf���Ă���A�u�g�b�v�^�v�̎x���ŒB����ڎw���B�u�����^�v�ł́A�O���l���t�◯�w���̑����A�C�O�̑�w�Ƃ̒�g�ȂǁA���K�͍Z���܂߂đ�w�̌����������ۉ��𑣂��A���̑����̑�w����{�ɂ��₷�����g�݂𑝂₷�B
�X�[�p�[�O���[�o����w�͍�N 5 ���A���{�̋���Đ����s��c�������B�@���ȏȂ����N 4 - 5 ���A���ۉ��Ɍ��������v�v��荞�\�z������A104 �Z 109 ���̐\�������B�@�u���E�̃g�b�v�X�N�[���ƘA���w�ʁi���s��j�v�A�u�A�W�A�n��ŃL�����p�X�W�J�i���É���j�v�Ȃǂ̍\�z����ꂽ�B�@��w�������Ƃ̕�������܂ސR������A�\�z�̓Ƒn����ڕW�l�̍����A�����\���Ȃǂ��l�����A�I�l�����B�@���ސR���Ɩʐڂōi�荞�Ƃ����B (���l�s�l�Aasahi = 9-26-14)
�y�g�b�v�^�z�@�i13 �Z�j�@�� �k�C���A�� ���k�A�� �}�g�A�� �����A�� ������Ȏ��ȁA�� �����H�ƁA�� ���É��A�� ���s�A�� ���A�� �L���A�� ��B�A�� �c���`�m�A������c
�y�O���[�o���������^�z�@�i24 �Z�j�@�� ��t�A�� �����O����A�� �����|�p�A�� �����Z�p�Ȋw�A�� ����A�� �L���Z�p�Ȋw�A�� ���s�H�|�@�ہA�� �ޗǐ�[�Ȋw�Z�p��w�@�A�� ���R�A�� �F�{�A�� ���ۋ��{�A�� ��ÁA�� ���ۊ���A�� �ʼnY�H�ƁA�� ��q�A�� ���m�A�� �@���A�� �����A�� �����A�� �n���A�� ���ہA�� �����فA�� ���w�@�A�� �����كA�W�A�����m
����Ƃ̏]�ƈ����@�d�� 8 �Ђ� 5 �N�O��葝��
���� 5 �N�ŏ���Ƃ̏]�ƈ����͂ǂ��ω������̂ł��傤���B�@�w��Ўl�G��x�ł́A���߂̌��Z���� 5 �N�O�̌��Z���i08 �N�x�j���ׁA�e��Ƃ̏]�ƈ������������܂����B�@���̊��Ԃ̓��[�}���E�V���b�N�Ⓦ���{��k�Ђ�����A�o�ϓI�Ō����傫�����������ł����A�����Ώ� 3,162 �Ђ� 58% �ɂ����� 1,840 �Ђ��]�ƈ��𑝂₵�Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B
�Ǝ�ʂɌ���ƁA�u���a�X�g���̂悤�ȃ^�C�����[�J�[�ɑ�\�����S�����i�� 83% �i15 �Ёj���A�g���^�����ԂȂǂ̗A���p�@��� 754% �i71 �Ёj���������Ă��܂��B�@�����Ԋ֘A��Ƃ́A�C�O�̎��Ɗg���ɔ����đ啝�ɐl���������Ă���悤�ł��B�@����A�،��Ƌ�s�͂Ƃ��� 6 ���ȏ�̊�Ƃ��������Ă��܂��B�@��������ȂǂŌ������Ɛт��������ق��A�x�X�̓��p���ȂǍ\�����v�Ől�������炵����Ђ������������߂ł��B (asahi = 9-13-14)