�D�w��L���ŋx�ƁA��Ƃɏ������@1 �l�ő� 100 ���~
�V�^�R���i�E�C���X�����ւ̕s������d�����x�݂����D�w���x�����邽�߁A�����J���Ȃ́A�D�P���̓������L���ŋx�Ƃ�������Ƃւ̏����������N�x�̑� 2 ����\�Z�Ă� 90 ���~���荞�B�@������ 1 �l������ő� 100 ���~���B�@�j���ٗp�@��ϓ��@�́A�Ђǂ�����ؔ����Y�̋��ꂪ����Ȃǂ̏ꍇ�A�Ζ��y����x�ƂȂLj�t�⏕�Y�t�̎w���Ɋ�Â����[�u�����悤�ٗp��ɋ��߂Ă���B�@���J�Ȃ́A�V�^�R���i���Ďw�j������B�@�����ւ̕s�������N�ɉe������Ƃ��Ĉ�t��Ɏw�������ꍇ���A���ʂɓK�p���邱�Ƃɂ��Ă���B
�����ΏۂɂȂ�̂́A�N���L���x�ɂƂ͕ʂ̋x�ɐ��x�Œ����� 6 ���ȏ���A�v 5 ���ȏ�D�w���x�܂�����ƁB�@5 - 19 ���Ԃ̋x�Ƃ� 25 ���~���������A���̌� 20 �����Ƃ� 15 ���~���Z����B�@�ő� 6 �J���قǒ�����₦�鐅���ŁA1 ��Ƃ����� 20 �l������Ƃ���B�@�D�w���V�^�R���i�Ɋ�������ƁA���Y�̏ꏊ������ꂽ��A�o�Y���ォ���q���������ꂽ�肷�郊�X�N������B�@�x�݂����Ă��������z���s���ŋx�߂Ȃ��Ƃ��āA�D�w�����̋x�ƕ⏞�����߂鐺���オ���Ă����B (���э��a�Aasahi = 5-28-20)
���{���~�āA�q�ǂ��H���ɖ����ց@�N�� 60 �L�����
�H��̈�Ƃ��āA���{���~�Ă�n��̎q�ǂ��H����t�[�h�o���N�ɖ����Œ���ƁA�_�ѐ��Y�Ȃ� 26 �����\�����B�@�]����_�����͊t�c���Łu�q�ǂ��H���Ȃǂ͐V�^�R���i�E�C���X�̊����g��Ŋw�Z���x�Z���钆�A�w�Z���H�̕⊮�@�\���ʂ����A���̖������ĔF�����ꂽ�v�Əq�ׂ��B�@�_���Ȃ͊w�Z���H�ł̂��͂�H�𐄐i���邽�ߔ��~�Ă���t���Ă������A�q�ǂ��H���Ȃǂɂ��g�傷��B�@1 �{�݂�����N�� 60 �L��������Ɍ��Ă���t����B�@�s�撬���̎Љ�����c���ʂ��Đ\�����t����B�@�₢���킹�͔_���Ȑ����������t������ (03�E3502�E7950) �ցB (asahi = 5-26-20)
�ݑ�Ζ� 7 ���u���������v�@���o�E�[�}�m�~�N�X�E�v���W�F�N�g����
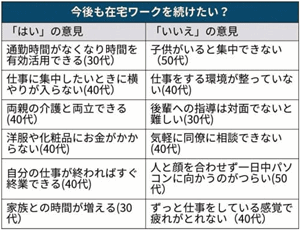
�d���Ɛ������������₷���Ǝq��Ē��̏����𒆐S�ɓ�������Ă����ݑ�Ζ����x�B�@3 ���ȍ~�A�����̊�Ƃ��Ώۂ��g�債���B�@4 �����{�A���o�E�[�}�m�~�N�X�E�v���W�F�N�g�̉�����Ώۂɒ��������{�B�@�u�ʋΎ��Ԃ�����Ƒ��Ƃ̎��Ԃ��������v�ȂǍݑ�Ζ������� 1,400 �l�� 74.8% ���u�V�^�R���i����������������v�ƌp������]�B�@����͎���ł��Ɩ������������Ȃ��悤�ɗl�X�Ȏ��ł�����Ƃ̍H�v�ƁA�R���i��̏������p�̕������Ă����B
�� �������ԁA�_���
�u�������q�ǂ������l���Ζ����₷���Ȃ����B�v�@�s���ݏZ�̗�؍����� (46) ���߂郁���J���� 4 ���A�K���Ζ����鎞�Ԃ̃R�A�^�C�����Ȃ������u�t���t���b�N�X�v���x�̎����������n�߂��B�@�������i�ƃR�~���j�P�[�V�������Ƃ��悤�ɁA�R�A�^�C�����]�� 12 ������ 16 ���܂łɐݒ肵�Ă����B�@�������A�q����ۈ牀�Ȃǂɗa�����Ȃ��ƒ�̎�����l���A�t���t���b�N�X�ɐ�ւ����B
������x���ȂǁA�ƒ됶���Ɨ������Ď����̃y�[�X�ŋƖ��Ɏ��g�߂�悤�A�������Ԃ��Ј���l�ЂƂ�Ɉς˂��B�@�u����̎��������̔����܂��āA�{�i�������������Ă����B�i�����J���j�v�@�t���b�N�X���̃R�A�^�C���́A���R�Ȓ��ł�������ƌ�������Ƃ����������B�@�s���ݏZ�̏��� (30) ���߂�R���T���e�B���O��Ђ� 3 �����{�A�q�����Ј���ΏۂɃR�A�^�C����P�p�B�@�K��̋Ɩ����Ԃ��m�ۂ���Ύn�ƁE�I�Ǝ��Ԃ����R�ɒ����ł��A�u�q��Q�������Ă���Ɩ��ɂ�����ȂǁA�����̓s���œ�����悤�ɂȂ����B�v
�ق��ɂ��u�q��Ē��̎Ј��ȂLjꕔ�ɗ��p����������Ă����t���b�N�X���x���S�Ј��Ɋg�傳�ꂽ�i40 ��j�v�A�u10 ������ 15 ���̃R�A�^�C���t���t���b�N�X����t���t���b�N�X�ɂȂ�A�玙�̕��S���y�����ꂽ�i30 ��j�v�A�u�ݑ�x�̗��p�T 2 ��܂ł��������ƂȂ�A�Ζ����Ԃ� 7 ������ 20 ���܂ł��A5 ������ 22 ���܂łɕύX�ɂȂ����i40 ��j�v�B�@�������A����� 24 ���Ԃ��ł��Ζ����\�ɂȂ�ƐS�g�̃o�����X������Ȃ��悤�ɂ���ΑӊǗ��̓���̖��͂���B�@�������A�ꏊ�ɔ���ꂸ�A�d���ɏW���ł��鎞�Ԃ������Ō��߂��邱�Ƃ͏���������@��𑝂₷�B
�� ���͂̈ӎ��ɕω�
����A�S�ГI�ɍݑ�Ζ�������u�o���Ă��Ȃ���x��ł���ƌ��Ȃ��Ă�����w���̈ӎ����ς�����i30 ��j�v�A�u���u����̂��Ƃ�ւ̕s�M�������@����A�\����Ȃ����ȑO�قNJ������d�������₷���Ȃ����i50 ��j�v�Ƃ�������������ꂽ�B�@�ݑ�Ζ��̗ǂ������������l�͍�����������A�u�D�P���ŊԂ��Ȃ��Y�x�B�@�q��ĂƂ̗������ł���Ɗ������i40�@��j�v�A�u�ʋΎ��Ԃ��Ȃ����A�ۈ牀���p���ԓ��Ńt���^�C���Ζ��������i30 �㏗���j�v�B�@�̗͂⎞�Ԃ̕s������������邽�߁A���ȏ�Ɏd���Ɏ����̗͂𒍂������Ƃ����ӗ~�ɂȂ����Ă����B
�����Ƃ��u����ς�ΖʂŎd���������i40 ��j�v�Ƃ��������B�@�u�ݑ�Ζ����������v�Ƃ����ӌ��̂Ȃ��ł��A�u�T 2 - 3 ���ݑ� OK �������i40 ��j�v�A�u�T 1�A2 �����x�i50 ��j�v�ƁA�ݑ�ƍݎЂ̐ܒ��Ă�]�ސ������������B
�u�e�����[�N�v�������l�҂̔�ÖM�F�E�����H�Ƒ�w�����͍ݑ�Ζ��𑱂��邽�߂Ɂu��Ƃ��Ј��ɑ��čŒ���K�v�Ȕz���� 5 ����v�Ƃ����B�@�u�����߂��ɂȂ�Ȃ��悤�ȍH�v�v�A�u����ł̋Ɩ����ւ̔z���v�A�u��������Ƒ��Ȃǂւ̔z���v�A�u�a�O�����ɘa���邽�߂̍H�v�v�A�u�Z�L�����e�B�[�̐��̓O��v���B�@�䕗��n�k�Ȃǂ̍ЊQ�A�{�l�̃P�K��a�C�A����玙�Ƃ���������ɑΉ����A�X���[�Y�ɍݑ�Ζ������{�ł���̐����������B�@��Ë����́u�o�c���_�ł̃����b�g�͑傫���B�@2 - 3 �N�ȓ��ɂ͍ݑ�Ζ���O��Ƃ����������ɐ�ւ����Ƃ��o�Ă���ȂǁA�傫�ȃ��[�u�����g�ɂȂ���\��������B�v�Ƙb���B
�� ��Ђ̃T�|�[�g�g�[
���Z�֘A�œ����s���ݏZ�̏��� (48) �̉�Ђ͈ꗥ 6 ���~�̕⏕�����x���B�@�����̓p�\�R�� (PC) ��V�������B�@���Ђł̓}�l�W���[�ȉ��ɋƖ��p PC ���x�����ꂸ�A���p PC ���g���Ă���A�Â��Ďg�����肪�����̂��Y�݂������B�@����V���������ƂŁu�Ɩ��������i�i�ɏオ�����B�v�@�s���ݏZ�̏��� (35) �̉�Ђ̓x�r�[�V�b�^�[���p�̕⏕���g��B�@�q�̑Ώ۔N������w 3 �N���珬�w 6 �N�ֈ����グ�A���p�̏���N�� 36 ����u3�A4 �����͉Ɋ܂߂Ȃ��v�Ƃ����B
�ق��ɂ��u�f�X�N�A���j�^�[�w������^���z��ōݑ�Ζ��蓖�A�� 1 ���~ �i40 ��j�v�A�u���M��Ƃ��� 1 �� 500 �~�i30 ��j�v�Ȃǎ�����u�����悭�������v�ɕς����p����Ђ����S�B�@�u����� FAX ���m�F�ł���悤�� PDF �ŋ��L�l�b�g���[�N��ɕۑ��i30 ��j�v�A�u�S�ēd�q��ŏ��F�i40 ��j�v�ȂǏ����ɑ����ꂪ���Ȏ��������̓d�q���Ō����A�b�v��}�����B
�܂��A�r�f�I��c�T�[�r�X (Zoom) ���g����Ƃ��ڗ������B�@�\�t�g�J���̃G�C�`�[���� 2 �����{����ЊO�̉�c�� Zoom �����p�B�@�V���⒆�r���Ђ̗̍p�̓I�����C���ʐڂőΉ����Ă���B�@���Ђɋ߂�����t������ (32) ���T 5 - 6 ���c�ɎQ�����u�Ɩ��̐i��̍����ŏ����ɗ}�����Ă���v�Ǝ�������B (nikkei = 5-18-20)
�u�V�����n�}�v����A�q�ǂ��H���� 4 �疜�~�@�R���i�x��
�u�V�����n�}�v�̈�_��Y���� (46)�A���g������ (45)�A����T�Ⴓ�� (43) �Ɠ��{���c���n�߂�����uLOVE POCKET FUND �i���̃|�P�b�g����j�v�́A14 ���ߑO�܂łɊ�t���z�� 1 �� 9 �疜�~�߂��ɒB���A�ŏ��̎x����Ƃ��āANPO �@�l�u�S���q�ǂ��H���x���Z���^�[�E�ނ��т��v�ɖ� 4 �疜�~����t����Ɣ��\�����B
�V�^�R���i�E�C���X�̉e���ŋx�Z�ɂȂ�A���H�ʼnh�{�̂���H�����\���ɂƂ�Ȃ��Ȃ������т̎q�ǂ������𒆐S�ɁA�n��c�̂���H�X�ȂǂƘA�g���āA���ٓ���H�ނ̒A���k�x�����s�������ɂ��Ă���Ƃ����B�@����́A�����ɂ���������鏗����q�ǂ��A����҂���x������ړI�� 4 �� 27 ���ɐݗ��B�@�� 1 �e�Ƃ��ĐV�^�R���i�E�C���X��Ɏ��g�ރv���W�F�N�g�\���A�u�V�����n�}�v�� 3 �疜�~����t���Ă����B����̏ڍׂ� �����T�C�g�B (�ɓ����Aasahi = 5-14-20)
�����蓖�A1 �l 1 ���~��lj��@�o�ϑ�A������ 1 �����
���{�E�^�}�� 5 ���A�V�^�R���i�E�C���X�̊����g������ً}�o�ϑ�̌��Ă��܂Ƃ߂��B�@�����蓖�̑��z��A�V�^�R���i�����ǂ̎��Ö�Ƃ��Ċ��҂����R�C���t���G���U��u�A�r�K���i��ʖ��t�@�r�s���r���j�v�̔��~�Ȃǂ荞�ށB�@7 ���ɐ������肵�A���{�W�O���S�̂̋K�͂Ȃǂ����\������j���B�@���{�� 5 ���A�����A�������}�̐�����������Ɍ��Ă�����B�@�q��Đ��т��x�����邽�߁A�����蓖�� 1 �l������ 1 ���~���A1 �����ő��z����B�@�A�r�K���ɂ��Ă� 200 ���l������~���邽�ߑ��Y���}���B�@�V�^�R���i�ւ̍���ً̋}�̎x�o�ɑΉ����邽�߁A�\����Ƃ��� 1 ���~���m�ۂ���B
�����������������тւ� 30 ���~�̌������t�́A���Ȑ\�����Ƃ���B�@�Ώۂ́A����������A�N���Ɋ��Z����ƏZ���Ŕ�ېŐ��т̐����܂ŗ������ތ����݂̐��сB�@����ɉ����A�����������������тɂ��A���̏��������݂��Ďx��������j���B�@�����E���Ƒ�ł́A�������Ȃǂ̏����ɉ����āA�t���[�����X���܂ތl���Ǝ�ɍő� 100 ���~�A������Ƃɍő� 200 ���~�̌��������t����B
����̐V�^�R���i�ɂ��o�ϓI�ȉe���ɂ��āA��ł́u���ő�̌o�ϊ�@�v�Ǝw�E�B�@���������̂��߂ً̋}�x���𒆐S�Ƃ���� 1 �i�K�ƁA������̌o�ς� V �����߂����� 2 �i�K�ɕ�������ŁA�� �����g��h�~���ÑԐ��̐����A���Ö�̊J���A�� �ٗp�̈ێ��Ǝ��ƌp���A�� �o�ϊ����̉A�� ���ՂȌo�ύ\���̍\�z�A�� ����̔��� - - ���̒��Ƃ����B
�����N���o�ύĐ����� 5 ���̃t�W�e���r�̔ԑg�ŁA���ь����̌������t�ɂ��āu���������K�v�����邩������Ȃ��v�Ƃ̍l�����������ق��A�x�ƕ⏞�̏������ł͑ΏۊO�ɂȂ��������Ƃɋ߂�l���u�����ɍ����Ă���l�ɂ͓͂��悤�ɍl���Ă���v�Ə��O���Ȃ��l���𖾂炩�ɂ����B (asahi = 4-5-20)
���@���@��
�x�Z�ɔ����������A�����Ƃ͑ΏۊO�@�u�E�ƍ��ʁv�ᔻ��
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g���h�����߂̋x�Z�ɔ����A�����J���Ȃ͎q�ǂ��̐��b�Ŏd�����x�ی�Ҍ����̏�������V�݂������A�����ƂȂǂœ����l�͑ΏۊO�ƂȂ��Ă���B�@�x���c�̂͌����������߂����A���J�Ȃ͉����Ȃ��\�����B�@���̏����ł́A���̗v�������A�ق��ē����l�͋ߐ悪���z 8,330 �~�i����j���A�t���[�����X�͖{�l���ꗥ���z 4,100 �~������B�@�������A�v���ł́u�\�͒c���v��u�\�͎�`�I�j�����s�����c�̂ɏ�������l�v�Ȃǂƕ��сA�u�������Ɓv��u�ڑ҂����H�Ɓv�̊W�҂�ΏۊO�Ƃ��Ă���B
���̂��߃l�b�g��ȂǂŁu�E�ƍ��ʂ��v�Ɣᔻ���o�Ă���A�x���c�́uSWASH�v�� 2 ���A�v���̌����������߂�v�]�����������M���J�����Ăɒ�o�����B�@�v�F�I�q��\�́u���̐��x���A�����œ����l�X�ւ̍��ʂ�Ό����������Ă���v�Ǝw�E����B�@����A���J�Ȃ̒S���҂́u�l�̐E�Ƃ����ʂ���Ӑ}�͂Ȃ��v�Ɛ����B�@�����ƂȂǂ������K��́A�ٗp�ێ��̏������Ȃǂɂ�����A��������l�̃��[����K�p�����Ƃ����B�@�������J���� 3 ���̊t�c���ŁA���O�̎�|�ɂ��āu���I�Ȏx���[�u�̑ΏۂƂ��邱�Ƃ��K�Ȃ̂��ǂ����v�Ɛ����B�@�u��舵����ς���l���͂Ȃ��v�Əq�ׂ��B (����A���э��a�Aasahi = 4-3-20)
���@���@��
�ЂƂ�e�ƒ���x�Z�������@�u�H���l�߂邵�� �c�v
�V�^�R���i�E�C���X�̊����g��ɂ�鏬�����Z�Ȃǂ̗Վ��x�Z���A�o�ϓI�ɋꂵ���ЂƂ�e�ƒ�̍��z���������Ă���B�@�q�ǂ�������ɂ��鎞�Ԃ������A�H�����M��Ȃǂ��c���ł��邽�߂��B�@���S���������ƒ�Ɏ�������ׂ̂铮�����L�����Ă���B�@���w 1 �N�̑��q�ƕ�炷�O�d���K���s�̊Ō�t�̏��� (42) �� 3 ���̂�����A�d������A��Ƃ��� 3 �����Ȃ��Ȃ��Ă����B�@����ɔ[�� 4 �p�b�N�A���� 1 �����A���l���B�@���q�͐H�א��肾���A���i�Ȃ� 2 - 3 ���ŐH�ׂ�ʂ��B
�����̐S�z�́A�Վ��x�Z�ŊO�o�����l�������Ă��鑧�q�̃X�g���X���H�ׂ邱�ƂɌ������Ă��邱�Ƃ��B�@�����̎���͌� 22 ���~�قǂŁA�������肬��̕�炵�B�@�����A3 ���̐H��͂���܂ł� 2 �{�ɂȂ肻���ŁA�g�[��Ȃǂ������ށB�@�u�����͐H����l�߂邵���Ȃ������B�v
���̒����ɂ��ƁA�����̂ЂƂ�e�ƒ�� 2 ���т� 1 ���т����ΓI�ȕn����Ԃɂ���B�@�ЂƂ�e�ƒ�̎x���Ȃǂ����Ă���S���� 20 �c�̂� 2 �� 29 �� - 3 �� 5 ���A�Վ��x�Z�Ɋւ���A���P�[�g�������B�@188 ���̉����A�H�����M��̑����̂ق��A�������ւ̕s���̐������������B�@�u���H���Ȃ��̂ŁA����������ށv�A�u�g�[����������邱�ƂɂȂ�̂ŁA������̐��������낵���i��������k�C���j�v�A�u�q�A��o�ł��邪�A�Z�k�Ζ��ɂȂ����������i���Q���j�v�A�u�Ƃɕ����߂��Ă��邱�ƂŐ��_��Ԃ��s���i���j�v�Ƃ������s���̐�����ꂽ�B
�A���P�[�g���Ăт����� NPO �@�l�u���z�̉Ɓi�K���s�j�v�́A��t���ꂽ�H�i�Ȃǂ������w��������ЂƂ�e�ƒ�ɓ͂���ً}�����Ɏ��g�ށB�@�Δn�����ݗ������́u�ЂƂ�e�͂炭�Ă��䖝���Ă��܂������B�@�����̐l���x�������悤�Ƃ��Ă���̂ŁA���k���Ăق����B�v�ƌĂт�����B�@���H��ǐH��h�����ƒn��̎q�ǂ��ɖ����������ŐH�������u�q�ǂ��H���v�����~���������B�@�����h�~���}��A�H����K�v�Ƃ���ƒ�ɓ͂��悤�Ƃ���c�̂�����B
���É��s�k��́u�킢�킢�q�ǂ��H���v�� 3 ���̊J�Â𒆎~�����B�@������ 1 ��̊J�×\��������� 4 ���́A���~��m�炸�ɗ���q�ǂ��̂��߂Ɏ����A��ł���H����p�ӂ����B�@�H���ɂ́A�u�����ŐH�ׂĂ��邩��w���L�т���v�ƕ��Ă���鏬�w����A�e���a�C�ŐH����p�ӂ���̂�����ƒ�̎q�ǂ����K���B�@�^�c�ψ����̐���ɒÎq���� (73) �́u���H���Ȃ����A���H�̎q���o�������Ȃ��B�@����Ȏ������炱���q�ǂ��H���Ƃ��ĉ����ł��邩�l���Ă��������B�v�Ƙb���B
���m������s�̏Ă����X�u�\�E���J���r�v�� 19 ���܂ŁA�s���̎����E���k��ی�҂�Ώۂɂ��ɂ��� 2 �Ɗ؍��̂�̃Z�b�g���A�����J���[���C�X�� 1 �����ꂼ�� 100 �H�قǖ������Ă���B�@�ꏊ�͉���s�̃X�[�p�[�K���u�����v�ŁA�����̌ߑO 11 �� - �ߌ� 1 ���B��]�҂ɂ̓}�X�N���z�z���Ă���B�@���L�s�В� (48) ����g�Ǝ҂ɐ���������ƁA�_�Ƃ���̉���Ђ���Ă⋍���A���̍������ꂪ�������Ƃ����B�@���В��́u�n���Œ��������������Ă�����Ă���̂ŁA�ǂ����Ƃ��������Ǝv�����B�@���͂��^�����Ă��ꂽ�B�v�Ƙb�����B (�Y������A���쐒�A�ۍ�m�W�Aasahi = 3-15-20)
���@���@��
�ی�҂̋x�Ǝ蓖�⏕�@�V�^�R���i ���w�Z�x�Z�Ɍ������{
���{�͊w�Z�̗Վ��x�Z�Ɍ����A�q�ǂ������ی�҂��x�Ƃ����ꍇ�Ɋ�Ƃ��o���蓖��⏕���鏕������n�݂���B�@�ٗp�ی������p���A�V�^�R���i�E�C���X��̓���[�u�� 3 ��������{����B�@�x�ی�҂����̎�����������B�@�����g���h�����߃C�x���g���Ȃǂ̎{�ݗ��p�̐�����s���{�����v���ł���悤�ɂ���@�Ă�������ɒ�o����B�@���{�W�O�� 29 ���ɋL�҉���A�������̋x�Z�Ȃǂւ̑Ή����������B�@�� 28 ���̏O�@�������Z�ψ���ŋx�Z�v���ɂ��āu��{�I�ȍl�����Ƃ��Ď������B�@�e�w�Z�A�n��ŏ_��ɂ����f�������������B�v�Əq�ׂ��B
�x�Ǝ蓖�͉�Гs���ŏ]�ƈ����x�܂����ꍇ�A������ 6 ���ȏ��⏞����悤��Ƃɋ`���t���Ă���B�@�Վ��x�Z�ɔ����ی�҂̋x�Ƃ͐��{�̗v���Ɋ�Â����߁A�������̓���Ƃ���B�@��Ƃւ̏������͏��w�Z�̎q�ǂ������ی�Ҍ����̎蓖�݂̂ɂ���������B�@�]�ƈ����x�߂�悤��Ƃɔz�������߂�B�@�������Ԃ��Z���ٗp�ی��ɉ������Ă��Ȃ��p�[�g�J���Ҍ����ɂ͈�ʉ�v�\�Z���瓯���̎x��������B�@�������ō��������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂��B �]�ƈ����x�܂���Ȃǂ��Čٗp���ێ������ƂɎx������u�ٗp�����������v���g�[����B�@�����֘A�̔̔��������Ƃւ̓����V�^�R���i�ʼne���������ƑS�ʂɍL����B
���{�͐M�p�ۏ؋���Z���z�����̏����� 100% �ۏ��鎑���J��x���ɂ��đS���̒�����Ƃ�����悤�ɑΏۂ��L����B�@�����g��h�~�Ɍ����Ė@����������B�@���{�������߂��u�ً}���ԁv��錾������A�����Ԃ�ڈ��ɓs���{���m�����O�o�̎��l�Ȃǂ�v���ł���ƋK�肷��B�@���ȏ�̖ʐς��鋳��{�݂�^���{�݁A����Ȃǂ̗��p���������߂�B�@�ᔽ���Ă������͂Ȃ��B�@�� 28 ���A�@�����ɂ��āu�����ɐ��������Ȃ�������Ȃ��B�@��}�̈ӌ������������B�v�Əq�ׂ��B�@��K�̓C�x���g�̒��~�Ȃǂ����߂Ă��肻�̖@�I�ȗ��t���ƂȂ�B (nikkei = 2-29-20)
�u�ۈ牀�������v���t�� 4 �l�� 1 �l�@�{�Ў�v�����̒���
���N 4 ���̓����Ɍ����ĔF�ۈ�{�݂̗��p��\�������̂́A1 ���I�l�ŗ��I�����q�ǂ����S���̎�v 59 �����̂Ŗ� 6 ���l�ɏ�邱�Ƃ������V���̒����ł킩�����B�@�\���҂ɐ�߂闎�I�҂̊����i���I���j�� 27.1%�B�@���{���������N 3 ���܂ł́u�ҋ@�����[���v���ڑO�ɔ��邪�A���I�����O�N��舫�����������̂��Ȃ��� 4 ���������B�@�ꕔ�̎����͍̂��H�Ɏn�܂����c������E�ۈ�̖������Ő\���҂��������Ƃ݂Ă���A�ڕW�B���͌��ʂ��Ȃ��B
�F�ۈ牀�⏬�K�͕ۈ牀�Ȃǂ̓����́A�ی�҂���̐\�����݂��s�撬������������B�@�V�N�x�ƂȂ� 4 ���̓������� 1 - 2 ������ɍs���� 1 ���I�l�ő唼�����܂�B�@�����V���́A���ߎw��s�Ɠ��� 23 ��A��N 4 �����_�őҋ@������ 100 �l�ȏア�������̂̌v 71 �s�撬��Ώۂ� 1 ���I�l�̌��ʂ��B�@13 ���܂ł� 62 �����̂��������A�������I�Ґ��𖾂炩�ɂ����̂� 59 �����̂������B
59 �����̂� 22 �� 1,087 �l���\�����݁A5 �� 9,850 �l�������Ă����B�@���I�����O�N��舫�����������̂� 23 �����́B�@���I�����ł����������͕̂��Ɍ���ˎs�� 44.5%�B�@�\���Ґ����O�N���� 1 �������A�S���҂́u�O�N�x�ɓ���Ȃ������q�ǂ��̂ق��A�������̑ΏۂƂȂ��� 3 - 5 �Ύ��̐\�����݂��������v�Ƃ����B�@���ꌧ���s ( 41.3%)�A�����s�`�� (41.0%) �Ƒ������B�@���{�͍�N 10 ������A���ׂĂ� 3 - 5 �Ύ��̔F�ۈ�{�݂�c�t���̗��p�������������ɁB�@�ꕔ�̎����̂ł́A�c�t����蒷�����Ԏq�ǂ���a����F�ۈ�{�݂̗��p����]����l���������Ƃ݂���B
������ 3 - 5 �Ύ��̐\���Ґ��͂����Ƃ���A62 �����̂̂��� 11 �����̂� 1 ���ȏ㑝�����Ă����B�@�O�N�� 2 �{�ɂȂ��������s�����ł́A2 �Ύ��܂ł�ΏۂƂ���ꕔ�̕ۈ�{�݂���̓]���҂��������Ƃ𗝗R�Ƃ��邪�A�O�N��� 6 �����������{�����s�ł́A�c�t���ɒʂ��Ă����ی�҂���ۈ牀�̗��p�ɂ��đ��k�����P�[�X������A�������̉e�����w�E�B�@3 ���߂������������s�i�����������ɂ��j�[�Y���Ƃ݂Ă���B
����A3 - 5 �Ύ��̐\�����݂� 1 ���ȏ㌸�����������̂� 18 �������B�@�O�N���甼�������`��́A�F�O�ۈ�{�݂��������̑ΏۂƂȂ������Ƃ������A�F�O�̗��p����]����l���������̂ł͂Ȃ����ƕ��͂��Ă���B�@�A���P�[�g�ł́A�������ɔ����ۑ���q�˂��B�@���� 27 �����̂̂��� 15 �����̂́A�����̂�ۈ�{�݂ł̕��S�����w�E�B�@�u���x�����ɕ��G�ŁA�ی�҂�{�݂ւ̐����ɋ�J���Ă���i���͌��s�j�v�A�u�������ɔ����ĕۈ牀�̗��p���Ԃ������A�ۈ�m�̓������ɉe�����錜�O������i�����s������j�v�Ƃ�����������ꂽ�B
���̂ق��A���p����{�݂ɂ���Ă͖������̑ΏۊO�ƂȂ�ꍇ�����邱�Ƃ���u���������m�ۂł��Ă��Ȃ��i���s�j�v�Ƃ̎w�E��A�u�F�O�{�݂̕ۈ�̎��̊m�ہi�����s��c��j�v�������������̂��������B (�I�c�D���A���R�֎q�A�ɓ������Aasahi = 3-14-20)
�O�@�� (3-17-19)