�S����! ���e�B���[�����K���������
����A�W�A�̍��A���e�B���[������̋Z�\���K�������m�����S���ŏ��߂Ď���邱�ƂɂȂ� 9 �� 19 ���A������g���l�c�m����\�h�K�₵���B�@�l�c���m���m����\�h�K�₵���̂́A���e�B���[���̃C���f�B�I�E�V���l�X�E�_�E�R�X�^��g�B�@���e�B���[���� 2002 �N�ɃC���h�l�V�A����Ɨ������l���� 134 ���l�̍��ŁA�_�Ƃ␅�Y�Ƃ���ȎY�Ƃ��B�@����A�S���ŏ��߂ēy���s�Ɛ{��s�Ŕ_�Ƃ̋Z�\���K�� �V �l������Ă��āA�C���f�B�I��g�́u���K���������M�d�Ȍo���ƒm���������ċA���Ă��Ă���邱�Ƃ����҂���v�Əq�ׂ��B�@���e�B���[������̋Z�\���K�� �V �l�� �P�W ���ɍ��m���肵���Ƃ������ƂŁA�P �����̍u�K���o�� �P�O ������V���E�K��g�}�g�Ȃǂ͔̍|�Ɍg���\��ŁA���コ��ɓ��e�B���[������ 9 �l�̋Z�\���K��������錩���݂��Ƃ����B (RKC ���m���� = 9-19-23)
�x�g�i������U�̋� 1 ���~�D��A���E���ւŎg�p�����^�� �Z�\���K���� 4 �l�ߕ�
�x�g�i������A�������U�̋� �P ���~�D�������̋��Z�@�ւŗ��ւɎg���Ȃǂ����Ƃ��Ē��F���̉�Ј��̒j�ƋZ�\���K���̒j���v �S �l���ߕ߂���܂����B�@�U���ʉݗA����s�g�̋^���őߕ߂��ꂽ�̂͒��F���{��ɏZ�ތ��x�g�i���l�ƃx�g�i���l�Z�\���K���̒j�� 3 �l�ł��B�@�x�@�ɂ��܂��ƁA�R���e�^�҂�͋��d�� 8 �� 17 ���A������`�ŋU�̋� 1 ���~�D 100 �����ו��ɕ��ꍞ�܂��q��@�Ńx�g�i������A�����A�ʖ��S���̋��Z�@�ւŗ��ւɎg�p�����^���ł��B
�R���e�^�҂�́A���̂ق��ɂ��A�V ���A�F�{�s������ɂ�����Z�@�ւŋU�̋� 1 ���~�D 6 ���𗼑ւɎg�����^����������Ă��܂��B�@������̂��̋��Z�@�ւ��U�D�ƋC�Â��A�x�@�ɓ͂��o�����ƂŎ��������o�B�@�x�@���A�h�ƃJ�����̉f���Ȃǂ���R���e�^�҂���肵�ߕ߂��܂����B�@���̌�̒��ׂŁA�x�g�i������U�D��A���������ƂȂǂ�������A14 ���܂łɎc��� 3 �l���ߕ߁B�@�x�@�́A�S���̔F�ۂɂ��āu�{���Ɏx�Ⴊ����v�Ƃ��Ė��炩�ɂ��Ă��܂���B�@�x�@�́A���ɋ��Ǝ҂�����\��������Ƃ݂Ē��ׂ�i�߂�ق��A�U�D�̐������@����胋�[�g�ɂ��Ă��Njy���Ă��܂��B (TKU �e���r�F�{ = 9-14-23)
���܂͐��k�� 6 �����O�����[�c�@��Ԓ��w���S���u�ږ�����v�̌��ݒn
�e�n�Ŗ�Ԓ��w�̐ݗ��������i��ł���B�@���łɒʂ����k�̒��ɂ́A���{����w�т����ƒʂ��O�����[�c�̐��k�����Ȃ��Ȃ��B�@�Ȃ��A���{��w�Z�ł͂Ȃ���Ԓ��w�Ȃ̂��B�@�É����֓c�s�� JR �֓c�w�O�̃r���ɍ��N 4 ���A�É����ŏ��߂Ă̌�����Ԓ��w�ƂȂ錧���ӂ��̂��ɒ��w�Z���J�Z�����B�@�V�����d�q����O�ɁA��̋����ł͐��w���A������̋����ł͓��{��̎��Ƃ��i��ł����B�@���Ƃ��Ă����v 6�l�̂��� 5 �l�͊O���Ƀ��[�c�������k�������B
��Ԓ��w�͗l�X�Ȏ���Œ��w�Z�ɒʂ��Ȃ������l�����Ȃ����߂Ċw�ԏꂾ�B�@����␔�w�����łȂ��A���p��ی��̈�Ȃǂ��w�ԁB�@���̍������́A��ɐ������ꂵ���w�Z�ɒʂ��Ȃ������l�����̊w�т̏ꂾ�������A2016 �N�ɐ�����������@��m�ۖ@�ŁA�w�ђ����̕ۏ�����n�������̂̐Ӗ��Ƃ���A���͊e�s���{���Ɛ��ߎw��s�s�ɖ�Ԓ��w�̐ݒu�����߂��B�@�����A�w�ђ�����K�v�Ƃ��Ă���͓̂��{�l�����ł͂Ȃ��B
���ȏȒ����ŊO���Ђ� 6 ��
�����Ȋw�Ȃ� 2020 �N�ɒ��������Ƃ���A��Ԓ��w�ɒʂ����k�� 8 �����u���{���Ђ�L���Ȃ��ҁv�A�܂�O���Ђ������B�@���̔����́u���{�ꂪ�b����悤�ɂȂ邽�߁v�ɒʂ��Ă����B�@22 �N�̒����ł��A�O���Ђ� 6 ���ɒB���Ă���B�@�u���I�Ȉږ������̋���@�ւ��Ȃ����{�ł͎�����A��Ԓ��w�����{�ꋳ����܂߂��A�ږ�����̖�����S���Ă��Ă���ƌ����܂��B�@����͐É��������ł��B�v�@���{�ɕ�炷�t�B���s���l�̎Љ�Ȃǂ��������鍂���K�E�É������勳���͎w�E����B�@��Ԓ��w�J�݂Ɍ������É����̗L���҉�c�ł͕��ψ����߂��B
�É����̒����ł��A���w��]�� 90 �l�̂����A79 �l���u���W����t�B���s���Ȃǂ̊O���o�g�҂���߂��B�@���ۂ̓��w�҂� 14 �l���������A7 �������O���Ƀ��[�c������B�@���{�Ő��܂�Ă����e���O���l�œ��{�ꂪ�قƂ�ǘb���Ȃ��l������B�@������o�҂��ŗ����������A���{����w�ׂȂ��܂ܕ�炵�Ă����l������B�@�܂��A����̂ǂ��炩�����{�l�œ��{��ł̉�b�ɂ͕s���R���Ȃ����A�w�K����̂͂ނ��������l������B
�f�Љ����ꂽ�x���̌��ߓ_��
�ӂ��̂��ɒ��w�ł͍��Ђ͖��Ȃ����A�ݗ����i���u���w�v�̐l�͓��w�ΏۊO���B�@���c�G�j�Z���́u��Ԓ��w�͓��{��w�Z�ł͂���܂���v�Ƌ�������B�@�������A���{�ꂩ��w�ԕK�v�����鐶�k�����Ȃ��Ȃ��B�@���Ȃ������w�ԕW���I�ȃR�[�X�̑��ɁA�����ɕK�v�ȓ��{�ꂩ��w�ԃR�[�X�A�w�K�̂��߂̓��{��R�[�X���p�ӂ����B�@���{�ꃌ�x�������コ���A�W���R�[�X�Ŋw�ׂ�悤�ɂ��Ă��炤�_�����B�@���c�Z���� 18 �N���猧���ςŖ�Ԓ��w�̊J�Z������S�������B�@�u�����ł킩���Ă͂����Ƃ͂����A���ۂɐ��k�Ɛڂ��钆�ŁA�O���l��O�����[�c�̎q���A���{����܂߂��w�т̖ʂŋꂵ���ɒu����Ă������Ƃ���������v�Ƙb���B�@�u�O�����[�c�̎q�̎x���͎����̂▯�Ԓc�̂Ȃǂōs���Ă��邪�A�f�Љ�����Ă���B�@�����̖�Ԓ��w�����ߓ_�ɂȂ��B�v�Ƙb���B
�É����́A�l���s�Ȃǂɑ����̊O�����[�c�̐l����炵�Ă����B�@�����A�����͂Ȃ��������S��ɊO�����[�c�̐l����炵�A��Ԓ��w�ւ̓��w��]�҂����邱�Ƃ������Ŗ��炩�ɂȂ����B�@�u��Ԓ��w�Ŋw�ђ��������Ƃ����O���l�̐��ݓI�j�[�Y�͂܂��܂�����B�@���w�ɂǂ��Ȃ��邩���ۑ�ł��B�v�@�����O���s�� 10 �N����O���l�����̏A�w�x������{��w�K���{�����e�B�A�ő�����Έ��b�q���� (64) �́A��Ԓ��w�ւ̓��w��]�҂�T���A�菑�쐬�Ȃǂ��x�����Ă���B�@������ʂ��A�O�����[�c�̐l�����̊w�т̋@������ނ���������Ɋ����Ă����B�@�o�҂��Ȃǂŗ��������l�����ɂƂ��āA���{���������Ɗw�т����Ă��A�w��N�ԂŐ��\���~�̓��{��w�Z�ɒʂ��o�ϓI�ȗ]�T�͂Ȃ��B
�{���ɕK�v�Ȃ��̂�
���Ƃ����āA�����w�Z�ł͊w������߂���Ɠ��w���ނ��������B�@�^�ǂ��w����ɊԂɍ����Ă��A���N���Ȃ����߁A�w�K���e����{�ꂪ�g�ɂ������ǂ����ɊW�Ȃ��A�`���I�ɑ��Ƃ������Ă��܂��B�@���̂��߁A���̐i�H�ɂȂ���ɂ����B�@���������l�ɂƂ��Ė����Œʂ����Ԓ��w�͑҂��]��ł����w�Z���ƐΈ䂳��͌����B
���{�̒��w���ƂƂ������i����A�i�w��]�E�Ȃǂ̓����J����B�@�����A�����Ȃ���3�N�Ԓʂ��̂͊ȒP�ł͂Ȃ��B�@�Έ䂳��́A��Ԓ��w�ւ̓��w������O�����[�c�̐l�����̔w������������A���ł͊w�ׂȂ��l�ɓ��{����������肵�Ă���B�@�����A�^��������Ă���B�@�u���̂悤�ȃ{�����e�B�A�́A��߂����Ȃ�����A��߂����ł��B�@�O�����[�c�̐l�̋�����A�i���I�ł͂Ȃ��{�����e�B�A��A�{���Ƃ͈Ⴄ�`�Ŗ�Ԓ��w�ɒS�킹��̂͌��E������Ǝv���܂��B�v (���c���Aasahi = 9-9-23)
�Z�\���K�����ꎖ�Ə�A7 ���Ŗ@�߈ᔽ�@����J���ǂ��ēw��
����J���ǂ� 5 ���A��N 1 �N�ԂɌ����ŊO���l�Z�\���K��������Ă��鎖�Ə� 243 �J���ɑ��āA�J����W�@�߈ᔽ�̋^���Ŋēw�����s���A������ 7 ���ɂ����� 166 �J���ňᔽ���m�F���ꂽ�Ɣ��\�����B�@�ᔽ�����������Ə�͑O�N�� 41 �J�����B�@�댯�h�~�[�u��ӂ�����A�K�v�Ȏ��i�������Ȃ��J���҂ɍ�Ƃ������肵�����S��ᔽ�� 76 ���ƍł������A�S�̂� 31.3% ���߂��B�@�����ŘJ�����ԂɊւ���ᔽ�� 34 �� (14.0%)�A���������̎x�����Ɋւ���ᔽ�� 32 �� (13.2%) �ȂǁB�@���ޑ����������Ă͂Ȃ������B (�����V�� = 9-6-23)
�O���l�Z�\���K����Ɉ�@�Ȏ��ԊO�J���������Ȃǂ̋^��
�@�D����ЂƎВ������ޑ����@���R�E�q�~�J�
�O���l�Z�\���K����Ɉ�@�Ȏ��ԊO�J�����������ȂǂƂ��āA�q�~�J����ē����q�~�s�̖D����ЂƂ��̎В������ޑ������܂����B�@�J����@�ᔽ�̋^���ŏ��ޑ������ꂽ�̂́A�q�~�s�������̒��̖D����ЁuMOSC �i���X�N�j�v�Ƃ��̎В� (43) �ł��B�@�q�~�J����ē��ɂ��܂��ƁuMOSC�v�́A�x�g�i���l�̋Z�\���K���Ɠ���Z�\�O���l�A���킹�� 6 �l�ɁA��@�Ȏ��ԊO�J�����������ق��A2022 �N 9 ���܂ł� 2 �N���̎c�Ƒ�̈ꕔ�A���킹�Ė� 250 ���~���x����Ȃ������^����������Ă��܂��B�@�܂��A��@�Ȏ��ԊO�J�����B�����ƁA�J����ē��̕������ɂ����̐����������Ƃ���Ă��܂��B�@�q�~�J����ē��͎В����e�^��F�߂Ă��邩�ǂ������炩�ɂ��Ă��܂���B (KSB ���˓��C���� = 8-30-23)
�O���Ђ̎q��ʂ��{�݁A�������ł�����@�u���{�̕ۈ�m�v�����
�� 1 ���l�̃u���W���l����炵�A�����Ƃ��x���鎠�ꌧ�B�@�O���Ђ̎q�ǂ������̎M�ƂȂ��Ă���F�O�ۈ�{�݂��A���̗c������E�ۈ�̖������̊��������i���Ă���B�@�����ƂȂ�u���{�̕ۈ�m���i�����E���v�̊m�ۂ�������߂��B�@�O���l�����̕ۈ�{�݂������S���̎����̂��A��������������B�@���ꌧ�������̃u���W���l�w�Z���ۈ�{�݁u�T���^�i�w���v�B�@1998 �N�A���n 2 ���̒��c�P���R�Z�� (66) ���n�߂��B�@�ۈ�{�݂ɂ͌��݁A0 - 5 �̃u���W����t�B���s���̊O���Ђ̎q�ǂ����� 22 �l������ 8 �s������ʂ��B
2019 �N 10 ������n�܂����c�ۖ������B�@�F�O�ۈ�{�݂��ΏۂƂȂ�ɂ́A�ۈ�m���i�҂̐���A�q�ǂ� 1 �l������̕ۈ玺�̖ʐςȂǁA���̈��̊�����K�v������B�@�������A���N 9 �����܂� 5 �N�Ԃ̗P�\���Ԃ��݂���ꂽ�B�@�w���ł� 4 �N�O������{�l�X�^�b�t�������A���{��ŏ��ލ쐬������ȂNJ�����w�͂����Ă����B�@�������A���H�s����{�݂ւ̗������蒲���ŁA������錩�ʂ��͗����Ă��Ȃ��B
�ی�҂̑����Ζ��ɍ��킹�ăo�X���}
�ł������n�[�h�����A���{�̕ۈ�m���i��L����E�����m�ۂ��邱�Ƃ��B�@���c�Z���́u���t�̖�肩��A�u���W���l�����{�̕ۈ�m���i�����͓̂���B�@25 �N�ԑ����Ă������A���������ł���ɂȂ�Δ��Ɍ������B�v�Ƙb���B �w���ɒʂ��q�ǂ���ی�҂̑唼�́A���{�ꂪ�s���R���B�@�ۈ�m�ɂ́A�|���g�K�����u���W�������̗������������Ȃ��B�@�u���W���̋������i�����E�������l���邪�A���{�̕ۈ�m���i�����E���̓p�[�g 1 �l�B�@�w���̋K�͂ł́A�Œ� 2 �l�̕ۈ�m���펞�Ζ�����K�v������Ƃ����B
�w���̉^�c�͕ی�҂���̌��ӂ�����B�@�����A�V�^�R���i�ɂ��ق��~�߂╨�����ŁA�ی�҂̐����͌������B �c�ۖ������ɂ��ی�҂ւ̕ۈ痿�⏕���A�w���ɂƂ��Ĉ��肵�������ɂȂ��Ă����B�@���c�Z����́A�H��œ����ی�҂̑����Ζ���c�Ƃɍ��킹�āA�����o�X�Ŏq�ǂ������𑗌}���Ă���B�@�q�ǂ����̒�������A�E�����a�@�ɘA��čs���B�@���Ē��j��������������n 3 ���̃n���P�W�����I���� (36) = ���ߍ]�s = �́u���{�ꂪ�����炸�A���{�̉��ɂȂ��߂Ȃ������B�@�e�̕s�K���ȋΖ��ɂ��Ή����Ă����w���́A�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ł��B�v�Ƙb���B
�����Ƃ̒S����@���͊�ɘa��v�]
���ꌧ���ɂ͋ߋE�S�̂� 6 ���A�� 1 ���l�̃u���W���l����炷�B�@���������Y�ɐ�߂鐻���Ƃ̊����͑S�� 1 �ʁB�@�����̓��n�u���W���l�炪�h���J���҂Ƃ��Đ����Ƃ��x���Ă���B�@���ɂ��ƁA��ɊO���Ђ̎q�ǂ����ʂ��F�O�ۈ�{�݂� 3 �{�݂���A���N 4 �� 1 �����_�Ŗ��A�w���v�� 150 �l���ݐЁB�@��������A�ۈ�m�̐������̊�����Ă��Ȃ��Ƃ����B�@�T���^�i�w���̉^�c���x������ NPO �@�l�͍��N 1 ���A�O�����呢�E���ꌧ�m���Ɩʉ�A�c�ۖ������̗P�\���ԉ������ɘa�Ȃǂ����⌧�ɋ��߂�v�]������n�����B
�O�����m��������܂ŁA�S���m����ȂǂŁA��ɘa�̗v�]���d�˂Ă����B�@���� 6 ���A�O���l�����{�݂ɂ��āu�O���̕ۈ�m�L���i�҂��\���Ȑl���z�u������ŁA���{�̎��i�҂� 1 �l�ȏ�z�u�v�Ƃ�������ɘa�����߂āA���ɗv�]�����o�B�@���q�ǂ��E�N�ǂ́u�|���g�K���ꂪ�ł���ۈ�m���m�ۂ���̂͌����I�ł͂Ȃ��B�@�F���ł͑Ή��ł��Ȃ��Z�[�t�e�B�[�l�b�g�̖������ʂ����Ă���w�����x���������B�v�Ƙb���B
�O���l�����̔F�O�ۈ�{�݂𑽐������鎩���̂ł��A����͓������B�@�����Ԋ֘A�H�ꂪ�W�܂鈤�m���B �����ő��̖� 9 ��l�̃u���W���l����炷�L���s�ł́A4 �� 1 �����_�ŁA6 �{�݂ɊO���Ƀ��[�c�̂���q�ǂ� 72 �l���ʂ��B�@�s�� 2020 �N�x�A�ۈ�̎��i�Ɂu�C�O�ɂ����鋳�����i�v��������悤���ɗv�]�����B�@�������蒲��������ۂ́A�s�̒ʖ��s���A�{�ݑ��ɏڂ�����̐��������Ă���B
�u�F�����x���̈��S�����v
�O���Ђ̐e�q�����̔F�O�ۈ�{�݂��^�c�����o�������� NPO �@�l���^�m�C�A�i�����s�j�̎R�c��H��\�����́u�O���Ƀ��[�c�����q�ǂ��̎��Ԃ�c�����A�K�ȕۈ�ɂȂ��邱�Ƃ́A�J���҂Ƃ��ĊO���l�������������{�Љ�̐Ӗ����v�Ǝw�E����B�@���̏�Łu�u���W���̕ۈ�m���i�҂����{�Ō��C����Ύ��i��F�߂�ȂǁA�����̐��I�m�����������l�ނ̈琬�x�������߂���B�@��ɘa�����ŏI���̂ł͂Ȃ��A�F�����x���̈��S�����m�ۂł���悤�s���ɂ��o�b�N�A�b�v���K�v���v�Ƙb���B (�ї����Aasahi = 8-23-23)
�O���l�Z�\���K���Ɍ� 100 ���Ԓ��̎��ԊO�J���@�đ�s�ٓ̕��X�����ޑ���
�O���l�Z�\���K���Ɍ� 100 ���Ԃ��鎞�ԊO�J�����������Ƃ��ĕđ�J����ē��� 17 ���A�đ�s�ٓ̕�������Ђƒj���H�꒷��J����@�ᔽ�̋^���ŏ��ޑ��������B�@�J��@�ᔽ�̋^���ŏ��ޑ������ꂽ�͕̂đ�s�̏���ٓ��X�� 48 �̒j���H�꒷�B�@�đ�J��ɂ��ƁA���̉�ЂƍH�꒷�͋��N 9 ������ 10 ���̊ԁA���ԊO�J���Ɋւ��鋦�肪�Ȃ��ɂ��ւ�炸�A�ٓ�������S������O���l�Z�\���K�� 2 �l���A 1 �����ōő� 100 ���Ԃ��鎞�ԊO�J�����������^���B�@�J����@�ł͋��肪�Ȃ��ꍇ�� 1 �� 8 ���Ԃ��ĘJ�������邱�Ƃ��֎~���Ă���B�@����ٓ��X�͑S���I�ɐl�C�������w�ق��E�̔����Ă���B (�R�`���� = 8-17-23)
��������A�x�m�R���Ŗ�h����C�O�̋Z�\���K�����莋
�u�J�ł��~�낤���̂Ȃ疽�Ɋւ��v
�A���s�j�X�g�̖������ (49) �� 13 ���uX �i���c�C�b�^�[�j�v���X�V�B�@�x�m�R���ŋN���Ă������Q�����B�@���݁A�x�m�R���ł͊C�O���痈����������̋Z�\���K������h���Ă��邱�Ƃ����ɂȂ��Ă���Ƃ����B�@������́u�Z�\���K��������Ă����Ɨl�A�x�m�o�R�̊댯���A���[���ƃ}�i�[��`���Ăق����ł��B�@���N���~�̎����͋Z�\���K���ň��܂��B�v�Ƃ����x�m�R�Ŏd�������Ă���W�҂̓��e�����p������Łu����͖{���ɐ[���Ȗ��B�@���ɂ͏���Ƀe���g��l�� �c�B
���E����������Ɓw�R���ł̖�h���悤�x�ƂȂ�̂�������܂��A�������A�J�ł��~�낤���̂Ȃ�A���Ɋւ��B�v�Ƃ��̊댯����i�����B�@���̏�Łu�����āA���̒��x�̎��o�œo���Ă���o�R�҂قǃS�~���̂ĂĂ������́B�@�܂��Z�\���K���͑�l���ł���Ă��邩��A�[���Ȗ��B�v�Ƃ��̖��_���w�E���Ă���B (���X�| = 8-13-23)
�O���l�Z�\���K������ ���Ə��̖@�߈ᔽ 7,200 ���� ���J��
�O���l�̋Z�\���K�������Ă��鍑���̎��Ə��̂����A��Ƃ̈��S�z�����s�\����������c�Ƒ�Ȃǂ̊��葝���������������������肷��Ȃlj��炩�̖@�߈ᔽ�����������Ə����A���N 1 �N�Ԃ� 7,200 ���������Ƃ������J���Ȃ̂܂Ƃ߂ł킩��܂����B�@�����J���Ȃ͋��N�A�O���l�������Ȃ���Z�p���w�ԋZ�\���K��������Ă���S���̎��Ə� 9,829 �����ɑ��ė������蒲�������{���܂����B�@���̌��ʁA�S�̂� 73.7% �ɂ�����A7,247 �����ʼn��炩�̖@�߈ᔽ��������A�����̌����A�@�߈ᔽ�̌����Ƃ��ɓ��v�����n�߂����� 15 �N�ȍ~�A�ł������Ȃ�܂����B
�ᔽ�ōł����������̂��A��Ƃ̈��S�z�����s�\���������肷����̂� 2,326 ���� 23.7% ���߁A�����Ŏc�Ƒ�Ȃǂ̊��葝�������̖������� 1,666 ���� 16.9% �ł����B�@���ɂ͎��ԊO��x���J������ 110 ���Ԃ��Ă����蒩�玞�Ԃ̂��ƂɃ^�C���J�[�h�őō��������肵�Ă������Ə����������Ƃ������Ƃł��B�@�܂��A�����Ȉᔽ���������Ƃ��ĘJ����ē������������P�[�X�� 21 ������܂����B�@�Z�\���K���̐��͋��N 12 ���̎��_�őS���ł��悻 32 �� 5,000 �l�ɂ̂ڂ��Ă��܂��B�@�����J���Ȃ́u�Z�\���K���̓K���ȘJ�������ƈ��S�̊m�ۂɌ����āA���Ə��ɑ���ē�w���ɗ͂����Ă��������v�Ƃ��Ă��܂��B (nikkei = 8-5-23)
�ݗ����i�Ȃ��q�ǂ��A7 �����ɓ��ʋ��t�^�ց@�@�����\�u�������v
�֓����@���� 4 ���A���{�Ő��܂�炿�Ȃ��狭���ދ������ƂȂ�A�ݗ����i���Ȃ��O���Ђ̎q�ǂ���ɑ��A�l���I�ȗ��R������{�ɂƂǂ܂邱�Ƃ��ł���u�ݗ����ʋ��v��^������j�𐳎��ɔ��\�����B�@�e���s�@�������Ă����P�[�X�������ȂLj��̏�����݂��邽�߁A�ݗ����i����q�ǂ��� 7 �����ƂȂ錩�ʂ����������B�@�������Ǔ�@�� 6 ���ɐ������A��F��̐\�����ł����҂ł���悤�ɂȂ����B�@����R�c�Ȃǂł́A���{�ł��������������Ƃ��Ȃ��q�ǂ����e�ƂƂ��ɑ��҂��ꂽ��A�Ƒ�������Ȃ�ɂȂ����肷�邱�Ƃւ̌��O��������A�ی�̂�������ۑ�ƂȂ��Ă����B
�o�����ݗ��Ǘ����ɂ��ƁA����̍ݗ����ʋ��̑Ώۂ́A���{�Ő��܂�A�����@�̎{�s���i6 ���̌��z���� 1 �N�ȓ��j�܂łɏ������Z�ŋ�����Ă���q�ǂ������B�@�����ދ��������o�����̂́A���{�ł̐�����������]����ꍇ�A��{�I�ɉƑ��ƂƂ��ɍݗ�����ʂɋ�����Ƃ����B�@�����A�e���s�@�ɓ������Ă�����A���� 1 1�N���̎��Y�������Ă�����A�����̑O�Ȃ��������肷��ꍇ�́u�ʼn߂�����������v������Ƃ݂Ȃ��A�Ώۂ���O�����Ƃ�z�肵�Ă���B
�����A�����@�̐����ɂ���đ��҂̃��[������������A�ݗ����i���Ȃ��܂܁A�ݗ����������q�ǂ��͍���A���Ȃ��Ȃ�Ƃ��������݂���A�u�������v�̑Ή��Ƃ����B�@�ݗ����i���Ȃ��A�����ދ��������o�Ă��A�������ފO���l�̂����A���{�Ő��܂����� 18 �Ζ����̎q�ǂ��͍�N�����_�� 201 �l�B�@����A�֓��@�����ʂ̎���𑍍��l�����A�ۂf����B
�ݓ��N���h�l�x���ٌ̕�m�u�������������v
�u�����g�A�Y�ݔ����ē����o�������_���B�v�@�֓��@���͋L�҉�ŁA�����𖾂������B�@����܂ŋ������҂̑Ώۂ̎q�ǂ��̕ی�ɑO�����Ȏp���������Ă������A���ǒ����ł́A���[���ᔽ�������O���l�ւ̌������ӌ��ɂ��z�����u�o�����X���Ƃ�̂͗e�Ղł͂Ȃ��v�Ƃ̌��������������߂��B�@�ݓ��N���h�l���x�����Ă����勴�B�ٌ�m�́A��F��\���҂ɂ��čݗ����ʋ��f����ہA�q�ǂ��̑��݂��\���ɍl������Ă��Ȃ������Ƃ��A����̕��j���u�@���̐������f�Ƃ��Ĉ��̕]���͂ł���v�Ƃ����B�@�����A�e�̎���ɂ���Ă͕ی�ł��Ȃ��ꍇ������Ƃ����_�́u����������̂͂�ނ����Ȃ����A�������������v�Ǝw�E�B�@�u�������v�̑Ή��Ƃ������Ƃɂ��Ă��u�����I�ɂ͋~�ς��Ȃ��Ƃ����錾�ɓ������A�s�����B�v�Ɣᔻ�����B (�v�ۓc�ꓹ�Aasahi = 8-4-23)
�q�q�ǂ��̍ݗ����ʋ����߂���@���̑Ή����j�r
�y�q�ǂ��̑Ώہz
�E ���{�Ő��܂�A�������Z�ŋ�����Ă���
�E ���{�ł̐������A�^�Ɋ�]���Ă����y�ΏۊO�Ƃ���e�̎���z
�E �s�@�ɓ�������
�E �U���ݗ��J�[�h�̎g�p��U�������ȂǓ��Ǎs���̍����Ɋւ��ᔽ������
�E �g�p�┄�t�Ȃǔ��Љ�̍����ᔽ������
�E ���� 1 �N���̎��Y��������
�E �����̑O�Ȃ�����
�@�i�o�����ݗ��Ǘ����ւ̎�ނɊ�Â��B�@�ʂ̎��Ă��ƂɎ���𑍍��l�����A������ꍇ������B�j
���w�Z���̊O���l���w���A�A�E��g��ց@�ݗ����i�̊��������
�o�����ݗ��Ǘ����́A���w�Z�𑲋Ƃ����O���l���w���̏A�E����g�傷��B�@�����Ȋw�Ȃ��F�肵�����w�Z�̑��Ɛ��̏ꍇ�A��w�����݂ɉ��߂�B �D�G�ȗ��w���ɍ����Œ蒅���ē����Ă��炤�_���B ���t�ɑ��Ƃ��闯�w���̐i�H�I���ɊԂɍ����悤�A�N���ɂ��K�C�h���C�������������j���B�@��w����w�Z�𑲋Ƃ������w���炪���{�ŏA�E����ꍇ�A�u�Z�p�E�l���m���E���ۋƖ��v�Ƃ����ݗ����i�邱�Ƃ������B�@���̍ݗ����i��F�߂邩�ǂ����̔��f�ł́A��U���Ă����ȖڂƁA�A�E��̋Ɩ��Ƃ̊֘A�����|�C���g�ɂȂ�B
���ǒ��̓K�C�h���C���ŁA�L������̒m���邱�Ƃ�ړI�Ƃ�����w�̑��Ǝ҂ɂ��ẮA��U�ȖڂƏA�E��̋Ɩ��Ƃ̊֘A�����u�_��ɔ��f�v����ƋK��B�@����A�E�Ƃ�������ɕK�v�Ȕ\�͂̈琬��ړI�Ƃ������w�Z�̑��Ɛ��ɂ��Ă͌����A�u�������x�v�̊֘A����K�v�Ƃ��A�呲��茵�i�ɉ^�p���Ă����B�@����A���̃K�C�h���C�������߁A���ȏȂ̔F��Z�̑��Ɛ��ɂ��ẮA�呲�̗��w���Ɠ������u�_��ɔ��f�v����悤�ɂ���B�@���Ȃ́A���̍������炪���H����Ă�����w�Z��F�肷��V���Ȑ��x��݂��A9 �����ɂ��F�肷��\��B
���{�w���x���@�\�ɂ��ƁA2021 �N�x�ɐ��w�Z�𑲋Ƃ������w���͖� 3 �� 2 ��l�ŁA���w���S�̂̔����߂����߂�B�@�����A�� 1 ���͋A���E�o�����Ă���B�@�ݓc���Y���c���߂�u���疢���n����c�v�� 4 ���A�O���l���w���̒蒅�Ɍ������������Ȃǂ�B�@2018 �N�ɖ� 48% �����������A�E�����A2033 �N�܂ł� 60% �Ɉ����グ��ڕW���f�����B (�v�ۓc�ꓹ�Aasahi = 7-29-23)
�l��s���̉�앪��A�O���l�J���Ҏ���ɘa�����J�n�@�ۑ��
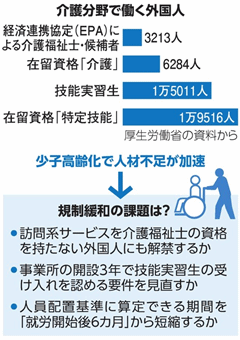
��쌻��̐l��s�����������邽�߁A�����J���Ȃ� 24 ���A�O���l�J���҂Ɋւ���K�����ɘa��������Ō����ɓ������B�@���݂͌����F�߂��Ă��Ȃ��K��T�[�r�X�̉��ւȂǂ��������A�R�~���j�P�[�V�����Ȃǂ̉ۑ���w�E����Ă���B�@���Ȃ͔N���܂łɕ��j�����܂Ƃ߂�l�����B
���̓������グ���L���҂�̌������ 3 ���ڂ̘_�_��B�@�@ ��앟���m�̎��i�������Ȃ��O���l�ɔF�߂��Ă��Ȃ��K��n�T�[�r�X�ւ̏]���A�A ���Ə��̊J�� 3 �N�ŋZ�\���K���̎����F�߂�v���̌������A�B ���{�݂̐l���z�u��ɋZ�\���K������Z��ł�����Ԃ��A�J�J�n�� 6 �J���Ƃ���v���̒Z�k�A�ɂ��č��㌟������B�@�ψ�����͋K���ɘa�Ɏ^������ӌ����オ��������A�R�~���j�P�[�V�����̖ʂ���T�d�_���o���B
���q����̉����ŁA��앪��̐l��s���͐[��������B ���Ȃ� 2019 �N�x�Ɣ�ׁA40 �N�x�ɂ͖� 69 ���l���₷�K�v������ƌ����ނ��A21 �N�x�܂ł̑������� �� 4 ���l�ɂƂǂ܂�B�@�K���ɘa���߂����̂́A���̎Y�Ƃɔ�ׂĒႢ�E���̏��������P���邱�ƂŐl�ނ��m�ۂ��A�O���l�J���҂ɖ�˂��L���ĕs������₤�_��������B
�ɘa��A����I�ȓ��e
������œ��Ȃ́u��쌻�ꂩ��͊O���l���l�ނ̋Ɩ��g���]�ވӌ�������v�Ɛ����B�@�Z�\���K���x�̔p�~���j��ł��o�������{�̕ʂ̗L���҉�c���A�V���x�ɂ��č��H�ɍŏI���܂Ƃ߂�̂܂��A��̓I�Ȋɘa������܂Ƃ߂�l�����������B�@�K����Ȃǂ̖K��n�T�[�r�X�͗��p�҂Ɖ��҂� 1 �� 1 �ōs�����Ƃ������A����܂Ŏ��i���Ȃ��O���l�ɂ̓R�~���j�P�[�V�����ʂ̕s������֎~����Ă����B�@�ψ�����͕����ŒS���������Ŋɘa��F�߂�ӌ����o������A�u�H����|���Ȃǂ͓K�ɑΉ��ł���\�͂����߂��A�T�d�Ȕ��f���K�v�v.�u���t�̖��A���{�̕����╗�K���l����Ƃ܂������v�Ƃ������w�E���������B
�Z�\���K���̎����F�߂�u3 �N�v�v���ɂ́u���Ə����ƂłȂ��@�l�P�ʂōl���Ă����̂��ǂ��v�Ȃǎ^���_�����������B�@�z�u��ւ̎Z��� 6 �J������Z�k����Ăɂ́u�������x�����A���K�����Ɩ��Ƃ��ďA�J���Ă���B�@�A�J������̃J�E���g���v�Ƃ̎^���_�̈���A�u���{�l�ł܂��͐l���z�u�������Ƃ��O������B�@���K���ŃM���M���������͍̂��ӂ������Ȃ��v�Ƃ̈ӌ����������B�@����A���J�Ȃ��������K���ɘa��͌���I�ȓ��e�ƂȂ��Ă���B�@�ψ�����́u�i���ۓI�Ɂj�O���l�ނ̎�荇���ɂȂ��Ă���B�@�I���K�v������B�v�ȂǂƔ��{�I�ȑ�����߂鐺�������ꂽ�B
��앪��ł� 17 �N 9 ���ɉ�앟���m�̎��i�擾�������Ƃ���ݗ����i�u���v��n�݁B�@�����A�n�[�h���͍����A���݂��̎��i�œ����̂� 6,284 �l�ɂƂǂ܂�B�@���{�͍Œ��� 5 �N�̍ݗ����ԂɌ�����Z�\���K���x��p�~������j�����A�ݗ����i�u����Z�\ 2 ���v�ɂ��ẮA�Ώۂ����݂̌��݂Ƒ��D�E���p�H�Ƃ� 2 ���삩��_�ƁA���ƁA���H���i�����A�O�H�Ȃ� 11 ����ɍL����ƌ��߂��B�@2 ���͉Ƒ��ѓ���i�Z���\���B�@�������� 2 ���̑ΏۂƂȂ��Ă��Ȃ��B�@�ݗ����i�����̕�������������{��\�͂����߂��Ă���B�@�ψ��̈�l�́u���͓��ɗv���𑼂̎Y�Ƃ�荂�����Ă���B�@���{�ɐl�����Ȃ��Ȃ��Ă���B�v�Əq�ׂ��B (�֍��T��Aasahi = 7-24-23)
�X�֕��̒��� MDMA �� 200 �� �x�g�i�����Ђ̋Z�\���K����ߕ߁E�����@���A�}�����^��
�x�g�i�����Ђ̒j�����A��������� 200 ���𖧗A���悤�Ƃ����^���ŁA�ߕ߁E��������܂����B�@����������m�������s�ɏZ�ރx�g�i�����ЂŁA�Z�\���K���̃z�A���E�~���E�h�D�b�N�e�^�҂ƁA��Ј��̃z�A���E�e�B�E�g�D�C�E�Y�I���e�^�҂́A���N 6 ���A��������� MDMA �� 200 ���i���[���i 120 ���~�����j���x�g�i�����疧�A���悤�Ƃ����^����������Ă��܂��B �@�ŊE�����C�O���瓞�������X�֕��̒�����A�{�g���ɓ�����������������܂����B�@�x�@�� 2 �l�̔F�ۂ𖾂炩�ɂ��Ă��܂���B (CBC = 7-22-23)
�X�[�_���l�ɍݗ����i�����ց@��s���܂����u�ً}���[�u�v
���R�Ə��R���g�D�u�����x������ (RSF)�v�̐퓬�������A�t���J�k�����X�[�_��������A�֓����@���� 14 ���A�X�[�_���l����s���𗝗R�ɓ��{�����ɂƂǂ܂葱���邱�Ƃ���]�����ꍇ�A�ʂ̎���܂��A�ً}���I�ȑ[�u�Ƃ��āA�A�J�\�ȍݗ����i��������Ɣ��\�����B�@�X�[�_���ł� 4 ���A���R�� RSF ���ՓˁB�@���Ԃ̉��P�Ɍ����������͌���ꂸ�A�����̐l�����O�ɓ���Ă���B
�o�����ݗ��Ǘ����ɂ��ƁA���{�����ɍݗ�����X�[�_���l�͖� 400 �l�B�@���݂̍ݗ����i�̊����������Ă���l������Ƃ����A�A�J�\�ȁu���芈���v�̍ݗ����i��F�߂�B�@�����ދ������܂��Ă���l�ɂ��Ă��A�{�l�̈ӎv�ɔ����đ��҂��邱�Ƃ͂��Ȃ��Ƃ����B�@�ߋ��ɂ��A�N�[�f�^�[�Ȃǂ��A�~�����}�[�l��ɓ��l�̑[�u���Ƃ����Ⴊ����B�@�֓��@���́A2021 �N�̃A�t�K�j�X�^���̐���������A���N�ɓ����� 137 �l�̃A�t�K�j�X�^���l���F�肵�����Ƃ����炩�ɂ����B�@��N�́A1 �N�Ԃ� 147 �l�̃A�t�K�j�X�^���l���ƔF�߂Ă���B (�v�ۓc�ꓹ�Aasahi = 7-14-23)
�u�s�@�c���x�g�i���l�A������ЂɁv���H���K�����p�����h���r�W�l�X���@��Њ��������q�@���{�x
�s�@�c�����Ă������Z�\���K���̃x�g�i���l�����Ă����Ƃ��ē��Ǔ�@�ᔽ�i�s�@�A�J�����j�e�^�Ől�ޔh����Ђ́u���X�v�� JAPAN�i��s����j�v�����Ј��̒j�炪�ߕ߂��ꂽ�����ŁA�j���u���ɂ������̉�Ђɕs�@�c���̃x�g�i���l��h�����Ă����v�Ƌ��q���Ă��邱�Ƃ� 5 ���A�{���W�҂ւ̎�ނŕ��������B�@���{�x�́A�h����Ђ����K�悩�瓦�S�����Z�\���K�����𗬃T�C�g (SNS) ��ʂ��ďW�߁A�s�@�ɓ������Ă����Ƃ݂Ď��ԉ𖾂�i�߂�B
�{�x�ɂ��ƁA���X�v���Ђ̊����Ј��A�����^��e�^�� (55) �́A�ߘa 3 �N 6 �� - ���N 3 ���A���K�悩�瓦�S�����s�@�c���̌��Z�\���K���̃x�g�i���l�j�� (36) ��ēc���X�i��s���j���o�c���郊�T�C�N���H��œ������Ă����^����������Ă���B�@���Z�\���K���́uSNS ��ʂ��ăx�g�i���l�R�~���j�e�B�[�ɃA�N�Z�X���A���X�v���Ђɂ��ǂ蒅�����v�Ɛ����B�@�{���W�҂ɂ��ƁA���e�^�őߕ߂��ꂽ�ēc���X�̖����́u�l��s���Ń��X�v���Ђ𗊂����v�Ƃ�����|�̋��q�����Ă���Ƃ����B
�{�x�̓��X�v���Ђ� SNS �Ŏ��H�����Z�\���K���̃x�g�i���l����W�߁A�l��s���ɂ�������Ƃɔh������r�W�l�X��W�J���Ă����Ƃ݂āA���Ђƃx�g�i���l�R�~���j�e�B�[�Ƃ̊W�ׂĂ���B�@�Z�\���K�����߂����ẮA�Ⴂ�����⌻��ł̖\�͂���ɍ����ŔN�� 7 ��l�����K�悩�玸�H���Ă���A���x�̌������Ɍ������c�_���i�߂��Ă���B (sankei = 7-5-23)
���@���@��
���H���K����W�܂� SNS �ŋ��l�@�s�@�A�J�����e�^�Ŕh����Њ����� 3 �l�ߕ�
�ݗ��������߂��A�s�@�ɑ؍݂��Ă����x�g�i���l�����T�C�N���H��œ��������Ƃ��āA���{�x�������ۂ� 14 ���A���Ǔ�@�ᔽ�i�s�@�A�J�����j�e�^�Ől�ޔh����Ёu���X�v�� JAPAN�i��s����j�v�� 50 ��̊����Ј���j 3 �l��ߕ߂����B�@�{���W�҂ւ̎�ނŕ��������B�@���S�����Z�\���K���炪�W�܂�𗬃T�C�g (SNS) ��ʂ��ăx�g�i���l�̎d�����������A����Ă����Ƃ݂��A�{�x�͎��ԉ𖾂�i�߂�B�@�{���W�҂ɂ��ƁA�ߕ߂��ꂽ�̂̓��X�v���Ђ̎Ј� 2 �l�ƁA���T�C�N���H����o�c����ēc���X�i��s���j�̖����̒j�̌v 3 �l�B
3 �l�͋��d���A���N 3 ������܂ł̖� 1 �N���ɂ킽��A�Z�\���K���Ƃ��ē������Ă����x�g�i���l�̒j������{���Ύs�̕ēc���X�̃��T�C�N���H��œ��������^����������Ă���B�@�{���W�҂ɂ��ƁA���K�悩�瓦�S�����x�g�i���l��ł��� SNS ��̃O���[�v��ʂ��A���U�������K��������X�v���Ђ��ٗp�B�@��ƈ��Ƃ��Ĕh�����Ă����Ƃ����B
���N 3 ���A�ēc���X�̍�ƈ� 4 �l�����Ǔ�@�ᔽ�i�s�@�c���j�̋^���Ō��s�Ƒߕ߂���Ĕ��o�B�@��������Ⴂ�����⌻��ł̖\�s�Ȃǂ���Ɏ��H�������Z�\���K���ŁA�Љ�Ȃǂ��������������� 15 ���~�قǂ������Ƃ��Ď���Ă����B �����ł͔N�� �V ��l����Z�\���K�������H���Ă���A�{�������́u���X�v���Ђ̂悤�ȃu���[�J�[�����s���Ă���\��������v�Ƙb���A�g�D���ׂ�B (sankei = 6-14-23)
�u����E���Ŋ�����������悤���߂�ꂽ�v�@����s�ŊO���l�Z�\���K�����s���Ȉ����i���@������
������������s�̂����ߍH��ŋZ�\���K���Ƃ��ē����Ă����t�B���s���l�̏��� �Q �l���A����s�ɂ���Z�\���K�����Ǘ�����c�̂ɑ��u���Ƀv���C�x�[�g�ȋ�Ԃ��Ȃ��v�A�u����E���Ŋ�����������悤���߂�ꂽ�v�Ȃǂ̕s���Ȉ��������Ƒi���A���Q�����̐������������Ă��邱�Ƃ�������܂����B�@�i���Ă���̂́A�t�B���s���l�� 20 ��� 30 ��̏����̎��K�� 2 �l�ł��B
���K���ٌ̕�m�ɂ��܂��ƁA�Q �l�͖���s���Y���U�������g�����Ǘ����闾�ł̐����ɂ��āu���N�I�Ȏ��K�����𑗂ꂸ�v���C�x�[�g�ȋ�Ԃ��Ȃ��v�Ƃ��Ă��܂��B�@�܂��A���̃X�^�b�t�Ɂu����E���Ŋ�����������悤���߂�ꂽ�v�ȂǂƂ��Ă��āA����A�g���ɑ��đ��Q���������߂�\��������Ƃ��Ă��܂��B
�u���̐l�̐�L�ł����ԁA�v���C�x�[�g�ȋ�Ԃ��m�ۂ���ĂȂ��B�����炪����Ă��邱�Ƃ��_��ᔽ��l���N�Q�Ȃǂ̖�肪����Ɩ@�I�ɑ��Q�������Ă��������ׂ��ł��A�Ƃ����ӎv�͓`�����B�i���K���ٌ̕�m�E�F���ٌ͕�m�j�v
����A����s���Y���U�������g���͍��̊�Œ�߂�ꂽ�Q���̍L�������Ă��Ȃ����Ƃ�F�߂Ă��āA����A���C���s���L�����m�ۂ���\��Ƃ��Ă��܂��B�@�܂��A����E���Ŋ�����������悤���߂����Ƃɂ��ẮA���K�����a�@�ł̐f�@��f�������Ƃ���A�g���̏����X�^�b�t 3 �l���������m�F���悤�Ƃ������߂������Ƃ��ċ��v�ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��܂��B�@�g����������A�ٌ�m�𗧂ĂĎ����m�F���s���Ă����Ƃ��Ă��܂��B (KTS �������e���r = 6-26-23)
�x�g�i���l�́u�Ńo�C�g�v�}���@�~���ŋZ�\���K�����������҂���
�O���l�Z�\���K��
�L���R�s�[ (6-23-23)
�O���l�Z�\���K���́u�J���g���v�����@�ė��c�̂ƘA�������@�ȘJ�����́u�}�~�́v��
�O���l�Z�\���K���̎����Ƃ��ē���u�ė��c�́v�ƘJ���g���̘A���������A�O���l�Z�\���K���̂��߂̘J���g�����������A19 ���ɓ����s���Ō������������B�@�ė��c�̂��哱�����g���̌����͒������Ƃ����B�@�ė��c�̂́A�C�O�̋Z�\���K������o���@�ւƍ����̎����Ƃ��Ȃ��A�����Ƃ̊ē������c���c�́B�A�������ɂ��ƁA�ė��c�̂̐����������č��̊č����ǂ����Ă��炸�A�ꕔ�̊ė��c�̂̉��ł͗ȘJ�����œ������K���ɖڂ��͂��Ă��Ȃ��Ƃ���������B
�A�������̌������ǒ��ŁA�J�g�̎��s�ψ����ɑI�o���ꂽ�{�i�������́u����I�Ȏ��g�݂��B�@������Ƃ����ė��c�̂��瑗��o�����K���̑������g�����ɂȂ�A�����Ƃɑ��ĘJ�������N�������Ȃ��}�~�͂ɂȂ�v�Ƙb�����B�@�ė��c�̂̓��a�i�Ђ��j�����g���i�F�{�s�j�̗������ŁA�����s�ψ����ɑI�o���ꂽ���c�^�����́u���͍����Ă��Ȃ��l�i�Z�\���K���j�ɂ��A�J�����̃��X�N������ی��̂悤�ȃC���[�W�Ő������Ċ��U���Ă��������v�ƌ�����B�@�����_�ł̑g�����́A�F�{���ƐÉ����̃x�g�i���l�ƃC���h�l�V�A�l�Z�\���K���̖� 30 �l�ŁA50 �l���x�ɑ����錩���݂Ƃ����B (���c�W��A�����V�� = 6-19-23)
���{�A�ݗ����i�u����Z�\ 2 ���v�� 11 ����g����t�c����
���{�� 9 ���A�n�������Z�\��L����O���l�J���҂��擾�ł���ݗ����i�u����Z�\ 2 ���v�����݂� 2 ���삩�� 11 ����֊g�傷��Ă��t�c���肵���B�@2 �����擾����Ζ������A�J���\�ɂȂ��A�Ƒ��̑ѓ����F�߂���B�@���{���l�������Љ�ɓ˓����钆�A�O���l�J���҂̉i�Z�ɓ����J���傫�ȓ]���_�ƂȂ�B�@����Z�\�͐l��s�����[���ȓ���Y�ƕ���ŊO���l������邽�߁A2019 �N 4 ���ɃX�^�[�g�����B�@�ݗ����Ԃ��ʎZ 5 �N�́u1 ���v�ƁA�ݗ����Ԃ̍X�V�ɏ�����Ȃ��u2 ���v������B�@1 ���͑������x�̒m���E�o���A2 ���͂��n�������Z�\�����߂���B �����������������ł���ΐE������R�ɑI�ׂ�u�]�Ёv���ł���B
1 ���͑S 12 ���삠��A�Ƒ��̑ѓ��͔F�߂��Ă��Ȃ��B�@����A2 ���͉Ƒ��̑ѓ����\�����A����܂ł́u���݁v�A�u���D�v�� 2 ���삵���F�߂Ă��Ȃ������B�@����A2 ���̒lj������܂����̂́A�� �r���N���[�j���O�A�� �����ƁA�� �����Ԑ����A�� �q��A�� �h���A�� �_�ƁA�� ���ƁA�� ���H���i�����ƁA�� �O�H�� - - �� 9 ����B12 ����̂����u���v�͕ʐ��x�� 2 ���Ɠ��l�̑ҋ����F�߂��Ă���A1 ���̑S����Ŗ������A�J���ł��邱�ƂɂȂ�B
�������A2 ���͌���ē҂Ƃ��ċƖ����ł�����x�̋Z�\�����߂��A�擾�̃n�[�h���͍����B�@���H�ȍ~�A�e����� 2 ���ւ̈ڍs���\�������ɂ߂鎎�����n�܂錩�ʂ��B�@�o�����ݗ��Ǘ����ɂ��ƁA3 �������݂� 1 ���̍ݗ��Ґ��� 15 �� 4,864 �l�A2 ���� 11 �l�B�@�O���l�J���҂̎���������ẮA���{�̗L���҉�c�� 4 ���A���ۍv����ړI�ɊO���l�̋Z�\���琬����u�Z�\���K�v���x��p�~���āA����Z�\�ɃL�����A�A�b�v���Ă��炤���߂̐V���x�̐ݗ������߂钆�ԕ��܂Ƃ߂Ă���B (�ѓc���A���R�͂�ȁAmainichi = 6-9-23)
���@���@��
�u����Z�\ 2 ���v�啝�g��ց@�O���l�J���ҁA�i�Z�ɓ��@���{���j
�l��s���̕���ŊO���l�J���҂������ݗ����i�u����Z�\�v�ɂ��Đ��{�� 24 ���A�ݗ����Ԃ̍X�V�ɐ������Ȃ��A�Ƒ����ѓ��ł���u2 ���v�����s�� 2 ���삩�� 11 ����Ɋg�傷����j�������}�Ɏ������B�@�^�}���̗������o�āA6 ���̊t�c�����ڎw���B�@�o�ϊE�Ȃǂ̗v�]�����[�u�ŁA���L������ŊO���l�̉i�Z�ɓ����J���]���_�ƂȂ邪�A�����}�̕ێ�h�Ȃǂ���́u������̈ږ��̎���ɂȂ���v�Ƃ������������\�z�����B
�� �l��s�����[���@2 ���� �� 11 �����
����Z�\�́A�[���Ȑl��s���ɑΉ����邽�߂ɁA���̐�含��������͂̊O���l������鐧�x�B�@2019 �N 4 ���ɓ�������A1 ���� 2 ��������B�@1 ���ɂ͈��H���i�����A�Y�Ƌ@�B�Ȃǐ����A�_�ƁA���Ȃǂ� 12 ���삪����A�u�������x�̒m���܂��͌o���v�����߂���B�@�ݗ����Ԃ̏���� 5 �N�ŁA�Ƒ��͑ѓ��ł��Ȃ��B�@1 ������̃X�e�b�v�A�b�v��z�肵�� 2 ���́u�n�������Z�\�v�܂ŕK�v�ŁA���ꓝ�����ł���m���Ȃǂ��v��B�@�ݗ����Ԃ̍X�V�ɐ����͂Ȃ��A�Ƒ��ѓ����\�����A�l��s�������ɐ[���Ȍ��݂Ƒ��D�E���p�H�Ƃ� 2 ����Ɍ����Ă����B
���N 2 �������݂ŁA1 ���͖� 14 �� 6 ��l���邪�A2 ���� 10 �l�ɂƂǂ܂�B ����Z�\���x�̓�������l��s���͑������A�e��������ǂ���Ȓ���o�ϊE�́u�l�ނ̒蒅�v�ɂȂ��� 2 ���̕���g���v�]���Ă����B ���{�͂��̓��̎����}�̊O���l�J���ғ����ʈψ���ŁA�������� 11 ����� 2 �����g�傷����j���������B�@��앪��́A�ݗ��������\�Ȏ��i�u���v�����ɕʓr���邽�߁A����Z�\ 2 ���ɂ͊܂߂Ȃ��Ƃ����B (asahi = 4-24-23)
���ǖ@�����Ă������ց@�^�}�A�̌�������@��\���������҉\��
��F��̐\�����ł��O���l�̑��҂��\�ɂ�����Ǔ�@�����Ă� 8 ���̎Q�@�@���ψ���ŁA�����A�������}�Ȃǂ̎^�������ʼn����ꂽ�B ��}�̓��{�ېV�̉�ƍ�������}���^�������B ��������}���@����ӌ��c�Ă̒�o�ȂǂŒ�R�𑱂��Ă������A�����Ă� 9 ���̎Q�@�{��c�ʼn��A�������錩�ʂ����B�@8 ���̖@���ς́A�����⋤�Y�Ȃǂ��̌��ɔ����钆�A���v���ψ����i�����j���E���ŊJ�ÁB�@�����̐ΐ��䎁�͓��_�Łu�@�Ă���������i��\���҂��j�������҂���A�����A����A�s�E����B�@�l�̖���D���@�Ăɂ͐�ɔ����v�Ƒi�����B�@�̌��̍ہA�ψ����Ȃɋl�ߊ������}�c�����^�}�c���Ƃ��ݍ����ɂȂ�ȂǁA�ψ���͈ꎞ���R�Ƃ����B
���{�́A��ƔF�߂��Ȃ�����������҂����ފO���l�������A�\�����d�˂đދ���Ƃ�悤�Ƃ���P�[�X���莋���Ă����B�@2021 �N�̒ʏ퍑��ŁA3 ��ڈȍ~�̐\���҂́u�����̗��R�v��������Ȃ���Α��҂ł���悤�ɂ��鋌�@�Ă�����ɒ�o�������A���ǎ{�݂ŃX�������J�l�̃E�B�V���}�E�T���_�}������i���� 33�j���S���Ȃ������ƂŐ��_�������B�@�̌������������o�܂�����B�@�����A����̉����ẮA���̍��i���ێ������܂ܒʏ퍑��ɒ�o���ꂽ�B
���҂�W����s�ׂȂǂ�Ώۂɔ����t���̑ދ����ߐ��x��n�݂���ق��A�����I�ɋA������ē����ł��Ȃ����Ԃ� 5 �N���� 1 �N�ɒZ�k���A���₩�ȋA���𑣂��B�@���҂܂Ō����A���e�Ƃ��Ă����K������߁A�x���҂�u�ė��l�v�̊ē��Ő����ł���u�ė��[�u�v��݂��A���e�����ɑދ��葱����i�߂�Ƃ��������e�����荞�܂ꂽ�B�@�������瓦�ꂽ�l����ɏ����ĕی삷��u�⊮�I�ی�Ώێҁv���x���n�݂���B�@�O�@�ł̐R�c�ŁA�����͓�F���R�������O�ҋ@�ւ̐ݒu�����߂���������Ȃ������B
����A�Q�@�R�c�ł́A��F��̕s���R�����ꕔ�̒S���҂ɕ��Ă������Ƃ��������A���ǂ̏�����Έオ���ɐ������܂��e�҂�f�@�����Ǝw�E�����ȂǁA���Ǎs�����߂����肪���X�ɔ��o�����B�@����ł��^�}�� 21 ���̍������������钆�A�̌������������B �@���ςł͐��ƍ߂̋K����������Y�@�Ȃǂ̉����Ă̐R�c���T���Ă���A�����Ƃ��Ă��u��������ʂ��Ȃ�������Ȃ��i�����j�v�Ƃ̎�����邱�Ƃ���A����ȏ�̒�R�����������B�@�㔼����ő�̑Ό��@�Ăƈʒu�Â���h�q��z�̍����m�ۖ@�Ă��߂���A���T�ɂ������܂��̌��œO��R�킷��\�����B (����]���A�������Aasahi = 6-8-23)
�� ���Ǔ�@�����Ă̍��q
- ��F��̐\�����ł��A3 ��ڂ̐\���ȍ~�͑��҂��\��
- ���҂�W����s�ׂȂǂɁA�����t���̑ދ����ߐ��x��n��
- ���e�̑���Ɏx���҂�̊ė����ɒu���u�ė��[�u�v��
- �������瓦�ꂽ�l����A��ɏ����ĕی삷��u�⊮�I�ی�Ώێҁv���x��n��