インド 13 億のマイナンバー コロナ禍で貧困層を救ったデジタル技術
新型コロナウイルスが猛威をふるったインドで、ワクチン接種や貧困層への給付金の配布にデジタル技術が活用されている。 膨大な情報管理を可能にする「インド版マイナンバー」だ。 「かつては遠くの役所まで出向いても、給付金をもらうための手続きが大変だった。 直接、銀行口座に送金してもらえるのは、とても助かった。」 東部コルカタの主婦ルマ・モンダルさん (57) は、コロナ禍で政府が行った現金給付についてこう語った。
以前は給付を受け取るために必要書類を用意して役所に行った。 担当者がいなかったり、賄賂を要求されたり。 大勢の請求者が群がり、あきらめて帰ってきたこともある。 今回、政府は約 4 億 2 千万人の貧しい人らに対し、計 6,900 億ルピー(約 9,900 億円)を給付。 市場で働く夫が職を失ったモンダルさんの口座にも、3 回に分けて計 1,500 ルピー(約 2,200 円)が振り込まれ、日用品の購入に充てることができたという。
ニューデリーの病院でコロナのワクチンを接種したシャシ・グプタさん (63) は、スマホにインド政府の提供するアプリをインストールし、そこから申請した。 「予約はスマホで 5 分もかからなかった。 昨日予約し、待ち時間はほとんどなかった。」 日本のように自治体から送られてくる接種券は必要ない。 接種の日時や場所をスマホで選んで予約し、接種後には証明書もスマホに届く。 各病院のワクチンの在庫状況もわかる。 インドでは 9 億回分以上の接種が終わった。
「世界最大の生体認証 ID プラットフォーム」
こうしたデジタル化を支えているのが、「アーダール」と呼ばれるインド版マイナンバーだ。 12 桁の個人識別番号で、アーダールはヒンディー語で「基礎」を意味する。 ワクチン接種では、希望者が予約時に専用アプリにアーダールの番号を登録し、本人確認する。 現金給付では、アーダールとひもづいている銀行口座に政府が送金した。
アーダールは、読み書きのできない人のために指紋や顔写真、虹彩(こうさい)といった生体認証を使って個人を識別し、なりすましによる不正を防ぐ。 2010 年から登録が始まり、これまでに 13 億人以上の登録が済んだとされる。 成人の 95% が保有しているとの調査結果もあり、「世界最大の生体認証 ID プラットフォーム」といわれる。
政府がアーダールを整備したのは、インドでは子の出生後の届け出が徹底されず、管理も行き届いていなかったためだ。 自動車免許やパスポートを持っていない人は、身分を証明できず、銀行口座をつくることもできなかった。 さらに政府は貧困層を正確に把握しきれず、必要な社会保障の補助金や政策が届かないばかりか、偽造された身分証明書による不正受給も多かった。 給付金が必要な人々に届く前に、役所などで中抜きにされてしまう問題もあった。
アーダールによって、貧困層の口座保有が増え、携帯電話を使った銀行振り込みなど、さらに用途は広がっている。 政府から付与された納税者番号とアーダールをひもづけることで、脱税の防止にも活用している。 迷子や誘拐された子を保護した際、親を見つけやすいという利点もある。
IT 人材を大量投入
個人識別番号を整備するにあたり、インドの強みは米国シリコンバレーで長年活躍したインド人企業家や IT 技術者の存在だった。 システム開発にも多くの民間技術者が関わってきた。 インド政府は担当の固有識別番号庁をつくった。 初代長官として整備を進めたのは、インド IT 大手インフォシスのナンダン・ニレカニ共同会長だ。
ニレカニ氏は取材に「個人の証明書がなくて銀行口座を作れない人が大勢いた。 今では 7 億人がアーダールと銀行口座をリンクさせている」と話す。 「パンデミックの時にこそ必要不可欠なものだということが証明された。 貧しい人への給付は、他国では時間も手間もかかったが、インドは迅速だった。 間違いなく人々の生活の『基礎』として役立っている。」 課題もある。アーダールは個人情報保護の観点からプライバシーの問題が最高裁で争われてきた。 政府は、銀行口座や携帯番号とのひもづけの義務化を撤回して任意とするなど、修正を迫られてきた。
スマホを持っていない人や、通信環境の整備が進んでいない農村部に住む人もいる。 昨年インド全土で実施されたロックダウンでは、食料のない出稼ぎ労働者らに対し、政府は経済対策として穀物を無料配給したが、アーダールカードを持っていなかったり、なくしていたりして、配給を受けられない人が多くいた。 こうした人たちがコロナ禍で、1 千キロもの道のりを故郷を目指して歩き続けることになり、酷暑で途中で命を落とした人もいる。
アーダールの整備計画に関わった政府国家計画委員会のナレシュ・チャンドラ・サクセナ元次官は「アーダールの重要性が国民に十分にまだ理解されていない」と話す。 「それでも政府による保護から取り残されてしまう人の数は激減した。 あらゆる政策の基盤になる有効なシステムになっているのは、間違いない。」と指摘する。 (ニューデリー = 奈良部健、asahi = 10-18-21)
日本は第 10 位、自由判定 … インターネット上の自由度ランキング 2021 年版
インターネットは今世紀に普及した技術の中でも、もっとも大きな変化を世界に与え、これまでにない情報伝達ツールとして歴史に刻まれるに違いない存在。 情報の概念は大きく覆され、価値も意義も一変し、多様な方面に多大な利便性と革新をもたらすことになった。 それとともに便利極まりないインフラでもあるインターネットに関し、自由に利用できるか否かに注目が集まっている。
情報のやり取りは諸刃の剣であり、自由な利用を好まない勢力もあるからだ。今回は国際 NGO フリーダム・ハウス (Freedom House) が毎年精査結果を発表しているインターネット上の自由度に関する報告書の最新版「Freedom on the Net 2021」から、世界各国のインターネット上の自由度の状況を確認する。
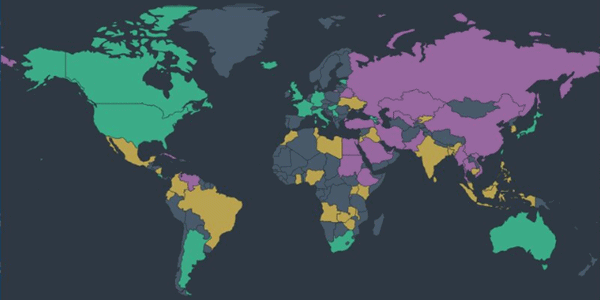
まずは直近分の 2021 年分となるスコアの確認。 「自由」、「やや自由」、「不自由」の区分された国ごとに、総合スコアと主要 3 要素ごとにチェックが入った = 加算されたスコアを確認していく。 値が大きい方が、インターネット上の自由度が高く、自由さを覚える国であると認識されている。 また、報告書にある地図の色分けによる状況確認も行う。
具体的な値では、トップはアイスランドの 96 点、次いでエストニアの 94 点。 以後カナダとコスタリカ、台湾、ドイツ、フランスとイギリス、ジョージア、そしてイタリアと日本が続く。 今回の序列の限りでは日本はイタリアと並び第 10 位。 数ポイントの差は誤差となり得ることを併せ考えると(3 項目の合算で 1 項目につき 1 ポイントの誤差が生じると試算すれば、合計値では 3 ポイントまでが誤差となりうるとの考え)、おおよそドイツ(6 位)から南アフリカ(14 位)ぐらいまでは日本と同程度のインターネット上の自由が得られていると見てよいだろう。 なおアジア太平洋地域で自由判定を受けているのは、台湾と日本、オーストラリアのみである。
インターネット上の自由度で不自由判定を受けた国を見ると、中国(10 点、極端な最下位)やイラン、ミャンマー、キューバといった強硬的な政治手法に基づいて国を統治している国や、宗教あるいは時代背景的に情報の自由な伝達が国家運営上望ましくないと判断されている国が多い印象がある。
メディア関連の調査結果でもよく問題視される話ではあるが、「インターネット」は本来インフラを主に指すのであり、それを利用して流通するコンテンツは付随的なものでしかない。 新聞やテレビ、ラジオのようなメディアとは体系的に異なるもの(新聞などはあくまでもそれぞれの媒体で伝えられる中身そのもの、さらにはそれを成す組織までも合わせ、言葉の意味としての主な対象となる)。 インターネットと比較するのなら新聞は紙媒体全体や流通ルートまで含めた包括的なもの、テレビならば電波の送受信機や放送局などとの比較が必要。
一方でインターネットは情報の発信が個人ベースで容易にできる、情報の展開の際に国レベルでの許認可が必要無いなど、これまでの情報送受信の媒体とは概念が大きく異なる。 今後インターネットを利用できる端末の普及率上昇とともに、情報を統制する必要がある国々においては、これまで以上に自由への束縛が強固なものとなっていくだろう。 (不破雷蔵、Yahoo! = 10-14-21)
大学の教科書を電子化して配信へ NTT 東西と大日本印刷が新会社
NTT 東西と大日本印刷は 5 日、大学の教科書を電子化して配信するサービスを担う新会社「NTT EDX (本社・東京)」をつくると発表した。 学生がオンラインで幅広いジャンルの教材に触れられる基盤をつくり、学びの質の向上と市場拡大をめざすという。 教材の配信を基盤上で管理し、教員が授業中に書き込んだ内容を投影したり、学生が履修科目を選ぶ前に試し読みできたりする機能を予定する。 大学が幅広い電子教材を扱えるよう新会社が著作権交渉の窓口になる。 紙の教科書と同じ価格での提供をめざすという。
コロナ禍で急速にオンライン授業が広がり、教材の電子化や共有をめぐる課題に対応する需要は大きいとみている。 新サービスには約 200 の出版社が関心を寄せているといい、5 年後に 100 億円超の売上高をめざす。 新会社のトップにつく NTT 西日本出身の金山直博社長は「出版社や書店と連携をして、教科書市場が少しでも伸びるようにしていきたい」と話した。 (山本知弘、asahi = 10-5-21)
ユーチューブ、誤情報の削除対象を全ワクチンに拡大へ
米グーグル傘下の動画投稿サイト「ユーチューブ」は 29 日、新型コロナウイルスのワクチンについて誤った情報を含む動画を削除してきた対応を拡大し、削除する対象をすべてのワクチンについての誤情報に広げると発表した。 誤情報がはしかや B 型肝炎など様々なワクチンに広がっている現状を踏まえた。 同社によると、コロナワクチンに関する誤情報の動画をこれまでに 13 万本以上削除したという。 同社は 29 日、「コロナのワクチンについての誤った主張が、ワクチン全体の誤情報に波及しているのを、我々は目にしている。 我々がコロナのワクチンについて始めた取り組みを、ワクチン全体に拡大すべき時だ。」と説明した。
同社は削除対象になる誤情報を「ワクチンが自閉症、がん、不妊症を引き起こす」、「ワクチンにはマイクロチップが含まれ、追跡される」、「ワクチンが人々の DNA を書き換える」、「ワクチンを接種しても、感染リスクの減少にはつながらない」などと列挙。 こうした動画は削除されるだけでなく、動画をアップした利用者は規約違反となって、アカウントの削除に至ることもある。 米国では、ワクチン接種を拒否する人が 8 千万人近くに上るとされる。 一部の人の間で、ワクチン全般に対する誤情報が広がっていることが指摘されている。 (サンフランシスコ = =尾形聡彦、asahi = 9-30-21)
テレビ東京、12 月にもネット同時配信 民放キー局が全局開始へ
テレビ東京は 30 日、テレビ番組を放送と同時にインターネットで見られる「同時配信」を 12 月にも始める方向で準備していると明らかにした。 民放共通の無料配信プラットフォーム「TVer (ティーバー)」を使い、午後 7 - 11 時台の番組を中心に配信を検討しているという。 石川一郎社長はこの日の定例社長会見で「テレビを持っていない方にも、我々の放送コンテンツを見ていただきたい。 この同時配信がもつ意味は大きい。」と期待を語った。 同時配信については、日本テレビが 10 月 2 日から民放キー局で最も早く始める。 テレビ朝日は「年明け」、TBS とフジテレビは「今年度中」にそれぞれ始める方向で準備している。 (野城千穂、asahi = 9-30-21)
◇ ◇ ◇
テレビ朝日、ネット同時配信を年明け開始で調整 午後 7 - 11 時台
テレビ朝日は 28 日、テレビ番組を放送と同時にインターネットで見られる「同時配信」について、年明けに開始する方向で調整していると発表した。 民放共通の無料配信プラットフォーム「TVer (ティーバー)」で、午後 7 - 11 時台を中心に一部の番組を配信する。
この日のオンライン定例会見で篠塚浩常務が「一部の番組の同時配信サービスを年明けに開始することを目指して調整している」と明らかにした。 利便性向上と、パソコンやスマートフォンなどテレビ以外のデジタル機器を通じてより多くの人に番組を見てもらう狙いだ。 民放他局では、日本テレビが 10 月 2 日から夜の時間帯の番組で始める。 日テレの杉山美邦社長は今月 27 日の会見で「デジタルで見た視聴者がテレビもさらに視聴し、回帰してもらうという効果を期待している」と述べた。 フジテレビや TBS Sも年度内の開始を目指している。 (弓長理佳、asahi = 9-28-21)
◇ ◇ ◇
日テレ、10 月から放送と同時にネット配信 TBS なども年度内検討
日本テレビは、テレビ番組を放送と同時にインターネットで見られる「同時配信」を 10 月 2 日から夜の時間帯の番組で始める。 テレビがなくても、スマートフォンやパソコンで地上波と同時に、国内なら地域にかかわらず視聴できるようになる。 民放では初で、TBS やフジテレビも年度内の開始を目指している。 若年層を中心にテレビ離れが進む中、テレビ局は新たな視聴者を獲得する方法を模索しており、放送と通信の融合が加速する。
日テレによると、民放共通の配信プラットフォーム「TVer (ティーバー)」で無料配信する。 2 日午後 7 時の「I LOVE みんなのどうぶつ園」から始める。 午後 7 - 11 時台のバラエティーやドラマの多くが対象となり、午後 8 時台は連日配信する。 同社は昨年 10 - 12 月、系列の読売テレビ、中京テレビの 2 局と同時配信を試行。 利用者のニーズが確認できたという。 キー局による同時配信が地域を越えて広がると、地方での視聴率や連動する広告収入が減るといった懸念があるが、この時間帯の番組配信に系列局の理解を得られたという。
放送関係者によると、民放キー局 5 局は足並みをそろえてこの秋に TVer で配信を始めることを模索していた。 ただ放送と異なる CM を同時配信用に流す場合には広告料など課題が多く、各局がそれぞれ調整を進める中、「関係者の理解が得られた(担当者)」日テレが先行した形だ。 日テレによると、番組中の CM はテレビと同じ場合も、違う場合もあるという。
TBS は、朝日新聞の取材に「今年度中の同時配信を検討中」と答え、フジテレビも既に年度内の開始のために調整中と表明している。 テレビ朝日、テレビ東京も検討中だが、時期は明らかにしていない。 NHK は昨春、受信契約世帯向けに番組の同時配信や見逃し配信をする「NHKプラス」を始めている。 (asahi = 9-17-21)
中国人民銀、仮想通貨を全面禁止 「違法」と位置付け
仮想通貨取引
記事コピー (6-18-17〜9-24-21)
リアルタイムのデータに名前を付けてハッキング封鎖 … 韓国研究グループが 新インターネット技術開発
韓国の研究グループが、急増するデータや変化するインターネットの活用環境に備えた、新しいインフラ技術を開発した。 韓国電子通信研究院 (ETRI) は 22 日、インターネットが単純な連結にとどまらず最適な情報処理をしながらも、セキュリティや検索の利便性を高めた「データ中心」ネットワーキングの基盤技術を開発したと発表した。
1975 年に開発された現在のインターネットの仕組みは、IP アドレスをベースとしたホスト間のつながりであり、データ配信のみを目的とした設計となっている。 このため、モバイル環境の移動支援、コンテンツの出典の正確性、データが原本と一致しているかを保証する完全性に限界がある。 特に最近では、仮想・拡張現実 (VR/AR) やメタバース等の大容量コンテンツ、交通システムや遠隔制御等の不具合や故障が起きてはならないサービス、基盤データが重要な人工知能サービスなどが増えるにつれ、データをさらに効率的に活用できるネットワークの革新が必要な状況だ。
ETRI が開発した新しいインターネット技術の核心は、データに名前を付与することでセキュリティを内在し、ネットワーキングとコンピューティングを融合することである。 新しいインターネットの技術が適用されると、CCTV、ドライブレコーダー、IoT 端末などから得られるリアルタイムのデータにそれぞれ名前が付与される。 そのため、応用段階で使うデータ名で簡単にデータを検索し、安全に自動で情報を受け取ることができる。
例えば、消防署では都市の至る所に設置したセンサーから、センサーの位置、センサー名、発生時間等からなるデータ名を受け取り、リアルタイムで関連情報が得られる通知サービスを容易に開発し、火災に効率的に対応することができるようになる。 従来はクラウドデータセンターにあるプラットフォームでセンサーデータを集め分析を行う必要があった。 ETRI 技術を適用すれば、データ名から火災の位置や時間などの関連情報が自動的に伝わるため、追加で分析処理をする必要ない。
データにセキュリティを内在しながら、データ伝達の過程で起こりうる操作の有無や不具合を感知することも可能となった。 そのため、誤動作も未然に防止し、権限のないユーザーのハッキングを防止することができる。 研究グループは、データ伝達とコンピューターを融合し、ネットワーク構造も簡潔にした。 処理が急がれる火災分析は、センサーと消防署間に近いコンピューティングの資源を割り当てる。 AI 学習のための処理は、遠隔にある高性能クラウドコンピューティングの資源を割り当てるなど、要求事項に応じてサービスを最適に処理することができるようになった。 これによりデータ活用度を高め、サービスをより効率的に開発することができる見通しだ。
研究グループは開発された技術を国家研究開発網 (KOREN) に適用し、安定的に動作することを確認し、実用化の可能性を立証した。 また、ルータ性能を検証する尺度であるフォワーディング (Forwarding) 性能が汎用サーバで 300Gbps を記録し、世界最高レベルのデータ中心によるネットワークの SW 技術力を有していることを明らかにした。 ETRI は新技術のサービス実証も積極的に推進している。
現在、釜山広域市、韓国科学技術情報研究院 (KISTI) と共に、釜山市内のリアルタイム環境監視のためのデータ分配インフラの実証を進めている。 ETRI 自主走行シャトル「オートビー」の V2X インフラにも適用、自主走行安全性と効率性を高めることができることを確認した。 キム・ソンミ ETRI ネットワーク研究本部長は「未来デジタルインフラに必要な技術を確保し、実用化の可能性を検証した。 新しいインターネット時代に跳躍できる基盤を整えた。」とし、「今後も多様な未来志向的環境に適用しながら完成度を高めていきたい」と述べた。 (WoW!Korea = 9-23-21)
ニュースへの対価、日本でも 米グーグルの「ショーケース」開始
米グーグルは 16 日、ニュース配信サービスの「ニュースショーケース」を日本国内で新たに始めたと発表した。 朝日新聞を含めた 40 社以上の報道機関がライセンス契約を結んで記事を提供し、グーグルが対価を支払う仕組み。 ショーケースでは提供社が選んだ記事を集めた「パネル」が表示され、利用者がパネルの中の見出しをクリックすると各社のサイトに移る。 利用者が気に入ったパネルを「フォロー」することもできる。 報道各社は自社サイトに利用者を誘導しやすくなる。
ニュースショーケースはドイツやフランス、英国など 12 カ国以上で始まっており、1 千社を超える報道機関が参加。 日本では全国紙や地方紙、通信社が参加する。 グーグルは昨年 6 月、世界のメディアにニュースの対価を支払う方針を示し、10 月には今後 3 年間で 10 億ドルを支払うと発表した。 経営環境が厳しくなっている新聞や雑誌などのメディアに対価を払い、質の高いコンテンツが減るのを防ぐ狙いがあるとしている。 (中島嘉克、asahi = 9-16-21)
講談社とアマゾン、直接取引を開始へ 「異例の事態」に衝撃広がる
ネット通販大手アマゾンと出版大手・講談社が今月から、取次会社を経由しない「直接取引」を始めたことが関係者への取材で分かった。 消費者に本を届ける日数の短縮やコスト削減を狙う。 取次会社などに衝撃が広がっている。 出版流通では、書店と出版社の間に問屋にあたる取次会社が入って全国に本や雑誌を配送する。 ネット書店のアマゾンも取次会社から書籍を入手し、消費者に届けてきた。 今回、講談社から直接、取り寄せることで、日数の短縮が期待される。
アマゾンジャパン広報部は直接取引の意義について「豊富な品ぞろえとお客様への迅速な配送が可能になる」としている。 直接取引の当面の対象は人気の 3 シリーズ「講談社現代新書」、「ブルーバックス」、「講談社学術文庫」の既刊本。 効果を見極めた上で他の書籍や新刊本への拡大を検討する。 アマゾンは従来、取次大手の日本出版販売(日販)などと取引する一方、講談社以外に約 3 千社と直接取引をしてきた。
ただ、業界をリードする講談社が直接取引に加わったことに、「異例の事態で衝撃は大きい(取次会社幹部)」と波紋が広がる。 講談社は 2016 年、アマゾンの電子書籍読み放題サービスから 1 千超の作品が削除されたとして強く抗議するなど、両社は緊張関係にあった。 (赤田康和、asahi = 9-16-21)
ネット中傷厳罰化へ 木村花さんら相次ぐ被害
インターネット上で相次ぐ誹謗中傷の被害を防ぐため、公然と人を侮辱した場合に適用される侮辱罪を厳罰化する刑法改正が法制審議会(法相の諮問機関)で議論されることになった。 拘留(1 日以上 30 日未満の収容)と科料(千円以上 1 万円未満の徴収)としている法定刑に、1 年以下の懲役・禁錮と 30 万円以下の罰金を追加し、これにより公訴時効も 1 年から 3 年に延ばすことが主な論点だ。
上川陽子法相が 14 日の記者会見で、16 日の法制審に諮問する考えを明らかにした。 答申を受け、法務省は来年の通常国会に改正法案を提出する方針。 ネット社会の定着とともに中傷被害も深刻化している。 昨年 5 月にはプロレスラーの木村花さん(当時 22)が、テレビ番組での言動をめぐり SNS で繰り返し中傷を受けた末に自ら命を絶った。 翌 6 月から法務省は侮辱罪の見直しに向けて検討してきた。
侮辱罪は、大勢の前で「バカ」、「死ね」などといった暴言を浴びせる行為が処罰対象となる。 罰則は拘留か科料で、明治時代に定められてから変わっておらず、瞬時に情報が広がる今の時代に合っていないとの指摘があった。 また、ネットに匿名で発信された場合には、利用した SNS や端末、プロバイダーなどから絞り込んでいく捜査に時間がかかるのに、公訴時効が短いと問題視する声もあった。
見直しを進めるなかで法務省は、侮辱罪が適用された過去の事件や海外の事例などを調査。 処分が軽く被害の実態に見合わないものも少なくなく、厳罰化により抑止を図る必要があると判断した。 侮辱罪に対し、「不正を働いた」などと具体的な事例を示して他人の名誉を傷つけた場合に適用される名誉毀損罪は、見直しの対象から外れた。 同罪の法定刑が 3 年以下の懲役か禁錮、50 万円以下の罰金で、相応に重い罰則のため事件の内容に応じた適正な科刑ができると判断された。
上川法相は会見で、ネット上の中傷について「取り返しのつかない重大な人権侵害につながるもので、決してあってはならない」と指摘。 「厳正に対処すべき犯罪であることを示し、抑止することが必要だ」と語った。 ネット上の中傷をめぐっては、加害者を特定しやすくする新たな裁判手続きを定めた改正プロバイダー責任制限法が 4 月に成立。 時間のかかる訴訟を経なくても裁判所が加害者の情報開示を SNS などの事業者に命じられるようになる。 来年末までに施行される見通しだ。 (伊藤和也、asahi = 9-14-21)
もうひとつの "コロナ" が迫る 「インターネットの大災害」とも
新型コロナは世界の災厄だが、いまひとつの "コロナ" が新たな災厄となって降りかかってくるかもしれない。 電磁波や粒子線を発する「太陽嵐」の活動ピークが数年後に迫っており、ネットワークが高度に発達した世界にとって初の経験となる。 最悪の場合、インターネットに大規模障害が起こり、膨大な損害が発生するおそれがあるという。
観測史上最大の太陽活動期
8 月下旬に開催されたデータ通信とネットワークの国際会議「SIGCOMM 2021」に合わせ、「超太陽嵐 : インターネット大災害への備え」という論文が発表された。 著者は、カリフォルニア大学アーバイン校の Sangeetha Abdu Jyothi 助教。 近く起こりうる大規模な太陽嵐によって、数時間あるいは数日もの停電が起こり、それが復旧した後に大規模なインターネットの停止が続くおそれがあるというものだ。 太陽活動には 9 年から 12 年(平均は 11 年)のサイクルがあり、その中で起こるのが太陽嵐だ。 太陽の表面で起こる爆発現象である「太陽フレア」や、「コロナ質量放出 (CME : Coronal Mass Ejection)」などのエネルギーが地球に降り注ぐことになる。
太陽フレアが地球に向かうと、地球の磁気圏を刺激し荷電粒子が極に向かう電気力線を加速させる気象現象が起こる。 これがオーロラだ。 一方で CME は磁気嵐を発生させ、プラズマが放出される。 このプラズマは、送電線網にダメージを与える。 太陽の最新の活動期は2020年に始まった。今回は観測史上最大の活動期になるとも予想されており、最も活発になるのは2025年ごろとみられている。 Abdu Jyothi 氏の論文では、大規模な太陽フレアと CME が与える影響を検証。 送電線網の設計は CME の影響を想定して緩和するようになっているが、インターネットはそうではないと警鐘を鳴らしている。
「ネットワーキング・コミュニティは概して、ネットワーク構成や DNS のような地理分散システム、データセンターなどの設計をする際、太陽嵐のリスクを見過ごしてきた」というのだ。
最も脆弱なのは北米
巨大な太陽嵐がインターネットに影響する仕組みはどうなのだろう。 インターネットインフラには、銅線ベースのものと光ファイバーがある。 後者は電気ではなく光を使うので影響は受けない。 そのため、光ファイバーを用いたインターネットインフラは大丈夫だという。 論文が問題視しているのは、銅線のケーブル。 例えば、長距離の海底ケーブルなどだ。 国をまたぐデータの 99% が海底ケーブルを通り、敷設が多い地域は、北米、欧州、そしてシンガポールだ。 このうち極地に近い方、高緯度の地域が、より太陽嵐の影響を受けやすくなる。
その海底ケーブルには 50 - 150 キロ間隔で中継器(リピーター)が設置されているが、ここで電気が使われている。 光素材が利用されていたとしても中継器がダウンする可能性があり、ケーブルの運用が止まるとネットワークも止まる。 保護機能から見ると、インターネットは障害発生時にリルーティングを行い、障害の程度が軽ければ速度の低下程度で済む。 しかし、Border Gateway Protocol (BGP) や DNS などが機能しなくなるとネットワークは停止してしまう。
また、一般的に欧州はケーブルが短いが、北米は長いという。 ケーブルが長いほど、いったん障害が発生した場合の復旧に時間がかかる。 こうしたことから、大規模な太陽嵐が発生した場合、北米のインターネットインフラが最も脆弱だと論文は予想している。 最悪、インターネットの停止が数カ月も続く可能性さえあるという。 このほか、インターネットは海底ケーブルだけではなく、衛星ベースのサービスもある。 こちらについても、衛星が直接太陽嵐にさらされることもあり、脆弱であることでは同じだという。
対応は進んでいない
被害の規模はどれくらいになるのだろう。 インターネットをモニタリングしている Netblocks.org の試算ツールによると、インターネットが 1 日ダウンした際の経済的損失は、全米の場合で 72 億ドル。英国だと 22 億 6,000 万ドル。 日本だと 19 億ドル(約 2,085 億円)だ。 これを紹介した Forbes によると、大規模な太陽嵐が発生する可能性は 1.6% から 12% だという。 幸いなのは、地球の陰になっている地域、夜側は影響を受けずに済みそうということだ。
新型コロナという危機で世界の混乱が続いている。 そんな中で、新たな危機を持ち出すことになるのだが、Abdu Jyothi 氏は「だからこそ」警告したと言う。 「パンデミックで、世界がいかに(非常時への)準備ができてないかが明らかになった」、「効果的に対処するプロトコルらしきものがなく、これはインターネットの耐性という点でも同じだ。」 こうしたことが論文執筆の動機になった、と Wired に語っている。
インターネットインフラが太陽嵐に対応できていないのは、ある程度、仕方がない面もある。 大規模な太陽嵐はまれで、記録されているものはわずかしかない。 約 160 年前の1859年には「Carrington Event」と呼ばれる観測史上最大の太陽嵐が発生。 欧州と北米で電報システムが停止した。 電話の登場以前のことだ。 このとき、ロッキー山脈でオーロラが見えたという記録もある。 100 年前の 1921 年には 3 日間の太陽嵐があり、やはり米国の電報システムが影響を受けた。
最近では、1989 年に中程度の太陽嵐が発生。 カナダ・ケベック州で電力会社が影響を受け、州全体で 9時 間の停電に陥った。 だが、現在のようにインターネットが張り巡らされ、重要インフラとなった状態で世界が太陽嵐を迎えた経験はない。 Forbes によると、各国の対応は進んでいないという。 例えば、Boris Johnson 英首相の元上級顧問、Dominic Cummings 氏が 5 月に、「(脅威に対する)英国の計画は完全に絶望的」と述べたことを挙げている。 (岡田陽子、Infostand = 9-6-21)
デジタル庁が発足 シンプルなロゴで「人に優しいデジタル化」目指す
行政のデジタル化の司令塔を担うデジタル庁が 1 日発足した。 コロナ禍のなかオンライン手続きの普及が課題で、「すべての行政手続きがスマートフォンで 60 秒以内にできる」ことをめざす。 マイナンバー制度の活用や、バラバラだった自治体システムの標準化も進める。 1 日午後に幹部人事の発表や発足式がある。 デジタル大臣には、デジタル改革相として設立準備をしてきた平井卓也氏が就く。 事務方トップの「デジタル監」には、一橋大学名誉教授の石倉洋子氏が起用される。
デジタル庁は 1 日ホームページで、使命として「誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化を」と掲げた。 約 600 人体制でスタートし、うち約 200 人は民間出身者が占める。 兼業で働く非常勤職員も多い。 母体となった内閣官房 IT 総合戦略室の職員による不適切な入札など、直前に問題が相次いだ。 官民の癒着の防止など、コンプライアンスの徹底が求められる。 デジタル庁の創設は、菅義偉首相が昨年 9 月の自民党総裁選で打ち出した。 今年 5 月にデジタル改革関連法が成立し、構想から約 1 年で動き始める。 (中島嘉克)
お金をかけずにロゴを作成
デジタル庁は1日、発足に合わせてロゴを公表した。 誰でも無料で利用できるオープンソースの書体を使い、白と黒の文字のシンプルなものだ。 シンボルマークはつくっていない。 「お金をかけずにスピード感をもってやる」ことを前提に、職員らが準備してきたという。 ロゴは「デジタル庁」と「Digital Agency」で、オープンソース書体の「Noto Sans」を採用した。 字間や太さなどはロゴとして扱いやすいように調整した。 白と黒がベースだが、「差し色」としてアクセントカラーを選べるという。
デジタル庁の母体となった内閣官房 IT 総合戦略室の職員らが、内部のデザイナーらを交えて議論してきた。 白と黒をベースにすることなどは、職員による投票で決めたという。 ロゴはホームページで公開しており、使用したい場合の問い合わせ方法も示している。 (中島嘉克、asahi = 9-1-21)
◇ ◇ ◇
注目されすぎた? デジタル庁初日、HP が接続不安定に
1 日に発足したデジタル庁のホームページが、昼すぎから断続的に接続しづらくなった。 新組織やロゴが注目され、アクセスが集中したことが原因とみられる。 同庁によると、いまのところシステム障害ではないとしている。 8 月末までは母体となる内閣官房 IT 総合戦略室が、「デジタル庁(準備中)」としたホームページを運用していた。 発足に合わせてリニューアルし、ロゴなども発表していた。 (平井恵美、asahi = 9-1-21)
動画配信、ねらうはテレビリモコン ボタン一つで画面に
最近発売されるテレビのリモコンに、ネット動画配信サービスのロゴを施したボタンがずらりと並ぶようになりました。 このボタンを押すと、配信の画面がポン。背景を取材すると、テレビ離れに危機感を強めた家電メーカーの変化や、競争が激しい動画配信業界の事情が浮かび上がってきました。
ネットフリックス先行、「一等地」を獲得
国内の主要メーカーが今年発売したテレビのリモコンには、昔ながらの選局ボタンなどのほかに、動画配信サービスのロゴもつけたボタンが、多いもので 7 つついている。 ネット接続機能を持つ機種を中心に、昨年より一気に数が増えた。 先行したのは、動画配信の世界最大手で 2015 年に日本でサービスを始めた米ネットフリックスだ。 同年 2 月発売の東芝「レグザ」のリモコンに、日本で初めてネットフリックスの専用ボタンが搭載された。
「(当初は)メーカーからは『そんな一等地はあげられない』と言われ、一筋縄ではいきませんでしたね。」 ネットフリックス日本法人のビジネス・デベロップメント部門ディレクター、下井昌人さんは 8 月半ばの記者会見で、こう振り返った。 「一等地」とは、リモコンの上部など目につきやすい位置のこと。 ここにワンタッチでネットフリックスの画面に飛ぶボタンをつけてもらうおうと、下井さんらは奔走した。
従来のリモコンでも、外付け機器などでテレビがネットに接続されていれば、いくつかのボタン操作を経て配信の視聴画面にたどり着くことはできる。 だが、放送のチャンネルのようにボタン一つでできれば、不慣れな人にも便利で、会員を増やしやすくなる。 ボタン搭載で先行したのは北米などだが、配信動画を大画面で楽しむためにテレビを買う層も増えるにつれ、国内メーカーも動いた。 若者のテレビ離れへの危機感や、メーカーが売りとしたい 4K 画質への対応で配信サービスが地上波放送より先行したことも背中を押した。
東芝などに続いて、ソニーもほどなく動画配信サービスのボタンを搭載した。 ソニーマーケティングジャパンの福田耕平統括課長は「ハードとしてのテレビとコンテンツをどう結びつけて購入してもらうかがビジネス上、非常に重要な課題になってきた」と話す。 動画配信で国内 3 位の U-NEXT (ユーネクスト)も、ネットフリックスの動きを横目に、水面下でメーカー各社に働きかけたという。 17 年の船井電機を手始めに、中国のハイセンス、ソニーなど年々搭載を増やし、今年はパナソニックなど 3 社が加わって計8社となった。
メーカーも消極姿勢から変化
「テレビは放送局を中心とした規格で作られてきただけに、かつてはメーカー各社もネット対応に積極的でなかった」と、U-NEXT の堤天心社長は言う。 放送局も長年、テレビのネット対応を快く思わず、13 年にはパナソニックのネット対応テレビの CM 放送を民放が拒んだことが明るみに出た。 テレビメーカー各社がネット接続への対応を本格化させたのは、10 年ほど前だ。 当初はテレビの基本ソフト (OS) がバラバラだったが、ここ数年で米グーグルの OS 「アンドロイド TV」が普及。 より多くの配信サービスに対応しやすい環境が整った。
調査会社 GEM パートナーズによると、定額制動画配信サービスの昨年の利用率は、前年比 8.1 ポイント増の 30.3%。 コロナ禍の「巣ごもり生活」もあって急伸した。 業界全体としては追い風だが、U-NEXT の堤社長は「一定以上の年齢層は(今も)放送が強い。 そうした方々に動画配信の世界に来てもらうための一策がボタン搭載だ。」 配信の視聴時間もテレビで見る方が長く、解約率が下がる傾向もみられるという。
サービスの認知度アップの手段に
日本では、動画配信の市場規模が米国より小さいのに事業者の数は多い。 激しい競争を続ける各社にとって、リモコンのボタンは認知度を高める有力な手段にもなっている。 米国発の Hulu (フールー)を日本で運営する HJ ホールディングスの於保(おほ)浩之社長は「ボタンにはロゴもついているので、(家庭に)置いてあるだけで宣伝にもなる」と語る。 18 年発売のソニーの機種からボタン搭載を始めた ABEMA の運営企業サイバーエージェントも「なじみのあるテレビのリモコンに常に ABEMA が表示されることで、利用の維持やきっかけになる」と言う。
TBS やテレビ東京などでつくる「Paravi (パラビ)」は今年 5 月発売のシャープの機種で初めてボタン搭載に乗り出した。 運営企業のプレミアム・プラットフォーム・ジャパンは「利用者の利便性向上やサービス認知のため参画した」としている。 ただ、ボタン搭載は多くの場合、配信サービス側がテレビメーカーに代金を払う必要がある。 「TSUTAYA TV」は 18 年に初めて東芝に搭載したもののそれきりに。 一方で 20 年にはソニーに搭載した。 運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブは「利用者の利便性は高くなるが、事業者としてはボタン設置に利用料が必要になるので、搭載するかどうかは費用対効果を見て検討する」としている。 (藤えりか、asahi = 8-29-21)
メルカリ、初の黒字 「巣ごもり」でフリマ活況
フリマアプリ大手のメルカリが 12 日発表した 2021 年 6 月期決算は、売上高が前年比 39.1% 増の 1,061 億円、純損益が 57 億円の黒字(前年は 227 億円の赤字)だった。 新型コロナ下の巣ごもり需要でフリマ事業が好調で、18 年の上場以来初の黒字だった。 主力の国内フリマ事業は中高年層の利用が広がり、流通総額が前年比 25% 増。 苦戦していた米国のフリマ事業も流通総額が同 68% 増えた。 山田進太郎社長はオンライン会見で「コロナで家にいる時間が増えたことで出品が増加し、増収効果が大きかった」と話した。
22 年 6 月期の業績予想は示していないが、足元では新たな施策を相次いで打ち出している。 スマホ決済サービス「メルペイ」では、メルカリの利用実績などをもとに金利や限度額が決まる少額融資サービスを 8 月から開始。 米国では、米ウーバーと連携した即日配送サービスを導入して利用者拡大をめざす。 (中島嘉克、asahi = 8-12-21)
関連情報 (7-28-21)