50% 以上省エネした「ZEB Ready」ビルが完成 通常業務しながら工事
大成建設は 28 日、同社の札幌ビルをリニューアルし、1 次エネルギー消費量を 50% 以上削減した「ZEB Ready」省エネビルが完成したと発表した。 同ビルの ZEB (ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化へのリニューアル工事は、通常業務を継続しながら進められた。 省エネのために取り入れられた技術などは下記のとおり。
タスク & アンビエント照明
個人スペースと共有スペースの照明を分けたタスク & アンビエント照明方式を採用し、各デスクにタスクライトを設置。 天井照明による照度 300lx、タスクライトによる照度 400lx を合わせ、机上面では執務に必要な照度 700lx を確保し、全体の照明エネルギーを削減。 新規開発の高効率な LED 照明および、照明器具下部面に光を拡散するプリントルーバーの採用により、LED 照明の眩しさを和らげ、柔らかな明るさを実現した。
T-Zone Savor / 照明を単体制御
人の在・不在を検知する人検知センサー情報により、照明器具を 1 灯単位で制御し、照明エネルギーの最小化を実現した。
T-Zone Savor / 省エネ状況の見える化表示
人検知センサーによる情報と連携し、在席による適正な明るさの状況や、人の在・不在情報を在(赤色)、不在(灰色)としてリアルタイムに表示し、T-Zone Savor による省エネ状況や効果をモニターで見える化し、建物運用開始後の在席情報管理により、利用者の意識向上を促し、省エネ化を図る。
同社は、おととし、同社技術センター ZEB 実証棟において「国内初の都市型 ZEB」の実証を行った。 その実績データやノウハウを活用し、ZEB 化のための計画・評価ツール「T-ZEB シミュレーター」を開発した。 今後も、同社では同ツールや、今回採用した照明技術をはじめとする ZEB 化技術などを活用し、ZEB 化を目指す建物の新築・改修を積極的に推進したい考えだ。 (環境ビジネス = 7-31-16)
プラスチック粒子、堆積物に蓄積 今世紀に入り量が急増
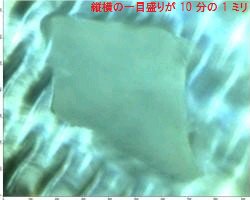
海洋汚染が問題になっているプラスチックの微小粒子「マイクロプラスチック (MP)」が海底の泥などの堆積物中に蓄積し、その量が 2000 年代に入って世界各地で急増していることを、東京農工大の高田秀重教授らのグループが 28 日までに突き止めた。 濃度は海水中よりも高く、泥の中にすむ底生生物への影響が懸念される。 高田教授は「堆積物が MP の集積場所の一つになっている。 プラスチックの使用量を減らすなどの対策が急務だ。」と警告している。 高田教授は、東京や東南アジア、アフリカの海底などで採取した堆積物を分析した。 (西日本新聞 = 7-28-16)
石炭火力発電で CO2 回収実験へ 環境省、今年度から
環境省は 25 日、地球温暖化対策で、石炭火力発電所の排ガスに含まれる二酸化炭素 (CO2) を回収、固定する技術 (CCS) の実証実験を、福岡県内で今年度から始めると発表した。 1 日あたり 600 トン前後の CO2 を回収する予定で、国内で初の大規模な実証実験という。 石炭火力発電所は発電効率が高い最新型でも、CO2 排出量が天然ガス火力発電所の約 2 倍と多いが、国内では新設計画が相次ぐ。 「2050 年までに温室効果ガスの排出を 80% 減らす」とする国の長期目標の達成のためには、CCS は重要な技術だ。
環境省は CCS 実用化に向け、今年度予算に 36 億円を計上。 東芝が出資する福岡県大牟田市の三川発電所を公募で選んだ。 東京大学や産業技術総合研究所などと共同で、排ガス中の CO2 の半分以上を化学溶液に吸収し、回収することを目指す。 30 年ごろまでの実用化を目指し、発電効率や環境への影響を今後 5 年以内に調べる。 (小堀龍之、asahi = 7-25-16)
再配達は減らせるか 自動運転車で宅配便の実験へ
宅配便の再配達を減らそうと、ヤマト運輸と大手 IT 企業、ディー・エヌ・エーは、自動運転の車で配達する実験を行うことで提携したと発表しました。 これはヤマト運輸とディー・エヌ・エーが、記者会見で発表したものです。 それによりますと、両社は、来年 3 月から特別に許可をとった地域で、自動運転の車を使い、宅配便を配達する実験を行う計画です。
専用に開発する自動運転車には、荷物を収納する箱が備えられています。 荷物を受け取る人は、車が自宅の前に到着すると出て行き、あらかじめメールで通知されたパスワードなどを入力して、自分あての荷物を取り出す仕組みです。 利用者は、受け取り場所や時間を自由に指定できるということです。 宅配業界では、人手不足が深刻です。 また、共働き世帯が増えるなどして、荷物が一度で届けられず、再配達になるケースが増加し、会社の大きなコスト負担になっています。
両社では、自動運転の技術を活用し、利用者が自分の好きな時間に受け取ることができる新しいサービスを導入できれば、コスト削減と利用者の利便性につながると考えています。 ディー・エヌ・エーの守安功社長は、「物流業界にとっていちばんの課題は、再配達による負担の増加で、今後は運転手の人手不足も厳しくなってくる。 自動運転の技術で、こうした課題を解決していきたい。」と話していました。 (NHK = 7-20-16)
飛行機がハイブリッドになる、電気で飛べば CO2 も騒音も少ない

ドイツのシーメンスが中心になって開発した電動の飛行機が初めての公開飛行に成功した。 出力 260 キロワットのモーターでプロペラを回転させて、1 トン近い重さの飛行機に推進力を与える。 モーターとエンジンを組み合わせて 100 人乗りのハイブリッド飛行機を実用化することが最終目標だ。 全長 7.5 メートルの小型飛行機「Extra 330LE」が、7 月 4 日にドイツ西部の空港で公開飛行にのぞんだ。 機体の前方にモーターを搭載して、電気だけでプロペラを回転させて飛ぶことができる。 モーターの最高出力は 260kW で、電気自動車の「日産リーフ」の 80kW と比べると 3 倍以上だ。
これほど高出力のモーターを搭載した電動の飛行機による公開飛行は世界で初めての試みだ。 電機メーカーのシーメンスが開発したモーターは重さが 50kg と軽量で、1 分間に 2,500 回転する能力がある。 この推進力で 1 トン近い重さの機体を飛行させることが可能になる。 機体の前方にはシーメンス製のモーターとインバーターのほかに、スロベニアの小型飛行機メーカーであるピピストレルが開発したバッテリー・モジュールを搭載している。 バッテリーの蓄電容量は公表していないが、7 月 4 日の公開飛行では 10 分間にわたって飛ぶことができた。
シーメンスは電動の飛行機の性能を強化しながら、次のステップでは商用のハイブリッド飛行機を開発する。 大手航空機メーカーのエアバスと共同で、2030 年までに 100 人乗りのハイブリッド飛行機を実用化する計画だ。 飛行距離を 1,000 キロメートルまで延ばして、近距離の運航に利用できるようにする。 そのためにはモーターの出力を 1 万 kW 程度まで引き上げる必要がある。 従来のジェットエンジンを搭載した飛行機と同様に、プロペラよりも推進力が大きいダクトファンを駆動するためだ。 シーメンスとエアバスは 2020 年をめどに技術面の実現可能性を実証したうえで、商用のハイブリッド飛行機の開発を進めることにしている。
騒音が小さくて夜間でも離着陸できる
ハイブリッド飛行機の利点はいくつかある。 第 1 に燃料の消費費を大幅に削減できる。 ハイブリッド自動車と同様に、モーターとガスタービンエンジンを組み合わせることで、飛行状態に合わせて最適な出力を発揮できるようになる。 たとえば離陸後の上昇時にバッテリーの出力を高めて推進力を引き上げる。 シーメンスによると、ハイブリッド飛行機は従来のジェット機と比べて燃料の消費量を最大 50% まで削減できる見通しだ。 燃焼に伴って発生する CO2 (二酸化炭素)や汚染物質も同程度の削減が見込める。 これが第 2 の利点で、地球温暖化対策として有効である。
さらに第 3 の利点として騒音が格段に小さくなる。 この点もハイブリッド自動車が実証済みだ。 飛行機の騒音が小さくなれば、これまで夜間の飛行が禁止されていた地域でも運航できる可能性が高まる。 機体の稼働率を向上させて、航空会社の収益を改善する効果が期待できる。 シーメンスは電動飛行機用のモーターを開発するにあたって、ドイツ政府が推進する航空技術研究プログラム「LuFo」の支援を受けた。 ドイツ政府は航空技術を他の産業にも活用できる戦略分野と位置づけていて、特に環境対策の面で先進的な技術の開発に重点を置いている。 (石田雅也、SmartJapan = 7-15-16)
高さ 150 メートルの巨大な洋上風力発電船、太平洋を福島沖へ曳航中

福島県の沖合 20 キロメートルに展開する浮体式の洋上風力発電所が完成に近づいている。 最後の 4 基目が組み立てを終えて 7 月 2 日に兵庫県を出航、800 キロメート離れた福島沖まで太平洋を航行中だ。 8 日の夜遅くに設置現場に到着する予定で、8 月 1 日から海底送電ケーブルの敷設工事が始まる。 2011 年度に始まった「福島復興・浮体式洋上ウィンドファーム実証研究事業」は、3 基の風力発電設備と 1 基の変電設備をすべて浮体式で建設する世界で初めてのプロジェクトである。 最後の 4 基目になる発電能力 5MW (メガワット)の開発が遅れていたが、ようやく福島沖の現場に設置できる段階を迎えた。
「ふくしま浜風」と名づけた 5MW の洋上風力発電設備は兵庫県の淡路島沖で風車の搭載作業を 6 月いっぱいで完了。 7 月 2 日の午前 8 時 30 分に福島沖に向けて曳航を開始した。 風車の回転直径は 126 メートルもあり、最高到達点は水面から 150 メートルになる。 風車の下は「アドバンストスパー」と呼ぶ六角形の浮体構造物が支えている。 淡路島沖を出航した洋上風力発電設備は太平洋上を東へ、3 - 4 ノット(時速 5 - 7 キロメートル程度)のゆっくりした速度で航行中だ。 予定通り進むと 8 日(金)の早朝には茨城県の沖合を通過して、昼過ぎには福島県の小名浜沖、そして夜の 10 時 30 分に設置現場に到着する。
すでに福島沖で運転中の 3 基のうち、最初の 2 基は東京湾で組み立てて福島沖まで曳航した。 3 基目の 7MW は長崎県で浮体を製造して、小名浜港まで曳航してから風車を搭載する方法をとった。 4 基目の「ふくしま浜風」は風車を搭載した状態で最長の距離を現場まで曳航する。 前方に 3 隻、後方に 1 隻の合計 4 隻で曳航しながら、周辺にも 3 隻の警戒船を配置する体制だ。
2016 年内に試運転開始へ
福島沖に展開する洋上風力発電設備は 4 基がそろって運転を開始すると、発電能力が 14MW に達して浮体式では世界最大の規模になる。 洋上風力発電の設備利用率(発電能力に対する実際の発電量)は標準で 30% 程度を想定できることから、年間の発電量は 3,680 万kWh (キロワット時)に達する見込みだ。 一般家庭の電力使用量(年間 3,600kWh)に換算すると 1 万世帯分を超える。
これだけ大量の電力を 20 キロメートル離れた福島県の沿岸部まで送るために、4 基のうち 1 基が変電設備として電力を集約する構成になっている。 運転中の 2 基の発電設備と変電設備は海底ケーブルでつながり、さらに変電設備から福島県の陸上までのあいだも海底ケーブルで接続済みだ。 「ふくしま浜風」も現場に到着した後に、設備の位置が移動しないように係留チェーンを海底まで下ろしてから、ケーブルの敷設工事に入る。 予定どおりに準備が進めば、8 月 1 日に敷設工事を開始して、1 カ月後の 9 月 2 日に完了する予定だ。 海底ケーブルで変電設備につながると、あとは調整作業を経て試運転を開始できる。
7MW の「ふくしま新風」の場合には、ケーブルの敷設完了から試運転開始まで約 3 カ月かかった。 5MW の「ふくしま浜風」も 9 月初めにケーブルを敷設できれば、12 月中に試運転を開始できる見通しだ。 年内には世界最大の浮体式による洋上風力発電所が福島沖で全面的に稼働する。 この壮大なプロジェクトが目指すのは世界で最先端の洋上風力発電所を実現して、福島の復興に向けた新しいエネルギー産業を発展させることにある。 海底に設備を固定しない浮体式の洋上風力発電では、波や風による揺れを抑えて安定稼働させることが最大の課題だ。 そのために 3 基の発電設備を支える浮体部分の構造を変えて、発電量や安全性などを比較検証する。
新たに加わる「ふくしま浜風」で採用したアドバンストスパー型は、六角形の構造物を 2 段に組み合わせて揺れを抑える。 2 段のうち下側の構造物のほうが大きくて、横幅は 51 メートルもある。 この巨大な構造物が水面下 33 メートルまで沈んで風車を支える仕組みだ。 すでに 2013 年 11 月から運転を続けている 2MW の「ふくしま未来」では、当初 2 年間の実績で設備利用率は平均 28.7% を記録した。 洋上風力発電の標準値 30% にはわずかに届いていないものの、ほぼ想定通りの発電量を上げている。 7MW と 5MW の 2 基のデータがそろえば、未来に向けて浮体式の洋上風力発電を広げる大きな一歩になる。 (石田雅也、SmartJapan = 7-8-16)
南極上空、オゾン層が回復の兆候 破壊物質規制が効果?
有害な紫外線をさえぎって皮膚がんの増加などから生物を守っているオゾン層が、南極上空で回復の兆候をみせているとの研究結果を、米英の研究チームが米科学誌サイエンスに発表した。 国際条約でオゾン層破壊物質を規制したことなどが効果をあげたと推測している。
破壊物質の代表格は、古い冷蔵庫やエアコンの冷媒、スプレーなどに使われた化学物質のフロン。 大気中に放出されると上空でオゾン層を壊す。 南極上空では、数十年前から穴があいたようにオゾン層が薄くなる「オゾンホール」が出現。 1987 年にオゾン層保護のための「モントリオール議定書」が採択され、各国でフロンの生産や使用などが規制された。
チームは、2000 年から 15 年間、オゾンホールが拡大する 9 月に南極で気象観測気球や衛星を使って観測した。 その結果、大きさは 00 年ごろにピークを迎え、その後 15 年間は変動しながらも小さくなっていることを確認。 約 450 万平方キロメートル縮小したと推測できた。 縮小の傾向は、破壊物質の排出量に基づいてオゾンホールの大きさを予測したシミュレーションの結果とも一致。 オゾンホールの大きさは、気温や噴火で放出される化学物質の影響も受けるとされるが、それらの影響を差し引いても、15 年間の縮小のうち約 350 万平方キロメートルは破壊物質の削減によるものと考えられるという。 (小坪遊、asahi = 7-5-16)
ネガワット取引、来年 4 月導入 節電通じて安定供給へ
経済産業省は 1 日、企業や家庭の節電で生まれた電力の余裕を売買する「ネガワット取引」制度の概要を示した。 来年 4 月から導入し、夏場など電力の需給が厳しいときに、需要を減らして電気の安定供給につなげる仕組みだ。
仲介役となる「ネガワット事業者」が家庭や企業と事前に契約し、電力の需給が厳しくなりそうな場合に節電してもらう。 生まれた電力の余裕を、電力小売事業者に販売し、売り上げの一部を協力した企業や家庭に報酬として支払う。 これまでも大手電力と電力を多く使う工場などの間で契約を結び、需給が厳しいときに節電を促す仕組みはあった。 今回の制度では、電力の小売事業者が他社エリアにある企業や家庭での節電分の余裕も買えるようになる。 (asahi = 7-1-16)
七夕や夏至にライトダウンの全国キャンペーン、4 時間の消灯で 700 万円の節電見込み
「ライトダウンキャンペーン」は、環境省の提唱したもので、施設や家庭の照明を消すことを呼びかけるものです。 6 月 21 日(夏至の日)及び 7 月 7 日(クールアース・デー、七夕)の夜 8 時から 10 時までの 2 時間、ライトダウンを実施するプロジェクトとなります。(一般社団法人エネルギー情報センター?新電力ネット運営事務局)
今回のライトダウンキャンペーンは、地球温暖化防止のため 2003 年から始まっており、これまで 14 年間継続して実施されてきました。 2003 年の当初は、夏至の日(6 月 21 日)を中心に、20 時から 22 時に施設の消灯を呼び掛ける取組でした。 2008 年には G8 サミット(洞爺湖サミット)が 7 月 7 日の七夕の日に開催されたことを受け、同日がクールアース・デイとして定められ、この日も 20 時から 22 時に消灯が実施されるようになりました。 このクールアース・デーは、「天の川を見ながら、地球環境の大切さを日本国民全体で再確認し、年に一度、低炭素社会への歩みを実感するとともに、 家庭や職場における取組を推進するための日」とされています。
今回の夏至におけるライトダウンにおいては、18,668 施設において節電が実施され、約 23.4万kWh の電気削減が見込まれています。 クールアース・デイについては、19,064 施設において、約 23.6万kWh ほどの電気削減見込みです。 ライトダウンキャンペーンの対象日時は、6 月 21 日と 7 月 7 日の両日における 20 時 - 22 時であり、合計 4 時間となります。 削減電力量は、合計で 47万kWh となり、電気料金を 1kWh あたり 15 円(業務用)と仮定すると、約 700 万円の電気代削減となります。
東京タワーやスカイツリー、大阪城など幅広い施設で実施
東京タワーは、基本的には日没から 24 時まで、2 種類のライトアップ(ダイヤモンドヴェール、ランドマークライト)を使い分け、毎日点灯しています。 また、スカイツリーや大阪城などの施設もライトアップをしておりますが、「ライトダウンキャンペーン」期間中は消灯される予定です。 民間企業も多数キャンペーンに参加しています。 例えば、マルイグループは 11 年間連続でキャンペーンに参加しており、今年も各店(一部店舗除く)が店外照明を中心にお店外周の光柱や壁面のマルイロゴを消灯します。 各店舗の光源タイプに合わせて、工夫をこらしたライトダウンが実施される予定です。 (新電力ネット = 6-19-16)
◇ ◇ ◇
電気を消して考えよう 19 日にキャンドルナイト
電気を消し、ろうそくの火のもとで環境や平和について考えるイベント「100 万人のキャンドルナイト」が 19 日、東京都港区の増上寺である。 今年で 14 回目。 東京タワーの消灯をカウントダウンするほか、音楽ライブが開かれる。 イベントを主催する「大地を守る会」の契約農家などがつくった有機野菜の販売も。 入場無料。 問い合わせは同会 (043・380・7760)。 (asahi = 6-8-16)
世界人口の 3 分の 1、天の川見られず 「光害」が影響
世界の人口の 8 割以上が街の照明などで夜空が明るくなる「光害」の影響を受けており、約 3 分の 1 は「天の川」が肉眼で見られなくなっていることが欧米の研究チームの分析でわかった。 米国民の約 8 割、日本では約 7 割が肉眼で見られず、最も深刻なシンガポールでは、ほぼ全土で夕方のように薄明るい夜が続き、自然の夜の暗さを感じなくなっているという。 米科学誌サイエンス・アドバンシズ(電子版)に論文が掲載された。 研究チームは高解像度の衛星写真を分析し、各国の地域ごとに自然状態の夜空に対し、人工光による「光害」の深刻度を 6 段階に分類した。
その結果、天の川が見られない都市部などに住む人口は、世界全体の約 3 分の 1。 先進国の割合が高く、米国では約 8 割、欧州で約 6 割、日本でも約 7 割に達した。 最も光害がひどいシンガポールでは、全土で人の目が暗いところに反応する「暗順応」が起きなくなるほどだという。 一方、アフリカ諸国では、人口の約 6 - 8 割が自然のままの夜空の下で暮らしており、一部の大都市を除き、多くの地域で天の川が見られる状態だった。 (ワシントン = 小林哲、asahi = 6-11-16)
企業の 1 割、省エネ不十分 経産省調査
経済産業省は 31 日、企業の省エネがどれだけ進んでいるかの調査結果を発表した。 エネルギーの消費実績を報告した全国 1 万 2,412 社のうち、9.7% の 1,207 社は消費が逆に増えるなど省エネができていなかった。 同省はこうした企業に同日付で注意喚起した。 原油換算で年間 1,500 キロリットル以上のエネルギーを使うメーカーや小売りなどさまざまな業種の大企業が対象。 2014 年度のエネルギー消費実績をもとに、省エネの達成度合いを 3 段階に分けた。 省エネがよくできている企業が 62.6%、普通が 27.7% だった。 (nikkkei = 5-31-16)
都市に絶滅危惧種、なぜ? 空港・団地 … 人工環境で繁栄
絶滅の危機に直面した希少種が見つけた安住の地は、なぜか都市の片隅。 そんな「不自然」な現象が時折、見つかるようになってきた。 人里近くの自然は多種多様な生物を育んできたが、人間生活の変化とともに包容力を失いつつある。 4 月末の晴天の日、大阪空港の脇にある公園を訪ねると、水色の金属光沢を放つ小さなチョウが地をはうように次々と飛んできた。 シルビアシジミ。 本来のすみかは、牛馬の餌や肥料を得るための草刈りで草丈が低く維持される河川敷などの草原だ。 適地が減り、国は絶滅の危険性が高い絶滅危惧 1B 類に指定。 埼玉や岐阜、愛媛などでは絶滅した。
それがなぜか爆音の響く空港で乱舞する。 足元はクローバー(シロツメグサ)やヒメジョオンなど外来植物だらけ。 大阪府立大の石井実教授は「悩ましい風景です」と漏らした。 石井さんらは 2003 年に空港での大発生を確認し、理由を探った。 一つは、空港は草丈が低く管理され本来の生息地と似ること。 もう一つは、幼虫が空港にない本来の餌のミヤコグサの代わりに外来のクローバーを食べることだ。 豊かとは言いがたい自然のもとで、希少種が偶然、適した条件を見つけた例は他にもある。 国の絶滅危惧 1B 類のツマグロキチョウは、愛知県の宅地などで外来植物のアレチケツメイを幼虫期の餌にし、増えた。
「希少種の復活イコール本来の自然の回復、ではない」と石井さんは言う。
■ 街中に「豊かな自然」
一方、たくさんの在来種が生息する「豊かな自然」が街中で見つかる例もある。 神戸市北部の団地内の斜面にある草地では 14 年、国の絶滅危惧 1A 類の多年草ヒメミコシガヤや兵庫県の準絶滅危惧種ギンランなど、各地で減少している草原性植物が 40 種近く見つかった。 兵庫県立淡路景観園芸学校の学生だった上村晋平さんと調査した同校の澤田佳宏准教授は「市内や近隣の農業地域でもだんだん減ってきた良好な環境だ」という。
農業地帯で良好な草地が減る理由の一つは、小さな農地をまとめて大規模化する農地改良だ。 工事で本来の草地がなくなると、草が再生するのに時間がかかる上に外来種も入りやすく、種数が減る。 耕作放棄も影響が大きい。 草刈りされなくなった草地を丈の高い草が覆い、低い草が生き残りにくくなる。 兵庫県北部では種数が 3 分の 1 以下に減った報告もある。 澤田さんは「団地では農家のかわりに管理者が草刈りを続けたため、昔と似た環境が維持され、植物が残ったのでしょう」と話す。
横浜市の住宅地に囲まれた二ツ池も都市に残る豊かな自然だ。 半世紀前に役割を終えた農業用ため池。 自然のなりゆきで十数年前からヨシなどの植物が茂るようになり、トンボが復活した。 県内で一度絶滅したアオヤンマなど約 40 種が住む。 神奈川県立生命の星・地球博物館の苅部治紀主任学芸員は「これだけ豊かな池は県内に他にはない」と言う。 トンボは新天地の開拓力が高く、新たに渡ってきたらしい。 だがなぜ、この池だけなのか。 「市街地なので、農薬の影響を免れたことが大きいのでは」と苅部さんは推測する。 (長野剛、asahi = 5-29-16)
「知床やベネチア、温暖化で危機」ユネスコが報告書
ユネスコ(国連教育科学文化機関)などは 26 日、地球温暖化で知床(北海道)やベネチア(イタリア)などの世界遺産が危機にさらされているとする報告書を発表した。 各国政府や観光産業などに、温室効果ガスの排出削減や被害の軽減策に取り組むよう促している。
報告書は、温暖化の影響が確認されている 29 カ国 31 カ所の自然遺産と文化遺産の状況をまとめた。 流氷が育む生態系が評価されている知床では流氷が減っている。 モアイで有名なイースター島(チリ)は海岸浸食で石像の近くまで波に洗われている。 南太平洋のニューカレドニアのサンゴ礁では大規模なサンゴの白化がみつかっている。 氷河が後退しているエベレスト一帯のサガルマータ国立公園(ネパール)などは観光収入への依存度が高く、地元経済への影響も大きい。 ガラパゴス諸島(エクアドル)などは温暖化の影響に加えて、過度な観光化も危機に拍車をかけているという。 (香取啓介、asahi = 5-26-16)
全大気の CO2 濃度、危険水準に 初の 400ppm 超え
環境省と国立環境研究所、宇宙航空研究開発機構は 20 日、温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」で観測した地球大気の二酸化炭素 (CO2) 濃度が、昨年 12 月に月平均で 400.2ppm に達したと発表した。 地表から上空約 70 キロまでの大気全体を観測できる衛星のデータで 400ppm 超えが確認されたのは初めて。
国連の気候変動に関する政府間パネル (IPCC) は、産業革命前からの気温上昇を 2 度未満に抑える国際目標の達成には 450ppm 程度にとどめる必要があるとしている。 400ppm 超えは危険な水準だ。 上空より濃度が高くなる地上の観測に基づく世界の月平均濃度は、すでに 400ppm を超えている。 いぶきの観測で、濃度上昇が上空を含む大気全体で続いていることが確かめられた。 観測では濃度は年約 2ppm ずつ上昇しており、この傾向が続けば年平均濃度も今年中に 400ppm を超えるという。 国立環境研の横田達也フェローは「温暖化の影響が出るのはずっと将来と思われているが、そんなに先ではない」と話す。 (小堀龍之、asahi = 5-21-16)
タイ、人気リゾート島が立入禁止に 観光客増え環境悪化
タイ・バンコク : 美しいビーチで観光客に人気のあった同国南部のタチャイ島が、無期限で観光客の立ち入り禁止となった。 タイ国立公園当局が 17 日、CNN に明らかにした。 観光客が増えすぎて生態系が著しく破壊されたためと説明している。 タチャイ島は国立公園に指定されたタイ南部シミラン諸島の北端にある。 真っ白なビーチは「タイのモルディブ」とも呼ばれ、ダイビングスポットとしても人気があった。
国立公園野生動植物保護局の担当者は、ゴミや食べ残しの放置に加え、ツアーボートから海に流れ込むガソリン、サンゴ礁の破壊といった問題が起きていると説明。 原因は観光客の増えすぎにあるとした。 「これほど小さな島なので、受け入れられる観光客は 1 日に数百人程度」、「それなのに(1 日に) 2,000 人近く来たこともあった」と担当者は話す。
タチャイ島は観光拠点プーケット島の約 137 キロ北西にあり、島内に宿泊施設はない。 訪れる観光客はほとんどが日帰りだが、テントに寝泊まりする泊りがけのツアーも運行されていた。 当局者によると、間もなくモンスーンの季節に入り、シミラン諸島のほかの島や沿岸部の国立公園も立ち入り禁止になる。 (CNN = 5-18-16)
温室ガス「2050 年までに 80% 減」 政府が閣議決定
政府は 13 日、温室効果ガスを「2050 年までに 80% 減らす」とする長期目標などを掲げた地球温暖化対策の計画を閣議決定した。 今月末にある主要 7 カ国 (G7) 首脳会議(伊勢志摩サミット)で、日本としても長期的に対策に取り組む姿勢をアピールする。
昨年末、温室効果ガス削減の新しい国際的枠組み「パリ協定」が採択され、各国は産業革命以前からの気温上昇を「2 度より十分低く保つ」との目標で一致した。 それには、今世紀後半には、温室効果ガスの排出を実質ゼロにするなど、大幅な削減が求められる。 伊勢志摩サミットはパリ協定採択後、初めての G7 サミットで、「気候変動・エネルギー」が主要な議題の一つ。 日本の温暖化対策は東京電力福島第一原発事故の影響で、国全体の対策がない「空白期間」が約 3 年続いていたが、温暖化対策への世界的な機運が高まる中で、計画の正式決定にこぎつけた。 (小坪遊、asahi = 5-13-16)
シャンゼリゼ、月 1 回歩行者天国に … 環境対策で
【パリ = 三好益史】 高級ブランド店などが立ち並び、世界一美しいとも言われるパリのシャンゼリゼ通りが 8 日、車両を通行止めにして歩行者天国となった。 パリでは車の排ガスによる大気汚染が深刻で、イダルゴ市長が環境対策として導入を決定。 来月から第 1 日曜は歩行者天国となる。 対象は直線約 2 キロ・メートル。 (yomiuri = 5-9-16)
省エネ技術普及へアピール 燃料電池車や未来型都市
「究極のエコカー」と呼ばれる燃料電池車 (FCV) の開発や、地域全体でエネルギーを効率的に利用する未来型都市「スマートコミュニティー」の取り組みで日本は世界をリードしている。 国内外での普及を目指し、今回の先進 7 カ国 (G7) エネルギー相会合は省エネ先進地の北九州市で開催し、日本の技術力をアピールした。
トヨタ自動車やホンダが国内で発売した燃料電池車は、水素と酸素で発電したエネルギーを使って走行し、温室効果ガスを排出しない。 G7 会合の会場では、内部構造を見えるようにした燃料電池車や、ガソリン車の給油に当たる水素の充填装置が展示された。 スマートコミュニティーの事例として、水素を活用して環境にやさしい街づくりを進める北九州市の取り組みも紹介した。 (sankei = 5-2-16)
ソーラー・インパルス、太平洋横断に成功 米加州に到着

燃料を一切使わない世界一周飛行に挑んでいる太陽光発電の実験機「ソーラー・インパルス 2」がこのほど、米カリフォルニア州マウンテンビューに着陸し、太平洋横断飛行を成功させた。 操縦士はスイス人探検家で精神科医のベルトラン・ピカールさん。 着陸後、CNN の取材に答え、「新しい時代が来た。 これは SF ではない。 クリーン技術は不可能を可能にできる。」と語った。 同機は 21 日にハワイを発ち、サンフランシスコ湾上空を数時間飛行した後に着陸した。
ソーラー・インパルス 2 の翼長はボーイング 747 型機と同程度。 しかし重さはスポーツ用多目的車 (SUV) ほどしかない。 飛行速度も自動車とほぼ同じで、ハワイからカリフォルニア州までの飛行に要した時間は約 62 時間だった。 世界 1 周を目指す同機の飛行は今回が 9 回目だった。 操縦はピカールさんと、スイス人技術者のアンドレ・ボルシュベルクさんが交代で担当している。
ソーラー・インパルス 2 は昨年 3 月、アブダビから世界 1 周の旅に出発し、同年夏の終わりにはアブダビに戻るはずだった。 しかし悪天候に見舞われて日本に緊急着陸した際に滑走路で機体が損傷。 修理を済ませた後に太平洋を横断して 7 月にハワイに到着した。 ハワイに着陸した時点でバッテリーが過熱して損傷していたことが分かり、修理に時間がかかってカリフォルニア州への出発は 10 カ月近くずれ込んでいた。 今後は大西洋を横断して欧州か北アフリカへ向かい、この夏の終わりには 3 万 5,000 キロの飛行を終えて中東へ戻る計画。 (CNN = 4-25-16)
前 報 (7-4-15)
パリ協定に 175 カ国署名 温暖化対策、米中の動向焦点
新たな地球温暖化対策の国際ルールである「パリ協定」の署名式が 22 日、ニューヨークの国連本部であった。 オランド仏大統領やケリー米国務長官ら 175 カ国(EU を含む)の首脳や閣僚らが出席し、協定書に署名した。 順調に行けば来年にも発効する。 パリ協定は、温室効果ガスの排出を今世紀後半までに「実質ゼロ」にすることを目指す。 昨年末の国連気候変動会議 (COP21) で各国が合意した。
日本は吉川元偉・国連大使が署名した。 署名は正式な批准に向けた国としての意思表示で、今後はそれぞれの国で批准手続きに入る。 発効には 55 カ国以上が批准し、その排出量が世界全体の 55% を上回ることが条件だ。 潘基文(パンギムン)・事務総長は「我々は時間との競争の中にある」として、各国に早期の批准を呼びかけた。 (小林哲 = ニューヨーク、香取啓介、asahi = 4-23-16)
突如に出現した巨大な穴は地球温暖化対策が待ったなしを示唆する時限爆弾だと科学者が指摘

地球温暖化によって異常気象や海水面上昇など、さまざまな環境問題が引き起こされると言われています。 一刻も早い地球温暖化対策が求められている状況で、近年、ロシアに次々と出現している直径数十メートルの巨大な穴は、地球温暖化進行を加速させるのではないかと懸念され始めています。
ロシアで初めて巨大な穴が出現したのは 2014 年のこと。 突如として出現した巨大な穴が上空のヘリから確認されたとき、それが一体何なのか分からず誰もが困惑したそうです。 直径 100 フィート(約 30 メートル)の穴は、隕石が落ちてできたという説や、ロシア軍の秘密の軍事兵器によってできたという説や、はてはエイリアンが作ったという説が現れるなど、さまざまな憶測を呼びました。 その後の調査によって、気温の上昇に伴って永久凍土が溶けて地中にあるメタンハイドレートがメタンガスとして噴出し、空中に飛散するときに巨大な穴を残したことが判明しました。
2014 年 7 月に最初の巨大な穴が発見されたときに、科学者からは世界的に起こっている地球温暖化の傾向から、今後も同様の事例が続くのではないかという指摘がされていましたが、その予想は的中。 シベリアを中心に同様の巨大穴が次々と発見されています。 メタンハイドレートがメタンガスになり大気中に大量に放出されれば、メタンガスは二酸化炭素の約 25 倍という極めて高い温室効果を持つため、地球温暖化の傾向はさらに加速度的に進みかねないという予想が出されています。
また、巨大な穴の中には、天然ガス田のわずか 6 マイル(約 10 キロメートル)という地点で見つかるものもあり、天然ガスとメタンガスという可燃性の気体が突如として放出されることで爆発が起こるのではないかと周辺地域の安全性についても問題視され始めているそうです。
シア科学アカデミーのバジリー・ボゴヤレンスキー博士は、衛星画像を用いた調査によって 20 個以上のクレーターを新たに確認。 これまで以上に緯度の高い場所にも見つかるなど、巨大な穴の出現範囲が広がっていると指摘しています。 ボゴヤレンスキー博士によると、穴がどこに出現するのかを予測するのは困難ですが、確実に増加する傾向にあるとのこと。 さらに、巨大な穴の出現に伴って地震が発生したという報告もあがっていると博士は述べています。
ロシアを中心に増え始めている巨大な穴は、地球温暖化によってもたらされており、同じ現象はアラスカなどの北米でも発生する可能性が指摘されています。 メタンハイドレート放出によってできる巨大な穴の出現によって、さらに温暖化が加速するという悪循環に入りつつある状況に対して、科学者からは地球温暖化対策を急ぐ必要性が訴えられてます。 (GigaZine = 4-17-16)
地球温暖化の理由の「10 分の 1」は中国によるもの
『ネイチャー』で発表された研究によると、地球温暖化の 10 パーセントは、中国による二酸化炭素排出が原因と考えられる。 しかし同時に、驚くべきことも判明した。 悪いニュースには、思いもかけなかったデータが混ざっていた。 『ネイチャー』で発表されたある研究において、李本綱の率いる中国の北京大学の科学者チームは、世界で初めて、地球温暖化における中国がどれだけ関与しているかを算定した。
特に、論文に付された論説においてドミニク・スプラクレンが明らかにしているように、この研究からは、「中国における化石燃料の使用による二酸化炭素の排出が、この数十年で劇的に増加した」こと、しかしまた、その間に「この国が地球規模の気候変化にどれだけ影響を与えたかについては、驚くべきことに一定のままだった」こと、そしてそれが[全体の]約 10 パーセントであることが判明した。
この事象について(推定される)理由を説明するためには、少し歴史を遡る必要がある。 科学者たちは、生物地球化学的・気候学的モデルを用いて、地球のいわゆる放射強制力への中国の寄与を評価した。 これは、気候システムのエネルギーバランス(すなわち、地球の大気システムの中に入るエネルギーから、同システムから出て行くエネルギーを引いたもの)の大きさのことだ。
惑星を熱する効果のある正の放射強制力は、温室効果ガスの濃度の変化により引き起こされる可能性がある。 これまでも、中国の急速な工業化が間違いなく気候変化にインパクトを与えたことは知られていた。 しかし、定量的にその大きさを確定させること、そしてとりわけ、さまざまな汚染物質の寄与を見分けることは非常に困難だった。
李本綱のチームは、このモデルによって、2010 年のみのものに加え、1750 年(つまり産業化以前の時代)から 2010 年までに含まれる期間における、地球の放射強制力に対する中国の寄与を定量化することに成功した。 発見したのは、化石燃料の利用に由来する二酸化炭素排出は、地球温暖化に最も大きく寄与した現象だが、メタンガスや黒色炭素エアロゾルも責任の一部を担っており、全体の 10 パーセントに達するということだ。 しかし、驚くべきことに、正味の寄与は、多かれ少なかれ常に同じだったということもわかった。
科学者たちによると、それは、大気中の硫酸塩の冷却効果によるものかもしれない。 硫酸塩は地球温暖化の効果を覆い隠すことで知られており、事実、その大気冷却への寄与は、産業化以前の時代の 10 パーセントから、現在は 30 パーセントにまで達している。 (Sandro Iannacc、WIRED = 4-11-16)
住宅用太陽光発電、4 割値下がり 「自給自足」近づく?
住宅用太陽光発電の設置費用などがここ数年で大きく下がり、20 年間使う場合の発電費用が、大手電力会社の電気料金とほぼ同じになったことが、自然エネルギー財団(東京都港区)の試算で分かった。 今後、電気をためる家庭用蓄電池の普及が進めば、電力会社に頼らない電気の「自給自足」も近づく。
同財団の木村啓二・上級研究員の試算。 太陽光パネル設置・維持費用と、20 年間使う場合の総発電量などから計算したところ、2014 年 10 - 12 月の 1 キロワット時当たり発電費用は 25.28 円で、10 年 4 - 6 月の 41.50 円から約 4 割下がった。 一方、この間の大手電力の家庭向け電気料金の平均は、東日本大震災後の原発停止や、円安による輸入燃料の高騰などで 20.37 円から 26.26 円に上がった。 (asahi = 4-4-16)
16 年度から始まる住宅省エネ表示「BELS」補助で活用
4 月 1 日から建築物省エネ法による住宅の省エネ性能表示制度がスタートし、販売・賃貸事業者へ省エネ性能表示が努力義務として課される。 表示方法としては、(1) 第三者認証に基づく表示「BELS」、(2) 自己評価、(3) 法律規定に基づく行政が認定する基準適合認定マーク - - の 3 つがある。
新築時などの省エネ性能を表示する住宅版の「BELS」は、申請手数料に対する補助に加え、中小工務店向け補助事業「地域型住宅グリーン化事業(優良建築物)」における申請要件の選択肢化や ZEH (ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)補助の申請時の加点要素とするなど、国の各種補助制度の要件として取り扱いが明確に位置づけられている。 (住宅産業新聞 = 3-31-16)