2015 年、世界経済の「勝ち組」と「負け組」
世界の経済成長の最終的な数値が集計されれば、2015 年は恐らくまた期待外れな 1 年として数えられるだろう。 各地の中央銀行は流動性の供給を続けた。 それでもなお経済成長は振るわず、原油価格は再び下落し、インフレは低調にとどまった。
15 年は好景気に沸いた国と景気減速に苦しんだ国の差が浮き彫りになった年でもある。 新興国の中では商品価格の急落でロシアやブラジルなどの大国が不況に沈んだ一方、インドやベトナムなどは経済が予想外に上振れした。 先進国では米国が雇用市場の堅調で 2006 年以来の利上げに踏み切ったが、隣国カナダでは景気低迷が深刻化した。
では、勝者と敗者を具体的に見てみよう。 先進国では、欧州小国の好調が際立つ。 アイルランドは 7 - 9 月期に 7% の経済成長率を達成。 ユーロ圏の 1.6% はもちろん、中国の成長率をも上回った。 対照的にフィンランドはさえなかった。 ギリシャ金融支援を声高に批判して存在感を示したが、製紙や家電など主要産業が苦戦したほか、ロシア向けの輸出需要冷え込みも打撃となった。 新興国ではベトナムやタンザニアの好調が目立った。 25 年ぶりの水準に低下したとはいえ、中国も成長率は他の新興国に比べれば依然として高い。 インドは 7 - 9 月期の成長率が予想を上回る 7.4% に上り、4 - 6 月期の 7% からさらに加速した。
負け組には前年と同じ顔ぶれが並ぶ。 ロシアは原油安が大きく響き、過去 20 年間で最長の景気後退が続く見通しだ。 ブラジルは商品安、政治混乱、汚職スキャンダル、財政赤字の拡大に圧迫される。 ゴールドマン・サックス・グループはブラジルが「全面的な恐慌」に陥りつつあると警告している。 また日本は速報値でマイナスとされた 7 - 9 月期の成長率が改定値でプラスに転じ、過去 3 年間で 2 回目のリセッション入りを免れた。 エコノミストの一部は日本経済が依然大きな課題に直面してはいるものの、全体的に改善の道を歩んでいると指摘する。 (Bloomberg = 12-31-15)
中韓 FTA が正式に発効 中国は 958 品目の関税を撤廃
中韓自由貿易協定 (FTA) は 20 日に正式に発効し、初めての関税削減も同時に始動した。 韓国側の提供した情報によると、中韓 FTA の正式な発効後に中国は 958 品目の関税を撤廃するという。
韓国産業通商資源部は 20 日、韓中(韓国と中国)、韓越(韓国とベトナム)、韓豪(韓国とオーストラリア)自由貿易協定は 20 日に正式に発効し、同日に初めて関税を引き下げた。 2016 年 1 月 1 日より、2 回目の関税削減を実施すると発表した。 韓国・聯合ニュースによると、初の関税削減を実施した後、中国とオストラリア産の輸入商品のうち、それぞれ 958 品目と 2013 品目の商品関税率はゼロになり、それにより多くの商品は 2016 年 1 月 1 日以降に関税を再び引き下げられることとなる。
韓国・News1 通信社によると、中韓 FTA の発効後に第 1 陣となる韓国の対中輸出商品は 2,600 余トンの硫黄で、税金を計 3,000 余ドル減免する。 中韓自由貿易協定の関税減免法案の規定に従い、中国側は関税品目数において 91% の関税を撤廃し、韓国からの輸入総額の 85% に相当するのに対し、韓国側は関税品目数において 92% の関税を撤廃し、中国からの輸入総額の 91% に相当する。 (中国・新華夏 = 12-21-15)
米が原油輸出解禁 40 年ぶり 日本の中東依存軽減
【ワシントン = 斉場保伸】 米議会上下両院は 18 日、1975 年から 40 年間続いた米国産原油の輸出禁止措置を撤廃する法案をそれぞれ賛成多数で可決した。 これにより、エネルギーを輸入に頼る日本にとっては原油の調達先を中東依存から分散する選択肢が広がるため、エネルギーの安全保障状況が大きく前進することになる。 輸出禁止措置の撤廃は米議会で 18 日可決された 2016 会計年度(15 年 10 月 - 16 年 9 月)歳出法案に含まれており、オバマ大統領の署名を経て成立した。
米国は 70 年代の第一次石油危機をきっかけに安保上の理由から「エネルギーの自給化(ニクソン大統領)」を掲げ、原油の輸出を原則禁止とした。 2000 年代になって中国経済の急成長などを背景に原油価格が高騰。 昨年夏までは 1 バレル = 100 ドルを超える水準で推移し、輸出は米国民の生活に直結するガソリン価格の高騰を招くとして困難とみられていた。
一方で「シェール革命」と呼ばれる新たな掘削技術の普及でここ数年、膨大な原油やガスが採掘されており、国内の原油がだぶつき気味になっていた。 さらに世界経済の減速に伴い原油価格は一時 1 バレル = 30 ドル台にまで下落し、エネルギー業界がダメージを受けていた。 共和党はエネルギー業界を支持基盤としており、輸出解禁を求めていた。 (東京新聞 = 12-19-15)
米利上げ、市場は好感 先導役、好景気維持が焦点
米国の中央銀行にあたる米連邦準備制度理事会 (FRB) が 16 日、2008 年から続けてきた「ゼロ金利政策」を終えた。 9 年半ぶりの利上げで、世界経済は新たな転換点を迎えた。 景気の足踏みが続く日本や欧州、低迷する新興国を尻目に、米国が好景気を維持できるかが焦点となる。
FRB の金融政策を決める連邦公開市場委員会 (FOMC) で、短期金利の指標となる「フェデラルファンド金利」の誘導目標を 17 日以降、いまの実質ゼロ水準から年 0.25 - 0.50% に上げることを決めた。 その後の利上げペースは緩やかになりそうで、市場は米景気が順調に回復していくと好感。 17 日の東京株式市場は日経平均株価の終値が前日より 303 円 65 銭高い 1 万 9,353 円 56 銭に上昇し、続く欧州市場でも株高が進んだ。 為替市場ではドルが買われ、1 ドル = 122 円台半ばの円安ドル高水準で取引された。
この利上げは、08 年の金融危機の震源地だった米国が、一足早く「非常時」から抜け出したことを意味する。 「ゼロ金利政策」と市場に大量のお金を流す「量的緩和政策」は日本銀行が採用した政策だったが、危機後に米国も導入。 一度はやめた日銀も形を変えて再開した。 欧州も同様に景気刺激を続ける。 日米欧の大規模緩和であふれた投資マネーは、新興国の高成長を支えてきた。 だが、すでに利上げを見越してマネーは新興国から引きあげられ、米国に還流している。
今後、日欧が緩和を続け、新興国の減速も強まれば、ドル高が進んで米国の輸出競争力を奪うリスクもある。 「グローバル経済の中で我々の運命は強くつながっている。」 FRB のイエレン議長は 16 日の記者会見で語った。 世界経済の先導役の米国が利上げを続けられるか、手探りは続く。 (五十嵐大介 = ワシントン、野島淳、asahi = 12-18-15)
■ FRB 決定のポイント
【政策金利の誘導目標】 「年 0 - 0.25%」から「年 0.25 - 0.50%」に引き上げ(17 日〜)
【景気認識】 米国景気は緩やかに拡大 雇用環境は今年に入って相当の改善
【物価上昇率】 年 2% の目標に中期的に近づくと相応の自信
【利上げペース】 緩やかに進むが、経済指標次第
米化学大手 2 社、合併合意 ダウ・ケミカルとデュポン
米国の化学大手ダウ・ケミカルと同業のデュポンは 11 日、対等合併することで合意したと発表した。 企業価値を示す株式時価総額を単純に合わせると、約 1,300 億ドル(約 15 兆 8 千億円)。 化学素材から農業関連分野まで幅広い事業を手がける巨大化学グループが誕生する。 新会社の最高経営責任者 (CEO) にはデュポンの現 CEO エドワード・ブリーン氏が就き、会長職にはダウ・ケミカルの CEO アンドリュー・リバリス氏が就任する。 合併後は、農業や高機能化学品などの三つの新しい会社に分割し、経営効率化をめざすという。 (ニューヨーク、asahi = 12-12-15)
◇ ◇ ◇
米ダウ・ケミカル、デュポンと統合交渉 10 日にも発表
米国の化学大手ダウ・ケミカルと同業のデュポンが、経営統合の交渉を進めていることがわかった。 複数の米メディアが伝えた。 10 日にも合意が発表される見通しという。
企業価値をあらわす株式の時価総額を単純に合わせると、約 1,200 億ドル(約 14 兆 6 千億円)。 ともに世界の化学業界を代表する企業で、統合後はそれぞれの事業を再編し、3 分割する案が出ている。 最近の業績に不満を持つ「物言う株主」が、両社に事業の再編で経営効率化を進めるように求めていた。 米国では、製薬大手ファイザーがアイルランドの同業アラガンを 1,600 億ドル(約 19 兆 5 千億円)で買収することで合意したと発表するなど、大型の M & A (合併・買収)が相次いでいる。(ニューヨーク = 畑中徹、asahi = 12-10-15)
米、中国を WTO に提訴 「外国製小型機に不当課税」
米通商代表部 (USTR) は 8 日、中国政府が外国製の小型航空機を不当な課税で差別しているとして、世界貿易機関 (WTO) に紛争処理の手続きに入るよう訴えた、と発表した。 自国製は免税扱いにする措置は公表しておらず、WTO の透明性のルールにも違反しているという。
USTR によると、中国政府は外国製の小型航空機に 17% の付加価値税を課す一方、自国製は不当に保護しているという。 免税扱いの対象には、中国政府などの共同出資会社が開発した小型ジェット旅客機「ARJ21」も入る。 三菱重工業などが手がける「MRJ (ミツビシ・リージョナル・ジェット)」とも競合するタイプだ。 2009 年のオバマ政権発足後、米国が WTO に提訴した事例は 20 件。 そのうち 11 件は中国が対象で、7 件で勝訴している。 (ワシントン = 五十嵐大介、asahi = 12-9-15)
SDR 採用でも人民元安を見込む投資家
際通貨基金 (IMF) が 11 月 30 日、中国人民元を来年 10 月から特別引き出し権 (SDR) を構成する通貨バスケットに加えることを決めたが、投資家の元安見通しに変わりはみられない。 投資家は中国経済がさらに減速すると予想し、中国人民銀行(中央銀行)が元を切り下げるとみている。 運用担当者らも、中国政府が自国の金融市場を外国の投資家に一段と開放するまで、各国中銀が元を準備通貨に加える動きは緩やかだろうと予想している。
それでも、元をドルとユーロ、英ポンド、円で構成する SDR の通貨バスケットに加えることを IMF が決めたため、長期的には元に対する国外からの需要が高まる可能性があると投資家はみている。 SDR への採用で、為替レートと金融システムに対する規制緩和を続けるよう中国政府は促されるだろう。 先日付為替相場でみると、オフショア(中国本土外)市場の 1 年先日付の対ドル元相場は直物よりも 3.5% 程度元安になっている。
バークレイズのアナリストは、引き続き一段の元安リスクがあるとみている。 30 日の顧客向けリポートで、「SDR への採用が人民元需要に及ぼす直接の影響は限定的だ」と述べた。 バークレイズでは、現在 1 ドル = 6.40 元程度の元相場が 2016 年半ばまでに 6.80 元になると予想し、オフショア元に対するドル買いを顧客に推奨している。
16 年 10 月に元が SDR の通貨バスケットに加わるため、各国中央銀行は外貨準備の持ち高を調整するだろう。 だが、SDR は世界の外貨準備のわずか約 2% を占めているに過ぎず、IMF によれば元の構成比率は 10.92% になる見通しなので、持ち高調整が元相場に及ぼす影響は限られる公算が大きい。
中国経済が減速しているため、中期的には一段の元安圧力も加わる可能性が高い。 中国の負債は経済規模に対し高水準にあり、商品(コモディティー)価格の下落で国内ではデフレ圧力が蓄積しているため、負債の管理がさらに難しくなっている。 投資会社ミレニアム・グローバル・インベストメンツの経済戦略グローバルヘッド、クレア・ディソー氏は「経済再建と債務解消の痛みを和らげるために便利な政策手段は、何らかの管理した通貨切り下げを行うことだ」と指摘した。 (James Ramage and Carolyn Cui、The Wall Street Journal = 12-1-15)
◇ ◇ ◇
人民元が「メジャー通貨」に IMF が「妥当」と報告書
国際通貨基金 (IMF) は 13 日、加盟国に資金を融通するための「特別引き出し権 (SDR)」の構成通貨に、中国の人民元を加えるのが妥当とする報告書をまとめた。 30 日の理事会で正式に決まれば、ドル、ユーロ、円、ポンドにならぶ五つ目の「メジャー通貨」の仲間になる。
IMF では、加盟国の出資額に応じて SDR と呼ばれる仮想通貨を割り当てている。 危機に直面した国は現在、SDR と引き換えにドルなどの四つの構成通貨で資金を受けられる。 今年はその構成通貨の 5 年に 1 度の見直しの年で、技術的な観点から検討していた。 構成通貨入りの判断には、その通貨を持つ国や地域の「輸出額の大きさ」と「通貨が自由に取引できるかどうか」の二つが判断基準とされる。 中国は 5 年前の入れ替え時に輸出額の基準を満たし、今回、取引の自由度も基準を満たしている、と判断された。 (ワシントン = 五十嵐大介、asahi = 11-14-15)
OPEC、原油 20 ドル台の懸念にも方針変更の気配なし
[ロンドン/ドバイ] 石油輸出国機構 (OPEC) は、政策立案の中心的役割を担うサウジアラビアに財政的苦難が訪れても積極的生産を維持する構えだ。 弱小加盟国は原油相場が 20 ドル台までさらに下落することを恐れ、警戒感を強めている。 ロシアを筆頭に OPEC 非加盟の主要産油国が協調して減産に参加しない限り、何ら政策の方向転換は実現しないとみられている。 ロシアは半年に一度の OPEC 総会に先立ち、OPEC の石油相らと会談を行うが、価格下落を食い止めるためにロシアが助けの手を差し伸べる可能性は小さい。
ある OPEC 加盟主要産油国の代表は「非加盟国が協力を申し出ない限り、変化は起きない。 OPEC 単独での減産はしない。」と話した。 OPEC が 6 月にウィーンで開いた総会で、サウジのヌアイミ石油鉱物資源相や他の富裕産油国の代表はほとんど喜びを隠せない状態だった。 増産によって台頭する競合サプライヤーから市場シェアを守るという昨年 11 月の OPEC の歴史的決定は効果を上げている。 原油価格が 65 ドル近辺で推移する中で OPEC はこのように宣言した。 しかし、6 カ月後の現在は 45 ドルまで下落した。 昨年中旬は 115 ドルまで上昇していた。
現在、加盟国の間では、21 世紀への変わり目に経験した 1 バレル = 20 ドル時代への逆戻りが語られるようになった。 イランに対する国際的な経済制裁が年内に解除されることに同国が自信を示していることが主な理由だ。
<強まる批判>
ロシアは 12 月 4 日にウィーンで開く OPEC 総会に先立ち、OPEC と非公式の協議に参加するが、ロシアが現在のスタンスを変更し、OPEC に協力して減産に応じる可能性はほとんどないと関係者は指摘する。 OPEC の 6 月の総会で政策維持を決めた際、明らかに大きな反対はなかった。 しかし、今回は OPEC のベネズエラなどのタカ派加盟国または弱小国からの反発が目に見えるようになり、同時に批判も強まっている。
別の加盟国代表は「サウジは減産を望んでおらず、何かが起きるとは思わない。 彼らは自ら墓穴を掘っており、他の加盟国にも災いを招いている。」 と突き放した。 OPEC 内の亀裂の深さを示す一例として、OPEC は 11 月に長期戦略の見直しで合意に至ることができなかった。 ロイターが把握した OPEC 文書の草案によると、イランやアルジェリアは OPEC が価格防衛を再開し、加盟国に対する割当制を通じて供給を管理すべきだと主張した。
しかし、こうした対策を支持する OPEC 内部の人々ですら、供給管理で合意できる可能性は低いとみており、前出の加盟国代表は「OPEC は生産比率の管理に向けた合意に達せず、サウジは現状の戦略を譲らないだろう。 割当制には到達しない。」と述べた。 OPEC は 2012 年に全体で日量 3,000 万バレルの生産目標を設定した際に割当制を廃止した。 ことしはこの上限を常時上回っており、これはサウジとイラクが過去最高の生産量となったことが要因だ。 OPEC の統計によると、10 月の生産は日量 3,138 万バレルに達した。
代表者らによると、日量生産 90 万バレルのインドネシアが 7 年ぶりに再加盟するのを機に、上限を 3,100 万バレルに引き上げる検討が行われる可能性がある。 来年の大きな不確定要素は、イランにどの程度の急速な余剰生産が可能かどうかだ。 OPEC 加盟の湾岸諸国は日量 10 万 - 20 万バレルを予想するが、イランは制裁解除から数カ月以内に 50 万バレルの増産が可能としている。
ベネズエラのエウロヒオ・デル・ピノ石油鉱業相は 22 日 「イランは制裁解除後にただちに増産すると発表しており、我々は対応を迫られる。 OPEC が価格戦争に突入することは認められない。 我々は市場を安定させる必要がある。」と語った。 来年 OPEC が方針変更できなかった場合、原油相場がどこまで下落するかという質問に対し、ピノ氏は「20 ドル台半ば」と答えた。
ゴールドマン・サックスは、世界的な過剰供給やドル高、中国の景気減速を理由に今年の原油価格が 20 ドルを下回る可能性があるとしていた。 大半のアナリストは、今の世界の大国との核開発抑制合意の下で、イランに対する制裁が来年春までに解除されるかどうかは疑わしいが、原油生産はいずれ増加に転じるとみている。
<苦悩するサウジ>
原油価格の崩壊によって OPEC は部分的に目標を達成したといえる。 世界の需要は拡大し、生産コストが比較的高い米国のシェールオイルの供給の伸びは抑制されたからだ。 来年の非加盟国の供給量も、苦戦する生産者側が設備投資を削減しているため、ほぼ 10 年ぶりに減少する見通しだ。 しかし、未だに世界では必要以上の原油が生産され続けている。 ロシアの生産量は予想外に過去最高を更新し、世界の原油在庫は膨れ上がっている。
OPEC の政策を主導するサウジの財政状況すらも一段と苦境に置かれている。 スタンダード・アンド・プアーズ (S & P) によると、サウジの今年の財政赤字の国内総生産 (GDP) 比は前年の 1.5% から 16% に急上昇する見通しだ。 サウジは今年の財政赤字は管理可能だと説明している。 しかし、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチは 23 日、サウジに対する圧力は非常に大きいため、ドルペッグ制を採用している通貨リヤルの切り下げ、または減産を迫られるとの見方を示した。
こうした減産は多くの競合産油国から戦略の失敗と解釈される方針の一大転換を意味する可能性がある。 逆に増産による長期的な見返りを期待するやり方は、サウジだけでなくカタール、アラブ首長国連邦 (UAE)、クウェートの裕福な湾岸諸国にとって依然として選ぶべき道のように思われる。 石油商社ガンボーの調査責任者デビッド・ファイフ氏は「現時点でサウジが市場シェア志向の戦略を転換しようとする兆候は何ら見られない。 サウジの戦略の耐久力は今後 12 - 18 カ月間のイラン、イラク、リビアによる増産によって試されるだろう。」と話している。 (Alex Lawler and Rania El Gamal、Reuters = 11-27-15)
日本の天気予報、40 カ国超で活躍中 ビッグデータ活用
世界各地の膨大な観測記録(ビッグデータ)をもとにした日本の天気予報が、世界で活躍している。異常気象が農作物に及ぼす影響が深刻化するなか、アジア諸国を中心に世界40カ国以上に普及。分析するコンピューターの進歩などで、予報の精度も年々向上している。
「まず、低気圧や高気圧を発達させる兆候を示すデータを見つけてください。」 17 日、東京・大手町の気象庁。 アジア各国の気象予報官らが、日本の職員から 1 カ月先の天気予報を行う際の注意点の説明を受けていた。 1 カ月予報では、高気圧や低気圧など規模の大きい現象から、気候の変化を捉えることが重要になるからだ。 8 回目を迎えた今年の研修には、パキスタンやミャンマーなど、アジアの 15 の国と地域から 15 人が参加し、20 日まで続く。 ベトナム水文気象予測センターのリ・ハさん (35) は「自国の 1 カ月予報は過去の統計を参考に作成する。 日本のように精度の高い予報を農業に役立てたい。」と話す。
気象庁が各国に無償で提供しているのが「数値予報」。 地球全体を 2 - 20 キロの格子状に区切り、各地点での気温や気圧などの膨大な観測データをスーパーコンピューターで計算。 高気圧や低気圧、前線の動きなど、今後の天気の移り変わりを予測する基礎データにあたる数値だ。 気象庁はこのデータを目的に応じたソフトで解析し、翌日や数カ月先の天気予報に活用。 各国は数値予報の一つで 20 キロ範囲で区切った「全球モデル」のデータ提供を受けて、1 カ月先の天気などを予測する。
予報の精度は、観測データの多さやスパコンの計算能力に左右される。 米英などの先進国もそれぞれ開発し、世界各国に提供するとともに精度を競っている。 気象庁は 2007 年ごろから外国への提供を開始。 09 年には世界気象機関からアジアの気象業務で指導的立場に指名され、各国が数値予報を使って正確な予報ができるように研修を開くようになった。 アジア以外にも、アフリカのケニアやリビア、オセアニアのフィジーにも提供する。
気象庁異常気象情報センターの大野木和敏所長は「日本のモデルが世界で活用されれば、不具合を改良する機会も増え、結果的に日本の予報精度も上がっていく」と話す。 (鈴木逸弘、asahi = 11-19-15)
米 10 月雇用は予想上回る 27.1 万人増・失業率 5%、12 月利上げ後押し
[ワシントン] 米労働省が 6 日発表した 10 月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が 27 万 1,000 人増となり、市場予想の 18 万人増を大きく上回った。 伸びは 2014 年 12 月以来最大。 失業率も 5.0% と前月の 5.1% から低下し、2008 年 4 月以来の水準となった。 5.0% は多くの連邦準備理事会 (FRB) 当局者が完全雇用と見なす水準。 労働市場が堅調に推移していることが示されたことで、FRB が 12 月の会合で利上げに踏み切る公算が大きくなった。
8 月、9 月分も当初発表から計 1 万 2,000 人上方修正された。 時間当たり賃金は 0.09 ドル増加。 前年比で 2.5% 増と、2009 年 7 月以来の大幅な伸びとなった。 不本意なパートタイム就業者や求職断念者も含めた広義の失業率は 0.2% ポイント低下の 9.8% と、2008 年 5 月以来の低水準をつけた。 一方、労働参加率は約 38 年ぶりの低水準の 62.4% で変わらずとなった。
10 月は幅広い業種で雇用が拡大した。 だが製造業はドル高の逆風が響き雇用は全く増えず、原油安の影響で鉱業は 4,000 人減少した。 一方、建設は 3 万 1,000 人増と、2 月以来の大幅な伸びとなった。 サービスは小売り、レジャーなどが大幅増となり 24 万 1,000 人増えた。 政府部門は 3,000 人増だった。 (Reuters = 11-6-15)
ミラノ万博閉幕 金賞・10 時間待ち … 日本館が一番人気
「地球に食料を、生命にエネルギーを」をテーマとしたイタリア・ミラノ万博が 31 日、半年間の会期を終え、閉幕した。 訪問者数は 2,100 万人を突破。 「和食を世界に売り込め」と日本中の自治体や食品メーカーなどが参加した「日本館」は、200 万人以上が来館し、展示デザイン部門で金賞を受賞。 参加した世界 140 以上の国や地域、国際機関の中でも高い人気を集めた。
日本館には、閉幕目前の 30 日にも 5 時間待ちの列ができていた。 日本館のリピーターになったというジョバンニ・バッザーナさん (66) は「日本食は地方色豊かで、酒の種類も豊富だと知った」と話した。 参加国・地域中で最大規模の敷地面積。 CG を駆使して日本の四季を紹介する展示や、観客参加型のショーが口コミで評判となり、10 時間待ちの日も。 「行列嫌いのイタリア人を並ばせた」と地元メディアでも話題になった。 26 日付のイタリア紙コリエレ・デラ・セラが発表した調査でも一番人気。 「詩情と科学技術のバランスが絶妙だ」と評価された。 (ミラノ = 山尾有紀恵、asahi = 11-1-15)
「日本の消費税率、さらに引き上げを」 IMF が提言
国際通貨基金 (IMF) は 30 日、日本が 2017 年 4 月に予定する消費税率 10% への引き上げ後も、「追加の財政健全化策が必要になる」として、消費税率のさらなる引き上げを求めた。
11 月にトルコで開かれる主要 20 カ国・地域 (G20) 首脳会議に向けた主要国の政策についての報告書を公表し、そのなかで「今後 10 年間で日本の国内総生産 (GDP) の 4.5% 分の財政健全化が必要になる」と指摘。 消費税率の段階的な引き上げや社会保障費の削減を求めた。 中国については、より持続的な成長を実現するため、金融市場の自由化や国営企業改革などの必要性を強調。 人民元については、今後 2、3 年で市場の動きに委ねた為替制度に移行するよう求めた。(ワシントン = 五十嵐大介、asahi = 10-31-15)
モンゴル、日本に熱視線 脱資源・中国頼みへ投資訴え
高い経済成長に陰りが出てきたモンゴルが、豊富な鉱物資源や中国との貿易頼みの成長モデルから脱却し、産業を幅広く育てようと模索している。 期待するのは、日本からの投資だ。人口 300 万人の資源大国の将来性を見込み、進出する日本企業も増えてきた。 ここ数年の開発ラッシュで、高層ビルやマンションが急速に増えた首都ウランバートル。 ただ、建設会社の関係者は「2 - 3 年前まではもうかったけど、いまは赤字。 良い建物をたてても買い手が少ないよ。」と、表情はさえない。
海外からの投資が減り、通貨安になって、物価は上がった。 市内に暮らす男性 (61) は「食品も値上がりして暮らしは大変だ。 一生懸命働いた末に、こんな生活になるとは。」とこぼす。 定職に就けない 2 人の息子の将来も気がかりという。 日本の 4 倍ほどの広さがあるモンゴル。 2011 - 13 年には 10% を超える高い経済成長が続いた。 石炭や銅、金などの鉱物資源が輸出の約 8 割を担う。 また輸出全体でみれば 8 割以上が隣国の中国向けで、中国経済の減速と資源の値下がりは大きな打撃だ。 14 年の成長率は約 8% で、15 年はさらに下がる可能性がある。
中国、そして石油の輸入が多いやはり隣国のロシア以外の国との経済交流を増やし、中小企業の育成など「鉱物資源に頼らない、競争力のある産業を育てていく(モンゴル政府高官)」ことが課題だ。 そこで期待を寄せるのが日本だ。 エルベグドルジ大統領は 8 月末、ウランバートルに来た経団連の幹部らに「これからは日本との経済関係をさらに発展させたい」と熱心に投資を呼びかけた。 (ウランバートル = 稲田清英、asahi = 10-18-15)
東京、8 年連続で世界 4 位 都市総合力ランキング
世界の主要都市を格付けする「世界の都市総合力ランキング」の 2015 年版で、東京は 08 年に調査を始めてから 8 年連続の 4 位だった。 森ビルが設立した森記念財団が 14 日発表した。 「文化・交流」、「経済」など 6 分野、70 の指標を得点化して主要 40 都市を比べた。 訪日外国人が増えたことで「文化・交流」の評価は上がったが、国際空港など「交通・アクセス」の分野の遅れが目立っている。 1 位は 4 年連続でロンドンで、上位に大きな変化はなかった。 大阪は順位を二つ上げて 24 位、福岡も一つ上げて 35 位だった。 (asahi = 10-15-15)
日本は競争力 6 位維持 世界経済フォーラム、インフラなど評価
【ジュネーブ = 原克彦】 世界経済フォーラムが 30 日発表した 2015 年版の「世界競争力報告」によると、日本の総合順位は前年と同じ 6 位だった。 項目別でも大きな変化はなく、インフラなど基礎的基盤が 24 位と1つ上がった一方、効率化の推進が 8 位と1つ下がった。 新興国ではインド(55 位)とベトナム(56 位)が大きく上昇した一方、ブラジル(75 位)は通貨変動もあり急落した。
日本は多くの個別項目で小幅な上昇・低下があり、全体で横ばい。 総じてインフラや教育、健康などの評価が高い一方で、財政赤字と公的債務の大きさが最下位かそれに近い順位で全体を押し下げる構図は変わらない。 もっとも上昇したのが「インフレ率」の評価で、前年の 62 位から一気に 1 位になった。 同フォーラムが適正とする水準に近くなったためだ。 安倍政権の経済政策「アベノミクス」が評価されたともいえるが、報告書の担当者は「構造改革など『第 3 の矢』は加速しておらず、効率化や技術革新ではまだやるべきことがある」と指摘する。
報告書は経済全体が安定することも重視しており、ブラジルが 57 位から 75 位へと転落したのは通貨急落などによる不安定さが要因という。 一方、ロシアは 45 位と前年の 53 位より上昇した。 評価に使われるデータは 14 年のものが大半で、次回の報告書では資源安の余波が全面的に反映される見通しだ。 世界 1 - 3 位はスイス、シンガポール、米国の順で前年と同じだった。
世界経済フォーラムは各国の政官財の指導者が集まる年次総会「ダボス会議」の主催団体として知られる。 競争力報告は 1979 年から発表しており、日本は 80 年代後半から 90 年代前半にかけて 1 位だったこともある。 ただ、評価基準が現在のものになった 05 年以降では、6 位が最高だ。 (nikkei = 9-30-15)
セブンがドバイに 1 号店 初の中東進出、独自メニューも
セブン & アイ・ホールディングスは 14 日、アラブ首長国連邦 (UAE) のドバイにセブン-イレブンを初出店したと発表した。 中東進出は初めて。 当初は七つの首長国のうちドバイに集中出店し、その後アブダビなどほかの首長国に展開していくという。
開店は現地の 13 日付。 現地の食文化にあわせたオリジナルメニューを開発し、ひよこ豆をすりつぶした「フムス」や、鶏肉の炊き込みご飯「チキンビリヤニ」なども提供する。 たばこは置くが、宗教上の理由から酒は売らない。 現地の王族が代表を務める地元資本の会社が運営する。 これまでセブン-イレブンの海外展開では米国法人が主導していたが、今回初めて立ち上げ段階から日本側が積極的に関わる。 (asahi = 10-14-15)
アップルが 3 年連続首位、トヨタ 6 位 世界ブランド番付
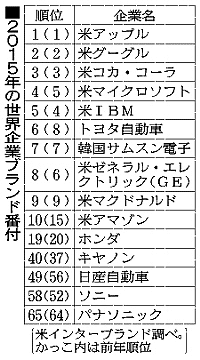
米調査・コンサル会社のインターブランドは 5 日、世界的企業の 2015 年版ブランド番付を発表した。 「iPhone」や「iPad」の人気が続く米アップルが 3 年連続で首位だった。 日本勢の最高はトヨタ自動車の 6 位で、前年の 8 位からアップした。 米企業がトップ 10 に 8 社入った。 2 位がグーグル、3 位はコカ・コーラで上位 3 社は前年と同じだった。 排ガス規制試験の不正に揺れる独自動車大手フォルクスワーゲン (VW) は、9 月に問題が発覚したことも反映させた結果、前年の 31 位から 35 位に後退した。
日本企業はトヨタのほかホンダ(19 位)、キヤノン(40 位)、日産自動車(49 位)、ソニー(58 位)、パナソニック(65 位)の計 6 社がトップ 100 に入った。 スマートフォン向けのゲームで出遅れた任天堂は前年の 100 位からランク外となった。 調査は、世界で展開する企業の収益性や消費者の支持をインターブランド社が独自集計し、順位を付けて毎年発表している。 今年で 16 回目となる。 (ニューヨーク = 畑中徹、asahi = 10-7-15)
IMF、世界成長予想を再引き下げ 中国経済減速や商品価格安で
[リマ] 国際通貨基金 (IMF) は 6 日公表した世界経済見通しで、コモディティ(商品)価格の低迷や中国経済の減速を理由に、世界の成長率予想を 7 月時点から引き下げた。 予想の下方修正は今年 2 度目。 IMF は、需要を喚起する政策が必要と指摘した。
世界成長率の予想は 2015 年が 3.1%、16 年は 3.6% で、7 月時点から 0.2% ポイント下方修正した。 4 月時点からはそれぞれ 0.4% ポイント、0.2% ポイントの下方修正となった。 主要国・地域では、米国の 15 年成長率を 2.6%、16 年を 2.8% と予想。 ユーロ圏は 15 年が 1.5%、16 年は 1.6%、日本は 15 年が 0.6%、16 年は 1.0% と予想した。 中国の成長率は 15 年が 6.8%、16 年は 6.3% と予想した。 見通しが特に悪化したのは新興国。 コモディティ価格急落を理由に 15 年の成長率予想を 4% に引き下げた。
IMF は「世界成長のリスクは引き続き下向き」としたうえで「中国経済の動向、コモディティ市場におけるリバランスのさらなる長期化、企業バランスシートの対外エクスポージャー拡大、資産価格の破壊的シフトに関連した資本フローの逆転といったリスクを鑑み、新興国や途上国の成長下方リスクは増大した」と指摘した。 米連邦準備理事会 (FRB) が利上げを視野に置く一方で、日銀や欧州中央銀行 (ECB) については追加緩和観測が出ている。
IMF は金融政策だけでは世界成長を再び勢いづかせることはできないと強調。 「財政的に余裕がある国々が補完的な財政政策を講じて世界経済のリバランスを後押しすることも重要で、とりわけ生産性向上や投資刺激に向けて需要を支援する構造改革が必要」とした。 (Reuters = 10-6-15)
多国籍企業に納税報告義務化へ OECD 報告書
先進国中心の 34 カ国でつくる経済協力開発機構 (OECD) は 5 日、多国籍企業の行き過ぎた節税を防ぐための国際的なルールをまとめた報告書を公表した。 税逃れに使われる「知的財産権」のやりとりを透明化して課税するのがねらいで、企業にはやりとりの実態や各国への納税状況の報告を義務づける。 8 日にペルー・リマで開かれる主要 20 カ国・地域 (G20)( 財務相・中央銀行総裁会議で報告され、11 月の G20 首脳会議で最終合意する。 46 カ国が参加する。
税務当局への報告が義務づけられるのは、連結の年間収入が 7 億 5 千万ユーロ(約 1 千億円)以上の企業。 日本企業では約 1 千社が対象になるとみられる。 2016 年以降の活動について、進出国ごとの所得や納税額、従業員数、主な事業などを国税庁に報告するよう義務づける。 与党内の議論を経て、年末の 16 年度税制改正大綱に盛り込まれる見通しだ。 (青山直篤、asahi = 10-6-15)
アンコール寺院遺跡、修理完成 奈文研が海外で初
カンボジアの世界遺産「アンコール遺跡群」で、奈良文化財研究所(奈文研、奈良市)が進めている石造寺院跡「西トップ遺跡(9 - 15 世紀)」の調査修理事業のうち、南祠堂の修理が終わり、23 日、現地で記念式典があった。 奈文研が海外の建造物で行う修理が完成するのは初めて。 遺跡は都城遺跡アンコールトム内にあり、中央・南・北の三つの石積みの祠堂からなる。 ヒンドゥー教寺院として造営されたが、途中で仏教寺院に転換したとみられる。
2002 年からの調査で、石材に木の根が入り込んで一部が崩れるなど危機的な状態にあることが判明。 12 年から南祠堂(14 世紀)の修理を始めた。 上下 2 段の基壇に石積みの本体が載る構造(高さ 4 メートル以上)だったが、基壇の一部が崩れるなどし、全面的に解体修理した。 カンボジアでは長い内戦で石造建造物の修理技術を持った人材が乏しく、奈文研は、「飛鳥美人」の国宝壁画で知られる高松塚古墳(特別史跡、奈良県明日香村)の石室を解体した技術力を生かし、修理と人材育成を進めてきた。
事業を指揮する奈文研の杉山洋・企画調整部長は「カンボジアが内戦の混乱から再生していく中、日本人が得意な文化支援でお役に立てることを示せたのではないか。 外交の最前線でも文化貢献は大きな意味を持っている。」と話す。 残る北、中央の両祠堂も順次修理し、20 年度までに完了させる計画だ。 遺跡の調査修理事業は、公益財団法人朝日新聞文化財団が 12 年度から助成している。(シエムレアプ = 塚本和人、asahi = 9-24-15)
ADB 総裁、AIIB 総裁候補と合意 協調融資を選定
アジア開発銀行 (ADB) の中尾武彦総裁は 21 日、中国が主導して設立するアジアインフラ投資銀行 (AIIB) の金立群(チンリーチュン)・総裁候補と北京で会談した。 両氏は、二つの銀行が協調融資するプロジェクト選びに入ることで合意した。
ADB の 21 日の発表文によると、両行は今後、ADB が手がけるプロジェクトについて、AIIB が融資で協力できるかを検討する作業に入るという。 AIIB には日本と米国が参加を見送っているが、この両国が主導する ADB は 5 月、中尾総裁が AIIB へ協力する意向を示していた。 AIIB は年内の設立を目指して準備が進む。 経験の少ない設立当初は、先行する ADB などの国際金融機関と協力した融資案件が多くなるとみられている。 (北京 = 斎藤徳彦、asahi = 9-21-15)
◇ ◇ ◇
アジア投資銀、参加 70 カ国超に = 初代総裁が見通し
【ソウル】 韓国の通信社・聯合ニュースによると、中国主導のアジアインフラ投資銀行 (AIIB) の初代総裁に選出された金立群・元中国財政次官は 9 日、AIIB の参加国数について「(創設メンバーの) 57 カ国から、近く 70 カ国余りに増えるだろう」と述べた。 訪問先のソウルで行われた企業関係者との懇談で発言した。 参加が 70 カ国を超えれば、日米が主導するアジア開発銀行 (ADB) の 67 カ国・地域を上回る。 (jiji = 9-9-15)
安保法制で転換迎える日本、「普通の国」なお遠く
[東京] 安全保障の関連法案が、週内に成立する公算が高まった。 自衛隊と米軍は中国を想定した備えができるようになるが、日本は「イスラム国」空爆のような作戦には今後も参加できず、英国やオーストラリアといった「普通の国」とは、まだ開きがある。 自衛隊の役割拡大に対する米国の期待が過剰に高まれば、かえって日米関係がぎくしゃくするとの指摘もある。
<第 1 列島線を防衛>
新たな法制による変化の 1 つが、日本周辺で活動する米軍を、領域の内外を問わず自衛隊が守れるようになることだ。 哨戒や訓練といった平時の活動中でも、武力衝突に発展した有事でも、日米が互いに守り合って共同作戦を行えるようになる。 中国は南西諸島からフィリピン、ボルネオ島まで伸びる島々を「第 1 列島線」という防衛線に設定している。 米軍の艦船や航空機を中国本土に接近させないようにするのが狙いだ。
米軍と自衛隊が共同哨戒や訓練を増やし、連携して動く態勢を整えれば、東シナ海で活動を強める中国へのけん制となりうる。 仮に平時から事態がエスカレートしても、日米共同で軍事衝突に対処することが可能になる。 米ウッドロー・ウィルソン・センターの客員研究員である道下徳成氏は、第 1 列島線を日米共同で防衛する作戦を立案できるようになると指摘する。 「軍事作戦の観点からは、これが最も重要だ」と、小泉純一郎政権で内閣官房副長官補付参事官補佐も務めた道下氏は言う。
<軍事作戦に日本を組み入れる>
新法制では、自衛隊による米軍の後方支援も拡大する。 日本の平和と安全に重要な影響を与える事態が起きたと判断すれば、南シナ海や中東といった日本から離れた場所でも、そこで戦う米軍に補給などを行うことが可能になる。 支援内容も、弾薬提供や発進準備中の戦闘機への給油にまで広がる。 「軍事作戦の中に日本を組み入れることができるようになる」と、知日派として知られる米戦略国際問題研究所 (CSIS) のマイケル・グリーン上級副所長は言う。 「日本が武力攻撃の任務を負うことはないが、共同で軍事作戦を立てるには十分だ」とグリーン氏は語る。
<「普通の国」の半分>
1991 年の湾岸戦争以来、自衛隊の役割を徐々に広げてきた日本にとって、新法制は大きな転換と言える。 一方で、英国やオーストラリアといった米国の他の同盟国と比べれば、「普通の国」にはなお遠いとの指摘もある。 新法制で集団的自衛権を行使するには、日本の存立が脅かされるなど 3 条件を満たす必要がある。 安倍晋三首相は、武力行使を目的に他国の領土へ自衛隊を派遣することは憲法違反で、中東のホルムズ海峡での掃海を除いて想定できないと説明。 イスラム国への空爆に参加することはないと繰り返してきた。
「これまで(普通の国の) 25% だったものが倍増して 50% になり、海外に自衛隊を派遣する柔軟性と能力が増す。 しかし『業界標準』からすれば、まだ 50% 足りない」と、豪ニューサウスウェールズ大学のアラン・デュポン教授は語る。 安倍首相が今年 4 月末に米議会で同盟強化を訴えた後、森本敏・元防衛相は米国内を回って法案や日米新ガイドライン(防衛協力の指針)について説明した。 「『ぜひ成立させてほしい』とみんなに言われたが、よく話を聞くと、国際法上、米国と同等な集団的自衛権を行使できるのではないかと誤解している専門家がいた」と森本氏は話す。
今年 3 月末に訪米し、似たような経験をした拓殖大学の川上高司教授は「日本と米国の間で認識のギャップがある。 実際にできることの間にギャップがあるので、摩擦が起きるのではないかと思う。」と懸念している。 (久保信博、リンダ・シーグ、Reuters = 9-16-15)