世界新車販売、過去最高の 8,300 万台 13 年 3% 増
米中の二大市場がけん引
2013 年の世界の新車販売台数が前年比 3% 増の 8,300 万台強と、4 年連続で過去最高を更新したもようだ。 中国、米国の二大市場が販売増をけん引。 需要が低迷した欧州や東南アジアなどの不調を補った。 14 年は米国の成長に陰りが出るとみられるものの新興国が販売を盛り返し、世界の新車販売台数は 8,800 万台前後に拡大する見通しだ。
調査会社フォーインによると、2013 年の世界の新車販売台数は 8,380 万台と、12 年実績(8,146 万台)を 230 万台強上回ったもようだ。 世界の新車需要は 08 年のリーマン・ショック後に一時停滞したが、経済成長が続く新興国を中心に 10 年以降は堅調に市場拡大が続いている。 世界最大市場の中国は前年比 1 割増の 2.150 万台前後になったとみられる。 自動車の普及が遅れていた内陸部へもマイカーブームが広がり「中国が世界市場をけん引する構図は当面続く(米フォード・モーター)」との見方は多い。
世界 2 位の米国も 7.6% 増の 1,560 万台と、6 年ぶりの高水準となった。 超低金利や株高を背景に、ピックアップトラックなど大型車の販売が好調だった。 世界 3 位の日本は消費増税前の駆け込み需要が下支えし、販売台数は 2 年連続で 500 万台超となったのが確実だ。
一方、欧州ではドイツの乗用車販売台数が 295 万台と同 4% 減り、3 年ぶりに 300 万台を割り込むなど停滞が続いた。 東南アジアも最大市場のタイが振るわず、主要6カ国は前年並み。 景気の先行き不安が強まったインドは同約 5% 減少したとみられる。 14 年は引き続き中国が販売を拡大。 東南アジアではインドネシアが伸び、南米ではアルゼンチンやチリの販売台数が増える。 米国は買い替え需要が一巡し、成長が鈍化しそうだ。 (北京 = 阿部哲也、nikkei = 1-4-14)
◇ ◇ ◇
米新車販売、前年比 7.6% 増 6 年ぶり 1,500 万台に
米調査会社オートデータが 3 日発表した 2013 年の米国の新車販売台数は、前年比 7.6% 増の約 1,560 万台になった。 リーマン・ショック前の 07 年(約 1,614 万台)以来、6 年ぶりに 1,500 万台の大台を超えた。
米国の新車販売台数は、リーマン・ショック後の不況で 09 年には約 1,042 万台まで落ち込んだが、その後は少しずつ増えてきていた。 13 年も景気回復を背景に、しばらく新車を買い控えていた人たちが購入に動いた。 連邦準備制度理事会 (FRB) の低金利政策で自動車ローン金利が下がり、買いやすくなったことも影響したとみられる。
メーカー別では、米フォード・モーターが前年比 10.8% 増の 249 万台と大きく伸ばした。 主力の大型車ピックアップトラックが 13% 増えたのが目立った。 最近は燃費のよい小型車だけでなく、大型車や高級車も売れだしている。 米最大手ゼネラル・モーターズ (GM) の高級ブランド「キャデラック」も 22% 増えた。 (asahi = 1-4-14)
韓国製造業に逆風 … ウォン高、中国勢と競争激化
安い製品を武器に「勝ち組」とされてきた韓国の製造業に、逆風が吹き始めた。 通貨ウォン高による輸出の減少に加え、国内外での競争が激化しているからだ。
◇ FTA の影
韓国自動車最大手、現代自動車の 2013 年 1 - 9 月期連結決算は、税引き後利益が前年同期比 4.2% 減の 6,863 億円だった。 今年に入ってからウォンの対ドル相場が 1,000 ウォン強で推移し、輸出が落ち込んでいるのに加え、傘下の起亜自動車と合わせて米国で 4 月に約 187 万台をリコール(回収・無償修理)するなどして信頼を低下させたことが、顧客離れを招いた。 さらに、シェア(占有率) 7 割以上を誇る国内市場も揺らいでいる。 今年 1 - 10 月の輸入車のシェアは 12% 強となり、最近 5 年間で 2 倍に伸びた。
背景には、所得水準の向上で欧州車を中心に高級輸入車の人気が高まっていることに加え、韓国政府の積極的な自由貿易協定 (FTA) 戦略がある。 対欧州連合 (EU) では 11 年 7 月、対米国では 12 年 3 月にそれぞれ FTA が発効し、8% だった自動車の輸入関税が段階的に下がっている。 16 年 7 月には、欧米からの輸入車には関税がかからなくなる。 そうなれば、現代自動車のシェア低下に拍車がかかる可能性もある。
◇ 鉄余り
鉄鋼大手ポスコも、13 年 7 - 9 月期決算の営業利益が、前年同期比 37.9% 減の 633 億円と大きく落ち込んだ。 大口顧客である国内自動車メーカーの需要が低迷している上、ライバルの中国メーカーがリーマン・ショック後に設備投資を大幅に拡大し、「鉄余り」の状況となっているためだ。
7 - 9 月期の営業利益がこれまでの最高を更新した電機大手サムスン電子にも、死角はある。 利益の大半を依存するスマートフォンは、安価な中国製などとの価格競争が激しくなっており、収益力の低下は避けられそうにない。 スマートフォンなどの特許侵害を巡って各国で起きている米アップルとの訴訟の費用が、経営の重しとなる恐れもある。 (yomiuri = 12-14-13)
◇ ◇ ◇
韓国の国家競争力 6 ランク下落の 25 位 … マレーシアより低く
韓国が、今年の世界経済フォーラム (WEF) による国家競争力評価で 6 ランク下落し、マレーシアよりも低い 25 位を記録した。 これは 2004 年の 29 位以降、9 年ぶりに最も低い順位だ。
比較対象の 148 カ国中、スイス・シンガポール・フィンランドは昨年と同様 1 - 3 位を占めた。 ドイツ・米国は前年よりそれぞれ 2 ランク上昇して 4、5 位に上がり、スウェーデン・香港・オランダ・日本・英国が 6 - 10 位の順に記録した。 アジア諸国だけで見ればシンガポール 2 位、香港 7 位、日本 9 位、台湾 12 位、マレーシア 24 位、中国 29 位となった。
韓国の企画財政部は、今年の WEF 国家競争力順位が大きく落ちたのは、北朝鮮からの威嚇が急に増した 4 月に調査が行われたためだと説明した。 12 部門にわけて行われる WEF 評価は、114 の細部項目のうち 80 項目が各国企業の最高経営責任者 (CEO) を対象に質問して評価するため、企業家の心理が悪化するとすぐに国家競争力の下落につながる。
こうした事情にもかかわらず今年の順位が大きく下がった部門は、韓国が慢性的に脆弱だという評価を受け入れた部分だ。 制度的要因(62 → 74 位)、労働市場効率性(73 → 78 位)、金融市場成熟度(71 → 81 位)の 3 部門が代表的だ。
この中の「制度的要因」の細部項目を見ると、なぜ低い評価を受けたのかが克明になる。 政治家に対する公共の信頼(117 位)、政府規制負担(114 位)、政策決定の透明性(133 位)、企業理事会の有効性(121 位)、少数株主の利益保護(109 位)といった分野は全て 100 位圏外の判定を受けた。 労働市場の効率性の部分でも労使間協力(129 位)、雇用および解雇慣行(109 位)は下位圏だった。 金融市場の成熟度の部分でも貸出の容易性(118 位)やベンチャー資本の利用の可能性(110 位)が 100 位圏外に留まった。
一方韓国は、スイス国際経営開発院 (IMD) の評価では今年まで 3 年連続で 22 位を記録した。 オ・サンウ企画財政部競争力戦略課長は「IMD は統計中心に評価し、WEF はアンケート調査の比重が大きく、調査結果に差がある」と話した。 (韓国・中央日報 = 9-5-13)
1 ユーロ 141 円台前半 5 年 2 カ月ぶりの円安水準
9 日の東京外国為替市場の円相場は、前週末 6 日発表の米国の雇用統計を受け、1 ドル = 103 円台前半の円安傾向で推移している。 対ユーロでも 1 ユーロ = 141 円台前半で 2008 年 10 月以来 5 年 2 カ月ぶりの円安水準だ。 午前 10 時時点は、前週末午後 5 時時点より 95 銭円安ドル高の 1 ドル = 103 円 08 - 09 銭、ユーロに対しては同 1 円 82 銭円安ユーロ高の 1 ユーロ = 141 円 31 - 33 銭。
雇用統計が市場予想を上回ったことで、米国の景気が順調に回復しているとの見方から、量的金融緩和の縮小が早まるとの観測が出て、ドル買いの動きが広がっている。 米国の雇用統計は欧州の株式市場も押し上げ、対ユーロでも円を売る動きが強まっている。 東京債券市場では、長期金利の指標とされる満期 10 年物国債の流通利回りが、前週末の終値と同じ 0.670% で取引されている。 (asahi = 12-9-13)
ドーハ・ラウンド、部分合意 = 01 年の開始以来「初成果」 - WTO、威信失墜回避
【ヌサドゥア(インドネシア)】 インドネシア・バリ島で開かれていた世界貿易機関 (WTO) の閣僚会議は 7 日、難航していた新多角的貿易交渉(ドーハ・ラウンド)で、貿易円滑化など 3 分野の「部分合意」を盛り込んだ閣僚宣言を採択、閉幕した。 ドーハ・ラウンドが 2001 年に始まって以来、具体的成果が出たのは初めて。
焦点だった農産物への補助金の扱いをめぐり、激しく対立していた米国など先進国とインドが妥協。 貿易円滑化の文書表現に不満を表明した中南米諸国も最終的に受け入れた。 多国間の貿易自由化を目指す WTO の交渉機能がまひし、威信が失墜する最悪の事態は土壇場で回避された。
WTO のアゼベド事務局長は閉幕に当たって「WTO 発足以来初めて合意の責務が果たせた」と成果を強調した。 加盟 159 カ国・地域が合意したのは、輸出入を促進するために税関手続きを簡素化する「貿易円滑化」、発展途上国の食糧安全保障を目的とした補助金の特例など「農業の一部」、後発発展途上国に対する優遇措置である「開発」の 3 分野。 交渉は途上国による農業補助金が焦点となった。
インドは WTO 協定に違反する一定額以上の補助金を認めるよう求めた。 米国や欧州連合 (EU) は補助金で安い農産物が輸出されれば、貿易価格がゆがめられると反対したが、恒久措置ができるまで特例を認めることで決着した。 (jiji = 12-7-13)
OECD : 世界の成長率見通し引き下げ - 日本は今年 1.8% 予想
経済協力開発機構 (OECD) は 19 日、今年と来年の世界経済の成長率見通しを下方修正した。 インドやブラジルなど新興市場国の景気拡大ペース鈍化を考慮した。 OECD は 19 日公表した半期経済見通しで、世界経済の成長率を今年が 2.7%、来年は 3.6% と予想した。 5 月時点ではそれぞれ 3.1%、4% と見込んでいた。 インドは今年が 3.4% (5 月時点は 5.7%)、来年が 5.1% (同 6.6%)、ブラジルは今年が 2.5% (同 2.9%)、来年は 2.2% (同 3.5%)と予測した。
OECD の主任エコノミスト、ピエールカルロ・パドアン氏はインタビューで、「新興国・地域の大部分には基本的に脆弱性があり、これまでのような成長は続けられないだろう」と発言。 「これら諸国は困難な時期に世界経済の成長をけん引する重要なサポート役を果たした。 現在は逆の状況になっているが、先進諸国も再び非常に好調な時期を迎えたとは言い難い」と分析した。
OECD の経済見通し引き下げは、リーマン・ブラザーズ・ホールディングスの破綻から 5 年が経過した今も、世界経済が依然としていかにもろいかを示すものだ。 ユーロ圏は今年に入ってリセッション(景気後退)を脱したものの、OECD はこの日の報告で、欧州中央銀行 (ECB) は追加緩和の方法を模索すべきだとし、米連邦準備制度は景気刺激の縮小を開始する前に今しばらく緩和姿勢を維持する必要があると指摘した。
米国とユーロ圏
OECD は米国の今年の成長率を 1.7%、来年は 2.9% と予想。 米国についての予想は 5 月時点からほぼ変わらず。 ユーロ圏は今年がマイナス 0.4%、来年はプラス 1.0% になるとの見通しを示した。 13 年についての従来予想はマイナス 0.6% だった。 パドアン氏は「欧州ではもっと景気を支援する金融政策が可能だ。 われわれはデフレリスクがあると考えている。」と述べた。
OECD は報告で、今月 7 日に予想外の利下げを実施した ECB について、過去最悪の失業率や銀行のデレバレッジ(借り入れ依存の解消)、タイトな信用環境に苦しむ域内経済をてこ入れするため、非伝統的な金融政策措置を検討すべきだとの見解を示した。 日本の成長率については、今年が 1.8%、来年が 1.5% と予測。 政府債務が国内総生産 (GDP) の 230% を超えている状況で、20 年の基礎的財政収支(プライマリーバランス)の黒字化に向けて「信頼に足る財政再建プラン」を持つことが「最優先課題」だと論じた。
中国
OECD は、世界経済見通しの変化に対応して政策調整を進めている中国について、「小規模な財政刺激策」で内需が回復し、今年が 7.7%、来年は 8.2% 成長になると予想した。 成長が近年に比べて低めとなる中でも、流動性と与信の拡大を抑制する必要があるとした上で、中国政府に社会保障の向上と金融自由化、税制改革を呼び掛けた。
パドアン氏は「中国は引き続き極めて力強い。 中国が他の国と違うのは、政府が迅速に経済の弱点に対処し、構造変化を通じて成長を続けてきた点だ。 ますます中間所得層中心の国になりつつある。」と指摘した。 OECD は今回初めて 15 年の成長率見通しを公表し、世界全体が 3.9%、米国が 3.4%、ユーロ圏が 1.6%、日本が 1%、中国が 7.5% と予想した。 (Bloomberg = 11-19-13)
グラウンド・ゼロにビル完成 建築家の槇文彦さん設計

【ニューヨーク = 真鍋弘樹】 9・11 同時多発テロで崩壊したニューヨークの世界貿易センター (WTC) ビル跡地「グラウンド・ゼロ」で事件後初めて、ビルが完成した。 日本人建築家の槇文彦さん (85) が設計した「4WTC」。 13 日の式典で、槇さんは「歴史的な日であり、建築家として幸せ」と語った。
72 階建て、高さ 298 メートルの 4WTC は、跡地に建てられる複数のビルの一つで、追悼施設のメモリアルパークに面している。オフィスのほか、市庁舎や地元港湾局が入居する予定で、式典にはマイケル・ブルームバーグ市長も参加した。 (asahi = 11-14-13)
第 3 四半期の米 GDP 速報値、年率 +2.8% に加速
[ワシントン] 米商務省が 7 日発表した第 3・四半期の国内総生産 (GDP) 速報値は、年率換算で 2.8% 増となり、2012 年第 3・四半期以来の高い伸びとなった。 前期の 2.5% 増から加速し、エコノミスト予想の 2.0% 増を上回った。 ただ、詳細を見ると強さに欠く内容となった。
最終需要の伸びが 1.7% にとどまり、エコノミストの間では、この水準では連邦準備理事会 (FRB) が量的緩和を縮小するには不十分との声が聞かれる。 また、在庫変動による押し上げが 0.83% ポイントと大きく、これを除くと成長率は 2.0% になる。 さらに個人消費支出と民間設備投資が大幅に鈍化し、FRB の緩和縮小見送りを正当化する形となった。
経済活動の 3 分の 2 以上を占める個人消費支出は 1.5% 増と、2011 年第 2・四半期以来の低い伸びとなった。 前期は 1.8% 増だった。 消費の鈍化は、夏季の気温が低かったために電力需要が弱くなったことが 1 つの要因だが、第 3・四半期に雇用の拡大ペースが鈍化したことで消費が抑えられた面もある。 消費支出の鈍化によって企業は在庫の削減を迫られる可能性があり、そうなれば第 4・四半期の成長率が押し下げられることなる。
ゴールドマン・サックスのエコノミストは、在庫変動の影響を踏まえて第 4・四半期 GDP の伸び率予想を従来の 2% から 1.5% に下方修正した。 景気の短期的な見通しがそれほど明るくないため、FRB は資産買い入れプログラムの縮小を来年に先送りするとみられている。 バンク・オブ・アメリカ・メリル・リンチのエコノミスト、ジョシュア・デナーレイン氏は「FRB が縮小を開始する前に確認したいとしている成長加速は、依然みられない」と指摘した。 景気の見通しが不透明なことから企業は雇用を増やすことに慎重で、設備投資も抑制している。
民間設備投資の中でも、機器への投資は 2012 年第 3・四半期以来の減少となった。 ただ、住宅を除く構造物への支出は、2 四半期連続で増加した。 一方、輸入の伸びが鈍化したことで貿易赤字の拡大が抑えられ、成長率を押し上げた。 貿易の寄与度は 0.31% ポイントだった。 政府調達は、州・地方政府の増加が寄与し 1 年ぶりに増加した。 ただ、連邦政府の支出は前四半期に続いて減少した。 住宅投資は、住宅ローン金利の上昇にも関わらず、大幅な増加となった。
年初からの財政引き締めで米経済の上半期の成長率は 1.8% だったが、緊縮財政の重しが取れることで、成長率は第 4・四半期に加速すると従来は予想されていた。 ただ、10 月の政府機関の閉鎖が悪影響を与えそうだ。 メシロウ・フィナンシャルの首席エコノミスト、ダイアン・スウォンク氏は「民間セクターは夏にかけて鈍化し、10 月の政府機関の一部閉鎖の影響に対する緩衝材の役割を十分に果たせなかった」と指摘した。 (Reuters = 11-8-13)
◇ ◇ ◇
米 ISM 非製造業景況指数 : 10 月は 55.4 に上昇、受注は低下
米供給管理協会 (ISM) が発表した 10 月の非製造業景況指数は市場予想を上回った。 米供給管理協会 (ISM) が発表した 10 月の非製造業総合景況指数 は 55.4 と、前月の 54.4 から上昇した。 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想の中央値は 54 だった。 同指数で 50 は活動の拡大と縮小の境目を示す。
ウェルズ・ファーゴのシニアエコノミスト、マーク・ビトナー氏は、一部政府機関の閉鎖について「連邦政府と関連性の強い分野ではマイナスの影響を受けただろうが、それ以外の景気は問題なかったようだ」と述べ、「非製造業部門はかなり堅調に推移している」と続けた。 ISM の非製造業には公益事業や小売り、ヘルスケア、住宅関連、金融など経済の約 90% を占める部門が含まれている。
10 月の総合景況指数を項目別に見ると、景況指数は 59.7 と前月の 55.1 から上昇した。 雇用指数は 56.2 と、前月の 52.7 から伸びた。 一方、新規受注は 56.8 と、前月の 59.6 から低下した。 (Bloomberg = 11-6-13)
◇ ◇ ◇
10 月の米新車販売、6 年ぶり高水準 6.5% 増
【ニューヨーク = 畑中徹】 米調査会社オートデータは 1 日、米国の 10 月の新車販売台数が 120 万 8,036 台だったと発表した。 1 営業日あたりでは前年同月比で 6.5% 増えた。 10 月としては 2007 年以来、6 年ぶりの高水準だ。
このペースのまま売れ続けたと想定すると、年間で 1,523 万台となる高水準だという。 10 月前半は、米政府機関の一部閉鎖もあって、「消費者心理が冷え込み、客足が鈍った(米大手メーカー)」が、その後は勢いが戻った。 メーカー別では米最大手ゼネラル・モーターズ (GM) が同 11% 増と好調。 最近はガソリン価格も下がっており、「燃費がよくなくても、大型車や高級車を求める傾向が強い(日系メーカー)」という。 大型車などに強みがある米国勢に追い風だ。 (asahi = 11-3-13)
◇ ◇ ◇
米製造業景況感指数、0.2 上昇し 56.4 10 月、2 年半ぶり水準
【ニューヨーク = 河内真帆】 米サプライマネジメント協会 (ISM) が 1 日発表した 10 月の製造業景況感指数は 56.4 で前月比 0.2 ポイント上昇した。 上昇は 5 カ月連続で 11 年 4 月以来、2 年半ぶりの高水準となった。 全体指数を構成する 10 項目中 7 つが前月比でプラスとなった。 「輸出」が前月比 5.0 ポイント上昇と最大の伸びを見せた。 「在庫」も同 4.0 ポイント上昇した。 一方「雇用」は 2.2 ポイント、「価格」が 1.0 ポイントそれぞれ低下した。 (nikkei = 11-2-13)
日本へ「アリガトウ」 援助隊、レイテ島で医療支援開始
台風 30 号がフィリピンを直撃してから 15 日で 1 週間。 多数の死傷者が出た中部・レイテ島タクロバンでは、日本の緊急援助隊医療チームの活動が始まった。 特設のテントには傷ついた人々が長い列を作った。 キャサリン・アモヤンさん (32) は出産を間近に控える弟夫妻にかわり、夫妻の子のハリー君 (2) を連れてきた。 ハリー君は溺れかけたところを救出されたが、脇腹を痛めた。 「ひどい状況だけど、信頼できる医療を受けられて助かる。 アリガトウ。」
国連によると、これまでに判明した犠牲者数は 4,460 人。 日本政府は近く、自衛隊員 1,180 人を被災地に送り込む方針を決めた。 日本人については 75 人と連絡がついておらず、安否確認のため、外務省幹部を急きょ在マニラ日本大使館に派遣した。 (asahi = 11-16-13)
ロシア首相、極東開発の失敗認める 「結果出ていない」
【モスクワ = 駒木明義】 ロシアのメドベージェフ首相は 24 日、プーチン政権が最重要課題と位置づける極東開発について「思うような結果が出ていない。 経済効果を生んでいない。 我々はそのことを声に出して言わねばならない。」と述べ、異例の率直さで失敗を認めた。
イタル・タス通信によるとメドベージェフ氏はこの日、ロシア極東コムソモリスクナアムーレで、自身が委員長を務める極東発展委員会の会合に出席。 「極東を抜本的に発展させるためのここ数年のすべての取り組みは、うまくいっていない」と指摘した上で、新しいアプローチが必要だという考えを示した。 一方で「もちろん奇跡は起きないし、予算が明日急に増えるわけではない」と課題が困難なことも認めた。
アジア太平洋地域の経済発展を取り込もうとするプーチン大統領は昨年極東発展省を新設。 インフラ整備を軸とする発展計画も策定したが実施が遅れており、担当相を更迭するなど態勢の立て直しに追われている。 (asahi = 10-24-13)
一時 4 年ぶりの円安ユーロ高水準 東京外為市場
23 日の東京外国為替市場は、前日公表された 9 月の米雇用統計が市場の予想を下回ったことを受け、「米国の量的緩和策が当面続く」との見方から、ドルが主要通貨に対してほぼ全面安になった。 午後 1 時時点の円相場は、対ドルで前日午後 5 時時点に比べ 77 銭円高ドル安の 1 ドル = 97 円 54 - 56 銭。 対ユーロでは、同 01 銭円高ユーロ安の 1 ユーロ = 134 円 47 - 50 銭。 対ユーロでは、一時、約 4 年ぶりの円安ユーロ高水準となる 1 ユーロ = 135 円 30 銭近辺をつけた。
午前中にユーロ高が進んだ要因について、市場では「ユーロは相対的に懸念材料が少なく、金融政策も緩和を縮小する方向にあるとして買いが進んだ(大手信託銀行)」とみられている。 23 日の東京債券市場でも、金利の先高感が薄らいだ米国の動きに連動して、長期金利が低下した。 指標になる満期 10 年物国債の流通利回りは、一時 5 カ月半ぶりの低水準となる年 0.600% まで下がった。 (asahi = 10-23-13)
米政府デフォルト回避へ 債務上限引き上げ案、両院可決
【ワシントン = 五十嵐大介】 米議会の上・下院は 16 日夜(日本時間 17 日午前)、米政府の債務(借金)上限を来年 2 月 7 日まで引き上げ、政府の一部閉鎖も解消する法案を可決した。 オバマ大統領は法案にすぐに署名すると明言しており、米政府の債務不履行(デフォルト)が回避された。
債務上限は、17 日の期限ぎりぎりの 16 日深夜に引き上げられることが決まった。 上・下院を通過した法案では、来年 1 月 15 日までの暫定予算を成立させることを通じ、10 月 1 日から続いている政府機関の一部閉鎖も即時に解消する。 与野党は同時に、赤字の削減策などについて協議する委員会を作り、今年 12 月中旬までに報告書をまとめることでも合意した。
焦点になっていた、オバマ政権の目玉政策「医療保険改革法(通称・オバマケア)」の扱いについては、「医療保険に加入する際に補助金を受ける人の所得確認を厳格化する」という微修正にとどまった。 共和党が求めていた、正副大統領や連邦議員、議会スタッフらを補助金対象から外すことは、盛り込まれなかった。 上院はこの法案を賛成 81 票、反対 18 票の大差で可決。 下院は、賛成 285 票、反対 144 票だった。 (asahi = 10-17-13)
◇ ◇ ◇
米政府、一時閉鎖の公算大 オバマケア予算で与野党対立
【ワシントン = 五十嵐大介】 米国の連邦政府が、17 年ぶりに一部閉鎖となる可能性が高まってきた。 今月末までに暫定予算案が成立しないと、政府運営のお金の手当てができなくなる。 オバマ政権の目玉政策「オバマケア(医療保険改革法)」を巡る与野党の対立は妥協点が見えないまま、期限を迎えようとしている。
野党・共和党が多数を占める米議会下院は 29 日、上院が可決した 2014 会計年度(13 年 10 月 - 14 年 9 月)の米連邦政府の暫定予算案を拒否し、下院の修正案を可決した。 オバマケアに反対する下院は、修正案に実施の 1 年延期や、財源となる医療機器を対象とした税金の廃止を明記。 一方、政府閉鎖に備え、軍の隊員に給料を払い続ける法案も可決した。
下院はもともと、オバマケア関連予算を削除した暫定予算案を可決したが、与党・民主党が多数を占める上院が 27 日、オバマケア予算を復活させた予算案を可決し、下院に送っていた。 上院案が 11 月 15 日までとした暫定予算の期間は、下院案では 12 月 15 日までと 1 カ月延ばした。 民主党はいかなる形でもオバマケアの変更には反対で、下院の予算案に賛成する可能性は低い。 ホワイトハウス報道官は 28 日、「共和党の要求は向こう見ずで無責任だ」と批判した。 (asahi = 9-30-13)
日本に構造改革求める 国際通貨金融委が声明採択
【ワシントン = 高田寛、五十嵐大介】 国際通貨基金 (IMF) の主な国や地域が、国際的な通貨や金融システムなどについて話し合う、国際通貨金融委員会 (IMFC) が 12 日、米ワシントンで開かれた。 IMFC は、日本に構造改革を求める内容を盛り込んだ声明を採択して閉幕した。 共同声明では、世界経済の現状について、「回復は継続している」としながらも、「新たなリスクが出現している」と指摘。 その一つとして、「多くの新興国で成長は緩やかになっている」ことを挙げた。
米国の債務上限問題については、主要 20 カ国・地域 (G20) 財務相・中央銀行総裁会議の声明と同様に、「米国は短期的な財政の不確実性に対処するために緊急の行動をとる必要がある」と求めた。 日本に対しても、「中期的な財政健全化と成長を活性化させるための構造改革を実施すべきだ」と要請した。
2010 年に決めた新興国の発言権を強くする IMF 改革については、今回の会合でも実質的な進展はなかった。 事実上の拒否権を持つ米国の議会が批准しないため実行できずにおり、新興国の間からは不満の声も上がっている。 このため、声明には「批准を完了していない全ての加盟国に、遅滞なくそれを行うよう求める」という文言を引き続き盛り込んだ。
米議会は、米国の相対的な存在感の低下につながる IMF 改革にもともと消極的とされる。 財政問題で与野党の対立は激化しており、批准のめどがたっていない。 (asahi = 10-14-13)
◇ ◇ ◇
世界成長率、2.9% に下方修正 IMF、新興国不振で
【五十嵐大介】 国際通貨基金 (IMF) は 8 日に公表した最新の世界経済見通しで、2013 年の世界経済の実質成長率予想を前年比 2.9% に下方修正した。 米国を中心に先進国が緩やかに回復する一方、インドや中国など新興国の減速がより鮮明になった。 見通しでは「世界経済は依然弱い」と分析。 世界の成長率見通しは、前回 7 月より 0.3% 幅の下方修正となった。
悪化の主な要因は、新興国の減速だ。 新興・途上国の成長見通しは、前回の 5% から 4.5% に引き下げられた。 特にインドは、5.6% か 3.8% と大幅な減速となった。 米国による巨額の金融緩和が縮小に向かうという観測から、新興国から資金が急速に流出し、「夏場にかけて金融環境が急速に引き締められた」と指摘した。 新興国について IMF は「内需拡大や規制緩和などの構造改革が必要」としている。 (asahi = 10-8-13)
◇ ◇ ◇
日本だけ 2% 成長に上方修正 IMF 経済見通し
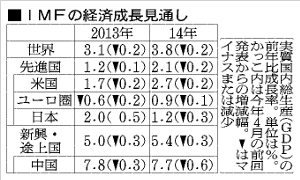
【ワシントン = 山川一基】 国際通貨基金 (IMF) は 9 日、最新の世界経済見通しを発表した。 新興国の伸び悩みなどを背景に、ほとんどの先進国と新興・途上国の成長見通しを下方修正した。 ただし日本だけは、日本銀行による金融緩和の効果を見込んで上方修正し、前年比 2.0% の成長を見込んだ。
2013 年の世界の成長率は 3.1% で 14 年は 3.8% と見込んだ。 いずれも今年 4 月時点の見通しから 0.2% 幅引き下げた。 「いくつかの新興国の低成長と欧州の不況が大きく響いている」という。 ただし日本は「金融緩和が民間需要に効果を及ぼす」として、13 年は 0.5% 幅上方修正した。 東日本大震災の反動で伸びた昨年(2.0% 増)と同じ成長を見込む。 それ以前でみると、10 年(4.7% 増)以来の高い成長率だ。 一方で、14 年は世界の景気鈍化の影響を踏まえ、0.3% 幅下方修正し、1.2% 増と予想した。 (asahi = 7-9-13)
◇ ◇ ◇
世界の成長率 2.2% に下方修正 2013 年、世銀見通し
【ニューヨーク = 佐藤大和】 世界銀行は 12 日、経済見通し(改訂版)を発表し、2013 年の世界経済全体の実質経済成長率を 2.2% と前回(1 月時点)に比べて 0.2 ポイント下方修正した。 中国やインドなど新興国とユーロ圏の景気を厳しく見直した。 一方、1 - 3 月期の高成長を踏まえ、日本は 1.4% 成長と 0.6 ポイントの上方修正とした。
米国は 2.0% 成長と前回予測 (1.9%) とほぼ横ばい。 一方、公共投資から民需主導の経済構造への転換を迫られている中国は、7.7% と前回から 0.7 ポイント引き下げた。 新興国経済の先行きを巡っては、米国の量的緩和策の縮小に伴う投資マネーの逆流を懸念材料と指摘した。 地域別で不振が目立つのがユーロ圏。 マイナス 0.6% と 2 年連続のマイナス成長が避けられないと判断した。
14 年の世界経済の見通しは 3.0% と、米中を軸とした成長加速を想定している。 日本は 1.4% 成長と、今年と同じ水準を見込んだ。 成長加速を実現するには規制緩和など構造改革の徹底が不可欠と指摘した。 (nikkei = 6-13-13)
WTO 交渉を後押し、共同声明を採択 APEC 閣僚会議
【ヌサドゥア = 藤田知也】 インドネシアのバリ島であったアジア太平洋経済協力会議 (APEC) の閣僚会議が 5 日、共同声明を採択して閉幕した。 声明では、世界貿易機関 (WTO) の多角的貿易交渉(ドーハ・ラウンド)を支持し、交渉を後押しすることなどを盛り込んだ。 12 月に開く WTO の閣僚会合で、税関手続きの簡素化や農業補助金、途上国の優遇措置の 3 分野で成果が出るよう連携していくことも明記した。
関税をなくすデジタル製品の品目を増やす情報技術協定 (ITA) の改定交渉も、12 月上旬までの決着をめざす方針を確認した。 交渉に消極的だった中国やタイも前向きな姿勢に転じるとみられ、決着に大きく近づくことになる。 (asahi = 10-5-13)
2013 年のイタリア財政赤字、EU 上限超過の公算 = IMF
[ローマ] 国際通貨基金 (IMF) は 27 日、2013 年のイタリアの財政赤字が対国内総生産 (GDP) 比 3.2% となり、政府目標の 2.9% や欧州連合 (EU) が上限とする 3.0% を上回るとの見通しを示した。 イタリアは、2012 年の財政赤字が対 GDP 比 3% となったことに加え、13 年は同 2.9% になるとの見通しを踏まえ、今年 5 月に EU の過剰財政赤字是正手続きを終了したばかり。 再び是正対象となることを回避するため、年内の緊縮実施が急務であることが浮き彫りになった。
IMF は、2013 年のイタリアの成長率をマイナス 1.8%、14 年はプラス 0.7% と予想。 イタリア政府が見込む今年のマイナス 1.7% と来年のプラス 1.0% よりもやや悲観的な見通しとなった。 公的債務削減に向けた措置としては、労働市場とサービスセクターの規制緩和や司法制度の合理化、行き詰まっている民営化の加速などに取り組むよう求めた。 (Reuters = 9-28-13)
米 FRB、金融緩和を継続 規模縮小の予想覆す
【ワシントン = 五十嵐大介】 米連邦準備制度理事会 (FRB) は 18 日、金融政策を決める連邦公開市場委員会 (FOMC) で、市場に大量のお金を流す「金融緩和」を現状のまま続けることを決めたと発表した。 市場では、金融緩和の規模を縮小するのではないかと予想する専門家が多かった。
FRB は 2008 年の金融危機後、市場に流すお金の量を金融政策の目安にする「量的緩和」を導入し、断続的に大規模な金融緩和を進めてきた。 昨年 9 月からは量的緩和の第 3 弾 (QE3) を始め、直近では毎月 850 億ドル(約 8.4 兆円)の国債などの金融資産を買い上げ、市場に大量のお金を流している。 (asahi = 9-19-13)
「絹の道」に経済ベルト 中国・習主席が提唱
【北京 = 佐藤大】 中央アジア歴訪中の中国の習近平国家主席は、ユーラシア大陸の経済連携強化を目指す「シルクロード経済ベルト」構想を提唱した。 13 日にキルギスで開かれる上海協力機構 (SCO) 首脳会議で、加盟国と同構想を協議する。 「アジア太平洋地域への回帰」を進める米国に対抗する狙いもありそうだ。
習氏はロシアで開かれた 20 カ国・地域 (G20) 首脳会合を挟み、トルクメニスタン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギスを訪問し、各国の大統領らと相次いで会談。 中央アジア地域への影響力を一層強め、同地域に豊富な石油・天然ガスの権益確保を加速させている。 習氏は 4 日、中国国有企業が、トルクメンで開発を進める埋蔵量世界 2 位のガルキニシュ・ガス田の生産開始式典に出席し「エネルギー分野の協力は両国の根本利益に合致する」と手放しで喜んだ。
シルクロード経済ベルト構想はカザフの大学で 7 日開かれた講演会で提唱。 習氏は「太平洋からバルト海まで物流の大動脈をつくる」と表明し「この周辺の人口は約 30 億で、市場の潜在力は唯一無二だ」と強調した。 経済ベルト構想は、中国と中央アジアのほか、ロシアやインド、パキスタンなども含めた広範な地域を想定しているとみられる。
また中国・新疆ウイグル自治区と接するキルギスでは 11 日、アタムバエフ大統領と会談。 両国は協力し、ウイグル族の独立勢力「東トルキスタン・イスラム運動 (ETIM)」に対する取り締まりを進めることで一致し安全保障面での関係強化も図った。 習氏は歴訪最終日の 13 日、キルギスの首都ビシケクで開かれる SCO 首脳会議で構想をあらためて説明し、加盟各国に同意を求める。 (東京新聞 = 9-13-13)
<上海協力機構 (SCO)> 中国、ロシアと中央アジア 4 カ国で構成する多国間協力組織。 2001 年 6 月に上海での首脳会議で創設。 経済や安全保障などの分野で関係を強めている。 モンゴル、イラン、インド、パキスタン、アフガニスタンがオブザーバー国として参加している。
リーマン・ショックから 5 年 開催意義問われる G20 首脳会合
【サンクトペテルブルク = 平尾孝】 6 日に閉幕した 20 カ国・地域 (G20) 首脳会合は、シリアへの軍事介入を検討する米国と、これに反対する議長国ロシアがともに、各国の支持を取り付ける動きが活発化し、これが焦点となった。 しかし、本来の経済サミットとしての存在感は、20 カ国の首脳が勢ぞろいした割には発揮できなかった。 発足のきっかけとなった 2008 年のリーマン・ショックから 5 年。 経済サミットとしての G20 の役割が問われている。
「一つのテーマに各国が意見を応酬するような議論はほとんどなかった。」 政府関係者は G20 会合での様子をこう説明した。
テーマごとの議論時間は約 2 時間で、20 カ国の首脳、国際通貨基金 (IMF) などの国際機関トップらが発言すると、他国の状況について意見したり、質問したりすることができないのが実情だ。 米国による量的金融緩和の縮小検討が、新興国からの資金流出を招いているとされる問題でも、「インフレや通貨の下落で自国の経済状況が厳しいことを語るだけで、米国への批判もなく、オバマ米大統領がそれに反応することもなかった(政府同行筋)」と一方通行だった。
G20 首脳会合は、リーマン・ショックの対応を先進国、新興国が連携して対処するために発足。 リーマン後も、ギリシャなど欧州の債務危機問題、先進国の財政健全化など世界経済に関するテーマが議題にあがった。 経済成長の著しい新興国と集中的に協議できる場として、主要 8 カ国首脳会議に比べて存在感を増していった。 今回は緊迫化するシリア問題をめぐる各国の対立が影を落とし、政治色の強い異例の会合となった。 政治的な問題を扱う機会が増えれば、経済サミットとしての意義が曖昧になる可能性もある。
第一生命経済研究所の嶌峰義清首席エコノミストは「取り立てて議論するテーマがなくても、年に 1 度、20 カ国の首脳が集い、経済状況の認識を合わせることの意味はあるはずだ」と指摘。 一方、ある財務省 OB は「もはや G20 首脳会合の役割は終わった。 準備会合を含めると費やす時間と労力に見合う成果はない。」と批判的だ。 (sankei = 9-7-13)