ネットバンキング不正送金、被害総額 5.5 億円
【吉田伸八】 インターネットバンキングの口座から預金が不正に送金される被害が止まらない。 警察庁のまとめでは、今年の被害は 20 日までに 615 件、被害額は計約 5 億 5 千万円にのぼっている。 送金手続きの際に 1 回限りで使う「ワンタイムパスワード」を盗み取る手口の広がりなどが原因とみられ、警察庁は利用者に対策を呼びかけている。
警察庁によると、被害が確認され始めた 2011 年は 165 件、約 3 億 800 万円で、12 年に 64 件、約 4,800 万円に減ったものの、今年急増している。 月別の被害件数を見ると、5 月までは 1 桁か 2 桁だったが、6 月以降は 100 件台で推移している。 被害が出ているのは、ゆうちょ、みずほ、楽天、三菱東京 UFJ、三井住友、りそな、シティバンク、住信 SBI ネット、セブン、ジャパンネット、北洋、十六、南都、大垣共立、八十二、埼玉りそなの 16 行と、行名を公表していない 2 行。 (asahi = 9-26-13)
家で動画見て予習、「反転授業」試行へ 佐賀・武雄市
【編集委員・氏岡真弓】 佐賀県武雄市教育委員会は小中学生全員に 1 台ずつ配るタブレット端末で、「反転授業」に取り組む方針を決めた。 子どもは授業の動画を入れた端末を持ち帰り、家で宿題として予習。 実際の授業ではわからない点を教え合ったり、議論しながら応用問題を解いたりし、学力の定着を目指す。 11 月に小学校 1 校で試行し、順次広げる。
反転授業は、これまで学校の授業で教えてきた基礎的な内容を家で学び、家で取り組んでいた応用課題を学校で学ぶよう「反転」させる方法だ。 米国で 2000 年代から急速に広がった。 日本では教員個人が取り組んでいる例はあるが、自治体単位で導入するのは初めて。 武雄市は 2010 年度から、小学校 2 校の 4 - 6 年生に 1 人 1 台ずつ iPad を貸与し、授業で使っている。 来年 4 月には小学生全員、15 年春には中学生全員にタブレット端末を配る予定で、計約 4,200 台を貸与する。 機種は決まっていない。
反転授業は先行して端末を使っている市立武内小で理科と算数の一部単元を選び、11 月から始める。 実証実験を重ねながら全校に順次広げ、全教科で試みる。 端末に入れる授業の動画は、まずは塾や出版社の開発したものを利用。 それを参考に学校現場でもつくり、増やしていく。
市教委の目指すイメージはこうだ。 まず教師自らが教科書をわかりやすく説明する動画を撮影する。 教材映像専用のサーバーから選んでもよい。 それらを 10 分ほどの映像にし、子ども一人ひとりの端末に入れる。 理解度チェックの簡単なテストも入れておく。 子どもはその端末を持ち帰り、自宅で動画を見て問題を解くのが宿題となる。 保護者の携帯電話には、宿題の内容を連絡し、家で勉強するよう促してもらう。
そして実際の授業。 教師はまず全員の端末のデータを集め、予習をしてきたか、テストの出来具合はどうかをチェック。 そのうえで、多くの子がつまずいている箇所を説明する。 子どもがわからないところを教えあったり、1 人の解き方を全員の端末で見て共有したり、学んだことを議論したりする場面をつくる。 授業後は、レベルに応じた復習問題をまた端末に入れて持ち帰らせ、わかっているかどうか確認する。
市教委が狙うのは、一人ひとりの理解度をその都度確認して進むことで、落ちこぼれをつくらないようにすること。 もう一つは子どもが話し合い、教え合う対話型の授業でコミュニケーション力を養うことだ。 端末には、映像を視聴し問題を解くことで、子どもが何回動画を見、どれだけ正解できたかの学習履歴が記録される。 教員はそれをもとに一人ひとりに理解度に応じた問題を出し、指導をすることも可能だ。
■ 保護者の協力が不可欠
佐賀県武雄市教育委員会の反転授業の導入は、ICT (情報通信技術)が授業方法を変える可能性を帯び始めたことを意味する。 反転授業の長所の一つ目は、一人ひとりが自分のペースで学べることだ。 説明の映像を家で見ることで、わからない子は何度でも繰り返し勉強でき、理解の早い子は、早い再生速度で聞くことができる。 二つ目は、それに続く教室での授業で議論したり、知識を応用する課題に取り組んだりと受け身ではない活動ができることだ。 結果として、子どもの学習時間は増えることになる。
10 月から市教委の教育監として ICT 教育に取り組む代田昭久・東京都杉並区立和田中前校長は「教員や家庭の協力を得ながら、落ちこぼれをつくらない公教育を目指したい」と話す。
ただ、課題も大きい。 一つ目は子どもがどこまで意欲を持って予習に取り組むかだ。 教材の魅力を高めることがカギを握る。 二つ目は低学年ほど、大人が映像を見るよう促す必要があり、保護者の協力が欠かせないことだ。 家庭環境の厳しい子どもには、放課後に学習の場を設けるなどの工夫が要る。 三つ目は教師が「教え込む人」から、「子どもとともに考え、話し合う人」へという、役割の変化にどこまでついていけるかだ。
他の自治体に広がるかどうかも未知数だ。 反転授業の導入には 1 人 1 台の端末が必要だが、大規模な自治体の場合、子どもの数が多く、財政負担が重くなる。 佐賀県は来春入学の県立高校の全新入生に 5 万円でタブレット端末を購入してもらう。 だが、自己負担が重いと負担撤回や軽減を求める声が出ている。 (asahi = 9-24-13)
《山内祐平・東京大学大学院情報学環准教授(学習環境デザイン論)の話》 「反転授業」は、近代の学校の基本である一斉授業のスタイルを ICT (情報通信技術)を用いて変えるものだ。 10 年後の教室では本命になり得る。 武雄市の目指す方向性を評価したい。
子どもは予習段階で基礎的な知識を身につけ、教室では応用課題に取り組む。 これまでの学校教育は基礎知識の習得か、活用力重視かの間を振り子のように動いてきたが、このスタイルだと両立できる。 自宅で予習する教材をどう充実させるか、授業を対話型に変えることに教員がどこまでついていけるか、保護者の理解をどう得るか、といった課題もある。 大きな改革だけに、教員同士で経験を共有しながら一歩一歩進めてほしい。
◇
〈反転授業 (Flipped Classroom)〉 教室で受けていた授業の動画を、自宅でタブレット端末やパソコンを使って視聴し、家で学んでいた応用問題などは教室で取り組むスタイル。 ICT (情報通信技術)の進歩で可能になった。 米国では 2000 年代から、オンラインの無料講座を活用する形で小中高に広がり、さらに大学で拡大している。
ソニー、軽量電子書籍新端末 サービス向上でアマゾン対抗
ソニーは 24 日、電子書籍専用端末「リーダー」の新製品を 10 月 4 日に発売すると発表した。 また、電子書籍の販売サイト「リーダーストア」のサービス強化のほか、米アップルのスマートフォン(多機能携帯電話)「iPhone (アイフォーン)」で利用できる専用アプリの提供も発表した。 電子書籍市場は米インターネット通販大手のアマゾンが運営する「キンドルストア」が圧倒的なシェアを占めており、ソニーはサービス向上などで巻き返しを図る。
ソニーが発表した新製品は重さ約 160 グラムと、アマゾンが 10 月 22 日発売予定の「キンドル」の最軽量モデルよりも 40 グラム強軽い。 大きさは文庫本を縦型にした程度で、画面の解像度を高めて読みやすくした。 ただ、電子書籍の専用端末を提供するだけでは、電子書籍市場で戦えないのが現状だ。
アマゾンや楽天は、スマホやタブレット端末向けの無料アプリを公開済みで「わざわざ専用端末を買う必要がないと思う人も多い。(家電量販店)」 2010 年から日本で電子書籍配信を始めたソニーは、当初は専用端末向けのサービスだったが、12 年からアンドロイド端末向けのアプリを公開。 新たに 10 月中旬から、アイフォーンや iPad (アイパッド)用にもアプリを提供する。 ソニーの電子書籍ビジネス担当の佐藤淳統括部長は「キンドルと比較しても選んでもらえるようなサービスに一歩進めた」と話している。
アマゾンのキンドルストアは昨年サービスを開始したばかりだが「国内の電子書籍サイト利用者の約半数が利用している」といった調査結果もあるほど浸透。 ソニーの佐藤統括部長も「アマゾンのキンドルは抜きんでている」と、同社の強さを認める。 背景にあるのは紙の書籍や家電などインターネット通販での実績。 新しく会員登録をしなくても、通販と同じ会員 ID でキンドルストアで買い物ができるためだ。 また、割引キャンペーンが多いなど販売価格の安さも人気の背景にある。
ただ、外国企業が海外にあるサーバーから音楽や書籍をネット配信する場合、国外の取引とみなされて消費税が課税されないため、キンドルストアでも消費税が必要なく、ライバル各社からは「不公平」との声も上がる。 一方、楽天は専用端末を販売した書店や量販店と、電子書籍販売の利益を分け合う仕組みを導入する。 実際の書店との連携を深めることで、アマゾンに対抗する構えだ。 (横山三加子、西浦久雄、mainichi = 9-24-13)
◇ ◇ ◇
電子書籍売上高 228% 増 2012 年、雑誌・新聞減
デジタルコンテンツ協会は 29 日、映像、音楽、文章などのコンテンツを扱う業界全体の 2012 年の売上高が、11 年比で 0.8% 増の 11 兆 8,940 億円だったと発表した。 電子書籍が同 228.6% 増、オンラインゲームが 139.1% 増と大きく伸びた一方、雑誌は 3.6% 減、新聞も 1% 減。 電子データ化されたデジタルコンテンツが市場全体の 63.7% を占め、過去最高の比率だった。 (asahi = 8-29-13)
日本語吹き込むと 1 秒で英語に 自動同時通訳の技術開発
【小堀龍之】 日本語をコンピューターに吹き込むと、ほぼ時間差なく英語に翻訳してくれる「自動同時通訳」の技術を、奈良先端科学技術大学院大の中村哲教授(情報科学)らが開発した。 東京五輪がある20年までの実用化を目指す。 25 日から愛知県豊橋市で始まる日本音響学会で発表する。
日本語は述語が最後の方に来るため、文末まで聞かないと意味がわからない。 同時通訳者は、意味をある程度予測しながら会話の途中で文を区切って訳し始めるが、既存の翻訳ソフトでは文末を待つ必要があり、話が長いほど時間差が大きくなる問題があった。
中村教授らは、日英対訳の文章 50 万対と単語 240 万対の情報をコンピューターにあらかじめ入力し、単語の並び順のパターンを分析。 ある単語が来た時に、そこで区切って翻訳できるかどうかを見極める方法を考案し、翻訳の精度を落とさず、遅れを従来の 5 秒から 1 - 2 秒まで縮めることに成功した。 実際に講演を翻訳させると、速さと正確さは経験 1 年ほどの同時通訳者と同程度だった。 (asahi = 9-24-13)
ヤフー「さわれる検索」 音声検索と 3D プリンター駆使
【内山修】 インターネット検索の大手ヤフーが、音声検索と 3 次元 (3D) の立体物をつくれる「3D プリンター」を組み合わせた新サービスを開発した。 「さわれる検索」と名付け、声で指示して立体物を取り出す仕組み。 視覚障害者らが、手触りで形を確かめられる。
公開した試作機に向かって、「キリン」、「スカイツリー」、「カブトムシ」などと言えば、最大でティッシュボックスほどの大きさの樹脂製の立体が「プリントアウト」される仕組みだ。 二つあるボタンは、操作しやすいよう大きくし、形と色を変えてある。 立体づくりには、設計データを蓄えておく必要がある。 いまは動物や虫、著名な建築物など約 110 種類あり、さらに増やす計画だ。 ヤフーは視覚障害がある児童らが通う筑波大付属視覚特別支援学校(東京都文京区)に試作機を貸し出しており、より広い活用方法を探る。 (asahi = 9-18-13)
9.18 に中国からサイバー攻撃? 紅客と黒客
中国の反日運動が激しくなる 9 月 18 日前後に、日本のサイトへの一斉攻撃が予想されている。 毎年のように行われている中国の「紅客(ホンクー : 政治的な意図を持ったサイバー攻撃者)」によるサイバー攻撃だ。
掲示板に日本へのサイバー攻撃予告が書かれる
9 月 18 日は、中国で反日運動が激しくなる日だ。 82 年前、中国東北部の奉天(現・遼寧省瀋陽市)近郊で、関東軍による「柳条湖事件」が起きた。 満州事変のきっかけとなっていることもあり、中国では「九一八事変」と呼ばれて、反日運動が激化する日と言われている。 この 9 月 18 日に、日本に対するサイバー攻撃が行われる可能性があるとして、警察庁、企業セキュリティー大手のラック、IBM セキュリティー・オペレーション・センターの Tokyo SOC が相次いで警告を出している。
IBM の Tokyo SOC によれば、すでに日本をターゲットとした攻撃予告が、掲示板などで確認されているとのこと(柳条湖事件が起こった 9 月 18 日に向けた攻撃予告に関する動向 : Tokyo SOC Report)。 また、警察庁によれば、攻撃の前兆とも言える DNS サーバーの探索行為が始まっている(中国を発信元とする再帰問い合わせ可能な DNS サーバの探索行為の増加について : 警察庁)。
9 月 18 日「九一八事変」では、毎年のように日本のサイトなどに対するサイバー攻撃が行われている。 IBMのTokyo SOCによる「中国からのブラインドSQLインジェクション攻撃送信元IPアドレス数の推移」によると、ここ 3 年間の中国からの攻撃件数がわかる。 毎年 9 月 10 日前後から SQL インジェクション攻撃が増え、9 月 16 日から 18 日前後にピークを迎えることがわかる。 今年はまだ兆候は見られないが、「9 月 18 日付近の休日にピークとなる傾向 (Tokyo SOC)」があるので、14 日から 18 日にかけて攻撃が増加しそうだ。
昨年は尖閣諸島の国有化と重なったため、9 月 18 日前後のサイバー攻撃はより激しいものとなった。 昨年の本連載の記事「中国サイバー攻撃の手口と対策 : サイバー護身術」でまとめているが、DDoS 攻撃(大量にデータなどを送りつけ接続不能にする攻撃)で、総務省統計局・防衛省・政府インターネットテレビなどの政府機関や、銀行・電力会社などの民間企業計 11 サイトがつながりにくくなった。
また、最高裁などのウェブサイトでは、ウェブサイトが改ざんされ、尖閣諸島に中国の国旗が掲げられている画像が掲載された。 今年も同様の攻撃が予想される。
日本を狙う「紅客」による二つのサイバー攻撃
中国では犯罪目的のハッカー(いわゆるクラッカー)のことを「黒客(ヘイクー)」と呼んでいる。 非合法・犯罪をイメージさせる「黒」を基にして、英語の Hacker と読みが近いことから「黒客」と呼ばれているようだ。
それに対して、政治的な目的を持ったハッカーのことを「紅客」と呼んでいる。 中国の愛国的なイメージである「紅」を基にしたもので、政治的な目的でサイバー攻撃などを行うハッカーのことである。 9 月 18 日に日本を攻撃してくるハッカーも、この「紅客(ホンクー)」だと言われている。 いわゆる「ハクティビズム」、「ハクティビスト」の中国版と考えればいいだろう。
ただし「紅客」は一つの組織ではなく、いくつもの組織に分裂しており、組織によって方針もバラバラのようだ。 この「紅客」が、掲示板やチャット、SNS での呼びかけに応じて日本を攻撃してくる可能性がある。 攻撃の手法として、セキュリティー大手・ラックでは以下の二つの危険性があるとしている。
● サーバーやサービスに対するサービス妨害攻撃
主に予想されるのは、大量にデータを送りつけるなどしてサーバーやサービスを止める DDoS 攻撃だ。 昨年はこれによって日本の官公庁などのサイトが一時的につながりにくくなった。 単純にボタンを連打する初歩的なものから、専用ツールを配布して多くの人に参加を呼びかけるパターンもあった。 対策としては、特定の国の IP アドレスブロック、サーバー・回線の増強、クラウドサービスへの切り替えなどがある。
● Web サーバーの改ざん(乗っ取りや情報窃取にもつながる)
SQL インジェクション攻撃、脆弱性を狙った攻撃などにより、ウェブサイトなどを改ざんするもの。 政治的な目的ではよく使われる手法で、昨年も政府系のサイトが乗っ取られて尖閣諸島の画像に差し替えられる事件があった。 また、パスワードを盗み取るウイルスをしのばせたり、パスワードリストを使った攻撃により、使いまわしパスワードを使用している管理者アカウントが攻撃を受ける場合もあるとしている。 対策としては脆弱性対策をしっかりすること、同一パスワードの使い回しを禁止するなどのパスワード対策も必要となる。
このように 9 月 18 日前後は、大規模なサイバー攻撃を受ける可能性がある。 企業の管理者はもちろんのこと、個人のサイト運営者も注意する必要がある。 ガードのゆるい日本の中小のサイトが狙われる可能性があるからだ。 特に最近は、WordPress など中小のサイトで使われているブログ・CMS が狙われている。 被害に遭わないように設定を見直し、パスワード管理を改めて厳重にしたい。(IT ジャーナリスト・三上洋、yomiuri = 9-13-13)
デジタル教科書で 13 社提携 端末での操作法統一
光村図書出版など教科書 12 社と、日立ソリューションズは 5 日、デジタル教科書事業で提携した。 タブレット(多機能携帯端末)で使うデジタル教科書の操作方法を統一。 教科書データは教室の端末にインターネット経由で配信する。 15 年以降に順次、商品化する。 教科書の国内市場は年 400 億円弱と低迷、デジタル教科書は 1 割弱とされる。 各社は提携で普及に弾みをつけたい考えだ。
13 社はデジタル教科書の開発と普及を手がける団体「コネッツ」を設立した。 参加企業は国語教科書を手がける光村図書出版、地図帳などを発行する帝国書院、歴史教科書の山川出版社など大手が中心。 電子黒板など教育関連システムに強い日立ソリューションズも参画した。
コネッツではデジタル教科書の閲覧専用ソフトを共同開発する。 ソフトをタブレットに入れれば、異なる教科書や端末でも、画像の拡大・縮小、画面への線や図形の書き込み、音声再生など基本的な操作方法を統一できる。 現在は各社がそれぞれデジタル教科書を制作しており、操作方法が会社や教科書ごとに異なるため、教師や生徒が操作に戸惑うといった問題が起きていたという。
新ソフトでは生徒が授業中に文字などを書き込んだデジタル教科書のページを保管して後で読み返したり、練習問題を何度も解き直したりなどといった使い方もできるようにする。
教科書各社と日立ソリューションズはデジタル教科書のデータを保管したり配信したりするクラウドシステムも開発する。 開発費用は日立ソリューションズが負担し、閲覧ソフトの利用料金を教科書会社が支払う。 米アップルの「iPad (アイパッド)」、米マイクロソフトの「ウィンドウズ 7」、「同 8」で利用できる。 他の教科書会社にも参加を呼びかけ、新システムを通じた配信サービスを充実させる。 (nikkei = 9-5-13)
「電子出版権」創設を大筋了承 文化審小委が中間まとめ
【藤井裕介】 文化審議会の出版関連小委員会は 5 日、著作権法を改正して「電子出版権」を創設する「中間まとめ」を大筋で了承した。 電子書籍に関する出版社などの権限を強め、海賊版対策や電子書籍の制作・配信をしやすくするための対応で、早ければ今月中に公表して意見を募る。 年内には最終的な検討結果をまとめる。 文化庁は、同委の検討を受けて、来年の通常国会に著作権法の改正案を提出する方針だ。 成立すれば、1970 年に今の著作権法ができて以来、44 年ぶりに出版をめぐる権利が見直されることになる。
著作権法では、紙の書籍の「出版権」は定めているが、電子書籍を発行する出版社などを保護する規定がない。 現状では、出版社は海賊版の発行をやめさせる訴訟を起こすことができず、作家が起こす必要がある。 「電子出版権」では、作家らとの間で契約を結んだ出版社が訴訟を起こせるようにする。 また、電子書籍の配信についても、出版社が販売サイトなど第三者に許可する権限を持てるようにする。 紙の書籍の出版権をもつ出版社などに限らず、広く「電子出版を引き受ける者」であれば、電子出版権を認める。 (asahi = 9-5-13)
語彙・読解力検定 HP 改ざん 閲覧でウイルス感染の恐れ
朝日新聞社とベネッセコーポレーションが共同で行っている「語彙・読解力検定」の公式ホームページ (HP) が外部からの不正アクセスにあい、HP の一部が改ざんされたことがわかった。 両社が 29 日、発表した。
HP は同日午後、いったん閉鎖した。 両社は HP を閲覧したパソコンがウイルスに感染した恐れがあるとして、ウイルス対策ソフトのチェックを呼びかけている。 不正アクセスの詳しい状況については調査中で、これまでに受検者の個人情報の流出は確認されていない。 検定を申し込んだ人には個別にメールを送り、事情を説明している。 電話での問い合わせも受け付けている(0120・110702、午前 9 時から午後 6 時まで、日祝除く)。
「語彙・読解力検定」は朝日新聞の記事などをもとに語彙や時事に関する知識、読解力を問う検定試験。 2011 年春から実施している。 (asahi = 8-29-13)
漫画に「2 次創作 OK」マーク TPP に備え新設
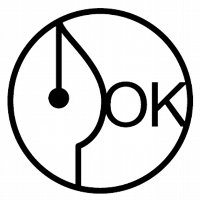
【赤田康和】 「同人誌での 2 次創作・販売は OK です。」 インターネット時代に合わせた作品の流通促進をめざす世界的団体「クリエイティブ・コモンズ」の日本支部が、ファンらの 2 次創作を漫画家が許可する際に自分の作品に付けるマークをつくった。 プロの漫画家赤松健さんが 28 日発売の「週刊少年マガジン」の新連載で初めて使う。
同人誌の即売会コミックマーケット(コミケ)などでは、ファンがプロの作品から登場人物や設定を借りてきて、新しい物語にした作品が流通している。 アマチュアによる 2 次創作の裾野の広がりが日本の豊かな漫画文化を支えているといわれる。 著作権法では、許可なく 2 次創作した作品を販売するのは違法。 ただ業界関係者によると、プロの漫画家がファンによる 2 次創作とその作品の小規模な販売を問題視した事例はほとんどない、という。 (asahi = 8-28-13)
産業制御システムを狙っているのは誰か?
トレンドマイクロ、サイバー攻撃の実態を調査
トレンドマイクロは、産業制御システム (ICS: Industrial Control Systems) へのサイバー攻撃の実態を調査・分析したレポート「産業制御システムへのサイバー攻撃実態調査レポート」の第 2 弾を公開した。
同社の調査・研究チームは、産業制御システムへのサイバー攻撃の実態を解明するための調査活動を、2012 年より行っている。 今回は、2013 年 3 月から 3 か月の期間で、新たな攻撃の傾向を把握するために追加調査を実施した。 追加調査では、水道設備のインフラ制御システムに見せかけたハニーポット(調査用おとりシステム)の設置個所を、日本を含む 8 か国 12 か所に拡大し、世界各国で攻撃活動を監視。 侵入したコンピュータの実際の所在地やシステム情報を分析する追跡用モジュールを使用し、さらに詳細な攻撃特性を分析したという。
調査結果によると、調査期間内に 16 か国から計 74 件のサイバー攻撃が確認された。 攻撃の詳細内容を分析すると、そのうち 10 件は社会インフラを支えるシステムの正常稼働を脅かす危険度が高い攻撃であることが判明した。 サイバー攻撃全体の発信元としては、ロシアが 43 件と最も多く、次いで中国 7 件、ドイツ 5 件。 危険度が高い攻撃では、中国からの攻撃が 5 件で最も多く確認され、次いでパレスチナ自治区 2 件、ドイツ・イギリス・フランスが 1 件ずつと、世界各地から産業制御システムへのサイバー攻撃が行われていることが分かったという。
また、攻撃を受けた国別では、ロシアが 66 件で最多、次いで中国 6 件、日本、アイルランド 1 件となり、世界各地のインフラが標的となっていることが分かる。 (インターネットコム = 8-28-13)
NY タイムズのサイト、アクセス不能に 外部から攻撃か
【ニューヨーク = 中井大助】 27 日午後、米紙ニューヨーク・タイムズのインターネットサイトに外部からアクセスすることができなくなった。 同紙によると、ドメインネーム(インターネット上の住所)を管理しているオーストラリアの会社が攻撃を受けたためで、「シリア電子軍」と呼ばれる組織が関与しているとみられる。
シリア電子軍は過去にも、AP 通信や英 BBC など、欧米のメディアのハッキングで「犯行声明」などを出しているほか、アサド政権を支持するメッセージも発信している。 27 日には、ツイッター社やハフィントン・ポストの英国サイトもハッキングした、とツイッターで主張している。 (asahi = 8-28-13)
「2 ちゃん」 5 万人の個人情報流出 「ビューア」利用者のアドレスやカード番号も
インターネット掲示板「2 ちゃんねる」の利用者約 5 万人のメールアドレスなど個人情報が 25 日深夜から 26 日未明にかけて外部に流出していることが分かった。 流出した情報にはクレジットカードや個人の氏名、住所、電話番号なども含まれている。
流出したのは、過去に 2 ちゃんねるに書き込まれた発言内容や掲示板(スレッド)を見られるシステム「2 ちゃんねるビューア」の利用者の個人情報。 メールアドレスや発言内容に加え、2011 年 7 月から 13 年 8 月までに申し込んだ利用者には住所や氏名のほか、クレジットカード番号やセキュリティーコードも流出しているとみられる。
2 ちゃんねるビューアの運営会社は 26 日朝、「該当範囲及び原因につきましては現在調査中です。 お客様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございません。」と公式サイトに掲載したが、のちに削除した。 同ビューアは、時間が経過して見られなくなった過去の掲示板を閲覧できたり、掲示板に書き込みする際の制約が減ったりする利点から最近、利用者が増えていた。 クレジットカード利用者は年間 33 ドル(3,234 円。 1 ドル = 98 円で計算)、ビットキャッシュ(電子マネー)では 3,600 円を支払うことで利用できる。
2 ちゃんねるでは、掲示板に個人情報や企業の内部情報が書き込まれて問題化することは珍しくないが、書き込んだ人の個人情報が大規模に流出したのはこれが初めてとみられる。 すでに掲示板上では同ビューア利用者の個人情報が相次いで書き込まれており、2 次被害が懸念されている。 2 ちゃんねるでは、開設者で元管理人の西村博之氏 (36) が、掲示板の管理事業を譲渡した後も広告収入を受け取り、東京国税局から約 1 億円の申告漏れを指摘されていたことが 24 日に明らかになったばかり。
一連の情報漏れについて、「2 ちゃんねる宣言(文芸春秋)」などの著書がある IT ジャーナリストの井上トシユキ氏は、「銀行などしっかりしている金融機関でも顧客の個人情報の流出は少なくない。 だから、利用者は、ネット上での情報管理は完璧ではないと認識した方がいい。」と指摘する。
「流出した情報はネットの世界で次々と転売されていく。 それを入手した悪意ある者が迷惑メールやサクラのメールとして送りつけてきたり、なりすまして商品を購入したりするようなことも起きる。 ネットに対しては、(現実の世界よりも)より慎重に向き合わないといけない。(井上氏)」 対策が急がれる。 (ZAKZAK = 8-26-13)
パソコンの覇者、スマホで落日 MS は世代交代を模索
【ジャクソンホール = 畑中徹、ワシントン = 山川一基】 米ソフトウエア最大手マイクロソフトのスティーブ・バルマー最高経営責任者 (CEO) が 23 日、1 年以内に退任すると発表した。 主力のパソコン関連事業の伸びが鈍っているため、経営を刷新して新たな事業を模索せざるを得なくなった。 スマートフォン(多機能携帯電話)などが台頭し、パソコンで一時代を築いた企業はいずれも苦戦を強いられている。
退任が発表された 23 日、ニューヨーク市場ではマイクロソフト株が前日より 7% 超も上がった。 バルマー氏は 2000 年に CEO に就いた時より売上高を 3 倍に増やしたが、投資家は経営を刷新して新しい路線に踏み出すことを望んだ。 バルマー氏は創業者のビル・ゲイツ氏と大学時代からの親友で、1980 年にマイクロソフトに入った。 CEO を譲り受けたころは IT バブル前夜。 世界の家庭にパソコンが急速に広がろうとしていた。 (asahi = 8-24-13)
米ナスダックでシステム障害 株式取引が 3 時間止まる
【ワシントン = 山川一基】 米アップルなど有力ハイテク企業や新興企業が多く上場している米ナスダック市場が 22 日、システム障害を起こし、約 3 時間にわたって取引ができなくなった。 同市場は昨年の米フェイスブック上場時にもシステム障害を起こしたばかりで、投資家の不信感が高まっている。
同市場の発表によると、午後 0 時 14 分(日本時間 23 日午前 1 時 14 分)、全ての株式取引が止まった。 投資家と情報処理システムをつないで価格情報を伝える機能に問題が起きたため、市場の混乱を防ぐために全取引を止めたという。 午後 3 時には一部株式の取引を再開し、午後 3 時 25 分には全株式の取引が復旧。 午後 4 時に通常通り取引を終えた。 ナスダック総合指数の終値は前日比で 38.92 ポイント (1.08%) 高い 3,638.71 だった。 (asahi = 8-23-13)
ヤフー、居住地別に避難勧告・指示 自治体の情報を配信
ヤフーは 22 日、ウェブサイトやスマートフォン向けアプリ「防災速報」で、避難勧告や避難指示など自治体が出す避難関連の情報の配信を始めた。 事前に居住地域などを登録すると、スマートフォンの画面にその地域の避難情報が表示される。 ウェブサイト「Yahoo! 天気・災害」では、すべての地域の避難情報を見ることができる。
総務省は 2011 年、自治体が出す避難情報などを集約し、マスメディアや携帯電話を通じて配信する「公共情報コモンズ」という仕組みの運用を始めた。 ヤフーはこの仕組みなどを利用し、今回の配信を始めた。 (asahi = 8-22-13)
電子地図に防災情報を集約 南海トラフ地震で国交省
国土交通省は 22 日、南海トラフ巨大地震の対策計画の中間とりまとめを決定した。 詳細な地形データが入った電子地図に、ヘリコプターや人工衛星からの浸水や土砂崩れの情報を集約した防災情報システムを構築することなどが柱。 時系列に沿った 4 段階の具体策や、事前の重点対策箇所も挙げた。 IT 活用ではほかに、携帯電話の位置情報やインターネットの投稿といった「ビッグデータ」から避難者や車の通行状況を分析する。 人口が集中する濃尾平野や大阪平野で先行的に取り組む。 (kyodo = 8-22-13)
「やりとり型」サイバー攻撃急増 … 半年で 33 件
企業と採用についてのやりとりなどをメールで繰り返した後、情報を盗み取るウイルスを仕込んだファイルを送りつける「やりとり型」のサイバー攻撃が今年 1 - 6 月、33 件あったことが 22 日、警察庁のまとめでわかった。 昨年確認されたのは 2 件しかなく、警察庁は「自然なやりとりで企業側を油断させ、ファイルを開かせようとする手口が急増している」と、警戒を呼びかけている。
同庁は、防衛、宇宙、原子力の各分野で先端技術を持つ約 5,000 社と情報共有の枠組みを作っている。 その中で、メールでウイルスを送りつける「標的型メール」を 201 件把握。 約 6 割にあたる 125 件は、無料で利用できるフリーメールだった。
「標的型メール」のうち 33 件が「やりとり型」で、最初に送られてきたメールの内容は、採用に関する問い合わせが 18 件と半数を超え、製品の不具合を指摘するものが 9 件。 企業が返答すると、これに応じる形で履歴書や不具合の内容を記録した文書などを装い、ウイルスを仕込んだファイルをメールに添付して送ってきた。 33 件で使われていたのは、いずれもフリーメール。 約 8 割の 26 件では、ホームページに公開されている企業のアドレスに送ってきた。 (yomiuri = 8-22-13)
「Skype for Outlook.com」が日本でも利用可能に
米マイクロソフト傘下のスカイプは、「Skype for Outlook.com」のプレビュー版を 4 月末に提供し始めていたが、19 日からは日本でも利用できるようになったと発表している。
Outlook.com は、無料で利用できる Web ベースの個人メールサービス。 Outlook.com から Skype を利用できるようにするのが「Skype for Outlook.com」。 Outlook.com でメールやメッセージにを受信した際、カーソルを相手の写真の上に合わせ、表示される Skype の音声通話またはビデオ通話をクリックすることで受信相手との通話が可能となる。
利用にあたっては、最新の Internet Explorer や Chrome、Firefox でプラグインをインストール。 すでに Skype アカウントを持っている場合は案内にしたがって手軽に Skype と Outlook.com のアカウントの統合が可能。 アカウント統合後は、Skype の連絡先を Outlook.com の連絡先に加えることもできる。 (加藤宏之、ASCII = 8-19-13)
Google 検索でパーソナルアシスタント機能が使用可能に - 米 Google
米 Google は 14 日(現地時間)、自分のフライト予定や宿泊予約、荷物の配送状況などを音声入力で手軽に確認できるパーソナルアシスタント機能を、デスクトップ PC/タブレット/スマートフォン向けの Google 検索で提供すると発表した。 まずは米国英語圏のユーザーに、数日かけて提供される。
提供される機能は、iOS でいう「Siri」のように、音声入力されたキーワードと関連する情報を、Gmail や Google カレンダー、Google+ 内のパーソナル情報をもとにピックアップ。 例えば自分のフライトは定刻どおりかと尋ねた場合、現在のフライト状況や今後の便の状況が通知される。 また、「予約は」、「ホテルは」などと尋ねた場合、予約している食事やホテルなどの店名や住所、地図、道順などを確認できるという。
Google はすでに、同種の機能をスマートフォン・タブレット端末向けパーソナルアシスタント機能「Google Now」で提供してきており、今回、Google にログインしていれば、デスクトップ PC などデバイスを問わず、Google 検索で同機能が使用できるようになった。 なお、機能のオン/オフ設定も可能で、従来の Web 検索に切り替えることも可能だ。 (MyNavi = 8-15-13)
バックアップ専用の SD カード SD メモリーカードをバックアップに使う新提案
パソコンに SD カードスロットがあるのはもはや普通のことになりましたが、デジタルカメラから写真を取り込むぐらいにしか使っていない人が多いのではないでしょうか。 ソニーが 8 月 20 日に発売する「バックアップ SD カード」は、そんな普段は空いているスロットを使って、大事なファイルの日常的なバックアップに使える注目の製品です。
今回ソニーが発売する「バックアップ SD カード」は、その名の通り、パソコンに保存したファイルをバックアップする SD カードです。 それ自体は普通のデータ保存用 SD メモリーカードで、16GB、32GB、64GB の 3 種が発売されます。 カード自体に特殊な機能があるわけではなく、専用のウィンドウズ用バックアップソフト「リアルタイム・バックアップ・ユーティリティ」が付属しているのが特徴です。
リアルタイム・バックアップ・ユーティリティは、指定したフォルダーをチェックして、ファイルが新しく保存されたり、更新・削除されたりすると、即座にそのファイルを SD メモリーカードにバックアップします。 つまり「週に一度の定期バックアップ」などではなく、ひんぱんに更新される書類ファイルなどの日常的なバックアップに使うわけです。
このソフトは、スロットに入っている SD カードの種類まで確認し、このバックアップ SD カードが入っているときだけバックアップするので、デジタルカメラの SD カードから写真を転送したいときには、カードを差し替えても大丈夫です。 デジタルカメラのカードにバックアップのデータが書き込まれるなんてミスは起こりません。 (斎藤幾郎、asahi = 8-15-13)
ウィンドウズ 8.1、10 月 17 日発売 不評うけ改良
【ダラス = 畑中徹】 米マイクロソフト (MS) は 14 日、パソコンやタブレット端末向けの基本ソフト (OS) 「ウィンドウズ 8」の改良版「ウィンドウズ 8.1」を、米太平洋時間の 10 月 17 日早朝(日本時間同日夜)に世界で同時に売り出すと発表した。 「8」の利用者は MS の配信サイトから無料でダウンロードできる。
昨年 10 月に売り出した「8」では、スマートフォンやタブレット端末でおなじみの、画面を触って操作するタッチパネル方式を導入した。 スタートボタンも廃止し、画面上にタイルのようなアプリを並べるデザインに刷新した。 その後、操作に慣れない利用者から「使いにくい」との指摘が相次いだ。 「8.1」は、画面左下に再び同じようなスタートボタンを配置し、これを使ってソフトの起動や設定ができるという。 MS は主力商品の改善で、販売のてこ入れをはかりたい考えだ。 (asahi = 8-15-13)
猛暑、ネットスーパーがクール 宅配ならアイス溶けない
連日の猛暑で、食料品などをインターネットで注文し自宅に届けてもらう「ネットスーパー」の利用が急拡大している。 店で買うと持ち帰る間に溶けてしまうアイスクリームや、重くて持ち帰るのが大変な飲料の注文が目立つ。 一方、クーラーは猛暑で壊れたりするケースも出ているといい、販売が急増している。
全国 24 都道府県 145 店でネットスーパーを展開するイトーヨーカ堂では、10、11 日の利用件数が昨年の同時期より 5 割増えた。 特に飲料や酒類、アイスクリームが好調という。 イオンのネットスーパーでも、5 - 11 日の売上高が昨年より 1 割以上増えた。 「ネットスーパーの市場自体も伸びているが、猛暑で出歩くのを控えた人が増えていることが理由の一つだろう(広報)」とみる。 (asahi = 8-14-13)
「アメーバ」に不正ログイン 24 万件超 サイバーエージェント
サイバーエージェントは 12 日、ブログやゲームなどを楽しめる会員制サービス「Ameba (アメーバ)」で、4 - 8 月に不正ログインがあったと発表した。 対象 ID は 24 万 3,266 件。 同社は、対象の利用者に個別にメールで連絡したほか、全利用者にパスワードの変更を呼びかけている。
利用者のニックネームやメールアドレス、生年月日、居住地域、性別、仮想通貨の購入・使用履歴などが閲覧された可能性がある。 仮想通貨の不正利用は現時点では確認されていない。 同社によると、他社で不正アクセスが相次いだのを受けて社内調査した結果、不正ログインがわかった。 他社サービスから流出した ID やパスワードを利用してログインされたとみられる。 (nikkei = 8-12-13)