官製ファンド乱立 総資金 4 兆円、「民業圧迫」批判も
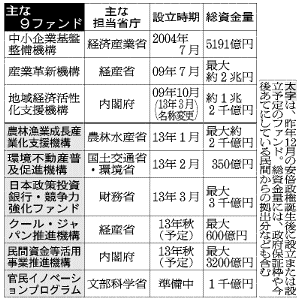
【大鹿靖明】 国が中心となり、民間の事業や企業に投資する官製ファンドの設立が相次いでいる。 安倍政権の経済政策アベノミクスの成長戦略を進める名目で、今秋以降、新たに 3 ファンドが立ち上がり、九つの主な官製ファンドの資金量は 4 兆円を超える。 官の投資の膨張には「民業圧迫」との批判も出ている。
経済産業省は今秋、日本のアニメや音楽などの海外展開を進めるファンドを運営するクール・ジャパン推進機構を設立する。 内閣府も、民間資金を生かして公共施設の建設・運営を促進するファンドを持つ民間資金等活用事業推進機構を立ち上げる。 文部科学省は、東大や京大などの大学発ベンチャーに投資するファンドを準備中だ。 3 ファンドで計 5 千億円規模になる。
1 月の安倍政権の緊急経済対策を受けて、農林水産省が、異業種との連携で第 1 次産品の輸出促進などを図る農林漁業成長産業化支援機構を拡充するなど、今年すでに三つのファンド(計 5 千億円規模)が発足している。 官製ファンドの資金源は、NTT 株や JT 株の配当収入による財政投融資特別会計や、政府保証をつけた民間金融機関からの借り入れなどだ。 これまでにできた産業革新機構などを合わせて、九つの主な官製ファンドの総資金量は合計 4 兆円超となる。
潤沢な資金量を背景に投資ビジネスに参入すれば、全体で 1 兆円に満たない民間の投資ファンドは歯が立たない。 このため、民間ファンドでつくる日本プライベート・エクイティ協会は「民業圧迫」に陥らないよう、官製ファンドの投資基準の明確化を求めている。 (asahi = 8-18-13)
初の 1,000 兆円突破 = 「国の借金」膨張止まらず - 1 人当たり 792 万円・6 月末
財務省は 9 日、国債や借入金、政府短期証券の残高を合計した「国の借金」が 6 月末時点で 1,008 兆 6,281 億円になったと発表した。 社会保障費など歳出増加に伴って借金の膨張に歯止めがかからず、3 月末から 17 兆 270 億円増え、初めて 1,000 兆円を突破した。 日本の厳しい財政事情が改めて浮き彫りになった。
7 月 1 日時点の人口推計(1 億 2,735 万人)で割ると、国民 1 人当たり約 792 万円の借金を背負う計算となる。 「借金」の内訳は、普通国債が 3 月末比 11 兆 3,470 億円増の 716 兆 3,542 億円、特殊法人への貸し付けの原資となる財投債は 1 兆 7,424 億円減の 107 兆 5,183 億円、政府短期証券は 8 兆 1,007 億円増の 123 兆 3,683 億円など。 財務省は 2013 年度末の「借金」は 1,107 兆 1,000 億円になると見込んでいる。 (jiji = 8-9-13)
IMF、日本に財政再建訴え 「アベノミクス効果 1 年」
【ワシントン = 山川一基】 国際通貨基金 (IMF) は 1 日、先進国の経済政策が世界に与える影響を分析した報告書を発表した。 日本については、政府の財政への懸念が膨らみ長期金利が 2% 上がると、世界の経済成長は 2% 目減りすると試算し、中期的な財政再建の重要性を訴えた。
報告書によると、安倍晋三政権による金融緩和や財政出動は、世界経済に短期的にはプラスの効果があるとしたが、約 1 年先には効果は弱まると指摘。 もし構造改革や財政再建などが失敗すれば、10 年後に日本の国内総生産 (GDP) は 4% 下がると分析した。 そのうえで、日本の財政に対する投資家の不安が高まり長期金利が上昇すると、株価下落などが起きて世界経済にも悪影響を与えるとした。 電話会見した IMF のエコノミストは「我々はアベノミクスを条件付きで支持する」と述べ、日本の構造改革と中期的な財政再建を促した。 (asahi = 8-2-13)
◇ ◇ ◇
麻生財務相、消費増税は予定通り実施との意向表明 - G20 閉幕後に会見
麻生太郎財務相と日本銀行の黒田東彦総裁は 20 日夕(日本時間同日夜)、モスクワで開かれた 20 カ国・地域 (G20) 財務相・中央銀行総裁会議の閉幕後に記者会見した。 財務相は消費税率の引き上げについて「予定通りやりたい」と述べ、今後の経済指標動向などを踏まえて 10 月ごろまでに最終決定する意向を示した。
一方、黒田総裁は日銀の政策について、G20 各国間で「一般的に言って理解はさらに深まっていると感じた」と述べた上で、市場や実体経済はおおむね想定どおりに動いているとして、金融緩和が「着実に効果を上げつつある」と表明。 2% の物価上昇率目標の達成に関しては「もっと時間が掛かる」との認識を示した。
今回の G20 会議は、世界経済について「回復はなお脆弱でばらつきがある」などとする共同声明を採択。 「多くの国において、失業率は過度に高い状況が続いている」と指摘し、「成長の強化と雇用の創出」が引き続き優先課題だと述べた。 (Bloomberg = 7-21-13)
来年度成長、実質 1% に減速 政府見通し、消費増税前提
【末崎毅】 来年度の国内総生産 (GDP) 成長率の政府見通しは、実質が 1.0%、物価変動を加味した名目が 3.1% になることがわかった。 来年 4 月に消費税率を 8% に引き上げることを前提にしているため、プラス成長は維持できるものの成長率は減速する。 内閣府が 8 月上旬に政府の経済財政諮問会議に示す。 今年度の GDP 成長率の政府見通しは、実質 2.5%、名目 2.7% という 2 月時点の見通しを実質 2.8%、名目 2.6% に修正する。 デフレによって名目が実質を下回る「名実逆転」はまだ解消しない。
消費税率を上げると、増税前にモノを買っておこうとする「駆け込み需要」の反動が出たり、家計が「負担増」になって消費が落ち込みやすくなったりするため、来年度の成長率にはブレーキがかかる。 実質 1.0% の政府見通しは、日本銀行の 1.3% の見通しより慎重だが、民間調査会社 41 社の平均 0.57% に比べると楽観的だ。
一方、日銀が金融緩和によって物価上昇率を上げようとしていることを見込み、来年度の名目成長率は 13 年度を上回るとみる。 安倍晋三首相は秋に、消費増税するかどうかを最終判断する。 政府見通しは消費増税を前提にしているが、あくまでも見通しなので首相の判断を縛らないという。 (asahi = 8-1-13)
景気判断、2 年半ぶり「回復」明記 日銀が上方修正
日本銀行は 11 日の金融政策決定会合で、景気の基調判断を「持ち直している」から「緩やかに回復しつつある」へ上方修正した。 上方修正は 7 カ月連続で、2011 年 1 月以来、2 年半ぶりに「回復」の表現を盛り込んだ。 過去最大の金融緩和策はこれまで通り続ける。 政策委員 9 人(総裁、副総裁 2 人、審議委員 6 人)の全員一致で決めた。
4 月にまとめた 13 - 15 年度の「経済・物価情勢の展望(展望リポート)」も再点検した。 「成長率、消費者物価ともにおおむね見通しに沿って推移すると見込まれる」として、15 年度に物価上昇率(消費増税分を除く)が 1.9% になるとの見通しは変更しなかった。 (asahi = 7-11-13)
◇ ◇ ◇
景気判断 8 地域で上方修正、内需主導で = 日銀地域経済報告
[東京] 日銀が 4 日発表した各支店の景気報告をまとめた「地域経済報告(さくらリポート)」によると、全国 9 地域のうち東北を除く 8 地域が、景気判断を今年 4 月の前回調査から引き上げた。 公共投資が増加しているほか、マインド改善で個人消費や設備投資も底堅く推移しており、内需主導による景気持ち直しの動きが地方経済にも広がりをみせている。
前回調査では全 9 地域が判断を引き上げており、2 期連続で 8 地域以上が上方修正するのはリーマンショック前の 2009 年 7、10 月調査以来、3 年 9 カ月ぶり。 判断を据え置いた東北は、前回調査でも判断を「回復しつつある」としており、震災復旧関連を中心に他地域よりも強めの認識を示していた。 地域経済改善は、2012 年度補正予算や 2013 年度本予算の執行に伴う公共投資の増加や株高による消費マインド改善など、内需が堅調に推移していることが背景。 為替円安や海外需要の持ち直しを受け、輸出・生産も増えている。
需要項目別では、公共投資は全地域が「増加」しているとしており、全 9 地域のうち 5 地域が判断を引き上げた。 個人消費は消費者マインドの改善を背景に、百貨店の高額品や自動車、旅行などが好調。 6 地域が判断を上方修正した。 消費税率引き上げ前の駆け込み需要もみられる住宅投資は 3 地域が引き上げ。 企業の景況感が改善する中、設備投資も 5 地域が上方修正している。
この結果、海外需要の持ち直しもあり、生産は北陸、中国を除く 7 地域が判断を引き上げた。 業種別にみると、自動車が好調な輸送機械のほか、建設関連需要の増加を背景とした金属製品や窯業・土石などから「増加傾向」、「持ち直し」との声が聞かれている。 一方、電子部品・デバイスは複数の地域から「弱めの動きを続けている」との指摘があった一方、「増加」「持ち直し」との報告もあったという。
雇用・所得については、多くの地域から厳しい状況にあるものの、労働需給面を中心に「緩やかに改善している」などの報告があり、6 地域が判断を引き上げている。 (伊藤純夫、竹本能文、Reuters = 7-4-13)
◇ ◇ ◇
業況判断指数、1 年 9 カ月ぶりプラスに 日銀短観
日本銀行が 1 日発表した 6 月の企業短期経済観測調査(短観)は、大企業・製造業の業況判断指数 (DI) がプラス 4 で、マイナス 8 だった前回 3 月調査から大幅に改善した。 改善は 2 四半期連続。 プラスになるのは、2011 年 9 月以来 7 四半期(1 年 9 カ月)ぶり。 昨秋からの円安の効果で、輸出が多い自動車産業の改善が続いている。 電気機械や鉄鋼も改善に転じた。 堅調な消費や公共事業の増加を背景に、サービスや建設の改善も続いている。 (asahi = 7-1-13)
◇ ◇ ◇
日銀、景気判断を引き上げ 5 カ月連続、消費改善
日銀は 22 日、金融政策決定会合を開き、国内景気の現状判断を「持ち直しつつある」とし、前回の「下げ止まっており、持ち直しに向かう動きもみられている」から引き上げた。 判断の上方修正は 5 カ月連続。 4 月に導入した大規模な金融緩和策の継続も全員一致で決めた。
安倍政権の経済政策「アベノミクス」により円安や株高が進み、消費者心理が改善して個人消費が伸びたほか、輸出が下げ止まっていると評価し、景気判断の引き上げを決めたもようだ。 日本経済の先行きは、金融緩和や経済対策の効果に加え、海外経済の回復で「緩やかな回復経路に復していく」とし、判断を据え置いた。 (kyodo = 5-22-13)
◇ ◇ ◇
日銀、全地域の景気判断引き上げ 3 四半期ぶり
日銀は 15 日発表した 4 月の地域経済報告(さくらリポート)で、全国 9 地域全ての景気判断を 1 月の前回報告から引き上げた。 為替相場の円安、株価の上昇を受けて消費や投資の意欲が改善しているほか、海外経済の復調も後押しした。 全地域の景気判断引き上げは昨年の 7 月以来 3 四半期ぶり。
ただ、関東甲信越や近畿、四国、九州・沖縄では、全体として「横ばい圏内」などと指摘し、地域により改善に出遅れ感があることも浮き彫りになった。 中小企業からは円安によるコスト増加への懸念の声も出ている。 今後、大企業と中小企業で景況感の受け止めに格差が生じる可能性がある。 (kyodo = 4-15-13)
◇ ◇ ◇
景況感、9 カ月ぶり改善 日銀短観、円安・株高効果
日本銀行が 1 日発表した 3 月の企業短期経済観測調査(短観)は、代表的な指標の大企業・製造業の業況判断指数 (DI) がマイナス 8 で、前回 12 月調査より 4 ポイント上昇し、昨年 6 月調査以来 3 四半期(9 カ月)ぶりに改善した。 安倍政権の経済政策「アベノミクス」で円安と株高が進み、米国や中国など海外経済が回復したのを背景に、景気の持ち直し傾向が鮮明になった。
短観は 3 カ月に 1 回、企業に景況感を聞く調査。 今回は 2 月 25 日 - 3 月 29 日に全国 1 万 6,98 社に聞き、98.9% が答えた。 DI は景気が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」とする企業の割合を引いたもので、マイナスなら景気が良くないことを示す。 大企業・製造業では、円安や海外経済の回復で輸出が増えた自動車の DI がプラス 10 と、前回から 19 ポイント上昇。 海外の景気回復で需要が増えている汎用機械もプラス 3 と 7 ポイント改善した。 (asahi = 4-1-13)
トヨタ、部品値下げ要求緩和 4 月から下請けに利益還元
【井上亮】 トヨタ自動車が 4 月から、下請け部品メーカーに求める部品の購入価格の引き下げを緩和していたことがわかった。 3 月までの値下げ率は 1.5% だったが、4 - 9 月に納入される部品は 1.0% とした。 円高の一服やコスト削減で業績が急回復してきたことから、値下げ要求を緩めて部品各社に利益を還元する。
トヨタは半期に 1 回、部品の購入価格を各社との交渉で改定している。 2010 年ごろからは毎回、1.5% 程度の値下げを求めてきた。 超円高が進んだ 11 年度下期と 12 年度上期は「円高協力」の名目も加えて 3% 程度を求めた。 業績が回復してきた 12 年 10 月からは 1.5% 程度と、以前の値下げ率に戻していた。
トヨタは円高でも収益が出せるようコスト削減や効率化を徹底。 13 年 3 月期決算で 5 年ぶりに国内事業の営業黒字化を達成し、14 年 3 月期の連結営業利益もリーマン・ショック前の水準に近い 1 兆 8 千億円を予想する。 このため、「トヨタだけがもうけるわけにはいかない(幹部)」と判断。 値下げ率を緩和した。 値下げ要求の緩和は、東海地方に多い部品メーカーには朗報で収益の底上げにつながりそうだ。 今後、雇用を増やしたり、給料を上げたりする動きにつながる可能性もある。 (asahi = 6-29-13)
5 月の消費者物価指数、7 カ月ぶり下げ止まる
【末崎毅】 総務省が 28 日発表した 5 月の全国の消費者物価指数(価格変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数。 2010 年 = 100)は 100.0 で、前年同月と同じになった。 物価が下げ止まったのは、昨年 10 月以来、7 カ月ぶり。 電気料金の値上げが最大の要因だ。
関西電力と九州電力が 5 月から家庭向けの電気料金を値上げしたことが響き、電気代は前年同月に比べ 8.8% 上がった。 輸入に頼っている火力発電の燃料費が円安でかさみ、電力会社の経営が悪化しているためだ。 都市ガス、灯油などのエネルギー代も上がった。 一方、4 月は前年同月比で 16.4% 減だったテレビが 5 月は 9.6% 減と下げ幅が縮まった。 ファストフード店がハンバーガーを一部値上げしたのを受けて、生鮮以外の食品の下落幅も縮まるなど、物価が下がり続ける「デフレ」がやわらぐ兆しもみられる。 (asahi = 6-28-13)
◇ ◇ ◇
4 月の消費支出 1.5% 増 = 4 カ月連続増 - 総務省
総務省が 31 日発表した 4 月の家計調査報告によると、1 世帯(2 人以上)当たりの消費支出は 30 万 4,382 円となり、物価変動を除いた実質で前年同月比 1.5% 増となった。 前年を上回ったのは 4 カ月連続。 安倍政権の経済政策「アベノミクス」による株高・円安で消費者心理が改善し、住宅の工事や外食、旅行などへの支出が増えた。
支出の内訳をみると、太陽光発電設備の設置などで住居関連が 19.2% 増となったほか、旅行や宿泊など教養娯楽が 5.6% 増、外食など食料が 2.7% 増と伸びた。 個人消費の基調判断は「持ち直している」に据え置いた。 勤労世帯の実収入は 47 万 9,854 円となり、実質で 2.9% 増と 2 カ月連続のプラス。 配偶者の収入増が寄与した。 (jiji = 5-31-13)
景気、78 社が「拡大傾向」 主要 100 社調査
【福山亜希】 全国の主要 100 社に朝日新聞が現在の景況感をたずねたところ、「拡大」、「緩やかに拡大」と答えた企業は計 78 社あり、昨年 11 月の前回調査の計 2 社から大幅に増えた。 政府・日本銀行の金融緩和策で円安株高が進み、個人消費や企業収益が上向いたとみる社が増えたためだ。 ただ、輸入物価の高騰など政策の副作用への不安も根強い。
調査は年 2 回で、今回は 6 月 3 - 14 日に原則として経営トップに面談した。 前回は、中国や欧州の景気減速を理由に計 94 社が「後退」、「緩やかに後退」、「足踏み状態」と答えたが、今回はゼロ。 「旅行に行く人が増えた(JTB の佐々木隆会長)」と、消費の回復を指摘する声が目立った。
一方で「富裕層の消費を刺激しているが、日常消費財は動き出していない(セブン & アイ・ホールディングスの村田紀敏社長)」、「実体経済は一部に明るさが見られる程度(アサヒグループホールディングスの泉谷直木社長)」など厳しい見方も。 先行きについても「金利が急騰する恐れがある(積水ハウスの阿部俊則社長)」などの声があがった。 (asahi = 6-22-13)
東京株、今年 2 番目の下げ = 円、93 円台に急騰
13 日の東京株式市場は、米株安と円高加速を嫌気して、全面安となった。 日経平均株価の終値は前日比 843 円 94 銭安の 1 万 2,445 円 38 銭と、日銀が新たな量的緩和を決めた 4 月 4 日の終値を下回った。 下落幅は今年 2 番目の大きさ。 円相場は 4 月 4日以来約 2 カ月ぶりとなる一時 1 ドル = 93 円台後半に急騰した。
前日の米国市場は金融緩和策の縮小懸念を背景に、ダウ工業株 30 種平均が下落。 東京市場もこの流れを引き継いだ。 中国などアジア市場が総じて軟調となったことも悪材料となった。 市場関係者は「『世界の資金の流れが大きく変化するのではないか』と投資家が警戒感を強めている(大手証券)」と指摘する。
東証 1 部全銘柄の値動きを示す東証株価指数 (TOPIX) は、前日比 52.37 ポイント安の 1,044.17 と急落した。 出来高は 32 億 6,458 万株、売買代金は 2 兆 6,935 億円。 東京外国為替市場は、日経平均株価が大幅下落する中、円を買ってドルを売る動きが強まった。 午後 3 時現在は 94 円 31 - 33 銭と前日比 2 円 49 銭の円高・ドル安。 (jiji = 6-13-13)
◇ ◇ ◇
日経平均、一時 580 円超す下げ 為替も円高ドル安水準
週明け 27 日の東京株式市場では株価が急落。 日経平均株価は一時、前週末より 580 円超も値下がりした。 「アベノミクス」への期待で急上昇した反動による下落に加え、世界経済の先行きへの不透明感が高まったためだ。 円相場も一時1ドル = 100 円台の円高ドル安水準となり、さらなる株安につながっている。
株価は取引開始直後から全面安の展開となった。 市場では、前週末の米ニューヨーク市場で株価が伸び悩むなど、世界的な景気回復への不安感が根強い。 そのうえ、外国為替市場では円高もじわりと進んだ。
このため、円高で利益が目減りする自動車など輸出関連企業の株が売られた。 内需関連の小売り・卸売りなども大きく下げた。 前週 23 日に1143円も暴落したため、投資家がいったん株を売って利益を確定しようと売り急ぐ動きもあり、下げが止まらない。 市場では「昨年末からの急な株高で過熱感があり、しばらくは調整が続く(大手証券)」との見方が出ている。
午前の終値は、前週終値より 455 円 11 銭 (3.11%) 安い 1 万 4,157 円 34 銭。 東京証券取引所第 1 部全体の値動きを示す TOPIX (東証株価指数)は、同 30.17 ポイント (2.53%) 低い 1,163.91。 出来高は 22 億 6 千万株。 (asahi = 5-27-13)
◇ ◇ ◇
日経平均急落、終値 1,143 円安 00 年 4 月以来
23 日の東京株式市場は、中国の経済統計の悪化をきっかけに全面安となり、日経平均株価が 1,100 円を超えて急落し、1 万 4,400 円台で取引を終えた。 午前中には一時 1 万 5,900 円台をつけるなど乱高下し、1 日の値動きは 1,400 円を超えた。
終値は、前日より 1,143 円 28 銭 (7.32%) 安い 1 万 4,483 円 98 銭。 下げ幅は 2011 年 3 月の東日本大震災直後や 08 年 10 月のリーマン・ショック後を超え、IT バブルが崩壊した 00 年 4 月 17 日の 1,426 円安以来の大きさになった。 東京証券取引所第 1 部全体の値動きを示す TOPIX (東証株価指数)は同 87.69 ポイント (6.87%) 低い 1,188.34。 東証 1 部の出来高は 76 億 5 千万株と、初めて 70 億株を超えて過去最高を記録。 売買代金も 5 兆 8,376 億円と過去最高をぬりかえた。 (asahi = 5-23-13)
◇ ◇ ◇
日経平均、一時 1 万 5,500 円台に 5 年 5 カ月ぶり
22 日の東京株式市場は、日経平均株価が前日終値より 59 円 67 銭高い 1 万 5,440 円 69 銭で取引が始まった。 その後も値上がりが続き、一時 1 万 5,500 円を超えた。 取引時間中に 1 万 5,500 円台にのせるのは、2007 年 12 月 27 日以来、約 5 年 5 カ月ぶり。 前日の欧米株式市場が値上がりしたことなどを受けて、幅広い銘柄で買い注文が先行している。 (asahi = 5-22-13)
◇ ◇ ◇
日経平均、一時 1 万 4,800 円台 約 5 年 4 カ月ぶり
【長崎潤一郎、湯地正裕】 13 日の外国為替市場で円が売られ、円相場は一時、約 4 年 7 カ月ぶりに 1 ドル = 102 円台前半まで値下がりした。 円安を好感して株は買われ、東京株式市場の日経平均株価は一時、約 5 年 4 カ月ぶりに 1 万 4,800 円台まで上がった。
10 - 11 日のロンドン郊外での主要 7 カ国 (G7) 財務相・中央銀行総裁会議で、円安に対して目立った批判が出なかったため、前週末からの円安がさらに進んだ。 13 日早朝(日本時間)のシドニー市場で一時、1 ドル = 102 円 15 銭まで下がり、2008 年 10 月 21 日以来の 102 円台をつけた。
ただ、その後の東京市場では、急落の反動で円を買い戻す動きも出て、1 ドル = 101 円台での取引が続いている。 午後 1 時時点は、前週末の午後 5 時時点より 48 銭円安ドル高の 1 ドル = 101 円 84 - 92 銭、対ユーロでは、同 04 銭円高ユーロ安の 1 ユーロ = 132 円 09 - 12 銭。
円安で輸出企業の利益が増えるとみて株を買う投資家は多く、13 日の日経平均は前週末に続いて大幅高になっている。 前週末終値と比べた上げ幅は一時、240 円を超えた。 午後 1 時時点では、前週末より 165 円 37 銭高い 1 万 4,772 円 91 銭。 東京証券取引所第 1 部全体の値動きを示す TOPIX (東証株価指数)は、同 19.06 ポイント高い 1,229.66。
午前の日経平均の終値は、同 225 円 76 銭 (1.55%) 高い 1 万 4,833 円 30 銭。 TOPIX は同 24.12 ポイント (1.99%) 高い 1,234.72。 出来高は 31 億 1 千万株。 市場では「金融緩和による大量の資金供給で世界的な株高傾向にある。 日本ではさらに円安が加わり、株価上昇の勢いが増している(大手証券)」との声が出ている。
一方、円とともに国債も売られ、東京債券市場では国債価格が下落(金利は上昇)した。 長期金利の目安になる新発 10 年物国債の流通利回りは一時、前週末の終値より 0.06% 幅上がり、0.750% をつけた。 2 月 18 日以来約 3 カ月ぶりの高い水準。 (asahi = 5-13-13)
◇ ◇ ◇
円相場、一時 1 ドル 101 円台 4 年 1 カ月ぶり円安水準
【篠健一郎、上地兼太郎】 10 日の東京外国為替市場で円安ドル高が進み、円相場は一時、1 ドル = 101 円台まで値下がりした。 2009 年 4 月以来、約 4 年 1 カ月ぶりの円安水準だ。 円安で企業の業績が良くなることへの期待から株価は大きく値上がりし、日経平均株価が一時、約 5 年 4 カ月ぶりの高値をつけた。
円安が進んだのは、前日 9 日の米国市場で米景気の回復期待が高まり、ドル買い円売りがふくらんだからだ。 同日のニューヨーク市場で約 4 年 1 カ月ぶりに 1 ドル = 100 円台をつけ、その後の東京市場でさらに 101 円台前半まで値下がりした。 市場では「米国経済の回復力が思ったより強いため、今後もドルが買われて円安が進む(大手信託銀行)」との見方が強い。
午後 1 時時点では、前日午後 5 時時点より、対ドルでは 2 円 12 銭円安ドル高の 1 ドル = 100 円 95 銭 - 101 円 03 銭。 対ユーロでは同 1 円 59 銭円安ユーロ高の 1 ユーロ = 131 円 72 - 74 銭。 (asahi = 5-10-13)
年 4.1% 増に上方修正 = 設備投資の下げ幅縮小 - 1〜3 月 GDP 改定値
内閣府が 10 日発表した 1 - 3 月期の国内総生産(GDP、季節調整済み)改定値は、物価変動を除いた実質で前期比 1.0% 増、年率換算で 4.1% 増となり、速報値(前期比 0.9% 増、年率 3.5% 増)から上方修正された。 プラス成長は 2 期連続。 上方修正は、新たに得られた経済指標を基に推計し直した結果、設備投資の減少幅が速報値に比べて縮小したのが主因。
物価の影響を反映した生活実感に近い名目 GDP も前期比 0.6% 増、年率換算 2.2% 増と、速報値(前期比 0.4% 増、年率 1.5% 増)から上方修正された。 実質 GDP の各需要項目では、設備投資が前期比 0.3% 減(速報値 0.7% 減)にマイナス幅が縮小。 特にプラントや産業機械などが上方修正された。 一方、公共投資は、緊急経済対策を盛り込んだ 2012 年度補正予算の執行の遅れを反映し、0.4% 増(同 0.8% 増)に下方修正された。
GDP 全体の 6 割を占める個人消費は 0.9% 増、輸出は 3.8% 増、輸入は 1.0% 増といずれも速報値と変わらなかった。 この結果、実質 GDP の増減にどれだけ影響したかを示す寄与度は、内需がプラス 0.6% (速報値プラス 0.5%)に拡大する一方、外需は速報値と同じプラス 0.4% となった。 (jiji = 6-10-13)
◇ ◇ ◇
GDP 年率 3.5% 増、2 期連続プラス
内閣府は 16 日、2013 年 1 - 3 月期実質国内総生産 (GDP) が、12 年 10 - 12 月期に比べて 0.9% 増えたと発表した。 この状況が 1 年続いた場合の年率だと 3.5% 増となる。 プラス成長は 2 四半期連続。 12 年度の GDP は前年度比 1.2% 増で、3 年連続のプラス成長となった。
安倍政権の経済政策「アベノミクス」や、日本銀行の金融緩和への期待から株価が上がったことを背景に、消費者心理が改善。 1 - 3 月の個人消費は前期比 0.9% 増となり、GDP 全体を押し上げた。 一方、設備投資は 0.7% 減っており、景気の本格回復をにらんだ投資にはまだ慎重な企業の姿勢がうかがえる。 (asahi = 5-16-13)
◇ ◇ ◇
GDP、2 年連続成長見通し 1 - 3 月期、個人消費好調
【末崎毅】 今年 1 - 3 月期の国内総生産 (GDP) は一部で消費意欲が強まったため、前期(12 年 10 - 12 月期)から 2 期連続のプラス成長になる見通しだ。 前期は物価変動をのぞいた実質成長率(年率)が 0.2% だったが、民間の研究所 16 社の 1 - 3 月期の予想は平均 2.75% になり、大きく伸びている。
内閣府は 16 日に 1 - 3 月期の GDP 速報を発表する。 四半期ベースでみると、前期の実質成長率は 0.04% だったが、民間 16 社の 1 - 3 月期の予想は平均 0.7% になっている。 16 社は GDP の 6 割をしめる個人消費がプラスになると予想している。 時計やカバンなどの高額品が売れているほか、昨年秋にエコカー補助金が終わって落ち込んだ自動車販売も「落ち込みがほぼ一巡した(みずほ総合研究所)」という。 (asahi = 5-2-13)
安倍総理「所得 10 年で 150 万円増」 "成長戦略第 3 弾"
ところ変わって成長戦略スタジアム。 絶対に進めなければならない規制改革。 決められるのでしょうか、安倍総理大臣の登場です。 まずは「薬のネット販売」。 99% の解禁を固めました。 続いては、今は認められていないサプリメントなどの効果の表示 …。 表示できるようにします。 そして、株式会社の農業参入は …、ここで反対団体が登場。 シュートは弾き返され、盛り込まれませんでした。 間もなく発表される会場から中継です。
(政治部・菅原裕和記者報告) こちらではあと 30 分ほど後で、安倍総理が成長戦略の第 3 弾について発表します。 これに先立ち、安倍総理は「成長戦略の一丁目一番地」と位置づける規制改革について答申を受けました。
安倍総理大臣 : 「安倍内閣は実行する内閣である。 まとめて頂いた改革事項を、一刻も早く実現に移していく。」
約 130 項目にわたる答申には、「雇用の流動化」を促すため、専門の職種や特定の地域に限定して働く「ジョブ型正社員」という制度を作ることも盛り込まれました。 ただ、以前から改革の必要性が叫ばれていた株式会社の農業参入や混合診療の解禁などは業界団体の抵抗に配慮し、議論すらしないまま先送りされました。
安倍総理は、成長戦略の成果として、1 人あたりの国民総所得を 10 年で 150 万円増やすという数値目標も表明します。 アベノミクスの「最後の矢」の全容がこの後の会見で固まります。 これを経済界やが市場がどう受け止めるかが、今後の安倍政権の命運を左右します。 (ANN = 6-5-13)
◇ ◇ ◇
薬ネット販売、原則解禁へ 高リスク品は新たな規制検討
安倍政権は 4 日、市販薬(一般用医薬品)のインターネット販売について原則解禁する方針を固めた。 全体の 1% 未満にあたる高リスク薬の扱いについては、安全性を確保するため、新たな販売規制を設ける方向でさらに調整を進める。
菅義偉官房長官や田村憲久厚生労働相ら関係 4 閣僚が 4 日朝、首相官邸で協議。 ネット販売と店頭販売では売り方を区別するべきではないと確認した。 ただ、発売から 3 年以内など安全性が確立されたと判断できない薬(全体の 1% 未満)については、どのような販売規制をつくるか調整がつかず結論を持ち越した。
菅官房長官は 4 日午前の記者会見で「最高裁の判決の趣旨を踏まえ、安全性に十分配慮するなかで、新たなルール策定に向けて検討している」と述べた。 安倍晋三首相は 5 日に打ち出す成長戦略第 3 弾で、ネット販売の原則解禁に言及し、14 日にまとめる成長戦略に盛り込む方針だ。 (asahi = 6-4-13)
地価上昇地区、全国の過半数に 大都市で回復鮮明 国交省 4 月調査
地価の回復傾向が広がってきた。 国土交通省が 29 日発表した 4 月時点の地価動向報告によると、全国 150 地区の 53% に当たる 80 地区が 3 カ月前に比べて上昇した。 上昇は 1 月時点から 29 地区増え、現行調査が始まった 2008 年 10 月以降、初めて半数を超えた。 大都市圏の商業地の上昇が目立ったほか、住宅地も堅調だった。
■ 再開発意欲高く
調査は全国の主な商業地と住宅地で 3 カ月ごとに実施。 地価調査の中では速報性が高い。 国交省は今回の結果を「従来の下落基調から上昇・横ばい基調への転換が広範に見られる」と分析。 安倍晋三政権の経済政策「アベノミクス」がオフィス需要や住宅投資回復への期待を生んだ形だ。
回復が鮮明なのは商業地(106 地区)だ。 上昇は 54 地区と前回から 23 地区増えた。 集客力の見込める商業施設周辺の地価が上昇しており、とうきょうスカイツリー駅周辺(東京・墨田)と、超高層複合ビル「あべのハルカス」を建設中の阿倍野(大阪市)は上昇率が 3% を超えた。
オフィスビルの需要増を受け、横ばいが続いた丸の内(東京・千代田)や大手町(同)の地価も上昇に転じた。 中規模ビルの多い八重洲・京橋地区でも再開発の機運が高まり、投資を呼び込んでいる。 住友不動産は東京・八重洲の老舗ホテル「八重洲富士屋ホテル(東京・中央)」の土地・建物を国際興業(東京・中央)から取得。 再開発を含め活用策を検討する。
住宅地(44 地区)も上昇が 26 地区と前回から 6 地区増えた。 南青山(東京・港)や高輪(同)、代官山(東京・渋谷)など都心の高級住宅街の地価が横ばいから上昇に転じた。 14 年 4 月の消費増税をにらんだ住宅の駆け込み購入の動きも地価を押し上げている。
三菱地所はアベノミクス効果で東京都心の高額マンションの販売が好調。 港区の高級住宅地や中央区の湾岸エリアで用地取得を進める方針だ。 三井不動産は「土地の入札への参加者が増え、競争は厳しくなっている。 (値がつり上がりやすい入札より)土地所有者との相対取引での仕入れを増やす」としている。
■ 地方はばらつき残る
地域別でみると、東京、大阪、名古屋の三大都市圏で上昇地区の割合が軒並み 5 割以上になった一方、地方圏は 34% にとどまる。天神(福岡市)や那覇新都心(那覇市)などが上昇に転じたが、東北の被災 3 県では仙台市の一部を除き、なお地価が下落基調にある。
今後の地価動向について、第一生命経済研究所の鈴木将之副主任エコノミストは「円安を追い風に国内景気の回復が続き、地価も当面は上向き傾向」とみる。 ただ最近の地価上昇は投資マネーの流入が演出している面もあり、足元では長期金利の上昇や株式相場の調整など逆風も吹く。
実際に消費者の所得が増えてこなければ、用地取得費の上昇分をマンションなどの販売価格に転嫁することは難しく、不動産業者にとっては頭が痛い状況だ。 持続的な地価上昇には企業業績や雇用・賃金の回復で、企業や個人の「実需」が盛り上がる必要がある。 (nikkei = 5-29-13)
対外純資産が過去最大に 12 年末時点、円安効果で
【五十嵐大介】 日本の企業や政府、個人が海外に持つ資産(対外資産)から、外国勢が日本国内に持つ資産(対外負債)を差し引いた「対外純資産」は、2012 年末時点で前年より 11.6% 増の 296 兆 3,150 億円で、3 年ぶりに過去最大になった。 財務省が 28 日発表した。 「対外資産」の残高は、13.8% 増の 661 兆 9,020 億円。 11 年末に 1 ドル = 77 円台だった円相場が、12 年末には 1 ドル = 86 円台と、1 年間で 9 円近い円安となったため、日本企業などが外貨建てでもっている資産を円に換算した時の評価額が上がった。
10 年、11 年は円高傾向が続いたが、12 年末に円安に転じたことが、3 年ぶりの過去最大更新につながった。 日本企業による海外投資が増えたことも影響した。 一方、外国人が日本で持っている資産を表す「対外負債」の残高も、15.7% 増の 365 兆 5,880 億円で過去最大になった。 海外投資家が持つ日本株の株価が上がったことなどが理由だ。 日本の対外純資産額は 1991 年以来 22 年連続で世界首位。 2 位の中国(約 150 兆円)、3 位のドイツ(約 121 兆円)を大きく上回った。 (asahi = 5-28-13)
安倍首相、成長戦略第 2 弾発表 農業・農村の所得倍増目標
安倍晋三首相は 17 日、東京都内で講演し、農林水産業の強化や民間投資の拡大などを柱とする成長戦略第 2 弾を発表した。 環太平洋パートナーシップ協定 (TPP) への交渉参加を控え、対策の焦点となる農業分野では、生産から加工、流通までを担う「6 次産業化」を進めて農業・農村全体の所得を 10 年間で倍増させるとの目標を掲げた。 首相は、その実現に向け、首相を本部長とする政府の「農林水産業・地域の活力創造本部」を来週新設すると述べた。
また、これからの 3 年間を「集中投資促進期間」と位置付け、税制、予算、規制改革など施策を総動員して企業の国内投資を促す考えを示した。 そのうえで「リーマン・ショック前の民間投資の水準である年間 70 兆円規模の設備投資を回復したい」と述べた。 首相は先月 19 日、医療、雇用、子育て分野の成長戦略を発表しており、今回の第 2 弾と合わせて、金融緩和、財政出動に続くアベノミクスの「3 本目の矢」のメニューがほぼ出そろった。
首相は「長いデフレ不況を振り返れば、まだまだ反転の兆しというレベルに過ぎないが、力強い成長軌道に乗せていくべく全力で取り組む」と強調。 デフレ脱却に向け、企業の投資マインドを政策的に刺激していく考えを示した。 具体的には、▽ 製品実験などで必要な規制緩和を個別企業に特例で認める「企業実証特例制度」の創設、▽ 中小企業や小規模事業者が個人保証なしで融資を受けられる新たな金融枠組み、▽ 設備の新陳代謝や経営改革、事業再編に取り組む企業への支援 - - などを挙げた。
また、首相は「若者が希望を持って働きたいと思える『強い農業』をつくり上げる」と表明。 国別、品目別の戦略を定め、現在 4,500 億円程度の農産物・食品の輸出額を 1 兆円規模にすることは「十分に可能」と説明した。 現在 1 兆円の「6 次産業化」市場を「10 年間で 10 兆円に拡大したい」とも訴えた。 さらに「農業の構造改革を今度こそ確実にやり遂げる」と約束。 農地を集積して生産性を高めるため、各都道府県に農地の中間的な受け皿機関を創設し、民間企業などに貸し付ける構想を披露した。 (mainichi = 5-17-13)