最低賃金、全都道府県で初の 1 千円超え 全国平均 1,121 円前後へ
最低賃金(時給)の今年度の改定額が 5 日、47 都道府県で決まる予定だ。 歴史的な物価高を踏まえ、初めて全都道府県で 1,000 円を超え、全国加重平均も昨年の 1,055 円から過去最高の 66 円程度上がり、1,121 円前後となる見通しだ。 最低賃金の引き上げ額は、厚生労働省の審議会が都道府県の経済情勢に応じて A - C ランクに分けて示す目安を参考に、各都道府県ごとの審議会が決める。 地域間格差の是正を図るため、地方の C ランクを 64 円とし、都市部の A、B ランク(63 円)より初めて高くした。
目安通りだと 1,118 円になる計算だったが、地方の審議では B、C ランクを中心に目安への上乗せが相次いだ。 引き上げ額が最も大きかったのは熊本の 82 円だった。 昨年 951 円を答申し、全国で最も低い最低賃金となった秋田では昨年から 80 円と大幅に引き上げ、1,031 円の答申をまとめた。 新しい最低賃金の最高額は東京の 1,226 円、最低額は高知、宮崎、沖縄の 1,023 円だった。 最高額と最低額の差は前年より 9 円縮んで 203 円になる。 全国で高水準の引き上げが相次いだ一方、準備期間が必要だなどとして、発効時期を遅らせる動きが地方で目立った。
最低賃金は答申後、異議申し立ての期間を経て例年 10 月に発効するのが通例。 だが、今年は 10 月中に発効するのは栃木など 20 都道府県にとどまった。 秋田は最も遅い来年 3 月 31 日とした。 厚労省賃金課によると、年度末に発効するのは 1975 年以来半世紀ぶりの遅さで、目安制度ができてからは初めてという。 今年度の地方審議をめぐっては、賃金向上担当相を兼務する赤沢亮正経済再生相が、福岡県や愛知県の知事に対して目安を上回る引き上げへの異例の協力を求めたほか、知事が目安への上乗せを地方の審議会に求める動きも目立った。
政府は目安を超えた都道府県に対して補助を出す方針を示していた。 目安を超える引き上げが相次いだ背景には、こうした政治的な動きもあったとみられる。 赤沢氏によると、最低賃金に近い水準で働く労働者は全国に約 660 万人いるとされる。 デフレ下で一般労働者の平均賃金が停滞するなかでも、政府は 2010 年代半ばからコロナ禍をのぞき最低賃金は 3% 超の引き上げを続けてきた。 地方では人手不足が深刻化しており、働き手を確保するためにも最低賃金の重要性は増している。 (南日慶子、asahi = 9-5-25)
熊本の最低賃金 82 円引き上げ 1,034 円へ 目安 18 円上回る大幅増
熊本県内の最低賃金について、熊本地方最低賃金審議会は 4 日、82 円引き上げて 1,034 円にするよう、熊本労働局長に答申した。 初めて 1 千円を超え、来年 1 月 1 日に発効する見通し。 82 円の引き上げは、4 日夕までに今年の答申があった 45 都道府県の最高額となる。 県内の引き上げ幅としても過去最大で、中央最低賃金審議会が示した熊本などの目安の 64 円を 18 円上回る。 熊本市の消費者物価指数で食料の増加率が 8.1% と高いことなどが根拠とされた。
審議では、労働者側は生計費の上昇などから大幅な引き上げを求め、使用者側は中小零細企業の支払い能力が追いつかない状況を訴え、隔たりが大きかった。 このため、例年は 8 月に出る答申が 9 月にずれ込んだ。 最後は公益委員の見解に基づいて多数決で決めたが、採決で使用者側は一部が退席し、残った委員も反対した。 8 月の大雨被害も考慮し、例年は 10 月中だった発効日を遅らせることには労使とも賛成した。
審議会の倉田賀世会長(熊本大学教授)は答申後、「合議で決める審議会の意義を損なわないため、労使にできる限りの歩み寄りを求めた。 労働者の生活保障を考え、特に食費の増加には注目した。 人材流出についても考慮した。」などと話した。 地域別最低賃金は、中央審議会が示す目安を参考に、学識者らの公益代表と労働者代表、使用者代表それぞれの委員の 3 者が都道府県ごとの地方審議会で引き上げ幅を議論して改定される。 (江口悟、asahi = 9-4-25)
最低賃金 1,118 円、過去最高 63 円引き上げ 全都道府県 1 千円台に
厚生労働省の中央最低賃金審議会は 4 日、最低賃金(時給)を全国加重平均で 63 円 (6.0%) 増の 1,118 円とする目安を決めた。 物価高に対応し、過去最高だった昨年の目安の 50 円 (5.0%) を大きく上回り、過去最高の上げ幅となった。 審議会の小委員会がこの日開かれ、労使の代表と公益代表の有識者で目安をまとめた。 現在の最低賃金は全国の加重平均で 1,055 円。 東京都が 1,163 円で最も高く、秋田県が 951 円と最も低い。 目安通りの引き上げとなれば全都道府県で初めて 1 千円を超えることになる。
目安は、労使の代表と公益代表の有識者で構成する中央審議会が毎年、都道府県を 3 ランクに分けて提示。 東京など大都市部の A ランクと B ランクは 63 円、地方などの C ランクは 64 円だった。 地域間格差の是正を図るため、経済力の低い C ランクの引き上げ額を、A ランクや B ランクより初めて高くした。 今後、これを参考に都道府県ごとの最低賃金を地方審議会が決め、秋に改定する。 昨年は徳島で目安を 34 円上回るなど、地方の審議で目安に上乗せする例が相次ぎ、全国加重平均の最低賃金はさらに高くなる可能性がある。
今年の審議では、労働者側が物価高騰や今春闘での正社員の賃上げ率が平均 5.25% と高水準になったことを踏まえ、過去最高だった昨年を大きく上回る引き上げを要求していた。 石破政権は「2020 年代に全国平均 1,500 円」との目標を掲げており、実現には年平均 7.3% の引き上げが必要だ。 賃金向上担当相を兼務する赤沢亮正経済再生相が経済団体の関係者と会談するなど、政権側も目標達成に向けて高水準の引き上げを求めていた。
一方、使用者側は引き上げに理解を示しつつ、企業規模や業種によってはコスト増を十分に価格転嫁できておらず経営を圧迫するなどと指摘。 6% を超える高水準の引き上げには慎重な姿勢を見せるなどして調整が難航し、小委員会は 1981 年以来 44 年ぶりに 7 回目の開催となった。
審議会には参考指標として食料の消費者物価指数の前年比伸び率 6.4% (24 年 10 月 - 25 年 6 月平均)や 1 カ月に 1 回程度購入する品目の伸び率 6.7% (同)といったデータが示され、使用者側への説得を続けた。 最終的には、生活必需品などの値上がりによって、最低賃金に近い働き手への影響が大きいことなどを重視して目安をまとめた。 (asahi = 8-4-25)
最低賃金「6.0% 以上」で続く調整 赤沢氏、経済団体と直接協議も
厚生労働省の中央最低賃金審議会は 1 日、最低賃金(時給)の今年の引き上げに向けて 6 回目の小委員会を開き、詰めの協議を進めた。 物価高騰を踏まえ、全国加重平均で過去最高となった昨年の 50 円 (5.0%) を大幅に上回る 6.0% (63 円) 以上の目安を示す方向で調整に入っている。 小委員会が 6 回目に及ぶのは 2010 年以来 15 年ぶり。 複数の関係者によると 1 日も 6.0% 以上の目安に向けた協議が続けられ、「賃金向上担当」を兼務する赤沢亮正・経済再生相も同日、経済団体の関係者と都内で会談し、高水準の引き上げに理解を求めた。
現在の最低賃金は全国の加重平均で 1,055 円。 東京都が 1,163 円で最も高く、秋田県が 951 円と最も低い。 6.0% 以上の目安が実現すれば全国平均で 1,118 円以上となり、全都道府県で初めて 1 千円を超えることになる。 目安は、労使の代表と公益代表の有識者で構成する中央審議会が毎年、都道府県を 3 ランクに分けて提示。 これを参考に都道府県ごとの最低賃金を地方審議会が決め、秋に改定する。 今年は、労働者側が物価高騰や今春闘での正社員の賃上げ率が平均 5.25% と高水準になったことを踏まえ、過去最高だった昨年を大きく上回る引き上げを要求している。
この動きに「20 年代に全国平均 1,500 円」との目標を掲げる石破政権も同調。 実現には年平均 7.3% の引き上げが必要で、政権側も目標達成に向けて高水準の引き上げを求めている。 厚労省は審議会に参考指標として食料品の消費者物価指数の前年比伸び率 6.4% (24 年 10 月 - 25 年 6 月平均)を示している。 一方、使用者側は引き上げに理解を示しつつ、企業規模や業種によってはコスト増を十分に価格転嫁できておらず経営を圧迫するとして、「6.0% 以上」の引き上げに慎重な意見もあり、調整が難航する可能性もある。 (asahi = 8-1-25)
「最低賃金大幅引き上げを」ミャンマー人実習生、福岡の審議会で訴え
7 月 31 日に開かれた福岡地方最低賃金審議会で、外国人技能実習生として最低賃金で介護の仕事をするミャンマー人女性 (24) が意見陳述した。 同じ仕事の日本人との賃金格差を指摘し、「大幅な引き上げ」を求めた。 厚生労働省によると、中央と地方の最低賃金審議会で技能実習生が意見陳述したのは全国初とみられる。 意見陳述は、北九州合同労働組合(ユニオン北九州)が支援して実現した。 ユニオン側は、自分の意思で職場を変われない技能実習生が低い賃金で働かされている実態を知ってもらおうと、女性を推薦したという。
女性は北九州市の社会福祉法人が運営する介護施設で働く。 陳述では、多くの技能実習生が母国の送り出し機関への支払いで抱えた 100 万円前後の借金の返済や家族への送金に追われる実情を説明。 一方で、女性の給与は最低賃金で計算され、手取りから家族に 10 万 - 15 万円を送金した残りの月 5 万円ほどで生活していると述べた。
女性は「同僚の日本人で最低賃金で働く人はいません」と同一労働同一賃金に反する状況にも触れ、「最低賃金が 1,500 円になれば、母国に送金しても 10 万円以上が手元に残り、自分のために使ったり、将来に向けて勉強したりすることもできます」と訴えた。 都道府県ごとの地方最低賃金審議会は毎年、労働局長から諮問を受け、最低賃金の金額を答申する。 審議の過程で労働者側と使用者側それぞれの意見聴取も行う。
時給は最低賃金 992 円、多くを家族に送金
この日の意見陳述や陳述後の女性の説明によると、女性は母国のクーデターと父親の失業で、大学を 3 年で辞めて働かざるを得なくなったという。 高校生の頃から日本のアニメが好きで、日本語を学んでいたこともあり、外国人技能実習生として 2023 年春に来日。 福岡県内で特別養護老人ホームなどを運営する北九州市の社会福祉法人に雇用され、介護施設でフルタイムで働いている。 基本給はずっと最低賃金で計算され、現在は時給 992 円。 夜勤が多い月は手取りで 22 万円ほどになるが、夜勤が少ない月は額面が 19 万円、手取りが 15 万 - 16 万円ほどにとどまるという。
来日前に母国の送り出し機関に 100 万円を支払う必要があり、そのための借金をした。 その借金分はすでに完済したが、現在も毎月、自分の生活費 5 万円ほどを差し引いた全額を、家族の生活や弟の学費のために送金しているという。 女性は意見陳述で、「私たち技能実習生の多くは 100 万円くらいの借金をして来日しています。 借金を返済し、家族の生活を支えるために給料のほとんどを送金しています。」と説明。 「私に限らず、一緒に働くミャンマーの実習生はみんなそうです」と話した。
また、日本人との賃金格差についても「最低賃金だと日本人は働かないと聞きました」と言及。 また、最低賃金の地域間格差があるため、技能実習生にも最低賃金が高い東京や大阪で働くことを望む人が多くなり、失踪の問題にもつながっている、という見方も示した。 女性は陳述後の取材に「ほかの技能実習生もみんな仕事が大変で、借金を抱えて働いている人が多いです。 とても緊張しましたが、みんなに代わって、意見を伝えることができてよかったです。」と話した。 (江口悟、asahi = 7-31-25)
最低賃金、議論始まる 参院選で各党「賃上げ」圧力 過去最高なるか
雇い主が働き手に支払うべき最低賃金(時給)について、今年の引き上げ幅の目安を決める議論が 11 日、厚生労働省の審議会で始まった。 物価高騰が続く中、50 円と過去最高の上げ幅となった昨年の目安額を、どの程度上回るかが焦点となる。 最低賃金は労使の代表と有識者でつくる中央最低賃金審議会が毎年夏に議論し、目安を提示。 その後、都道府県ごとの地方審議会が目安を参考にそれぞれの金額を決め、10 月以降に引き上げられる。
昨年は、中央審議会が目安として 50 円の引き上げ幅を示し、最終的に全国平均で過去最高の 51 円 (5.1%) 上がり 1,055 円となった。 歴史的な物価高が続く中、中央審議会では今年も高水準の目安額が示される公算が高まっている。
物価高超えられない賃上げ
コメなどの食料品やエネルギー価格の高騰で、実質賃金の計算に使う消費者物価指数は 6 カ月連続で 4% 超。 物価の影響を考慮した働き手 1 人あたりの「実質賃金」は 5 カ月連続でマイナスだ。 労働組合の中央組織・連合が 3 日に発表した今年の春闘での正社員の賃上げ率は平均 5.25% と、1991 年の 5.66% 以来 34 年ぶりの高さだったが、物価高騰に賃上げ効果が打ち消されている現状だ。
こうした状況を踏まえ、20 日投開票の参院選では、主要各党が最低賃金の引き上げを公約に掲げる。 自民党は「2020 年代に全国平均 1,500 円達成を目指す」と訴え、立憲民主党も「全国で早期に 1,500 円以上に引き上げ」と主張。 れいわ新選組などは「全国一律 1,500 円」を掲げる。
政権目標の達成には、年 7.3% の引き上げ必要
石破政権も「20 年代に全国平均 1,500 円」を目標に掲げ、その実現には、過去最高だった昨年を大きく上回る年平均 7.3% の引き上げが必要。 加えて、朝日新聞が全国の知事を対象に実施した最低賃金をめぐるアンケートでも 9 人がそれぞれの水準について「低い」との認識を示しており、最低賃金をめぐる政治の動きや行政トップの認識などが、引き上げの議論にも影響を与えそうだ。 中央審議会の議論は参院選後に本格化し、7 月末にも目安が提示される見通し。 昨年と同水準の引き上げが続けば、最終的な最低賃金は全都道府県で 1 千円を超える。 (宮川純一、asahi = 7-11-25)
最低賃金に 9 知事が「低い」 人材流出に危機感 朝日新聞アンケート
朝日新聞は 47 都道府県知事に最低賃金に関するアンケートを実施した。 それぞれの最低賃金の現在の水準について、判断を示した 30 人のうち、岩手、埼玉など 9 人が「低い」と回答した。 労使が入る審議会で決まる水準に行政トップが明確に異議を示したもので賃金格差による人材流出などへの危機感が現れた形だ。
最低賃金をめぐっては、石破政権が 2020 年代に全国平均を 1,500 円に引き上げる目標を示し、今夏の参院選でも大きなテーマの一つになっている。 最低賃金の水準の評価では「妥当」と回答したのは宮城、神奈川、大阪など都市部を中心に 21 人。 「低い」は青森、岩手、秋田、茨城、群馬、埼玉、福井、佐賀、沖縄の 9 人で、東北や北関東で目立った。 951 円で全国最下位の秋田の鈴木健太知事が「女性や若者の人口流出の背景には、賃金水準をはじめとする雇用環境の地域間格差がある」と回答するなど、人材流出に危機感を募らせる声が多かった。 1,163 円で最も高い東京は「その他」を選び判断は示さなかった。
2020 年代 1,500 円目標 「反対」は 1 県
最低賃金は経済団体と労働組合の代表、有識者の公労使でつくる厚生労働省の審議会が目安を示し、都道府県ごとの地方最低賃金審議会が水準を決める。 知事が関与する仕組みはない。 そのため、「県がコメントすることは好ましくないと考える(奈良)」と回答自体を避けるケースもあったが、北海道大の安部由起子教授(労働経済学)は「知事が低いと答えた背景には、近隣自治体との金額差や全国最下位への危機感がありそうだ」と分析。 知事の「低い」との認識が地方審議会での議論に影響を与える可能性もある。
一方、最低賃金をめぐっては昨年、徳島の後藤田正純知事が地方審議会に出席して引き上げを求め、84 円という異例の引き上げ額を実現した。 知事が審議に関与する仕組みの必要性をたずねたところ、「公労使の議論を尊重するべきだ」との回答が 30 人にのぼり、「県の関与は現行の議論の自立性を損なうため慎重になるべきだ(兵庫)」との意見もあった。 「検討するべきだ」は、徳島のほか、群馬、佐賀の 3 人で、「徳島ショック」と呼ばれた政治主導の手法は広がりを欠いているようだ。 安部教授は「過度に介入すれば現行制度が壊れてしまうため、ルールを守ろうという考えの知事が多いことがうかがえる」と指摘した。
石破政権が掲げる「1,500 円」の実現目標は賛成が 9 人。 評価自体を避ける「その他」の回答が目立ち、「賃上げ原資を確保できる環境整備(千葉)」を求める意見があった。 反対は島根県の丸山達也知事の 1 人で「達成を可能にする具体的な政策がないのに、実現困難な目標だけを示して事実上強制することには反対」とコメントした。 アンケートは全国の知事を対象に 6 月に実施し、全知事から回答を得た。
都市部とその周辺 二極化の様相
物価高や人手不足に伴う人材獲得競争を背景に、最低賃金の水準や決定の仕組みをめぐる知事の認識は、最低賃金の高低を反映して、都市部とその周辺で二極化の様相を呈している。 全国で最も最低賃金が高い東京の小池百合子知事は水準も含め、すべての質問に「その他」を選び、決定の仕組みも「国において適切に運用されるべきである」などと回答し、距離を置く。 福岡や宮城などの都市部も軒並み、水準を「妥当」と答え、決定過程への知事の関与についても「公労使の議論を尊重するべきだ」と慎重だ。
一方、水準を「低い」と答えたのは茨城など 9 人。最低賃金の高い都市部への人材流出の問題意識を反映しているとみられ、中でも埼玉に接する群馬の山本一太知事は「知事が積極的に関与できる仕組みを検討していく必要がある」、福岡の隣の佐賀の山口祥義知事は「県からの意見聴取を義務付けるなど、地域課題等を踏まえた幅広い議論が可能となる仕組みが必要」と知事が関与できる仕組みを求めた。
「公労使」重視でも…
ただ、全体では知事の関与を求めたのは徳島を加えた 3 人。「公労使」で決まるシステムを尊重しつつ、いかに適切な賃上げを実現させるかのバランスを重視する様子が浮かぶ。 山形の吉村美栄子知事は「県政を預かる立場にある知事の意見も一定程度反映することが望ましい」と現行のシステムに注文をつけた。 秋田の鈴木健太知事も「中長期的な視点による広範なデータ分析が必要」と指摘した。
必要な施策について複数回答可で尋ねたところ、価格転嫁の推進が 38 人と最も多く、中小企業向けの補助金の拡充が 26 人と続いた。 長崎の大石賢吾知事は「地域を支える中小の経営悪化を招かないよう、国においては対策を総動員してもらいたい」と国に注文を付けた。 埼玉の大野元裕知事は「県として価格転嫁により実質賃金上昇の原資確保に向けて国に先駆けた対策を重ねてきたが、企業のサプライチェーンは全国に広がっている」と回答。 京都の西脇隆俊知事も「生産性向上をはじめとした中小企業の伴走支援体制の強化」などを国に求めていることを明らかにした。
地域間格差を解消するために、最低賃金の「全国一律化」も議論となっているが、一律化を求める主張は 2 人にとどまり、「反対」は 9 府県。 総じて慎重な意見が多かった。 「地域によって事情が様々であり、全国一律とすると大きな混乱が生じるおそれがある(福岡県の服部誠太郎知事)」など、地域によって異なる経済状況が主な理由としてあげられている。 (南日慶子、北川慧一、編集委員・沢路毅彦、asahi = 7-5-25)
最賃 1,500 円へ政府が参考目標を提示 「データ先走り」経営側懸念
政府は 23 日、首相官邸で開いた経済政策に関する会合で、最低賃金を 2020 年代に全国平均 1,500 円に引き上げる目標に向けた参考の一つとして、欧州連合 (EU) 指令が掲げる「賃金分布の中央値の6割」という目標設定を示した。 具体的な参考モデルを明示し、政府目標の実現に道筋をつけたい考えだ。
この日の「新しい資本主義実現会議」では、人材育成などとならび、最低賃金の引き上げも議論。 政府は文書で「高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続する」とし、「EU 指令においては、賃金の中央値の 60% や平均値の 50% が最低賃金設定に当たっての参照指標として、加盟国に示されている」と強調。 「これらに比べて、我が国の最低賃金が低い水準となっていることも踏まえるべきではないか」として目標達成への参考になり得るとの認識を示した。
類似の指標としては、労働組合の中央組織・連合が 23 年、35 年ごろに中央値の 6 割まで引き上げる目標をまとめた。連合の試算では23年時点で日本の最低賃金は中央値の5割弱にとどまる。 経済協力開発機構 (OECD) のデータによると、「フルタイム労働者の平均賃金に対する最低賃金」は、23 年で中央値の 46.01% だった。
最低賃金の引き上げ幅は、日本では毎年、公労使で構成される審議会で「労働者の生計費」、「一般的な賃金水準」、「企業の支払い能力」の 3 要素に基づいて決まる。 近年は上げ幅が拡大し、昨年は過去最大の 51 円 (5.1%) 上昇し、全国平均は 1,055 円になった。 一方、労働政策研究・研修機構の調査によると、日本の最低賃金(昨年 1 月時点)はオーストラリア、ドイツ、英国、フランスの半分程度で、カナダ、米国、韓国などを下回っている。
石破政権はさらなる引き上げが必要だとして 1,500 円への目標を掲げるが、今後5年間で 445 円の引き上げが必要。 単純計算だと年平均 7.3% 増となり、使用者側からの反発も大きく、EU の目標設定の例示には、使用者側の理解を広げる狙いもありそうだ。 ただ、会合に出席した日本商工会議所の小林健会頭は朝日新聞の取材に、EUの目標設定について、「欧州の平均賃金は、若年層と非正規ワーカーは除外している。 データだけが先走ると変な形になってしまう」と話した。 (宮川純一、asahi = 4-23-25)
雇用調整助成金の申請、年間 50 件から 1 日 300 件に急増
テレワーク進まぬ 労働局が悲鳴「集団感染起きたらどうなる!?」
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、事業主が払う休業手当を政府が補う雇用調整助成金(雇調金)の申請が急増し、受け付け業務を担う労働局の業務負担が増している。 テレワーク推進を呼び掛ける立場ながら、在宅での勤務への移行も進んでおらず、職員からは「職場で集団で感染したら業務の運営が厳しくなる」と不安の声も聞かれる。
◆ 「リーマン・ショック時はるかに上回る忙しさ」
2 月上旬、千葉市中央区の雑居ビル内の一室。 千葉労働局の非常勤職員ら約 50 人が雇調金の申請受け付け業務に追われていた。 労働局近くで借りた部屋で、受け付けから審査、支給決定通知書の送付までを行う。 電卓や分厚いファイル、チェックリストを手にした職員らは、ひっきりなしに鳴る電話に応対していた。 厚生労働省によると、雇調金は景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的に休業するなどした場合に支払われる。 2020 年 4 月、コロナの影響により経営が悪化した事業者に対して、1 日当たりの支給上限額や助成率が引き上げられる特例措置が導入された。
千葉労働局では、コロナ前は年間約 50 件だった申請件数は現在は 1 日約 300 件に上るようになり、申請受け付けのための非常勤職員と派遣職員を約 100 人増員した。 提出された申請書類は不備があることも多く、職員らは電話で事業主に確認しながら手続きを進め、支給要件を尋ねる問い合わせにも応対する。 担当者は「リーマン・ショック時をはるかに上回る忙しさ」と打ち明ける。
◆ 在宅勤務は「数 % 程度」
申請受け付け業務のテレワークへの移行は進んでいない。 コロナ感染拡大が始まった 20 年以降の雇調金の申請件数が 90 万件を超える東京労働局では、一部の職員から「在宅勤務でできないか」という声が上がっているというが、テレワークをしている職員は「体感として数 % 程度(同労働局担当者)」という。
申請受け付け業務に携わる職員は「テレワークを導入するにはセキュリティー対策が必要。 業務をこなしながらテレワークへの移行を短期間で行うのは難しい。」と説明。 一方で、「職場内でクラスターが発生したら業務が停止するかもしれない」と不安を語る。 各地の労働局を管轄する厚労省は、コロナ感染拡大当初から、テレワークを推進してきた。 東京労働局の担当者は「推進しながらも、厳しいところにあることは認識している」とするが、テレワーク態勢の強化について具体的な方策は示さなかった。 (鈴木みのり、東京新聞 = 2-28-22)
雇用調整助成金の特例措置 6 月末まで延長へ 厚労省
雇用調整助成金の特例措置について、厚生労働省は新型コロナの影響が続いているとして、ことし 6 月末まで延長することを決めました。 雇用調整助成金は、企業が従業員の雇用を維持した場合に、休業手当などの一部が助成される制度で、新型コロナの影響を受けた企業を対象に特例措置が設けられています。 具体的には「まん延防止等重点措置」などの対象地域で、休業や営業時間の短縮などに協力した企業や、直近 3 か月の月平均の売り上げが 3 年前までのいずれかの年と比べて、30% 以上減少した企業には一日当たりの上限額を 1 万 5,000 円に、助成率を大企業と中小企業いずれも最大 100% に引き上げています。
それ以外の企業についても助成率を中小企業は最大 90%、大企業は最大 75% に引き上げています。 特例措置の期限は 3 月末までとなっていましたが、厚生労働省は、新型コロナの影響が続いているとして、ことし 6 月末まで延長することを決めました。厚生労働省は当初5月末まで延長する方向で調整を進めていましたが、与党内から、さらなる支援の強化を求める意見が出たことなどから、6月末まで延長することにしました。 厚生労働省によりますと、雇用調整助成金の支給額は、特例措置が設けられたおととし 2 月からことし 2 月 18 日までに 5 兆 3.000 億円余りに上っています。
後藤厚生労働相「まずは命と暮らしをしっかり守る」
後藤厚生労働大臣は、記者団に対し「今のオミクロン株の流行状況や経済の状況など考えて決定した。 今後、政府を挙げて経済と新型コロナ対策の両立に向けてしっかりと対応していく。 まずは、命と暮らしをしっかり守っていくということに努めたい。」と述べました。 (NHK = 2-25-22)
雇用保険料引き上げ承認 失業給付分、10 月から - 厚労省審議会
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の雇用保険部会は 7 日、失業手当などに充てる「失業等給付」の保険料率を 10 月から半年間、労使で計 0.6% に引き上げることなどを盛り込んだ報告書を承認した。 9 月までは現在の 0.2% に据え置く。 新型コロナウイルス感染拡大で雇用調整助成金(雇調金)の支給が急増、財源が枯渇したため労使の負担増を決めた。 厚労省は報告書を踏まえ雇用保険法などの改正案を 17 日召集の通常国会に提出する。 (jiji = 1-7-22)
世耕氏、雇用保険料引き上げに懸念「コロナ禍で適切なのか」
自民党の世耕弘成参院幹事長は 17 日の記者会見で、雇用保険料率の引き上げについて、「料率を上げることが決まろうとしている。 (新型)コロナの出口が見えない中で国民に負担をお願いするというのは本当に適切なのか」と述べた。 引き上げに懸念を示した形だ。
雇用保険料は失業給付などに充てられ、会社と従業員が分担して納める。 コロナ禍で雇用調整助成金の支出が大きく増えたことなどから財政が悪化し、政府は料率を引き上げようとしている。 料率を引き上げれば来年4月以降、会社と従業員の負担が増える。 世耕氏は引き上げについて、「必要性は理解するが、党内で十分議論し、上げるなら国民の理解をしっかり得た上で行うことが何よりも重要だ」と政府に対応を求めた。 自民党幹部は「給料が高くない人の手取りを直撃する」と述べ、国民の負担感が増えることによる来夏の参院選への影響を懸念する。 (asahi = 12-17-21)
雇用保険 2.2 兆円を追加投入へ 補正予算で財源不足の急場しのぐ
厚生労働省は今年度の補正予算案に、雇用保険の追加財源として約 2.2 兆円を計上する方向で調整に入った。 雇用保険は、コロナ禍対応の雇用調整助成金(雇調金)の支出が 5 兆円近くに膨らんで財源がほぼ底をついており、税金の投入で急場をしのぐ考えだ。 政府はコロナ禍による失業増を防ぐため、雇用を維持して休業手当を払う企業を支援する雇調金の給付水準を引き上げて拡充。 コロナ禍に伴う雇調金の支出は、2020 年春から今年 11 月までに 4.8 兆円を突破した。 リーマン・ショック直後の 09 年度に支出した額の 7 倍を超す規模だ。
雇調金の財源となる雇用保険制度は原則、企業と働き手が分担して払う雇用保険料でまかなわれている。 その年に入る保険料のほか、景気が安定している時に保険料を積み立て、不況時の支出に備えている。 コロナ禍が長引き支出が増えた結果、雇調金などに使える積立金の残高は 19 年度末に約 1.5 兆円あったが、20 年度末にゼロになった。 本来なら失業給付に使う別の財源からも資金を回したため、この財源の積立金残高も 19 年度末の約 4.5 兆円が今年度末には約 4 千億円まで減る見通しだ。 税金もすでに雇調金のために約 1.1 兆円を投じた。
いまも雇調金は月 2 千億円規模の支出が続く。 政府はコロナ禍対応の特例措置の一部を来年 3 月まで維持することを決めている。 雇調金は失業を防ぐ一定の役割を果たしたと言われる一方、成長が見込める分野への転職をしにくくしているという指摘もある。 財政難のため、厚労省の審議会が現在、来年度の保険料引き上げを議論しているが、労使双方の委員が警戒感を示している。 政府が 2 兆円を超す税金の投入を検討するのは、当面の財政に余裕を持たせ、保険料の急激な引き上げを避けられるようにする狙いもある。 (橋本拓樹、山本恭介、asahi = 11-21-21)
雇用調整助成金の不正受給 2 件 休業手当など助成する制度
新型コロナウイルスの影響を受けた企業などが雇用を維持するために利用できる「雇用調整助成金」の不正な受給が(長野)県内で 2 件あったことがわかり、長野労働局は返還するよう命じました。 「雇用調整助成金」は企業が従業員を休ませるなどして雇用を維持した場合に国が休業手当などの一部を助成する制度で、新型コロナの影響を受けた企業を対象に助成率を引き上げる特例措置が設けられています。
この助成金をめぐっては全国的にも不正が相次いでいますが、県内でも昨年度から今年度にかけて 2 件、不正な受給があったことが長野労働局への取材でわかりました。 2 件はいずれも新型コロナの影響で従業員を休ませているように装う、うその書類を国に提出し、あわせておよそ 190 万円を不正に受け取っていたということで、労働局はこの 2 つの事業所に対して返還するよう命じました。 長野労働局は「県内で不正受給があったことは大変残念だ。 不正が疑われる事案には事業所の訪問による調査などで厳正に対応する。」と話しています。 (NHK = 11-17-21)
業績悪化の証明、最初だけ? 雇調金膨らみ強まる「要チェック」の声
コロナ禍対応の雇用調整助成金は支出が 5 兆円に迫る
コロナ禍の特例対応で支出が 5 兆円に迫る雇用調整助成金(雇調金)をめぐり、利用企業による業績悪化の証明が、初回申請時だけですむ運用を問題視する声があがっている。 要件を満たさない企業も利用している可能性がある。 25 日にあった厚生労働省の審議会でも、チェックを厳しくするよう求める意見が出た。 「業況が回復し、適用要件に該当しなくなった企業には支給する必要性はない。 速やかに確認することが重要だ。」 25 日の審議会で、委員の一人が訴えた。
焦点は雇調金の「業況特例」と呼ばれる要件だ。 3 カ月の月平均売上高が前年か前々年同期より 3 割以上減なら該当する。 雇調金の 9 月の支出 2,100 億円のうち、約 5 割が業況特例によるものだった。 大企業に絞ると 7 割を業況特例が占める。 雇調金を継続して使う企業は支給申請のたびに休業実績の書類などを出し直す。 だが、業績悪化の証明書類は初回だけ。 2 回目以降は不要になっているという。
業況は業界ごとに異なる。 飲食、観光業などは引き続き事業環境が厳しい一方、製造業などでは急回復した分野もある。 チェックを求める声が強まる背景には、雇調金の支出が 10 月までに累計 4 兆 6 千億円を超え、雇用保険の財政が厳しくなっていることもある。 岸田文雄首相が 10 月 14 日の記者会見で、雇調金の特例を来年 3 月まで延ばすと明言したこともあって、財源問題がますます先鋭化している。
コロナ禍の初期には支給を急ぐために申請方法を簡略化した面もあった。 だが足もとでは厚労省幹部からも「事務手続きは増えるが、もう一度要件を確認すれば、業況特例の申請をする企業は数割減るのでは」と、期待の声が漏れる。 慶応大学の土居丈朗教授(財政学)は「特例が続くことで長期間休業している人もいるだろうが、それはすでに失業に近い」と指摘する。 雇調金が労働市場の活性化を妨げている恐れもあるとして「いま一度、休業と失業の捉え方、何のリスクに備えた制度なのかを見直す必要もある」と話す。 (山本恭介、asahi = 10-25-21)
雇用調整助成金 : 企業が休業などを迫られても従業員の雇用を守って休業手当を払ったら、国から助成金を受け取れる制度。 本来の助成は 1 人あたりの日額上限8,265 円、休業手当の最大 3 分の 2 だが、政府がコロナ禍対応で昨年春から内容を拡充。 現在、業績が一定以上悪化した企業には「業況特例」として日額上限 1 万 5 千円、最大 10 割を助成している。 それ以外は原則、日額上限 1 万 3,500 円で最大 9 割。
雇用保険 財源不足に備え負担も論じよ
コロナ禍の長期化で雇用調整助成金の支給総額が膨らみ、雇用保険の財政が逼迫ひっぱくしている。 保険料引き上げに関する論議を深めたい。 厚生労働省の労働政策審議会が雇用保険の財源確保のあり方について検討を始めた。 年末までに結論を出すという。 雇用調整助成金は、失業を回避するため、従業員を解雇せずに休業にとどめた企業に対し、休業手当の一部を支給する仕組みだ。 政府は昨年から、新型コロナウイルス対策として金額や助成率を引き上げる特例措置を講じてきた。
コロナ禍の下でも、日本の失業率は諸外国ほど上がっていない。 今年の労働経済白書は、助成金によって、失業率が月平均 2.6 ポイント抑制されたと分析している。 失業の増加は、社会的にも影響が大きい。 雇用の安全網を強化していくことが大切である。 2018 年度に 20 億円だった助成金の支給総額はコロナ流行後に急増し、昨年以降の累計は 4.5 兆円に及んでいる。 このため、財源確保が課題となっている。 助成金は本来、雇用保険料を元手とする積立金で賄う制度だが、特例法によって、昨年度以降、失業手当の積立金から 1.6 兆円を借り入れ、一般会計から 1.1 兆円を投入してきた。 それでも払底しつつあるという。
まず、当面の財源を確保せねばならない。 19 年度に 4.4 兆円あった失業手当の積立金は今年度末には 4,000 億円まで減る見込みで、一般会計からの追加的な支出も避けられまい。 来年度以降も見据え、企業と従業員が負担する雇用保険料について、どの程度が望ましいかを議論することが不可欠である。 保険料率は現在、労使の合計で賃金の 0.9% だ。 原則は 1.55% だが、コロナ禍前までは雇用情勢が堅調で財源にゆとりがあったため、低く抑えてきた。 財源が不足しているとはいえ、コロナ禍にある企業や働き手の現状を考慮すれば、大幅な負担増は難しい。 段階的な引き上げが現実的ではないか。
助成金は現在、休業者 1 人当たり 1 日最大約 8,300 円から、1 万 5,000 円に引き上げる特例措置を講じている。 コロナの感染状況や雇用情勢を踏まえ、特例を縮小していく時期を見極めることが重要になろう。 従業員を休業させたと偽って、企業が助成金を不正受給する例が相次いでいる。 刑事告発するなど、対策も強化してもらいたい。 (yomiuri = 10-10-21)
上場 620 社が雇用調整助成金を受給 20 年度、6 社に 1 社
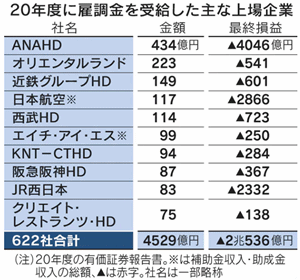
上場企業の 6 社に 1 社が 2020 年度に雇用調整助成金を受け取っていたことが、日本経済新聞の集計で分かった。 新型コロナウイルス禍の打撃が大きい空運や鉄道など非製造業を中心とした約 620 社で、受給総額は 4,500 億円を超えた。 コロナ禍特例による増額措置が続いているうちに、収益を回復させられるかが課題となる。
雇調金は従業員の休業手当の一部を国が助成する制度で、仕事の減った企業の雇用維持を促す狙いがある。 コロナ禍による特例措置で 1 人あたり上限が 1 日 1 万 5,000 円に拡充され、12 月末まで延長される。 厚生労働省によると 20 年度の支給決定額は 296 万件で 3 兆 1,555 億円だった。 日本経済新聞が上場企業約 3,800 社の 20 年度(20 年 4 月期 - 21 年 3 月期)の有価証券報告書を集計したところ、622 社が営業外収益や特別利益などで雇調金収入を計上した。 受給総額は約 4,530 億円と雇調金全体の 1 割強を占める。
正社員の雇用を下支え
622 社の 3 月末の連結従業員数(臨時従業員を除く)は 19 年度比 0.7% 減の 249 万人とほぼ横ばいだった。 正社員の雇用は雇調金による下支えが鮮明だ。 一方、契約社員やパートなど臨時従業員数は 9.6% 減の 121 万人で、約 13 万人減った。 特にサービス業は 20% 減と影響が大きい。 外食などがコロナ禍で店舗閉鎖を進め、バイトを減らしている事情がある。 622 社の売上高は前の期比 17% 減の 82 兆円、最終損益は合計で 2 兆円の赤字(前の期は 2 兆 6,000 億円の黒字)で、雇調金収入がなければさらに赤字が拡大していた。 上場企業全体(売上高 7% 減、純利益 5% 増)より落ち込みが大きい。
最多は ANA、434 億円
業種別に見ると、非製造業が 371 社・3,611 億円と社数ベースで 6 割、金額ベースで 8 割を占めた。 受給額が最も多いのはサービス業で 1,202 億円(177 社)。鉄道・バス(993 億円)、空運(558 億円)が続いた。 ANA ホールディングスは 434 億円と上場企業で最も多く「乗務員や地上職員などすべての職種で活用した」という。 外食ではクリエイト・レストランツ・ホールディングスが「休業した店舗の社員の賃金の補填として活用」して 75 億円を計上している。
一方、製造業では自動車(21 社・186 億円)が最多だった。 三菱自動車(60 億円)やヤマハ発動機(23 億円)のほか、ユニプレスなど部品メーカーも多かった。 雇調金を受け取った 622 社のうち、21 年度の業績予想を開示している約 520 社をみると、9 割強が黒字転換や増益を計画。 最終赤字を見込むのは 38 社と 7% にとどまる。 大半の企業がワクチン普及を前提としており、雇調金の特例措置が切れる前に業績が回復するかどうかが焦点だ。 野村総合研究所未来創発センター制度戦略研究室長の梅屋真一郎氏は「従業員の生活を守りつつ、成長産業への移行を支援するような施策が必要」と話す。
財源や「出口」、課題も露呈
雇用調整助成金の支給決定件数は 2021 年 8 月時点で 418 万件となった。 失業率の悪化を防ぐ目的からは、コロナ禍で一定の効果があったとの指摘は多い。 例えば 20 年 4 月 - 10 月の完全失業率は平均 2.9% だったが、助成金がなければ 5.5% 程度という高い水準になっていたと労働経済白書は分析する。 ここに来て課題も見えてきた。 政府は支給要件を緩めたり助成を拡充したりする措置を特例として続けるが、財源が底を突き始めている。
支給額は 20 年 3 月からの累計で 4.1 兆円超。 国の一般会計からの投入は予算ベースで支給額の 4 分の 1 に達する。 別事業の積立金からの借り入れなどでしのいできたが逼迫度合いは解消されない。 追加の国費投入や企業・働き手の雇用保険料を 22 年度にも引き上げる検討を迫られている。 雇調金の特例とそれに頼る構造が長引けば、成長分野への労働移動を結果的に遅らせるという側面もある。 日本総合研究所の山田久副理事長は「ワクチン接種が進む今秋以降を見据え、日本も出口を探す時期にきている」と指摘する。
海外を見ると、例えばドイツには雇調金と同じような「操業短縮手当」があり、コロナ禍で拡充に動いた。 英国などは雇用支援の多くを国費でまかなう。 事業を縮小すれば世論の反発を招く恐れがあるため、各国ともに出口戦略に悩む。 (nikkei = 8-15-21)