久々の外国クルーズ船 博多に震災後初寄港
福岡市の博多港に 3 日朝、東日本大震災後に途絶えていた外国からのクルーズ客船が寄港した。 市や九州運輸局の職員が歓迎の横断幕を掲げて出迎える中、乗客は観光に出かけた。
客船は、ドイツの船会社が所有する「ブレーメン(約 6,700 トン)」。 5 月 30 日に中国・上海を出港後、鹿児島、長崎と回って福岡を訪れた。 乗客はドイツやオーストリア、メキシコなどからの約 80 人。 11 日の北海道・小樽到着まで船旅を楽しむ。 3 日午前に希望者が福岡タワーや太宰府天満宮などをめぐり、正午ごろ大阪に向けて出港した。
福岡市は国内外のクルーズ客船誘致に力を入れ、博多港への寄港は 2006 年の 20 回から昨年は 84 回に増えた。 今年は 77 回を見込んでいたが、震災の影響で予定が 46 回まで減った。 次回の外国クルーズ客船の寄港は 8 月に予定されている。 (asahi = 6-3-11)
◇ ◇ ◇
クルーズ船が春と一緒にやってきた 博多港

福岡市の博多港に 6 日朝、バミューダ船籍のクルーズ船オーシャン・プリンセス(3 万 277 トン)が寄港、春からのクルーズ船の季節が到来した。 2011 年の外国船の博多寄港は 55 回と 1 割減の見込み。 人気が出る東北や需要が持ち直す地中海向けとの競争に正念場の年となる。
船旅と寄港地を楽しむクルーズ船は外国人観光客を呼び込む有力な手段。 ロシア・ウラジオストクから着いた 650 人は、太宰府などで 1 日を過ごして広島に向かった。 船は改修した中央埠頭に停泊。 遠くて殺風景と不評だった貨物用の箱崎地区から移動した。 福岡市は、土産が並びバスが待てる建屋を設け、九州新幹線とあわせて博多を売り込む。 市港湾局の担当者は「寄港数が戻るようがんばりたい」と話す。 (大畑滋生、asahi = 3-8-11)
岩手沿岸部、高台の地価上昇 一部地区はバブル期水準
岩手県の被災地で津波による浸水を免れた高台の土地が、一部で値上がりを始めた。 政府や県が、住宅や公共施設の「高台移転」を検討していることが背景にある。 投機目的の買い占めなどに発展すれば街の再建の障害になるため、県は実態調査に乗り出した。
朝日新聞が県沿岸部の複数の不動産業者に取材したところ、大船渡市で震災前に坪 10 万円前後だった宅地が、13 万 - 15 万円に上がっていた。 主に市内を南北に走る国道 45 号の山側の地域で、不動産業者によると、大手プレハブメーカーが造成を打診してきた例もある。 地区によっては「バブル期の価格水準に戻りつつある」という。
宮古市や釜石市でも、一部の高台の宅地を中心に 2 割前後、地価が上がっている。 山田町でも売れ残っていた坪 8 万円の土地 2 区画が 10 万円で売れた。 (asahi = 5-30-11)
記憶遺産、文科省置いてけぼり 「様子見」中に先越され
炭鉱記録画家山本作兵衛 (1892 - 1984) の絵画や日記など計 697 点が、福岡県田川市などの申請でユネスコの世界記憶遺産に国内で初めて登録されることが決まった。 今月になって藤原道長の「御堂関白記」などの申請を決めた文部科学省は、自治体に先を越された形となり、波紋が広がっている。
記憶遺産は 1992 年にユネスコが始めた制度。 文科省は 2004 年ごろ、国宝などの中から推薦を検討したが、文化庁側から「国宝の順位付けにつながるのは良くない」との慎重論が出て、選定を見送った。 ある政府高官は「文化庁は文化財を価値付けし、秩序を作ってきた。 それを荒らされたくないという意識が出た。」と指摘する。 (asahi = 5-26-11)
◇ ◇ ◇
筑豊の炭鉱画、国内初の「記憶遺産」に 山本作兵衛作
世界の人々の営みを記録した歴史的文書などの保存と振興をめざすユネスコの「世界記憶遺産」に 25 日、福岡県田川市などが所有・保管する炭鉱記録画家、山本作兵衛 (1892 - 1984) の絵画や日記などが登録された。 同日、英マンチェスターで開かれた国際諮問委員会を経て、ユネスコ事務局長が承認した。 記憶遺産への登録は国内では初めて。
記憶遺産は 1992 年に始まった事業。 これまでに、フランスの手書き版「人権宣言」やアンネの日記など 76 カ国 193 件が登録されている。
山本作兵衛は現在の福岡県飯塚市生まれ。 7 歳ごろから父について炭鉱で働き始め、採炭夫や鍛冶工として、筑豊地域の中小の炭鉱で働いた。 63 歳で炭鉱の警備員として働き始めたころ、孫らに当時の生活を伝えようと炭鉱の絵を描き始めるようになった。 92 歳で亡くなるまで描いた絵は 2 千枚近いと言われる。
申請していたのは、田川市が所有・保管する絵画 585 点、日記 6 点、雑記帳や原稿など 36 点と、山本家が所有し福岡県立大(田川市)が保管する絵画 4 点、日記 59 点、原稿など 7 点で、計 697 点。 (asahi = 5-25-11)
沖縄振興は「県の主体的役割」 県の要望踏まえ政権方針
2012 年度から 10 年間にわたる新たな沖縄振興計画の策定をめぐり、菅政権は「沖縄振興における県の主体的役割」を前面に掲げる方針を固めた。 従来の計画策定は「国の責務」を軸として進めてきたが、沖縄県側の長年の要望を踏まえて方針を転換する。 24 日に首相官邸で開く沖縄政策協議会の振興部会で沖縄県側に伝える。
沖縄の振興計画は復帰以来 10 年ごとに策定され、現行の第 4 次計画は 02 - 11 年度が対象。 菅政権は今年 8 月をめどに、11 年度末に期限を迎える沖縄振興特別措置法に代わる新法案の骨子をまとめ、これに伴う新振興計画の検討に入る方針だ。 その際には「県の主体的役割」と「国の責務」を明記する。 (asahi = 5-23-11)
JR 高速船、博多 - 韓国・麗水間に 来年の世界博期間中
博多港と韓国・釜山港を結ぶ高速船、ビートルを運航する JR 九州高速船は、来年 5 - 8 月に韓国南部の麗水(ヨス)市で開かれる世界博覧会に合わせて、博多港 - 麗水港の間で定期便を就航させる方針を固めた。 今のところ定期運航は会期中だけの予定だが、閉幕後の定着もめざすという。
麗水市は韓国南部の全羅南道の港町で人口 30 万人。 周辺は史跡や海岸湿地があり、新たな観光地として注目されている。 来年の世界博は「生きている海 息づく沿岸」がテーマで、95 カ国が参加、1 千万人の来場を見込んでいる。 関係者によると、ビートルの新航路は博多港 - 麗水港を約 3 時間 45 分で結ぶ。 運航本数は週 3 往復程度になりそうだという。 釜山航路は韓国企業との共同運航だが、新航路は JR 九州高速船が単独で運航する。
これまで麗水と日本を結ぶ直行便はなく、日本からの観光客は、釜山からバスで 3 時間、ソウルからは電車やバスで 5 時間かかっていた。 直行便就航で、世界博への日本人の集客と、来場者が日本へ足を延ばす効果が期待できるという。 (asahi = 5-22-11)
◇ ◇ ◇
中国人ご一行様、お久しぶりです 福岡あげて熱烈歓迎
東日本大震災の発生後初めての中国からの団体ツアー客が 29 日、福岡市の福岡空港に到着し、5 泊 6 日の九州周遊に向かった。 震災で落ち込んだ海外からの観光客を呼び戻すきっかけに、との期待を込めて、福岡では知事や市長らが法被姿で出迎えた。 「ニーハオ」、「ウエルカム・トゥ・フクオカ」のかけ声と「熱烈歓迎」の横断幕。 29 日午後、福岡空港に着いた中国・西安からのツアー客 40 人は、日本側の歓待に笑顔で応えつつも戸惑うような表情を見せた。
一行の歓迎式で観光庁の山田尚義審議官は「震災で一部地域は大きな被害を受けたが、九州をはじめ多くの地域では通常通り」と強調した。 九州観光推進機構会長の石原進・JR 九州会長も「九州は震災の地域から 1 千キロ以上離れていて、まったく安全」と呼びかけた。 ツアー客一人ひとりに記念品も用意された。
手厚いもてなしには、わけがある。 昨年、九州・山口の空港や港から入国した外国人は中国や韓国を中心に過去最高の約 110 万人を記録。 今年は九州新幹線の全線開通もあり、さらなる増加が期待されていた。
それが震災で暗転した。 シンクタンクの九州経済調査協会が 3 月下旬、九州の観光施設を調べたところ、キャンセルは 141 施設で約 12 万人にのぼり、うち 5 万人が海外からの客だった。 九州に寄港する海外クルーズ船も、4 月 1 日の時点で年間予定の 4 分の 1 にあたる 31 隻がキャンセルとなった。 3 月に日本を訪れた中国からの客は前年同月の半分に落ち込んだ。
九州経済白書によると、昨年に九州を訪れた外国人の経済効果は 1,512 億円で、1 人平均 15 万 2 千円を消費していた。 地域経済への影響は小さくない。 日本側には、海外からの客を呼び戻したいとの思いが強い。 福岡県の小川洋知事は歓迎式で「今回の旅行を周りにお伝えいただき、九州、日本に数多くお越しいただくことを願っています」と頭を下げた。 空港を出るバスに手を振り、笑顔で見送った。
ツアーの一行は長崎、熊本、大分を回り、博多どんたくも見物する予定だ。 (土屋亮、熊谷徹也、asahi = 4-29-11)
◇ ◇ ◇
新博多駅ビル、目標上回る 726 万人来場 開業 1 カ月
JR 博多駅に 3 月 3 日開業した「JR 博多シティ」の運営会社は 4 日、開業して 1 カ月間の来場者数が 726 万人となり、目標の 600 万人を上回ったと発表した。 中核施設の博多阪急の 3 月の来店客数は 454 万人。 博多シティを訪れた人のうち 6 割強が立ち寄ったことになる。 3 月の売上高は計画額を 13% 上回る 43 億円だった。 (asahi = 4-4-11)
七滝・大和沢のダム計画中止 国の再検証対象で初
国土交通省は 19 日、熊本県御船町で計画していた国直轄の七滝ダムと、青森県が弘前市で計画していた大和沢ダムの建設を中止すると発表した。 国は 2009 年の政権交代後、全国 83 のダムについて建設の是非を再検証している。 いずれもその対象で、初めての中止決定となった。
七滝ダムは御船川の洪水対策として計画され、総事業費 395 億円。 御船川は水害を繰り返しており、88 年 5 月には九州地方を襲った豪雨で堤防が決壊し、死者・行方不明者 3 人、家屋全半壊 79 戸などの被害を出した。 91 年から建設に向けた調査が始まったが、88 年の豪雨被害をきっかけに大規模な河川改修が進められ、堤防がかさ上げされた。 03 年には、流域自治体が「水余り」でダムは不要と方針転換するなど、利水面でも必要性が低下していた。
民主党政権がダムに頼る治水の見直しを進める中、今年 2 月、国交省九州地方整備局の事業評価監視委員会で中止方針が了承されていた。 大和沢ダムは県が建設する国の補助ダムで、総事業費 287 億円。 水質改善が主な目的だったが、下水道整備が進むなどし、県は中止の判断をしていた。 (asahi = 5-20-11)
鹿児島湾でレアメタル発見 国内販売量の 180 年分
9 割以上を中国からの輸入に頼る希少金属(レアメタル)の一種「アンチモン」の鉱床を、岡山大や東京大などのグループが鹿児島湾の海底で発見した。 埋蔵量は、国内の年間販売量の 180 年分と推定される。 ただし、強い毒性によって採掘の際に海洋汚染が生じる恐れがあるため、実際に採掘するには新たな技術の開発が必要という。
研究の成果は、22 日から千葉市で開かれる日本地球惑星科学連合大会で発表される。 アンチモンは、繊維を燃えにくくする難燃剤や半導体などに広く使われ、日本は 95% 以上を中国から輸入している。
鉱床が見つかったのは、2003 年に気象庁が「活火山」に指定した若尊(わかみこ)カルデラの一部。 桜島の北東約 5 キロの鹿児島湾内にあり、約 2 万 5 千年前に大噴火した姶良(あいら)カルデラの主要火口という。 07 年に約 200 度の熱水噴出孔を発見した山中寿朗・岡山大准教授(地球化学)らが、付近の鉱物を調べていた。
鉱床は、水深約 200 メートルの海底に、厚さ 5 メートルで直径 1.5 キロの円状に広がっていた。 エックス線の調査で平均約 6% 含まれていることがわかり、全量は約 90 万トンになると推定した。 昨年の国内販売量は約 5 千トンで、180 年分がまかなえる計算になる。 中国では含有量約 0.5% の岩石から抽出しているといい、鹿児島湾の鉱床の方が効率よく取り出せるという。
ところが、アンチモンにはヒ素と同じ毒性があるため、海砂利と同じような方法で採掘すると海中に拡散する恐れがある。 体内に蓄積した魚介類を通し人体にも害を及ぼしかねない。 山中准教授は「海洋汚染を防ぎながら海底から取り出す技術を開発できれば、自給が可能になる」と話している。 (長崎緑子、asahi = 5-15-11)
宮城県漁協、漁業権開放に反対決議 「特区構想」に反発
津波で被害を受けた水産業の再生に向け、宮城県の村井嘉浩知事が漁業権を開放する「特区構想」を政府の復興構想会議で提案したことに対し、同県漁協は 11 日、臨時役員会で「漁協組織の根幹を揺るがすもので、容認できない」と決議した。
構想は、地元漁協が事実上独占してきた漁業権を民間に開放し、復興に民間資本を生かすのがねらい。 県漁協は「民間企業は利潤追求が第一義で、これに合わなければ撤退し、地域に荒廃と崩壊が残される。 われわれは企業に隷属するつもりはない。」と主張。 漁協と連携した復興計画の立案を県に求めた。 (川端俊一、asahi = 5-11-11)
◇ ◇ ◇
漁業権の民間開放提案へ 宮城知事が特区構想
宮城県の村井嘉浩知事は、地元の漁協が事実上、独占してきた漁業権を民間に開放する特区構想をまとめた。 津波で壊滅的な被害を受けた水産業の施設や漁船などの再生に民間資本を生かすためだ。 ただ、漁協からの反発もありそうだ。
10 日午後の菅政権の東日本大震災復興構想会議で提案する。 村井氏は先月 23 日の構想会議で、水産業の施設や漁船などを国費で整備する「国有化」構想を発表。 今回の特区構想で新たに漁業権を得る組織は、国有化 3 年後をめどに株式会社化を目指す組織や、地元の漁業者が新たに設立する組織を想定している。
現行の漁業法では、漁業権は地元漁協が優先的に得られる仕組みになっている。 カキの養殖に必要な「区画漁業権」の場合、区画ごとに都道府県知事が免許を出す対象は、地元漁業者が多く入っている漁協を「第一順位とする」と明記。 定置網も同趣旨の扱いとなっている。
特区構想では、これらの規制を緩和。 集計が済んだ分だけで 3,936 億円(10 日現在)にのぼる水産関連施設の被害の復旧・復興に民間資本を生かしつつ、漁業の近代化・効率化も進めて、水産業の活性化を狙う。 宮城県内は、2007 年に 31 漁協が合併した「1 県 1 漁協」体制。 ただ、地域や浜ごとに被害状況や後継者の有無などの差が大きい。 地域ごとに独自で再生を目指すことを今回の構想で支援することも念頭にある。 (田伏潤、高橋昌宏、asahi = 5-10-11)
◇ ◇ ◇
水産業再生へ「国有化」構想 宮城知事が提案へ
宮城県の村井嘉浩知事は、津波で壊滅的な被害を受けた水産業の施設や漁船などを国費で整備する「国有化」を進め、再生を目指す構想をまとめた。 被害が甚大で、民間資金での復興は困難と判断。 将来的には施設を民間が買い取り、運営母体を株式会社化する計画だ。
23 日の菅政権の東日本大震災復興構想会議で提案するが、水産庁は国有化には否定的で、被災自治体の提案は焦点の一つになる。 漁船、養殖施設、水産加工施設といった水産関連施設の多くは、個人や民間会社の所有物。 宮城県内に約 1 万 3 千隻あった漁船の 9 割は津波で大破し、水産関連施設の被害は集計が済んだ分だけで 3,936 億円(22 日現在)に上る。
知事の構想では、これらの施設を国の資金で再整備。 石巻市や気仙沼市に複数の運営母体を設立し、運営資金も国が支出する。 実際に仕事にあたるのは地元の漁業関係者で「公設民営」に近いイメージだ。
三陸沖は世界 3 大漁場の一つで、宮城県の漁業・養殖と水産加工品の生産量は 2008 年に全国 2 位。 だが、男性漁業従事者約 8 千人の 4 割が 60 歳以上で高齢化が進んでいるため、「新たな借金をして一から立て直すのは難しい(県幹部)」という事情がある。
再生が順調に進めば、県外も含む民間からの出資を募り、3 年後をめどに株式会社化を目指す。 こうした取り組みを通じて、漁業の経営基盤を震災前より強くすることも視野に入れている。 ただ、構想の実現に向けたハードルは低くない。 運営母体の具体的な設計図は固まっておらず、政府の理解が得られるかどうかは不透明。 共存を目指す漁協との調整も水面下で始まったばかりだ。 (田伏潤、asahi = 4-23-11)
自慢のスギと大工、仮設住宅建設で役立つ 岩手・住田町
良質な建材になる気仙スギの産地・岩手県南部沿岸で、木造仮設住宅の建設が進む。 江戸時代から宮大工の技を持つ気仙大工が活躍した林業と製材業が盛んな地域で、震災復興で見込まれる木材需要を地域浮揚の足がかりにしたいとの思いがある。 被災者の雇用も生んでいる。
同県住田町の町営住宅跡地にこぢんまりとした、さわやかな白木の壁の木造住宅が 13 戸建った。 町が 4 月下旬に建てた木造仮設住宅だ。 壁も床も気仙スギなどの木材を使った一戸建てで、2DK で約 30 平方メートルの間取りは標準的なプレハブ仮設と同じ。 町は 5 月中旬までに約 100 戸を造る計画だ。 「木のぬくもりと、においがある。 被災者もほっと一息つけるのではないか。」と 4 月末に視察に訪れた阿久津幸彦・内閣府政務官も関心を示した。
木造仮設住宅は、多田欣一町長が今年初めに町の第三セクター・住田住宅産業に開発を指示していた。 町の基幹産業である林業と木工の販路拡大のための一策だった。 大災害に備え、資材を備蓄してはどうかと国に働きかけているさなかに、東日本大震災が起きた。 「まさか、自分たちの足元で、こんなに早く必要になるとは思わなかった」と多田町長は話す。
町によると、床や壁に使う資材は町内の木材加工工場であらかじめ処理済みで、現場での組み立ては簡単だ。 1 戸あたり約 250 万円と、コスト面でもプレハブと遜色がないという。 仮設住宅は通常、災害救助法に基づき県が設置するが、今回はミュージシャンの坂本龍一さんが代表の森林保護団体モア・トゥリーズ(東京都)がまかなう。 必要な資金約 3 億円を負担すると町に申し出た。 団体はインターネットなどを通して寄付を募るという。
岩手県も、県産材を活用した仮設住宅の建設を目指す。 県内で必要と見込む約 1 万 8 千戸のうち、約 1 万戸はプレハブを発注。 残りの大半は木造で、公募で選んだ 21 業者に発注する。 住田住宅産業もその一つで、佐々木一彦社長は「仮の住まいとはいえ、木の家で安らいでもらいたい。 将来、住宅を再建するときに、気仙スギの家を選んでもらえれば。」と話す。
◇
住田町の木材加工会社「けせんプレカット事業協同組合」の工場は、大型連休中もフル稼働している。 岩手県陸前高田市の佐々木輝昭さん (26) が先輩社員の指導を受けながら、仮設住宅用の木材を機械で加工していた。 組合が被災者を対象に募集した臨時職員に採用された。 同組合は約 200 人のグループ社員の給与を 7 - 10% 削るワークシェアリングで、75 人の臨時職員を募っている。
佐々木さんは自宅を津波で流され、父を亡くした。 夏に向けて野菜の苗を植えたビニールハウスは全滅。 「塩害とがれきで畑がいつ元に戻るかわからない。 仕事が見つかったのは本当にありがたい。」と話す。 復興需要への期待もある。 組合によると、震災直後に一時、落ち込んだ受注は 4 月に入って回復。 その後は仮設住宅や住宅再建をにらんで、ふだんの倍近い受注があるという。
泉田十太郎専務理事は「住宅再建の動きが本格化すれば、臨時雇用の一部は社員として採用できる」とみる。 輸入材におされ、木材価格の低迷に泣いてきた林業農家もこうした動きを注視している。 気仙地方森林組合のはの木澤(はのきざわ、「はの」は木へんに爪)光毅・代表理事組合長は「家を建てるときに木材の産地にまでこだわる人はまだ少ない。 復興を通して、気仙スギのブランドを知ってもらえれば。」と期待している。 (野崎健太、asahi = 5-9-11)
「平泉」世界遺産へ登録勧告、旅行客増に期待
「平泉」の世界文化遺産への登録勧告が出た 7 日、JR 平泉駅前のそば店では観光客らが新聞号外を手に「わあ、すごい!」と歓声を上げた。 中尊寺境内では桜が散るなか、観光客は例年より少なめだった。 初めて参拝した青森県八戸市の高校 1 年古武家(こぶけ)亮太さん (15) は日本史の教科書で見たという金色堂を見物して「正式な遺産になった後にもう一度来たい」と話した。
今回、国際記念物遺跡会議(イコモス)は、金色堂を含む中尊寺、毛越寺などの四つの庭園と金鶏山について仏国土(浄土)を表す資産として顕著な普遍的価値があると認定した。
ただ、登録には柳之御所遺跡を除外することを条件とした。 奥州藤原氏の館跡であり、浄土思想との直接的な関連性が薄く、顕著な普遍的価値があるとまでは言えないという判断からだ。 名称も「平泉 - 仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群」から「平泉 - 仏国土(浄土)を表す建築・庭園」へ変えるよう勧告した。
盛岡大教授で平泉文化遺産センターの大矢邦宣館長は「除外は、イコモスの指摘のように以前から心配していた点だ。 その関連で名称も変更された」と解釈し、「今回は除外によって平泉の価値を認めてくれたと思う」と勧告に好感を示した。 (石間敦、asahi = 5-8-11)
被災地のイトーヨーカ堂閉店見直しも セブン & アイ会長
流通最大手、セブン&アイ・ホールディングスの鈴木敏文会長は 6 日、朝日新聞のインタビューに応じ、傘下の大手スーパー、イトーヨーカ堂の閉店計画について、東日本大震災の被災地域では計画を見直す方針を明らかにした。
イトーヨーカ堂は 2009 年から約 30 店を閉鎖するリストラ策に着手し、11 年度も 7 店程度の閉鎖を計画している。 対象には東北地方の店舗も含まれていたと見られるが、鈴木会長は「震災後、東北の売り上げは良く、閉店を検討していた所も続けることができる。 商品供給を続ける流通業者としての義務もある。」と見直しを示唆した。 全体の閉店数も減らす見込みだ。
傘下の大手コンビニエンスストア、セブン-イレブン・ジャパンの被災店舗に対しては、所有者が建て直す場合、5 千万円を上限に低利融資する制度を新設。 仮設住宅の入居者向けの店舗出店のため「地元自治体と協議している」という。
今夏の節電が求められる東京電力管内の店舗について、セブン-イレブンが LED 照明導入などによってピーク時電力の 25% を削減するほか、グループ各社も照明の LED 化や昇降機の間引き運転などで「休業せずに節電目標を達成できる」とした。 一方、復興財源に消費増税をあてることに対しては「まず税金ありきでは消費が完全に萎縮してしまう」と反対の姿勢を示した。 (斎藤徳彦、asahi = 5-7-11)
4 月の都区部の消費者物価指数、2 年 1 カ月ぶりプラス
総務省が 28 日発表した東京都区部の 4 月の消費者物価指数(中旬速報値)は生鮮食品を除く総合で 99.0 となり、前年同月比 0.2% 上昇した。 プラスになるのは 09 年 3 月以来 2 年 1 カ月ぶり。 昨年 4 月から始まり、2010 年度の物価を押し下げていた高校授業料無償化の影響がなくなったことが反映した。 エネルギー価格の高騰も影響した。 (asahi = 4-28-11)
夏のオフィスは北海道へ 東京で募集 涼しく停電知らず
北海道倶知安町の倶知安観光協会はこの夏、国際的なスキーリゾート地の比羅夫地区のリゾートマンション(コンドミニアム)や別荘を、電力不足が心配されている首都圏の企業にオフィス用として提供する計画を進めている。 「クーラーいらずで停電知らず。 夏のオフィスは涼しい北海道へどうぞ。」と呼びかけている。
マンションや別荘の多くはニセコでスキーを楽しむオーストラリア人や華僑の所有。 夏の間は安値で避暑用に貸し出しており、敷金や礼金はいらない。 光ファイバーケーブルを備え、居住空間も広く、家電製品も備えている。 机やいす、コピー機など事務機器や車が必要な場合は、同協会がレンタルをあっせんする。 部屋代は光熱費込み、2 ベッドルームタイプで月額約 21 万円から。 長期利用だと 3 カ月目以降は月 11 万円ほどに値引く。 現時点で約 30 室を確保している。
比羅夫地区は、新千歳空港・札幌からそれぞれ約 2 時間かかり、営業部門など人の動きを伴う部門には不向きだが、出版企画、デザイン、プログラム開発など IT 関連、翻訳などノートパソコンで仕事ができる小規模な企業には適しているという。 倶知安の夏の平均最高気温は 7 月で 24.1 度、8 月で 25.2 度と東京よりも約 5 度低く、クーラーはいらない。
長期滞在ができる団塊世代も募集する。 同協会は「電力不足に悩む首都圏企業に対する支援も震災支援の一環。 こちらも震災の影響で観光客が落ち込んでおり、新しい需要を開拓したい。」と期待している。 27 日午後 2 時から、東京都千代田区の外国人記者クラブで、IT 企業関係者向けに説明会も開く。 問い合わせは同協会 (0136・22・3344) へ。 (asahi = 4-22-11)
ディズニーシー 28 日に再開 ランドは 23 日から夜間も
千葉県浦安市の東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドは 20 日、東日本大震災の影響で休業中の東京ディズニーシーの営業を 28 日に再開すると発表した。 従業員の出勤体制などが整ったためで、来場者が多いゴールデンウイークに間に合った。 東京ディズニーランドは、入園料を値上げする 23 日から夜間営業を始め、「エレクトリカルパレード」も復活させる。
東京ディズニーシーの開園時間は午前 9 時 - 午後 10 時で、ほぼ通常の営業時間になる。 休業するアトラクションはないが、今月から始める予定だった開園 10 周年イベントは延期する。 ディズニーランド、シーいずれも 1 日券は大人 6,200 円に値上げされる。 15 日に営業を再開した東京ディズニーランドの開園時間は午前 8 時 ^ 午後 10 時となる。 パレードは多くの電飾を使うが、同社広報部は「深夜に充電しているので、ピーク電力には影響しない」としている。 (asahi = 4-20-11)
◇ ◇ ◇
東京ディズニーランド、15 日に再開 夜間営業は自粛
東日本大震災で休園中の東京ディズニーランド(千葉県浦安市)が 15 日に営業を再開する。 運営するオリエンタルランドが 12 日に発表した。 計画停電が終了し電力の安定供給が可能となったため。 節電に考慮して夜間の営業は自粛する。
当面の営業時間は午前 8 時から午後 6 時。 料金は通常通りで、1 日券は大人 5,800 円、中学・高校生 5 千円、幼児・小学生 3,900 円。 23 日からは、昨年 12 月に発表した値上げを予定通りに行い、大人 6,200 円、中学・高校生 5,300 円、幼児・小学生 4,100 円となる。
直営のディズニーアンバサダーホテルと東京ディズニーランドホテルは 15 日、シルク・ドゥ・ソレイユシアター東京は 23 日にそれぞれ再開する。 休園中の東京ディズニーシーとホテルミラコスタは、大型連休前にも営業を再開したい考え。 照明や噴水、空調などの使用を抑えて節電に取り組み、電力の供給状況を見極めた上で、夜間営業の再開も検討する。 園内に大型のガス自家発電機を建設することも検討しており、完成後は全体の消費電力の 7 割程度をまかなう計画だ。
再開日の 4 月 15 日は、83 年のディズニーランド開業日に当たる。 JTB の 3 月の国内から関東への旅行予約数が前年同期の 4 割に激減するなど、旅行業界からも再開を望む声が高まっていた。 (asahi = 4-12-11)
「世界のベスト 50」に東京・南青山と六本木の料理店
イタリアのミネラルウオーター・メーカー、サンペレグリノが後援する「世界のベスト・レストラン 50」が 18 日にロンドンで発表され、東京・南青山のフランス料理店「レ・クレアシヨン・ド・ナリサワ」が 12 位、六本木の日本料理店「龍吟(りゅうぎん)」が 20 位に入った。
ナリサワは昨年の 24 位に続いて 3 年連続のランクインで、アジアのトップだった。 龍吟は昨年の 48 位に続いて 2 年連続で選ばれた。 1 位はデンマークにある北欧料理店「ノーマ」で、2 年連続となった。 ベスト・レストラン 50 の発表は今年で 10 年目。 世界各国の料理評論家やシェフなど約 800 人が過去 1 年半以内に訪れた店に投票して順位を決める。 (asahi = 4-19-11)
大阪のレンタルオフィス「満室」 首都圏から移転需要
大阪市中心部で「レンタルオフィス」と呼ばれる短期契約の簡易型オフィスが引っ張りだこだ。 東日本大震災の影響で、東京など首都圏から本社や中枢機能を移す需要が高まっているためだ。 レンタルオフィスは、月単位で事務スペースを借りることができ、契約の翌日から入居が可能。 「手軽さ」と「便利さ」が売りで、家具や IT 設備も完備し、共有の会議室なども必要に応じて借りられる。
全国展開する大手のサーブコープジャパン(東京・新宿)は、大阪市内 3 カ所で、10 人程度が入れる事務スペースをそれぞれ数十単位で確保し、貸し出している。 大阪・心斎橋と江戸堀のオフィスは震災前は 7 割を切る稼働率だったが、震災後は「全く空きがない状況(小川紅葉〈くれは〉・日本シニアマネージャー)」という。
借り手の中心は、外資や海外の政府機関。 ふつうは 1 社あたり数十人規模だが、「100 人を超すような規模での問い合わせも受けている。(同)」 首都圏などで今夏予想されている大幅な電力不足の問題を受けて、3 カ月間の短期契約を変更し、6 月以降も延長する申し込みが増えているという。
大阪市内に 2 カ所のレンタルオフィスを展開する日本リージャス(東京・新宿)も移転需要の増加を受け、震災前は会議室として運営していた部分を事務スペースに変えるなどして対応。 貸し出しができる面積を 1.7 倍以上に増やしたという。 ただ、こうした「移転」の動きは一時的なものにとどまっている模様で、通常のオフィスビルの空室率は依然として高い水準だ。 (佐藤亜季、asahi = 4-13-11)
◇ ◇ ◇
関西のホテル、3 連休「満室」 関東の客や企業から予約
19 日からの 3 連休、関西のホテルで「満室状態」が相次いでいる。 予約客には東北・関東からの被災者や、拠点を関西に移す企業の社員らの姿が目立つという。
JR 京都駅と直結するホテルグランヴィア京都は、震災直後に観光客らのキャンセルが続いたが、その後、東北、関東からの予約客が増え、連休中は満室になった。 担当者は「特に関東からの予約が多い。 被害の少なかった関西で連休を過ごそうという方が多いのでは。」とみている。
大阪・梅田の大阪第一ホテルでは、東京電力による計画停電が実施されている関東を離れ、関西に活動の拠点を移す企業十数社から予約が相次いだ。 50 室近い部屋をおさえる企業もあった。 梅田の大阪新阪急ホテルは、3 連休を関西で過ごす予定だった観光客に加え、外資系企業からまとまった数の予約が入り、空室がない状態という。 (asahi = 3-19-11)
パンダ、3 年ぶりにお目見え 上野動物園
東日本大地震による一連の影響により、3 月 17 日から休園していた恩賜上野動物園(東京都台東区)は 1 日から、再開園と併せ、2 月 21 日に中国から来日した 2 頭のジャイアントパンダの一般公開を始めた。 上野動物園でジャイアントパンダが公開されるのは、リンリンが死亡した 08 年以来 3 年ぶり。 公開初日には約 2 万 2 千人が来園し、パンダの愛らしい姿などを楽しんだ。
1 日、午前 10 時の開園に先立ち、午前 9 時 30 分ごろにそれぞれの屋外放飼場に姿を見せたメスのシンシンとオスのリーリーは、多くの報道陣を前にしても動じることなく動き回り、家族連れが放飼場前に二重、二重の人垣を作っても、来園者の目の前で堂々と竹をほおばった。
同日は晴天だったこともあり多くの家族連れでにぎわった。 埼玉県草加市から祖父に連れられて来たという小学生の女の子は、「パンダは大きくて、テレビで見るよりもかわいかった」と笑顔をはじけさせた。 上野動物園によると同園の入園者数は、震災直後の週末である 3 月 12、13 日は 4,563 人、6,354 人と例年の 4 分の 1 程度に落ち込んだが、パンダ公開後初の週末となった 4 月 2、3 日は、2 万 6,214 人、2 万 7,223 人と例年並みの入園者数まで回復したという。
同園では 10 日まで被災者の入園料を無料とするほか、東京都内への避難者を対象に専用バスでの無料招待も実施。 東京都では、多摩動物公園、葛西臨海水族館、井の頭自然文化園でも 10 日までの期間、被災者の入園料を無料にする。 (情報提供 : 観光経済新聞社、サーチナ = 4-8-11)
◇ ◇ ◇
上野動物園のパンダ、地震で一般公開延期
東京都は 16 日、上野動物園(台東区)で 22 日から予定していたジャイアントパンダ 2 頭の一般公開を延期すると発表した。 新たな公開時期は未定。 東日本巨大地震の余震などが続く中、「多数の来園者の安全を確保できない」という理由で、同園や多摩動物公園、葛西臨海水族園、井の頭自然文化園の計 4 園は 17 日から当面の間、休園する。
2 頭は今年 2 月、中国から上野動物園に来園。 公募でオスはリーリー(力力)、メスはシンシン(真真)という日本名がつき、同園では約 3 年ぶりの一般公開となる予定だった。 今月 11 日に都内で震度 5 強の地震が発生した際、リーリーは少し落ち着かない様子を見せたというが、現在は 2 頭とも元気な様子で、都は「できる限り早く公開したい」としている。 (yomiuri = 3-16-11)
◇ ◇ ◇
パンダ歓迎大使に大橋のぞみさん 公式キャラも発表
約 3 年ぶりにジャイアントパンダを迎えた上野動物園(東京都台東区)で 26 日、「うえのパンダ歓迎大使任命式」が開かれ、タレント大橋のぞみさんが「歓迎大使」に任命された。 小宮輝之園長は来日した 2 頭の近況について「順調に環境になじんでいる」と報告した。
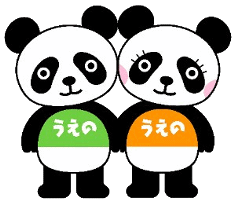
任命式は上野観光連盟などで構成する「うえのパンダ歓迎実行委員会」が主催。 小宮園長から「任命証」を授与された大橋さんは「多くの方にパンダを見てほしい。 私も一日も早く見たい。」と話した。 パンダ好きという大橋さんは、さっそく小宮園長に「パンダはおっとりしているけど、走るんですか?」と質問。 園長から「野生のパンダは、山で知らない動物に出くわすと走って逃げる。 速いですよ。」と教わり、「へーっ」と驚いていた。
小宮園長は、21 日夜に到着した雄の比力(ビーリー)と雌の仙女(シィエンニュ)の近況について「日本の竹を気に入ってくれて、食欲旺盛。 1 日 10 キロ以上もふんをしている。 ニンジンやリンゴも食べる。」と説明。 比力は到着した夜こそ「そわそわして」動き回ったが、翌日から落ち着いたという。
一方、仙女は「ずっと、どーんと構えている感じ。」 今は飼育舎の別々の部屋で暮らしているが「ともに落ち着いている。 近いうちに同居させることができるかもしれない。 そうなると繁殖への期待も高まる。」と話した。
◇
式では実行委が作った公式キャラクター「うえのパンダ」も発表された。 上野の繁華街の至るところにうえのパンダの旗が掲げられ、関連グッズも今後発売される。 このキャラクターは、もともとは 2009 年 10 月に上野観光連盟が始めたキャンペーン「うえのにパンダを!」のバッジに描かれていたもの。 08 年 4 月にリンリンが死んで上野動物園のパンダがいなくなって以来、「上野振興のためパンダ復活を」と運動を進めたシンボルだ。
観光連盟では地元の小学校や幼稚園の子どもたちにバッジを配り、パンダの絵や「うえのどうぶつえんにまたきたらいいな」とメッセージを書いてもらった。 色紙 65 枚と模造紙 3 枚を 09 年 11 月、石原慎太郎都知事に見せ、パンダ復活を要望したという。 石原知事は当時、中国に支払う高額なレンタル料に難色を示していたが、10 年 2 月にパンダ借り受けを決め、「地元から強い要望があった」と説明した。 記者会見で「どこからの要望か」と聞かれ、「幼稚園」と答えている。
実行委は「子どもたちの願いが通じたのでしょう」と考え、パンダ復活の願いを込めたバッジの絵柄をそのまま使い、文言を「うえのにパンダを!」から「うえのパンダ」に変えて、公式キャラクターに生かした。 26 日は、寄せ書きした区立忍岡小学校などの子どもたちが招かれ、大橋さんと記念写真に納まった。 (中川文如、asahi = 2-27-11)
歌舞伎座、伝統美残す化粧直し 外観デザイン発表

松竹は 5 日、現在建て替え中の歌舞伎座(東京・銀座)の外観デザインを発表した。 劇場は第 4 期 (1950 - 2010) の建物とほぼ同じデザインにし、背後に立つ地上 29 階建ての高層オフィスビルは、劇場正面側の壁面に日本建築の様式を採り入れ、伝統を損なわない陰影ある外観にするという。 新しい歌舞伎座は 13 年春に完成する予定。
共同設計者の隈研吾さんは「高層ビルは、歌舞伎座を引き立てるため、日本建築で捻子連子(ねりこれんじ)と呼ばれるような、縦線を強調したデザインをモチーフとする壁面にした。 ビルを 35 メートル後ろに下げて、劇場には屋上日本庭園を設け、憩いの場とする」と話した。 また、松竹の大谷信義会長は、災害時には帰宅困難者 3 千人を収容する場として劇場を提供したいと語った。 (asahi = 4-6-11)
水の注文 10 - 20 倍 山梨の工場フル回転 心配は停電
被災地支援に加え、複数の都県の水道水から基準値を超える放射性ヨウ素が検出されたことなどからミネラルウオーターの需要が急速に高まっている。 日本ミネラルウオーター協会によると、山梨県は 2010 年には全国の生産数の約 3 割を占め、全国 1 位の生産数量を誇る。 県内に取水工場を置くメーカーは「被災地や消費者のため」と増産への取り組みに懸命だ。
「オーダーはふだんの 10 - 20 倍。 電話はひっきりなし。 とても対応できない。」 甲州市にミネラルウオーターの生産の主力工場を持つサーフビバレッジの常務取締役三尾秀幸さんは嘆く。
ミネラルウオーターの工場は東日本大震災の翌日から 24 時間のフル稼働。 それでも生産能力に限界があり、前年同期の約 1.8 倍ほどしか生産ができていない。 そのうえ、別のメーカーに委託しているペットボトルのキャップやラベルの生産工場が被災し、震災後入荷が少ない状態だ。 「綱渡り状態。 こんな状態が続けば死活問題。」とも。
北杜市白州町に工場があるサントリー。 震災後は前年同期比約 1.6 倍の増産体制だ。 広報担当者は「需要は被災地に限らず、全国的に高い」と話し、4 月は前年同月比 1.5 倍の生産を予定している。
また、同町にミネラルウオーターの主力工場を置くコカ・コーラ社の製品を作っている白州ヘルス飲料の工場でも、被災地向けの生産が続く。 節電のため、日中は 3 分の 1 ほど工場の電灯が消され、薄暗い。 同工場は 2 月末ごろから、夏の需要に向け、24 時間のフル稼働。 その中でも、消費者庁が、保存方法などを表示しない出荷を被災地向けに限って認めたことを受け、25 日までラベルを貼らないミネラルウオーターの生産も行った。 (asahi = 3-27-11)