新幹線 EX 予約、さくら・みずほ「圏外」に 不便と批判
携帯電話やパソコンから新幹線の切符が購入できる東海道・山陽新幹線の「エクスプレス (EX) 予約」サービスで、来春から一部の切符が買えなくなる。 手軽で便利と人気だが、ほかの JR とのサービス内容の提携が見送られたからだ。 JR 内部からも「乗客には不便なだけだ」と疑問の声が上がっている。
JR 品川駅(東京都港区)では 1 日平均で約 5 万 5 千人が新幹線を利用する。 平日朝、会社員らの多くがカードを改札機にかざし、次々と列車に乗り込む。 東海道・山陽新幹線の EX 予約の会員だ。
EX 予約は JR 東海が東海道区間で 2001 年に始め、06 年に JR 西日本が山陽区間に広げた。 携帯電話やパソコンから希望の座席を選んで購入でき、発車 6 分前まで無料で列車変更できる。 08 年にはカードが切符がわりになる「EX-IC」を始め、乗車 3 日前までに予約すれば特別割引もある。 景気が悪化する中、出張が多い会社員らの人気を呼び、会員は東京、名古屋、大阪、福岡など沿線を中心に約 174 万人。 1 日約 9.6 万件の利用がある。
だが、EX 予約では来年 3 月 12 日に山陽新幹線から九州新幹線に乗り入れる「みずほ」と「さくら」の切符が買えない。 最速の「みずほ」は新大阪と鹿児島中央を今より 1 時間 17 分短縮して3 時間 45 分で結ぶ目玉列車だ。
「のぞみ」、「ひかり」、「こだま」なら博多までの切符は買えるが、博多から先は買えない。 それだけでなく、新大阪 - 博多間で予約していた「のぞみ」、「ひかり」、「こだま」から列車を変更する場合、「みずほ」や「さくら」が都合のいい時間に走っていても、変更はできない。
山陽・九州の乗り入れを前に、JR 西日本はネット予約サービス「e5489 (イーゴヨヤク) plus (プラス)」を拡充した「e5489」の開始を決定。 自社管内だけだった新幹線の予約範囲を新たに九州まで広げると決めたが、EX 予約との提携は見送られたからだ。
携帯電話を使う JR 東日本の「モバイル Suica」が「みずほ」や「さくら」を利用できないのも、EX 予約としか提携していないのが理由。 JR 東は「こちらから JR 東海に『九州まで延ばして』とは言えない」と弁明する。 ネット掲示板では「不便だ」、「時代に逆行している」など、JR への批判の声があふれている。
ただ、JR 西の EX 予約会員(約 36 万人)の場合、すべてが e5489 plus の会員にもなっており、来春からの e5489 なら「みずほ」も「さくら」も利用できる。 JR 九州の「列車予約サービス」も、九州と山陽だけでなく、東海道新幹線も従来通り切符が買える予定だ。
だが、EX 予約やモバイル Suica の会員が JR 西や九州の会員サービスを利用して「みずほ」や「さくら」を利用しようとしても、EX 予約などが「売り物」にするチケットレスサービスは使えず、乗換駅の窓口で切符を改めて受け取らなくてはならない。
JR 東海は「安全で確実な直通運転をするのが最優先。 ネット予約サービスの提携は落ち着いた段階で前向きに考えたい」と説明。 JR 西も「費用のかかるシステム改修を JR 東海にお願いするのは難しい」と話す。 その上で、両社とも「『乗客にとって不便』との指摘は理解できる」として、駅窓口で購入できる割引切符を案内するなどしていくという。 (宮嶋加菜子、小林誠一、asahi = 12-20-10)
次の本命? ホンダ、PHV と EV を国内初公開
ホンダは 20 日、外部から充電できるプラグインハイブリッド車 (PHV) と、電気自動車 (EV) の試作車を国内で初公開した。 PHV は電気モーターとエンジンで走るハイブリッド車 (HV) の一種で、モーターで走る時間がより長く、EV に近い。 ホンダは PHV と EV を 2012 年に発売する。
PHV は中型セダンの「インスパイア」をもとに製造した。 排気量 2 リットルのエンジンに二つの電気モーターを搭載。 電池大手ジーエス・ユアサコーポレーションとの合弁会社が製造する、大容量のリチウムイオン電池を使う。 モーターだけで約 25 キロ走行でき、モーターとエンジンを併用すると 1 千キロほど走れる。 EV は小型車「フィット」を改造したもので、モーターだけで 160 キロ以上走れる。 東芝のリチウムイオン電池を使う。 (asahi = 12-20-10)
日産と三菱自、「軽」開発の合弁検討へ
日産自動車と三菱自動車は 14 日、日本市場向けの軽自動車の開発を手がける、合弁会社の設立の検討を始める、と発表した。 また、三菱自のタイ工場で日産のピックアップトラック「ナバラ」を生産するとともに、将来的には 1 トンクラスのピックアップトラックの開発も共同で行う方針。
OEM (相手先ブランドによる生産)供給の拡大にも着手。 日産からは国内向けに小型商用車を供給。 三菱自から日産へは中東市場向けの SUV (多目的スポーツ車)を供給する。 (asahi = 12-14-10)
車内照明に新幹線表示板 … 鉄道も LED 化進行中

省エネで店やオフィスに発光ダイオード (LED) が普及するなか、鉄道の車両や案内表示にも LED を使う動きが本格化してきた。 阪急電鉄は 8 日、すべての車内照明に LED を使った車両を新たに神戸線に投入すると発表。 車両以外でも新幹線表示板で列車ごとに色分けする取り組みも来春には新大阪駅で始まる。
阪急は神戸線に外側の前照灯(ヘッドライト)以外、運転席や車内のすべての照明に LED を採用した車両(8 両 1 編成)を投入、今月 17 日から運転を開始する。 車両の代替に合わせて、日立製作所と共同開発。 オール LED 照明の車両は阪急電鉄では初めての導入で、全国の大手私鉄でも珍しいという。 今後も代替ごとに LED 化車両の導入を進めていく。
従来の蛍光灯より消費電力が 2 割少なく、これまで 1 年半だった寿命は 10 年以上に長期化。 初期投資はかかっても省エネや環境配慮をアピールでき、交換する頻度や手間を考えて採用に踏み切った。
一方、来年 3 月 12 日から山陽・九州新幹線の直通運転が始まる新大阪駅。 JR 東海では、改札口の発車の案内表示の照明に、どんな色も表現できる LED を使って、新たに投入される新大阪 - 鹿児島中央を最速 3 時間 45 分で結ぶ「みずほ」をオレンジ、みずほより停車駅の多い「さくら」をピンクで表示する。 これまでは、のぞみが黄、ひかりが赤、こだまが青だった。 (佐藤亜季、asahi = 12-13-10)
日産 EV 「リーフ」、一番乗りは米の IT 起業家
【サンフランシスコ = 山川一基】 日産自動車は 11 日、米国で電気自動車 (EV) 「リーフ」の販売を始めた。 普通乗用車クラスの EV 量販は世界初となる。 連邦政府や州からの補助金を差し引くと実質的な負担額が地域によっては 100 万円台となる大手メーカー車の登場で、EV の普及が一気に進むか注目される。
リーフ第 1 号を手に入れたのはサンフランシスコ市近郊に住むIT起業家のオリビエ・シャルイさん (31)。 同市役所前で開かれた販売開始イベントに臨み、1 回の充電で約 160 キロは走るリーフについて「とても静かで快適。 日々の通勤にはこれで十分だ。 それを超える長距離運転なんて 3 年に 1 度くらいしかない。」と購入理由を語った。
リーフの米国での販売価格は 3 万 2,780 ドル(約 275 万円)から。 米連邦政府やカリフォルニア州からの補助を差し引くと、実質的な負担額は最低 2 万 280 ドル(約 170 万円)となる。 リーフは米国での予約分 2 万台、日本での 6 千台すべてが埋まっており、来年前半に受注を再開する予定。 (asahi = 12-13-10)
◇ ◇ ◇
GM の電気自動車「ボルト」、日本向け販売を検討

米ゼネラル・モーターズ GM) が、補助発電機がついた電気自動車 (EV) 「シボレー・ボルト」の日本での販売を検討している。 日本市場での主な輸入 EV は米テスラ社製で、約 1,300 万円と高額だが、GM の EV は大幅に安くなる可能性が高い。 日本勢の EV と同等の価格となり、販売競争が激しくなりそうだ。 GM はボルトを 4 万 1 千ドル(約 340 万円)で年内に米国で発売し、来年後半に中国でも発売する。
日本では、GM 日本法人が来年に数台を試験的に輸入し、社用車として使うなどして日本の交通状況に合うかどうかを調べる。 その後、ハンドルの位置を右に変えるなど仕様を日本向けに一部変更し、早期に一般向けに販売することを検討している。 日本法人の石井澄人社長は「日本でも『ボルト』を求める声があり、販売を実現させたい」と話す。
ボルトは電池に充電された電気でモーターを回して走行し、充電分の電気がなくなると、ガソリンエンジンで発電しながら走行する。 日本では、国内の自動車大手が相次いで EV に参入。 三菱自動車が軽自動車「アイミーブ(398 万円)」を販売しているほか、日産自動車も年内に「リーフ(376 万円)」を発売する。 トヨタ自動車とホンダも 2012 年に発売する予定だ。 (金井和之、asahi = 11-20-10)
全日空がつくる格安航空、本社は関空へ
全日本空輸が設立する格安航空会社 (LCC) の本社が関西空港島に置かれる見通しとなった。 関空のビルには空き室も目立ち、関西国際空港会社の業績にも好影響を与えそうだ。 関係者が 10 日、明らかにした。
全日空は来年 1 月上旬にも LCC を正式に設立し、社名や新社長、人員などの体制を発表する。 このうち、本社について東京都内での設置も検討したが、効率的に業務をこなしてコスト削減を図るために空港内に置いた方がいいと判断したとみられる。 現在、賃貸料や使用面積について関空会社と交渉に入っている。
関空会社は、LCC 専用のターミナルを 2 期島内に建設する予定。 このため LCC の本社も 2 期島に近い 1 期島の北側のビルで調整しているとみられる。 全日空によると、2011 年度の後半に関空を拠点とした路線網でスタート。 当初は小型機 5 機ほどで始め、14 年ごろには 15 - 20 機を使い、年間約 600 万人の利用客を見込んでいる。 本社機能も就航路線や便数と共に拡充していく方針だ。 (asahi = 12-11-10)
線路の雪を車両カメラで監視 東海道新幹線、遅れ防止
JR 東海は今冬から、雪による列車の遅れを減らすため、線路内の雪を監視する新システムを本格導入する。 東海道新幹線の N700 系車両の下部にカメラを取り付け、走行時の雪の舞い上がりを監視する。 映像をもとに速度規制解除の判断を早める。
高速走行すると線路の雪が舞い上がり、車両下部に雪の塊が付着。 その塊が落ちて敷石をはじくと車両破損につながる。 このため積雪時に速度を規制するが、走行中は雪の舞い上がりを直接確認する方法がなく、規制解除の判断を遅らせる要因になっていた。
雪が多い岐阜羽島 - 京都間では、線路側にもカメラを設置する。 JR 東海は、新システムの導入によって、雪による列車の遅れが平均 1 - 2 分短くなるとみている。 2009 年度の東海道新幹線の雪による遅れは平均 2.8 分で、30 分以上の遅れも 213 本にあった。 (信原一貴、asahi = 12-6-10)
開業初日でも午後には空席 … 東北新幹線、今後に課題
4 日、東京 - 新青森の全線が開業した東北新幹線は始発こそほぼ埋まったものの、午後は空席も目立った。 初日の乗車状況はまとまっていないが、JR 東日本によると、11 月下旬時点の下り「はやて」の初日の予約は 6 割程度で、列車によっては 3 割に満たないものもあったという。 経済効果に期待がかかる一方で、課題は大きい。
初日は強風でダイヤも乱れた。 4 日午後 5 時半、3 時間遅れで新青森駅に着いた列車で里帰りした横浜市の女性 (77) は「6 時間もかかっては新幹線の意味がない ・・・。」 途中の仙台などで多くの乗客が降り、新青森到着時は約半数の席が空いていた。
下北半島や十和田湖への玄関口、七戸十和田駅(青森県七戸町)で降りる観光客もまばらで、地元のタクシー運転手の女性 (43) がこの日乗せた県外観光客は 1 組。 十和田湖方面行きのバスでも、乗客が 1 組しかいない便があったという。 青森市が造成した新青森駅前には広大な空き地が広がる。 小売店はコンビニ 1 軒だけ。 同駅に観光客が集まり過ぎると約 4 キロ離れた中心街がさびれるとして大型商業施設を規制しているためだ。
青森県が 2008 年に公表した需要予測では、県と首都圏を往来する人は 05 年の 152 万人から 12 年に 181 万人に増えるとされるが、達成は微妙だ。 延伸事業に 1,850 億円負担した青森県は今後、年 100 億円超の返済が続き、県自身が「新幹線は高い買い物」と認める。 JR 東日本の幹部は「ビジネス需要と京都のような観光名所を併せ持つ東海道新幹線とは性格が違う。 まだ注目されていない東北ならではの魅力を発掘する必要がある。」と話す。 (asahi = 12-5-10)
◇ ◇ ◇
一番列車、15 分遅れで東京着 東北新幹線全線開業
東北新幹線は 4 日、八戸(青森県八戸市)から新青森(青森市)まで延伸し、全線開業した。 東京 - 新青森は最速 3 時間 20 分で結ばれ、これまでより 39 分短縮された。 当面は現行の「はやて」だけだが、来年 3 月 5 日に走り始める新型車両「E5 系」の「はやぶさ」は最高時速 300 キロで、さらに 10 分短縮する。
東京駅からは新青森行き始発「はやて 11 号」が午前 6 時 28 分に定刻通り出発。 出発式で JR 東日本の大塚陸毅会長は、大宮 - 盛岡の暫定開業から 28 年かかったことに触れながら「一歩ずつ延びてようやく全通した。 来年 3 月には青森と鹿児島が新幹線でつながる。 高速鉄道で地域活性化に貢献したい。」と話した。
一方、新青森駅から定刻の同 6 時 31 分にほぼ満員で出発した東京行き「はやて 12 号」は、盛岡駅での秋田新幹線との連結作業でトラブルがあり、東京駅には 15 分遅れの同 10 時 6 分に到着した。
東北新幹線は 4 日午前 11 時 14 分、郡山 - 福島間の風速計が規制値(秒速 30 メートル以上)を超え、秋田、山形新幹線とともに東京 - 盛岡間で運転を見合わせていたが、午後 1 時 11 分に運転を再開した。 上下 8 本が運休し、22 本に遅れが出て約 1 万 7 千人に影響が出た。 (asahi = 12-4-10)
車の「横滑り防止装置」義務化へ 国交省、まずは新車で
カーブや雨の道で自動車がスリップしそうになるのを防ぐ「横滑り防止装置 (ESC)」が、すべての新車の乗用車につくようになる。 センターラインをはみ出して衝突するなど横滑りによる交通事故が多いため、国土交通省が自動車メーカーに装着を義務づける方針を固めた。
まず、2012 年 10 月以降に全面改良(フルモデルチェンジ)して発売する新型車に義務づける。 既存車種も 14 年 10 月以降には装備に追加する必要がある。 軽自動車は設計変更に手間がかかるため、新型車が 14 年 10 月以降、それ以外は 18 年 2 月以降とする。 ESC は 1990 年代半ばに実用化された。
センサーがタイヤの回転数やハンドルの角度、車の向きなどを監視し、タイヤが滑りそうになると、エンジンの回転数を落としたり、自動でブレーキをかけたりして車の動きを修正する。 ESC 装着で、カーブを曲がりきれなかったり、雨道でスリップしたりする事故を防ぎやすくなり、交通事故の発生率が 3 割ほど下がるという試算もある。 ただ、装置をつけるには 5 万 - 10 万円のコストがかかり、価格も上がるため、国内の新車の装着率は 1 - 2 割にとどまっている。
高速走行が多い欧米では義務化を決めている国が多く、11 - 12 年ごろから適用される。 ドイツではすでに新車の 8 割についているという。 装着は世界的な流れになりつつあり、国交省は日本も装着の義務化が必要と判断した。 (西村宏治、asahi = 12-4-10)
中国の新幹線、時速 486 キロを記録 営業用の世界最高
【北京 = 小山謙太郎】 中国鉄道省が北京 - 上海間で建設している新幹線で 3 日、試験走行があり、鉄輪式の営業用車両としては、世界最高速度の時速 486.1 キロを記録した。 中国中央テレビなどが伝えた。
この路線は来年、営業開始の予定で、北京市と上海市を最短 4 時間で結ぶ。 最高速度を記録したのは国産の新型車両 CRH380A。 JR 東日本の東北新幹線「はやて」などで使われる E2 系の技術を基礎に、独自開発したとされる。 日本国内の営業用車両の試験での最高速度は、2003 年に上越新幹線で E2 系が記録した 362 キロ。 鉄輪式の実験用列車の世界最高記録は仏 TGV の 574.8 キロ。 (asahi = 12-3-10)
◇ ◇ ◇
時速 500 キロ列車、中国が開発着手 実現なら世界最速
【広州 = 小林哲】 新華社通信によると、中国が時速 500 キロ以上のスピードで走る超高速列車の研究開発を始めた。 実際に乗客を運ぶ列車が実現すれば、営業運転で中国の高速鉄道がもつ世界最高の同 350 キロを大幅に上回るスーパー列車が登場することになる。
中国鉄道省の何華武・首席エンジニアが 18 日、湖北省であった国際フォーラムで明らかにした。 今年 9 月、中国が独自開発したとしている次世代高速列車が、上海 - 杭州(浙江省)間の試運転で時速 416.6 キロを達成。 同氏によると、さらに性能を高めた時速 400 - 500 キロで走る超高速列車の開発がすでに始まっており、500 キロ以上で走った際の振動制御の研究などが進んでいる。
中国の高速列車は、もともと日本や欧州の技術移転を受けて開発された。 9 月末現在で同国内の高速鉄道網は 7 千キロを超え、2020 年までに日本の新幹線網の 8 倍近い 1 万 6 千キロを整備する計画がある。 海外輸出にも力を入れており、超高速列車の開発で中国の鉄道技術の高さをアピールする狙いもありそうだ。 (asahi = 10-21-10)
新型ヴィッツ、ガソリン車最高の燃費 26.5 キロ実現
トヨタ自動車は 2 日、12 月下旬に全面改良して発売する小型車「ヴィッツ」の燃費が、ガソリン 1 リットルあたり 26.5km と発表した。 軽自動車を除くガソリン車では、日産自動車の「マーチ」の 26.0km を抜き、最も低燃費という。 エンジンの改良や車体の軽量化、信号待ちなどの停止時にエンジンが自動停止する「アイドリングストップ機能」の搭載で低燃費を実現した。 (asahi = 12-3-10)
トヨタ、インドで新興国向け小型車発売 最安値 89 万円
【バンガロール(インド南部) = 久保智】 トヨタ自動車は 1 日、新興国向けに新たに開発した小型車「エティオス」をインドで発売した。 排気量 1.5 リットルのセダン型で、最低価格は 49.6 万ルピー(約 89 万円)。 現地でのトヨタ車としては最安値だ。 急成長するインドの小型車市場で巻き返しを狙う。
ハッチバック型(排気量 1.2 リットル)の発売は 2011 年 4 月で、価格は 40 万ルピー半ばの見込み。 販売目標は合わせて年 7 万台。 同日から注文を受け付け、生産は 12 月末からバンガロール近郊に建設したインド第 2 工場で始める。 来年には、インドで一般的なディーゼル車も発売。 将来は輸出も計画している。
トヨタは低価格車の発売で出遅れ、新興国市場のシェアが伸び悩んでいる。 12 年以降は、中国やブラジル、タイなどでも低価格の小型車を投入する計画で、エティオスはトヨタの新興国戦略の先行きを占う試金石にもなる。 (asahi = 12-1-10)
◇ ◇ ◇
ホンダ、インドやタイ向け低価格車を発表 出遅れ挽回へ
【バンコク = 高野弦】 ホンダは 11 月 30 日、アジアの新興国向けに開発した小型の低価格車「Brio (ブリオ)」の試作車を発表した。 価格はインド向けの仕様で 90 万円以下に設定する。 市場全体が大きく伸びる中で、100 万円を切る車がなかった同社は巻き返しをはかる。
ブリオは排気量 1.2 リットル。 タイとインドで生産、タイでは 2011 年 3 月、インドでは同年中の発売開始を予定。 将来は周辺国に輸出する。 インド仕様の価格は、最も安いもので 50 万ルピー(約 90 万円)以下に抑え、タイ仕様は約 40 万バーツ(約 112 万円)を最低価格にする。
ホンダがこれまで、これらの地域で販売した車で最も安いのは、約 130 万円の「ジャズ(インド向け、排気量 1.2 リットル、日本名フィット)」。 スズキ、現代自動車などに続き、今年に入って、フォード、ゼネラル・モーターズなど米国勢も約 60 万円の小型車を投入し、販売台数を伸ばしている。 (asahi = 11-30-10)
ホンダ「フィット EV」、トヨタ「RAV4EV」を公開
【ロサンゼルス = 山川一基】 ホンダは 17 日、ロサンゼルス自動車ショーで、家庭用電源などから充電できる電気自動車 (EV) 「フィット EV」の試作車をメディア公開し、2012 年に日米で発売すると発表した。 ホンダが EV を発売するのは 15 年ぶり。 トヨタ自動車も、米自動車ベンチャーのテスラ・モーターズと共同開発したスポーツ用多目的車 (SUV) 「RAV4EV」を公開した。
フィット EV は現行の小型車フィットをベースに開発する。 ホンダはこれまでハイブリッド車 (HV) や燃料電池技術に力を入れてきた。 EV は 97 年に発売したことがある。 伊東孝紳社長は朝日新聞などの取材に「通勤用などに一定の需要が見込めるので EV もそろえておきたい」と語った。 価格は未定だが「競争力のある価格にしたい」という。 ホンダはガソリンエンジンと家庭用電源からの充電を併用するプラグイン HV も、2012 年に日米などに投入する。
トヨタの RAV4EV には、今年資本提携したテスラが、モーターやバッテリーなど主要駆動部品を供給する。 生産拠点や日本での発売計画、価格は未定だ。 日系メーカーでは、三菱自動車が EV 「アイミーブ(398万円、国の補助金 114 万円)」を販売。 日産自動車も今年 12 月に EV 「リーフ(376 万円、同 77 万円)」の販売を始める。 日本の大手 4 社の EV 計画がこれで出そろった。
ロサンゼルス自動車ショーは米 4 大自動車ショーの一つ。 米国内外の自動車メーカーなど約 80 社が環境対応車などを展示。 一般公開は 19 - 28 日。 (asahi = 11-18-10)
プリウス国内向け生産、来年から半減 補助金終了に対応
トヨタ自動車がハイブリッド車「プリウス」の国内向けの生産台数を来年 1 月から急激に減らすことが 17 日、分かった。 11 月の生産計画は月に約 3 万 1 千台だが、来年 1 月は半分の約 1 万 5 千台。 9 月にエコカー補助金が終了し、受注が一段落していることに対応する。 トヨタが主要部品メーカーに示した生産計画によると、12 月は約 2 万 3 千台に減らす。 来年 2 月は約 1 万 4 千台、3 月は約 1 万 3 千台と、順次減らす計画だ。
昨年 5 月に発売されたプリウスは、最低価格が 205 万円。 エコカー補助金の追い風を受け、一時は納車まで 9 カ月待ちの品薄状態になった。 国内の新車ランキングは 10 月まで 17 カ月連続首位。 ただ、現在は品薄状態も緩和され、2 - 3 週間程度で納車している販売店もある。
トヨタ系の販売関係者によると、プリウス以外の車種も含めた受注台数は現在、前年の同時期より 4 割少ない。 「その中でプリウスはまだ売れている方だが、ふつうの車並みになった」という。 (久保智、asahi = 11-18-10)
高速無料化で車の量倍増 実験 3 カ月平均、国交省発表
国土交通省は 12 日、全国 37 路線 50 区間の高速道路で実施している無料化の社会実験の結果を発表した。 スタートした 6 月後半から 9 月末までの約 3 カ月間の平均交通量は約 2 倍に増えたという。 高速道に車が流れ、並行する一般道の渋滞が解消したと成果を強調したが、一部の高速道で新たな渋滞も発生したという。
実験前と比べると、東九州道の西都 - 宮崎西は平日が 5.76 倍(8 月)、休日が 6.23 倍(同)に増えた。 山形道の庄内空港 - 酒田も休日が 4.18 倍(同)、東北中央道の山形上山 - 山形中央は平日が 4.83 倍(9 月)に増えた。
一方、50 区間のうち平日には約 1 割の区間、休日には約 2 割の区間で渋滞が起きた。 特に京都丹波道路の丹波 - 沓掛では実験開始後、ほぼ毎日発生するようになった。 他の交通機関への影響は「大きな変動はみられない」としたが、高速バスの旅客は前年同月比で減っている。 (asahi = 11-12-10)
日米路線、各連合一体でコスト減 米も独禁法適用除外
【ニューヨーク = 山川一基】 米運輸省は 10 日、日米路線における米独占禁止法の適用除外 (ATI) を認可したと発表した。 これを受け、日本航空が加盟する国際航空連合「ワンワールド」と、全日本空輸が加盟する「スターアライアンス」は来年初めにも、太平洋路線の運営をそれぞれ実質的に一体化する。
対象となるのはワンワールドの日航、米アメリカン航空の 2 社と、スターの全日空、米ユナイテッド航空、米コンチネンタル航空の 3 社。 日本の国土交通省は先月、両連合に日本の独禁法の適用除外を認可しているため、各社はこれで提携強化に踏み出せる。
両連合はそれぞれ、独禁法下では禁じられている路線運営と販売の一体化を進め、太平洋路線の収益をコスト負担などに応じて分配する方式に移る。 日航とアメリカン航空は 10 日、「よりよいサービスを提供するほか、一層の効率化とコスト削減を推進する」とコメントした。
利用者にとっては、競争が進むことで運賃の低下やサービスの向上が期待できる。 経営再建中の日航にとっては、ドル箱の太平洋路線で、アメリカンと利益やコストをどう分け合っていくのかが大きな経営判断となる。 (asahi = 11-11-10)
ビックカメラに電気自動車展示 三菱自と連携協定
電気自動車 (EV) を世界に先駆けて量産化した三菱自動車と、家電量販大手のビックカメラは 9 日、EV の普及に向けて連携する協定を結んだ。 EV 販売で自動車メーカーと家電量販店が手を組むのは初めて。 自動車が家電と同じ売り場で売られる時代が、一歩近づいたと言えそうだ。
連携の第一弾として、三菱自の EV 「アイミーブ」が、ビックの有楽町店本館(東京都千代田区)にお目見えした。 ビックはまず首都圏の 4 店でアイミーブを展示し、順次全国の店舗に広げる。 試乗会などのイベントも企画する。 購入を希望する客がいれば、ビックが三菱自の販売店に取り次ぐ。
協定調印式でビックの宮嶋宏幸社長は「EV は未来の乗り物という印象があるが、補助金は充実し充電環境も進んでいる。 より多くの人に知ってもらい販売増に貢献したい。」と述べた。 三菱自の益子修社長も「EV は充電、蓄電、給電など家電的な利用が可能で、業界を超えた協業が欠かせない」と強調した。 (asahi = 11-9-10)
スカイマーク、A380 で国際線参入へ 14 年度めど
スカイマークは 8 日、2014 年度をめどに国際線に参入する、と発表した。 エアバス社の総 2 階建て機「A380」 6 機を、国内の航空会社としては初めて購入する。 オープンスカイ(航空自由化)を機に、国際線への本格参入を目指す。 スカイマークの国際定期便が実現すれば、日本航空、全日本空輸に続き、国内で 3 社目となる。 日本の航空会社の国際線進出は 1986 年の全日空以来となる。 新規航空会社としては初。
スカイマークは、政府が米国と先月結んだオープンスカイ協定を、アジア諸国にも拡大する予定であることや、成田や羽田の首都圏空港の発着枠が 14 年度までに約 1.5 倍増えることから、決断した。
スカイマークは 1998 年に新規参入。 使用機体をボーイング社の 177 人乗りの小型機「737」だけにして運航や整備のコストを節約。 また、運賃を大手の半額程度に抑えて集客力を上げ、事業を拡大してきた。 2002 年から韓国やグアムに国際チャーター便を飛ばし、定期便に意欲を示していた。 就航路線は公表していないが、欧州線などを念頭に置いている模様。 経営再建中の日航や、国際線拡大中の全日空には脅威となる。
ただし、スカイマークは安全上のトラブルが相次ぎ、国土交通省から今年 4 月に業務改善勧告を受けている。 小型機に特化した運航態勢を短期間で超大型機に拡大して、問題が起きないか同省から厳しくチェックされる可能性がある。
A380 は、最大 800 席を設置できる世界最大の旅客機。 豪華な内装が特徴で、独ルフトハンザ航空など海外 3 社が成田空港に乗り入れている。 11 月、豪カンタス航空の同型機のエンジンが飛行中に破損。 運航を停止する事態となった。 (asahi = 11-8-10)
さよなら 181 系 国鉄時代のディーゼル特急はまかぜ

国鉄時代から 40 年にわたって全国の非電化区間を走り、大阪と鳥取を結ぶ特急「はまかぜ」の車両として活躍してきたディーゼル車両「キハ 181 系」が 6 日、定期運行から引退する日を迎えた。 午後 6 時すぎ、はまかぜが JR 大阪駅から出発すると、約 800 人の鉄道ファンらがラストランを見送った。 大出力のエンジンで力強く山間部を走る姿が人気で、はまかぜには 1982 年から起用された。
8 月に架け替えられた兵庫県香美町の余部橋梁(きょうりょう)を見下ろす展望台にもこの日、雄姿を収めようと多くの人がカメラを手に詰めかけた。 30 代の男性は「地味だが、戦後を代表する車両。 引退してしまうのはさみしい。」と話していた。 7 日からは、新型の「キハ 189 系」の車両がはまかぜに使われる。 (asahi = 11-6-10)
環境自動車税、12 年導入目指す 総務省、構想を公表
総務省は 2 日、自動車の保有にかかる自動車重量税や自動車税、軽自動車税を一本化して課税する「環境自動車税」構想を公表した。 2012 年の導入をめざし、導入以降に登録された新車から適用対象とするという。 現在は排気量と車体重量に応じて税額が決まるが、排気量と二酸化炭素 (CO2) 排出量を基準に改める。 小型車よりも税負担が軽い軽自動車は負担を引き上げ、格差を縮小するとしている。
総務省にとっては、国税である自動車重量税を地方税に衣替えして、地方自治体の財源を確保するねらいがある。 今後、政府税制調査会に提案するが、財務省や与党内での調整はまだついていない。 自動車業界は増税につながりかねないとして反発しており、議論は難航しそうだ。 (asahi = 11-3-10)
羽田からサンフランシスコへ復活一番機 国際定期便

羽田空港(東京都大田区)で 31 日、国際定期便が復活した。 1978 年の成田空港開港以降、羽田の国際線はチャーター便扱いだったため、定期便は 32 年ぶり。 羽田では 30 日深夜から、就航を祝う航空会社の式典が続いた。 冬ダイヤが始まった 31 日に定期便として就航するのはサンフランシスコやホノルル、ソウルなどの 11 都市。来年 2 月までにロンドンなど 6 都市が加わり、17 都市になる。
復活一番機は日本航空のサンフランシスコ行き。 午前 0 時 4 分に飛び立った。 日航が 54 年に国内初の国際定期便を就航したのも羽田発サンフランシスコ行きだった。 86 年に成田から国際定期便を始めた全日本空輸は、羽田初の国際定期便となるロサンゼルス行きが同 7 分に離陸した。
国際線ビルには 21 日のオープン以来、観光客も詰めかけている。 京急電鉄と東京モノレールの利用者は開業後 1 週間で計約 33 万人。 想定より平日は 2 倍、土日は 3 倍の人出だという。 国際定期便の予約も好調だ。 日航と全日空の 11 月の羽田発着の便は 75 - 80% が売れている。 (asahi = 10-31-10)
◇ ◇ ◇
羽田新国際線ターミナルオープン セレモニー相次ぐ
羽田空港(東京都大田区)の新しい国際線旅客ターミナルビルと 4 本目の滑走路(D 滑走路、2,500 メートル)が 21 日、オープンした。 ビルの出発・到着ゲートでは航空会社などのセレモニーが相次ぎ、本格的な再国際化を祝った。
午前 5 時 41 分、細かい雨が降る中、香港発の全日空便(乗客 202 人)が到着。 世界初の段差のない搭乗橋が機体に取り付けられ、客室乗務員らが「祝 羽田空港新国際線ターミナル初便」と書かれた横断幕で乗客を出迎えた。 31 日からは定期便の就航が始まり、来年 2 月までに海外 17 都市と結ばれる。 都心まで最速 13 分で結ぶ東京モノレールと京急電鉄の新駅も開業した。 (asahi = 10-21-10)
ハイブリッド、新車販売の 1 割に 09 年度
エコカーとして人気のハイブリッド車 (HV) が、新車市場の 1 割近くを占めたことが明らかになった。 日本自動車工業会によると、2009 年度の HV の国内出荷台数は 46 万 6,631 台で、前年度の 3.85 倍。 トヨタ自動車が「プリウス」を発売して 13 年。 HV は存在感を増している。
エンジンと電気モーターで走る HV は、トヨタが 1997 年に世界で初めて量産化し、99 年にはホンダも参入した。 HV の出荷台数は、2000 年度は 1 万 3 千台だったが、原油価格高騰などでエコカーへの関心が急速に高まり、10 年で 40 倍程度に拡大した。 09 年度は軽自動車も含めた新車全体の出荷台数(475 万台)の 1 割弱にあたる。
09 年にホンダが「インサイト」を 189 万円で売り出すと、プリウスも対抗して価格を下げるなど低価格化が進んだ。 最近では政府のエコカー補助金も普及を後押しした。 今月初めにはホンダが「フィットハイブリッド」を 159 万円で発売してさらに低価格に。 日産も「フーガハイブリッド」で 10 年ぶりに独自開発の HV を発売。 販売競争が激しくなっている。 (江渕崇、asahi = 10-31-10)
◇ ◇ ◇
日産が初の HV 本格投入 高級車フーガ、小型並み燃費に
日産自動車は 26 日、高級セダン「フーガ」にハイブリッド車 (HV) を追加すると発表した。 日産が国内で HV を売り出すのは、2000 年に「ティーノハイブリッド」を 100 台限定で販売して以来 10 年ぶりで、初の本格投入となる。

日産は電気自動車 (EV) を環境戦略の主軸に据えているが、普及に時間がかかるため、HV を積極投入することにした。 「フーガハイブリッド」は、ガソリン 1 リットルで 19 キロ走る。 燃費は同型のガソリン車の約 2 倍で、1.5 リットルのガソリンエンジン車並み。 (asahi = 10-26-10)
◇ ◇ ◇
フィット、主流はもう HV 受注の 7 割占める ホンダ
ホンダがハイブリッド車 (HV) を追加して 8 日発売した新型「フィット」の受注が、20 日時点で月間販売目標(1 万 4 千台)を超える 2 万 1 千台に達した。 このうち 71% が HV で、当初の 4 割程度という見込みを大きく上回っている。 全体の 4 割ほどが旧型のフィットからの買い替えだという。 (asahi = 10-21-10)
◇ ◇ ◇
プリウス特別仕様車発売へ 販売落ち込み、てこ入れ狙う
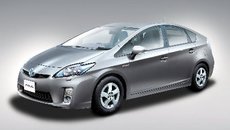
トヨタ自動車は 19 日、ハイブリッド車「プリウス」の特別仕様車を来月 1 日に発売すると発表した。 トヨタのハイブリッド車の国内累計販売が 7 月、100 万台を超えたことを記念したもの。 エコカー補助金の終了で落ち込む販売のてこ入れをねらう。
プリウスの「S」と「G」の 2 グレードの車をベースに、省電力・長寿命の LED (発光ダイオード)を使ったヘッドランプを装備。 シート表皮など内装も充実させた。 燃費はベース車と変わらず、ともに 1 リットル当たり 35.5 キロ。 価格は「S」の特別仕様車が、ベース車より 16 万円高い 236 万円、「G」は 31 万円高い 276 万円。
19 日には、ハイブリッド車「SAI」の LED ランプ付き特別仕様車を、ひと足早く発売した。 価格はベース車より 22 万円高い 360 万円。 エコカー補助金の終了に伴い、トヨタの 9 月の国内受注は、前年同月より約 4 割減った。 トヨタは、ミニバン 6 車種や高級セダン「マーク X」などの特別仕様車を発売。 ミニバンを買う際に純正カーナビゲーションを付けると、3 万円を現金還元するキャンペーンを展開するなど、販売の下支えに躍起だ。 (asahi = 10-19-10)

待ち合わせは列車眺めながら JR 大阪駅「時空の広場」
来春リニューアルされる JR 大阪駅の大屋根(東西約 180 メートル、南北約 100 メートル)の真下で、行き交う列車を一望できる「時空(とき)の広場」が 26 日、報道公開された。 広場は南北の駅ビルをつなぐ連絡通路の屋上部分にあり、JR 西日本によると、完成時にはオープンカフェが出店したり、週末にイベントが開催されたりする。 金と銀の二つの時計も置かれ、待ち合わせの名所にもなりそうだ。
駅北側に新築中の新北ビル(28 階建て)の 14 階にできる「天空の農園」も同時に公開された。 ここでは、ぶどうやハーブなど約 20 種類が栽培される予定で、駅構内のレストランで提供されることも検討されている。 (asahi = 10-27-10)