ベトナム、2016 年のアパレル輸出成長率は 8% と繊維公団が予測
2016 年のベトナムからの縫製製品輸出は 8% 増加し、輸出額は 295 億ドルから 300 億ドルに達するだろうとベトナム繊維公団 (Vinatex) の Hoang Ve Dung 副社長は予測する。 現在、ベトナムは世界のアパレル輸出上位 5 ヵ国のひとつであり、2015 年の縫製製品輸出額はおよそ 280 億ドルであった。 ベトナムからの縫製製品の輸出増加は、同国のさまざまな自由貿易協定の締結や国内での生産量増加に基づき予測されたものであると Ve Dung 副社長は最近行われたベトナムメディアとの会見で述べている。
2015 年、ベトナムから主要市場への縫製製品輸出は安定したペースで成長しており、成長率はそれぞれ米国 12.95%、EU 5.96%、日本 7.95%、韓国 8.77% であった。 繊維公団のグループ企業である Garment 10 Joint Stock Company、Phong Phu Textile and Garment Corporation、Viet Tien Garment Company、Hoa Tho Textile and Garment Joint Stock Corporation 等が輸出の伸びに貢献している。
繊維公団については、Tran Viet マーケティング部長は、同公団は 2015 年に 35 億米ドル相当を輸出しており、世界経済の低迷にもかかわらず、前年比 10% の成長であったと話す。 2015 年、繊維公団は株式化計画を完了し、複数の繊維事業への新規投資を行った。 これら事業により、2020 年までに完成品に占める国内原材料の割合が 65% まで上昇することが期待されていると Viet 部長は話す。 (DigimaNews = 1-5-16)
◇ ◇ ◇
「脱中国」が止まらないアパレル … 過去最多のストにはうんざり、ベトナム台頭許す大国の凋落
アパレル業界で世界の工場として大きな存在感を示したきた中国が、技術力をつけたベトナムやミャンマーといった東南アジア諸国に追い上げられている。 5 年ほど前に約 8 割を占めていた日本への中国からの衣料品の輸入額シェアは現在 60% 台と急減、米国の輸入シェアは 30% 台にまで低下したことが大和総研のレポートで明らかになった。 かねてより指摘されていた繊維製造の「脱中国」の動きが、データ上も裏付けられた形だ。
米国は 2010 年をピークに減少
生産コストの低さを武器に海外から企業を呼び込み、成長をとげてきた中国。 しかし、アパレル業界では、その勢いに陰りが見える。 大和総研が 12 月初旬に公表したレポートによると、2010 年の日本への中国からの輸入シェアは 80.5% を占め、圧倒的な強さを誇っていた。 しかし、翌 11 年以降、急激にシェアが落ち、14 年は 66.8% にまで縮小した。
これに対して、シェアの大きく伸ばしていたのがベトナム。 脱中国のシフト先の筆頭格に位置付けられる。 日本のベトナムからの衣料品の輸入シェアは 10 年の 5.9% から 14 年は 10.1% に伸び、この 5 年間で 4.2 ポイントも拡大した。 ほかの東南アジアでもシェアを広げ、ミャンマーが 2.3%、インドネシア 2.2%、カンボジア 1.6%、バングラデシュは 1.6% とそれぞれ伸びた。 これら 5 カ国だけでも日本の衣類輸入の 22% のシェアを占めるようになった。
中国からの衣料品の輸入シェアの低下は、世界最大の市場である米国でも同様だ。 右肩上がりに伸びていた米国での中国からの衣料品の輸入シェアは 10 年の 40.9% をピークに減少へと転じ、14 年は 37.9% に低下した。 逆に約 10 年前には 4% にも満たなかったベトナムのシェアは、14 年には 11% にまで上昇した。
人件費が 5 年で約 2 倍
「生産拠点としての中国の魅力が低下している。 この傾向は当面は変わらないだろう。」 大和総研の中村昌宏シニアコンサルタントはこう分析する。 中国でのアパレル生産に変調をもたらした直接の引き金は、同国の人件費の高騰にほかならない。 工場などが集積する中国・深センでは、1 カ月あたりの労務コスト(基本給、社会保障費など含む)が 11 年度に 500 ドル(6 万 1,000 円)を突破。 14 年度調査は約 700 ドル(約 8 万 6,000 円)にのぼった。 上昇幅は過去 5 年で約 2 倍にのぼる。
一方、ベトナムのハノイは、1 カ月あたり 247 ドル(14 年度)と深センの半分程度。 ミャンマーのヤンゴンで 172 ドル、カンボジアのプノンペンで 157 ドルと今の中国に比べれば、人件費は格段に安い。 しかも、中国に後れをとっていた生産性も技術移転によって向上し、企業の東南アジア進出を促している。
労働争議は急増
今後、中国での生産動向はどうなるのか。景気が減速すれば、労働コストが低下して、また生産が盛り返すはずだが、現実は理屈通りにはいかない可能性が強い。 中国での労働争議は目に見えて増え、労使協調が極めて困難な状況に陥っているためだ。 香港に拠点を置く「中国労工通訊(中国労働者通信)」によると、2015 年に中国本土で発生したストライキや抗議活動は、2,300 件にのぼり、すでに昨年よりも約 1,000 件近く上回っている。 11 月は月間件数としては過去最大の 301 件に達したという。 米ウォールストリート・ジャーナル(電子版)が伝えた。
中国当局が発表した 11 月の景況感を示す製造業購買担当者指数 (PMI) は 49.6 で、好不況の判断の節目である 50 を 4 カ月連続で割り込んだ。 中国政府は昨年 11 月以来、6 度の利下げや公共投資などの景気対策を踏み切ったが、効果は十分に出ず、中国国内の需要が大きく減退していることが伺える。 ベトナムやミャンマーなど「チャイナ + ワン」とみなされるライバル国での投資過熱に伴う労務コストの急騰などの "敵失" がない限り、中国への回帰は望めそうにない。 (sankei = 12-16-15)
アパレル各社、春物衣料を前倒し投入 値引き販売避ける
アパレル各社が春物衣料の販売時期を前倒しにする。 三陽商会は婦人服ブランドを 2015 年より数週間早く展開する。 「マッキントッシュフィロソフィー」で通常 2 月上旬に売り出してきた春物を、16 年は 1 月末に前倒しする。 セールを例年より短縮するのに合わせ、値引きしない新商品で顧客をひき付ける。 同社は「ポール・スチュアート」で入学式などに着られるセットアップスーツの販売を始めたほか、主力ブランド「エポカ」や「マッキントッシュロンドン」で冬から春にかけて着られる商品を 1 月に販売する。
ワールドも紳士服の「タケオキクチ」で春物を 1 カ月早く並べて値引き前の販売を増やす。 オンワード樫山も主力ブランド「23区」で春まで着られる素材のシャツを 12 月に売り始め、販売は好調という。 百貨店では「消費者は本当に欲しいものでないと安くなっても買わない」とみて、セールの開始時期を遅らせたり、期間を短くしたりする傾向が広がっている。
アパレル企業はこれまで会員向けの値引きやタイムセールを繰り返し、最終的に過半数の商品を値引きするなどして利益を圧迫してきた。 各社はセール期の 1 月でも値引きせずに売れる春物や、端境期の商品を手厚くそろえて収益改善を図る。 消費増税以降、各社の販売不振は顕著で、15 年 11 月の全国百貨店売上高が 8 カ月ぶりに前年を下回るなど、足元では暖冬の影響も出ていた。 (nikkei = 1-3-16)
「今治タオル」認定受けず 35 万枚出荷 吸水性満たさず
愛媛県今治市のタオルメーカー「一広(いちひろ)」は 22 日、同社の関連会社が高級タオル「今治タオル」の品質基準の認定を受けていないのに、少なくとも 35 万枚を正規認定品として全国に出荷していたと発表した。 すでに店頭から回収を終えたとしている。 周辺のメーカーでつくる「四国タオル工業組合(今治市)」は、「水につけると 5 秒以内に沈む」などを条件とする独自の品質基準を設けている。 組合の認定検査で基準を満たせば今治タオルを名乗り、ロゴマークを付けて販売できる。
一広によると、11 月に組合が実施した品質抜き打ち検査で、関連会社が今治タオルとして出荷した 1 枚が吸水性などの基準を満たさなかった。 さらに調査したところ、認定を受けないまま計 20 種類の製品を今治タオルとして出荷していたことも判明した。 担当者が多忙を理由に検査に出さなかったという。 一広の越智逸宏社長は「管理ミスで消費者のみなさまに多大なご迷惑をかけた」と謝罪した。 (直井政夫、asahi = 12-22-15)
日給 40 円で深夜まで アパレル産業の底辺、児童労働の実態(バングラデシュ)
中国に次いで世界第 2 位のアパレル輸出国であるバングラデシュ。 その輸出額は年間 250 億ドル(約 3 兆円)にも上るというが、国の経済を支えているのは過酷な環境で働く子供たちであった。 英メディア『dailymail.co.uk』がダッカ近郊のある縫製工場の様子を詳細に報じ、世界に衝撃を与えている。
アジア最貧国の一つとも言われ人口密度の高い国としても知られるバングラデシュにとって、アパレル産業は国の経済の要である。 輸出先の 60 パーセントが西欧、23 パーセントが北米で、有名アパレルブランドの進出も著しいが、安全基準を満たさない下請け工場の存在も長年指摘されてきた。 小さな町の一角で工場専用の建物を持たず、電気系統や防火対策など安全上に問題がある企業も多数あるなか、2013 年にダッカ近郊で死者 1,100 人以上を出した縫製工場ビル「ラナ・プラザ」崩壊事故以後、建築基準が徹底され急速に改善されつつあると言われている。
しかしながら、メキシコ出身の写真家、クラウディオ・モンテサーノ・カシージャスさんが、旧市街(オールドダッカ)を観光した際に迷い込んだという Keraniganj の路地には、明らかに違法な縫製工場がひしめきあい、汚染水が川に垂れ流しにされていた。 こちらの画像には、縫製工場の狭い部屋で寝泊りしながら働く子供たちの姿が写し出されている。 出来上がった服にタグをつけたり、生地を染めたり、ミシンの修理をしたりと、どんな作業でもこなすという子供たちは、学校にも行かず 1 週間のうち休みは半日だけだ。 日給は約 40 円で明け方から夜遅くまで働く。
この業界の初任給が 5,300 タカ(約 8,200 円)とされるなか、この工場の労働者の月給は 800 タカ(約 1,200 円)、どんなに頑張っても 1,950 タカ(約 3,000 円程だという。 子供たちはよりよい生活を夢見て地方からやってくるが、工場から外出することはほとんどないのであろう。 仕事が終わると工場の敷地内でシャワーを浴び、食事をして眠る。 工場とはいっても電気配線がむき出しで並び、非常口や消火器も設置されていない劣悪な状態だ。
ユニセフは、バングラデシュの 10 歳から 14 歳の児童労働は 100 万人と公表しているが、近年は低年齢化が進み、その数を把握しきれていないのが現状だ。 またバングラデシュ政府は縫製工場の 80 パーセントは安全基準を満たしており違法な工場は閉鎖するなど体制を強化しているというが、過剰な人口や貧困など根底にある問題を解決しない限り子供たちの過酷な労働に終わりはない。 (Techinsight = 12-13-15)
学校や塾でもかっこよく デサントの子ども向けコート

デサントは、サッカー用品ブランド「アンブロ」から、スポーツするときだけでなく、学校や塾などへも着ていきやすいデザインの子ども向けコート「ジュニアウォッシャブルハーフコート」を全国のスポーツ店などで発売した。 サッカーする子を持つ母親の声を採り入れ、裏地にメッシュを入れて洗濯後に乾きやすくした。 色と大きさの違いで 16 種類ある。 価格は税込み 1 万 2,852 円。 (asahi = 12-5-15)
ナカノアパレル、東京の本社を山形へ メード・イン・南陽発信
女性用衣料の生産・販売を手掛けるナカノアパレル(東京・中央、中野憲司社長)は来春をメドに、本社を山形県南陽市に移転する。 拠点工場のある同市に本社を移し、今後は工場を増強して百人規模で採用を増やす。 欧米の有名ブランド品の生産も受託するが、そうした取引の拡大には、地方に本社を置く方がイメージ向上につながると判断した。
山形県に本社を移転するのは、(1) 拠点工場がある、(2) 地方発ブランドで世界に売り込む、(3) 災害リスクなどが高い東京の緊急時に備える - - といった理由がある。 従業員の住居の確保など地元の受け入れ体制を整えたうえで、来年 3、4 月ごろに移転したい考え。 営業部門などは東京に残し、実際に移るのは中野社長ほか少数にとどまる。 ただ、現在、約 100 人が働く工場を今後は 200 人規模に増強する。 中国・無錫の工場は人件費が上昇、日本製のブランド力も加味すれば国内回帰も可能とみて、うち 50 人はベトナム人を採用する。 現在、中国 7 割、国内 3 割の生産比率を数年内に半々にする。
山形県の中でも果樹やワインなどの食文化や自然に恵まれた地域に本社を置くイメージアップ効果も期待する。 首都圏のデザイナー志望の学生の中には、地方でデザインの仕事に携わりたいと希望する人も増えているといい、こうした人材を呼び込む。 特に、欧米ブランドからの受託では、「東京より地方に拠点のあることが高い評価につながりやすい(中野社長)」という。 ホームページも年明けに南陽を前面に打ち出したものに刷新、英語版も用意する。
同社は 1988 年、奈良県生駒市で設立、2006 年から東京に本社を置く。 女性用ブラウスやカットソーなどを生産。 ジルサンダーやプラダなどの海外ブランドやオンワードの五大陸などの生産を受託する。 日中合わせて年 100 万枚、うち山形では 36 万枚を生産し、年商は約 36 億円。 山形工場は 12 年に「4℃」ブランドの F & A アクアホールディングス(現・ヨンドシーホールディングス)から取得した。 (nikkei = 12-3-15)
百貨店大手、4 社が売上減 気温高めで冬物衣料不振
大手百貨店 4 社が 1 日発表した 11 月の売上高(既存店ベース)は、いずれも 8 カ月ぶりに前年を下回った。 訪日外国人向けの免税品は引き続き好調だったが、気温が平年より高く、冬物衣料が不振だった。 三越伊勢丹ホールディングスが 1.7% 減、大丸松坂屋を運営する J フロントリテイリングは 2.9% 減、高島屋は 1.5% 減、そごう・西武は 3.0% 減だった。 (asahi = 12-2-15)
保湿クリームもう不要? 帝人が「着られる」化粧品開発
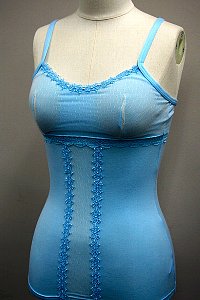
帝人は 30 日、衣類にしみ込ませた化粧品成分で肌の潤いを保ち、荒れを防ぐ「着られる」化粧品を開発したと発表した。 女性用肌着やアームカバーなどの 6 品を「ラフィナン」のブランド名でつくり、来年 3 月ごろから自社の通販サイトなどで売り始める。 肌の表面を健康な状態の弱酸性に保つ効果を持つ「リンゴ酸」をポリエステル繊維にしみ込ませた。 50 回洗濯しても成分がほぼ落ちないよう工夫した。 医薬品医療機器法に基づく化粧品の製造販売許可を東京都から 5 月に取得。 肌着などの形をした化粧品は「国内初になる(同社)」という。
運動や入浴後の肌が乾燥しやすい時に着ると、保湿クリームや乳液を塗る必要がなくなるという。 30 - 40 代の女性がターゲット。 1,500 - 4 千円前後で直接小売りするほか、素材もアパレルメーカーに売り込む。 スポーツ衣料大手のデサントも同日、「ラフィナン」を使った新商品群を立ち上げると発表。 ヨガ向けの T シャツやパンツなど 7 品を来年 3 月に出すという。 (asahi = 11-30-15)
大量生産のファッションの代償とは? 映画「ザ・トゥルー・コスト」
ファストファッションと呼ばれるような服が、どのように作られているのか? 経済的に貧しい国での、低賃金の長時間労働、劣悪な労働環境、そして環境汚染 …。 2013 年 4 月にはバングラデシュで縫製工場の入った 8 階建てのビルが倒壊して、1,100 人以上の死者、約 3,000 人がけがをした事故もあった。 そうしたことはかなり知っていたつもりだけれど、現実感を伴ったものではなかった。
東京・渋谷のアップリンクで公開中のドキュメンタリー映画「ザ・トゥルー・コスト(真の代償)」は、ファストファッションの服作りの現場が思っていたよりはるかに過酷で代償も大きいことを示している。 また、十分に知らないでいたことへの反省という "代償" をも迫る内容だった。 映画では、縫製工場とそこで働く女性たちの生活や思い、工場からの汚染水や農薬による深刻な健康被害、川や海などの汚染による漁業被害の実情を、それとは対照的なファッションショーの華やかな舞台や先進国の服の売り場のにぎわいなどの光景を織り交ぜながら淡々とリポートしていく。
バングラデシュの首都ダッカの縫製工場で働く一児の母シーマは、朝から 1 日 12 時間以上働き、つかの間の夜はバラックのような寮で寝るだけ。 休みは月 1、2 回。 それでも驚くほどの低賃金だが、そのほとんどを田舎の家族に送金している。 子どもに会えるのは年に 1、2 回しかないという。
衝撃的だったのは、カンボジア・プノンペンの縫製工場で 2014 年、賃上げを要求する工員のデモに政府の治安部隊が発砲する場面だった。 それにより 4 人の死者と多くの怪我人が出た。 一人の女性はこう訴える。 「私たちの血で作ったものを、誰にも着てほしくありません。」 そんな服を、品質のわりには安いとの理由で、喜んで買って着ることができるのだろうか?
アメリカのサンクスギビングデー翌日のバーゲンセールでは、価格をさらに下げた服やバッグが並ぶ会場に大勢の買い物客が殺到。 大きなかごにお買い得品をこれでもかと詰め込む姿も。 その姿は楽しげで、楽しみのために必要以上に鳥や動物たちを追い回して殺すハンターたちを思い起こさせる。
代償は、服作りに直接かかわらない人たちにも及ぶ。 インドの皮革工場から出た汚染水は、周辺地域の人たちの健康に大きな影響を与えているようだ。 皮膚にダメージを負った女性の顔は、まるで破れた大きな顔面マスクを被ったように見えて心が痛む。 服作りにはさまざまな有害化合物が必要で、大量に作ればそれだけ大量の有害物質が排出される。 服が大量に作られ消費されれば、大量のごみにもなる。 燃やせば温室効果ガスも出る。 製作過程も含めてファッション・アパレル産業が排出する炭酸ガスの量は、石油産業に次いで第2位なのだという。
この映画では、こうした問題に危機感を持って活動している人たちの発言も紹介している。 環境問題にこだわるファッションデザイナー、ステラ・マッカートニーは「巨大で強欲な(ブランド)企業が大きな利益を上げているのに、何百万という(この分野)の労働者たちになぜ適切な支援ができないのでしょうか」と語っている。
大量生産・消費がもたらす弊害が限界に差し掛かっているのは、ファストファッションに限らず、多くの高級ブランドでも状況はさほど変わりはない。 そして、ファッション産業だけだというわけでもない。 しかし本来は長期耐久品だった服を消耗品にしてしまった現代のファッションは、これから率先して大量生産のあり方を変えていく義務があるのではないかと思う。
そのためには服を着る側が、作る側で起きていることについて、知らなかったりそのふりをしたりではいけない。 誰かが、または何かが大きな犠牲になっているような服を着る「自由」などはないはずだし、そんな服を着てファッション本来の楽しみなどは味わえないのだから。 (上間常正、asahi = 11-27-15)
ホームファッション市場 2014 年は 1.3% 増の 3 兆 4,359 億円
矢野経済研究所は 11 月 24 日、「ホームファッション市場に関する調査結果 2015」を発表した。 調査によると、2014 年のホームファッション小売市場規模は前年比 1.3% 増の 3 兆 4,359 億円だった。 2009 年以降は上昇に転じ、3 兆円規模を維持するまでに回復している。 2014 年は消費税増税の駆け込み需要の反動減もあり、アイテム分野によっては前年割れもあったが、市場全体としては 2013 年の市況を引き継いで堅調に推移した。

2015 年のホームファッション小売市場規模は 2.0% 増の 3 兆 5,041 億円を予測する。 新たな需要を開拓するために、男性向け、女性向け、子供向け、シニア向け、若年層向けや介護用途など細かくターゲットを明確化した機能性商品の多様化が進む。 特に寝装寝具分野では商品特性を説明するような第三者機関のデータや情報などをベースとした商品開発が活発化することで、新たな消費者需要が開拓されるという。 (流通ニュース = 11-24-15)
西陣の織物「ス−パースター」ウェア 本田選手も協力
ミズノは、昨年に復活させた「スーパースター」のブランドから、西陣の織物を使ったプレミアムジャケットを 12 月上旬に売り出す。 京都市の織物業「細尾」が、スポーツウェア向けに開発した生地を活用した。 西陣の織物のスポーツウェアは珍しいという。 50 着限定で、定価は税別 12 万円。 全国のミズノ直営店などで販売する。
絹糸ではなくポリエステルで織ることで、通気性を持たせ、簡単に洗えるようにした。 卍(まんじ)の形をくずして連ねた「紗綾型(さやがた)」やツツジなどの柄が見えるデザイン。 サッカー日本代表の本田圭佑選手の意見も参考にした。 (新宅あゆみ、asahi = 11-19-15)
アシックス/国内アパレル工場(大牟田工場)の経営権を譲渡
株式会社アシックスは、2016 年 1 月 4 日付けで、国内のアパレル生産子会社(100% 子会社)であるアシックスアパレル工業株式会社が運営する大牟田工場(福岡県大牟田市)の全事業を会社分割によって新設会社に承継させるとともに、新設会社の株式の一部を帝人株式会社の 100% 子会社である帝人フロンティア株式会社に譲渡することが決定しましたのでお知らせします。
本件後も、アシックスアパレル工業株式会社と帝人フロンティア株式会社は出資者として、共同で大牟田工場の経営を行い、「MADE IN JAPAN」に特化した国内生産を行います。 なお、業績に与える影響は軽微です。 (e-LogiT = 11-18-15)
【新設会社概要】
会社名 : 帝人フロンティアアパレル工業株式会社
設立 : 2016 年 1 月
本社 : 福岡県大牟田市合成町 88 番地
事業内容 : アシックスのスポーツウエアの製造
クラリーノ 50 年 ランドセルから超高級ブランドへ
クラレは、ランドセルの素材で知られる人工皮革「クラリーノ」で、手触りや風合いなどを天然皮革に近づけた新製品を開発した。 中国製などの標準的な人工皮革が出回るなか、1965 年の販売開始から 50 年の節目に超高級バッグなどへのシフトを強め、拡大をねらう。
次世代と位置づける開発品の特徴は、軽さや水ぬれへの強さなど人工皮革の良さを保ちつつ、なめし加工を手がけるイタリアの業者と協業して天然のように仕上げたことだ。 ミラノで 9 月にあった見本市では「プロが天然皮革と間違えたほどだった(同社)」という。 伊藤正明社長は「100 年続くよう、がんばりたい」と国内の初披露の式典で意気込んだ。
2009 年に開発した製法を使って組織の密度を約 2 倍に高め、コラーゲン繊維からなる天然皮革と似た構造にすることに成功。 革製品の歴史が長い欧州の超高級ブランドを狙える、と照準を定めた。 最初は門前払いだったが、何度も試作して回り、今年になって提携が実現した。 なめし加工をしやすい改良もした。 クラリーノは、クラレが靴の素材として開発した世界初の人工皮革だ。 ランドセル向けは 70 年に始まったが、販売量に占める割合でみれば 1 割程度にとどまる。 超高級品のバッグやジャケットといった新たな市場の開拓をめざす。(伊沢友之、村井七緒子、asahi = 11-17-15)
最大級の繊維・アパレル OEM・ODM 展示会 「AFF・大阪 2016」申込開始
10 月 21 - 23 日、AFF 株式会社、一般社団法人日中経済貿易センターの主催による「AFF・東京 2015」は東京池袋・サンシャインシティ文化会館にて開催しました。 展示面積が 8,500m2 に達し、合計 401 社が 472 ブースで出展しました。 3 日間で 4,871 名のバイヤーにご来場いただきました。
AFF は今まで 26 回を開催し、日本最大級の繊維・アパレル OEM・ODM 展示会として、繊維・アパレル業界の皆様に多くの発展チャンスを提供いたします。 近年、東南アジア関係の企業や「インダストリー 4.0」で新技術の導入された企業の出展が拡大しています。
「AFF・大阪 2016」は 2016 年 4 月 12 - 14 日に大阪・マイドームに開催する予定です。 アパレル、素材、服飾品、副資材、ホームテキスタイルなど様々な製品を展示する予定です。 今回は 1 - 3 階の展示ホールを使用し、展示面積が 6,000m2 に達します。 今回の「AFF・大阪 2016」は業界の皆様に高く期待され、出展申込が殺到しました。 ブースの定数に達しましたら、申込みを締め切りますので、出展を希望される方はお申込みください。 (Mr. Huang、PR Wire = 11-16-15)
中国失速で国内アパレル破綻 11 件 業界直撃 … 今後も続くか
中国経済の失速が絡んで日本企業が経営破綻に追い込まれた事例が、10 月は 11 件あったことが 10 日、東京商工リサーチがまとめた調査で明らかになった。 昨年 1 月の調査開始以降、2 カ月連続で月間最多件数を記録。 同社は「中国リスクに関連した破綻は今後も続く」とみている。 繊維・衣服卸売業など、アパレル関係だけで 5 件発生。 このうち、徳島県美馬市の下着メーカーは中国の人件費高騰、東京都文京区のアパレルメーカーは中国で縫製する製品の品質問題が発端で破産開始決定を受けた。 (sankei = 11-11-15)
アパレル工場の現実と将来とは? 日本初、学生向けアパレル工場サミット開催
ライフスタイルアクセントが展開するアパレル工場直結のジャパンブランド「ファクトリエ(Factelier)」が、日本初となる学生に向けた工場サミット「学生のためのアパレル工場サミット 2015」を銀座で 11 月 14 日開催する。 「アパレル工場を見てわかった現実と将来の可能性」などをテーマにトークセッションを行うイベントで、「ファッションしらいし」の白石正裕社長や伊勢丹新宿本店バイヤーの額田純嗣などが参加。 参加無料で、現在ウェブサイトで応募受付を開始している。
国内で流通するアパレル品の国産比率が 50.1% から 3% にまで減少し、アパレル工場数も減少の一途をたどっている現状を踏まえ、「学生のためのアパレル工場サミット 2015」では、工場で働くスタッフや日本製商品を扱う事業者、百貨店のバイヤーなどを招き、これからの "メイドインジャパン" の魅力や進むべき道と課題、人材採用における問題点などについて議論。
トークセッションテーマは「都会と地方、どっちが得か。 工場の所在地がもたらすもの。」や「日本はなぜ今 "メイドインジャパン" なのか」などで、ランチ交流会も実施。 登壇企業には、和田メリヤスやクスカ、スマイルコットンなどがあり、同イベントを通して工場で働くことを志す学生を増やしていきたい考えだ。 (FashionSnap = 11-10-15)
〈アパレル大手の EC〉 軒並み 2 桁増収/デジタルシフトが加速
アパレルメーカー大手の EC 売上高が拡大している。 15 年 7 月から 9 月に本決算や中間決算を迎えた企業のEC売上高は軒並み 2 桁増収だった。 各社は消費行動の変化を受けて EC の商品供給体制を強化しているほか、オムニチャネルを見据え、店舗と EC サイトの会員情報を統合するなどデジタルシフトを推し進めている。 「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングを筆頭に、ベイクルーズグループ、アダストリア、ユナイテッドアローズ、オンワード樫山が前期比または前年同期比で 2 桁増収だった。
増収率が前年同期比 4.1% 増にとどまった TSI ホールディングスも、全社売上高が減収だったことを踏まえれば EC の好調ぶりが目立つ。 ファッションアイテムを EC サイトで購入する消費者が増える中、アパレル各社は EC の商品供給体制を強化して売り上げを伸ばしてきた。 例えばユナイテッドアローズは、あらかじめ確保した EC の在庫が薄くなった際、実店舗の在庫を EC に振り替えるなどフレキシブルに運用している。 ベイクルーズは約 2 年前、「ゾゾタウン」以外の EC サイトの在庫情報を一元化し、在庫の引き当てを適正化することで機会損失を低減した。
各社はオムニチャネルを見据え、店舗と EC のポイント統合や在庫連携、顧客 ID の統合なども順次進めている。 スマートフォンからの試着予約や店頭取り置きサービスも広がり始めた。 将来は顧客の属性や購買履歴、行動履歴などを EC と店舗で統合して分析し、顧客ごとにメルマガを出し分けたり、ECサイトの表示内容を変えたりするワン・トゥ・ワン・マーケティングを計画している。
アパレル大手がデジタルシフトを加速している背景には、「円安で仕入れコストが上昇したため、店舗よりも販売コストを抑えられるネット通販にシフトしている(アパレル大手の EC 事業責任者)」という事情もある。 「アパレル業界は現在、業態転換の過渡期(同)」にあり、各社はデジタルシフトのための社内体制の変革や設備投資を継続する見通し。 14 年時点で約 1 兆 3,000 億円とされるアパレル EC 市場は当面、拡大が続きそうだ。 (日流ウェブ = 11-9-15)
井関奈央さん 生糸を引く繭、年 100 万個
■ 西予市野村シルク博物館 繰糸工(32 歳)
国産の生糸を再び普及させ、織物作家に気軽に使ってもらいたい - -。 愛媛県でただ一人の繰糸工として、年間約 100 万個の繭から重さ 200 キロほどの生糸を引く。 勤め先は、同県西予市の中心部から車で 30 分の四国山地の山あいにある。 かつて養蚕が盛んだった地域だ。 工場では、同時に 16 本の生糸を引く多条繰糸機が、約 80 個の繭をころころと踊らせている。 1 個の繭からとれる糸の長さは 1,600 メートルにも及ぶが、1 本ずつはクモの糸のように細い。 そのため、5 - 6 個分をより合わせたものが 1 本の生糸になる。
ここで作られる生糸は、「白いツバキのような気品と光沢がある」とも言われる。 触れると柔らかく、一般相場の約 3 倍の値段で取引される。 2013 年には伊勢神宮の式年遷宮で奉納されたほどの「特別な品」だ。 繭は市内の養蚕農家から蚕が元気に動いている状態で仕入れる。 成虫になって繭を破ると糸が引けなくなるため、すぐに高温で乾燥させて中の蚕を殺してしまうのが一般的だ。 だが、それでは熱で品質が落ちてしまう。 コストはかかるが繭を冷蔵し、蚕の成長を鈍らせ、保存している。
繭を軟らかくするための煮る作業も手間をかける。 普通は沸騰した湯を使うが、ここでは低温で時間をかけて煮る。 高温でたんぱく質を傷めないようにするためだ。 繭の大きさや硬さには違いがある。 温度と時間は調整が必要だ。 軟らかすぎると糸がまっすぐにならず、節が出やすくなる。 硬すぎると糸がすっと引けない。 「『ちょうどいい』だけが正解。 日々勉強です。」
糸を繰る機械もゆっくり動かす。 生糸を引っ張る力をゆるくすることで、「光沢のある、ふわふわでかさ高な糸」にするためだ。 機械が動いている間も気が抜けない。 糸にわずかな節があると、糸がまっすぐにならず、染めの工程でムラができてしまう。 機械が引く髪の毛よりも細い糸の、わずかな節も見逃さず、切り取る。 その目は、毎日の積み重ねで養った。
地元育ちだが、最初から生糸に興味があったわけではない。 シルク博物館の染織講座を受けに来る都会の人たちを見て、「みんな何やっているんだろう」と不思議に思っていた。 しかし、見ているうちに「手に職をつけたい」と思うようになった。 受講してみると、同じ作業を繰り返すことが好きだった性格にぴったり合っていた。
養蚕農家が減り続けていることに心配が募る。 市内にはかつて 1,883 戸あったが、今では 6 戸になった。 国内の生糸生産量は昭和初期の約 4 万 5 千トンをピークに減少し、昨年は約 26 トンに。 中国産など輸入生糸は 500 トン近くまで増えており、国産生糸の存在感は薄れている。 ここの生糸も、もうかる仕事ではないが「伝統を絶やさないために」の思いで続けられている。 繰糸工になって 5 年。 「次世代にバトンタッチするまでがんばる」が目標。 悩みは、仕事の相談や情報交換ができる仲間がいないこと。 「仲間ができるほどに養蚕農家が増えてほしい」との願いは切実だ。(細見るい、asahi = 11-2-15)
<プロフィル> いせき・なお 愛媛県西予市出身。 県立野村高校を卒業後、地元スーパーでレジを担当。 2010 年、西予市の嘱託職員になり、野村シルク博物館で生糸をつくる繰糸工として働く。
◇ 凄腕のひみつ
足袋型スニーカー
一日中立ちっぱなしのため、足にかかる負担が大きい。 体にいいものを探していた 2 年前、デパートの健康フェアで足袋型スニーカーを見つけた。 親指とそれ以外の指が分かれていて、フィット感があって履き心地がいい。 普通の靴に比べて、指先に力を込めやすいところも気に入っている。 黒地に入った差し色のピンクが気分を上げてくれる。
糸切り・ねこ
節のないまっすぐな生糸にするためには、左手親指にはめた糸切りが欠かせない。 5 年間使い続けている。 できた生糸はねこを使って市販の糸で束ねていく。
伊勢丹、無印良品も注目 アパレルに広がる国産志向
ファッション業界で日本製品に対する評価が高まっている。 町工場の直営店から高級ブランド、生活雑貨店「無印良品」に至るまで国産のヒット商品が生まれ始めている。 背景にあるのは、訪日外国人によるインバウンド消費だけではない。 日本人の間で日本製への再評価が広がり、ブームでは終わらない潮流を起こしつつあるようだ。
■ 腕を上げても裾が上がらないシャツ
相撲の聖地、東京・両国国技館近く。 清澄通り沿いにある 1 軒の洋服店に鹿児島県、徳島県といった遠方から買い物客が次々と訪れる。 お目当ては中堅メーカー、丸和繊維工業(東京・墨田)のブランド「INDUSTYLE TOKYO (インダスタイル トウキョウ)」の商品だ。 「5 枚のワイシャツをまとめ買いする人もいますよ。」 本社 1 階にある直営店で話すのは同社営業第 2 グループの西川知哉マネジャーだ。 男女用のワイシャツ 1 枚で税別 1 万 5,000 円からと安くはない。 町工場発の商品が、なぜこの価格帯で売れるのか。
同ブランドのワイシャツは体にフィットするのに、腕を上げたり肩を回したりしても引きつらない。 大きく背伸びをすると、一般のシャツは裾がスーツのパンツからはみ出て、だらしない印象になりがちだ。 ところがインダスタイルの商品は腕を上げても裾がほとんど上がらない不思議なシャツなのだ。 秘密は「動体裁断」と呼ぶ独自の縫製技術にある。 「人間の皮膚を研究し、動くことを前提とした型紙づくりをした(丸和繊維の伊藤哲朗常務)」といい、特許を取得している。 ポロシャツのようなニット素材(編み物)で少し伸縮性があり、肌触りも柔らかい。
今では伊勢丹新宿本店メンズ館や大丸東京店などの百貨店や直営店、ネット通販で販売している。 2015 年 12 月期の売上高は 2 億円程度と、前期より 5 割増えそうという。 顧客の大半は日本人で 20 歳代後半から 70 代まで幅広い。 男性が中心だが、少しずつ女性も増えてきおり、「店頭で試着した後、2 回目以降はネットで買うリピーターが広がっている(西川氏)」という。
同社がインダスタイルを始めたのは 2011 年。 墨田区内の縫製工場を回っていた伊勢丹のバイヤーが試作品に目をとめた。 試着したバイヤーは着心地の良さに驚き、取引がスタート。 ボタンの位置や袖口(カフス)の幅など、伊勢丹の助言を受けて開発を進めた。 無名のメーカーブランドが売れるかは分からない。 伊勢丹は当初 3 カ月分として 100 枚単位で仕入れたところ、予想を上回る反響で 1 カ月ほどで完売。 追加販売に踏み切った。 「個人によって『かっこいい』の価値観は異なる。 だが、着心地の良さは万人共通で感じられる。」と伊藤常務は話す。 技術力に裏打ちされた着心地の良さでファンを獲得している。
伊勢丹と同じく日本の工場の技術力に目を付けたのが、イタリアの高級紳士服エルメネジルド・ゼニアだ。 今秋、日本製などにこだわった限定商品を発売した。 イタリアのデザインに日本の生地を使い、縫製も日本の職人が手がけている。 同社が日本向けに限定商品を売り出すのは初めてだという。 「テーラリング」、「カジュアル」、「デニム」、「アクセサリー」という 4 種類のテーマに沿って、日本のクリエーターと開発したジャケット(43 万円から)、クラボウと国産のデニムにこだわって生産したシャツ(10 万 6,000 円から)などをそろえる。 まず「銀座グローバルストア(東京・中央)」で売り出し、「大阪グローバルストア(大阪市)」でも扱っている。
■ 国産衣料に注力する無印良品
大手小売りにも動きは広がる。 「無印良品」を展開する良品計画は、衣料品ブランド「MUJI Labo (ムジラボ)」で 15 年秋冬物からほぼ全品を日本製に切り替えた。 新潟県や群馬県で生産したニット、愛知県と岐阜県にまたがる「尾州」で織った毛織物など全国の産地と協力して原材料をそろえる。
ムジラボを担当する衣服・雑貨部の山内良介課長代行は「世界的に強みのある日本の地域と組み、より品質の良いものを作りたい」と話す。 もともとムジラボでは栽培時の農薬を抑えたオーガニックコットンなどの素材にこだわってきた。 シンプルで実用性の高い服を掲げて、婦人服と紳士服を展開。 外部のデザイナーを起用し、価格も通常の無印良品ブランドより高い設定だ。 都市部の大型店を中心に、国内外の約 40 店で売っている。
海外で人気の無印良品の店舗は訪日客も多いが、松崎暁社長はムジラボを日本製に切り替えた狙いについて「インバウンド消費を取り込むためという考えは全くない」と言い切る。 日本の有力産地と組み、「そこでしか作れない、織れない技術」にこだわる。 店頭案内や接客などを通じて、日本の消費者に質の高さなどを訴えていく戦略だ。
業界団体の日本ファッション産業協議会は織りや編み、染色、縫製を国内で手掛けた商品を純国産とする認証制度「J クオリティ」を始め、今年の秋冬物から専用タグのついた様々な商品が登場している。 アパレル大手の TSI ホールディングスが同業のワールドから国内工場を買収し、日本製品の割合を高めるという動きも出てきた。
ただ、日本製ファッションへの再評価が一部の服好きなファンだけにとどまってしまっては、もったいない。 日本の繊維事業所は約 1 万 3,000 カ所と 20 年で 4 分の 1 近くに減少した。 産地の特徴や職人の技術を盛り込み、価値のある商品として消費者に伝え続けられるか。 一過性ではない業界を挙げた取り組みが問われている。 (早川麗、nikkei = 10-30-15)